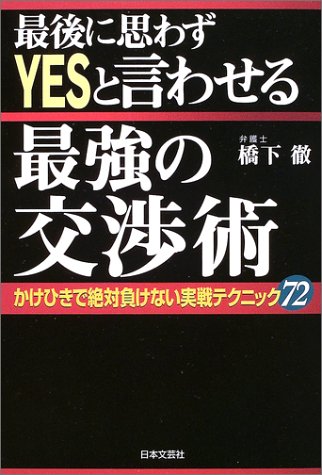- 著者
- 永井 靖 中越 洋 平 重喜 岩嵜 正明
- 出版者
- The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers
- 雑誌
- 電子情報通信学会論文誌 A (ISSN:09135707)
- 巻号頁・発行日
- vol.J96-A, no.1, pp.22-33, 2013-01-01
ハードウェアアクセラレータを含むシステム設計では,早い工程でのハードウェアとソフトウェアの機能分割が課題である.この課題に対し,我々は新規回路の記述前に性能を予測し必要性能を満足するハードウェア化機能を設計するDFSMBT手法[14]を提案した.しかし,多重タスク環境を採用し,動作周波数が未定なシステムの設計では,DFSMBT手法の適用は困難である.多重タスク環境ではシステムの動作が単純な繰返しとならず,加えて,動作周波数が変化するとアクセラレータのシステム全体性能に対する寄与率が変化する.このため,手作業では性能の予測が難しい.本論文では,再利用可能なハードウェアモジュールとソフトウェアを組み合わせたシミュレータを用い,設計システムのメモリアクセスパターンを把握し,システム性能を予測する改良DFSMBT手法を提案する.そして,本手法をネットワーク暗号アクセラレータシステムの開発に適用した例を示す.また,開発前の予測と実機における性能を実測比較し,本手法の有効性を示す.
1 0 0 0 OA 祝日大祭日歌詞並楽譜
- 出版者
- 吉岡平助
- 巻号頁・発行日
- 1893
1 0 0 0 アフリカ大陸におけるホットスポット火山活動の地球物理学的研究
- 著者
- 浜口 博之 西村 太志 林 信太郎 KAVOTHA K.S. MIFUNDU Wafu NDONTONI Zan 森田 裕一 笠原 稔 田中 和夫 WAFULA Mifundu ZANA Ndontoni WAFULA Mifun ZANA Ndonton KAVOTA K.S.
- 出版者
- 東北大学
- 雑誌
- 国際学術研究
- 巻号頁・発行日
- 1990
この研究は,(1)ホットスポット火山の多いアフリカ大陸の深部構造の解明,並びに(2)ニアムラギラ火山のマグマ活動調査の2項目に大きく分けられる.1990年度の現地調査は予定通り実施され,当初の目的は達成された.1991年度は,現地調査の最中の9月23日にザイ-ルの首都キンシャサを中心に政情不安に端を発した暴動が起こり,日本大使館の退避観告に基づき調査を途中で中断し,隣国に緊急避難しそのまま帰国する結果となった.このため,この年度の調査事項の実施については,不完全なものにならざるを得なかった.以下,2年間の研究実績を項目別に分けて簡潔に示す.1.広帯域地震観測.0.05秒〜370秒に渡って一様な感度を持つCMGー3型とパソコンを用いた地震波収録装置を,1990年度はザイ-ル東部のルイロ地震観測所(LWI)に設置した.1991年度は,キンシャサ効外のビンザ気象局の地下地震計室(BNZ)に設置したが,最後の調整の直前に暴動が起こり,一部未完な状態のまま今日まで観測は続けられている.従って,地震計の再調整を含む良好なデ-タの取得は今後の課題として残された.この観測と並行して実施してきたアフリカ大陸下の深部構造については,(イ)アフリカ直下でコア・マントル境界(CMB)が盛り上がっていること,(ロ)マントル最下部のD"領域ではS波速度が3〜5%遅いこと,逆に,アフリカ大陸の外では数%速いこと,並びに,(ハ)コア表面の温度は,アフリカ大陸を含むA半球がその反対側の太平洋を含むP半球より数10mケルビン高温であること,などが明かとなった.これらの結果はアフリカ大陸に於いてホットスポット火山の密度が高い理由の解釈に重要な手がかりとなる.2.火山性地震・微動観測.1990年度は,CRSN(ザイ-ル自然科学研究所)の定常観測点(4点)の他に,8月13日〜11月29日まで火山地域内で8点の臨時地震観測を実施した.11月20日にこの地域では過去最大のM4の地震がニイラゴンゴ火山南方10kmに起きた.観測結果はこの地震により火山性地震やマグマ活動は励起されず,逆に地溝帯中軸の地震が活発化した事が明らかにされた.また,ニアムラギラの側噴火(キタツングルワ)のストロンポリ式噴火に伴う地震は火口直下0.2〜0.5kmの深さに集中し,その発震機構はマグマの噴出時に働くほぼ鉛直下方のSingle Fo
- 著者
- 西野 衆文 池田 耕太郎
- 出版者
- メヂカルフレンド社
- 雑誌
- 看護技術 (ISSN:0449752X)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, no.14, pp.1252-1255, 2003-12
1 0 0 0 OA 児童の食べ残しの行動に関わる要因の検討
- 著者
- 谷口 貴穂 赤松 利恵
- 出版者
- 日本健康教育学会
- 雑誌
- 日本健康教育学会誌 (ISSN:13402560)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.1, pp.24-33, 2009 (Released:2010-06-04)
- 参考文献数
- 25
- 被引用文献数
- 3
目的:「もったいない」と思う気持ち(食べ物を捨てるときに感じる気持ち)を食事摂取に関わる要因として加え,食べ残しの行動の予測要因を検討すること.方法:都内の公立小学校の5・6年生の児童2,070人を対象に,自記式の質問紙に基づく横断調査を実施した.食べ残しの行動の予測要因として,「もったいない」と思う気持ちと,食べ残しの多い野菜摂取に関わる要因(嗜好,結果期待,学校菜園活動,家庭のしつけ)や,野菜を食べる頻度と食べ残しの行動との関連を調べた.性別で野菜摂取に関わる要因が異なることから,男女別で食べ残しの行動の予測要因を検討した.結果:1,994人から回答を得た.女子よりも男子の方が食べ残しの行動をしないと回答した.食べ残しの行動の予測要因は男女で異なったが,食べ残しの行動に最も影響を与えていたのは,男女とも野菜の嗜好で,次が「もったいない」と思う気持ちであった.結論:「もったいない」と思う気持ちは,食べ残しの予測要因となり,2番目に強く食べ残しの行動に影響を与えていた.食べ残しの行動に最も影響を与えていたのは,野菜の嗜好であった,これらのことから,「もったいない」と思う気持ちを育てること,野菜の嗜好を変えることにより,食べ残しが減ると考えられた.
1 0 0 0 OA 如何に国語を教ふ可き乎
1 0 0 0 OA 313 潜在微小き裂の概念を用いた異材接合端の強度の統一的評価
- 著者
- 久保 司郎 井岡 誠司
- 出版者
- 社団法人日本材料学会
- 雑誌
- 学術講演会講演論文集
- 巻号頁・発行日
- vol.46, pp.109-110, 1997
1 0 0 0 OA 数理社会学の数理モデルと経済学のゲーム理論
- 著者
- 七條 達弘
- 出版者
- 数理社会学会
- 雑誌
- 理論と方法 (ISSN:09131442)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.2, pp.253-270, 2011 (Released:2012-09-01)
- 参考文献数
- 14
数理社会学における数理モデルと経済学におけるゲーム理論を対比しながら,社会学としての数理モデルについて論じる.意識変数を取り扱う等,主観的領域に一歩踏み込むのが社会学における数理モデルの特徴であると論じ,そのようなモデルは,たとえ,ゲーム理論の均衡分析で人々の行動を記述できる場合でも有意義であると論じる.さらに,数理社会学において土台となる基本原則を持つことを提案し,具体的に,三つの基本原則を使い,いくつかの数理モデルが,基本原則の派生型と解釈できる事を示す.
1 0 0 0 和歌文学大辞典
- 著者
- 伊藤嘉夫 [ほか] 編
- 出版者
- 明治書院
- 巻号頁・発行日
- 1962
1 0 0 0 中世文学 : 資料と論考
- 著者
- 武田 利勝
- 出版者
- 早稲田ドイツ語学・文学会編集委員会
- 雑誌
- Waseda Blätter (ISSN:13403710)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, pp.22-41, 2007-03-25
- 著者
- 小野 豊 木村 重 井上 丁 森 治
- 出版者
- 神戸大学
- 雑誌
- 兵庫農科大學研究報告. 畜産学編 (ISSN:04415450)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, no.1, pp.1-4, 1963
1 0 0 0 OA 官報
- 著者
- 大蔵省印刷局 [編]
- 出版者
- 日本マイクロ写真
- 巻号頁・発行日
- vol.1929年02月20日, 1929-02-20
1 0 0 0 OA 官報
- 著者
- 大蔵省印刷局 [編]
- 出版者
- 日本マイクロ写真
- 巻号頁・発行日
- vol.1925年09月03日, 1925-09-03
1 0 0 0 OA 電解重合
- 著者
- 山崎 升 中浜 精一
- 出版者
- 公益社団法人 高分子学会
- 雑誌
- 高分子 (ISSN:04541138)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, no.10, pp.804-807, 1964-09-20 (Released:2011-09-21)
- 参考文献数
- 15
- 被引用文献数
- 1
1 0 0 0 オオシマアカネズミの腹毛に見られる性的及び季節的多型について
- 著者
- 今泉 吉典
- 出版者
- THE MAMMAL SOCIETY OF JAPAN
- 雑誌
- 哺乳動物学雑誌: The Journal of the Mammalogical Society of Japan (ISSN:05460670)
- 巻号頁・発行日
- vol.4, no.4, pp.102-106, 1969
オオシマアカネズミの標本95点を調査した結果,次のことが判明した。(1)夏毛と冬毛は背毛では刺毛の有無により,腹毛では色彩によってほぼ判定することができる。(2)更毛は年2回,4・5月と10・11月に行なわれる。(3)腹毛には夏毛・冬毛ともほぼ2つの色型があり,冬毛よりも夏毛の方が明らかに濃色である。(4)腹毛の色彩は夏毛・冬毛とも♂ よりも♀のほうが濃色の傾向が強い。
- 著者
- Kawamura Kimitaka Izawa Yusuke Mochida Michihiro Shiraiwa Takayuki
- 出版者
- Elsevier
- 雑誌
- Geochimica et Cosmochimica Acta (ISSN:00167037)
- 巻号頁・発行日
- vol.99, pp.317-329, 2012-12-15
- 被引用文献数
- 91
We successfully detected biomass burning tracers including levoglucosan and vanillic, p-hydroxybenzoic and dehydroabietic acids in an ice core (153 m long, ca. 300 years old) taken from Ushkovsky ice cap (altitude, 3903 m), the Kamchatka Peninsula, Northeast Asia. Concentrations of total organic carbon (TOC) were also determined in the ice core. Levoglucosan, which is produced by pyrolysis of cellulose and hemicellulose and thus is a general tracer of biomass burning, showed sporadic peaks in the years of 1705, 1759, 1883, 1915, 1949 and 1972, with the largest peak in 1949. However, its concentrations did not show a systematic increase in the last century although the concentration peaks seemingly corresponded to the higher ambient temperatures in the northern high latitudes. In contrast, dehydroabietic acid, a specific tracer of the pyrolysis of conifer resin, showed a gradual increase from the early 1900s to 1990s with a significant peak in 1970. Contributions of dehydroabietic acid to TOC also showed an increasing trend for the 20th century. Similarly, vanillic and p-hydroxybenzoic acids presented higher concentrations in the last half-century with sporadic peaks in 1705, 1759 and 1949. This study showed that general biomass burning tracers such as levoglucosan have been sporadically transported over the glacier of the Kamchatka Peninsula. In contrast, the ice core record of dehydroabietic acid indicated that fires of boreal conifer forest have more frequently and increasingly occurred in Far East and Siberia during the last century and transported to the Northwestern Pacific. The present study demonstrates that organic tracers of biomass burning preserved in ice core could provide historical records of biomass burning and boreal forest fires.
1 0 0 0 OA MRI検査におけるインプラントと体内外金属物質の情報集約
- 著者
- 小林 昌樹 小林 正人 染野 竜也 内山 弘実 小野 祐樹
- 出版者
- 公益社団法人 日本放射線技術学会
- 雑誌
- 日本放射線技術学会雑誌 (ISSN:03694305)
- 巻号頁・発行日
- vol.67, no.10, pp.1314-1319, 2011-10-20 (Released:2011-10-26)
- 参考文献数
- 5
- 被引用文献数
- 1
In Japan, various types of MRI equipment, having varying magnetic field strengths, are widely used. However, the biggest problem encountered while utilizing an MRI is the scarcity of information and guidelines pertaining to implants, internal, and external metallic objects. This leads to uncertainty when an unspecified object is encountered during an examination andcreates the possibility of performing an ambiguous MRI. Therefore, this study classified a range of objects into 12 categories using database management software. An attempt was made to create an environment where reference and comparison of products could be performed. This study also investigated the ways and extent to which medical equipment package inserts reference the MRI. With the co-operation of various corporations and the use of information such as medical equipment package inserts, product information was collected and an environment for the reference and comparison of products became available. In addition, it became apparent while examining these package inserts that orthopedic products had the least information available. It is likely that this information will be useful in medical settings and this kind of database will become increasingly necessary in the future.