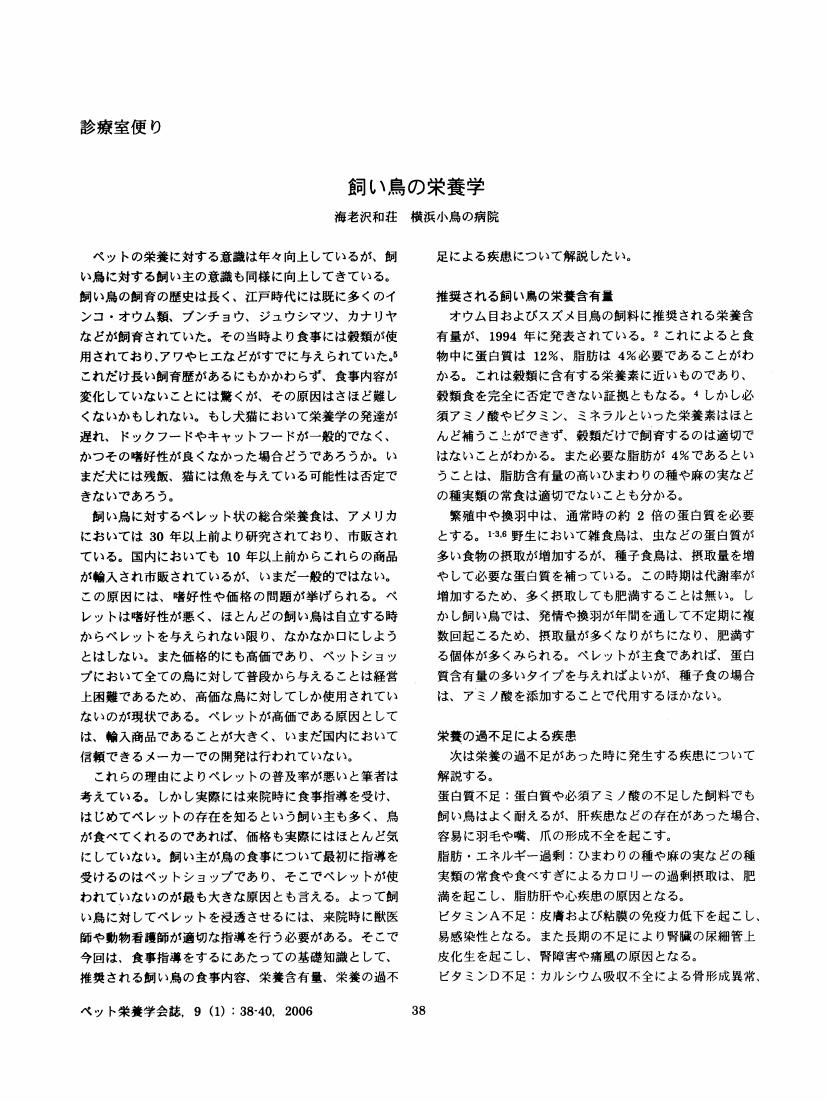4 0 0 0 OA 南洋群島統治と宗教 : 一九一四〜二二年の海軍統治期を中心にして
- 著者
- 出岡 学
- 出版者
- 公益財団法人 史学会
- 雑誌
- 史学雑誌 (ISSN:00182478)
- 巻号頁・発行日
- vol.112, no.4, pp.477-497, 2003-04-20 (Released:2017-12-01)
This article intends to analyze the religious policy of the Japanese Navy, which occupied Micronesia in 1914, in relation to the international situation at that time. At the beginning of its occupation, the Navy permitted German missionaries to inhabit the Islands and educate the natives out of "respect for civil rights". However, after schools were established in the Islands by the Japanese, the missionaries were sent into exile from the Islands. Their absence caused difficulties in ruling over the native people, so the Navy decided to introduce Japanese priests into the Islands. After the Germans were exiled from the territory occupied by the Allies, the Japanese Navy commanded the German missionaries to leave the Islands in June 1919. The introduction of Japanese missionaries was determined by the Japanese cabinet out of fear that American missionaries would flood the Islands. Because their activities were remarkable in the movement for the independence in Korea beginning on March 1, 1919. To banish missionaries of American Board of Commissioners for Foreign Missions from the Islands, the Navy, first, negotiated with the Japanese Congregational Church, but the Treaty of Versailles obliged the Navy to assign Catholic missionaries to Catholic Churches. So the Navy also began negotiations with the Vatican. Consequently, Japanese missionaries of the Japanese Congregational Church and Roman Catholic Spanish missionaries were introduced into the Islands. The author concludes that the Japanese Navy became interested in introducing missionaries into Micronesia, not simply because ruling the natives would have been difficult without religion, but because the international situation in those days compelled the Navy to introduce missionaries into the Islands, with extreme subtlety and minute attention.
4 0 0 0 OA 我々はどのようにしたら「言説」に支配されないのか?
- 著者
- 楊 沛 ヨウ ハイ
- 雑誌
- 立教大学ランゲージセンター紀要 = The journal of Rikkyo University Language Center
- 巻号頁・発行日
- vol.38, pp.99-118, 2017-10-25
4 0 0 0 OA 官報
- 著者
- 大蔵省印刷局 [編]
- 出版者
- 日本マイクロ写真
- 巻号頁・発行日
- vol.1930年11月06日, 1930-11-06
4 0 0 0 OA 官報
- 著者
- 大蔵省印刷局 [編]
- 出版者
- 日本マイクロ写真
- 巻号頁・発行日
- vol.1922年06月09日, 1922-06-09
4 0 0 0 OA 官報
- 著者
- 大蔵省印刷局 [編]
- 出版者
- 日本マイクロ写真
- 巻号頁・発行日
- vol.1930年10月24日, 1930-10-24
4 0 0 0 モンゴル(Mongol)帝國(大元)の華北投下領硏究
- 著者
- 舩田 善之
- 出版者
- 朋友書店
- 雑誌
- 中国史学 (ISSN:09176578)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, pp.139-156, 2014-10
4 0 0 0 OA 解体新書の神経学
- 著者
- 小川 鼎三
- 出版者
- 順天堂医学会
- 雑誌
- 順天堂医学 (ISSN:00226769)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.1, pp.29-33, 1969 (Released:2014-11-22)
- 著者
- 中村 隆志
- 出版者
- 情報文化学会
- 雑誌
- 情報文化学会誌 (ISSN:13406531)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, no.1, pp.60-65, 2011-07-31
公共空間において「ケータイのディスプレイを見る行為」が目立ち始めた時期,ならびにその増加傾向を探るための調査を行った。今回の調査対象として,恋愛ドラマを活用することの意義を検討し,その上で恋愛ドラマ内に登場するエキストラに注目して調査を行った。1996年から2010年までに放映された恋愛ドラマを調査した結果,「ケータイのディスプレイを見る行為」を行うエキストラは,2000-2001年の間に目立って増え始めたことと,2008-2010年の間に顕著に増加することの2点の確認できた。この2つの増加傾向を引き起こすための条件として,当時の通信環境,ケータイ端末,サービスなどの変化があったことを考察した。
- 著者
- 山田 綾 門間 陽樹 龍田 希 仲井 邦彦 有馬 隆博 八重樫 伸生 永富 良一 エコチル調査宮城ユニットセンター
- 出版者
- 日本運動疫学会
- 雑誌
- 運動疫学研究 (ISSN:13475827)
- 巻号頁・発行日
- pp.2020, (Released:2021-01-13)
目的:日本人女性を対象に,妊娠前および妊娠中,産後1.5年と3.5年の身体活動レベルの経時変化を記述することを主たる目的とし,さらに,産後1.5年と3.5年で低い身体活動レベルを維持してしまう要因について探索的に検討することを目的とした。 方法:子供の健康と環境に関する全国調査(エコチル調査)の宮城ユニットセンター独自の調査に参加同意した女性1,874名を対象とした。身体活動はIPAQ短縮版を用いて,妊娠前,妊娠中,産後1.5年および3.5年に測定し,低身体活動と中高身体活動の2カテゴリーにそれぞれ分類した。さらに,育児期の産後1.5年と3.5年で低い身体活動レベルを維持してしまう要因については,出産時年齢,婚姻状況,学歴,就労状況,出産歴,再妊娠有無,非妊娠時BMI,過去の運動経験の有無,妊娠前および妊娠中の身体活動レベルを説明変数とし,ポアソン回帰分析を実施した。 結果:低身体活動に該当する女性の割合は,妊娠前で51.7%,妊娠中で64.5%,産後1.5年で92.0%となり,産後3.5年では65.3%であった(妊娠前の割合と比較してすべての時点でP < 0.001)。産後1.5年と3.5年で低身体活動を維持してしまう要因は,出産時年齢が高いこと,高学歴,産後の仕事の継続,休止および未就労,過去の運動経験なし,妊娠前と妊娠中の低身体活動レベルであった(P < 0.05)。 結論:妊娠~育児期における女性は低い身体活動レベルに該当する者が多く,産後1.5年で最も高い値を示した。育児期に低身体活動を維持してしまう要因は,高年齢,高学歴,産後の就労継続,未就労および休止,過去の運動経験なし,妊娠前および妊娠中の低身体活動レベルであった。
4 0 0 0 OA 研究ノート 『陳十四夫人伝』と『西遊記』の類似について
- 著者
- 廣田 律子 Hirota Ritsuko
- 出版者
- 神奈川大学
- 雑誌
- 麒麟 (ISSN:09186964)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, pp.25-28, 2009-03-31
4 0 0 0 OA 水棲生物の遊泳運動メカニズム
- 著者
- 伊藤 慎一郎
- 出版者
- バイオメカニズム学会
- 雑誌
- バイオメカニズム学会誌 (ISSN:02850885)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, no.3, pp.203-206, 2010 (Released:2016-04-15)
- 参考文献数
- 1
水棲生物を系統樹から形態学的に分類すると彼らの遊泳運動メカニズムが大まかに分類できてくる.さらに生活形態を見ると運動形態が自ずと定まってくる.彼らの運動メカニズムは大きく揚力推進メカニズムと抗力推進メカニズムとに二分できる.前者は恒常的に遊泳するもの,後者は逆に常日頃は不活発であるが,非常時には瞬発力を発揮できるものである.生活形態が中心となって,自然淘汰によって生活に関わるエネルギーが最小になるように運動モードが決定しているようである.本解説ではそれぞれのメカニズムを述べると共に,さらに分類できるものは具体例を挙げて詳細な運動メカニズムを述べている.
4 0 0 0 OA 飼い鳥の栄養学
- 著者
- 海老沢 和荘
- 出版者
- 日本ペット栄養学会
- 雑誌
- ペット栄養学会誌 (ISSN:13443763)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, no.1, pp.38-40, 2006-04-10 (Released:2012-09-24)
- 参考文献数
- 6
4 0 0 0 IR 講演 リューベック法の体系化 : バルデヴィク写本(1294年)をめぐって
- 著者
- コルデス アルブレヒト 田口 正樹
- 出版者
- 北海道大学大学院法学研究科
- 雑誌
- 北大法学論集 = The Hokkaido law review (ISSN:03855953)
- 巻号頁・発行日
- vol.71, no.1, pp.117-140, 2020
4 0 0 0 OA 新自由主義的統治に関する批判的考察 : フーコーの統治性理論を手がかりに
- 著者
- 張 林倩 ZHANG Linqian
- 出版者
- 名古屋大学大学院教育発達科学研究科
- 雑誌
- 名古屋大学大学院教育発達科学研究科紀要. 教育科学 (ISSN:13460307)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, no.1, pp.51-63, 2018-10-01
Neoliberalism has gained status as a dominant manner of discourse since the 1970’s, yet its concepts remain vague and difficult to evaluate. Foucault’s Theory of Governmentality offers a theoretical framework from which to critically evaluate neoliberalism. This paper attempts to reconsider neoliberalism critically using Foucault’s Theory of Governmentality. First, I review the history of neoliberalism and describe its characteristics. Neoliberalism, first created in Germany and the United States in 1930’s, was not the regression of Classical liberalism; rather it was attempt to demarcate the possibility and limitation of government intervention. Next, utilizing Foucault’s Theory of Governmentality, I reexamine neoliberalism critically. According to neoliberal governance, economic growth gives justification to the state when it experiences a crisis. When this occurs, the positions of economic power and legal power within a society are reversed. Thus, neoliberalism has the effect of breaking down the border between the social arena and the market; society becomes commercialized and market by homo-economics. This results is an internalization of the market principle, with society governing via investing in itself in order to manage risk, In this way, neoliberalism makes it possible to justify itself by reorganizing the legal system. Additionally, neoliberalism established a hegemony by producing a system of homo-economics with its neoliberal governing model.
4 0 0 0 OA 小沢登高氏の業績
- 著者
- 河東 泰之
- 出版者
- 一般社団法人 日本数学会
- 雑誌
- 数学 (ISSN:0039470X)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, no.4, pp.419-426, 2009 (Released:2012-02-29)
- 参考文献数
- 43
4 0 0 0 OA 磁気圏ダイナモと磁気圏磁場トポロジー
4 0 0 0 La défaite de l'érudition
- 著者
- Blandine Barret-Kriegel
- 出版者
- Presses universitaires de France
- 巻号頁・発行日
- 1988