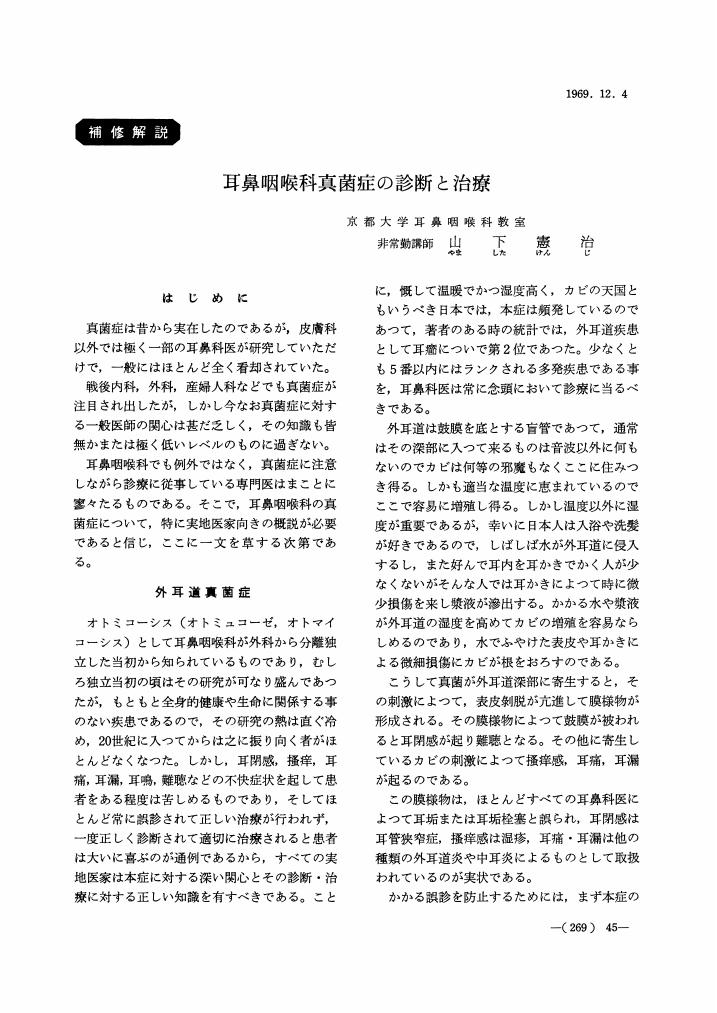3 0 0 0 OA 五苓散が奏効した癌性腹膜炎腹水の一例
- 著者
- 雨宮 修二
- 出版者
- The Japan Society for Oriental Medicine
- 雑誌
- 日本東洋医学雑誌 (ISSN:02874857)
- 巻号頁・発行日
- vol.44, no.2, pp.179-184, 1993-10-20 (Released:2010-03-12)
- 参考文献数
- 3
- 被引用文献数
- 2 2
末期胃癌に伴い大量の腹水が貯留した患者に対し五苓散を用い, 大量利尿を通じて腹水が減少し退院させることができた。経過中西洋医学的利尿剤は一切使用せず, 電解質の乱れはまったくみられなかった。
3 0 0 0 OA 立位での前足部荷重における多裂筋・最長筋・腸肋筋の筋活動について
- 著者
- 國枝 秀樹 末廣 健児 大沼 俊博 渡邊 裕文 石濱 崇史 鈴木 俊明
- 出版者
- 関西理学療法学会
- 雑誌
- 関西理学療法 (ISSN:13469606)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, pp.43-47, 2014 (Released:2014-12-27)
- 参考文献数
- 5
- 被引用文献数
- 1
The purpose of this study was to investigate the electromyographic (EMG) activities of the multifidus, longissimus, and iliocostal muscles in the standing and forefoot standing positions in order to understand the relationship between each muscle activity and thoracolumbar extension in the forefoot standing position. This study recruited 10 healthy male volunteers (mean age: 28.4 ± 6.1 years). The EMG activities of the multifidus, longissimus, and iliocostal muscles were measured in the standing and forefoot standing positions. The values of the integrated EMG activities of each task were compared. Each muscle showed a significant increase in the value of the integrated EMG activities in the forefoot standing position (p<0.01). The activities of the iliocostal muscles were separated into two types: Group A, in which the EMG activities did not increase much, and Group B, in which the EMG activities clearly increased. In group A, the forefoot standing position involved extension of the hip joint, and lumbar alignment was almost identical to that in the standing position. In group B, lumbar lordosis and anteversion of the pelvis were significantly greater in the forefoot standing position than in the standing position.
3 0 0 0 OA 社会調査の困難
- 著者
- 桜井 厚
- 出版者
- The Japan Sociological Society
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.4, pp.452-470, 2003-03-31 (Released:2009-10-19)
- 参考文献数
- 40
- 被引用文献数
- 1
社会調査は, 現代社会で認知され定着してきた一方で, さまざまな問題や困難な状況に直面している.それらの問題を大きくわければ, ひとつは社会調査の方法論に関する社会学の問題, もうひとつは調査の対象とされる社会の側から要請される問題があげられる.本稿では, 方法論の混乱と対立がおもに伝統的な実証主義的立場とあたらしく台頭した構築主義的立場の認識枠組みの違いにあり, 社会における困難とは調査者と被調査者の関係を軸にしたポリティクスと倫理の問題であると考え, それらの実情と論点について述べた.実証主義と構築主義の認識枠組みは, 何を現実と考えどのように把握するかで大きく異なる.社会的現実は唯一の事実なのか, それともフィクションなのか.調査過程は, 被調査者から情報を引き出すことなのか, それとも被調査者と相互的に現実を構築することなのか.さらに, 調査者と被調査者の関係が構造と相互性の2つのレベルの非対称性によって構成されていることに注意を促し, それをふまえながらもその変革のさまざまな可能性についてもふれている.また, それにともなう調査倫理の制度化の必要性と制度化にあたっての困難にも言及した.
3 0 0 0 OA 発達障害を併せ有する聴覚障害児と手話
- 著者
- 大鹿 綾
- 出版者
- 日本手話学会
- 雑誌
- 手話学研究 (ISSN:18843204)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, pp.31-38, 2016-12-15 (Released:2017-12-27)
- 参考文献数
- 18
- 被引用文献数
- 1
Oshika et al (2014) suggested that 37.4% of Deaf or Hard-of-Hearing children had developmental disorders-like difficulties. This figure may include secondary difficulties due to hearing impairment. However, it seems to be a higher than that of hearing children (6.5%). Deaf or Hard-of-Hearing children with Learning Disabilities may show some hardship in their language usages. High image representation of the sign language may support them to develop the network through their language, and to understand Japanese grammar. Deaf or Hardof-Hearing children with Autism Spectrum Disorder sometimes have difficulties in communication achievement because of unique expression of their sign language, and weakness of the situation understanding and metacognition. It will be useful for them to learn how to talk with the other party into their consideration, to device how to SST (Four-panel cartoon, use of video).
3 0 0 0 OA 敗走者の生と真理 : 大岡昇平をめぐって
- 著者
- 丹生谷 貴志
- 出版者
- 神戸市外国語大学外国学研究所
- 雑誌
- 神戸市外国語大学外国学研究 = Annals of foreign studies (ISSN:02899256)
- 巻号頁・発行日
- vol.79, pp.151-206, 2011-03-31
- 著者
- 堀 智弘
- 出版者
- 一般財団法人 日本英文学会
- 雑誌
- 英文学研究 支部統合号 (ISSN:18837115)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, pp.63-70, 2018 (Released:2019-02-07)
3 0 0 0 OA 発音評価の相違
- 著者
- 渡辺 裕美 松崎 寛
- 出版者
- 公益社団法人 日本語教育学会
- 雑誌
- 日本語教育 (ISSN:03894037)
- 巻号頁・発行日
- vol.159, pp.61-75, 2014 (Released:2017-03-21)
- 参考文献数
- 22
- 被引用文献数
- 1
日本人教師,ロシア人教師,一般日本人各20名にロシア語母語話者の発音評価を求め,その評定値と,評価後のコメントを分析した。分析の結果,日本人教師は,ロシア語母語話者の典型的な発音特徴が見られた場合に評価が厳格化し,日本語母語話者にとっての異音が見られた場合に評価が寛大化した。一方,ロシア人教師は,ロシア語の単音やストレスアクセントなどのロシア語の特徴が見られた場合に評価が厳格化し,「ほんをよむ」が「ほのよむ」になるような,拍の減少と[n]が同時に見られた場合に評価が寛大化した。以上の結果をもとに,教師の評価特性について考察した。
- 著者
- 増田 都希
- 出版者
- 日仏歴史学会
- 雑誌
- 日仏歴史学会会報 (ISSN:24344184)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, pp.18-34, 2015 (Released:2020-04-01)
3 0 0 0 OA 耳鼻咽喉科真菌症の診断と治療
- 著者
- 山下 憲治
- 出版者
- 耳鼻咽喉科展望会
- 雑誌
- 耳鼻咽喉科展望 (ISSN:03869687)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, no.4, pp.269-276, 1969-08-15 (Released:2011-08-10)
3 0 0 0 OA 雇用形態が男性の結婚に与える影響
- 著者
- 趙 〓 水ノ上 智邦
- 出版者
- 日本人口学会
- 雑誌
- 人口学研究 (ISSN:03868311)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, pp.75-89, 2014-06-30 (Released:2017-09-12)
- 被引用文献数
- 1
本研究の目的は,晩婚化・非婚化問題の原因解明のため,男性の結婚に焦点を当て,男性の結婚経験は雇用形態によりどのような影響を受けているのかについて「就業構造基本調査(平成19年)」(総務省)を用いて実証的に分析することである。本稿では,女性は結婚相手の選択に際し,男性の将来所得を示すシグナルを観察し,それを基に結婚を決定しているという仮説を立てる。男性の将来所得のシグナルとしては,現在の雇用形態(正規雇用,非正規雇用),初職の雇用形態,職業や学歴などが利用されると考えられる。上記仮説を,「就業構造基本調査」の個票データを用いて検証し,男性の結婚経験率に与える要因を分析した。さらに,その要因が年齢階級によってどのように変容するのかを分析している。分析結果から得られた知見は次の通りである。第1に,将来所得のシグナルである雇用形態が,全年齢階級にわたって男性の結婚経験に影響を与える。具体的には非正規雇用と非就業であることが結婚経験率を低下させる。第2に,初職の雇用形態が非正規であったことは,それ以前の世代とは異なり,バブル崩壊以後に大学を卒業した世代に対して結婚経験の確率を低下させた可能性がある。第3に,学歴は20代から30代においては将来所得のシグナルとして有効ではなく,むしろ高学歴であることは若年層において結婚のタイミングを遅らせる効果を持つことが明らかになった。
3 0 0 0 OA 古代アステカ社会における「戦争」の機能
- 著者
- 井関 睦美
- 出版者
- 明治大学教養論集刊行会
- 雑誌
- 明治大学教養論集 (ISSN:03896005)
- 巻号頁・発行日
- vol.499, pp.1-20, 2014-03-31
3 0 0 0 OA 脳波の基礎知識
- 著者
- 人見 健文 池田 昭夫
- 出版者
- 一般社団法人 日本臨床神経生理学会
- 雑誌
- 臨床神経生理学 (ISSN:13457101)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, no.6, pp.365-370, 2014-12-01 (Released:2016-02-25)
- 参考文献数
- 7
- 被引用文献数
- 1
脳波記録に携わる技師は, 電極配置法, モンタージュ, 電極のタイプ, インピーダンス, フィルターの原理を理解した上で, 脳波計の設定や電極装着を行う必要がある。検査開始後は, 正常および異常の脳波, 賦活時の脳波変化などに注意しつつ脳波記録を行う。さらに近年普及したデジタル脳波計の特徴を生かして, Density modulated spectral array (DSA) の活用, あるいはモニター上で脳波記録中の表示に適切なモンタージュの切り換えを行い, リアルタイムでより適切な脳波活動の評価を行うことがのぞまれる。また検査技師も脳波の判読の過程と結果を積極的に活用して脳波判読医と互いの情報意識の共有を行う。判読者の立場も理解した上で脳波記録を行うことで, 総合的な脳波検査と判読の質的維持と向上がもたらされる。臨床発作時あるいは脳波上発作パターンが出現した場合には, 適宜医師および他の検査技師に連絡し対処する役割も求められる。
3 0 0 0 OA 音楽再生音の最適聴取レベルにおける男女間の差
- 著者
- 濱村 真理子 岸上 直樹 岩宮 眞一郎
- 出版者
- 一般社団法人 日本音響学会
- 雑誌
- 日本音響学会誌 (ISSN:03694232)
- 巻号頁・発行日
- vol.70, no.10, pp.525-533, 2014-10-01 (Released:2017-06-02)
様々な楽曲を用いた最適聴取レベルの測定実験を調整法によって行い,男女の間で音楽の最適聴取レベルに差が生じ,男性の聴取レベルの方が高いことを明らかにした。男女の最適聴取レベルに差が生じる要因を検討するために,音楽再生音とノイズの大きさ評価実験を行った。いずれの刺激の場合も男性の方が女性よりも同一呈示音圧レベルの音をより「小さい」と評価していた。女性の最適聴取レベルは男性にとっては「小さい」と感じられている可能性がある。そのため,男性が「丁度よい」と感じるには女性の最適聴取レベルよりも聴取レベルを高く設定する必要が生じ,その結果として男女の音楽再生音の最適聴取レベルに差が生じたと考えられる。
- 著者
- Natsuki Sugaya Shion Tanaka Kenji Keyamura Shunsuke Noda Genki Akanuma Takashi Hishida
- 出版者
- The Genetics Society of Japan
- 雑誌
- Genes & Genetic Systems (ISSN:13417568)
- 巻号頁・発行日
- pp.23-00013, (Released:2023-06-16)
- 参考文献数
- 56
- 被引用文献数
- 1
Homologous recombination (HR) is a highly accurate mechanism for repairing DNA double-strand breaks (DSBs) that arise from various genotoxic insults and blocked replication forks. Defects in HR and unscheduled HR can interfere with other cellular processes such as DNA replication and chromosome segregation, leading to genome instability and cell death. Therefore, the HR process has to be tightly controlled. Protein N-terminal acetylation is one of the most common modifications in eukaryotic organisms. Studies in budding yeast implicate a role for NatB acetyltransferase in HR repair, but precisely how this modification regulates HR repair and genome integrity is unknown. In this study, we show that cells lacking NatB, a dimeric complex composed of Nat3 and Mdm2, are sensitive to the DNA alkylating agent methyl methanesulfonate (MMS), and that overexpression of Rad51 suppresses the MMS sensitivity of nat3Δ cells. Nat3-deficient cells have increased levels of Rad52-yellow fluorescent protein foci and fail to repair DSBs after release from MMS exposure. We also found that Nat3 is required for HR-dependent gene conversion and gene targeting. Importantly, we observed that nat3Δ mutation partially suppressed MMS sensitivity in srs2Δ cells and the synthetic sickness of srs2Δ sgs1Δ cells. Altogether, our results indicate that NatB functions upstream of Srs2 to activate the Rad51-dependent HR pathway for DSB repair.
3 0 0 0 OA ペルフルオロオクタン酸はラット肝における脂肪酸分解を亢進する
- 著者
- 川畑 公平 川嶋 洋一 工藤 なをみ
- 出版者
- 日本毒性学会
- 雑誌
- 日本毒性学会学術年会 第42回日本毒性学会学術年会
- 巻号頁・発行日
- pp.P-77, 2015 (Released:2015-08-03)
【目的】フッ素化界面活性剤であるペルフルオロオクタン酸(PFOA)は難燃剤、乳化剤、撥水剤等に使用されてきたが、化学的に安定で環境中に残留し、また、ヒトにおける半減期が長いため、ヒトの健康への影響が懸念されている。PFOAをラットに投与すると、脂質代謝が広範に撹乱され、脂肪酸のβ酸化に関与する酵素が誘導されることが報告されている。一方で、ペルフルオロカルボン酸を投与すると肝臓にトリグリセリド(TG)が蓄積される。そこで本研究では、肝スライスを用いてPFOAにより脂肪酸のβ酸化が亢進するかを評価した。【方法】9週齢の雄性WistarラットにPFOA0.01% (w/w)含有飼料を1週間摂取させた。ラットより肝臓を採取し、precision cut sliceを調製し、Krebs-Henseleit buffer中で[14C]16:0また[14C]18:1n-9とインキュベートし、ex vivoで代謝物の生成速度を測定した。また、肝ホモジネートを用いて、in vitroでのミトコンドリアとペルオキソームのβ酸化活性を評価した。肝TGおよびリン脂質の量は、構成脂肪酸をGCで分析することにより定量した。【結果および考察】肝スライスを用いると、PFOA群における16:0および18:1n-9のβ酸化活性は、それぞれ対照群の約1.5倍、1.7倍に上昇した。ホモジネートを用いて評価したところ、16:0および18:1n-9のβ酸化活性はミトコンドリアでそれぞれ1.9倍、2.4倍、ペルオキソームでそれぞれ3.2倍、1.9倍に上昇した。PFOA群における肝臓中の総脂肪酸量は対照群と比較してむしろ有意に増加した。以上の結果より、PFOAを投与すると肝臓のβ酸化活性が上昇するにもかかわらず、肝臓中の脂肪酸量は低下しないことが明らかとなった。
3 0 0 0 OA 候補者の「声」の高低と得票率 : 2014年衆議院選挙小選挙区立候補者の分析
- 著者
- 岡田 陽介 オカダ ヨウスケ Yosuke Okada
- 雑誌
- 応用社会学研究 = The journal of applied sociology
- 巻号頁・発行日
- vol.63, pp.97-112, 2021-03-24
3 0 0 0 OA 18世紀モスクワにおけるペストの流行と暴動に関する史料
- 著者
- 豊川 浩一
- 出版者
- 駿台史学会
- 雑誌
- 駿台史學 (ISSN:05625955)
- 巻号頁・発行日
- vol.178, pp.99-125, 2023-03-23
3 0 0 0 OA 『ユートピアと社会主義』序文
- 著者
- レヴィナス エマニュエル 合田 正人
- 出版者
- 京都ユダヤ思想学会
- 雑誌
- 京都ユダヤ思想 (ISSN:21862273)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, no.2, pp.S402-S407, 2019-06-29 (Released:2023-04-13)
3 0 0 0 OA 分子シミュレーション入門 1 モンテカルロ法と分子動力学法の誕生
- 著者
- 三上 益弘
- 出版者
- 分子シミュレーション学会
- 雑誌
- アンサンブル (ISSN:18846750)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, no.2, pp.108-112, 2018-04-30 (Released:2019-07-04)
- 参考文献数
- 32
初回は,モンテカルロ法と分子動力学法の誕生の歴史について述べたい.モンテカルロ(MC)法の誕生の契機は第二次世界大戦中の原子爆弾の開発において,媒質中の中性子拡散を正確に予測するために,主としてスタン・ウラムにより創始され,フォン ノイマンはその命名者となった.一方,分子動力学(MD)法は,アルダーらにより,剛体球系で創始され,ソフトコア系に拡張され結晶の放射線損傷のシミュレーションに適用された.その後,MC, MD法ともに物質科学に本格的に利用されるようになった.