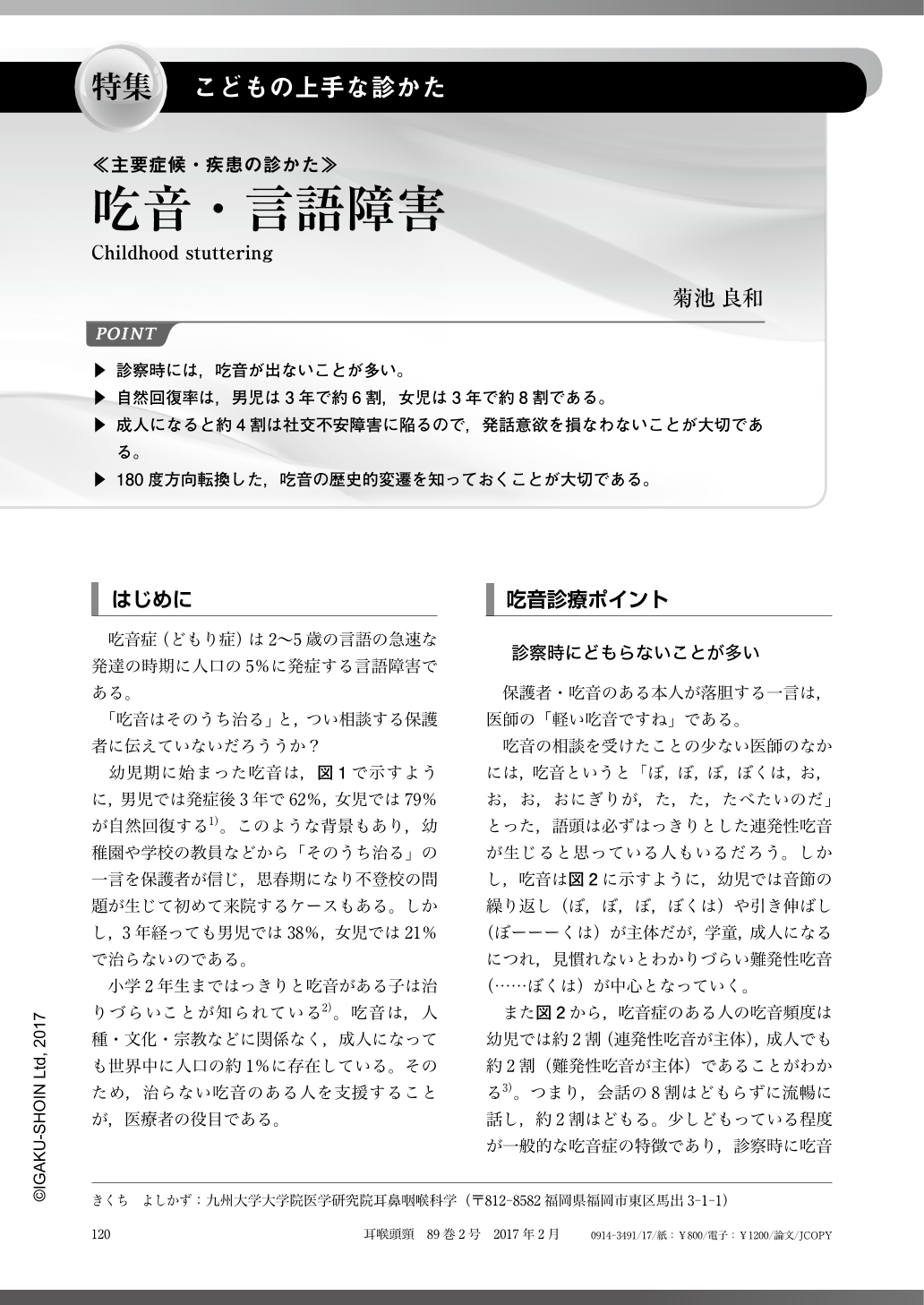3 0 0 0 歎異抄の英訳
- 著者
- 撫尾 清明
- 出版者
- 九州龍谷短期大学
- 雑誌
- 九州龍谷短期大学紀要 (ISSN:09116583)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, pp.A349-A385, 1993-03-20
3 0 0 0 高麗郡 (Komagun) 一三〇〇年 : 物と語り : 特別展
- 著者
- 埼玉県立歴史と民俗の博物館 [編]
- 出版者
- 埼玉県立歴史と民俗の博物館
- 巻号頁・発行日
- 2016
3 0 0 0 OA 時間制約と時間圧力が品質評価に与える影響の検討
- 著者
- 三富 悠紀 秋池 篤
- 出版者
- 特定非営利活動法人 グローバルビジネスリサーチセンター
- 雑誌
- 赤門マネジメント・レビュー (ISSN:13485504)
- 巻号頁・発行日
- pp.0170508a, (Released:2018-01-18)
- 参考文献数
- 32
消費者は時間圧力を感じた時に、時間圧力を感じていない時とは異なる行動をとることがこれまで指摘されてきた。しかしながら、先行研究では外在的に与えられる時間制約と消費者自身が内在的に感じる時間圧力について区別する必要性が指摘されているものの両者を同時にとらえようとした定量的な分析は不足している。本稿ではこの点に着目し、時間制約の有無と時間制約の強さを操作した上で、消費者に電気ケトルの品質を評価してもらい、時間圧力を測定した。測定結果を分析した結果、時間制約は消費者の品質評価に直接影響は与えておらず、時間圧力を介して間接的に影響を与えていることが明らかとなった。本結果より、消費者自身が内在的に感じる時間圧力を重視した分析をする必要性が示される。
- 出版者
- 労務行政
- 雑誌
- 労政時報 (ISSN:13425250)
- 巻号頁・発行日
- no.3834, pp.11-25, 2012-11-23
3 0 0 0 OA カーリングのストーンが曲がるメカニズム -シンプルな左右説の提案-
- 著者
- 亀田 貴雄 佐渡 公明 鹿野 大貴
- 出版者
- 公益社団法人 日本雪氷学会/日本雪工学会
- 雑誌
- 雪氷研究大会講演要旨集 雪氷研究大会(2017・十日町) (ISSN:18830870)
- 巻号頁・発行日
- pp.140, 2017 (Released:2017-12-14)
3 0 0 0 OA カーリングストーンのカール機構 -前後摩擦差起因説の検討-
- 著者
- 対馬 勝年 森 克徳
- 出版者
- 公益社団法人 日本雪氷学会/日本雪工学会
- 雑誌
- 雪氷研究大会講演要旨集 雪氷研究大会(2016・名古屋) (ISSN:18830870)
- 巻号頁・発行日
- pp.83, 2016 (Released:2017-02-18)
3 0 0 0 OA 流氷観光船ガリンコ号2
- 著者
- 高山 鉄章 播田 安弘
- 出版者
- 公益社団法人 日本マリンエンジニアリング学会
- 雑誌
- 日本舶用機関学会誌 (ISSN:03883051)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.8, pp.584-590, 1998-08-01 (Released:2010-05-31)
- 被引用文献数
- 1 1
“Garinko-go2”is a new type Icebreaking vessel with Archimedean cylindrical screw-rotors at the bow as means for breaking ice floes, and has such features as larger Icebreaking capability as compared with conventional ones. In the ice sea, by rotating the Icebreaking rotors, spiral blades arranged around them dig into ice surfaces, and thus, their rotational motion enables the vessel to move ahead while breaking ice. This vessel can break 0.4m-thick ice floes at a speed of 2 knots, and maximum breakable ice thickness is about 0.6mMain particulars of this vessel are as follow: 150 gross tons, length overall 35m, width 7m, depth 2.7m, draft 1.9m, 1010 ps diesel engine lset, 195 passengers, and crusing speed 10 knots. Two Archimedean cylindrical screw-rotors are driven by hydraulic motors with a 500 ps diesel engine.This vessel was built in October 1996 for full-fledged commerical navigation to succeed her predecessor“Garinko-go”which had been in operation since 1987 until 1996, and then put into operation in Feburary 1997 off the Monbetsu coast in the Sea of Okhotsk to where lots of ice floes drift from Siberia.
3 0 0 0 読む 綿矢りさ「勝手にふるえてろ」論
- 著者
- 小谷 瑛輔
- 出版者
- 日本文学協会
- 雑誌
- 日本文学 (ISSN:03869903)
- 巻号頁・発行日
- vol.64, no.6, pp.52-56, 2015-06
3 0 0 0 OA 頭書増補訓蒙圖彙 21巻
3 0 0 0 OA J-GLOBAL knowledge
- 著者
- 木村 考宏 川村 隆浩 渡邊 勝太郎 松本 尚也 佐藤 智宣 櫛田 達矢 松邑 勝治
- 出版者
- 一般社団法人 人工知能学会
- 雑誌
- 人工知能学会論文誌 (ISSN:13460714)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.2, pp.N-F73_1-12, 2016-03-01 (Released:2016-03-31)
- 参考文献数
- 9
- 被引用文献数
- 1 1
In order to develop innovative solutions in science and technology, Japan Science and Technology Agency (JST) has built J-GLOBAL knowledge (JGk), which provides papers, patents, researchers' information, technological thesaurus, and scientific data as Linked Data, which have been accumulated by JST since 1957. The total size of all datasets is about 15.7 billion triples, and the JGk website provides a SPARQL endpoint to access part of the datasets. This paper describes several issues on schema design to construct a large-scale Linked Data, and construction methods, especially for linking to external datasets, such as DBpedia Japanese. Finally, we describe performance problems and the future works.
- 著者
- Paul WICKING
- 出版者
- Japan Language Testing Association
- 雑誌
- JLTA Journal (ISSN:21895341)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, pp.76-89, 2017 (Released:2017-12-13)
- 参考文献数
- 2
- 被引用文献数
- 3
Any discussion about English education in Japan is invariably bound up with a discussion about assessment. All too often, such discussions have focused on entrance examinations and other high stakes summative tests. However, language testing and assessment do not take place in a vacuum, but are deeply affected by broader social and cultural contexts, as well as individual features of the school and the classroom. In particular, perhaps more than any other factor, it is the teachers who have great influence over how tests are created, conducted and interpreted. In order for universities to foster an environment in which reliable assessment can take place, it is not enough to provide well-designed, rigorous tests. It is also imperative that teachers’ beliefs and practices concerning assessment be taken into account. This paper seeks to answer the question, what are the assessment beliefs and practices of EFL teachers working in Japanese universities? To answer this question, survey responses were gathered from English language teachers working in Japanese higher education. The results indicated some slight differences in belief and practice between native speaker teachers and non-native speaker teachers, as well as between full-time and part-time teachers. Despite these differences, it seems that most teachers have a learning-oriented approach to assessment. The findings provide support and direction for policy-makers and educational leaders seeking to promote better testing practice.
3 0 0 0 OA ドールハウスとメルヘンの世界
- 著者
- 梅本 建夫
- 出版者
- 神戸文化短期大学
- 雑誌
- 神戸文化短期大学研究紀要 (ISSN:09167870)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, pp.27-39, 1996-03-31
3 0 0 0 ドゥルーズと美学(平成九年度博士論文(課程)要旨)
- 著者
- 前田 茂
- 出版者
- 大阪大学
- 雑誌
- 大阪大學文學部紀要 (ISSN:04721373)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, pp.124-125, 1999-03-10
3 0 0 0 OA アメリカにおけるエアリア・スタデイによる日本研究と日本の近代化
- 著者
- Yukiko N. Bedford
- 出版者
- 一般社団法人 人文地理学会
- 雑誌
- 人文地理 (ISSN:00187216)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.6, pp.504-517, 1980-12-28 (Released:2009-04-28)
- 参考文献数
- 95
3 0 0 0 吃音・言語障害
- 著者
- 菊池 良和
- 出版者
- 医学書院
- 雑誌
- 耳鼻咽喉科・頭頸部外科 (ISSN:09143491)
- 巻号頁・発行日
- vol.89, no.2, pp.120-124, 2017-02-20
POINT ●診察時には,吃音が出ないことが多い。 ●自然回復率は,男児は3年で約6割,女児は3年で約8割である。 ●成人になると約4割は社交不安障害に陥るので,発話意欲を損なわないことが大切である。 ●180度方向転換した,吃音の歴史的変遷を知っておくことが大切である。
3 0 0 0 OA 大学1年次コンピュータリテラシ科目でのアセンブリ言語プログラミング体験
- 著者
- 植村 修二
- 出版者
- 日本雑草防除研究会
- 雑誌
- 雑草研究 (ISSN:0372798X)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.2, pp.36-45, 2012-06
筆者が「帰化植物メーリングリスト」へ投稿した情報などをもとに,帰化植物の同定,侵入・定着の近年の特徴,定着後の分散についてまとめた。輸入物資を扱う貿易港やそれらが運ばれる工場などは,第二次大戦後非意図的に帰化植物が繰り返し集中して侵入したため「帰化センター」と呼ばれた。現在,「帰化センター」として機能する場所は激減したが,輸入緑化種子や園芸用土の夾雑種子,観賞用植物の逸出やマニアによる移植など侵入経路は多岐にわたり,帰化植物の侵入が広範囲にわたっている。定着後の分散事例としては,花が美しいため意識的に除草を免れて道路沿いに伝搬したナガミヒナゲシ,都市部や市街地の舗道に適応した路面間隙雑草や大規模開発に伴う造成地に広がる先駆植物となる帰化植物などが挙げられる。問題となる帰化植物の侵入,分散および繁茂に対しては,刈り取りを行うことで抑制することが有効な手段になりうる。
3 0 0 0 OA 心不全とCOPD
- 著者
- 弓野 大
- 出版者
- 公益財団法人 日本心臓財団
- 雑誌
- 心臓 (ISSN:05864488)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, no.4, pp.398-401, 2013 (Released:2014-09-13)
- 参考文献数
- 13