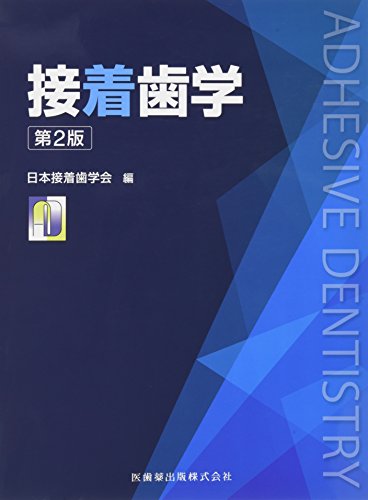3 0 0 0 OA 室生犀星「浮気な文明」の周辺 : 犀星のおせっかいと朔太郎の離婚
- 著者
- 高瀬 真理子 タカセ マリコ Mariko Takase
- 雑誌
- 実践女子短期大学紀要
- 巻号頁・発行日
- vol.30, pp.A1-A12, 2009-03
3 0 0 0 「脆弱性(Vulnerability)」とは何か
- 著者
- 池谷 壽夫
- 出版者
- 名古屋哲学研究会
- 雑誌
- 哲学と現代 (ISSN:03878821)
- 巻号頁・発行日
- no.31, pp.59-77, 2016-02
- 著者
- Marie Tabaru Ryusuke Fujino Kentaro Nakamura
- 出版者
- ACOUSTICAL SOCIETY OF JAPAN
- 雑誌
- Acoustical Science and Technology (ISSN:13463969)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.2, pp.167-170, 2015-02-01 (Released:2015-03-01)
- 参考文献数
- 9
- 被引用文献数
- 3
3 0 0 0 IR 書評 浜本満著『信念の呪縛 : ケニア海岸地方ドゥルマ社会における妖術の民族誌』
- 著者
- 浜田 明範
- 出版者
- くにたち人類学会
- 雑誌
- くにたち人類学研究 (ISSN:18809375)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, pp.1-9, 2014
本書は、ケニア海岸地方のドゥルマ社会を30 年に亘って調査してきた著者による妖術についての民族誌である。著者によるドゥルマ社会についての単著としては、2001 年に出版された『秩序の方法:ケニア海岸地方の日常生活における儀礼的実践と語り』[浜本 2001]があり、本書は二冊目に当たる。『秩序の方法』の出版後、著者はジェームズ・クリフォードの『文化の窮状』[クリフォード 2003]を太田好信らと共訳し、その延長線上に編まれた教科書的な論文集『メイキング文化人類学』[太田・浜本 2005]に収められた論文で独自の民族誌論を展開している。本書には、新たに書き下ろされた多くの章が含まれるが、直接的には、2007 年以降に著者が精力的に発表してきた理論的・民族誌的論考の延長線上に位置づけることができる。そのうちのいくつかは加筆修正した上で本書にも採録されており、新たに書き下ろされた章と合わせて一貫性が持たされている。しかし、本書の内容は、2005 年以前の著作とも密接に関連しており、それらとの関連を射程に入れた上で理解されるべきである。
3 0 0 0 OA Publication of a TIGG Special Issue, “Galectins updated: new discoveries, revisions and rebuttals”
- 著者
- Jun Hirabayashi
- 出版者
- FCCA(Forum: Carbohydrates Coming of Age)
- 雑誌
- Trends in Glycoscience and Glycotechnology (ISSN:09157352)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.170, pp.E83-E83, 2017-11-25 (Released:2017-11-25)
3 0 0 0 接着歯学 = Adhesive dentistry
3 0 0 0 「限界集落」とその支援をめぐるエスノグラフィー
- 著者
- 藤守 義光
- 出版者
- 工学院大学
- 雑誌
- 工学院大学研究論叢 (ISSN:21866635)
- 巻号頁・発行日
- no.51, pp.81-95, 2013-10-31
3 0 0 0 OA 令子内親王家の文芸活動-院政前期の内親王とその周辺-
- 著者
- 髙野瀬 惠子 タカノセ ケイコ Keiko TAKANOSE
- 出版者
- 総合研究大学院大学
- 巻号頁・発行日
- 2009-03-24
院政前期において注目すべき人物に令子内親王(1078〜1144)がいる。令子内<br />親王は白河天皇の第三皇女として生まれ、賀茂斎院を勤めた後に鳥羽天皇の准母として皇<br />后となった。院号こそ受けなかったが、院政前期に未婚の皇女が立后して皇室を支えた事<br />例として、その存在の意義は小さくない。そして内親王家で行われた文芸活動もまた考究<br />すべき面を持つ。<br />令子内親王は、母・賢子の養父である藤原師実とその室麗子によって、摂関家で養育さ<br />れた。従って斎院時代(1089〜99)には師実・師通親子の手厚い後見を受けており、<br />摂関家の文化的豊かさを象徴する存在であった。その華やかな内親王家の和歌活動を伝え<br />るのが『摂津集』であり、同じ時期の摂関家の和歌活動を伝えるものに『肥後集』がある。<br />この二集には、摂関家の盛儀歌合や廷臣を率いた花見など、伝統的美意識を継承した催事<br />に関わる和歌が多く収められているが、そこには摂関家の伝統と権威を守り文化的主導権<br />を保ち続けようとする師実・師通親子の意識の反映がある。この時期の令子内親王家は「摂<br />関家文化圏」にあったと言ってよく、それは先行研究において指摘されていた。しかし、<br />令子内親王斎院期には、紫野の斎院御所に於いて神楽が年二回(夏神楽と相嘗祭後朝神楽)<br />催行されていたことや、音楽との関わりも多い廷臣と女房の交流などに、芸能流行の時代<br />の貴族社会の一面を具体的に知ることが出来る。<br />令子内親王が斎院を退下した康和元(1109)年六月、関白師通が三十六歳で薨去し<br />た。これにより摂関家が大きな痛手を被り、自河院政が進行する。内親王は退下後も師実<br />夫妻との関係が深かったが、康和三(1101)年二月、師実もまた薨去した。その翌年、<br />令子内親王は同母弟の堀河天皇に寄り添うように内裏に入り、弘徽殿に住むようになった。<br />この時期の『殿暦』『中右記』の記事からは、令子の内裏入りに、堀河天皇と摂関家(忠<br />実)との結合、天皇と白河院との紐帯をそれぞれ強めるという政治的事情もあつたことが<br />察知される。天皇が大切にする姉令子内親王とその女房たちは、今度は天皇を中核とした<br />文芸活動の中に身を置いた。それは『堀河百首』が作られた時期である。内親王自身は歌<br />人ではなかったが、少なからぬ歌詠み女房を擁する前斎院令子方では、中宮篤子方と同様<br />に、天皇側近の歌人らとの盛んな交流が行われた。『大弐集』はこの時期の令子家の生活<br />を具体的に伝えている。ここでは、百首歌と関連する題詠歌、隠し題などの技巧的・遊戯<br />的な歌、漢詩文の影響を受けた物語的な連作等が見られるが、それらにこの時期の天皇と<br />廷臣らの嗜好と新風の模索が表れている。令子家は、堀河天皇を中心とした文化活動の中<br />にあってその特色を体現するものであり、いわゆる「堀河歌壇」の持つ明るく活動的な雰<br />囲気をよく反映していた。<br /> 嘉承二(1107)年、堀河天皇が崩じると、新帝鳥羽が幼少であったことから令子内<br />親王が准母となって立后し,皇后宮となった。これによって令子内親王とその女房らは、<br />今度は「鳥羽天皇後宮文化圏」とでも言うべきものに属することになった。この時期の令<br />子家の具体的な姿を伝える女房歌集はないが、『金葉和歌集』等に皇后宮令子周辺の和歌<br />を拾うことが出来る。遺された断片的な資料から、令子家の和歌活動は小規模で即興性が<br />あり、小弓・蹴鞠・管絃、或いは今様や神楽歌などと場を同じくすることも多かったこと<br />が窺われる。その背景に、内裏や摂関家での大規模な歌合や物合がなくなり、文化活動が<br />「家」レベルや仲間同士で行われる傾向が強まったことがある。令子家の和歌は、総じて<br />個性的なものとも斬新なものとも言い難い、伝統的な詠みぶりである。しかしながら、皇<br />后宮令子が歌詠み女房を多く抱え、また音楽や物語を愛好する「風雅な宮」(『今鏡』)<br />として存したことは、後宮の中心としての必要性に沿ったことでもあった。史料に散見する<br />皇后宮の行事等からも、後宮の伝統を継承し維持することが期待されていたことが窺われ<br />るのである。<br /> このように令子内親王の人生がそのまま内親王家の文芸活動のあり方に影響したため<br />に、その活動は一貫性やオリジナリティーのないものと見なされがちで、文芸の場や内容<br />の詳細と特質に対する研究は十分には行われてこなかった。しかし、強い個性を持たず、<br />貴族社会の状況が色濃く反映したものであつたこと自体に、令子内親王家の特色と存在意<br />義があると言うべきである。白河・鳥羽両院の時代、すなわち院政の開始から確立に至る<br />時代、貴族社会が激しく変貌する中で生きた令子内親王は、斎院、前斎院、皇后宮、太皇<br />太后宮と、呼称の異なる各期において、環境も少しずつ異なる所に身を置いた。その結果<br />として、各時期の皇室と貴族社会の具体的状況と変化の様相を、内親王家のありようにも<br /> 文芸活動にも反映し続けることになったからである。貴族社会の状況を反映したという点<br />では、令子の同母姉妹(郁芳門院媞子、土御門斎院禎子)や堀河天皇中宮篤子の各内親王<br />家の文芸活動にも見ることが出来るが、とりわけ令子内親王は、六十六年の生涯において<br />長期間重い立場にあった点が重要である。<br /> 白河院政から鳥羽院政に至る時代は、いま、歴史学において中世社会の出発期として注<br/ >目される。この時代の文学の研究には『堀河百首』や『金葉和歌集』等、主要作品を読み<br />解くことが重要であるが、それらの精確な読解のためには、周辺の文芸の場のあり方と人々<br />の意識、貴族の生活実態を探ることが不可欠である。令子内親王家及びその周辺の文芸活<br />動を精査し特質を考察することは、この時代の文学の研究のために必要であり、延いては<br />和歌史の研究にも寄与するものである。
- 著者
- 和田 拓哉 福地 健太郎
- 出版者
- 電子情報通信学会
- 雑誌
- 電子情報通信学会技術研究報告 = IEICE technical report : 信学技報 (ISSN:09135685)
- 巻号頁・発行日
- vol.117, no.73, pp.107-114, 2017-06-01
- 著者
- 鳥羽 耕史
- 出版者
- 国際日本文化研究センター
- 雑誌
- 日本研究 (ISSN:09150900)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, pp.218-221, 2017-10
- 著者
- 川崎 真弘
- 出版者
- 筑波大学
- 雑誌
- 新学術領域研究(研究領域提案型)
- 巻号頁・発行日
- 2013-06-28
発達障害児に見られる「逆さバイバイ」のように、視点と身体表象の重ね合わせはコミュニケーション時の発達障害の一つとして重要な未解決問題である。本研究では、視点と身体表象の重ね合わせを健常者と発達障害者で比較し、発達障害の方略の違いを調べた。PCディスプレイ上に呈示された人の両手のうち一方がタッピング動作をし、被験者はその動作と同じ手でタッピングをすることが要求する運動模倣課題を用いた。方略の聞き取り調査より、定型発達者の多くが視点取得の方略を取るのに対して、発達障害群の多くは逆に心的回転の方略をとった。反応時間によるパフォーマンス結果から、心的回転を報告した被験者だけで回転角度依存性が観測されたため、この聞き取り調査が正しかったことを確認した。また、その方略の違いは発達障害のスケールの中でも「こだわり」や「コミュニケーション」のスコアと有意に相関した。さらに発達障害者は定型発達者とは異なり、自分がとった方略と異なる方略を強制されると有意にパフォーマンスが悪化した。この課題遂行時の脳波と光トポグラフィの結果を解析した結果、発達障害者は自分がとった方略と異なる方略を強制されると有意に前頭連合野の活動が増加することが分かった。前頭連合野の活動は従来研究で認知負荷と相関することが示されている。つまり、発達障害者は視点取得の戦略を使うと心的負荷がかかることが示唆された。以上の結果より発達障害者は他社視点を使う視点取得の方法より自己視点を使う心的回転を用いて運動模倣を行っていることが示された。今後はこのような戦略の違いがどのようにコミュニケーション困難と関係するかを分析する必要がある。
3 0 0 0 OA 書評と紹介 : 山田昭次・古庄正・樋口雄一著『朝鮮人戦時労働動員』
- 著者
- 飛田雄一
- 出版者
- 法政大学大原社会問題研究所
- 雑誌
- 大原社会問題研究所雑誌
- 巻号頁・発行日
- vol.2006年(8月), no.573, 2006-08-25
3 0 0 0 OA 官報
- 著者
- 大蔵省印刷局 [編]
- 出版者
- 日本マイクロ写真
- 巻号頁・発行日
- vol.1922年01月14日, 1922-01-14
3 0 0 0 OA 国際私法における相続人の不存在 -結果志向の法思考の批判検討-
- 著者
- 伊藤 敬也
- 出版者
- 早稲田大学法学会
- 雑誌
- 早稻田法學 (ISSN:03890546)
- 巻号頁・発行日
- vol.87, no.3, pp.1-28, 2012-03-20
- 著者
- 海老塚 明 片岡 浩二
- 出版者
- 大阪市立大学
- 雑誌
- 經濟學雜誌 (ISSN:04516281)
- 巻号頁・発行日
- vol.108, no.2, pp.16-32, 2007-09
3 0 0 0 OA メディアによる遊びの発達段階による変化
- 著者
- 増田 公男
- 出版者
- 金城学院大学
- 雑誌
- 金城学院大学論集. 人間科学編 (ISSN:04538862)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, pp.41-54, 2000-03-20
3 0 0 0 ICONE23-1566 FUNDAMENTAL STUDY OF SOURCE TERM FOR SEVERE ACCIDENT ANALYSIS OF MOLTEN SALT REACTORS
- 著者
- Michio Yamawaki Yuji Arita Takayuki Terai Tadafumi Koyama Koichi Uozumi Yuma Sekiguchi Masami Taira
- 出版者
- The Japan Society of Mechanical Engineers
- 雑誌
- Proceedings of the ... International Conference on Nuclear Engineering. Book of abstracts : ICONE (ISSN:24242934)
- 巻号頁・発行日
- pp._ICONE23-1, 2015-05-17 (Released:2017-06-19)
- 被引用文献数
- 1 1
Source term for severe accident analysis of molten salt reactors(MSRs) has been investigated as part of preliminary efforts to develop MSRs. As a severe accident of MSRs, exposure of heated fluoride fuel molten salt to atmosphere was assumed to take place. Vaporization of fluoride molten salt was studied by means of the two methods, the Knudsen effusion mass spectrometry as well as the transpiration method. The former was applied to pseudo-binary fluoride systems to clarify the behaviors of cesium and iodine in the fluoride molten salt. The latter was applied to the mixture of CsI and FLiNaK. These experiments were carried out as the first step of the source term studies, so that interaction with air components has not been covered yet. From this study, useful information related to the source term for MSRs have been obtained. This work suggests how to solve the problem to establish the source term for severe accident analysis of MSRs.
- 著者
- 飯盛 元章
- 雑誌
- 大学院研究年報 文学研究科篇 (ISSN:13452436)
- 巻号頁・発行日
- no.46, 2017-02-20
【査読付論文】
- 著者
- 星野 晴彦
- 出版者
- 文教大学
- 雑誌
- 人間科学研究 (ISSN:03882152)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, pp.115-122, 2010-03-01
社会福祉の先人たちの足跡や、青年海外協力隊のソーシャルワーク部門に志願する人々の熱意を見ていると、苦難の状況にあって、支援を必要とする人々のために献身し、自分たちを高めていくパワーを感じさせられる。このパワーはソーシャルワークの地道な実践の継続を支えてきたと言えよう。筆者はこのパワーは、ミッション意識を中核とする次のようなプロセスにあるのではないかと考えている。 「ソーシャルワーク実践に専心し、ソーシャルワーカー自身の中に、ミッション意識(自分たちがやりたいことでなく、社会から何を求められているのかを考え、自ら意味付けする)を抱くことで、自分へのこだわりを超越し、そして自分自身の生きる意味へと再統合していくプロセスである。」 本稿は上記のプロセスに関して、文献研究により検討した。特に、このミッション意識の意義について、そして実践現場においてこのミッション意識がいかに形成されるのかについて論じていく。筆者はあえてこの「超越」と「再統合」の重要性を強調したい。