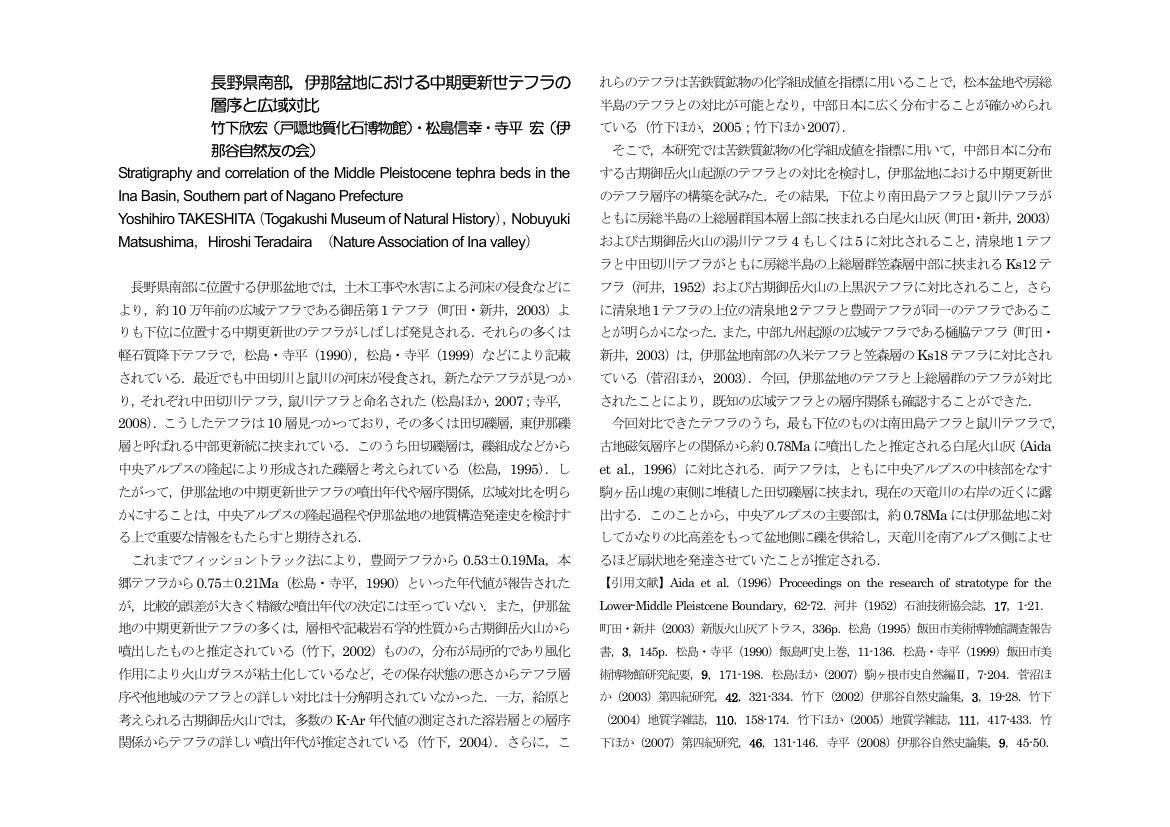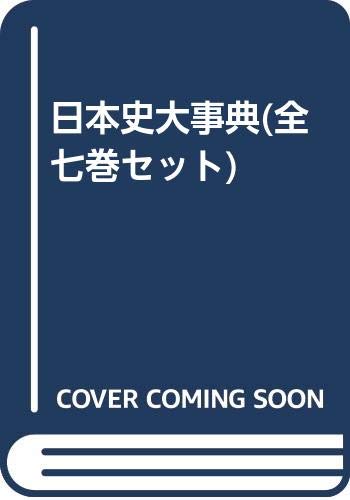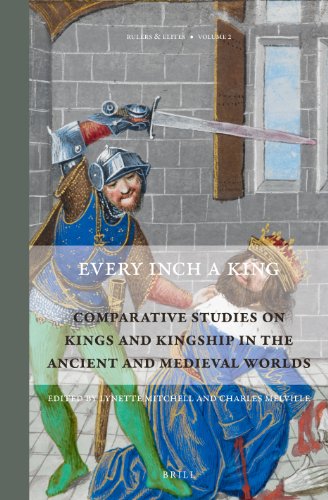3 0 0 0 OA 全周囲立体モニタ技術の実用化
- 著者
- 清水 誠也 水谷 政美 鶴田 徹
- 出版者
- 一般社団法人 映像情報メディア学会
- 雑誌
- 映像情報メディア学会誌 (ISSN:13426907)
- 巻号頁・発行日
- vol.68, no.1, pp.J24-J29, 2014 (Released:2013-12-20)
- 参考文献数
- 8
筆者らは,駐発車を含むさまざまな運転状況でのドライバ視覚支援を目的とし,4台の車載カメラ映像をもとに,自車両の近傍だけではなくより広い範囲の状況を立体感のある全周囲立体映像として合成し,視点を自由に動かしながら表示できる全周囲立体モニタ技術を開発した.本技術により,駐車時,交差点右左折時,高速道路の本線合流時などさまざまな運転状況に応じて死角のない車両周辺映像をリアルタイムに合成し,車載モニタで確認できるようになった.全周囲立体モニタ技術は,すでにドライバ視覚支援製品として実用化されており,ドライバの安心・安全の向上を通して社会に貢献している.本稿では,全周囲立体モニタ技術の原理について述べた後,実用化の課題であったカメラ間の視差と輝度差への対処について示す.さらに車載組込み系システムへの実装と,実車両への適用について報告する.
3 0 0 0 OA 地域課題の発見から解決に向けた地理学と隣接分野のアプローチ
- 著者
- 秋山 千亜紀
- 出版者
- 公益社団法人 日本地理学会
- 雑誌
- E-journal GEO (ISSN:18808107)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, no.2, pp.322-328, 2017 (Released:2017-12-28)
- 著者
- Sven WOHLGEMUTH Kazuo TAKARAGI
- 出版者
- The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers
- 雑誌
- IEICE TRANSACTIONS on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences (ISSN:09168508)
- 巻号頁・発行日
- vol.E101-A, no.1, pp.149-156, 2018-01-01
Threats to a society and its social infrastructure are inevitable and endanger human life and welfare. Resilience is a core concept to cope with such threats in strengthening risk management. A resilient system adapts to an incident in a timely manner before it would result in a failure. This paper discusses the secondary use of personal data as a key element in such conditions and the relevant process mining in order to reduce IT risk on safety. It realizes completeness for such a proof on data breach in an acceptable manner to mitigate the usability problem of soundness for resilience. Acceptable soundness is still required and realized in our scheme for a fundamental privacy-enhancing trust infrastructure. Our proposal achieves an IT baseline protection and properly treats personal data on security as Ground Truth for deriving acceptable statements on data breach. An important role plays reliable broadcast by means of the block chain. This approaches a personal IT risk management with privacy-enhancing cryptographic mechanisms and Open Data without trust as belief in a single-point-of-failure. Instead it strengthens communities of trust.
3 0 0 0 OA 長野県南部,伊那盆地における中期更新世テフラの層序と広域対比
- 著者
- 竹下 欣宏 松島 信幸 寺平 宏
- 出版者
- 一般社団法人 日本地質学会
- 雑誌
- 日本地質学会学術大会講演要旨 第116年学術大会(2009岡山) (ISSN:13483935)
- 巻号頁・発行日
- pp.141, 2009 (Released:2010-03-31)
- 参考文献数
- 13
3 0 0 0 OA 近代輸送体系の形成と港湾の性格変化:瀬戸内・山陰地帯を事例として
- 著者
- 中西 聡
- 出版者
- 北海道大学經濟學部 = HOKKAIDO UNIVERSITY SAPPORO,JAPAN
- 雑誌
- 經濟學研究 (ISSN:04516265)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, no.3, pp.231-250, 1999-01
3 0 0 0 OA 官報
- 著者
- 大蔵省印刷局 [編]
- 出版者
- 日本マイクロ写真
- 巻号頁・発行日
- vol.1891年08月29日, 1891-08-29
3 0 0 0 IR ヴァイツゼッカー演説と「5月8日」の歴史意識 -ドイツにおける戦後50年- (2)
- 著者
- 山本務
- 出版者
- 駒澤大学外国語部
- 雑誌
- 論集 (ISSN:03899837)
- 巻号頁・発行日
- vol.44, pp.209-228, 1996-09
3 0 0 0 Every inch a king : comparative studies on kings and kingship in the ancient and medieval worlds
- 著者
- edited by Lynette Mitchell Charles Melville
- 出版者
- Brill
- 巻号頁・発行日
- 2013
3 0 0 0 OA 光の感受性障害に関する研究の動向について
- 著者
- 尾形 雅徳 熊谷 恵子
- 出版者
- 障害科学学会
- 雑誌
- 障害科学研究 (ISSN:18815812)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, no.1, pp.149-161, 2016-03-31 (Released:2017-07-20)
- 参考文献数
- 27
Scotopic Sensitivity Syndrome(以下、SSS)と言われる視知覚に関連した障害がある。 この障害は、文字や文章を読む際に歪みや不快感が生じるものである。その症状は有色フィルムやレンズを使用することで改善が見られる。欧米では、1980年に、そして日本では2006年にこの障害の研究が始まり様々な視点からSSSは検証されている。日本において、このSSSの研究を進めていくにあたって、どのような視点で研究を行っていくかの知見を得るため、本稿ではSSSのスクリーニング方法、有色フィルムの効果、SSSの有症率についての研究に焦点を当て、それぞれの課題を明らかとすることした。第一にスクリーニング方法においては、様々な方法で試みられ検証されたスクリーニング検査において、チェックリストでのスクリーニングが重要であることが明らかとなった。第二に有色フィルムの効果においては、読みに困難がある場合でも条件によってその効果は変わるということが明らかとなった。最後に有症率においては、欧米では20%から38%、日本では6%と推定されることが明らかとなった。
3 0 0 0 OA 貨幣の本源的概念についての覚書
- 著者
- 泉 正樹 Izumi Masaki
- 出版者
- 東北学院大学学術研究会
- 雑誌
- 東北学院大学経済学論集 (ISSN:18803431)
- 巻号頁・発行日
- no.180, pp.15-44, 2013-03-10
3 0 0 0 OA 作用素環への入り口
- 著者
- 竹崎 正道
- 出版者
- 一般社団法人 日本数学会
- 雑誌
- 数学 (ISSN:0039470X)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.1, pp.89-101, 2003-01-24 (Released:2008-12-25)
- 参考文献数
- 9
3 0 0 0 IR 認知症カフェにおける初期認知症者支援の実践
- 著者
- 家根 明子
- 出版者
- 奈良女子大学大学院人間文化研究科
- 雑誌
- 人間文化研究科年報 (ISSN:09132201)
- 巻号頁・発行日
- no.30, pp.133-143, 2014
It is important to encourage accurate knowledge regarding dementia and increase thepreventive support for patients with dementia. The Five-Year Plan for Promotion of DementiaMeasures ("Orange Plan"), formulated by the Ministry of Health, Labour and Welfare in2012, has indicated that initiatives, such as Dementia Cafés, will be necessary in the future.The present study involved the establishment of a local Dementia Café, led by a physicianand run on a planned trial basis for five times over a period of 6 months, with the voluntaryparticipation of specialists who agreed to conduct sessions at the café. Observations of theevents occurring at the café, which were obtained through implementation of this initiativewere analyzed and included in the discussion. These observations comprised the main stateof participants and contents of conversations, meetings held at the café after the completionof each session conducted by the specialists. The observations clarified the following threeissues faced during the support of individuals with early dementia, :(1)promotion of accurateknowledge regarding dementia, and implementation of preventive support: the participationand support as the severity of dementia increases;(2)evaluation of Dementia Café from theviewpoints of individuals with dementia, their families, and specialists; and (3) expansion of suchcafés, which would establish a foundation for the support of individuals with early dementiawho live in rural areas.
3 0 0 0 OA 三重県の発電所のRDF 貯蔵サイロでの火災と爆発
- 著者
- 八島 正明
- 出版者
- 安全工学会
- 雑誌
- 安全工学 (ISSN:05704480)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, no.3, pp.169-176, 2011-06-15 (Released:2016-08-31)
- 参考文献数
- 35
2003 年8 月14 日,多度町(現・桑名市)にあるごみ固形化燃料(RDF)貯蔵サイロ内で小爆発が発生し,その後サイロ内でくすぶり続けていた.19 日,サイロが爆発し,サイロの屋根で消火活動を行っていた消防職員2 名が死亡,サイロのそばにいた作業員1 名が負傷する災害が発生した.RDF(Refuse Derived Fuel)は新燃料の一つとして脚光を浴びたが,この事故災害を契機に,爆発・火災の危険性があることが社会に知れ渡ることになった.本件では3 回に分けて報告するが,その1 では災害の概要と被害状況を述べる.
- 著者
- 橋本 謙二 石間 環 藤田 有子 張 琳
- 雑誌
- 日本アルコール・薬物医学会雑誌 = Japanese journal of alcohol studies & drug dependence (ISSN:13418963)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, no.2, pp.118-125, 2013-04-28
- 参考文献数
- 43
3 0 0 0 OA 極北日本 : 樺太踏査日録
3 0 0 0 OA 第3次アーミテージ・ナイ報告書とTPP
- 著者
- 星野 三喜夫 HOSHINO Mikio
- 出版者
- 新潟産業大学附属東アジア経済文化研究所
- 雑誌
- 新潟産業大学経済学部紀要 (ISSN:13411551)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, pp.1-16, 2013-02
2012年8月に第3次アーミテージ・ナイ報告書が発表された。同報告書は米共和党、民主党の知日超党派・有識者による米国から日本への真摯な政策提言である。3次報告書は日米関係が漂流する中にあって、日本への叱咤激励と日本「一級国家」論を盛り込んでおり、日本は、本報告書にある熱いメッセージを強く認識すべきである。報告書に示された提言に日本が応えず、日米関係と日米安全保障体制の維持・強化について強い意思を示さなければ、報告書にあるように日本は国際社会において二級国家になり下がってしまう。3次報告書の提言の1つである日本のTPP参加について、日本が、国内の既得権益を守ろうとする組織や団体の圧力に屈し、21世紀の世界秩序を塗り替えるほどの大きな枠組みであるTPPへの参加を躊躇すれば、日本は、国際的なリーダーシップや発言力の低下を免れない。TPPは日米の「特別な関係」の構築にとって重要なツールでありプロセスである。日本はTPPの通商面に加え、政治安全保障上の意義を国際関係の中で正確に捉え、早急にこれに参加すべきであり、それが世界第3位の日本の東アジアとアジア太平洋、そして広く世界に対して果たす責務でもある。