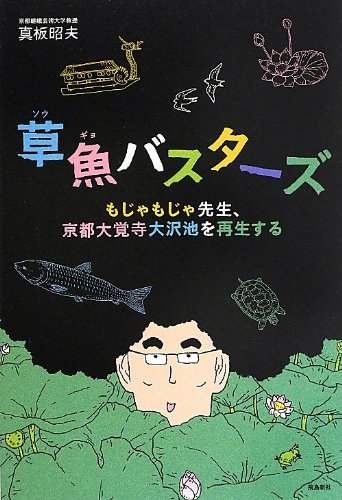3 0 0 0 OA 鉄隕石の微細構造と磁性
- 著者
- 小嗣 真人 三俣 千春
- 出版者
- 公益社団法人 日本金属学会
- 雑誌
- まてりあ (ISSN:13402625)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, no.3, pp.103-109, 2010 (Released:2012-11-01)
- 参考文献数
- 49
3 0 0 0 IR 適切な福祉利用の確保とその公法的構成(一)
- 著者
- 林 倖如
- 出版者
- 名古屋大学
- 雑誌
- 名古屋大學法政論集 (ISSN:04395905)
- 巻号頁・発行日
- vol.249, pp.1-62, 2013-06-25
3 0 0 0 OA 「あやとり」「折り紙」の学習過程における脳波及び心理的変化
- 著者
- 野田 さとみ 佐久間 春夫
- 出版者
- 日本バイオフィードバック学会
- 雑誌
- バイオフィードバック研究 (ISSN:03861856)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.1, pp.29-36, 2010-04-25 (Released:2017-05-23)
- 被引用文献数
- 1
本研究では,手指の運動を伴う遊びであるあやとりの特徴を明らかにするために,類似する遊びとして折り紙を取りあげ,動作パターンの学習過程について比較検討を行なった.被験者は健康な女性10名であった.あやとり課題・折り紙課題はそれぞれ動作パターンを記憶するための練習時間を設定し(練習中),練習後は3分間連続して課題を行なった.測定項目は,生理指標として脳波の周波数帯域別含有率の変化,心理指標として坂入らによる「心理的覚醒度・快感度を測定する二次元気分尺度」および遂行の自己評定とした.脳波の結果から,前頭部においては課題に関わらず練習中よりも練習後でα1波,α2波,β波の含有率の増加が認められた.中心部・頭頂部では,あやとりは練習中・練習後にβ波が変化しないのに対し,折り紙では練習中に比べ練習後でβ波の増加が認められ,あやとりよりも折り紙の方が動作パターンを記憶して行うことで中心部・頭頂部が活性化することが示された.自己評定の結果からは,練習中・練習後に関わらず折り紙に比べあやとりの方が集中して取り組んでいたことが示された.以上の結果から,動作パターンを記憶して行なった場合,あやとり・折り紙ともに意識的に手順を想起しながら行うことにより覚醒が高まること,あやとりに比べ折り紙は視覚情報への依存度が高く動作手順の遂行への集中を要することが示された.一方,自己評定の結果からは動作パターンを記憶しているかに関わらず折り紙よりもあやとりの方が集中していたと報告され,これは,あやとりは常に糸を一定の形に保たなければならないという活動特性によるものと考えられた.
- 著者
- 篠原 結城
- 出版者
- 関東学院大学人文学会英語文化学部会
- 雑誌
- Oliva (ISSN:13432168)
- 巻号頁・発行日
- no.22, pp.79-97, 2015
3 0 0 0 OA 南川文里著『アメリカ多文化社会論――「多からなる一」の系譜と現在』
- 著者
- 塩原 良和
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.67, no.3, pp.345-347, 2016 (Released:2017-12-31)
- 著者
- 齋藤 基一郎
- 出版者
- 植草学園大学
- 雑誌
- 植草学園大学研究紀要 (ISSN:18835988)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, pp.77-92, 2010-03
3 0 0 0 IR 戴季陶民族主義の脈絡--反日と恐日にゆれた自己保存主義
- 著者
- 董 世奎
- 出版者
- 名古屋大学大学院 国際言語文化研究科 日本言語文化専攻
- 雑誌
- 言葉と文化 (ISSN:13455508)
- 巻号頁・発行日
- no.6, pp.121-139, 2005-03
- 著者
- Toshihisa Ishikawa Kohtaro Yuta Yukio Tada Akihiko Konagaya
- 出版者
- Chem-Bio Informatics Society
- 雑誌
- Chem-Bio Informatics Journal (ISSN:13476297)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, pp.110-111, 2017-12-31 (Released:2017-12-04)
- 参考文献数
- 3
藤田稔夫氏(ふじた・としお=京都大名誉教授、医農薬化学)が今年8月22日午前11時47分、病気のため京都市内の病院で死去されました。享年88歳。昨年10月には京都大学で開催された第44回構造活性相関シンポジウムで米寿をお祝いしたところでした。藤田先生はCorwin Hansch教授(米国)と共に定量的構造活性相関の方法を確立され、医薬農薬などの多方面で分子設計に多大な影響を与えてきました。さらに、藤田先生はEMIL (Example-Mediated Innovation for Lead Evolution)の方法を開発して、人工頭脳(AI)に基づく創薬分子デザインの可能性を追求されてこられました。藤田先生の先進的な考えとアプローチは私どもの模範とするところです。この追悼文をもって藤田稔夫先生の偉業をかみしめつつ、ご冥福をお祈り申し上げます。
3 0 0 0 OA ロールズの功利主義批判と「人格の区分の重視」
- 著者
- 池田 誠
- 出版者
- 北海道大学大学院文学研究科
- 雑誌
- 研究論集 (ISSN:13470132)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, pp.21-33, 2010-12-24
本稿では、ジョン・ロールズの『正義論』における功利主義批判のキーワード「人格の区分の重視(taking the distinction between persons seriously)」について考察する。ロールズによれば、功利主義やそれが提案する道徳原理である功利原理は現実の人々の「人格の区分」を重視しない。この批判は、功利主義は全体の功利の最大化のためなら平等や公正な分配を無視した政策でさえ支持するという政策・制度レベルの批判ではない。むしろこれは、功利主義は功利原理の各人への「正当化」および正当化理由のあり方に対し無頓着であるという、道徳理論・方法論レベルの批判である。ロールズによれば、功利主義は人格を、「不偏の観察者」という想像上の管理者によって快い経験や満足を配分されるのを待つ単なる平等な「容器」のようなものとみなす。だがロールズによれば、われわれの常識道徳は、人格を、自らに影響を与える行為・制度に対し、自らの観点から納得の行く正当化理由の提示を請求する権利を持つものとみなしている。この各人の独自の観点や正当化理由への請求権を認めること、これこそが「人格の区分」を重視することにほかならない。 以上の事柄を『正義論』での記述に即してまとめたのち、私は、アンソニー・ラディンによるこの批判の分析・論点整理(Laden 2004)に依拠し、ロールズ自身に向けられてきた「人格の区分の軽視」批判が、ロールズ正義論の全体を把握し損ね、近視眼的に眺めてしまうがゆえの誤りであることを示すとともに、ロールズの「人格の区分」批判の論点が功利主義の根底に潜む「非民主的」性格にあったことを明らかにする。その後、結論として、ラディンの分析に対する私なりの考えと異論を述べるとともに、ロールズ正義論が現代倫理学において持つ意義について触れたい。
3 0 0 0 菊池寛 : 短篇と戯曲
3 0 0 0 IR 対立する家族の二つの機能 : データが示す家族機能の変化
- 著者
- 千葉 聡子
- 出版者
- 文教大学
- 雑誌
- 文教大学教育学部紀要 (ISSN:03882144)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, pp.47-58, 2000
本稿では、子どもの社会化機能の強化が教育問題との関連で家族に求められている現状を踏まえ、近代家族の基本的機能である「成員の情緒的安定機能」と「子どもの社会化機能」の遂行状況を官庁による調査データを用いて検討することを第一の目的とし、「成員の情緒的安定機能」の強調と「子どもの社会化機能」の弱化を確認した。またこうした家族の機能の変化の確認から、近代家族の二つの機能にはそもそも並存が難しい要因が含まれており、社会による個人のコントロールの方法に変化が生じている、という仮説を提示した。
3 0 0 0 草魚バスターズ : もじゃもじゃ先生、京都大覚寺大沢池を再生する
3 0 0 0 OA 奠都三十年 : 明治三十年史・明治卅年間国勢一覧
- 出版者
- 博文館
- 巻号頁・発行日
- 1898
3 0 0 0 <書評> 秋元律郎著「権力の構造」
- 著者
- 矢沢 澄子
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.1, pp.81-84, 1982-06-30
3 0 0 0 <書評>盛山和夫著『権力』
- 著者
- 西阪 仰
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, no.1, pp.163-164, 2001-06-30
3 0 0 0 OA 職業性ストレスと抑うつの関係における職場のソーシャルサポートの緩衝効果の検討
- 著者
- 小松 優紀 甲斐 裕子 永松 俊哉 志和 忠志 須山 靖男 杉本 正子
- 出版者
- 公益社団法人 日本産業衛生学会
- 雑誌
- 産業衛生学雑誌 (ISSN:13410725)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, no.3, pp.140-140, 2010 (Released:2010-06-02)
- 参考文献数
- 47
- 被引用文献数
- 5 10
職業性ストレスと抑うつの関係における職場のソーシャルサポートの緩衝効果の検討:小松優紀ほか.東邦大学医学部看護学科―目的:本研究は,職業性ストレスと抑うつの関連性における職場のソーシャルサポート(以下サポート)の緩衝効果について検証することを目的とした. 対象と方法:調査方法は無記名自記式質問紙を用いた横断的研究である.対象者は某精密機器製造工場に勤務する40歳以上の男性712名であった.調査項目は,年齢,職種等の属性,抑うつ,職業性ストレス(仕事の要求度・仕事のコントロール),職場のサポート(上司のサポート・同僚のサポート)等であった.職業性ストレスと職場のサポートの測定はJCQ職業性ストレス調査票(JCQ)を用いた.抑うつは抑うつ状態自己評価尺度(CES-D)を用い,得点が16点以上の者を抑うつ傾向とした.職業性ストレス,サポートについては各尺度の得点を中央値で二分し,得点の高い群を高群,低い群を低群とした.職業性ストレスおよびサポートの高低別のCES-D得点の平均値の比較をt検定にて行った.またCES-D得点を従属変数とし,対象者の属性,職業性ストレス,サポート,職業性ストレスとサポートの交互作用項を独立変数として階層的重回帰分析を行った.交互作用が有意であった場合には,年齢を共変量として共分散分析を行い,職業性ストレスの高低別にサポートの高低がCES-D得点に及ぼす効果を検討した. 結果:調査の結果,全対象者のうち抑うつ傾向者は23.2%であった.仕事の要求度の高低別のCES-D得点は,高群が低群よりも有意に高かった.仕事のコントロール,上司のサポート,同僚のサポートそれぞれにおけるCES-D得点は,各低群が高群よりも有意に高値であった.階層的重回帰分析を行った結果,仕事の要求度,仕事のコントロール,上司のサポート,同僚のサポートはそれぞれCES-D得点に対する有意な主効果が認められた.さらに仕事のコントロールと上司のサポートの要因間でCES-D得点に対する有意な交互作用が認められた.また,仕事のコントロールの低い状況でのみ,上司のサポート高群よりも低群のCES-D得点が有意に高値であった. 結論:これらのことから,上司によるサポートは仕事のコントロールの低さと関連する抑うつを緩衝する効果がある可能性が示唆された. (産衛誌2010; 52: 140-148)
3 0 0 0 ベトナム・ホイアンにおける町並み保存システムの形成過程と特徴
- 著者
- 安藤 勝洋 福川 裕一 友田 博通
- 出版者
- Architectural Institute of Japan
- 雑誌
- 日本建築学会計画系論文集 (ISSN:13404210)
- 巻号頁・発行日
- vol.80, no.708, pp.379-389, 2015
- 被引用文献数
- 3
This study aims to clarify the formulation process and structural features of historic conservation system of Hoi An ancient town in Viet Nam. The conservation work began after the Vietnam War, and its process can be classified into 4 phases in accordance with the enactment and implementation of policies. Through reviewing the process, we found that the following features have played important roles. 1) a conservation fund created by revenues of tourist ticket. 2) the regeneration of state-owned buildings has played leading roles for the conservation. 3) professional organizations are responsible for both tangible and intangible cultural heritage conservation.
3 0 0 0 地域福祉の推進と共助の拡充 (堺正一教授退職記念号)
- 著者
- 稲葉 一洋
- 出版者
- 立正大学社会福祉学部
- 雑誌
- 人間の福祉 : 立正大学社会福祉学部紀要 (ISSN:13429191)
- 巻号頁・発行日
- no.28, pp.35-48, 2014