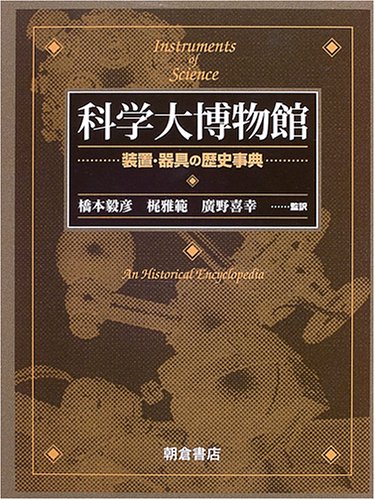3 0 0 0 OA 女子短大生の飲み物に関する調査
本調査では、女子短大生における飲み物の摂取の実態を、把握することを目的として、本学短大生466名を対象に、朝・昼・夕・間食における飲み物についてのアンケート調査をし、次の結果を得た。1)朝・昼・夕の主食は、御飯が最も多く、その時の飲み物は、お茶類が高い値を示した。昼食では、砂糖の添加されている飲み物が多く飲まれていた。主食がパンの場合は、他の主食に比べ、ジュースの割合が高かった。2)調査した学生の80%の者が、1日1回は間食を摂っており、昼食後〜夕食前、夕食後に摂った者が、朝食後〜昼食前の約4〜5倍いた。間食の飲み物では、砂糖の添加された物が多く飲まれていた。3)朝・夕食は家で、昼食は学校で摂ったと答えた者が多く、間食は場所を問わず摂っていた。飲み物の形態は、朝・夕食は、自分で作った者が多く、昼・間食では、缶、ビン、その他(パック等)の飲み物が多かった。4)1日の缶入り飲み物の摂取状況は、1缶(53%)、2・3缶(13%)、飲まなかった(34%)であった。1週間の摂取状況は、3〜5缶と答えた者が78%と多かった。5)飲み物の選択基準としてあげたうち、多かった物は、嗜好、食べ物との組合わせであった。その中でも、嗜好と答えた者は、全体の60%を占めていた。
3 0 0 0 OA 反日デモと暴徒と群集心理
- 著者
- 澤 喜司郎
- 出版者
- 山口大学
- 雑誌
- 山口經濟學雜誌 (ISSN:05131758)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.5, pp.683-704, 2006-01-31
3 0 0 0 IR 書評 池田喬『ハイデガー 存在と行為 : 「存在と時間」の解釈と展開』
- 著者
- 松橋 俊輔
- 出版者
- 東京大学大学院教育学研究科基礎教育学研究室
- 雑誌
- 研究室紀要 (ISSN:02857766)
- 巻号頁・発行日
- no.38, pp.105-110, 2012-06
書評・映画評Book reviews
3 0 0 0 OA 水俣にまなぶ
- 著者
- 原田 正純
- 出版者
- 日本ハンセン病学会
- 雑誌
- 日本ハンセン病学会雑誌 (ISSN:13423681)
- 巻号頁・発行日
- vol.78, no.1, pp.55-60, 2009 (Released:2010-12-21)
- 参考文献数
- 9
- 被引用文献数
- 1 2
Minamata disease (MD) was first recognized in May 1956. Its first recognized victims were 3 and 5 years old children. Environmental contamination most rapidly and seriously affected the physiologically and socially weak among the residents. Methylmercury (MeHg) had accumulated in fishes and shellfishes and those who ate them had been poisoning with it.MD is an indirect poisoning by MeHg through the food chain as a result of environmental contamination, and is the first known disease to cause abnormalities in the fetus due to a toxic substances passing through the placenta. In 1962 MeHg poisoning through the placenta was found for the first time in the world. It used to be considered that poisoning was caused by direct exposure to a toxic substance, and that toxic substances did not pass the placenta. MD had implications in various fields. Namely it also stirred up legal, ethical, and eugenic arguments concerning fetal protection. Also man thought about a man's worth.
3 0 0 0 OA 大口徑比寫眞レンズの發達
- 著者
- 伊藤 宏
- 出版者
- 公益社団法人 応用物理学会
- 雑誌
- 応用物理 (ISSN:03698009)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.2-3, pp.44-54, 1952 (Released:2009-02-09)
- 参考文献数
- 20
3 0 0 0 エティックとエミック
- 著者
- 森 雅雄
- 出版者
- 日本文化人類学会
- 雑誌
- 民族学研究 (ISSN:00215023)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.2, pp.p229-236, 1988-09
- 著者
- 山田 政寛 北村 智
- 出版者
- 日本教育工学会
- 雑誌
- 日本教育工学会論文誌 (ISSN:13498290)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.3, pp.353-362, 2010
- 参考文献数
- 38
- 被引用文献数
- 1
教育学習研究において社会的存在感が着目されてきている.社会的存在感は学習意欲の向上や学習満足度の向上に対して有効であるとされているが,これらの知見は1つの社会的存在感の概念で説明されたものではない.社会的存在感の考え方が複数存在し,その違いによって研究知見も異なる.システムデザインや協調学習の評価のためには,「社会的存在感」に関する考え方や知見が整理されていることが望ましい.本稿では「社会的存在感」概念に関する考え方をSHORTらの考え方,GUNAWARDENA,TUらの考え方,GARRISONらの考え方に大別し,それぞれの考え方ごとにどのような研究が行なわれているのかを整理する.またその3つの考え方にもとづく測定法を整理することで「社会的存在感」概念が何の評価に関わるのかを議論する.
3 0 0 0 OA トヨタ自動車躍進譜
- 出版者
- 豊田自動織機製作所自動車部
- 巻号頁・発行日
- 1937
- 著者
- Daisuke FUKUI Gen BANDO Koji FURUYA Masanori YAMAGUCHI Yuji NAKAOKA Masao KOSUGE Koichi MURATA
- 出版者
- 公益社団法人 日本獣医学会
- 雑誌
- Journal of Veterinary Medical Science (ISSN:09167250)
- 巻号頁・発行日
- pp.12-0231, (Released:2012-09-04)
- 被引用文献数
- 1 6
An outbreak of encephalitozoonosis occurred in a rabbit colony at a zoo in Japan. Throughout the two years after the onset, all 42 rabbits were investigated clinically, pathologically and serologically for prevention and control of the disease. Eleven rabbits (11/42, 26.2%) showed clinical symptoms. Of 38 rabbits examined to detect specific antibodies against Encephalitozoon cuniculi, 71.1% (n=27) were found seropositive; 20 out of 30 clinically healthy rabbits (except for 8 clinical cases) were seropositive. The infection rate was 76.2% (32/42), including five pathologically diagnosed cases. The results of serological survey revealed that asymptomatic infection was widespread, even among clinically healthy rabbits. However, encephalitozoonosis was not found by pathological examination in any other species of animals kept in the same area within the zoo. Isolation and elimination of the rabbits with suspected infection based on the results of serological examination were carried out immediately; however, encephalitozoonosis continued to occur sporadically. Therefore, all the remaining rabbits were finally slaughtered. Then, the facility was closed, and all the equipment was disinfected. After a two-month interval, founder rabbits were introduced from encephalitozoonosis-free rabbitries for new colony formation. Since then, encephalitozoonosis has not been seen in any animals at the zoo. In this study, biosecurity countermeasures including staff education, epidemiological surveillance and application of an “all-out and all-in” system for rabbit colony establishment based on serological examination were successfully accomplished with regard to animal hygiene and public health for the eradication of E. cuniculi.
3 0 0 0 フォーミュラ競技車両の設計製作教育について
- 著者
- 鈴木 隆
- 出版者
- 日本設計工学会
- 雑誌
- 設計工学 (ISSN:09192948)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, no.10, pp.543-548, 2011-10-05
3 0 0 0 IR 地域社会における地方議会・地方議員の存在
- 著者
- 油川 洋 Hiroshi Aburakawa
- 出版者
- 尚絅学院大学
- 雑誌
- 尚絅学院大学紀要 (ISSN:13496883)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, pp.103-114, 2005-01
3 0 0 0 IR 日本文学研究の魅力と喜び -村上春樹と井原西鶴の作品を例として-
- 著者
- 広嶋 進 Hiroshima Susumu
- 出版者
- 神奈川大学経営学部
- 雑誌
- 国際経営教育
- 巻号頁・発行日
- vol.5, pp.17-23, 2012-06-30
Ⅰ 学問研究の魅力と経営学部での学修方法
3 0 0 0 OA 歴史と生の哲学
- 著者
- ウイルヘルム・デイルタイ 著
- 出版者
- モナス
- 巻号頁・発行日
- 1934
3 0 0 0 OA 批判主義に基く哲学的教育学
- 著者
- ゲルハルト・パウル・ナトルプ 著
- 出版者
- 同文館
- 巻号頁・発行日
- 1924
- 著者
- モハッゲグダーマード モスタファ
- 出版者
- 同志社大学
- 雑誌
- 一神教学際研究 (ISSN:18801072)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, pp.61-73, 2005
イスラーム文化全般、特にイスラーム法を専門とする幾人かの欧米の学者たちは、これまで第一次的資料でなく、(しっかりした根拠に欠けた)脆弱な法源に依拠してきた。彼らによって、時に特殊な考えを一般化することや、誤った結論が導き出された。さらに悪いことには、彼等の安易な一般化はメディア記者によって、時に真実のように喧伝されてきた。このようなことが、イスラーム国際法に関する最近の誤謬ある記述を多く招くことになったのである。本稿における著者の意図は、クルアーンとスンナ(慣行)というイスラーム固有の資料に基づいて、真のイスラームを提示することである。これは、特に9・11事件の一連の出来事の後で、現存する誤解を取り除くことに貢献するであろうと思われる。このため、本稿では以下のようなことを簡潔に議論していく:イスラームと平和、平等の原理、宗教上の適用および社会面での適用、イスラームにおける寛容さの原理と普遍的同胞関係、宗教的協力の先例、平和の訴え、「啓典の民」との論争、宗教的同胞関係、普遍的同胞関係。
3 0 0 0 めばえの記録
- 著者
- 青森市立長島小学校情緒障害児学級めばえの教室 [編]
- 出版者
- 青森市立長島小学校情緒障害児学級めばえの教室
- 巻号頁・発行日
- 0000
3 0 0 0 科学大博物館 : 装置・器具の歴史事典
3 0 0 0 IR 批判的思考におけるsoft heartの重要性
- 著者
- 道田 泰司 Michita Yasushi
- 出版者
- 琉球大学教育学部
- 雑誌
- 琉球大学教育学部紀要 (ISSN:13453319)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, pp.161-170, 2002-03
批判的思考を行うためには,「共感」や「相手の尊重」のような,soft heartが必要になることが論じられた。それは第一に,批判を行う前提として「理解」が重要だからであり,相手のことをきちんと理解するためには「好意の原則」に支えられた共感的理解が必要だからである。このことは,-聴して容易に意味が取れると思われる場合でも,論理主義的な批判的思考を想定している場合でも同じである。共感的理解には,自分の理解の前提や枠組みをこそ批判的に検討する必要がある。そのことが,臨床心理学における共感のとらえられ方を元に考察された。また,批判を行うためには理解の足場が必要であること,それを自分と相手に繰り返し行うことによって理解が深まっていくことが論じられた。最後に,このような「批判」を伴うコミュニケーションにおいては,「相手の尊重」というもう1つのsoft heartも重要であることが,アサーティプネスの概念を引用しながら論じられた。
3 0 0 0 IR 新従属論の理論的意義-資本主義の世界性を中心に-
- 著者
- 中嶋 慎治
- 出版者
- 同志社大学
- 雑誌
- 經濟學論叢 (ISSN:03873021)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, no.3, pp.69-87, 1987