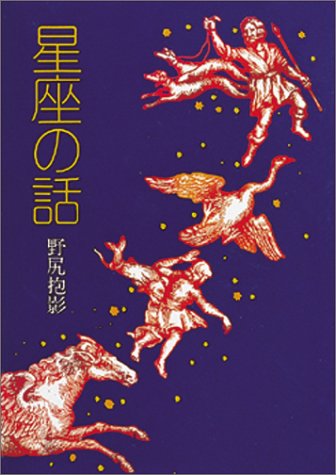2 0 0 0 OA 養護教諭に必要な医療的ケア : 短期大学における看護学実習
- 著者
- 永石 喜代子 小川 裕美 Kiyoko NAGAISHI Hiromi OGAWA
- 雑誌
- 鈴鹿短期大学紀要 = Journal of Suzuka Junior College (ISSN:13450085)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, pp.71-87, 2010-01-01
In late years, the children who are required the particular support became a big issue.We think that in its background, there is the increase of children needing medical care in a general school, and the most of them are needing the action of medical care, such as absorption of the phlegm, self withdrawing of urine and the tubal feeding, and these cause embarrassment of teacher whether or not it is possible for the action of the medical care.We think today, so it is going to be placed these medical actions as a new role of the Yogo teacher, teacher will be required the recognition for the medical action.However, now, these educations and trainings of medical care are not established for the students aiming for teacher and teachers yet.Therefore, In this study , through "the guide learning" as one of the way of educational method about the training of the medical care, we tried to grasp the evidence of the promotion of the student's learning will and needs for school nurse.We analyzed the obtained result, through the accomplishment degree of nursing training I, and clarified the effectiveness and problem of "the guide learning" in the medical care.
2 0 0 0 OA パイオニアにきく 第13回
- 著者
- 玉野 和志 石井 由香理 池口 佳子 堀田 裕子
- 出版者
- 日本質的心理学会
- 雑誌
- 質的心理学フォーラム (ISSN:18842348)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, pp.49-58, 2021 (Released:2022-04-20)
2 0 0 0 OA 日本における相撲協会の財団法人化に関する研究 1925年の大日本相撲協会の設立を中心に
- 著者
- 楊 紅梅 齋藤 健司
- 出版者
- 一般社団法人 日本体育・スポーツ・健康学会
- 雑誌
- 日本体育・スポーツ・健康学会予稿集 第72回(2022) (ISSN:24367257)
- 巻号頁・発行日
- pp.399, 2022 (Released:2022-12-22)
日本における相撲の歴史は長く、奈良時代の相撲節会、鎌倉時代の武家相撲、江戸時代の勧進相撲など、多様な形式で行われて。特に、江戸時代になると全国で勧進相撲が興行として行われ、1781年に相撲会所が結成され、庶民の娯楽文化として定着した。その後、江戸時代が終了し、西洋文化を取り入れて明治維新、日本社会の近代化がすすめられる過程で、このような社会の変革に相撲団体も対応し存続を図る必要性が生じた。そして、1889年に東京大角力協会が結成され、1925年に財団法人大日本相撲協会が設立されました。この財団法人大日本相撲協会の設立以後、日本においては、相撲協会が法人化に伴う組織改革を繰り返しながら団体組織として維持発展してきた。本研究は、日本の伝統的な文化である相撲が近代社会の変革に対応し、西洋の文化及び制度との衝突を克服することができたのは、この団体の法人化にあると考えた。そこで、まず、本研究では、相撲協会が初めて法人化された1925年の大日本相撲協会の設立までを研究の対象とし、相撲協会の法人化の過程を明らかにし、法人化の歴史的な意義を考察することを研究の目的とした。また、本研究では、相撲協会の財団法人化という制度の変化について、歴史的新制度論の分析の視角に基づいて、歴史的な制度の変化の過程を明らかにした。相撲協会の財団法人化という制度の変化がどのような歴史的過程で行われたのか、制度の変化に影響を与えた歴史的事実や関係するアクターの行動を明らかにした。また、1925年の大日本相撲協会の財団法人化の政策決定過程について考察した。具体的には、1909年に常設館が開館し国技として大相撲興行制度が整備されていく過程、1925年に摂政杯を契機に東、西相撲協会が合併し、大相撲が統一され、その後財団法人となる過程、そして財団法人設立後、組織·制度などの改革が行われる過程を明らかにした。
2 0 0 0 OA <研究論文>不妊および不妊治療経験がもたらす 妊娠中の感情への影響
- 著者
- 岡田 啓子
- 出版者
- 田園調布学園大学
- 雑誌
- 田園調布学園大学紀要 = Bulletin of Den-en Chofu University (ISSN:18828205)
- 巻号頁・発行日
- no.9, pp.173-185, 2015-03-25
不妊治療後に妊娠した妊婦は自然妊娠の妊婦と比べて,情緒不安定になりやすく,その後の育児においても子どもを過保護に扱ったり,過剰な期待をするといった育児への不適応が指摘されていた。これらの研究では不妊そのものを妊娠や育児への不安の主な原因としているが,不妊であったこと自体が問題となるだけではなく,治療中の経験がその後の妊娠に対する感情に影響を与えると考えるべきであろう。本稿では不妊治療中のストレスや夫婦関係が妊娠中の女性や男性に与える影響を明らかにすることを目的とし,検討を行った。不妊治療を経て妊娠した女性は,妊娠したことに対して肯定的な感情を強く持つ反面,それを強く望んでいた者ほど流産に対しての不安が高いという先行研究が支持されたほか,不妊治療中に家族との関係によって生じたストレスと妊娠への感情との間に関連が認められた。一方,男性に関して不妊治療経験の有無と“親になること”という意識との間に関連は認められなかった。しかし,不妊治療期間における夫婦関係のあり方によっては,エリクソンのいう「世代性」への意識が強められることがうかがえた。
2 0 0 0 OA 〔謡本〕
- 巻号頁・発行日
- vol.定家,
2 0 0 0 OA 〔謡本〕
- 巻号頁・発行日
- vol.竜田,
2 0 0 0 OA 〔謡本〕
- 巻号頁・発行日
- vol.角田川,
2 0 0 0 OA 〔謡本〕
- 巻号頁・発行日
- vol.昭君,
2 0 0 0 OA 脳波の測定と着用感評価
- 著者
- 山本 貴則
- 出版者
- 一般社団法人 日本繊維機械学会
- 雑誌
- 繊維機械学会誌 (ISSN:03710580)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.3, pp.P103-P107, 2000-03-25 (Released:2009-10-27)
- 参考文献数
- 11
- 被引用文献数
- 1
2 0 0 0 OA AMPA受容体の生理機能 −受容体機能発現から疾患まで−
- 著者
- 鈴木 岳之 都筑 馨介 亀山 仁彦 郭 伸
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬理学会
- 雑誌
- 日本薬理学雑誌 (ISSN:00155691)
- 巻号頁・発行日
- vol.122, no.6, pp.515-526, 2003 (Released:2003-11-20)
- 参考文献数
- 45
- 被引用文献数
- 12 14
グルタミン酸AMPA受容体は中枢神経系において速い興奮性神経伝達を担う重要なイオンチャネル型受容体である.この受容体は4つのサブユニットからなるテトラマーであり,その構成サブユニットはGluR1~4までの4種に分類され,さらにそれぞれがスプライシングバリアントを持つ.また,そのサブユニットのうちGluR2では,その第2膜親和性領域(イオンチャネルポアを形成する部分)にRNA編集によるグルタミンからアルギニンへの変換が生じている部位がある(Q/R部位).このアルギニンへの変換を受けた編集型GluR2サブユニットを構成成分に含むAMPA受容体はほとんどカルシウム透過性を持たないが(タイプ1受容体),含まないAMPA受容体は高いカルシウム透過性を示す(タイプ2受容体).受容体形成時には,このサブユニットの会合の段階でGluR2サブユニットを含むAMPA受容体の方が含まないものよりも形成されやすい調節を受けている可能性が示唆されている.また,各サブユニットの細胞内での輸送に関してもサブユニットにより異なる輸送機構が働いている可能性も明らかにされてきている.このようにAMPA受容体形成はサブユニット段階での種々の調節を受けていることが明らかとなってきている.タイプ2受容体がそのカルシウム透過性により神経脆弱性の発現に関与していることは知られているが,筋萎縮性側索硬化症の患者の脊髄運動神経においてはRNA編集が正常には行われず,Q/R部位がグルタミンのままのGluR2サブユニット(非編集型GluR2)が多く存在しており,その結果カルシウム透過型AMPA受容体が多く発現していることが明らかとなった.また,グリア細胞にはタイプ2AMPA受容体が発現しているが,ここに編集型GluR2を強制発現させるとグリア細胞の突起の退縮や神経膠芽腫細胞の増殖抑制などが観察された.このように,AMPA受容体は生体内において通常の興奮性神経伝達だけではなく,特にそのカルシウム透過性により神経機能や病態に深く関わっている可能性がある.
2 0 0 0 OA 〔謡本〕
- 巻号頁・発行日
- vol.志賀,
2 0 0 0 OA 集中治療室の病棟業務における臓器系統別患者評価法導入の効果
- 著者
- 吉廣 尚大 冨田 隆志 橋本 佳浩
- 出版者
- 一般社団法人日本医療薬学会
- 雑誌
- 医療薬学 (ISSN:1346342X)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, no.6, pp.445-452, 2016-06-10 (Released:2017-06-10)
- 参考文献数
- 13
- 被引用文献数
- 5 2
This study investigated whether the review of systems (ROS), an evaluation method that covers all organ systems, improves the quality of pharmaceutical care provided in intensive care units (ICUs). We retrospectively examined patients from the respiratory and emergency intensive care departments admitted to the ICU of our hospital in 2012 (before the introduction of ROS; non-ROS group, n = 93) and in 2014 (after the introduction of ROS; ROS group, n = 65). The number of pharmaceutical interventions and adverse drug events prevented by pharmacists per 1000 patient days were higher in the ROS group (265.7 and 57.8 for the ROS group and 190.8 and 39.9 for the non-ROS group). Pharmacists' proposals were accepted at a significantly higher rate in the ROS group than in the non-ROS group (89.5% vs 72.3%, P < 0.01), and the accepted proposals in the ROS group were implemented for a wider range of organ systems. These results indicate that the ROS was helpful in terms of identifying the patients' clinical manifestations and evaluating the adequacy and safety of medication administered in the ICU, which resulted in improved and precise proposals by pharmacists. Moreover, the ROS approach introduced in this study was considered to be suitable for pharmaceutical activities in the ICU and to contribute to improving the quality of pharmaceutical care.
2 0 0 0 OA 〔謡本〕
- 巻号頁・発行日
- vol.項羽,
2 0 0 0 OA jPOSTリポジトリとJPDMデータジャーナルの活用
- 著者
- 奥田 修二郎
- 出版者
- 日本プロテオーム学会
- 雑誌
- 日本プロテオーム学会誌 (ISSN:24322776)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, no.1, pp.1-7, 2022 (Released:2022-08-05)
- 参考文献数
- 14
jPOST(Japan ProteOme STandard Repository/Database)プロジェクトでは,プロテオミクス分野におけるFAIR(Findable, Accessible, Interoperable, Re-usable)データ原則に基づきプロテオームデータのリポジトリベースを運用・開発している.このjPOSTリポジトリは世界中のプロテオミクス研究者から登録された大量のプロテオームデータを管理している.また,これらのデータの再利用促進のために日本プロテオミクス学会主導で2019年にJournal of Proteome Data and Methods(JPDM)という新しいデータジャーナルが創刊された.JPDMでは生データが得られた手法の詳細を記述するData descriptor論文を主に扱う.本論文では,jPOSTプロジェクトが推進しているリポジトリ及びデータジャーナルの現状について議論したい.
2 0 0 0 OA 〔謡本〕
- 巻号頁・発行日
- vol.清経,
2 0 0 0 OA 妊娠中の白血球増多と白血球活性度
- 著者
- 飯島 悟 高山 典子 久保 武士 岩崎 寛和 菊池 佑二
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本バイオレオロジー学会
- 雑誌
- 日本バイオレオロジー学会誌 (ISSN:09134778)
- 巻号頁・発行日
- vol.4, no.2, pp.26-32, 1990-06-30 (Released:2012-09-24)
- 参考文献数
- 20