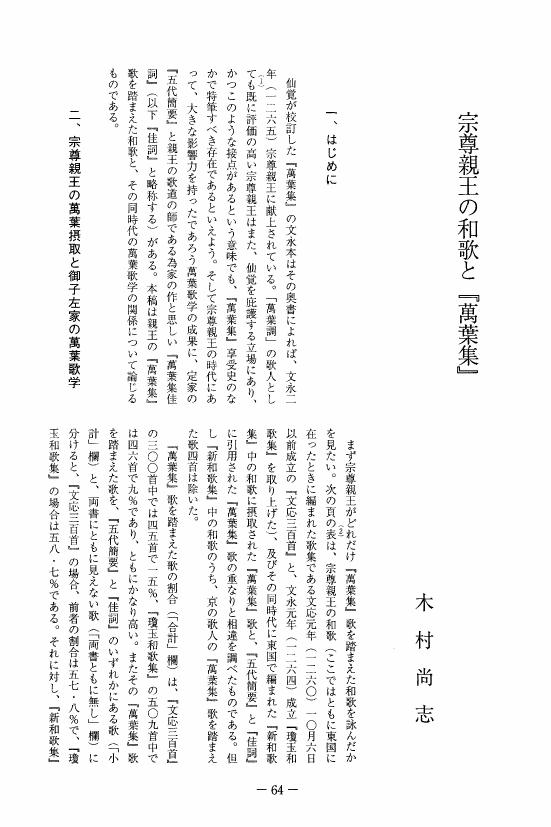2 0 0 0 OA はまる脳,リスク志向な脳:ウイルスベクターによる島皮質機能操作
- 著者
- 溝口 博之 山田 清文
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬理学会
- 雑誌
- 日本薬理学雑誌 (ISSN:00155691)
- 巻号頁・発行日
- vol.153, no.5, pp.224-230, 2019 (Released:2019-05-14)
- 参考文献数
- 35
依存症は世界銀行・WHO(世界保健機関)が報告するDALY(障害調整生命年)によると,世界トップ10に入る健康を脅かす疾患である.中でも,アルコール乱用を初めとする物質依存・薬物使用障害のDALYは若年層において非常に高い数値を示している.国内に目を向けても,薬物逮捕ラッシュの芸能界が表すように薬物汚染は止まっていない.また統合型リゾート推進法の成立により日本でもカジノが解禁されることから,ギャンブル依存者の急増という社会的且つ医薬学的問題も懸念される.さらにWHOはゲーム障害を精神疾患と認定したことからも,新たな依存症の包括的理解に向けた機序解明と医学的に適切な予防対策や治療戦略の発信が期待されている.ではなぜ,私たちはゲーム,ギャンブル,薬物に〝はまる〟のか? なぜ,一度手を染めた人はリスクを負っても危険ドラッグや覚せい剤の売買をするのか? なぜ治療したはずなのに依存症は再発するのか? どうして自分をコントロールできなくなるのか? そして,こうした症状は脳のどこから生まれるのか? 私たちはちょっと変わった視点(意思決定)から,依存者の脳と心の問題に迫ってきた.一方,近年の目まぐるしい実験技術の進歩により,遺伝子発現を制御するための多種多様なウイルスベクターが開発された.細胞特異的に遺伝子を発現させ,その細胞・神経の活動をコントロールすることも可能となった.今ではウイルスベクターを用いた行動薬理実験が当然のように行われ,顕著で分かりやすい研究成果が発表されている.著者らもこの手法を用いて特定の脳領域の活動や細胞活性を操作した時の意思決定について検討してきた.本稿では,意思決定について概説するとともに,当研究室で行ったウイルスベクターを用いた意思決定・行動選択研究への応用について述べる.
2 0 0 0 OA 大正期から現在までの 童謡をめぐる社会的イメージの変遷
- 著者
- 井手口 彰典
- 出版者
- 社会学研究会
- 雑誌
- ソシオロジ (ISSN:05841380)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.2, pp.3-20, 2015-10-01 (Released:2020-06-20)
- 参考文献数
- 36
「童謡」という言葉は今日、子供のための歌(とりわけ大正時代以降に発表されたもの)を指す名称として一般に用いられている。だが具体的に何をもって童謡とするのかはしばしば曖昧であり、たとえば学校唱歌やアニメソング、また近年の子供向けヒット曲を童謡と呼ぶのか否かは文脈によって異なる。 童謡をめぐるこうした概念の揺れは、この言葉が持つ歴史性と深く関係していると考えられる。そこで本稿では、童謡が子供のための歌という基本的な意味を獲得した大正期から現代までを対象に、音楽学者E・W・ポープのモデルを援用しつつ、童謡の社会的イメージの変遷過程を明らかにする。ポープによれば、社会に登場した異文化由来の記号は、当初「エキゾチック(/国際的/モダン)」なものとして受容されるが、次第に「普通」のものとして定着し、やがて「懐かしい(/国民的な/伝統的な)」ものへと推移していくことがあるという。童謡もまた、このモデルに沿った変化を見せている。すなわち、大正期に登場した童謡はモダンかつエキゾチックなものであったが、昭和に入るとレコードとラジオの普及によって普通のものになり、さらに一九六〇年代末頃からは徐々に懐かしさの対象へと変わっているのだ。 今日我々が漠然と抱いている「童謡」観は、この「懐かしい」段階に相当するものである。だがそうした理解は決して絶対的なものではなく、状況次第では「エキゾチック」ないし「普通」の時代の認識が呼び戻されることも少なくない。このことが、「童謡」という言葉が持つ社会的イメージの多様さの原因になっていると考えられる。
- 著者
- 北山 敦康
- 出版者
- 静岡大学教育学部
- 雑誌
- 静岡大学教育学部研究報告. 教科教育学篇 (ISSN:0286732X)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, pp.77-87, 2006-03
2 0 0 0 OA 福翁百話・福翁百余話
2 0 0 0 OA 宗尊親王の和歌と『萬葉集』
- 著者
- 木村 尚志
- 出版者
- 中世文学会
- 雑誌
- 中世文学 (ISSN:05782376)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, pp.64-72, 2009 (Released:2018-02-09)
- 著者
- 熊本 哲也
- 雑誌
- 岩手県立大学社会福祉学部紀要 = Bulletin of the Faculty of Social Welfare, Iwate Prefectural University (ISSN:13448528)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, no.1, pp.11-26, 2002-09-30
The Purloined Ribbon at the end of the Livre second of Jean-Jacques Rousseau's Confessions is known for the possibilities of various readings. The two most outstanding readings are: psychoanalytic literary analysis and deconstruction literary analysis. The former does not differentiate the "narrator" from the "narrated" in the text. The latter denies finally the analysis of the unconscious level and neglects the importance of the first half of the text while it is bound for the speech-act theory. In short, the precedent analysis tends to rely on theories and lacks the careful textual analysis. In order to construct a more inclusive literary critique, this paper focuses upon the desire theme of "The Death of Mme Vercellis" for it allows us to see the complicated interactions in the text. The textual analysis reveals that the words place (position) and perte (loss for the death) in the first half of the text are used effectively to show the analogical relationship between Mme Vercellis and her servant Marion to whom Jean-Jacques makes a false accusation of the stolen ribbon. By doing so, the narrator extends the meaning of place and perte to signify the symbolic death of Marion and sees Marion identifying with Mme Vercellis. In other words, Marion has the necessity to suppleer (fulfill) the loss of Mrs. Vercellis and has a role as a substitution to morn the deaths of both Mme Vercellis and Marion. Therefore, the exceeding desire of the narrator shows the connection between the text of "death" in the first half and the text of Stolen Ribbon Incident in the latter half of the Episode. The ribbon Jean-Jacques purloined literally ties the two texts by representing his "desire" and "mourning" for Mme Vercellis and Marion. In this sense, the purloined ribbon is just like a Freud's "bobbin" in The Beyond of the Pleasure Principle.
2 0 0 0 OA 日本における社会意識としての神観念
- 著者
- 定島 尚子 現代行動科学会誌編集委員会
- 出版者
- 現代行動科学会
- 雑誌
- 現代行動科学会誌 (ISSN:13418599)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, pp.1-5, 1995-09-01
お盆やお彼岸に先祖の墓参りをする人がクリスマスを祝い、その一週間後には神社に初詣でに行く…。私たち日本人の生活では、神道の要素、仏教の要素、キリスト教の要素が混在している。私達にとって宗教とは、神とは、どのような存在なのだろう。かつてイザヤ・ベンダサンは、「日本人は日本教徒等という自覚は全くもっていないし、日本教等という宗教が存在するとも思っていない。…(中略)…しかし日本教という宗教は厳として存在する。これは世界で最も強固な宗教である。というのは、その信徒自身すら自覚せぬまでに完全に浸透しきっているからである」(1)という指摘をしている。とすれば、“日本教”の教義、即ち、日本人の信仰形態の基底となる意識とはなんだろう。日本人の神観念の特徴の一つに“神人合一観”があると言われるが、私はこの言葉に深い興味を覚えた。つまり日本人にとって神霊は、極めて身近な存在と観念されているが故に殊更に意識することが無いのではないか、と考えたのである。こうした観念こそが、私達自身にさえ自覚し得ない程に深く浸透している宗教の基になっているように思える。そこで本研究ではこうした観点から日本人の神観念について考察していくことにする。
2 0 0 0 OA 海外における送電線着雪事故調査について
- 著者
- 黒岩 大助
- 出版者
- 公益社団法人 日本雪氷学会
- 雑誌
- 雪氷 (ISSN:03731006)
- 巻号頁・発行日
- vol.44, no.1, pp.43-47, 1982-03-30 (Released:2009-09-04)
- 参考文献数
- 3
- 著者
- Taku Suzuki Ryogo Furuhata Takuji Iwamoto
- 出版者
- The Japanese Society of Internal Medicine
- 雑誌
- Internal Medicine (ISSN:09182918)
- 巻号頁・発行日
- pp.0604-22, (Released:2022-10-19)
- 参考文献数
- 2
- 被引用文献数
- 1
2 0 0 0 OA 間質性肺疾患に対する呼吸リハビリテーションの課題と展望:Conの立場から
- 著者
- 花田 匡利 及川 真人 名倉 弘樹 竹内 里奈 石松 祐二 城戸 貴志 石本 裕士 坂本 憲穂 迎 寛 神津 玲
- 出版者
- 一般社団法人 日本呼吸ケア・リハビリテーション学会
- 雑誌
- 日本呼吸ケア・リハビリテーション学会誌 (ISSN:18817319)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.1, pp.93-98, 2022-12-26 (Released:2022-12-26)
- 参考文献数
- 20
近年,間質性肺疾患に対する呼吸リハビリテーションに関する報告が集積され,診療ガイドラインにおいても弱いながら推奨されるレベルに位置付けられている.しかし,不均質な病態かつ,難治性疾患という本疾患の基本的特徴は呼吸リハビリテーションに様々な影響を及ぼし,COPDを対象として確立されたエビデンスの高いプログラムを適用できないことも少なくない.そのため今後,従来の呼吸リハビリテーションとは異なる疾患特異的な方法論の確立,さらには維持プログラムのあり方が重要な課題となる.
2 0 0 0 OA 肺癌患者における肺切除術後の低酸素血症遷延の要因
- 著者
- 瀬川 凌介 及川 真人 花田 匡利 名倉 弘樹 新貝 和也 佐藤 俊太朗 澤井 照光 永安 武 神津 玲
- 出版者
- 一般社団法人 日本呼吸ケア・リハビリテーション学会
- 雑誌
- 日本呼吸ケア・リハビリテーション学会誌 (ISSN:18817319)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.1, pp.110-116, 2022-12-26 (Released:2022-12-26)
- 参考文献数
- 19
【目的】肺癌の外科治療では,術後に遷延する呼吸不全によって酸素療法の継続を余儀なくされる患者も存在する.本研究は,退院時に酸素療法を必要とした患者の割合と,その臨床的特徴を明らかにすることを目的とした.【対象と方法】本研究は単施設の後方視観察研究であり,2009年から2018年に長崎大学病院にて肺切除術を施行された肺癌患者を対象とした.診療録より,対象者背景,術前の呼吸機能および身体機能,手術関連項目,術後経過,退(転)院時転帰を調査した.【結果】解析対象者は1,256件で,そのうち46件(3.7%)が酸素療法継続となった.酸素療法継続に対して重要度が高い評価項目を推定するランダムフォレスト解析において,術前の肺拡散能や6分間歩行試験中の酸素飽和度低下が抽出された.【結語】肺切除術後患者において,術前の肺拡散能や6分間歩行試験中の酸素飽和度低下は,術後の酸素療法の必要性を予測する指標となる可能性が示唆された.
- 著者
- Susumu Yagome Takehiro Sugiyama Kosuke Inoue Ataru Igarashi Ryotaro Bouchi Mitsuru Ohsugi Kohjiro Ueki Atsushi Goto
- 出版者
- Japan Epidemiological Association
- 雑誌
- Journal of Epidemiology (ISSN:09175040)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.10, pp.476-482, 2022-10-05 (Released:2022-10-05)
- 参考文献数
- 25
- 被引用文献数
- 11
Background: Regular visits with healthcare professionals are important for preventing serious complications in patients with diabetes. The purpose of this retrospective cohort study was to clarify whether there was any suppression of physician visits among patients with diabetes during the spread of the novel coronavirus 2019 (COVID-19) in Japan and to assess whether telemedicine contributed to continued visits.Methods: We used the JMDC Claims database, which contains the monthly claims reported from July 2018 to May 2020 and included 4,595 (type 1) and 123,686 (type 2) patients with diabetes. Using a difference-in-differences analysis, we estimated the changes in the monthly numbers of physician visits or telemedicine per 100 patients in April and May 2020 compared with the same months in 2019.Results: For patients with type 1 diabetes, the estimates for total overall physician visits were −2.53 (95% confidence interval [CI], −4.63 to 0.44) in April and −8.80 (95% CI, −10.85 to −6.74) in May; those for telemedicine visits were 0.71 (95% CI, 0.47–0.96) in April and 0.54 (95% CI, 0.32–0.76) in May. For patients with type 2 diabetes, the estimates for overall physician visits were −2.50 (95% CI, −2.95 to −2.04) in April and −3.74 (95% CI, −4.16 to −3.32) in May; those for telemedicine visits were 1.13 (95% CI, 1.07–1.20) in April and 0.73 (95% CI, 0.68–0.78) in May.Conclusion: The COVID-19 pandemic was associated with suppression of physician visits and a slight increase in the utilization of telemedicine among patients with diabetes during April and May 2020.
- 著者
- 川嶋 恵子 和栗 夏海 宮崎 玲子 田中 哲哉 三浦 多佳史 前田 純子 Keiko KAWASHIMA Natsumi WAGURI Reiko MIYAZAKI Tetsuya TANAKA Takashi MIURA Sumiko MAEDA
- 出版者
- 国際交流基金
- 雑誌
- 国際交流基金日本語教育紀要 (ISSN:13495658)
- 巻号頁・発行日
- no.11, pp.37-52, 2015
JF 日本語教育スタンダード準拠の海外の成人向け教科書『まるごと日本のことばと文化』の開発に合わせ、関西国際センターでは、この教科書を使って学ぶ学習者のためのサポートサイト「まるごと+(まるごとプラス)」を開発した。「『日本語を使ってできること』が増やせる」、「『リアリティ』のある練習ができる」、「大人が『楽しく使える』」の3つをキーコンセプトとして定め、課題遂行を意識した練習、異文化理解のための情報やきっかけを提供するサイトを目指すこととした。「まるごと+」は教科書の「入門A1」、「初級1 A2」の2つのレベルに対応した種々のコンテンツを提供しており、動画を使った会話練習や異文化理解のためのコンテンツを中心に、学習者や教師から好評を得ている。本稿では、「まるごと+」の開発方針とそれをどのように具現化したか、また、サイトの反響を報告する。
2 0 0 0 IR 水系Naイオン電池の電解液濃度効果
2 0 0 0 OA 薬害の教訓から考える——薬害エイズと血液行政——
- 著者
- 花井 十伍
- 出版者
- 日本保健医療社会学会
- 雑誌
- 保健医療社会学論集 (ISSN:13430203)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, no.2, pp.1-7, 2017-01-31 (Released:2018-07-31)
本稿では、輸入血液製剤による血友病患者等のHIV感染事件(薬害エイズ)の被害者であるという立場から、薬害エイズと呼んでいる一連の現象を概括するとともに、薬害という社会現象の多様性にも言及する。被害者が薬害の教訓を活かして欲しいと祈念するとき、それは制度的問題だけではなく、被害者が生きてきた経験そのものを知り、行動して欲しいという願いを含意するのである。
2 0 0 0 OA わが国の平均寿命の男女格差について(1)近年の男女格差について
- 著者
- 西田 茂樹 綿引 信義
- 出版者
- The Japanese Society of Health and Human Ecology
- 雑誌
- 民族衛生 (ISSN:03689395)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, no.3, pp.127-138, 1996-05-31 (Released:2010-06-28)
- 参考文献数
- 12
- 被引用文献数
- 1
Life expectancy of woman at birth usually exceeds that of man in developed countries. The purpose of this study is to explain the reason of such sex differential in life expectancy at birth in Japan in recent years, analyzing sex differentials of age-specific death rates and mortality rates by causes of death. The calculated life table and vital statistics in 1990 were employed for the analysis. The analysis of age-specific death rate showed that the sex differential of mortality in age 50 and over explained around 70% of the sex differential in life expectancy at birth. In contrast, the sex differential of mortality rate in age 0 explained only 1 % of the difference. From the analysis of mortality rate by causes of death, it was shown that sex differentials of mortality from malignant neoplasm, heart diseases, cerebrovascular diseases, pneumonia and bronchitis, suicide, and accidents mainly contributed to the recent sex differential of life expectancy at birth. Of these causes, malignant neoplasm was the leading contributor to the sex differential in life expectancy at birth. From these results, it is considered that elongation of male life expectancy at birth would be possible by improving the life-style.
2 0 0 0 IR ドイツにおける起訴法定主義
- 著者
- 内田 一郎
- 出版者
- 早稲田大学法学会
- 雑誌
- 早稲田法学 (ISSN:03890546)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, no.2, pp.333-357, 1965-03
2 0 0 0 OA 全学的な教育の質保証のための学生調査のデザイン
- 著者
- 村上 公子 栃澤 健史
- 出版者
- 日本インスティテューショナル・リサーチ協会
- 雑誌
- 大学情報・機関調査研究集会 論文集 第11回大学情報・機関調査研究集会 論文集 (ISSN:24363065)
- 巻号頁・発行日
- pp.150-151, 2022-11-11 (Released:2022-12-26)
教育の質保証においては、大学が提供するカリキュラムを中心とする教育に関する継続的な改善の取組が重要であり、そのためには教育成果の把握とそれに基づく自己点検・評価の実施と情報公開が欠かせない。学修者本位の教育が求められるなかでは、教育成果の把握において、学生の実態と意識を適切に把握することが重要となる。本報告は、大阪医科薬科大学を事例とした全学的な質保証のための学生調査デザインを報告する。
2 0 0 0 OA ピア・プレッシャーと従業員の自発性 : 先行研究の整理と理論的対立に関する研究
- 著者
- 金子 麻美 カネコ アサミ Asami Kaneko
- 雑誌
- 立教ビジネスデザイン研究
- 巻号頁・発行日
- vol.16, pp.33-44, 2019