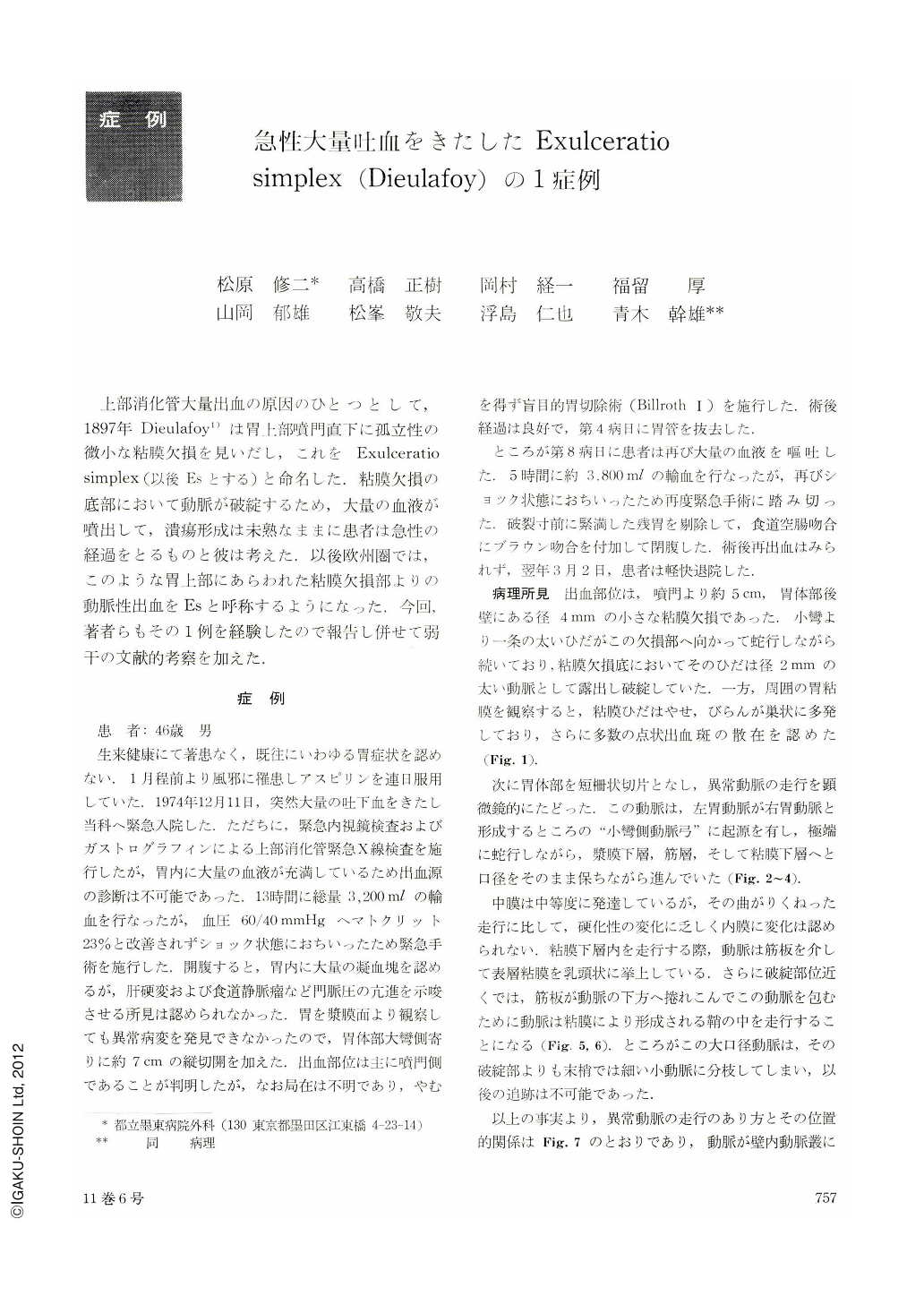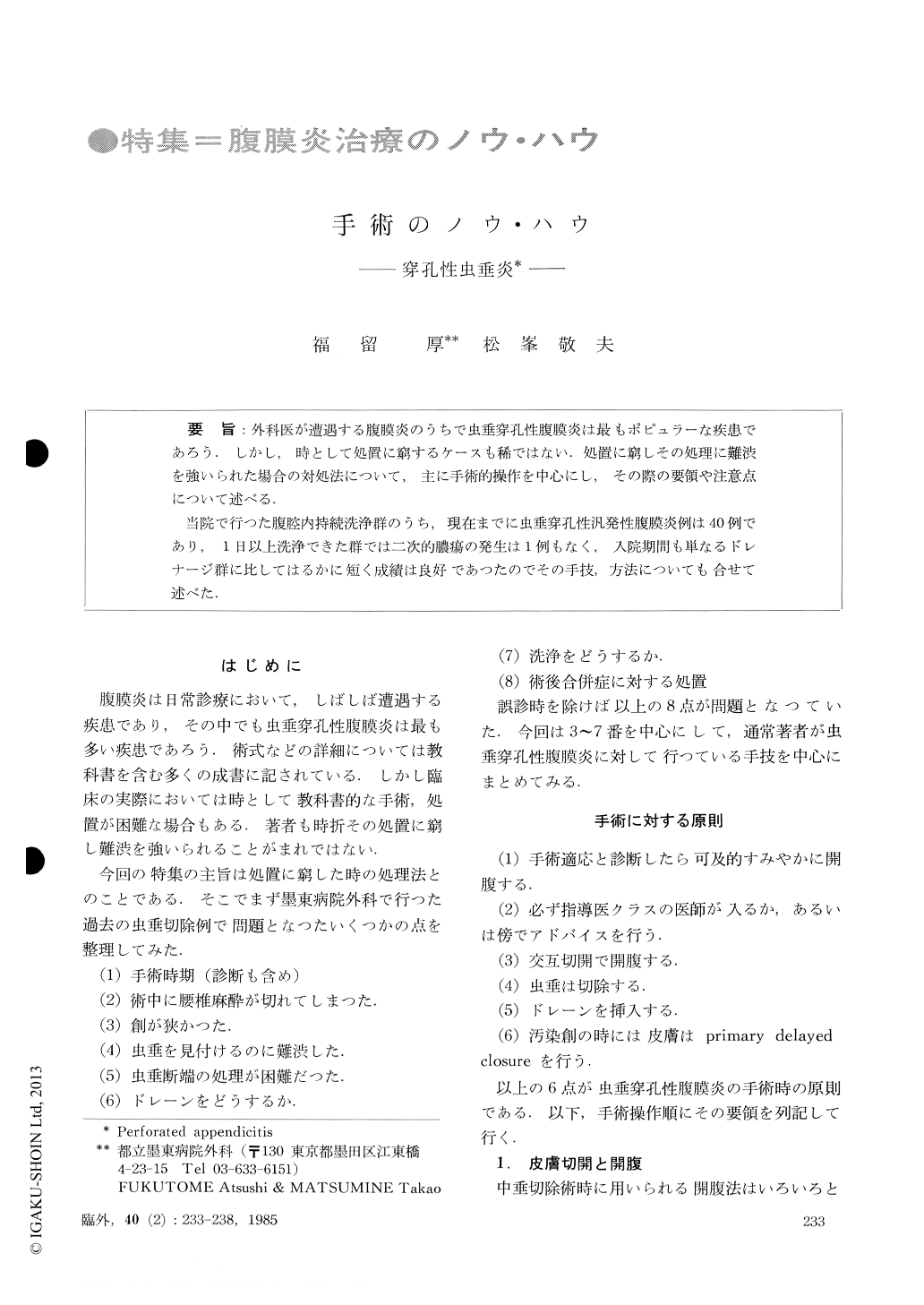2 0 0 0 OA 深層学習の中性子反射率への応用
- 著者
- 青木 裕之
- 出版者
- 日本結晶学会
- 雑誌
- 日本結晶学会誌 (ISSN:03694585)
- 巻号頁・発行日
- vol.64, no.4, pp.255-256, 2022-12-15 (Released:2022-12-17)
- 参考文献数
- 3
2 0 0 0 OA 東京湾で漁獲されたアメリカウミザリガニ
- 著者
- 工藤 孝浩
- 出版者
- 神奈川県立生命の星・地球博物館(旧神奈川県立博物館)
- 雑誌
- 神奈川自然誌資料 (ISSN:03889009)
- 巻号頁・発行日
- vol.2013, no.34, pp.41-42, 2013 (Released:2022-04-17)
A specimen of Homarus americanus H. Milne Edwards, 1837 was collected by beam trawl net at bottom off Yokohama, Tokyo Bay. This is the first record on the bases of specimen from the bay.
2 0 0 0 OA 後悔経験から適応に至るプロセスの個人差に関する検討――制御焦点と認知的感情制御に着目して
- 著者
- 伊藤 拓
- 出版者
- 日本パーソナリティ心理学会
- 雑誌
- パーソナリティ研究 (ISSN:13488406)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.1, pp.18-31, 2022-05-20 (Released:2022-05-20)
- 参考文献数
- 31
- 被引用文献数
- 1
本研究では,人が後悔を経験した後,適応的な変容に至るまでのプロセスを検討することを目的とした。大学生430名に対し,質問紙調査を行った。後悔の調整方略を規定する要因として「制御焦点」,後悔の調整方略として「認知的感情制御」,後悔の機能として「準備機能」に着目し,制御焦点が認知的感情制御に影響を与え,認知的感情制御が後悔を介して準備機能に影響を与えるというモデルを検討した。結果から,後悔の準備機能に至るいくつかのプロセスの存在が示唆された。例えば,促進焦点によって促された「肯定的再評価」が,後悔を低減するとともに,準備機能を促進するというプロセスや,予防焦点によって促進された幾つかの不適応的方略が,後悔を増大し,後悔が準備機能を促進するというプロセスなどが存在するようであった。また,不適応的方略の中でも促進焦点と結びつくものや,適応的方略の中でも,予防焦点と結びつき,後悔を増大するものの存在も示唆された。
- 著者
- 三宅 芙沙 増田 公明
- 出版者
- 一般社団法人 日本物理学会
- 雑誌
- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)
- 巻号頁・発行日
- vol.69, no.2, pp.93-97, 2014
放射性同位体の存在量測定による年代推定は,自然科学や考古学などの様々な場面で応用されている.測定対象となる同位体には^<14>Cや^<10>Beなどがあり,これらは地球に飛来して大気に突入した宇宙線が,大気中の原子核と相互作用することによって作られる.同位体の半減期と平均的な生成量がわかっているので,その濃度を調べることによって生成からの経過年数を知ることができる.逆に,年代がわかっている試料,例えば樹木の年輪や極地方の氷床中の同位体濃度を調べれば,当時の宇宙線の強度を知ることができる.宇宙線によって生成された^<14>Cは,二酸化炭素^<14>CO_2となり,さらに樹木へと取り込まれて年輪内で固定されるため,年輪中の^<14>C濃度は過去の宇宙線強度を「記録」しているのである.したがって太陽フレア,超新星爆発,ガンマ線バーストといった突発的高エネルギー宇宙現象も,^<14>C濃度の急激な増加として,その痕跡が記録されている可能性がある.このような背景のもと,我々は6-12世紀における屋久杉年輪中の^<14>C濃度を1-2年分解能で測定してきた.その結果,西暦774-775年,993-994年にかけての2つの^<14>C急増イベントを発見した.これらは1年程度の時間で急激な^<14>C濃度の上昇を示した後,10年のオーダーで減衰していく様子がきわめて似ており,同じ原因によって引き起こされたことが示唆される.さらにこの2イベントについては,ヨーロッパ産の年輪中の^<14>Cと南極の氷床中の^<10>Beにおいても全く同時期に濃度の異常上昇があったことがわかり,屋久島付近における局所的な現象ではなく,地球規模で何らかの大きな変動を与えた突発的宇宙現象がその原因であることが決定的となった.すぐさま,その宇宙現象が何であったかについての活発な議論が始まった.先に述べた太陽フレアやガンマ線バーストなどの現象について,その発生頻度や放出されるエネルギー,地球に与える影響などについて定量的評価が行われた.現在のところ最も有力と見られているのは,太陽表面の爆発によって地球に大量の放射線が降り注ぐSolar Proton Event(SPE)という現象である.また,見つかった2イベントにおける^<14>C濃度の上昇量を説明するためには,その規模は現在知られている最大の太陽フレアの10倍から数10倍であることも明らかになった.これまでに多くの研究者によって年輪中^<14>Cの1-2年分解能の測定が行われてきた期間は,合計すると約1,600年分になる.そしてその期間中,このような大規模なイベントが少なくとも2度起こっているというのは注目すべきことである.^<14>C濃度の上昇はきわめて短い時間で起こっており,本研究のような1-2年の分解能による測定で初めて発見することができるものであるが,この分解能による測定がなされていない期間に,このようなイベントがまだ過去に多く隠されている可能性は高いのである.過去の大規模フレア現象の頻度を正確に把握することで,太陽活動メカニズムの新しい知見を得るとともに,将来における「宇宙気象」の予測へとつながることなどが期待される.また観測史上最大のキャリントンフレア(1859)でも世界的に大きな影響があったことが知られており,その数10倍の規模のフレアが「珍しくない」とすれば,現代社会活動への諸影響を考えることも大変に重要である.
上部消化管大量出血の原因のひとつとして,1897年Dieulafoy1)は胃上部噴門直下に孤立性の微小な粘膜欠損を見いだし,これをExulceratio simplex(以後Esとする)と命名した.粘膜欠損の底部において動脈が破綻するため,大量の血液が噴出して,潰瘍形成は未熟なままに患者は急性の経過をとるものと彼は考えた.以後欧州圏では,このような胃上部にあらわれた粘膜欠損部よりの動脈性出血をEsと呼称するようになった.今回著者らもその1例を経験したので報告し併せて弱干の文献的考察を加えた. 症例 患 者:46歳 男 生来健康にて著患なく,既往にいわゆる胃症状を認めない.1月程前より風邪に罹患しアスピリンを連日服用していた.1974年12月11日,突然大量の吐下血をきたし当科へ緊急入院した.ただちに,緊急内視鏡検査およびガストログラフィンによる上部消化管緊急X線検査を施行したが,胃内に大量の血液が充満しているため出血源の診断は不可能であった.13時間に総量3,200mlの輸血を行なったが,血圧60/40mmHgヘマトクリット23%と改善されずショック状態におちいったため緊急手術を施行した.開腹すると,胃内に大量の凝血塊を認めるが,肝硬変および食道静脈瘤など門脈圧の亢進を示唆させる所見は認められなかった.胃を漿膜面より観察しても異常病変を発見できなかったので,胃体部大彎側寄りに約7cmの縦切開を加えた.出血部位は主に噴門側であることが判明したが,なお局在は不明であり,やむを得ず盲目的胃切除術(Billroth Ⅰ)を施行した.術後経過は良好で,第4病日に胃管を抜去した.
2 0 0 0 手術のノウ・ハウ—穿孔性虫垂炎
外科医が遭遇する腹膜炎のうちで虫垂穿孔性腹膜炎は最もポピュラーな疾患であろう.しかし,時として処置に窮するケースも稀ではない.処置に窮しその処理に難渋を強いられた場合の対処法について,主に手術的操作を中心にし,その際の要領や注意点について述べる. 当院で行つた腹腔内持続洗浄群のうち,現在までに虫垂穿孔性汎発性腹膜炎例は40例であり,1日以上洗浄できた群では二次的膿瘍の発生は1例もなく,入院期間も単なるドレナージ群に比してはるかに短く成績は良好であつたのでその手技,方法についても合せて述べた.
2 0 0 0 OA Longitudinal Association Between Oral Status and Cognitive Decline Using Fixed-effects Analysis
- 著者
- Sakura Kiuchi Taro Kusama Kemmyo Sugiyama Takafumi Yamamoto Upul Cooray Tatsuo Yamamoto Katsunori Kondo Ken Osaka Jun Aida
- 出版者
- Japan Epidemiological Association
- 雑誌
- Journal of Epidemiology (ISSN:09175040)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.7, pp.330-336, 2022-07-05 (Released:2022-07-05)
- 参考文献数
- 50
- 被引用文献数
- 2 13
Background: Although the feasibility of randomized trials for investigating the long-term association between oral health and cognitive decline is low, deriving causal inferences from observational data is challenging. We aimed to investigate the association between poor oral status and subjective cognitive complaints (SCC) using fixed-effects model to eliminate the confounding effect of unobserved time-invariant factors.Methods: We used data from Japan Gerontological Evaluation Study (JAGES) which was conducted in 2010, 2013, and 2016. β regression coefficients and 95% confidence intervals [CIs] were calculated using fixed-effects models to determine the effect of deteriorating oral status on developing SCC. Onset of SCC was evaluated using the Kihon Checklist-Cognitive function score. Four oral status variables were used: awareness of swallowing difficulty, decline in masticatory function, dry mouth, and number of teeth.Results: We included 13,594 participants (55.8% women) without SCC at baseline. The mean age was 72.4 (standard deviation [SD], 5.1) years for men and 72.4 (SD, 4.9) years for women. Within the 6-year follow-up, 26.6% of men and 24.9% of women developed SCC. The probability of developing SCC was significantly higher when participants acquired swallowing difficulty (β = 0.088; 95% CI, 0.065–0.111 for men and β = 0.077; 95% CI, 0.057–0.097 for women), decline in masticatory function (β = 0.039; 95% CI, 0.021–0.057 for men and β = 0.030; 95% CI, 0.013–0.046 for women), dry mouth (β = 0.026; 95% CI, 0.005–0.048 for men and β = 0.064; 95% CI, 0.045–0.083 for women), and tooth loss (β = 0.043; 95% CI, 0.001–0.085 for men and β = 0.058; 95% CI, 0.015–0.102 for women).Conclusion: The findings suggest that good oral health needs to be maintained to prevent the development of SCC, which increases the risk for future dementia.
2 0 0 0 OA 絹及び他の繊維素材布の熱伝導性
- 著者
- 山田 晶子
- 出版者
- The Japanese Society of Sericultural Science
- 雑誌
- 日本蚕糸学雑誌 (ISSN:00372455)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.4, pp.266-271, 1997-08-28 (Released:2010-07-01)
- 参考文献数
- 8
- 被引用文献数
- 2
絹と他の繊維素材布の熱伝導率を熱線法により20℃, 65%R. H. の環境で計測した。布の重ね枚数を50枚以上の厚さにすると, 再現性のある計測が可能である。布の構造的な特徴は, 低荷重で計測した布厚さから求められる繊維体積率に表れ, 布の熱伝導率は, 繊維体積率と一定の関係を示した。一般的に, 繊維体積率が増えると, 熱伝導率も高くなるが, 絹では羊毛と同様にその変化が小さく, 綿, 麻, ポリエステルでは変化が大きい。絹と他の繊維素材を比較すると, 絹は羊毛に次いで大きく, ポリエステル, 綿, 麻の順に熱伝導率が高くなることが分かった。布の熱伝導率λkから, 空気分率に相当する熱伝導率λaを引いて求めた繊維固有の熱伝導率λkfは, 絹では0.25と最も低くまた素材毎に固有な値を示した。布の熱伝導率λkと繊維固有熱伝導率λkfは相関を示し (0.68), フィラメント織物の絹・ポリエステルでは, 繊維固有熱伝導率に較べて布の熱伝導率が高く, 綿・羊毛などの紡績糸織物では布の熱伝導率が低い傾向が認められた。絹では, 繊維固有熱伝導率が繊維中最も低いが, 布になると羊毛より高く, ポリエステルより低いという特徴を示した。
2 0 0 0 宮崎駿にみる身体感覚 : 体感体験と創造性
- 著者
- 高橋 徹 松下 正明
- 出版者
- 日本病跡学会
- 雑誌
- 日本病跡学雑誌 (ISSN:02858398)
- 巻号頁・発行日
- no.82, pp.75-86, 2011-12
2 0 0 0 OA COVID-19下の情報拡散
- 著者
- 鳥海 不二夫
- 出版者
- 横断型基幹科学技術研究団体連合(横幹連合)
- 雑誌
- 横幹連合コンファレンス予稿集 第11回横幹連合コンファレンス
- 巻号頁・発行日
- pp.A-4-6, 2020 (Released:2020-11-21)
In 2019, COVID-19 began to spread in Wuhan, China, and became a pandemic that spread around the world. In the information society, various information is able to be diffused through social media. In such a situation, the diffusion of inappropriate information is called Infodemic, which has become a major social problem. In this paper, we investigate the diffusion of information on social media, which is a new information source in the modern information society. We have clarified how we shared and spread information under COVID-19. The results allowed us to capture shifts in topics of interest, which indicates that people may be losing interest in COVID-19 infection prevention information. We also found that “anger” emotions were often diffused on a large scale, which indicates that social anxiety may be increasing.
2 0 0 0 OA Teicopianin高用量投与の有用性と血中濃度
- 著者
- 上田 康晴 野口 周作 牧 真彦 上笹 宙 望月 徹 畝本 恭子 黒川 顕
- 出版者
- 公益社団法人 日本化学療法学会
- 雑誌
- 日本化学療法学会雑誌 (ISSN:13407007)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.1, pp.8-16, 2007-01-10 (Released:2011-08-04)
- 参考文献数
- 26
- 被引用文献数
- 4
救急領域におけるmethicillin-resistant Staphylococcus aums (MRSA) 感染症に対するteicoplanin (TEIC) の高用量投与 (初日1,600mg/日, 以降800mg/日) を実施し, 本薬剤投与後の血中トラフ値推移と有効性および安全性との関係について検討し, 下記の成績が得られた。(1) MRSAに起因する肺炎10例, 創部感染症2例に対するTEICの臨床的有効率は, 100%であった。(2) 細菌学的効果は全症例のうち, 消失9例, 減少1例, 菌交代2例, 不変0例であった。TEIC単独治療8例では消失7例, 減少0例, 菌交代1例, 不変0例で, 他薬剤併用治療4例では消失2例, 減少1例, 菌交代1例, 不変0例であった。なお全12例中4例にPseudomoms aeruginosaとの複数菌感染が認められた。(3) 投与例では本薬剤に起因する副作用は認められなかった。(4) TEIC血中トラフ値は, day2で17.5±6.7μg/mL, day4で163±6.3μg/mLと若干低下するものの定常状態となり, day8でも20.5±6.9μg/mLとTEICの蓄積は軽微であった。さらに各症例で, 血中濃度のばらつきも認めなかった。(5) TEICの高用量投与はその効果に抜群のキレがあり, しかも安全性の高いことが示され, 重症MRSA感染症の治療において非常に有用な投与法であると考えられた。
- 著者
- 福元 俊一 入江 紀嘉
- 出版者
- 一般社団法人日本建築学会
- 雑誌
- 学術講演梗概集. B-2, 構造II, 振動, 原子力プラント (ISSN:13414461)
- 巻号頁・発行日
- vol.2001, pp.793-794, 2001-07-31
2 0 0 0 OA 宇宙で作る氷の結晶(ヘッドライン:凍る化学と凍らない化学)
- 著者
- 古川 義純
- 出版者
- 公益社団法人 日本化学会
- 雑誌
- 化学と教育 (ISSN:03862151)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.6, pp.238-241, 2012-06-20 (Released:2017-06-30)
国際宇宙ステーション「きぼう」において,氷点下に冷却した水中で氷結晶の成長実験を行った。結晶の成長に伴い発生する潜熱のため,結晶内部や周辺には温度の分布が生じる。水の密度は温度に依存して変わるため,地上の重力下ではこれに起因する対流が発生し,これを避けることはできない。これに対し,宇宙空間では,長時間にわたる極めて良質な無重力環境が実現されるため,対流が完全に抑制され,理想的な環境での結晶成長の観察が可能である。本実験では,宇宙で使う実験装置の開発を行い,宇宙での見事な氷結晶の成長の様子を世界に先駆けて観察し,映像に収めることに成功した。宇宙では,見事な対称性を持つ結晶パターンが観察され,氷結晶の形態不安定化のメカニズムの解明に大きく貢献した。
2 0 0 0 OA 被害者の自殺事例と不法行為帰責論の今日の展開
- 著者
- 石橋 秀起 イシバシ ヒデキ Ishibashi Hideki
- 出版者
- 三重大学社会科学学会
- 雑誌
- 三重大学法経論叢 (ISSN:02897156)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.2, pp.1-53, 2004-03-15
論説 / Article
2 0 0 0 OA アルコール性脳障害の神経病理 ―一次性アルコール性認知症は存在するか? 剖検報告―
- 著者
- 池田 研二
- 出版者
- 認知神経科学会
- 雑誌
- 認知神経科学 (ISSN:13444298)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.3, pp.175-180, 2014 (Released:2017-04-12)
- 被引用文献数
- 1
アルコール認知症には一次性と二次性があるが、一次性アルコール認知症の存在については議論がある。アルコール依存症の自験剖検例の検討から、一次性アルコール認知症と考えられた1 症例の脳病理を紹介した。特徴は前頭葉を中心に皮質第III 層の錐体細胞の萎縮〜脱落であった。萎縮細胞は脳回の頂部に多く、谷部には少なかったことや海馬や小脳皮質プルキンエ細胞には見られなかったことから、この萎縮細胞は虚血性変化ではなく単純萎縮と考えられた。一次性アルコール認知症の議論にはさらなる症例の蓄積が必要である。
2 0 0 0 OA 抒情詩人レオパルディ随想
- 著者
- Talamanti Rosa
- 出版者
- イタリア学会
- 雑誌
- イタリア学会誌 (ISSN:03872947)
- 巻号頁・発行日
- no.2, pp.22-24, 1953-11-30
- 著者
- Hideo SUZUKI
- 出版者
- Center for Academic Publications Japan
- 雑誌
- Journal of Nutritional Science and Vitaminology (ISSN:03014800)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, no.6, pp.587-594, 1995 (Released:2011-02-07)
- 参考文献数
- 18
- 被引用文献数
- 10 13
A nutritional analysis was conducted on the dietary intake of a group of 6 vegan children aged 7 to 14 who had been living on a vegan diet including brown rice for from 4 to 10 years, and on that of an age-matched control group. In addition, their serum vitamin B12 levels and other data (red blood cell count, hematocrit, hemoglobin, etc.) were determined in the laboratory. In vegans' diets, 2-4g of nori (dried laver), which contained B12, were consumed daily. Not a single case of symptoms due to B12 deficiency was found. There were no statistically significant differences between the two groups with respect to any of the examination data, including B12 levels (p<0.05). Therefore, consumption of nori may keep vegans from suffering B12 deficiency.
2 0 0 0 OA 懲罰的損害賠償の現代的展開
- 出版者
- 日本私法学会
- 雑誌
- 私法 (ISSN:03873315)
- 巻号頁・発行日
- vol.2017, no.79, pp.151-157, 2017-04-30 (Released:2021-04-01)
- 参考文献数
- 4
- 著者
- 渡邊 優生 Yuuki WATANABE
- 雑誌
- 鈴鹿国際大学紀要Campana = Suzuka International University journal campana (ISSN:13428802)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, pp.151-168, 2007-03-20
It is well known that in response to the increase of foreigners in Japan, many volunteer associations have developed to teach foreigners Japanese. Additionally, in recent years the term Multicultural Coexistence is often heard. In this paper I intend to consider Japanese language volunteer activities in City A from the perspective of Multicultural Coexistence. I will also discuss the social role of Japanese language volunteers after analyzing their current role within Japanese society. Finally, I intend to investigate the current problems of Japanese language volunteers and connect these issues to activities that can be put into practice in the future.