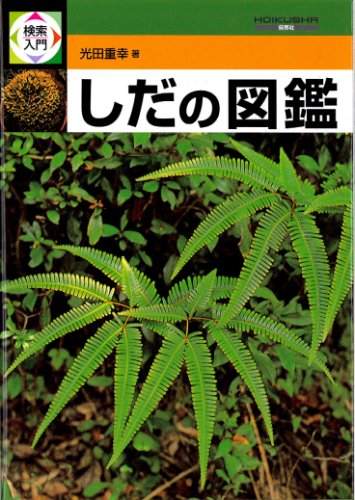2 0 0 0 OA 本朝尊卑分脈 10巻
2 0 0 0 OA 口蓋扁桃摘出術: 術後出血例の検討
- 著者
- 土井 彰 田村 耕三 赤木 博文
- 出版者
- 日本口腔・咽頭科学会
- 雑誌
- 口腔・咽頭科 (ISSN:09175105)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, no.3, pp.305-310, 2008-06-10 (Released:2010-06-28)
- 参考文献数
- 11
- 被引用文献数
- 2
口蓋扁桃摘出術後の出血は, 手術当日や術後1週間前後に多い. クリティカルパスウエイの中には, 術後1週間前に退院するものがあるが, 退院後の術後出血に関して, 十分に説明を行い注意文書を渡しているにもかかわらず, 術後管理の適否が問われる可能性がある. 退院後の術後出血では, 出血に対する迅速な対応ができないだけでなく, 不幸な転帰をとった場合, 出血状況および患者とその家族の対応や経過が立証しづらい状況にあり, 患者にとっても利益になるとは言いがたい. このような現状を踏まえ, 当院での口蓋扁桃摘出術後の症例について報告した.
2 0 0 0 OA 『水滸伝』中の美人描写
- 著者
- 曺 述燮
- 出版者
- 愛知淑徳大学交流文化学部
- 雑誌
- 愛知淑徳大学論集. 交流文化学部篇 (ISSN:21860386)
- 巻号頁・発行日
- no.3, pp.1-15, 2013-03-29
2 0 0 0 OA Transformerと自己教師あり学習を用いたシーン解釈手法の提案
- 著者
- 小林 由弥 鈴木 雅大 松尾 豊
- 出版者
- 一般社団法人 人工知能学会
- 雑誌
- 人工知能学会論文誌 (ISSN:13460714)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.2, pp.I-L75_1-17, 2022-03-01 (Released:2022-03-01)
- 参考文献数
- 63
Ability to understand surrounding environment based on its components, namely objects, is one of the most important cognitive ability for intelligent agents. Human beings are able to decompose sensory input, i.e. visual stimulation, into some components based on its meaning or relationships between entities, and are able to recognize those components as “object ”. It is often said that this kind of compositional recognition ability is essential for resolving so called Binding Problem, and thus important for many tasks such as planning, decision making and reasoning. Recently, researches about obtaining object level representation in unsupervised manner using deep generative models have been gaining much attention, and they are called ”Scene Interpretation models”. Scene Interpretation models are able to decompose input scenes into symbolic entities such as objects, and represent them in a compositional way. The objective of our research is to point out the weakness of existing scene interpretation methods and propose some methods to improve them. Scene Interpretation models are trained in fully-unsupervised manner in contrast to latest methods in computer vision which are based on massive labeled data. Due to this problem setting, scene interpretation models lack inductive biases to recognize objects. Therefore, the application of these models are restricted to relatively simple toy datasets. It is widely known that introducing inductive biases to machine learning models is sometimes very useful like convolutional neural networks, but how to introduce them via training depends on the models and is not always obvious. In this research, we propose to incorporate self-supervised learning to scene interpretation models for introducing additional inductive bias to the models, and we also propose a model architecture using Transformer which is considered to be suitable for scene interpretation when combined with self-supervised learning. We show proposed methods outperforms previous methods, and is able to adopt to Multi-MNIST dataset which previous methods could not deal with well.
2 0 0 0 OA 1848年革命期のダルマチアにおける国民統合の問題
- 著者
- 石田 信一
- 出版者
- 東欧史研究会
- 雑誌
- 東欧史研究 (ISSN:03866904)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, pp.35-58, 1994 (Released:2018-12-01)
2 0 0 0 IR 特別養護老人ホームを経営する社会福祉法人の 地域での公益的な活動に関する文献的検討
- 著者
- 神部 智司
- 出版者
- 大阪大谷大学
- 雑誌
- 大阪大谷大学紀要 = Bulletin of Osaka Ohtani University (ISSN:18821235)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, pp.99-108, 2019-02-20
2 0 0 0 IR 特集 総合政策学部シンポジウム講演会 現代日本における住まいの貧困
- 著者
- 稲葉 剛 岡本 祥浩
- 出版者
- 中京大学総合政策学部
- 雑誌
- 総合政策フォーラム (ISSN:18810071)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, no.11, pp.3-20, 2016
2 0 0 0 OA 「個別主義の帝国」ロシアの中央アジア政策 : 正教化と兵役の問題を中心に
- 著者
- 宇山 智彦
- 出版者
- 北海道大学スラブ研究センター
- 雑誌
- スラヴ研究 (ISSN:05626579)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, pp.27-59, 2006
This paper aims to challenge various traditional views of the Russian Empire: that it was a ruthless "Russirier"; that it had a universalistic and hannonious principle for integration; that in its last stage the empire was transforming itself to a nation-state. I try to do so by examining history of two unsuccessful projects of the Russian Empire in Central Asia, that is, Christianization as propagation of a universalistic ideology, and military conscription as a tool of nation building. Debates on Christianization of Central Asians began in the 1860s. The Kazakhs and Kyrgyz were considered to be half-Muslims, unlike Tatars and Uzbeks ("Sarts"), and therefore relatively easy targets for propagation of Orthodoxy. Opponents to Christianization, however, maintained that it could antagonize Muslims (including Kazakhs and Kyrgyz) and cause disorders. In Turkistan, whose Muslim sedentary population was called "fanatic," Governor-General Kaufman practically prohibited missionary activities. He did not object to General Kolpakovskii's support to missionary activities among the Kazakhs, Kyrgyz and Kalmyks in Semirech'e, but the results of proselytism there were meager. Throughout the second half of the nineteenth century, only about one thousand Central Asian natives converted to Orthodoxy. The Tsar's manifesto of religious toleration in April 1905, which conditionally sanctioned conversion from Orthodoxy to other faiths, dealt a final blow to missionaries. Most of the baptized Central Asians went back to Islam and almost no one was newly converted after this. Scenes of the revolt of 1916 in Semirech'e, where rebels killed monks and Russians in arms gathered in church squares, were highly symbolic in the sense that the Orthodox Church, after all, belonged to the Russians, not the native peoples of Central Asia. The second part of the paper examines discussions on military conscription of Central Asians, who were exempted from it as inorodtsy (aliens). One of the arguments for conscription was the necessity of strong cavalry in preparation for possible wars with China and Afghanistan. Officers cited the high quality of Central Asian nomads as horse-riders, and emphasized that military service was a powerful tool of Russification and the best school to teach public order. Again, a major argument against military conscription was the possibility of disturbances. Many officers feared that military service would give the population leaders for possible insurrections. Some also insisted that the conditions of military service radically contradicted the mode of life of nomads who were accustomed to unlimited freedom. Overall, they alleged that Central Asians' "low blagonadezhnost' (trustworthiness) and grazhdanstvennost' (level of civic development)" was a fundamental obstacle to their conscription. Officers evaluated the combat ability of various ethnic groups differently. They generally regarded the sedentary population of Turkistan as cowards and called the Kazakhs excellent horsemen but not necessarily courageous warriors, but were fascinated by the splendid quality of the Turkmen as warriors. This fascination gave birth to the exceptional case of the Turkmen irregular cavalry. After 1905, Russian nationalists increasingly asserted that Russians bore an unjustly heavy burden in defending the empire, and called for drafting inorodtsy. During World War I, the Ministry of War drew up a bill to draft almost all the ethnic groups of the empire, but the Ministry of Interior nixed it. In 1916, the government suddenly decided to mobilize Central Asians not as soldiers but as laborers, which gave rise to a huge revolt. On the whole, discussions of military service by Central Asians (which continued for more than half a century) took the character of a chicken-and-egg problem. Would military service enhance their grazhdanstvennost' and Russify them, or did military service require a sufficiently high level of grazhdanstvennost' and Russification? Eventually, officials who mistrusted inorodtsy always managed to block conscription proposals. Reasons for the failure of the two projects were partly rooted in the Russian bureaucracy. Permission for missionary activities was often given after much delay or was not given at all. The Orthodox Church itself had a hierarchical and bureaucratic structure. By contrast, Muslim mullahs went into the steppe as peddlers and healers without bureaucratic procedures, and could easily adapt themselves to local society. Moreover, officials' grasp of local situations was shaky. They thought that native administration of volosts and villages formed an "impermeable curtain" and hindered them from knowing Muslim life. The most important point of my analyses is the particularistic features or Russian policy. Many officials shared the view that it was desirable to Russify Central Asians, but there was hardly any resolute determination to carry out concrete measures for this purpose. They were interested in passive maintenance of stability rather than active integration and Russification. They did not just differentiate Central Asians from the Russians, but also differentiated nomads from sedentary people, the steppe oblasts from Turkistan. Officials were obsessed with the idea that they had to discuss the pros and cons of a policy measure in relation to every single region or ethnic group. This attitude of alienating (or otherizing) Central Asians and classifying them is what I call particularism. Particularism partly derived from a character inherent to autocratic empires. In such empires, a subjugated country or people pledged allegiance separately to the monarch, and were given peculiar privileges and obligations. But in the second half of the nineteenth and early twentieth centuries, quasi-academic discourses on ethnic characters added new meanings to particularism. Courageousness, warlikeness, trustworthiness and grazhdanstvennost' were considered to be characters of ethnic groups rather than qualities of individuals. This tendency to attach excessively great importance to ethnic characters was a product of Orientalism and the mind of the colonial state.
2 0 0 0 OA 超音波検査による甲状腺癌集団検診と穿刺吸引細胞診の成績
- 著者
- 小俣 好作 望月 敬司 千野 正彦 井口 孝伯 飯田 龍一 渡辺 秀夫 山本 雅博 古家 正道 浅尾 武士 田中 昇
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本臨床細胞学会
- 雑誌
- 日本臨床細胞学会雑誌 (ISSN:03871193)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, no.4, pp.680-685, 1985 (Released:2011-11-08)
- 参考文献数
- 20
- 被引用文献数
- 5 2
超音波検査による8,976名の甲状腺癌集団検診において, 496名の穿刺吸引細胞診が施行され, 男性14名 (0.22%), 女性19名 (0.69%) に甲状腺癌を発見した. 癌の最大径の平均は11.9±4.2mmであり, その半数以上が10mm以下の小型癌であった.
2 0 0 0 OA 乳頭癌の遺伝子異常
- 著者
- 光武 範吏
- 出版者
- 日本内分泌外科学会・日本甲状腺外科学会
- 雑誌
- 日本内分泌・甲状腺外科学会雑誌 (ISSN:21869545)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.1, pp.2-5, 2021 (Released:2021-05-27)
- 参考文献数
- 10
甲状腺乳頭癌(papillary thyroid carcinoma:PTC)は甲状腺癌の約9割を占める頻度の高い癌である。PTCでは,mitogen-activated protein kinase(MAPK)経路を恒常的に活性化する変異が主たるドライバー変異とされ,PTC発生に大きな役割を果たしている。成人ではBRAFV600E 変異が多いが,年齢が低くなるとRET/PTCなどの融合遺伝子の頻度が上がる。また,放射線被ばくによって発生するPTCでも融合遺伝子の頻度が高い。近年,これらに加え,TERTプロモーター変異が注目され,この変異を持つPTCは,臨床病理学的な悪性度が高く,予後不良であることが分かってきた。この変異は,年齢と非常に強い相関があり,45歳くらいから検出されるようになり,高齢者ではその頻度が急増する。現時点で最もインパクトの高い変異である。
- 著者
- 廣光 俊昭
- 出版者
- 日本経済政策学会
- 雑誌
- 経済政策ジャーナル (ISSN:13489232)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, no.2, pp.51-72, 2022-04-27 (Released:2022-04-27)
- 参考文献数
- 34
現世代の決定は後続世代の厚生に影響を与える。世代間問題の解決のため、世代間に互恵性を導入したモデルを用いた考察を行う。モデルを模した経済実験を通じ、世代間で起こりうることへの洞察を深める。実験からは、後続世代役が先行世代役の振る舞いに同調することが明らかにされる。同調の存在を考慮すると、先行世代が協力に高い関心を持つ場合、世代を通じて協力の程度が高まる一方、先行世代の協力への関心の低い場合には、世代を通じて協力は低調におわる。
2 0 0 0 OA パネルデータからみた非正規雇用の現状と正規雇用への転換
- 著者
- 高橋 勇介
- 出版者
- 日本経済政策学会
- 雑誌
- 経済政策ジャーナル (ISSN:13489232)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.2, pp.1-12, 2021-04-30 (Released:2021-04-30)
- 参考文献数
- 14
- 被引用文献数
- 1
本稿では、非正規雇用から正規雇用への移行要因について、パネルデータを用いて検証した。本稿の主な結論は以下のとおりである。雇用保険に加入している、教育訓練給付制度を利用中である場合、正規雇用への移行が促進されていることが分かった。また、男性においては、医療・社会保険・社会保障の業種で、正規雇用への移行が進んでおり、雇用契約期間のない非正規雇用のほうが、正規雇用への移行が進みやすいことも判明した。
- 著者
- 後藤 謙太郎 増田 靖
- 出版者
- 一般社団法人 経営情報学会
- 雑誌
- 経営情報学会誌 (ISSN:09187324)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.3, pp.151-166, 2021-12-15 (Released:2021-12-24)
- 参考文献数
- 46
本稿の目的は,会社αの研究所で27年間にわたって開発され,製品化に至った製品Xの開発プロセスの中で生成された実践知の生成・変容・継承過程を,製品系譜学を用いた調査により明らかにすることである.そのため,調査方法として,実務者が研究者となり,自身の実務現場を調査する,創発的ビジネスフィールドリサーチを採用した.また実践共同体とバウンダリー・オブジェクトの概念を用いて分析を行った.その結果,企業研究所の組織実践における実践知の生成・変容・継承過程を明らかにし,社内に継承された実践知と,実践に埋もれ形式知化できるがされてこなかった実践知との質的な違いを見出した.
- 著者
- 谷 謙二 斎藤 敦
- 出版者
- 公益社団法人 日本地理学会
- 雑誌
- 地理学評論 Series A (ISSN:18834388)
- 巻号頁・発行日
- vol.92, no.1, pp.1-22, 2019-01-01 (Released:2022-09-28)
- 参考文献数
- 39
- 被引用文献数
- 7
2018年3月に公示され,2022年から実施される新高等学校学習指導要領では,「目標」と「内容」に地理情報システム(GIS)の利用を掲げた新科目「地理総合」が必履修科目とされた.本研究では全国の高等学校に対してアンケート調査を行ってGIS利用の現状と課題を明らかにし,「地理総合」の実施に向けて必要な対応を検討した.調査の結果,高校でのGIS利用率は23.9%であった.GISを利用している教員は,地理を専門とし,大学でGISを実習形式で学ぶか,GIS研修を経験し,情報機器の整備された学校に勤務する傾向がみられた.GIS利用者は無償のGISソフトやサービスを利用し,WebGISへの期待が大きい.GIS利用の課題として情報機器の整備が第一に挙げられ,普通教室での投影機器とインターネット接続の普及が急務である.その上でGISを利用できる教員を研修等により増やす必要がある.GIS研修に際しては,教員の意欲や技術を考慮し,WebGISの閲覧・操作を中心とした簡便な内容が求められる.
2 0 0 0 OA 地域在住の高齢者を対象としたクレアチニンとうつ症状および認知機能との関連
- 著者
- 李 成喆 島田 裕之 朴 眩泰 李 相侖 吉田 大輔 土井 剛彦 上村 一貴 堤本 広大 阿南 祐也 伊藤 忠 原田 和弘 堀田 亮 裴 成琉 牧迫 飛雄馬 鈴木 隆雄
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学Supplement Vol.41 Suppl. No.2 (第49回日本理学療法学術大会 抄録集)
- 巻号頁・発行日
- pp.0161, 2014 (Released:2014-05-09)
【はじめに,目的】近年の研究によると,心筋こうそく,脳卒中など突然死を招く重大な病気は腎臓病と関連していることが報告されている。クレアチニンは腎臓病の診断基準の一つであり,血漿Aβ40・42との関連が示されている。また,糖尿病を有する人を対象とした研究ではクレアチンとうつ症状との関連も認められ,うつ症状や認知症の交絡因子として検討する必要性が指摘された。しかし,少人数を対象とした研究や特定の疾病との関係を検討した研究が多半数であり,地域在住の高齢者を対象とした研究は少ない。さらに,認知機能のどの項目と関連しているかについては定かでない。そこで,本研究では地域在住高齢者を対象にクレアチニンが認知機能およびうつ症状とどのように関連しているかを明らかにし,認知機能の低下やうつ症状の予測因子としての可能性を検討した。【方法】本研究の対象者は国立長寿医療研究センターが2011年8月から実施した高齢者健康増進のための大府研究(OSHPE)の参加者である。腎臓病,パーキンソン,アルツハイマー,要介護認定者を除いた65才以上の地域在住高齢者4919名(平均年齢:72±5.5,男性2439名,女性2480名,65歳から97歳)を対象とした。認知機能検査はNational Center for Geriatrics and Gerontology-Functional Assessment Tool(NCGG-FAT)を用いて実施した。解析に用いた項目は,応答変数としてMini-Mental State Examination(MMSE),記憶検査は単語の遅延再生と物語の遅延再認,実行機能として改訂版trail making test_part A・B(TMT),digitsymbol-coding(DSC)を用いた。また,うつ症状はgeriatric depression scale-15項目版(GDS-15)を用いて,6点以上の対象者をうつ症状ありとした。説明変数にはクレアチニン値を3分位に分け,それぞれの関連について一般化線形モデル(GLM)を用いて性別に分析した。【倫理的配慮,説明と同意】本研究は国立長寿医療研究センターの倫理・利益相反委員会の承認を得た上で,ヘルシンキ宣言を遵守して実施した。対象者には本研究の主旨・目的を説明し,書面にて同意を得た。【結果】男女ともにクレアチニンとMMSEの間には有意な関連が認められた。クレアチニン値が高い群は低い群に比べてMMSEの23点以下への低下リスクが1.4(男性)から1.5(女性)倍高かった。また,男性のみではあるが,GDSとの関連においてはクレアチニン値が高い群は低い群に比べてうつ症状になる可能性が高かった1.6倍(OR:1.62,CI:1.13~2.35)高かった。他の調査項目では男女ともに有意な関連は認められなかった。【考察】これらの結果は,クレアチニン値が高いほど認知機能の低下リスクが高くなる可能性を示唆している。先行研究では,クレアチニン値は血漿Aβ42(Aβ40)との関連が認められているがどの認知機能と関連があるかについては確認できなかった。本研究では先行研究を支持しながら具体的にどの側面と関連しているかについての検証ができた。認知機能の下位尺度との関連は認められず認知機能の総合評価指標(MMSE)との関連が認められた。しかし,クレアチニンとうつ症状においては男性のみで関連が認められたことや横断研究であるため因果関係までは説明できないことに関してはさらなる検討が必要である。【理学療法学研究としての意義】老年期の認知症は発症後の治療が非常に困難であるため,認知機能が低下し始めた中高齢者をいち早く発見することが重要であり,認知機能低下の予測因子の解明が急がれている。本研究ではクレアチニンと認知機能およびうつ症状との関連について検討を行った。理学療法学研究においてうつや認知症の予防は重要である。今回の結果は認知機能の低下やうつ症状の早期診断にクレアチニンが有効である可能性が示唆され,理学療法研究としての意義があると思われる。
2 0 0 0 OA パターン・ランゲージの開発を通じた相互研修型FDの実践コミュニティに関する事例検討
- 著者
- 長田 尚子 デイヴィス 恵美 髙尾 郁子 神崎 秀嗣 田中 浩朗
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育工学会
- 雑誌
- 日本教育工学会研究報告集 (ISSN:24363286)
- 巻号頁・発行日
- vol.2022, no.3, pp.34-41, 2022-10-03 (Released:2022-10-03)
継続的な授業改善を支援するために,実践コミュニティの存在が重要な役割を果たすとされている.しかしながら,実践コミュニティを誰がどのように構築するのか,そこで参加するメンバーはどのように行動するのか,そこでの行動によってコミュニティがどのように発展するのか,等については十分解明されていない.本研究では,相互研修型大学横断型FDの機会を通じて発展した実践コミュニティについて,当事者によるパターン・ランゲージの開発活動における談話例を用いて考察を深め,FDの領域における実践コミュニティ研究に関する課題を明らかにする.