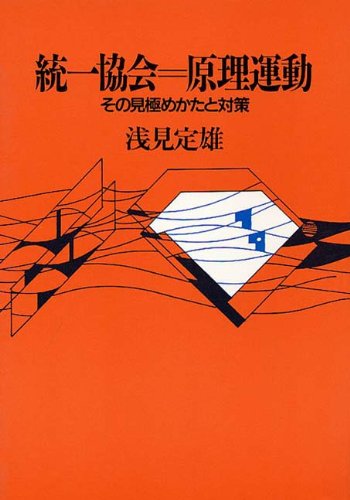2 0 0 0 OA 馬琴読本『開巻驚奇侠客伝』論 : 『封神演義』『通俗武王軍談』との関連を中心に
- 著者
- 三宅 宏幸
- 出版者
- 日本文学協会
- 雑誌
- 日本文学 (ISSN:03869903)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.2, pp.9-19, 2010-02-10 (Released:2017-08-01)
書翰に「挾客伝は得意の作」と書いた馬琴は、読本『開巻驚奇侠客伝(かいかんきょうききょうかくでん)』第一集自序に、書名にもなる「侠」を「身を殺して仁を成す者」と定めた。本稿では、馬琴が「仁」を持つ「侠客」を表現するため、「仁徳」を大義とする周王朝が殷王朝を伐つ殷周革命に取材した、中国白話小説『封神演義(ほうしんえんぎ)』及び通俗軍談『通俗武王軍談(つうぞくぶおうぐんだん)』を利用したことを指摘する。さらにこの殷周説話が、『侠客伝』の世界や構想に関わることを明らかにする。
2 0 0 0 OA 制御から媒介へ
- 著者
- 福田貴成
- 出版者
- 未来の人類研究センター
- 雑誌
- コモンズ (ISSN:24369187)
- 巻号頁・発行日
- vol.2022, no.1, pp.15-40, 2022 (Released:2022-05-11)
この論考は、父の介護経験の回想をもとに、介護における言語の機能と意味をメディア研究者の立場から考察したものである。2007年から父の没する2013年まで、筆者はヘルパー等のスタッフとともに父の介護に従事した。その過程では、父の心身状態についての詳細なメモ、そしてスタッフ間の情報共有を目的とする連絡ノートなど、相当量の言語記録が残されることとなった。 そこから読み取れるのは、とりわけ介護生活の初期において、言葉は主に「制御」的機能を果たしていたという点である。それは父の生の制御と同時に、スタッフの制御を目的としたものであった。そこに見られるのは「支配」への無意識の欲望であり、利他を標榜しながら結果的に利他を損なっていたことの痕跡である。 制御への傾向は介護の進展とともに変質してゆく。連絡ノートからはスタッフへの一方的な指示が消え、連携を促進する言語運用が目立つようになる。換言すれば、言葉は制御を離れ、「媒介」としての機能を見せ始める。さらにそこには、介護実践の全体が主従関係から解放され、ポジティヴな意味での「メディア経験」へと変容するさまが読み取れる。「制御」から「媒介」へのこうした移行について、本論では伊藤亜紗の利他論、そしてロラン・バルトの音楽聴取論を参照しつつ論じた。 末尾では、「制御から媒介へ」という図式には回収できない残余の存在を指摘した。ここで参照したのは、精神科医中井久夫の「徴候」概念である。時に不要なほどに詳細なメモは、制御欲の発露であると同時に、目の前で弱りゆく生命のなかに感知された微細な徴候——生命の終焉のサイン——の記録でもあったのではないか。そうした理解に基づくならば、筆者の介護生活における言語とは、来たるべき死と現在そして過去とをつなぐ「メディア」としての機能をも担っていたと言えよう。こうした意味で、筆者にとっての介護とは、二重の意味での「メディア経験」であったと考えられる。
2 0 0 0 OA Little Portugal and the Changing Spatial Structure of the Portuguese Community in Toronto
- 著者
- TAKAHASHI Koki
- 出版者
- The Association of Japanese Geographers
- 雑誌
- Geographical review of Japan series B (ISSN:18834396)
- 巻号頁・発行日
- vol.88, no.1, pp.1-22, 2016-02-15 (Released:2016-02-17)
- 参考文献数
- 43
- 被引用文献数
- 2 3
This study attempts to propose an alternative framework for examining the transformation process of traditional ethnic neighborhoods and understanding the changing spatial structure of ethnic communities in multiethnic cities in contemporary North America. Since the beginning of immigration, the Portuguese have been residing in Toronto for more than half a century. This community now faces a generational change. Toronto’s Portuguese community is examined by focusing on the ethnic functions that comprise its residences, businesses, and organizations in order to dismantle the complicated spatial structure of today’s ethnic community. From the 1970s through the early 1980s, such ethnic functions were concentrated in Little Portugal, located near downtown Toronto. During the 1980s, however, Portuguese residential space began to spread from Little Portugal to Toronto’s northern corridor and western suburbs. After the mid-1990s, Portuguese organizations relocated to the northern corridor. Moreover, the number of Portuguese businesses has decreased since the beginning of the 2000s, consequent to the aging of first-generation Portuguese and the inflow of non-Portuguese people, or gentrifiers. In other words, ethnic functions relocated from Little Portugal in multiple stages. However, Portuguese entrepreneurs still manage approximately half of the businesses in Little Portugal, and this traditional ethnic neighborhood remains the core area of the Portuguese community. Today, the Portuguese in Toronto utilize plural spaces depending on the content of their activities. Although the Portuguese community is spatially dispersed, its social ties are maintained on the basis of ethnicity, and these three spaces are thus closely connected with each other.
2 0 0 0 ブラウザの拡張機能を用いた脆弱なOAuth2.0実装の検知
- 著者
- 国広 真吾 鄭 俊俊 猪俣 敦夫 上原 哲太郎
- 雑誌
- 研究報告インターネットと運用技術(IOT) (ISSN:21888787)
- 巻号頁・発行日
- vol.2022-IOT-58, no.5, pp.1-8, 2022-07-05
OAuth2.0 を用いてユーザ認証の統合を行う Web アプリケーションが広く普及している.OAuth2.0 にはクロスサイトリクエストフォージェリ (以下 CSRF) 攻撃等に対する脆弱性が存在しており,開発者が Web アプリケーションに OAuth2.0 を実装する際に,URL に state パラメータを付与する等の対策をすることが必要とされている.しかし,CSRF 攻撃等に脆弱であるまま OAuth2.0 を実装している Web アプリケーションが複数確認されている.本研究では,CSRF 攻撃等に脆弱な OAuth2.0 の実装をしている Webアプリケーションを検知し,ユーザへ知らせる事で CSRF 攻撃等の被害を未然に防ぐ事を目的とし,ブラウザの拡張機能を用いて検知する手法を提案した.結果,ブラウザの拡張機能を用いることで,CSRF 攻撃への対策が不十分なまま OAuth2.0 実装をしている Web アプリケーションを検知することが可能であった.
2 0 0 0 統一協会=原理運動 : その見極めかたと対策
- 出版者
- 一般社団法人 電気学会
- 雑誌
- 電気学会論文誌A(基礎・材料・共通部門誌) (ISSN:03854205)
- 巻号頁・発行日
- vol.142, no.5, pp.NL5_1-NL5_4, 2022-05-01 (Released:2022-05-01)
2 0 0 0 OA 水の違いによる緑茶成分の抽出率
- 著者
- 渋谷 和代 左官 愛野 江端 恵加 渡部 絵里香 数野 千恵子 西島 基弘
- 出版者
- 日本調理科学会
- 雑誌
- 日本調理科学会大会研究発表要旨集 創立40周年日本調理科学会平成19年度大会
- 巻号頁・発行日
- pp.95, 2007 (Released:2007-08-30)
【目的】 緑茶を水道水、アルカリ電解水、およびRO水(逆浸透膜で得られた水)で抽出し、カテキン類、メチルキサンチン類、L-アスコルビン酸およびテアニンの抽出率の比較検討を行った。また、市販緑茶(18種類)中のそれらの含有量について検討した。 【方法】 緑茶の抽出は、茶葉を一定条件で抽出後、ろ液を試験溶液とした。カテキン類、メチルキサンチン類およびL-アスコルビン酸はHPLCを用いた。HPLC用カラム: J’sphere ODS – H80(4μm,4.6mmi.d.× 250mm)を用いた。L-アスコルビン酸はカラムは0.1Mリン酸一アンモニウムで置換したLiChrosorb-NH2(10μm,4mmi.d.× 250mm)を用いた。テアニンは、アミノ酸分析計で分析した。 【結果】 緑茶抽出液のカテキン類では、特にEGC、EGCG、EC、ECGが多く検出されEGC、EGCG、EC共にRO水の抽出が最も良く、次いでアルカリ電解水、水道水の順であった。ECはRO水、水道水、アルカリ電解水の順となった。メチルキサンチン類については、カフェインが最も多く検出され、RO水での抽出が最も良く、アルカリ電解水、水道水の順であった。テアニンについては、いずれの試料水も同程度検出された。市販緑茶のカテキン類は30~75mg/100mlであるが、「特保」や商品名に「濃い」と表示されているものは、100 mg/100ml以上のものが多く見られた。カフェインについても同じ製品では多く検出されたが、テアニンは特に多くはなかった。市販緑茶のL-アスコルビン酸は、3~40mg/100mlと製品により大きな差が見られた。
2 0 0 0 OA 水道浄水における中空糸膜浸漬型膜モジュール
- 著者
- 上原 勝 角田 務
- 出版者
- 日本膜学会
- 雑誌
- 膜 (ISSN:03851036)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, no.5, pp.316-327, 1995-09-01 (Released:2011-03-04)
- 参考文献数
- 25
- 被引用文献数
- 1 1
The study of water purification comes up to the stage of improving a whole system. Membranes and membrane modules should be modified or revised for the better performance. The membrane module ⌈STERAPORE F⌋ of Mitsubishi Rayon Co., Ltd is introduced as an example of improvement of them.
- 著者
- Hiroyuki Akai Koichiro Yasaka Haruto Sugawara Taku Tajima Masaaki Akahane Naoki Yoshioka Kuni Ohtomo Osamu Abe Shigeru Kiryu
- 出版者
- Japanese Society for Magnetic Resonance in Medicine
- 雑誌
- Magnetic Resonance in Medical Sciences (ISSN:13473182)
- 巻号頁・発行日
- pp.mp.2022-0020, (Released:2022-07-09)
- 参考文献数
- 27
- 被引用文献数
- 5
Purpose: This study aimed to evaluate whether the image quality of 1.5T magnetic resonance imaging (MRI) of the knee is equal to or higher than that of 3T MRI by applying deep learning reconstruction (DLR).Methods: Proton density-weighted images of the right knee of 27 healthy volunteers were obtained by 3T and 1.5T MRI scanners using similar imaging parameters (21 for high resolution image and 6 for normal resolution image). Commercially available DLR was applied to the 1.5T images to obtain 1.5T/DLR images. The 3T and 1.5T/DLR images were compared subjectively for visibility of structures, image noise, artifacts, and overall diagnostic acceptability and objectively. One-way ANOVA and Friedman tests were used for the statistical analyses.Results: For the high resolution images, all of the anatomical structures, except for bone, were depicted significantly better on the 1.5T/DLR compared with 3T images. Image noise scored statistically lower and overall diagnostic acceptability scored higher on the 1.5T/DLR images. The contrast between lateral meniscus and articular cartilage of the 1.5T/DLR images was significantly higher (5.89 ± 1.30 vs. 4.34 ± 0.87, P < 0.001), and also the contrast between medial meniscus and articular cartilage of the 1.5T/DLR images was significantly higher (5.12 ± 0.93 vs. 3.87 ± 0.56, P < 0.001). Similar image quality improvement by DLR was observed for the normal resolution images.Conclusion: The 1.5T/DLR images can achieve less noise, more precise visualization of the meniscus and ligaments, and higher overall image quality compared with the 3T images acquired using a similar protocol.
2 0 0 0 OA 憲法改正に関わる国民投票法における最低投票率設置についての検討
- 著者
- 大西 斎
- 出版者
- 九州法学会
- 雑誌
- 九州法学会会報 九州法学会会報 2015 (ISSN:24241814)
- 巻号頁・発行日
- pp.32-34, 2015 (Released:2017-08-10)
2 0 0 0 OA サケ由来の栄養が河畔林内の菌類(キノコ)に及ぼす影響(会員研究発表論文)
- 著者
- 長坂 有 長坂 晶子
- 出版者
- 北方森林学会
- 雑誌
- 北方森林研究 (ISSN:21867526)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, pp.109-112, 2013-02-18 (Released:2018-04-04)
2 0 0 0 OA 北上山地山村における森林利用の諸相(環境と歴史)
- 著者
- 岡 惠介
- 出版者
- 国立歴史民俗博物館
- 雑誌
- 国立歴史民俗博物館研究報告 = Bulletin of the National Museum of Japanese History (ISSN:02867400)
- 巻号頁・発行日
- vol.105, pp.319-355, 2003-03-31
本稿は,北上山地の山村における藩政時代以来の森林利用を,商品生産や生活のための利用などに分類しながらその実態を洗い出したものである。商品生産のための利用としては,藩政時代にその起源が求められる養蚕,狩猟,たたら製鉄,牛飼養,大正から昭和初期以降の枕木生産,製炭,昭和30年以降のパルプ・用材生産がある。年間伐採量を推定すると,森林に与えるダメージが大きかったといわれているたたら製鉄用の製炭による森林伐採は,昭和期の製炭やパルプ・用材生産のための森林伐採に比べればその規模は小さい。また,たたら製鉄は三陸沿岸に比較的多く,製塩の燃料用木材の伐採も同様で,北上山地の中央部では大規模な伐採はなかった。製炭による大規模な森林伐採は,昭和10年ごろからの自動車道路の開削によってスタートし,途中からパルプ・用材生産に移行しながら,林道の延長・整備によって昭和60年代まで継続し,安家の主たる生業の位置にあった。この50年以上にわたる森林伐採に耐えうる大径木の豊富な森林は,安家川中下流域では,たたら製鉄衰退後の明治から大正期に蓄積され,また上流域では藩政時代以来の蓄積によるものであったと考えられる。生活の中では様々な森林の植物が利用され,資源の枯渇を招くような採取はみられず,また道具類の素材になる性質・形状をもった野生植物が,巧みに利用されてきた実態が浮かび上がってきた。また信仰儀礼のための森林資源の利用が多く,山村の人々の心の部分においても,森林の資源が欠かせなかったことが確認できた。現在の森林利用の重要なものに燃料としての利用があり,未来にむけた循環型社会のモデルとして,山村の薪の伝統的な利用形態を支えていく地域のシステム作りが必要であると考えられる。
2 0 0 0 OA プロジェクト紹介 : 富山ライトレール
2 0 0 0 OA 吃音者に対するアクセプタンス&コミットメント・セラピー—症例研究—
- 著者
- 藤原 慎太郎
- 出版者
- 一般社団法人 日本認知・行動療法学会
- 雑誌
- 行動療法研究 (ISSN:09106529)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, no.3, pp.293-303, 2016-09-30 (Released:2019-04-27)
- 参考文献数
- 12
- 被引用文献数
- 2
本研究では、自動車ディーラーで働いていた吃音症状がある男性に対してアクセプタンス&コミットメントセラピー(ACT)を実施した効果について検討した。実施した介入は、吃音の回数を減らすことを目標とするのではなく、ACTの構成要素である価値に沿った行動活性化を中心に生活の質(QOL)を改善することを目標とした。対象者のQOLの評価のため、対象者が好んでいた余暇活動など対象者の価値に基づいた行動が生起した回数を記録した。結果的に、介入前はほとんど見られなかった余暇活動が増加し、また直接の介入対象ではなかったものの主観的な吃音の回数も減少し、これらの効果は3カ月後のフォローアップまで維持されていた。本研究では吃音者のQOL改善にACTが有用で、また介入の直接の目標ではないが吃音の減少に役立つ可能性が示された。
2 0 0 0 OA 歯口清掃による動揺度の改善 動揺度測定装置 (TMC-01) を用いての検討
- 著者
- 森田 学 鶴見 真由美 平岩 弘 坂田 真理子 岸本 悦央 近藤 充宏 渡邊 達夫
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本歯周病学会
- 雑誌
- 日本歯周病学会会誌 (ISSN:03850110)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.1, pp.205-210, 1987-03-28 (Released:2010-08-25)
- 参考文献数
- 21
- 被引用文献数
- 3 2
歯口清掃による歯の動揺度の改善を, より客観的に評価することを日的として, 動揺度測定装置 (TMC-01) を考案し, 臨床応用を試みた。この装置は, 歯を水平方向に移動させるのに必要な荷重を連続量 (g) で表示するものである。外来患者20名 (被検歯総数216本) を対象に, 来院時毎に, 徹底した歯口清掃と歯間部の清掃を主日的とした刷掃指導を行った。動揺度は, 初診時, 2週, 4週, 8週後にTMC-01を用いて測定し, 同時にプラーク付着状態も診査した。その結果, (1) 動揺歯の荷重平均は, 初診時101g, 2週後141g, 4週後147g, 8週後157gであり, 短期間のうちに著明な改善が認められた。 (2) 2週後で74%, 8週後で85%の動揺歯に改善が認められた。 (3) 初診時, 79g以下の力で動揺を示した歯は, 2週以後の改善傾向が減少したが, 809以上の力で動揺を認めた歯は, 期間全体を通じて改善した。以上より今回用いた装置は, 動揺度の測定に応用できる可能性が示唆された。
- 著者
- 坂野 達郎
- 出版者
- 一般社団法人 日本原子力学会
- 雑誌
- 日本原子力学会誌ATOMOΣ (ISSN:18822606)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.5, pp.268-272, 2017 (Released:2020-02-19)
- 参考文献数
- 7
無作為抽出した市民(ミニ・パブリックス)による討議を政策に反映させるための社会実験が世界各地で行われている。討論型世論調査は,そういった手法の一つである。本稿では,2015年3月に高レベル放射性廃棄物処分方法をテーマとしてWeb会議システムを用いて実施した討論型世論調査の概略を報告するとともに,同手法を合意形成や政策決定に活用する可能性について述べる。
2 0 0 0 IR 出版検閲における便宜的法外処分
- 著者
- 浅岡 邦雄
- 雑誌
- 中京大学図書館学紀要 = CHUKYO UNIVERSITY BULLETIN OF THE LIBRARY SCIENCE
- 巻号頁・発行日
- no.38, pp.1-22, 2018-03-01