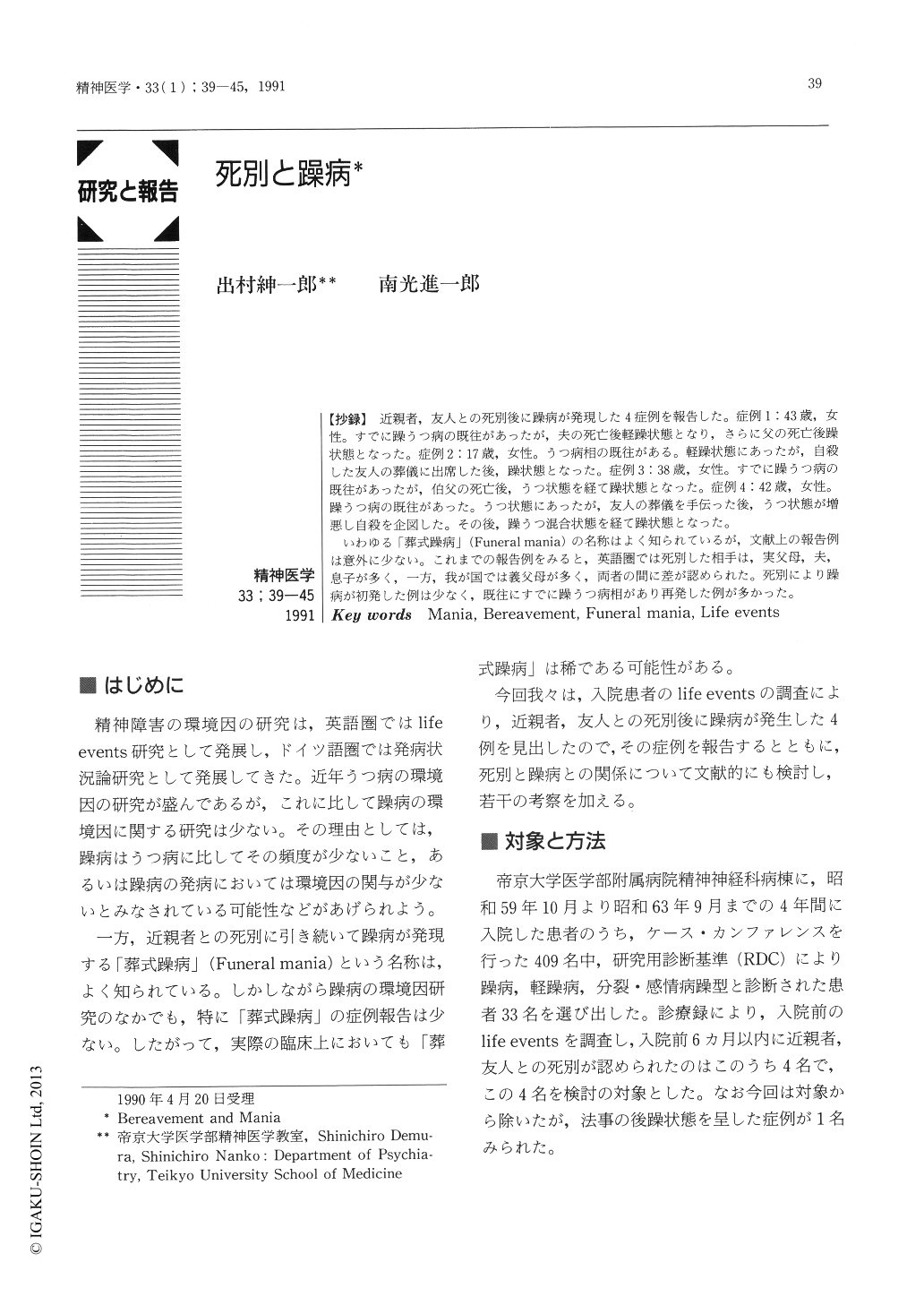2 0 0 0 OA テーマパークが都市に与える影響と街づくりに関する研究 東京ディズニーランドを対象として
- 著者
- 大迫 道治 横内 憲久 桜井 慎一
- 出版者
- 公益社団法人 日本都市計画学会
- 雑誌
- 都市計画論文集 (ISSN:09160647)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, pp.385-390, 1994-10-25 (Released:2019-02-01)
- 参考文献数
- 18
SPECIFICALLY, WE INVESTIGATED THE EFFECTS OF TOKYO DISNEYLAND ON THE FINANCES, CITIZEN'S CONSCIOUSNESS AND BUSINESS ESTABLISHMENTS IN THE CITY OF URAYASU, IN WHICH THE THEME PARK IS SITUATED. REGARDING ITS INFLUENCE ON MUNICIPAL FINANCES, IT WAS FOUND THAT THE DISNEYLAND-RELATED TAX REVENUE OF THE CITY WAS SO LARGE THAT IT ACCOUNTED FOR 10% OF THE CITY'S TOTAL TAX REVENUE. AS FOR THE PARK'S EFFECTS ON RESIDENTS' CONSCIOUSNESS, IT WAS LEARNED THAT MANY CITIZENS HAVE FAVORABLE IMPRESSIONS, NOT BECAUSE OF THE CREATION OF AMUSEMENT FACILITIES, BUT BECAUSE OF THE IMPROVEMENT OF THE CITY'S IMAGE. LITTLE INFLUENCE WAS NOTICED ON BUSINESS ESTABLISHMENTS, ON THE OTHER HAND. AS SEEN IN SCARCE NEW JOB CREATION OR INSIGNIFICANT LOCAL BUSINESS DEVELOPMENT STEMMING FROM TOKYO DISNEYLAND.
2 0 0 0 OA 長尾真先生を偲んで
- 著者
- 井佐原 均
- 出版者
- 一般社団法人 情報科学技術協会
- 雑誌
- 情報の科学と技術 (ISSN:09133801)
- 巻号頁・発行日
- vol.71, no.8, pp.k-1-k-2, 2021-08-01 (Released:2021-08-01)
2 0 0 0 IR カノッサの屈辱
- 著者
- 伊藤 保
- 出版者
- 上智大学外国語学部
- 雑誌
- 上智大学外国語学部紀要 (ISSN:02881918)
- 巻号頁・発行日
- no.6, pp.81-108,図1p, 1972-03
2 0 0 0 OA 青年期における恋愛と性行動に関する研究(1)デート状況と性行動の正当性認知との関係
- 著者
- 牧野 幸志 マキノ コウシ Koshi MAKINO
- 雑誌
- 経営情報研究 : 摂南大学経営情報学部論集
- 巻号頁・発行日
- vol.16, no.2, pp.1-10, 2009-02
本研究は,親しい関係にある男女が,どのようなデート状況において,どの程度の性行動を正当と考えるかを検討した。実験計画は,被験者の性別(男性,女性)×デートに誘う側(男性,女性からそれとなく,女性)×デート内容(映画,飲み会,相手のアパートへ,自分のアパートへ)の3要因被験者間計画であった。被験者は,大学生・短大生240名(男性120名,女性120名,平均年齢18.42歳)であった。従属変数は,性行動レベル別に,キス,ペッティング,性交の3測度であった。 3要因分散分析の結果,いずれの性行動測度においても,女性よりも男性のほうが,性行動を正当と認知していた。また,デート内容がより親密なものになるにつれて,性行動の正当性認知が高くなった。さらに,性行動レベルが進むにつれて,正当性の認知は低くなった。特にペッティングと性交については正当性認知が低かった。予想された被験者の性別とデートに誘う側の交互作用,3要因の交互作用は見いだされなかった。
2 0 0 0 OA 腰部脊柱管狭窄症診療ガイドライン2011
- 著者
- 稲毛 一秀 大鳥 精司 折田 純久 高橋 和久
- 出版者
- 一般社団法人 日本内科学会
- 雑誌
- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)
- 巻号頁・発行日
- vol.105, no.10, pp.2007-2011, 2016-10-10 (Released:2017-10-10)
- 参考文献数
- 6
- 著者
- Yamaguchi Atsushi
- 出版者
- 北海道大学大学院水産科学研究院
- 雑誌
- 北海道大学水産科学研究彙報 (ISSN:24353353)
- 巻号頁・発行日
- vol.71, no.1, pp.29-37, 2021-08-03
Respiratory oxygen consumption rates (at the two temperatures of 0-50 m and 50-200 m depth strata) and day/night biomass in the top 50 m water column were determined on adult female Metridia pacifica at twelve stations in the western/ eastern subarctic Pacific and one station in the oceanic Bering Sea during summer. At each station, the respiration rates at 0-50 m depth temperatures were used to estimate ingestion rates during nighttime by assuming empirical carbon budget efficiencies, and rates at 50-200 m to estimate respiratory carbon flux during daytime. The abundance of the females in the upper 50 m at night varied between 27 and 5,422 inds. m−2 and no specimen was collected from the same layer at daytime throughout the stations. The size of the females varied regionally from 25 to 77 μg C ind.−1. As a result, diel vertical migrant biomass of the females varied greatly from one station to the next (1 and 309 mg C m−2). Weight-specific respiration rates of the females were 2.2-6.3 μl O2 mg C−1 h−1, which was a function of experiment temperatures and body mass (C) of the females. Taking into account of residence time at 0-50 m and 50-200 m in the day, daily population ingestion was estimated as 0.04-11.04 mg C m−2 day−1, which accounted for 0-2.4% of primary production at each station. Daily population respiration in the 50-200 m was calculated as 0.02-9.39 mg C m−2 day−1, which corresponds to 0-10% of the POC flux down from the euphotic zone.
- 著者
- 後藤 崇志
- 出版者
- 心理学評論刊行会
- 雑誌
- 心理学評論 (ISSN:03861058)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, no.2, pp.129-144, 2020 (Released:2021-08-05)
- 参考文献数
- 89
Individuals usually imagine the future, set goals, make plans, and invest much effort in achieving these goals. However, individuals also often fail to achieve their goals by giving in to temptation. “Being good at self-control” is traditionally assumed to be key in achieving future goals. The present paper aims to clarify what “being good at self-control” means by reviewing psychological research about self-control. We suggest that the concept of “good at self-control” can be organized into two dissociated concepts: (1) “good at conflict resolution,” based on executive function (or cognitive control) and value representation (e.g., temporal discounting, value integration), and (2) “good at goal achievement,” based on value updating (e.g., habituation, goal internalization). We discuss related issues such as socialization or the agentic aspect of self-control, and we suggest avenues for future research on organizing the concept of self-control.
2 0 0 0 死別と躁病
【抄録】 近親者,友人との死別後に躁病が発現した4症例を報告した。症例1:43歳,女性。すでに躁うつ病の既往があったが,夫の死亡後軽躁状態となり,さらに父の死亡後躁状態となった。症例2:17歳,女性。うつ病相の既往がある。軽躁状態にあったが,自殺した友人の葬儀に出席した後,躁状態となった。症例3:38歳,女性。すでに躁うつ病の既往があったが,伯父の死亡後,うつ状態を経て躁状態となった。症例4:42歳,女性。躁うつ病の既往があった。うつ状態にあったが,友人の葬儀を手伝った後,うつ状態が増悪し自殺を企図した。その後,躁うつ混合状態を経て躁状態となった。 いわゆる「葬式躁病」(Funeral mania)の名称はよく知られているが,文献上の報告例は意外に少ない。これまでの報告例をみると,英語圏では死別した相手は,実父母,夫,息子が多く,一方,我が国では義父母が多く,両者の間に差が認められた。死別により躁病が初発した例は少なく,既往にすでに躁うつ病相があり再発した例が多かった。
- 著者
- 工藤 保則
- 出版者
- 仁愛大学
- 雑誌
- 仁愛大学研究紀要 (ISSN:13477765)
- 巻号頁・発行日
- vol.4, pp.57-66, 2006-03-31
10代については,これまでそのどこかに焦点をあてた研究はされてきたが,10代という10年間を単位として社会学的に研究されることはほとんどなかった.しかし,10代という時期は,時間的連続性の中でまとまった状態として,社会学的にもあらためて考える価値のある10年間だと考えられる.本稿は,その間題意識のもと,筆者がこれから行おうとしている,「都市と地方」の「10代」を比較しながら,それぞれの「地域性」とかかわる,かれらの「社会化」「ライフコース」についての研究の序説となるものである.
2 0 0 0 OA 半導体圧力センサの温度特性の解析
- 著者
- 嶋田 智 西原 元久 山田 一二 田辺 正則 内山 薫
- 出版者
- The Society of Instrument and Control Engineers
- 雑誌
- 計測自動制御学会論文集 (ISSN:04534654)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, no.10, pp.946-951, 1984-10-30 (Released:2009-03-27)
- 参考文献数
- 10
This paper describes an analysis of the temperature characteristic of piezoresistive semiconductor pressure sensors and its improvement. In this analysis the non-linear temperature dependence of thermal expansion of silicon is considered to calculate the thermal stress in the silicon diaphragm. The temperature characteristic of the sensor is then calculated considering the non-linearity of piezoresistive coefficients for temperature. This analysis reveals that the temperature characteristic strongly depends on the difference in thermal expansion between the silicon diaphragm and its mounting die. The appropriate dimension of the mounting die which minimizes this thermal stress is calculated and a trial pressure sensor is manufactured. The trial pressure sensor with a compensating circuit consisting of thermisters and resisters shows a good temperature characteristic; the zero point change and the span change are less than±1% for temperature range -40∼120°C.
2 0 0 0 OA 結合位相振動子系の安定性と同期現象
- 著者
- 中尾 裕也
- 出版者
- 公益社団法人 計測自動制御学会
- 雑誌
- 計測と制御 (ISSN:04534662)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.4, pp.335-342, 2016 (Released:2016-04-22)
- 参考文献数
- 33
2 0 0 0 OA 民族論の発展のために : 民族の記述と分析に関する理論的考察
- 著者
- 名和 克郎
- 出版者
- 日本文化人類学会
- 雑誌
- 民族學研究 (ISSN:24240508)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.3, pp.297-317, 1992-12-30 (Released:2018-03-27)
本稿の目的は, 「民族」に関する議論を, 理論的な側面において前進させることにある。前半では, 主観的定義と客観的定義, 重層性, 相対性, 「名」の問題など, 従来行われてきた「民族」に関する幾つかの議論を批判的に検討する。後半では, 筆者の「民族」に関する基本的な立場を, 内堀の民族論を大幅に援用しつつ述べる。民族は実体としては存在せず, 「名」と実体をめぐる民族論的状況のみが存在していること, 「民族」の原初的側面と手段的側面の関係は, 「民族」による個体の死の代替という仮説によって説明出来ること, 「民族」とは, 内堀が抽出した機構を通じて, 個体の死の代替物として想像される集団と定義出来ること, ネイションやエスニシティの問題もこうした機構無しには考えられないこと, ネイションとエスニック・グループの連続性を見失うべきでないこと, 民族誌家は「○○族は」という抽象化にはあくまで慎重であるべきことが主な論点である。
2 0 0 0 OA ラダ行音の構音発達についての研究
- 著者
- 大塚 登
- 出版者
- The Japan Society of Logopedics and Phoniatrics
- 雑誌
- 音声言語医学 (ISSN:00302813)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.3, pp.243-249, 1997-07-20 (Released:2010-06-22)
- 参考文献数
- 14
幼児の構音発達において/r/は/s, dz, ts/とならんでもっとも獲得の遅れる音, /d/は比較的早期に獲得されるとされてきた.しかし, 小学校入学前後の子どもでは聴覚弁別能力の未発達により/r/と/d/の誤りは互いに密接に影響しあうため, 別個に考えるより同一の誤りととらえるべきこと, 構音の誤りが書字にもあらわれるという報告もなされている.本報告では書字検査をもちいて小学校1, 2年生におけるラダ行音の構音獲得の状態をしらべた.1年生では7月では7%+α, 9月では約6%, 2年生では4%の子どもがまだ構音確立していないという結果をえた.同時に, 構音確立したあるいは確立間近の群では検査語間の難易度により誤答率に差が生じたが, 確立していない群では一様だった.検査語間の難易度と誤答率の関係から, 構音発達の予測の可能性が示唆された.
- 著者
- 本郷 隆
- 出版者
- 東京大学法科大学院ローレビュー編集委員会
- 雑誌
- 東京大学法科大学院ローレビュー
- 巻号頁・発行日
- vol.6, pp.127-162, 2011-09
2 0 0 0 烏口突起ホールインワンガイドの開発
- 著者
- 柴田 陽三 緑川 孝二 内田 洋子 渡辺 伸彦 緒方 公介 伊崎 輝昌
- 雑誌
- 肩関節 = Shoulder joint (ISSN:09104461)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.2, pp.351-355, 1997-06-25
- 被引用文献数
- 1
2 0 0 0 OA 一小児専門病院における最近24年間での精子凍結保存の経験
- 著者
- 角田 治美 古舘 和季 日野 もえ子 落合 秀匡 太田 節雄 種山 雄一 沖本 由理
- 出版者
- 日本小児血液・がん学会
- 雑誌
- 日本小児血液・がん学会雑誌 (ISSN:2187011X)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, no.5, pp.392-398, 2015 (Released:2016-02-06)
- 参考文献数
- 22
今回我々は,当施設(一小児専門病院として)での,最近24年間に行った思春期男性患者の精子保存の経験を報告する.2003年以前は,成人男性患者に対しても精子保存に関する全国的なガイドラインは存在しなかった.しかし我々は1990年以降思春期男児とその家族に治療関連性不妊と精子保存の説明を行い,同意が得られれば精子保存を行ってきた.現在まで精子保存の対象者は15例となり11例にはその説明を十分に行った.しかし2例は治療の緊急性により説明を行わず,2例は医師側の手違いにより説明を怠った.説明を行った11例中4例は精子保存を拒否している.保存を行った7例のうち2例が結婚し,1例は生殖補助技術により挙児を得,もう1例は妊孕性が回復し妻が自然妊娠した.1例は未婚であるが前処置軽減により造精能が回復した.現在まで精子保存を継続している患者は2例である.精子保存の本来の目的は妊孕性温存であるが,そのこと自体が精神的な励みになり,患者のQOL向上に寄与していると考えられる.良質な精子を得るためには治療前に精子を凍結保存するべきで,血液・腫瘍専門医は常にそのことを念頭に置き,患者に対して情報提供を行い他の医療者にも啓発していくことが必要である.精子保存に関する問題点として患者の適応基準,医療者側の情報提供の乏しさ,患者へのコミュニケーション不足,高い未婚率, 費用面などが挙げられ,今後我々は検討と対策を講じていかなければならない.
2 0 0 0 OA キアスム、非連続の連続 西田哲学と後期メルロ=ポンティ存在論の接するところ
- 著者
- 加國 尚志
- 出版者
- 西田哲学会
- 雑誌
- 西田哲学会年報 (ISSN:21881995)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, pp.72-84, 2017 (Released:2020-03-21)
La philosophie de Nishida Kitarô et la phénoménologie, malgré leur discordance qui s’impose à première vue, partagent en réalité d’importants points communs dans leur problématique fondamentale. Leur point de contact pourrait se trouver dans “le maintenant éternel”, qui est la notion ultime de la philosophie de Nishida, et dans “le présent vivant”, qui est la notion la plus fondamentale pour la philosophie transcendantale de Husserl. Le concept de “continuité du discontinu” chez Nishida nous permet de comprendre des termes contradictoires, par exemple, l’individu et l’universel, l’un et le multiple, à la faveur de leur coexistence dans l’identité en contradiction absolue ou dans la simultanéité des instants discontinus. Il nous permet de trouver le schéma de la dialectique absolue de Nishida, distinguée de celle de Hegel qui fait disparaître la contradiction de départ en synthèse finale comme négation de la négation. On peut trouver aussi une “dialectique” virtuelle, qui réconcilie la contradiction entre la présentation originelle et la dé-présentation, la présence originelle et l’absence, dans “le présent vivant” chez Husserl. Alors que Husserl n’a jamais utilisé le terme “dialectique”, Fink et Merleau-Ponty, ses successeurs, ayant développé la phénoménologie transcendantale husserlienne jusqu’au point où elle se transforme en ontologie du monde, font se détacher et se réactiver la dialectique virtuelle de leur ancêtre. L’ontologie de l’Être sauvage de Merleau-Ponty, qui rejette le négativisme aussi que le positivisme, s’en prend à la pensée dialectique de Hegel et de Sartre — laquelle définit l’être et le néant comme une contradiction absolue —, et exige de saisir l’être, plus primordial que cette contradiction, dans le mouvement infinie de “l’hyperdialectique”. Dans ses cours sur la dialectique, Merleau-Ponty évoque ainsi la thèse de la dialectique chez Platon :“L’identité est différence de différence.” La dialectique que Merleau-Ponty a trouvée consiste en une relation où l’identité et la différence, ou bien l’immanence et la transcendance, s’enveloppent l’une l’autre. Cette relation réciproque, il la trouve dans des expressions de Valéry telles que “chiasme” et “réversibilité”. Valéry a défini le chiasme comme l’échange des regards entre deux individus, entre moi et toi, comme l’état où l’on ne peut pas être ni un ni deux. C’est ici que nous pourrons comparer la philosophie de Nishida et celle de Merleau-Ponty, dans leur effort commun pour dépasser la pensée dialectique de Hegel, laquelle circonscrit la limite et la fin de la métaphysique occidentale, et où nous pourrons chercher leur point commun de départ pour la nouvelle métaphysique que l’on attend aujourd’hui.
- 著者
- 金谷 美和
- 出版者
- 日本文化人類学会
- 雑誌
- 文化人類学 (ISSN:13490648)
- 巻号頁・発行日
- vol.70, no.1, pp.77-98, 2005-06-30 (Released:2017-09-25)
本研究は、インド西部グジャラート州カッチの女性によって着用されている頭に被る布オダニーの着用に注目し、布の着用を通して作られるヒンドゥーとムスリムの境界について考察したものである。衣服が、着用者の属性を示し、コミュニティ間の境界を示す機能をもっことは知られている。しかし、コミュニティの境界そのものや、境界を指標する衣服は固定的ではなく、衣服の着用者の所属するコミュニティの外部との関わりのなかで変化してゆくものであるインドが英国の植民地から独立して以降、境界の明確化、差異化が進行しており、宗教的なアイデンティティの高まりや、宗教の違いによってコミュニティを区別することは、そのような変化の過程として捉えるべきである。オダニーは、婚家において女性が特定の姻族の男性から顔を隠すアンダルという既婚女性の慣習の媒体であり、その機能や意味はヒンドゥーとムスリムによって共有されていた。しかし、ここ50年ほどの間で、オダニー着用の方法や意味は、ヒンドゥーとムスリムで異なる方向に変化していった。その変化によって、ヒンドゥーとムスリムの境界は、衣服の違いとして明確になっていった。衣服による可視的な差異と境界の明確化と並行して、ヒンドゥーとムスリムという宗教の違いが、次第にコミュニティ帰属の最も重要な要素として人々に認識されるようになっていったのである。