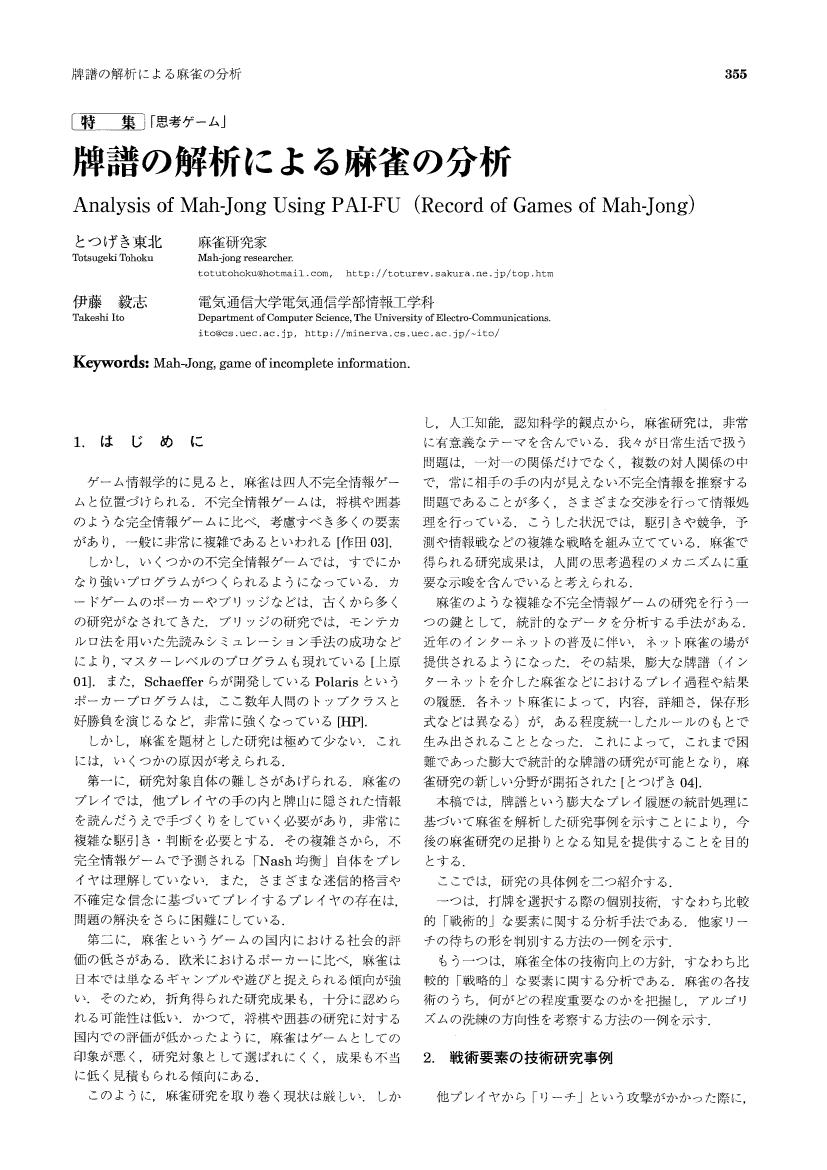- 著者
- 田中 乙菜
- 出版者
- 一橋大学学生支援センター学生相談室
- 雑誌
- 一橋大学学生相談室年報
- 巻号頁・発行日
- no.2, pp.1-10, 2020-12
本研究は、新型コロナウイルス感染症拡大に際し、学生相談室において継続的電話相談に従事した相談員にインタビューを実施し、その体験を明らかにした。インタビューの結果、電話相談がもつ面接の構造の難しさがあること、またその一方で、継続的に電話相談を実施することで、面接構造に変化が生じ、相談内容や、相談者・相談員の関係性が、対面相談時と同様になっていくこと等が示された。これらの結果をもとに、継続的電話相談の構造や意義、ならびに継続的電話相談が相談員に与えた影響について考察を深め、新型コロナ収束後における継続的電話相談のあり方について検討を行った。
2 0 0 0 IR 占領期沖縄における尖閣諸島沖の海底油田問題
- 著者
- 宮地 英敏
- 出版者
- 九州大学附属図書館付設記録資料館産業経済資料部門
- 雑誌
- エネルギー史研究 (ISSN:02862050)
- 巻号頁・発行日
- no.32, pp.107-127, 2017-03
2 0 0 0 戦後初期における旧軍関係教育機関出身者への施策
- 著者
- 白岩 伸也
- 出版者
- 教育史学会
- 雑誌
- 日本の教育史学 (ISSN:03868982)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, pp.45-57, 2017
<p>After the Potsdam Declaration, the Japanese government had to decide on the treatment of former military educational institution graduates (hereinafter referred to graduates), while attempting to transform the country's self-image from "Imperial Japan" to "Democratic Japan". The Ministry of Education tried to transfer many graduates to other schools. However, various discussions over the measure developed. This paper clarifies the formation of the measures for graduates in early postwar Japan by focusing on the trend of "demilitarization" and "democratization" and its scope.</p><p>In August 1945, the Ministry of Army and Navy began to negotiate with the Ministry of Education to transfer graduates to other schools. As a result, the Cabinet decided upon "preferential transfers" for graduates. However, when students started to criticize and CIE (Civil Information and Education Section) started to intervene, preferential transfers were abolished in November. "Restrictive transfers" that limited the number of graduates to ten percent of a school's capacity was determined in February 1946. Nevertheless, opinions criticizing restrictive transfers or insisting upon the necessity of re-education appeared. In addition, the discrepancy between the text of the Constitution of Japan and the Fundamental Law of Education and the measures was pointed out.</p><p>As described above, the measures were formed through "consultation" and "crossbreeding" with the Ministry of Army and Navy, the Ministry of Education, and CIE. The scope of "demilitarization" was interpreted differently by each organization, so that "demilitarization" and "democratization" developed a relationship of mutual conflict and reliance. It may be considered that the achievement of "demilitarization" and "democratization" was hindered, thus affecting later historical developments.</p>
2 0 0 0 OA 『前世記憶をもつ子どもたちの調査研究 -スリランカの転生のケースを中心に -』
- 著者
- 西田 みどり
- 雑誌
- 大正大學研究紀要 (ISSN:2186246X)
- 巻号頁・発行日
- no.101, pp.103-153, 2016-03-31
- 著者
- 内田 綾子
- 出版者
- アメリカ学会
- 雑誌
- アメリカ研究 = The American review (ISSN:03872815)
- 巻号頁・発行日
- no.54, pp.209-229, 2020
- 著者
- 清水 文枝
- 出版者
- 世界政経調査会国際情勢研究所事務局
- 雑誌
- 国際情勢 : 紀要 (ISSN:03858928)
- 巻号頁・発行日
- no.90, pp.197-206, 2020-03
- 著者
- 花田 智之
- 出版者
- 法政大学法學志林協會
- 雑誌
- 法學志林 = Review of law and political sciences (ISSN:03872874)
- 巻号頁・発行日
- vol.117, no.3, pp.121-149, 2020-03
2 0 0 0 OA 極域プランクトンーその特質の理解ー
本研究の目的は、極域に生息する海洋生物特に、食物網の底辺を支える植物・動物プランクトンに着目し、昇温や海洋酸性化に代表される環境の激変に対してこれら低次生物がどのように応答するのかを明らかにすることを目的としている。具体的には、西部北極海を研究対象海域とし、1)酸性化の脅威にさらされている炭酸塩プランクトンの応答の定量的評価、2)亜寒帯域に生息する植物プランクトン種の温暖化による極域進出の可能性の把握、3)他の海域に生息する種には見られない極域プランクトン種の特異的な機能を明らかにすることを目的としている。平成30年度は以下の研究を実施した。1海洋観測:西部北極海に2点設置したセジメントトラップ係留系の回収ならびに再設置とともにCTD/採水観測、各種センサーによる観測も行う。また、回収された係留系に蓄積された1年分の各層の流向・流速データについて衛星観測による海氷広域分布データとともに時系列の解析を行う。以上の計画どおり実施した。2海洋観測試料分析/データ解析ならびに遺伝子分析手法開発:回収された時系列セジメントトラップの生物起源粒子について検鏡による群集組成と18SrRNA配列を用いた定量的群集解析を実施する計画であった。検鏡観察による群集組成解析はほぼ計画通り実施したが、遺伝子解析については、再度、ホルマリン試料からの遺伝子レスキューの過程の見直しを実施しているところである。3プランクトンの培養・飼育実験ならびにMXCT法開発:北極海由来のプランクトンの炭化水素合成系酵素遺伝子について、現在も引き続き探索を行なうとともに、炭化水素合成量がこれまでより単位細胞あたり1桁多くなるような生育培養条件を見出す事ができた。MXCT法については、新たにオートサンプラー開発を行い、プランクトンの骨格密度測定の効率を上げ、高精度な解析が短時間で可能になるようシステムの高度化を行った。
2 0 0 0 IR 広橋兼秀の有職研究 : 中世貴族社会における「揚名介」認識の一例として
- 著者
- 渡辺 滋
- 出版者
- 国立歴史民俗博物館
- 雑誌
- 国立歴史民俗博物館研究報告 = Bulletin of the National Museum of Japanese History (ISSN:02867400)
- 巻号頁・発行日
- vol.190, pp.29-55, 2015-01
古代社会で発生した揚名官職(肩書だけで権限・給与が与えられない官職)をめぐっては、有職学(儀式・官職などに関する先例研究)の一環として、また『源氏物語』に見える「揚名介」の実態をめぐって、前近代社会のなかで長期に渡り様々な人々による検討がなされてきた。ところが先行研究では、一部の上級貴族をめぐる個別的・断片的な事例を除き、その展開過程について十分な分析がなされないまま放置されている。そこで本稿では、関連資料が豊富に現存する広橋家の事例を中心として、中世貴族社会における関連研究の展開を解明した。具体的に取り上げたのは、おもに広橋兼秀(一五〇六~一五六七)による諸研究である。国立歴史民俗博物館に所蔵される広橋家旧蔵本から、兼秀によって作成された関連資料を検出・分析することで、従来未解明だった広橋家における情報蓄積や研究展開の諸過程を解明した。その結果、彼の集積した諸情報は家伝のものだけでなく、周辺の諸家からもたらされたものも少なくないことが判明した。そこで中世の広橋家における有職研究の過程で蓄積された情報や、それに基づく研究成果を相対化するため、同家の周辺に位置する一条家・三条西家などにおける研究の展開も検討した。このように中世貴族社会における関連研究の展開過程も分析した結果、諸家における研究が相互に有機的関連を持っていたことや、とくに広橋兼秀の場合、一条家における研究成果から大きな影響を受けていた実態が判明した。以上のような展開のすえ、最終的に近世の後水尾上皇などへと発展的に継承される解釈が、基本的には中世社会のこうした営みのなかで形成されたことが確認された。There have been several studies on honorary official posts arisen during the Nara and Heian period. These studies, however, focused mainly on the investigation of institutions covering relevant historical materials and a true picture of "yomei no suke ", neglecting the analysis of its developmental process. Therefore, this article clarifies the development of relevant studies on Japanese aristocratic society during the Middle Ages by focusing on the case of the Hirohashi family whose relevant materials are left in large numbers. Several studies conducted by Kanehide Hirohashi (1506–1567) were addressed. I unraveled the Hirohashi family's accumulation of information and research development which had been not explored by detecting and analyzing relevant materials of old book collection of the Hirohashi family collected by Kanehide which are kept in the National Museum of Japanese History. The analysis revealed that materials collected by Kanehide were not only the ones of the Hirohashi family but also the ones brought by other aristocratic families nearby. Therefore, I examined the research development on other nearby families such as Ichijyo family and Sanjonishi family in order to compare the study on the Hirohashi family with the one on other nearby families. The analysis of developmental process of other relevant studies on aristocratic society during the Middle Ages confirmed that researches on several families were related to one another systematically and the studies of Kanehide Hirohashi drew significant influence from the research on Ichijo family. This analysis confirmed that the interpretation handed down to the retired emperor Gomizunoo in the early modern period was formed through these endeavors during the Middle Ages.
- 著者
- 小林 良彦 中世古 貴彦
- 出版者
- 北海道大学 高等教育推進機構 オープンエデュケーションセンター 科学技術コミュニケーション教育研究部門(CoSTEP)
- 雑誌
- 科学技術コミュニケーション (ISSN:18818390)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, pp.3-16, 2019-07
科学技術コミュニケーター像の探求に有益な情報提供を行うための試行調査として,求人・求職支援ポータルサイト「JREC-IN Portal」に掲載された求人情報の分析を行った.本研究では,5カ月間の調査を通して得た83件の求人情報における雇用条件や応募要件,また,そこから読み取れる職務や職能の実情を調べた.結果として,それらの求人情報を,URAや産官学連携コーディネーターを含む「URA相当」,研究機関や研究プロジェクトの広報担当者から成る「科学広報」,ジオパーク専門員を含む「科学館スタッフ」,そして,ファンドレイザー等の「その他」に大別することができた.さらに,担う職務や求められる職能が求人情報において詳述されていない,という現状も明らかにすることができた.これらの結果からは,想定する職種分類に応じた科学技術コミュニケーター養成のコンテンツ開発が求められること,そして,科学技術コミュニケーターの専門的な能力が未だ十分に認知されていない状況が示唆された.
- 著者
- 渡辺 滋
- 出版者
- 古代学協会
- 雑誌
- 古代文化 = Cultura antiqua (ISSN:00459232)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, no.4, pp.473-493, 2014-03
2 0 0 0 揚名国司論 : 中世的身分表象の創出過程
- 著者
- 渡辺 滋
- 出版者
- 公益財団法人 史学会
- 雑誌
- 史学雑誌 (ISSN:00182478)
- 巻号頁・発行日
- vol.123, no.1, pp.64-89, 2014
This article examines the early stages of the widespread acceptance and use in Japan of a new indicator of ranked status in the attachment of the prefix "yomei" 揚名 to the names of bureaucratic posts, a practice that is first seen in 10th century. The author takes up the actual case of attaching the prefix yomei to the post of provincial governor (kokushi 国司), clarifying its origins and historical development. Yomei-kokushi was used in the case of appointees who were considered to be of equal rank to a provincial governor, but were not entrusted with the actual duties of the post. Beginning with their appearance in the mid-Heian period, there is no doubt that the earliest yomei-prefixed appointments included neither official duties nor salaries. However, concerning the situation from the late Heian period on, the research to date diverges in opinion, leaving no solid conclusions. This state of affairs is what prompts the author to reexamine the related source materials from the period and in so doing finding three different definitions of "yomei", on of which consists of the prefix attached to the name of office and meaning, "an official title with no actual authority". The custom of attempting to obtain such a title began in the capital (Kinai 畿内) region during the 10th century, then spread to the outer provinces during the 11th century. The motives by which such a title was obtained were not only pecuniary through outright sale of the office, but also the desire on the part of patrons to bestow titles upon their subordinates for the purpose of strengthening ties of clientship. Up through the 11th century, the number of available yomei appointments was limited to less than the number of qualified applicants and involved a continuous turnover rate of from several months to a year. Later on, the title gradually decreased in value, until even yomei titles of low level local administrators became viewed as worthless. That being said, titles based on the bureaucracy defined by the ancient Ritsuryo legal codes, which by the beginning of the medieval period had long been empty of meaning, now became worth obtaining as expressions of ranked status throughout medieval society. The appearance of the title yomei-kokushi in the 10th century can therefore be placed within the context of symbols determining ways of thinking about how medieval Japanese society was supposed to function.
2 0 0 0 OA 違法性のある薬物 : 麻薬, 覚せい剤等(<特集>犯罪捜査に利用される化学)
- 著者
- 井上 堯子
- 出版者
- 公益社団法人 日本化学会
- 雑誌
- 化学と教育 (ISSN:03862151)
- 巻号頁・発行日
- vol.44, no.8, pp.506-509, 1996-08-20 (Released:2017-07-11)
麻薬, 覚せい剤, 大麻等の薬物事犯に関する記事が新聞に載っていない日はない位に乱用薬物は大きな社会問題のひとつであり, 特に, 最近は, 中高生のみならず小学生にまでその魔の手がのびてきている状況にある。これら違法性のある薬物の捜査には, 押収物件が違法性のある薬物か否かを検査することが不可欠であり, 特に, 捜査現場では, 迅速, 簡便かつ確度の高い予備検査が要求され, それぞれの薬物に比較的特異性の高い呈色反応が利用されている。
2 0 0 0 OA 詐欺罪の保護領域について 近年の判例を素材にして
- 著者
- 成瀬 幸典
- 出版者
- 日本刑法学会
- 雑誌
- 刑法雑誌 (ISSN:00220191)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.2, pp.281-294, 2015-02-28 (Released:2020-11-05)
2 0 0 0 東京都かすみケ関における空気中のホルムアルデヒド濃度
著者らが開発したホルムアルデヒド自動計測器を東京都内の国設自動車解説ガス霞ケ関測定所に収納し,1968年から常時測定を実施している。本報は最近9年間(1968~1976)のホルムアルデヒド濃度の測定結果をまとめたもので,つぎのようなことがわかった。<BR>ホルムアルデヒド濃度の1時間値は1ppbから73ppb,日平均値は1ppbから27ppb,月平均値は3.1ppbから19.1ppb,年平均値は4.6ppbから10.5ppbであった。ホルムアルデヒド濃度の日平均値は対数正規分布を示すことが認められた。ホルムアルデヒド濃度の日平均値とその目の瞬間最高値との関係はおおよそ1:2である。ホルムアルデヒド濃度は正午頃がもっとも高く,季節的には6月から8月の夏季に濃度が高く,とくに高濃度ホルムアルデヒド(1時間値20ppb以上)の出現には光化学反応が関与していることが認められた。
2 0 0 0 OA ソーシャルワークにみる行動療法アプローチの意義(展望,<特集>社会福祉と行動療法)
- 著者
- 津田 耕一
- 出版者
- 一般社団法人 日本認知・行動療法学会
- 雑誌
- 行動療法研究 (ISSN:09106529)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.2, pp.119-132, 2003-09-30 (Released:2019-04-06)
行動療法は、専門的な社会福祉実践であるソーシャルワークにおいて実践価値の高いものとして受け入れられている。本稿では行動療法がソーシャルワークに導入された経緯を概観し、ソーシャルワークにおける役割を検証する。特にソーシャルワークの趨勢となっている生活モデル、エンパワメント概念、ストレングスの視点と行動療法の関係を整理する。生活モデルに基づくソーシャルワークも行動療法も人間と環境との関係を重視しており両者の接点を見出す。最後に、わが国における行動ソーシャルワークの現状、課題、展望について考察する。
2 0 0 0 OA 〈侵略文学〉の文学史・試論
- 著者
- 小峯 和明 Komine Kazuaki
- 出版者
- 福岡大学研究推進部
- 雑誌
- 福岡大学研究部論集 A:人文科学編 = The Bulletin of Central Research Institute Fukuoka University Series A:Humanities (ISSN:13464698)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, no.6, pp.1-8, 2013-03
2 0 0 0 OA 酒母育成法 (三)
- 著者
- 杉山 晋朔
- 出版者
- 公益財団法人 日本醸造協会
- 雑誌
- 日本釀造協會雜誌 (ISSN:0369416X)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.5, pp.351-359, 1936 (Released:2011-11-04)
2 0 0 0 OA 牌譜の解析による麻雀の分析(<特集>思考ゲーム)
- 著者
- とつげき東北 伊藤 毅志
- 出版者
- 一般社団法人 人工知能学会
- 雑誌
- 人工知能 (ISSN:21882266)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, no.3, pp.355-360, 2009-05-01 (Released:2020-09-29)
2 0 0 0 OA 押川春浪『英雄小説 武侠の日本』の小説像 : 素材・構造・執筆動機を鍵として
- 著者
- 武田 悠希
- 出版者
- 日本近代文学会
- 雑誌
- 日本近代文学 (ISSN:05493749)
- 巻号頁・発行日
- vol.91, pp.1-16, 2014-11-15 (Released:2017-06-01)
本稿は、押川春浪の代表作とされる「海底軍艦」シリーズの論点となってきた「武侠」の定義が語られる『武侠の日本』を取り上げ、春浪が本作をどのように作り上げたのかを明らかにしようとするものである。特に、これまでの研究に欠けていた、春浪の創作態度を見るという視点を媒介させることによって、これまでの観念的に措定されたナショナリズムを指摘するにとどまる段階からの脱却をはかりたい。その際に手がかりとして、素材、構造、執筆動機を取り上げ、同時代言説との比較検証に留意することで、春浪が『武侠の日本』の創作にあたって、同時代の中での批判的意識を「面白さ」として加工し、それを小説という媒体に託すことを試みていたことを論証する。