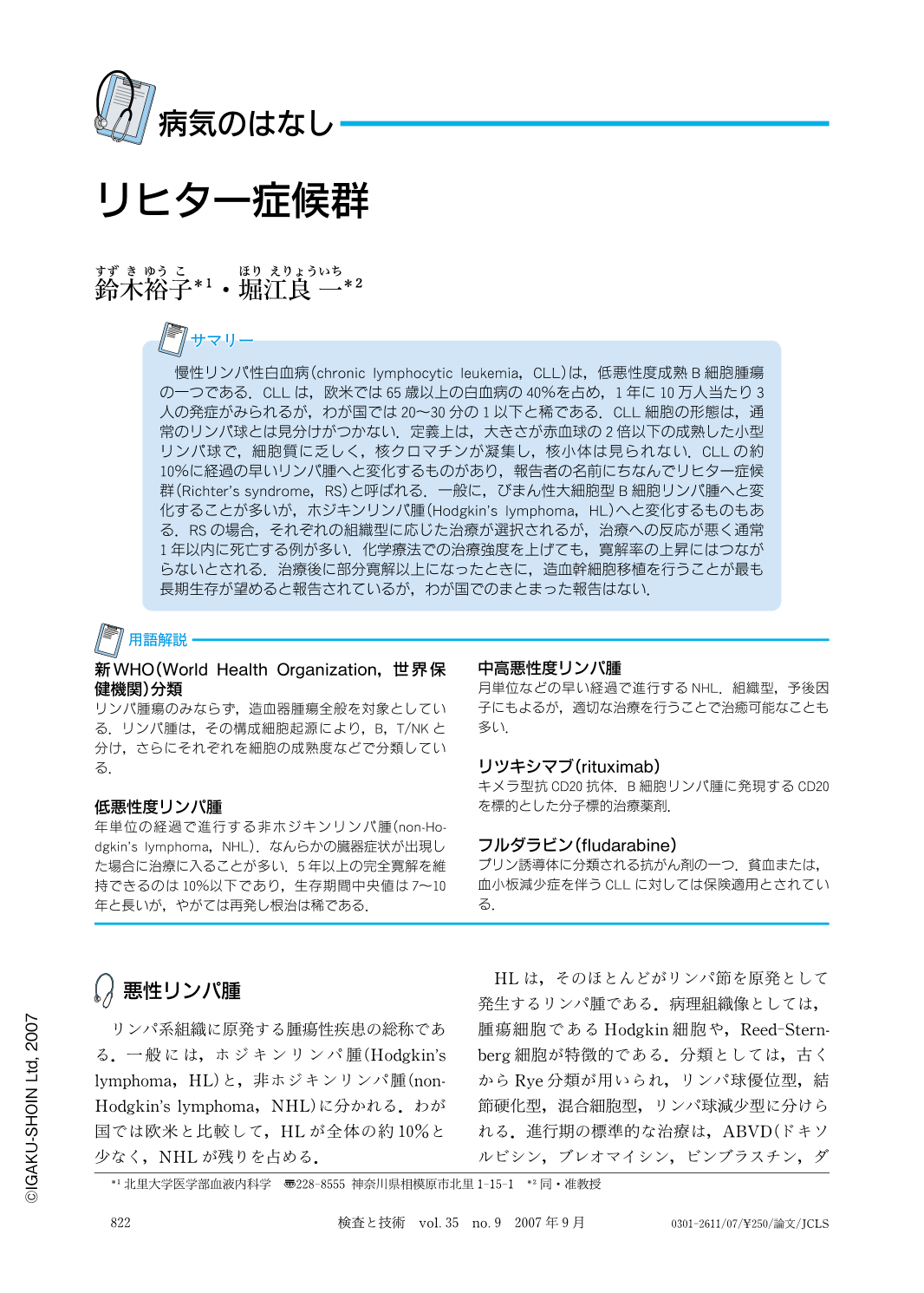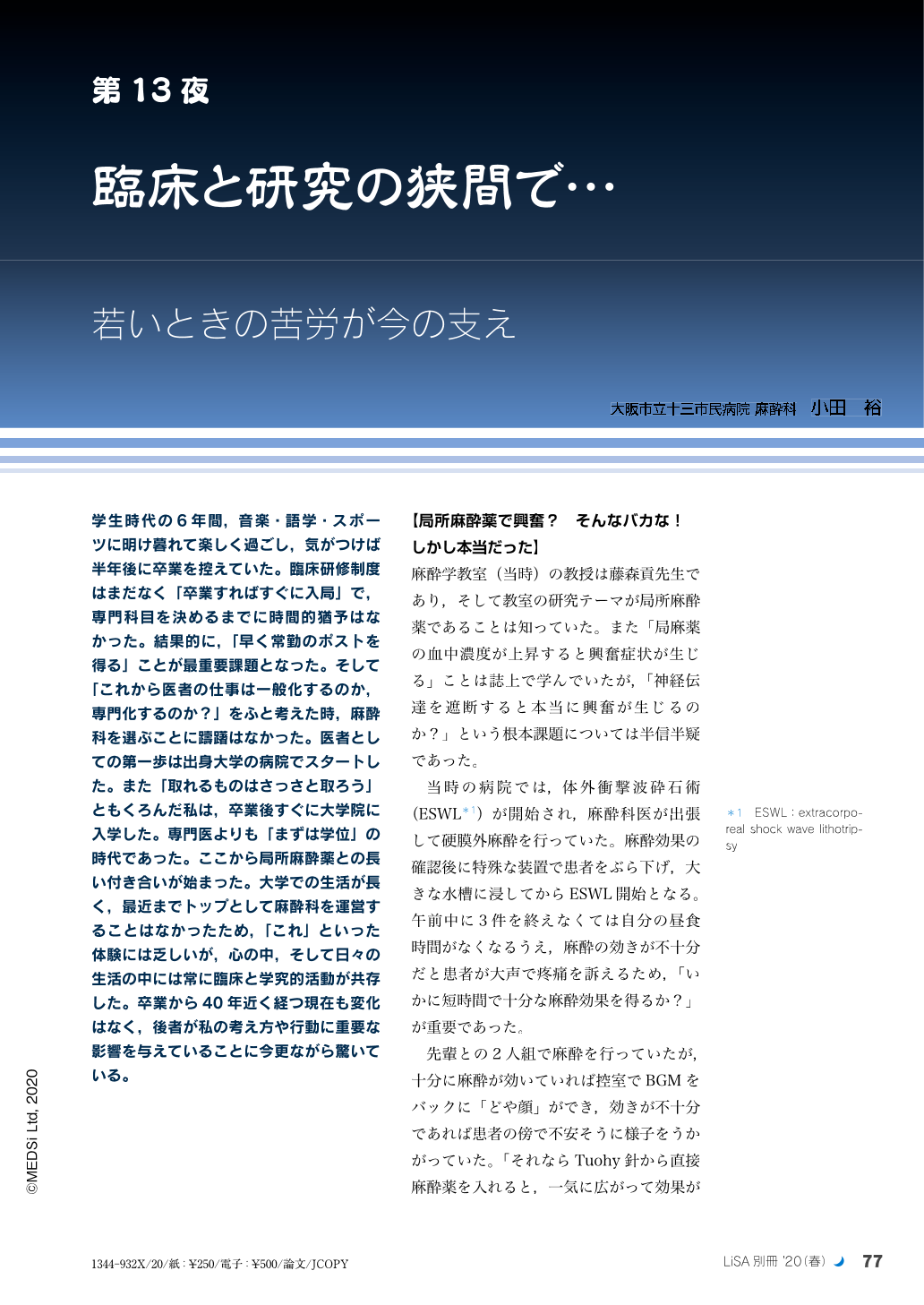- 著者
- 鈴木 陽一
- 出版者
- 一般社団法人 映像情報メディア学会
- 巻号頁・発行日
- pp.27-32, 2012-10-30 (Released:2017-09-21)
- 参考文献数
- 25
情報通信技術の進歩に伴い,マルチメディア情報通信技術の高次化への期待が高まっている。その方向の一つは,より自然でリアルなコミュニケーションシステムの実現であろう。そのためには,情報の受け手である人を意識し,臨場感や迫真性,自然性など高度感性情報の創出技術及びその評価技術を確立していく必要がある。本稿では,まず,従来用いられてきた感性情報である臨場感を取り上げ,質問紙調査から得られたデータに基づき,臨場感の本質とは何かについて議論を行う。次に,背景的・空間的な「場」の本物らしさに関係すると考えられる臨場感に対して,前景情報を中心とした本物らしさに関連すると考えられる感性印象である「迫真性」を取り上げ,両者の相違について論じ,今後の感性評価に対して,提案を行う。
2 0 0 0 OA インターネット上における名誉毀損について
- 著者
- 岡田 好史
- 出版者
- 専修大学法学会
- 雑誌
- 専修法学論集 (ISSN:03865800)
- 巻号頁・発行日
- vol.100, pp.143-156, 2007-07-24
2 0 0 0 OA 水温躍層面におよぼす風の影響
- 著者
- 和田 明
- 出版者
- 公益社団法人 土木学会
- 雑誌
- 海岸工学講演会講演集 (ISSN:04194918)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, pp.137-142, 1965-11-15 (Released:2010-06-04)
- 参考文献数
- 8
- 被引用文献数
- 2
- 著者
- 河田 博
- 出版者
- 福岡大学
- 雑誌
- 福岡大学医学紀要 (ISSN:03859347)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.4, pp.289-298, 2003-12
2 0 0 0 OA Java言語いま何が課題なのか:応用の新展開 -メタコンピューティングへの応用-
2 0 0 0 OA 序論 「濱田徳海コレクション」目録の整理と考察
- 著者
- 氣賀澤 保規
- 出版者
- 東洋文庫
- 雑誌
- 氣賀澤保規編『濱田徳海旧蔵敦煌文書コレクション目録』(東洋文庫、2020年)
- 巻号頁・発行日
- pp.i-vii, 2020-03-12
- 著者
- ポンサピタックサンティ ピヤ
- 出版者
- 京都産業大学
- 雑誌
- 京都産業大学論集. 社会科学系列 (ISSN:02879719)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, pp.3-19, 2018-03
本研究の目的は,現代タイ社会における若者の精霊信仰にメディアが及ぼす影響を明らかにすることである。筆者は,2016 年9 月に,タイの若者の精霊信仰に対する考えかたを調査するために,タイ・バンコクの大学生を対象にアンケート調査をおこなった。 本論文は,この調査の結果および2015 年の調査を元に,タイの若者の信仰と,それに対するメディアの影響に焦点をあてて考察する。本論文は,その調査の中で特に,マスメディアと精霊信仰の役割についての質問項目をとりあげ分析考察をめざすものである。また,2015 年の調査と比較し,その意識変化を探りたい。調査の結果,タイの若者の多くは,テレビドラマやテレビ番組,映画から精霊に関するイメージや情報を得ていることが明らかになった。そして,若者がイメージする男性精霊は特定のものに集中しているが,イメージされる女性精霊は多様であることがわかる。さらに,現代タイ社会において女性の精霊は男性の精霊より怖いイメージで,男性の精霊は女性の精霊よりも優しいイメージで捉えられている。なお,2015 年と翌年の調査結果を比較した結果,ほとんど違いは見られないが,特定の精霊はテレビなどのメディアに出演することによって,より一層イメージされやすくなる傾向にあることが明らかになった。このような研究結果により,タイの若者は,テレビや映画などのメディアに表象される精霊イメージの影響を受けていると考えられる。
2 0 0 0 OA ヒト上肢の特徴
2 0 0 0 OA 構造ベース創農薬による硝化抑制剤の開発~農薬開発に必要なイノベーション~
2 0 0 0 OA Overview of evaluation technologies for rehabilitation from viewpoints of service co-creation
- 著者
- MOCHIMARU Masaaki
- 出版者
- 脳機能とリハビリテーション研究会
- 雑誌
- Journal of Rehabilitation Neurosciences (ISSN:24342629)
- 巻号頁・発行日
- pp.200622, (Released:2020-06-24)
Rehabilitation is a co-creative medical service that strongly requires patient involvement. Encouraging patients to continue rehabilitation is an important role of medical services, and evaluation technology is also important from that perspective. The evaluation technology for rehabilitation was developed from the physical structure evaluation using medical images to the physical function evaluation using motion capture, ground reaction force and digital human models. Also, the idea that what should be restored is not only physical function but also daily-living function has been advocated, and standard description and evaluation of daily-living functioning have been promoted since the latter half of the 1990s. Furthermore, since 2000, research to evaluate functional recovery of the cranial nervous system, which controls motor function recovery, has made rapid progress in the field of neuro-rehabilitation. The rehabilitation evaluation has been integrated by the evaluation of the physical function, daily-living functioning, and the functional recovery of the cranial nervous system. In the future, these three functional evaluation technologies will be implemented in cooperation with advanced medical equipment that can be used in hospitals and wearable equipment and nursing robots that can be used in daily life. We believe that each person will be able to continue their daily rehabilitation with motivation while confirming to what extent the effects of rehabilitation are exerted on their cranial nerves, motor functions, and daily-living functions.
2 0 0 0 リヒター症候群
サマリー 慢性リンパ性白血病(chronic lymphocytic leukemia,CLL)は,低悪性度成熟B細胞腫瘍の一つである.CLLは,欧米では65歳以上の白血病の40%を占め,1年に10万人当たり3人の発症がみられるが,わが国では20~30分の1以下と稀である.CLL細胞の形態は,通常のリンパ球とは見分けがつかない.定義上は,大きさが赤血球の2倍以下の成熟した小型リンパ球で,細胞質に乏しく,核クロマチンが凝集し,核小体は見られない.CLLの約10%に経過の早いリンパ腫へと変化するものがあり,報告者の名前にちなんでリヒター症候群(Richter's syndrome,RS)と呼ばれる.一般に,びまん性大細胞型B細胞リンパ腫へと変化することが多いが,ホジキンリンパ腫(Hodgkin's lymphoma,HL)へと変化するものもある.RSの場合,それぞれの組織型に応じた治療が選択されるが,治療への反応が悪く通常1年以内に死亡する例が多い.化学療法での治療強度を上げても,寛解率の上昇にはつながらないとされる.治療後に部分寛解以上になったときに,造血幹細胞移植を行うことが最も長期生存が望めると報告されているが,わが国でのまとまった報告はない.
- 著者
- Kanae Yasumatsu Jun-ichi Nagao Ken-ichi Arita-Morioka Yuka Narita Sonoko Tasaki Keita Toyoda Shoko Ito Hirofumi Kido Yoshihiko Tanaka
- 出版者
- Japanese Association for Laboratory Animal Science
- 雑誌
- Experimental Animals (ISSN:13411357)
- 巻号頁・発行日
- vol.69, no.2, pp.250-260, 2020 (Released:2020-04-24)
- 参考文献数
- 33
- 被引用文献数
- 15
Maternal immune activation (MIA) by an infection is considered to be an important environmental factor of fetal brain development. Recent animal model on MIA induced by polyinosinic:polycytidylic acid, a mimic of viral infection, demonstrates that maternal IL-17A signaling is required for the development of autism spectrum disorder (ASD)-like behaviors of offspring. However, there is little information on bacterial infection. In this study, we aim to elucidate the influence of MIA induced by lipopolysaccharide (LPS) to mimic a bacterial infection on fetal brain development. We demonstrated that LPS-induced MIA promoted ASD-like behaviors in mouse offspring. We further found that LPS exposure induced acute phase immune response: elevation of serum IL-17A levels in MIA mothers, upregulation of Il17a mRNA expression and increase of IL-17A-producing γδ T cells in the uterus, and upregulation of Il17ra mRNA expression in the fetal brain. Blocking of IL-17A in LPS-induced MIA ameliorated ASD-like behaviors in offspring. Our data suggest that bacterial-induced maternal IL-17A pathway promotes ASD-like behaviors in offspring.
2 0 0 0 第13夜 臨床と研究の狭間で…—若いときの苦労が今の支え
- 著者
- 小田 裕
- 出版者
- メディカル・サイエンス・インターナショナル
- 巻号頁・発行日
- pp.77-81, 2020-04-10
学生時代の6年間,音楽・語学・スポーツに明け暮れて楽しく過ごし,気がつけば半年後に卒業を控えていた。臨床研修制度はまだなく「卒業すればすぐに入局」で,専門科目を決めるまでに時間的猶予はなかった。結果的に,「早く常勤のポストを得る」ことが最重要課題となった。そして「これから医者の仕事は一般化するのか,専門化するのか?」をふと考えた時,麻酔科を選ぶことに躊躇はなかった。医者としての第一歩は出身大学の病院でスタートした。また「取れるものはさっさと取ろう」ともくろんだ私は,卒業後すぐに大学院に入学した。専門医よりも「まずは学位」の時代であった。ここから局所麻酔薬との長い付き合いが始まった。大学での生活が長く,最近までトップとして麻酔科を運営することはなかったため,「これ」といった体験には乏しいが,心の中,そして日々の生活の中には常に臨床と学究的活動が共存した。卒業から40年近く経つ現在も変化はなく,後者が私の考え方や行動に重要な影響を与えていることに今更ながら驚いている。
2 0 0 0 OA セラミック外論 (1)
- 著者
- 素木 洋一
- 出版者
- 公益社団法人 日本セラミックス協会
- 雑誌
- 窯業協會誌 (ISSN:00090255)
- 巻号頁・発行日
- vol.68, no.773, pp.C160-C165, 1960-05-01 (Released:2010-04-30)
2 0 0 0 OA 立身出世主義の論理と機能
- 著者
- 竹内 洋
- 出版者
- 日本教育社会学会
- 雑誌
- 教育社会学研究 (ISSN:03873145)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, pp.119-129,en217, 1976-09-30 (Released:2011-03-18)
The notion of “Risshin-Shusse” and its functions can be briefly summarized as follows:(1) To rise in the world (“Risshin-Shusse”) or not was considered identical with winning or being defeated in life. This compulsive notion was to force “Shusse”-minded people to reject the usual institutional means and those who failed into despair.(2) There was, however, another kind of “Risshin-Shusse” notion, which contributed greatly to preventing people from such deviation and from despair. It was, what could be called, a double-image notion of “Risshin-Shusse”. One image was that the more secular value a man had, the more moral value he had. The other image, which was quite to the contrary in the content, was that the more secular value a man had, the less moral value he had.(3) The third notion of “Risshin-Shusse” was that of small upward mobility in non-elite, that was also regarded as “Shusse”. While the opportunities to try to rise radically in the world became less, this notion kept the fervor of “Risshin-Shusse”.(4) The fourth notion of “Risshin-Shusse” was one that was considered “Komyo”(acquiring fame). This notion had relevance not only to status-orientation, but also to achievement-orientation. This particular notion is thought to have worked as innovation energy toward the Japanese modernization.
2 0 0 0 OA 高橋源一郎『官能小説家』を読む : 〈名前〉をめぐる闘争(読む)
- 著者
- 菅 聡子
- 出版者
- 日本文学協会
- 雑誌
- 日本文学 (ISSN:03869903)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, no.12, pp.62-66, 2003-12-10 (Released:2017-08-01)
2 0 0 0 IR 琉球諸島出土「高麗系瓦」の製作技法と年代――グスク瓦の基礎的研究――
- 著者
- 石井 龍太
- 出版者
- 法政大学沖縄文化研究所
- 雑誌
- 沖縄文化研究 (ISSN:13494015)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, pp.141-187, 2014-03-31
- 著者
- 中川 洋一郎
- 出版者
- 中央大学経済学研究会
- 雑誌
- 經濟學論纂 = The journal of economics (ISSN:04534778)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.5, pp.257-284, 2017-03
2 0 0 0 何もない私たち:小熊英二『1968』をめぐって
- 著者
- 新倉 貴仁
- 出版者
- ソシオロゴス編集委員会
- 雑誌
- 書評ソシオロゴス
- 巻号頁・発行日
- vol.6, no.2, pp.1-13, 2010