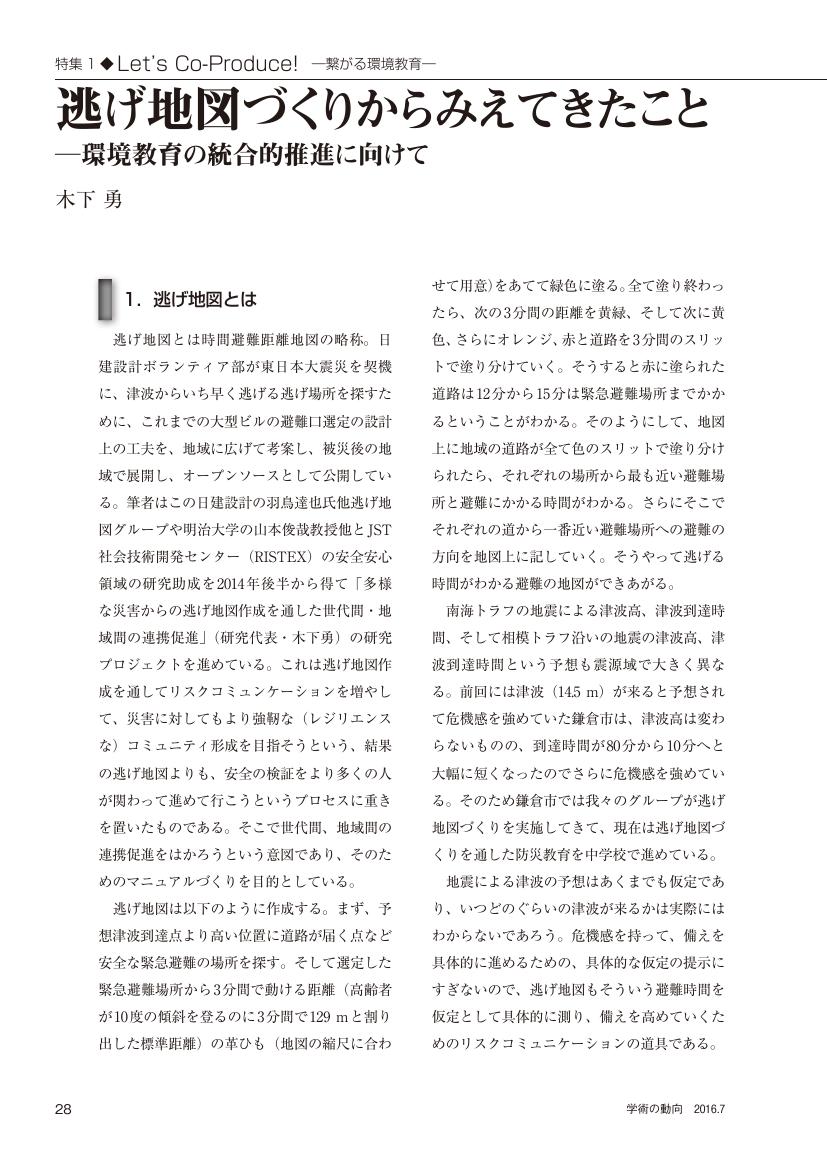2 0 0 0 OA 地方の幹線都市間バスの変遷にみる諸問題の考察
- 著者
- 大島 登志彦
- 出版者
- Japan Society of Civil Engineers
- 雑誌
- 土木史研究論文集 (ISSN:13495712)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, pp.35-44, 2007-06-15 (Released:2010-06-04)
- 参考文献数
- 7
The local bus-service on the trunk line connected two cities (omnibuses between adjacent or middlefar cities with the frequent-service) which were gained an important source of income for local bus companies were reduced more than in rural-area since 1970's. Through this era and such process, the writer analyses the case study of some Bus-routes from Takasaki or Maebashi city in Gunma prefecture about the vicissitude of relation between the bus-operation and the railway (comparison with the fare and the convenience), the influence involves the rationalization of the operation and the problem of management and policy in the local bus-business, on bus-routes around Takasaki and Maebashi cities in Gunma-prefecture.
2 0 0 0 シンギュラリティと人類の生存に関する総合的研究
本研究は、人類よりも知的な人工システムが技術的に可能になる日であるとされるシンギュラリティを巡り、その技術予測としての妥当性、そこで用いられる「人類よりも知的」の意味を明らかにし、その基礎作業の上で、なんらかの意味でのシンギュラリティが起こりうるという仮定にもとづき、予防的にシンギュラリティに人類はどのように対処すべきかを検討し、提言することを目指す。平成29年度は、シンギュラリティの「哲学的問題」として(1)知能爆発の可能性(必然性?)を論証する回帰的議論は果たして妥当か。(2)知性・知能とは何か。そもそも機械はどのような心的能力をもちうるか。(3)知能爆発の結果、倫理や価値(真・善・美)はどうなるのか。(4)シンギュラリティ後の世界において、われわれ人間はどんな役割を果たせるのかという問題群を取り出した。また、これまでに「シンギュラリティ」について書かれた言説について包括的なサーベイを行い、技術予測、シンギュラリティ概念、知性の概念、コンピュータ観、人間観等にかかわる基礎的概念について、著者によって大きく異なることを見出し、それを整理し、「シンギュラリティ」についてどのように論じるべきかというメタ的・方法論的なことがらについて結論を得た。それは、研究代表者により『人工知能学大事典』の「シンギュラリティ」の項目執筆というかたちで発表された。その他、シンギュラリティについて考察するのに関わりをもつ副次的概念や問題(とりわけ機械が犯した失敗についての責任の所在、機械は責任主体になりうるかという問題)について、研究成果を得て、さまざまな媒体で発表した。
- 著者
- 吉田 賢彦 初田 隆 寺元 幸仁
- 出版者
- 美術科教育学会
- 雑誌
- 美術教育学:美術科教育学会誌 (ISSN:0917771X)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, pp.445-459, 2015-03-20 (Released:2017-06-12)
これまでの児童画コンクールの是非をめぐる論議においては,子どもが入選作品をどのように捉えているのかといった,子どもの視点にたった考察が欠けているのではないかと思われる。そこで本稿では,コンクール入選作品を刺激対象として,これらを子どもと教師がどのように評価するのか,また,コンクールの入選作品であるという事実認識が作品の価値判断にどういった影響を及ぼすのかを調査・考察した。結果,子どもと教師の作品評価の枠組みや,標準的な作品イメージを基にコンクール作品の評価を行っていること,子どもの評価枠組みは教師の評価に影響を受けていることなどを示すことができた。
- 著者
- 米倉 律
- 出版者
- NHK放送文化研究所
- 雑誌
- 放送研究と調査 (ISSN:02880008)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, no.8, pp.62-75, 2012-08
2 0 0 0 OA 幼児期におけるコオーディネーション研究の理論的基礎
- 著者
- 加納 裕久 Hirohisa KANO
- 雑誌
- 人間発達学研究 = Bulletin of The Graduate School of Human Development Aichi Prefectural University (ISSN:18848907)
- 巻号頁・発行日
- no.7, pp.51-64, 2016-03-01
- 著者
- 梶原 洋一
- 出版者
- 史学会 ; 1889-
- 雑誌
- 史学雑誌 (ISSN:00182478)
- 巻号頁・発行日
- vol.128, no.4, pp.432-456, 2019-04
2 0 0 0 OA 中学校におけるいじめ抑止を目的とした心理教育的プログラムの開発とその効果の検討
- 著者
- 中村 玲子 越川 房子
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育心理学会
- 雑誌
- 教育心理学研究 (ISSN:00215015)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, no.2, pp.129-142, 2014 (Released:2015-03-27)
- 参考文献数
- 36
- 被引用文献数
- 5 3
いじめはその深刻さが指摘されており, 学校現場での対応が求められている問題である。いじめの減少困難や助長の要因として傍観者が挙げられており, 傍観者層の多寡は, 被害者の多寡と最も強い有意な相関を示すことが見出されている(森田, 1990)。本研究では中学生を対象としたいじめの抑止を目的とする心理教育的プログラムを開発し, その効果の検討を行った。プログラムは, いかなるいじめも容認されないとする心理教育と, いじめへの介入スキルの学習から構成された。プログラムの所要時間は授業1回分であり, 対象校生徒の実情に合った内容を用いての, ソーシャル・スキルス・トレーニングの技法に基づくロール・プレイングを含むものであった。事前・事後分析の結果, 本研究で開発されたいじめ抑止プログラムは, いじめ停止行動に対する自己効力感といじめ否定規範の向上, いじめ加害傾向の減少に一定の効果をもつことが示された。また, いじめの抑止のためには, いじめ否定規範の高い生徒にはいじめに介入するためのスキルの学習が, いじめ否定規範の低い生徒にはスキルの学習と同時にいじめ否定規範を高める指導・支援を行うことが有効である可能性が示された。
2 0 0 0 OA 逃げ地図づくりからみえてきたこと
- 著者
- 木下 勇
- 出版者
- 公益財団法人 日本学術協力財団
- 雑誌
- 学術の動向 (ISSN:13423363)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.7, pp.7_28-7_34, 2016-07-01 (Released:2016-11-04)
- 参考文献数
- 6
2 0 0 0 OA 怪談話の「盛り上がり」を加味したVRコンテンツの自動生成システム~文章導仮想怪談~
- 著者
- 髙木 亜蘭 小林 龍成 長谷川 稜馬 谷口 航平 濱川 礼
- 雑誌
- エンタテインメントコンピューティングシンポジウム2019論文集
- 巻号頁・発行日
- vol.2019, pp.40-45, 2019-09-13
本論文では、ユーザが選択したテキスト形式の怪談文章の盛り上がり箇所を自動判別することで、内容に関連した怪奇現象の「演出」を行い、抑揚を付加した「声」で語るVRコンテンツの自動生成を行うシステム「文章導仮想怪談」を提案する。怪談は古くから存在し、現代でも楽しまれている文化の一つである。その楽しみ方の一つとしてVR怪談が存在している。しかし、VR怪談は対応している怪談の数が少ない。そこで我々は、ユーザがインターネット上に数多く存在する怪談文章を用いることで、多くの怪談文章に対応できる応用性のあるシステムを開発した。
2 0 0 0 農家ライターがリポート 農業ワールド2016
- 著者
- 橋本 哲弥
- 出版者
- 家の光協会
- 雑誌
- 地上 = Good earth (ISSN:09137815)
- 巻号頁・発行日
- vol.71, no.1, pp.58-63, 2017-01
- 著者
- 古賀 一男
- 出版者
- 日本教育心理学会
- 雑誌
- 日本教育心理学会総会発表論文集
- 巻号頁・発行日
- no.35, 1993-10-08
本研究課題では,1歳未満の乳幼児の眼球運動を正確かつ定量的に記録するための新しい方法を開発すると共に,その方法を用いて乳幼児の眼球運動から眼科的あるいは認知発達的な見地から発達の不具合を早期に検出するという極めて限定した目的で研究が進められている.本研究課題では,言語的コミュニケーションが不十分な場合でも被験者の眼球運動を定量的に計測する手法を確立することと,その応用例を示すことを採取的な目標としている.特に萌芽的研究の限られた期間内に上記の目標のみをアクション・アイテムとして設定し確実に方法を確立することを目指す.初年度では,赤外光による角膜反射光法をとるため薄暗い中で撮影が行えるよう、現有システムに、リモートコントロール可能な赤外線カメラと、複数カメラ間の同期をとるための装置を追加した.さらにXY-tracker(浜松ホトニクス:フレーム内の最明点を検出し、その座標値をXY軸同時にデジタル出力できる)を用い、XY-trackerで追った眼球運動と頭部運動の軌跡を解析することで眼球の移動量や方向などを定量的に測定するシステムを構築した。このシステムを用いて引き続きデータの取得を継続し,また取得されたデータの解析を行い.新規に考案されたアルゴリズムを用いて,すでに取得された乳幼児の眼球位置の較正を試みた.
2 0 0 0 IR コーヒーとドイツ帝国 : 国境を越えた飲み物 (シリーズ特集 歴史学の「国境」(7))
- 著者
- 南 直人 Minami Naoto
- 出版者
- 大阪大学西洋史学会
- 雑誌
- パブリック・ヒストリー (ISSN:1348852X)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, pp.1-16, 2014
シリーズ特集 歴史学の「国境」7
2 0 0 0 真相を追え
- 著者
- ブレット・ハリデイ 著 福島正実 訳 小林泰彦 絵
- 出版者
- 盛光社
- 巻号頁・発行日
- 1966
- 著者
- 得丸 公明
- 雑誌
- 研究報告音声言語情報処理(SLP)
- 巻号頁・発行日
- vol.2011-SLP-86, no.16, pp.1-8, 2011-05-09
今日に至るまで,文法とは何か,文法のメカニズムはどうなっているのかということについて,十分に検討が行なわれたり,議論されたり,解明されることはなかった.デカルト派言語学を自認するチョムスキーが提起した難題「ヒトは状況に応じて新しい文を作ることができ,それをたった一度発話するだけで,聞き手がただちにそれを理解できるのはなぜか」を,生成文法論者を含めてまだ誰も解明できていない(1).チョムスキー自身は「この問題が人間の知的な能力の範囲内にはない」,「神の介在なしにはありえない」と述べている(2).だが,未解明の理由のひとつは,構造主義の「形態素」・「遺伝子型/表現型」概念と似て非なる「語形成素」・「深層構造/表層構造」という概念を用いるためではないか.また言語のメカニズムは社会科学でも自然科学でもなく,符号理論として取り扱うべきではないか.筆者は,ヒトの言語は脳内の自律的な神経細胞ネットワーク上で作動するデジタル通信システムであり,文法は情報源符号化と通信路符号化という二つのデジタル符号化メカニズムのシナジー(相乗)効果によって生み出された一連の機能を指し示す音響符号語であると考える.デカルトの結論に反して動物も論理装置や概念をもっており,ヒトのヒト以外の動物に対する質的相違は二重符号化文法に求められる.