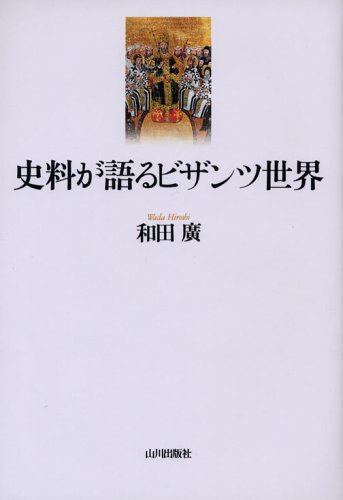1 0 0 0 RNNのアクティブフィルタへの適用
- 著者
- 和田 義毅 山田 浩太郎 ペチャラニン ナレート 田口 亮 曽禰 元隆
- 出版者
- 一般社団法人電子情報通信学会
- 雑誌
- 電子情報通信学会総合大会講演論文集
- 巻号頁・発行日
- vol.1995, no.2, 1995-03-27
近年のパワーエレクトロニクス機器の普及に伴い増加している、家電、OA機器、産業機械から高調波電流により、機器の焼損、振動、騒音などの障害が生じている。この対策として、アクティブフィルタ(以下AF)により高調波電流を打ち消す方法が注目されている。AFにおいて、負荷電流波形から、高調波成分量を解析する手法としてリカレントニューラルネットワーク(以下RNN)を適用する。波形変換に優れた能力を持ち波形の解析機構を学習によって自動的に獲得する能力を持っているRNNを用いることで、高調波解析能力について研究する。
1 0 0 0 史料が語るビザンツ世界
1 0 0 0 2205.尼崎沖フェニックスにおける焼却灰の力学的特性
- 著者
- 岩谷 文方 三宅 達夫 和田 眞郷 丸山 敦司
- 出版者
- 公益社団法人地盤工学会
- 雑誌
- 土と基礎 (ISSN:00413798)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, no.6, pp.5-10, 1992-06-25
- 被引用文献数
- 10
1 0 0 0 OA 東寺講堂立体曼荼羅の思想的背景
- 著者
- 鍵和田 聖子
- 出版者
- 龍谷大学
- 雑誌
- 龍谷大学大学院文学研究科紀要 (ISSN:13433695)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, pp.140-156, 2006
1 0 0 0 わが国の慢性透析療法の現況(2000年12月31日現在)
1 0 0 0 OA 微生物の浸透圧調節
- 著者
- 大和田 琢二 匂坂 勝之助
- 出版者
- 公益社団法人 日本農芸化学会
- 雑誌
- 化学と生物 (ISSN:0453073X)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.6, pp.360-368, 1990-06-25 (Released:2009-05-25)
- 参考文献数
- 12
- 被引用文献数
- 2
- 著者
- 和田 攻
- 出版者
- 杏林書院
- 雑誌
- 保健の科学 (ISSN:00183342)
- 巻号頁・発行日
- vol.44, no.8, pp.572-578, 2002-08
1 0 0 0 地域研究活動 能登文化財保護連絡協議会の活動
- 著者
- 和田 学
- 出版者
- 地方史研究協議会
- 雑誌
- 地方史研究 (ISSN:05777542)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, no.6, pp.77-79, 2012-12
1 0 0 0 OA 大雪山の高山蛾類の採集記録とノート
1 0 0 0 OA 1.先端巨大症
- 著者
- 生山 祥一郎 名和田 新
- 出版者
- 一般社団法人 日本内科学会
- 雑誌
- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)
- 巻号頁・発行日
- vol.83, no.12, pp.2058-2063, 1994-12-10 (Released:2008-06-12)
- 参考文献数
- 5
先端巨大症は成長ホルモン(GH)の過剰分泌が骨端線閉鎖後に生じた場合に起こる病態で,ほとんどの場合下垂体のGH産生腺腫が原因である. GHおよびソマトメジンCの分泌増加に基づく骨・軟骨・軟部組織の肥大により特異な症候を呈し,血管障害や悪性腫瘍の合併が予後を左右する.診断はGHの過剰分泌と腫瘍の局在を証明することである.経蝶形骨洞手術による腺腫摘出が治療の第一選択であるが,薬物療法や放射線療法を行うこともある.
1 0 0 0 OA 八代海における植物プランクトンの増殖に与える水温,塩分および光強度の影響
- 著者
- 紫加田 知幸 櫻田 清成 城本 祐助 生地 暢 吉田 誠 大和田 紘一
- 出版者
- 公益社団法人 日本水産学会
- 雑誌
- 日本水産学会誌 (ISSN:00215392)
- 巻号頁・発行日
- vol.76, no.1, pp.34-45, 2010 (Released:2010-05-13)
- 参考文献数
- 42
- 被引用文献数
- 20 29
室内において,八代海における主要な植物プランクトンの異なる水温,塩分および光強度条件下における増殖特性を調べ,現場において各種の動態とそれらの環境条件との関係を調査した。水温および塩分に対する増殖応答特性は種によって異なっていたが,増殖のために要求する光強度はいずれの種でも大差なく,ほとんどの供試生物の増殖速度は 80 μmol m-2 s-1 で飽和した。現場における季節的な種変遷パターンは水温および塩分の変化と,短期的な動態は水中光の強度の変化と同調していた。
1 0 0 0 11. Webを用いたインタラクティブテキストの開発
- 著者
- 香川 豊宏 西明 仁 瀬々 良介 三輪 邦弘 田代 陽美子 小川 和久 和田 忠子 湯浅 賢治 坂元 英知 市原 隆洋 原田 理恵 太田 隆介
- 出版者
- 福岡歯科大学学会
- 雑誌
- 福岡歯科大学学会雑誌 (ISSN:03850064)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.4, 2001-12-30
近年ネットワーク上でのWebテキストが色々検討されてきており,当大学においても教育用データベースのサーバーが設置されて数年が経過している。しかしその内容はHTMLによるテキストやJPEG画像のみの教科書的なサイト運営に留まっており,インターネットの持つ双方向メディアとしての能力が十分に発揮されていないのが現状である。しかし,現在利用可能な最新のインターネット技術を用いれば,従来の印刷物をこえる双方向メディアとしてのWebテキストになることは十分に期待できる。そこで今回はフリーソフトであるGifBuilder1.0を用いてgifアニメーションのWebテキストへの利用を検討した。今回は二等分法についてのGifアニメーションを用いたコンテンツ作成を試みた。その結果Gifアニメーションを作成する場合にはフレームレートを1/100S〜100/100Sまで自由に選べるが,1/30S〜1/50Sに設定するのがアニメーションのスピードとして適切と思われた。また,画像の転送スピードを考慮して一つのアニメーションのファイル容量は100kbyte前後が望ましいと思われる。100kbyteであれば,あくまでも計算上ではあるがISDN128kbpsのネットワークで5秒以内の転送時間でアニメーションを読み込むことが可能である。またHTMLの一つであるイメージマップを用いることによりX線画像の解剖についての学習も行いやすいと思われた。今後はR-ASHやMPEGによる動画などをコンテンツに加え,学生が自己学習しやすいようなWebテキストを開発していきたい。
1 0 0 0 OA 栄華物語詳解
- 著者
- 和田英松, 佐藤球 共著
- 出版者
- 明治書院
- 巻号頁・発行日
- vol.巻1, 1907
1 0 0 0 重合メッシュ法を用いた疲労き裂進展シミュレーション
- 著者
- 菊池 正紀 和田 義孝 高橋 真史
- 出版者
- 一般社団法人日本機械学会
- 雑誌
- 日本機械学会論文集. A編 = Transactions of the Japan Society of Mechanical Engineers. A (ISSN:03875008)
- 巻号頁・発行日
- vol.74, no.742, pp.812-818, 2008-06-25
- 参考文献数
- 15
- 被引用文献数
- 10
Fatigue crack growth under mixed mode loading conditions is simulated using Superimposed-FEM (S-FEM). By using S-FEM technique, only local mesh should be re-meshed and it becomes easy to simulate crack growth. By combining with re-meshing technique, local mesh is re-meshed automatically, and curved crack path is modeled easily. At first, slant crack problem is solved. It is shown that results agree with conventional solutions, and verified the availability of this technique.Then two-crack problems are solved in several cases by changing each crack location. Stress intensity factors are evaluated and interaction effect between two cracks is discussed. Results are compared with crack coalescence criteria, and it is verified that these criteria are reasonable ones.
1 0 0 0 鳥取県岩美町の海岸に漂着したルリガイの殻長組成と繁殖
- 著者
- 岡野 元哉 和田 年史
- 出版者
- 日本貝類学会
- 雑誌
- Venus (Journal of the Malacological Society of Japan) (ISSN:13482955)
- 巻号頁・発行日
- vol.70, no.1, pp.58-62, 2012
We investigated size structure and reproduction of violet shell <i>Janthina prolongata</i> stranded on the coast of Iwami-cho in eastern part of Tottori Prefecture, southwestern Sea of Japan, on 27 September, 2010. Shell length (SL) exhibited a bimodal size distribution with a range of 6.08–40.36 mm. Our results also indicated that individuals of more than 27.4 mm SL laid egg capsules under their bubble raft. Moreover, there was a significant positive correlation between the length of egg capsules and SL. Larger individuals had shrunken and differently colored egg capsules on the forefront of bubble raft, suggesting that <i>J. prolongata</i> might lay egg capsules intermittently.
1 0 0 0 鳥取県岩美町の海岸に漂着したルリガイの殻長組成と繁殖
- 著者
- 岡野 元哉 和田 年史
- 出版者
- 日本貝類学会
- 雑誌
- Venus (Journal of the Malacological Society of Japan) (ISSN:13482955)
- 巻号頁・発行日
- vol.70, no.1, pp.58-62, 2012
We investigated size structure and reproduction of violet shell Janthina prolongata stranded on the coast of Iwami-cho in eastern part of Tottori Prefecture, southwestern Sea of Japan, on 27 September, 2010. Shell length (SL) exhibited a bimodal size distribution with a range of 6.08–40.36 mm. Our results also indicated that individuals of more than 27.4 mm SL laid egg capsules under their bubble raft. Moreover, there was a significant positive correlation between the length of egg capsules and SL. Larger individuals had shrunken and differently colored egg capsules on the forefront of bubble raft, suggesting that J. prolongata might lay egg capsules intermittently.
- 著者
- 大和田 道雄 田中 セツ子
- 出版者
- 愛知教育大学
- 雑誌
- 愛知教育大学教科教育センター研究報告 (ISSN:02881853)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, pp.131-139, 1986-03-15
- 著者
- 石上 久 竹谷 小百合 大和田 彩
- 出版者
- 日本看護協会出版会
- 雑誌
- 日本看護学会論文集. 看護管理 (ISSN:13478184)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, pp.245-248, 2012
1 0 0 0 ヒト核DNAにおけるミトコンドリアDNA様配列の解析
- 著者
- 岩井 浩一 大谷 学 和田野 安良 岩村 幸雄
- 出版者
- 茨城県立医療大学
- 雑誌
- 茨城県立医療大学紀要 (ISSN:13420038)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, pp.33-44, 2002-03
我々は, 健康な成人を対象に, 持久的運動負荷を加えることによって, ミトコンドリアDNA(mtDNA)に4977-bpの欠失(common deletion)が発現し, 数日後にその欠失が消失することを見いだした。その一連の実験の際, 2名の被験者において, common deletionの欠失配列とは異なる長さの配列が検出された。そこで, 本研究では, この塩基配列の構造について詳細な分析を試みた。まず, シークエンス分析を行い. mtDNA様配列の塩基配列を決定したところ, 2名の被験者においてこの塩基配列は全く同一であった。さらに詳細に検討を行ったところ, この塩基配列はmtDNAの塩基配列とかなり一致していることが明らかになった(類似度:88%)。また, これらの塩基配列をもとにアミノ酸配列を予測し, 読み枠(ORF)解析によりその詳細な構造を探った。これらの結果から, このmtDNA様配列は, 生物の進化の過程でmtDNAの遺伝子が核DNAに挿入されたもので, その変異が現在まで引き続いて核DNA中に組み込まれている可能性が示唆された。
1 0 0 0 OA 飛騨地方北部特に跡津川断層付近の地震活動と発震機構
- 著者
- 和田 博夫 三雲 健 小泉 誠
- 出版者
- 公益社団法人 日本地震学会
- 雑誌
- 地震 第2輯 (ISSN:00371114)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.3, pp.281-296, 1979-09-25 (Released:2010-03-11)
- 参考文献数
- 28
- 被引用文献数
- 2 3
Seismicity in the northern Hida region, Japan, has been routinely observed since May, 1977 at telemeter-network stations of the Kamitakara Geophysical Observatory, and about 1500 local shocks with magnitudes greater than 0.5 have been located. (1) The observation reveals high seismicity along the Atotsugawa fault, along the northern Japan-Alps, south of Mt. Norikura and Mt. Ontake, and near Hida-Osaka, with focal depths shallower than 20km. (2) Seismic activity along the Atotsugawa fault is high at the eastern and western portions, with an intermittent zone of low activity, extending over 70km. Epicenters are deviated about 2-3km north of the fault trace, and this deviation together with focal depth distribution suggests a slightly northwestwardd dipping fault plane. All these shocks are confined above 13km, suggesting either that the fault plane extends down to this depth, or that minor brittle fractures do not take place under the depth due to some flow propertities of rock materials there. (3) Nine shocks along the fault show focal mechanisms consistent with right-lateral strike-slip evidenced by geological and geomorphological surveys (MATSUDA, 1966). (4) Heavy damage along the fault region at the time of the 1858 Hida earthquake (M=6.9) appears to indicate that this large earthquake was caused by faulting motion of the Atotsugawa fault. Most of the present seismic activity along the fault might be associated with some readjustments of residual stresses around there.