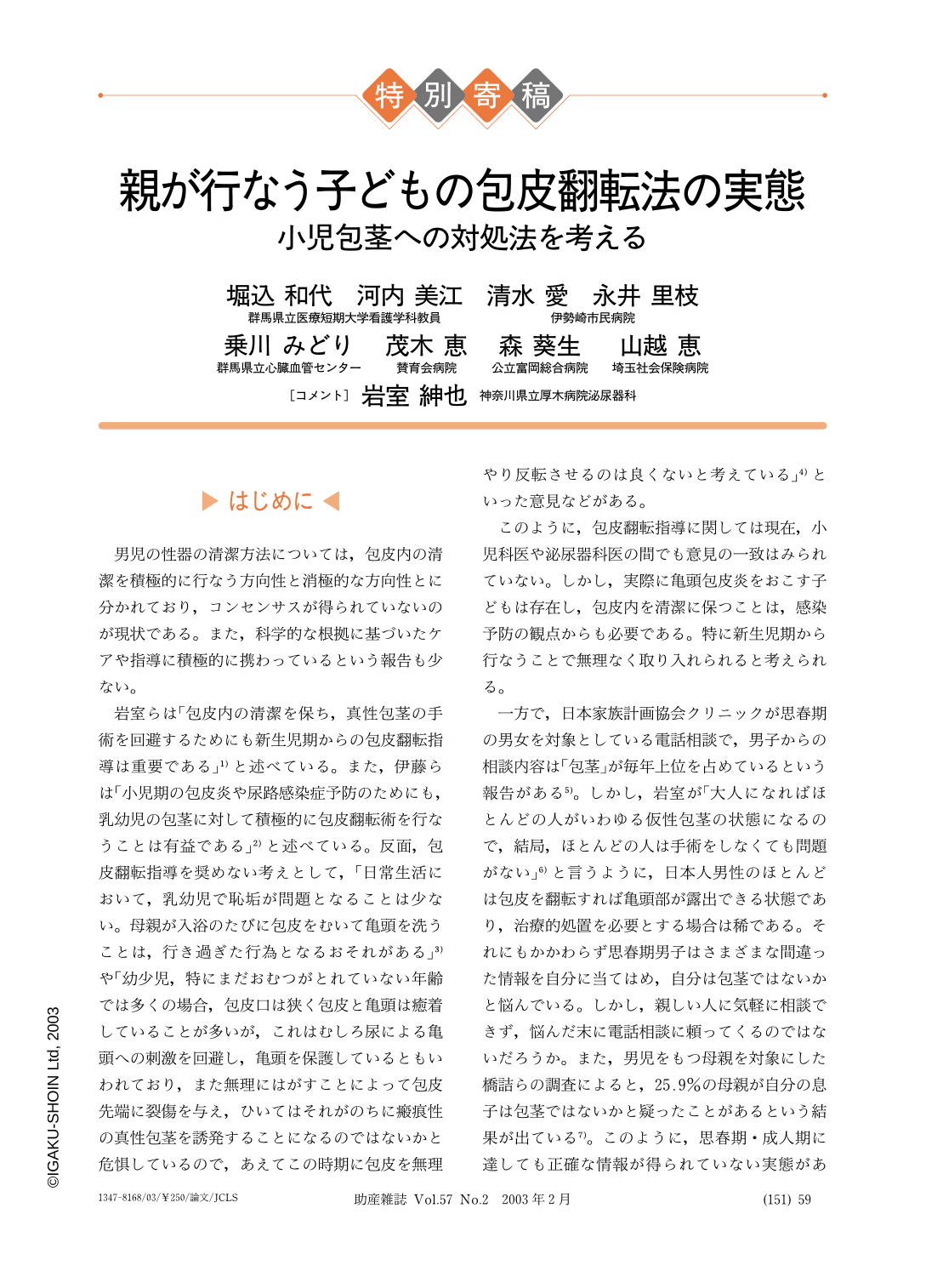53 0 0 0 親が行なう子どもの包皮翻転法の実態―小児包茎への対処法を考える
- 著者
- 堀込 和代 河内 美江 清水 愛 永井 里枝 乗川 みどり 茂木 恵 森 葵生 山越 恵 岩室 紳也
- 出版者
- 医学書院
- 雑誌
- 助産雑誌 (ISSN:13478168)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.2, pp.151-159, 2003-02-01
はじめに 男児の性器の清潔方法については,包皮内の清潔を積極的に行なう方向性と消極的な方向性とに分かれており,コンセンサスが得られていないのが現状である。また,科学的な根拠に基づいたケアや指導に積極的に携わっているという報告も少ない。 岩室らは「包皮内の清潔を保ち,真性包茎の手術を回避するためにも新生児期からの包皮翻転指導は重要である」1)と述べている。また,伊藤らは「小児期の包皮炎や尿路感染症予防のためにも,乳幼児の包茎に対して積極的に包皮翻転術を行なうことは有益である」2)と述べている。反面,包皮翻転指導を奨めない考えとして,「日常生活において,乳幼児で恥垢が問題となることは少ない。母親が入浴のたびに包皮をむいて亀頭を洗うことは,行き過ぎた行為となるおそれがある」3)や「幼少児,特にまだおむつがとれていない年齢では多くの場合,包皮口は狭く包皮と亀頭は癒着していることが多いが,これはむしろ尿による亀頭への刺激を回避し,亀頭を保護しているともいわれており,また無理にはがすことによって包皮先端に裂傷を与え,ひいてはそれがのちに瘢痕性の真性包茎を誘発することになるのではないかと危惧しているので,あえてこの時期に包皮を無理やり反転させるのは良くないと考えている」4)といった意見などがある。 このように,包皮翻転指導に関しては現在,小児科医や泌尿器科医の間でも意見の一致はみられていない。しかし,実際に亀頭包皮炎をおこす子どもは存在し,包皮内を清潔に保つことは,感染予防の観点からも必要である。特に新生児期から行なうことで無理なく取り入れられると考えられる。 一方で,日本家族計画協会クリニックが思春期の男女を対象としている電話相談で,男子からの相談内容は「包茎」が毎年上位を占めているという報告がある5)。しかし,岩室が「大人になればほとんどの人がいわゆる仮性包茎の状態になるので,結局,ほとんどの人は手術をしなくても問題がない」6)と言うように,日本人男性のほとんどは包皮を翻転すれば亀頭部が露出できる状態であり,治療的処置を必要とする場合は稀である。それにもかかわらず思春期男子はさまざまな間違った情報を自分に当てはめ,自分は包茎ではないかと悩んでいる。しかし,親しい人に気軽に相談できず,悩んだ末に電話相談に頼ってくるのではないだろうか。また,男児をもつ母親を対象にした橋詰らの調査によると,25.9%の母親が自分の息子は包茎ではないかと疑ったことがあるという結果が出ている7)。このように,思春期・成人期に達しても正確な情報が得られていない実態がある。 男子が思春期になってから,誤った情報に左右されず,身近な人間関係の中で日常的に,自分の性器に関する正しい知識や対処の仕方を獲得するには,出生時から排泄や清潔のケアを引き受ける母親のかかわり方が重要であると考えられる。
52 0 0 0 OA オオクロバエ体内におけるH5N1インフルエンザウイルスの生存に関する研究
- 著者
- 澤邉 京子 佐々木 年則 星野 啓太 伊澤 晴彦 倉橋 弘 主藤 千枝子 棚林 清 堀田 昭豊 山田 章雄 小林 睦生
- 出版者
- 日本衛生動物学会
- 雑誌
- 日本衛生動物学会全国大会要旨抄録集 第58回日本衛生動物学会大会
- 巻号頁・発行日
- pp.18, 2006 (Released:2006-06-07)
2004年京都府丹波町での鳥インフルエンザ発生時に採集されたクロバエ類の消化管から高率にH5N1亜型高病原性鳥インフルエンザウイルスを検出、分離したことを昨年の本大会で報告した。その後、人為的にウイルスをクロバエに摂食させ、ハエ体内でどの程度の期間ウイルスが維持されるかを検討したので報告する。オオクロバエの羽化後14日の雌成虫に、H5N1亜型低病原性インフルエンザウイルス(A/duck/Hyogo/35/01)培養液を脱脂綿に滲み込ませ3時間摂食させた。その後、餌用寒天培地の入った三角フラスコ内に個別にクロバエを入れ一定期間維持した。経時的にクロバエを冷凍殺虫し、表面をMEM培養液で洗浄後、消化管(そ嚢、腸管)を摘出した。フラスコ内壁に付着した排泄物ならびに吐出物をMEM培養液で洗い回収し、虫体洗浄液と混和した。ウイルス液を滲み込ませた脱脂綿も同様に一定期間保管した。1 そ嚢、2 腸管、3 フラスコ内壁・虫体洗浄液、4 脱脂綿のそれぞれをMEM培養液で破砕、あるいは攪拌してウイルス乳剤を調整し、ウイルス遺伝子検出とウイルス分離に供した。ウイルス遺伝子はRT-PCRおよびnested PCRで確認し、感染性ウイルスは発育鶏卵接種後HA試験およびFluA+B(BD社)で分離の成否を判定した。同時にMDCK細胞培養を用いてウイルス力価を測定した。その結果、オオクロバエ摂食後14日までのほとんどの検体からウイルス遺伝子は検出され、感染性ウイルスはオオクロバエの体内で少なくとも24時間生存することが示唆された。オオクロバエは1日に数kmは容易に移動することから、その距離内にある近隣の鶏舎などにウイルス活性が保持された状態のウイルスがオオクロバエによって運ばれる可能性は高く、本ウイルスの伝播、拡散にオオクロバエなどのハエ類が貢献することは十分に考えられる。
52 0 0 0 OA 伊達政宗の絶縁状
- 著者
- 堀越 祐一
- 出版者
- 学校法人國學院大學 國學院大學北海道短期大学部
- 雑誌
- 滝川国文 (ISSN:24336378)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, pp.25-40, 2021 (Released:2021-07-16)
- 参考文献数
- 16
- 著者
- 堀田 昌寛 遊佐 剛
- 出版者
- 一般社団法人日本物理学会
- 雑誌
- 日本物理學會誌 (ISSN:00290181)
- 巻号頁・発行日
- vol.69, no.9, pp.613-622, 2014-09-05
現在広範なテーマを巻き込みながら,量子情報と量子物理が深いレベルから融合する量子情報物理学という分野が生まれ成長しつつある.なぜ様々な量子物理学に量子情報理論が現れてくるのだろうか.それには量子状態が本質的に認識論的情報概念であるということが深く関わっていると思われる.ボーアを源流とする認識論的な現代的コペンハーゲン解釈は量子情報分野を中心に定着してきた.この量子論解釈に基づいた量子情報物理学の視点からは存在や無という概念も認識論的であり,測定や観測者に対する強い依存性がある.本稿ではこの「存在と無」の問題にも新しい視点を与える量子エネルギーテレポーテーション(Quantum Energy Teleportation;QET)を解説しつつ,それが描き出す量子情報物理学的世界観を紹介していく.QETとは,多体系の基底状態の量子縺れを資源としながら,操作論的な意味のエネルギー転送を局所的操作と古典通信(Local Operations and Classical Communication;LOCC)だけで達成する量子プロトコルである.量子的に縺れた多体系の基底状態においてある部分系の零点振動を測定すると,一般に測定後状態の系は必ず励起エネルギーを持つ.これは基底状態の受動性(passivity)という性質からの帰結である.このため情報を測定で得るアリスには,必ず測定エネルギーの消費という代償を伴う.またアリスの量子系は量子縺れを通じてボブの量子系の情報も持っている.従ってアリスは,ボブの系のエネルギー密度の量子揺らぎの情報も同時に得る.これによって起こるボブの量子系の部分的な波動関数の収縮により,測定値に応じてアリスにとってはボブの量子系に抽出可能なエネルギーがまるで瞬間移動(テレポート,teleport)したように出現する.一方,この時点ではまだボブはアリスの測定結果を知らない.またアリスの測定で系に注入された励起エネルギーもまだアリス周辺に留まっており,ボブの量子系には及んでいない.従って対照的にボブにとってはボブの量子系は取り出せるエネルギーが存在しない「無」の状態のままである.このように,現代的コペンハーゲン解釈で許される観測者依存性のおかげで,エネルギーがテレポートしたように見えても因果律は保たれている.非相対論的モデルを前提にして,系のエネルギー伝搬速度より速い光速度でアリスが測定結果をボブに伝えたとしよう.アリスが測定で系に注入したエネルギーはボブにまだ届いていないにも関わらず,情報を得たボブにも波動関数の収縮が起こり,自分の量子系から取り出せるエネルギーの存在に気付く.そしてボブは測定値毎に異なる量子揺らぎのパターンに応じて適当な局所的操作を選び,エネルギー密度の量子揺らぎを抑えることが可能となる.その結果ボブは平均的に正のエネルギーを外部に取り出すことが可能となる.これがQETである.このQETは量子ホール系を用いて実験的に検証できる可能性が高い.一方,相対論的なQETモデルはブラックホールエントロピー問題にも重要な切り口を与える.
50 0 0 0 OA 成人における麻疹・おたふくかぜ・風疹混合(MMR)ワクチンの 安全性と副反応
47 0 0 0 OA ハタハタ Arctoscopus japonicus の卵塊が多色化する要因
- 著者
- 森岡 泰三 堀田 和夫 友田 努 中村 弘二
- 出版者
- 公益社団法人 日本水産学会
- 雑誌
- 日本水産学会誌 (ISSN:00215392)
- 巻号頁・発行日
- vol.71, no.2, pp.212-214, 2005 (Released:2005-07-15)
- 参考文献数
- 9
- 被引用文献数
- 3 3
ハタハタの卵色の決定に関与する要因を把握するため,異なる餌料で半年間飼育した 2 群から得た成熟卵や餌料の抽出液の吸光度を比較した。オキアミとイカナゴを混合した餌料で育成した群は配合飼料の群に比べて卵,餌料とも吸光度が大きく,群の間に有意差が認められた。前者の卵色は濃い赤や黄色,後者は淡い緑が基調となっており,餌料成分は卵色の決定に関与する要因の一つと推定された。
47 0 0 0 OA 桜と薔薇 : 和英対照日本歴史
46 0 0 0 自己回帰型言語モデルによる個人の移動軌跡の生成
- 著者
- 水野 貴之 堀込 泰三 藤本 祥二 石川 温
- 雑誌
- 2023年度 人工知能学会全国大会(第37回)
- 巻号頁・発行日
- 2023-04-06
In August 1942 dengue fever broke out in Nagasaki, a port city located in the Kyushu District, Japan. It soon spread over other cities, recurring every summer until 1944. This was not only the first dengue epidemic in Japan proper but also was one of the most widespread dengue epidemics recorded in a temperate region, involving at least 200,000 typical cases. It was obvious that the principal vector was Aedes albopictus which distributes in the Main Islands of Japan, particularly south of 38-39°N. At that time an important factor promoted transmission of the infection. A number of water tanks had been set up for the purpose of extinguishing fires caused by bombardment during the war, and the tanks were occupied by innumerable mosquitoes. Large-scale application of insecticides was not then possible. Since the early work by Yamada (1917a, b), it had been believed that Ae. aegypti mosquitoes do not habit in Japan proper, excepting the Ryukyu and Ogasawara Islands. Contrarily, Oguri (1945) and Oguri and Kobayashi (1947,1948) reported that they found Ae. aegypti in the Ushibuka area of Kyushu (32°N) during September 1944 to May 1947. Several other investigators obtained similar survey data as those of Oguri and Kobayashi (1947,1948). The species, either adults or larvae, completely disappeared, however, from there after 1955. In another survey it was observed that, inside a cargo boat which plied between Japan and dengue-prevalent Southeast Asian countries, many Ae. aegypti were seen flying and also larvae were caught from small water deposits on the decks. It was thought that Ae. aegypti were transferred into Japan probably by boat, and that the mosquito settled in a particular area of Japan for several years. There was no definite evidence as to whether or not the imported Ae. aegypti had some role in the 1942-1944 Japanese dengue epidemics. However, serious precautions must be taken against the possible danger that vectors of infectious diseases may be introduced into an originally non-endemic area. Biological and epidemiological aspects relative to these problems are discussed.
44 0 0 0 マイクロカプセルを介した化学物質の新たな環境動態の解明と評価
化学物質の新たな存在形態となりうる、マイクロカプセルを介した化学物質の環境中動態、野生生物の蓄積および生態影響について明らかにする。マイクロカプセルとは、芯材に様々な化学物質を封入した微細な粒子状物質を指す。カプセルに封入された化学物質は、化学物質本来の化学構造から推定される環境動態とは異なる動きを示す。よってその動態解明は新たな研究分野として重要である。本研究ではマイクロカプセルの水環境中での拡散・環境動態および水生生物に与える影響を明らかにし、さらに揮発性・難水溶性の化学物質を内包したマイクロカプセルを合成し、カプセル化した場合としない場合とでの生物影響の差を調べる。
43 0 0 0 OA Kounis症候群により心停止をきたした2症例
- 著者
- 福永 寛 櫻木 悟 藤原 敬士 藤田 慎平 山田 大介 鈴木 秀行 宮地 剛 川本 健治 山本 和彦 堀崎 孝松 田中屋 真智子 片山 祐介
- 出版者
- 公益財団法人 日本心臓財団
- 雑誌
- 心臓 (ISSN:05864488)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, no.SUPPL.2, pp.S2_154-S2_158, 2011 (Released:2012-12-05)
- 参考文献数
- 3
Kounis症候群とはアレルギー反応に伴い急性冠症候群をきたす症候群であり, 冠攣縮に合併したタイプ1とプラーク破裂に伴う血栓形成に起因するタイプ2に分類される. 今回, われわれはKounis症候群により心肺停止をきたした2症例を経験したので報告する.症例1: 76歳, 男性. 腰部脊中柱管狭窄症の術中にセフォペラゾンを投与したところ, アナフィラキシーショックを発症した. 下壁誘導にてST上昇を認めたため急性冠症候群と診断, 緊急冠動脈造影にて右冠動脈#1に血栓および#4AVに完全閉塞を認めた. 血栓吸引療法のみで再疎通が得られた.症例2: 61歳, 男性. 起床時より四肢・体幹に蕁麻疹を認め, その後, 心肺停止となり, 当院へ搬送された. 心肺蘇生術にて心拍再開したが, その後, 心室頻拍が頻発, 急性冠症候群を疑い緊急冠動脈造影を施行した. 冠動脈に有意狭窄は認めなかったが, 心電図上胸部誘導で一時的にST上昇を認めたため, 左前下行枝の冠攣縮と診断した.
43 0 0 0 スッポンの生食により感染したマンソン孤虫症の1例
- 著者
- 堀口 裕治 山田 稔
- 出版者
- 日本皮膚科学会大阪地方会・日本皮膚科学会京滋地方会
- 雑誌
- 皮膚の科学 (ISSN:13471813)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, no.1, pp.39-43, 2013 (Released:2013-06-21)
- 参考文献数
- 18
75歳,男性。スッポンの卵を生で食べた約8週後,右側腹部にそう痒を伴う赤い結節が生じた。初診時,径約 15mm の隆起性で柔らかい赤色結節が見られ,近傍の皮下に浸潤をふれた。パンチ生検を行ったところ,結節の中に白色の紐状の寄生虫をみとめた。その表面の性状,頭部の形,虫体内の石灰小体の存在からマンソン裂頭条虫のプレロセルコイドと同定した。また,血清中の抗マンソン裂頭条虫抗体価の上昇を確認した。生検時に幼虫を除去したのちには再発はみられず,3ヶ月の経過で抗体価は減少した。本例をスッポンの卵の生食により罹患した早期のマンソン孤虫症と診断した。文献的にもスッポンの生食は寄生虫に感染する可能性があると考えた。(皮膚の科学,12: 39-43, 2013)
43 0 0 0 OA 全身性毛細血管漏出症候群の1例
- 著者
- 菅原 里恵 堀中 繁夫 八木 博 石村 公彦 小口 渉 矢野 秀樹 石光 俊彦
- 出版者
- 公益財団法人 日本心臓財団
- 雑誌
- 心臓 (ISSN:05864488)
- 巻号頁・発行日
- vol.44, no.11, pp.1432-1436, 2012-11-15 (Released:2014-04-03)
- 参考文献数
- 17
脱水と溢水を繰り返し,心不全加療に難渋し全身性毛細血管漏出症候群と診断した症例を報告する.症例は66歳,男性.入院時の主訴は意識障害でBP 85/63mmHgと低血圧,血液検査ではHt上昇ならびに低アルブミン血症が認められたため,大量補液にて血圧は改善するも溢水となる.その翌日から急に5,000mL/日以上の多尿が認められ脱水となることを繰り返した.各種ホルモン検査および負荷試験はいずれも異常は認められなかった.しかし,尿中Na排泄量が多いため食塩負荷およびフルドロコルチゾンの投与を開始し増量したところ,再び溢水に伴う体重増加や心拡大,胸水貯留が認められたが用量の調整にて上記発作を出現することなく安定した状態で約2年間,外来通院内服加療した.再度心不全発症し,入院治療するも死亡.全身性毛細血管漏出症候群は,非常に稀な疾患であるが通常の加療に反応しないうっ血性心不全には,当疾患も鑑別疾患の1つとして念頭におくべきと考えられる.
42 0 0 0 OA 地域学習と地方就職: フィールドワーク授業が卒業生の勤務地に与える効果
- 著者
- 堀内 史朗 松坂 暢宏
- 出版者
- 数理社会学会
- 雑誌
- 理論と方法 (ISSN:09131442)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.2, pp.213-220, 2022 (Released:2023-03-24)
41 0 0 0 OA BCG関連リンパ節炎の1例
- 著者
- 堀江 靖 加藤 雅子 永見 光子 杉原 千恵子 八島 正司
- 出版者
- 公益社団法人 日本臨床細胞学会
- 雑誌
- 日本臨床細胞学会雑誌 (ISSN:03871193)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, no.4, pp.274-275, 2000-07-22 (Released:2011-11-08)
- 参考文献数
- 3
A case of BCG-related lymphadenitis is presented. After BCG vaccination, an enlarging mass was noted in the left axillary region of a 1-year-old boy. Imprint smear cytology of the extirpated lesion revealed aggregates of epithelioid and tingible-type histiocytic cells without a necrotic background. Histologically, the lesion showed granulomatous nodules composed of epithelioid histiocytic cells and Langhans' giant cells without associated caseous necrosis. Immunohistochemically, the epithelioid histiocytic cells were positive for and-BCG antibody, lysozyme and CD 68. It is necessary to distinguish this BCG-related lymphadenitis from tuberculous lymphadenitis.
41 0 0 0 OA 仏教ブームについて:僧侶による一般向けの取り組み・イベントに関する2012 年の調査から
- 著者
- 堀江 宗正
- 巻号頁・発行日
- 2013-03-29
40 0 0 0 OA 任意の凸多面体は重なりのない展開図に展開できるだろうか?
「任意の凸多面体は,辺を切り開くことで,その面が重ならないように展開することができるだろうか?」これは,計算幾何学の未解決問題の1つである.より正確に言い換えると,「任意の凸多面体は,単純で自己交差のない多角形に辺展開することができるだろうか?」という問いである.展開図と言うと,小学校の算数の時間に,立方体や直方体の箱をチョキチョキと切り開いたのを思い出される方が多いだろう.本稿では,その頃には出てこなかった「単純」や「自己交差」,「辺展開」といった見慣れないキーワードの解説から始め,上記の未解決問題へのアプローチと関連研究について述べる.
40 0 0 0 OA 都立公園内における特異的な池の堆積物中の放射性セシウムの水平・垂直分布
- 著者
- 小豆川 勝見 堀 まゆみ 髙倉 凌
- 出版者
- 一般社団法人 日本環境化学会
- 雑誌
- 環境化学 (ISSN:09172408)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.3, pp.77-81, 2018-09-20 (Released:2019-03-22)
- 参考文献数
- 19
We investigated the dynamics of air dose rate and radiocesium (134Cs and 137Cs) in pond sediments at urban environment, Hikarigaoka Park, Tokyo, where drained the water from the pond on Dec. 2017 for the first time after the Fukushima accident (Mar. 2011). The average of the air dose rates at the height of 1 m outside/inside the pond was 0.069±0.024 μSv/h (n=1926, Ave ±1σ), which did not conflict with the decontamination criteria. The distribution of radiocesium in sediment was totally uniform. The maximum radioactivity of pond sediments was 58.3 Bq/kg-wet, and that of average was 30.6±11.4 Bq/kg-wet (n=80, Ave ±1σ). The maximum inventory was 4.10 kBq/m2, which was clearly less than the inventory (6.94 kBq/m2) when assuming the pond as Japanese paddy field. This fact showed that the pond had the small accumulation effect of radiocesium at the time of our survey. It is estimated that this effect is caused by a mechanism that constantly circulates the pond water.
- 著者
- 堀江 宗正
- 出版者
- 日本宗教学会
- 雑誌
- 宗教研究 (ISSN:03873293)
- 巻号頁・発行日
- vol.85, no.4, pp.1042-1043, 2012-03-30
40 0 0 0 OA 東京湾における放射性セシウムの現状解析
- 著者
- 亭島 博彦 江里口 知巳 柳田 圭悟 堀口 文男
- 出版者
- 海洋理工学会
- 雑誌
- 海洋理工学会誌 (ISSN:13412752)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, no.2, pp.1-11, 2014 (Released:2014-06-26)
- 参考文献数
- 35
We investigated radioactivity concentrations of 134Cs and 137Cs in river waters, Tokyo Bay sediments and Japanese whitings (Sillago japonica) lived in Tokyo Bay. Water samples were taken from Arakawa river mouth and Edogawa river mouth. Due to precipitations at inland areas, the river mouth waters had high concentrations of suspended solid (SS) and radiocesium on July 3 2012. The water sample taken from Arakawa river mouth showed higher concentration of radiocesium than that of from Edogawa river mouth. The sediment sample taken from Arakawa river mouth showed the highest concentration of radiocesium in sediments which were sampled on July 3 2012. In the vicinities of river mouth at the sea, sediments showed decreasing of radiocesium concentration (Bg/1,000 cm3 of sediment) with distance from river mouths, but there was no the same distribution pattern with the radiocesium concentrations (Bg/kg of dried sediment) of them. Values of 134Cs/137Cs activity ratio in sediments suggested that the 137Cs, which was generated by nuclear weapon tests or others before the Fukushima Daiichi Nuclear Power Station accident, was included in the river mouth sediments, and these estimated values was 80 Bq/kg-dry in Arakawa river mouth, and 30 Bq/kg-dry in Edogawa river mouth. Effective ecological half-lives of radiocesium in the sediments taken from off the coast of Kisarazu-shi, Chiba, were about one year of 134Cs and about three years of 137Cs. We recognized that the radiocesium activity concentrations in Japanese whitings living in Tokyo Bay are in safe level as a food. Effective ecological half-life of 137Cs in Japanese whiting was estimated for 1.1 ± 0.4 year. Values of 134Cs/137Cs activity ratio of Japanese whitings in 2012 suggested that the radiocesium exposed experience of each fish differed from two year old fish and three year old fish.