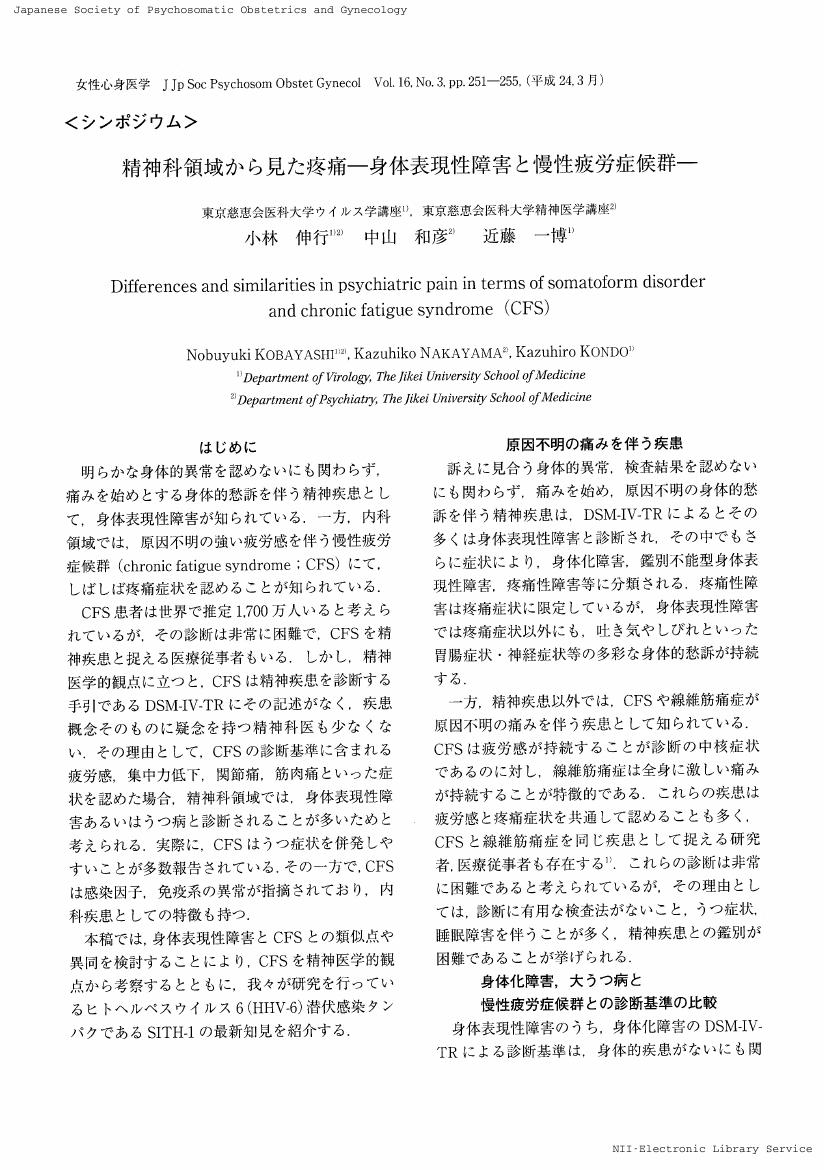2 0 0 0 OA 少量アスピリンの抗血小板療法について 血小板凝集能からの検討
- 著者
- 谷口 直樹 山内 一信 近藤 照夫 横田 充弘 外畑 巌
- 出版者
- 一般社団法人 日本老年医学会
- 雑誌
- 日本老年医学会雑誌 (ISSN:03009173)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, no.6, pp.463-468, 1981-11-30 (Released:2009-11-24)
- 参考文献数
- 10
aspirin は抗血小板薬として従来より各種血栓症の治療に使用されている. 近年 aspirin の大量投与は prostacyclin 合成を阻害し, 血栓生成に作用すると指摘され, その投与量が再検討されつつある. 本研究の目的は aspirin の種々の単回および連日投与における血小板凝集能抑制効果を検討することより, その至適投与量を決定することである. 対象は虚血性心疾患, 弁膜症および大動脈炎症候群などの心疾患患者71名であり, 健常人13名を対照とした. aspirin 1日80, 160, 330, 660および990mg連日投与群における4μM ADP最大凝集率には有意差は認められず, いずれの群の凝集率も aspirin 投与を受けていない健常群のそれに比して低値を示した. aspirin 160mg以上の単回投与では投与後1時間以内に凝集能抑制効果が出現した. 単回投与の凝集能抑制効果持続日数の平均値は330mg投与では4日, 660mgでは5.5日, 1320mgでは6日であった. aspirin による胃腸障害, 出血等の副作用の出現頻度は dose dependent であることを考慮すると, 本薬を長く投与する必要がある場合, 可及的少量が望ましい. ADP凝集抑制効果の観点からは1日量80mgの連日投与または160mgの隔日投与が至適投与法と考えられた.
2 0 0 0 IR 癒しの神学 : ティリッヒを手掛かりに
- 著者
- 近藤 剛
- 出版者
- 関西学院大学
- 雑誌
- 神學研究 (ISSN:05598478)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, pp.127-142, 2004-03-31
- 著者
- 太田 千鶴子 近藤 明子 小林 重雄
- 出版者
- 一般社団法人日本認知・行動療法学会
- 雑誌
- 行動療法研究 (ISSN:09106529)
- 巻号頁・発行日
- vol.4, no.2, pp.91-104, 1979-09-30
本研究の目的は1対1の行動療法的訓練において,改善されにくいとされていた児童対児童の相互作用,遊びに必要なルールの理解を通じて集団遊びを形成することである。集団は「ことばのおくれ」,「他児と遊べない」を主訴とする児童6名で構成されている。対象児は自閉症と診断された3名である。目的を達成するために(1)つなひき,(2)電車ごっこという課題が設定された。第一期では,動作模倣,第二期では,かけっこ,つなひき,サーキット,第三期では,つなひき,電車ごっこを中心プログラムとした。1セッションは各課題とフリープレイから成っている。セッションは週1回,20〜30分で計19回行なわれた。これにより,次のような結果が得られた。1 動作模倣 3児とも達成率が増加し,特にT児は第7〜13セッションにおいて著しい伸びを示している。2 つなひき 次のようなルールの理解度を検討した。(1)合図を守る(2)後方へ引く(3)終点がわかる(4)勝ち負けがわかる(5)応援する。Y児はどのルールも理解できていない。T児は,どのルールもほぼ完全に理解可能となり,K児はルールの(1)〜(3)のみ確実に理解できた。3 電車ごっこ 3児ともお客さん,運転手,駅長などの役割を達成し積極的に参加できるようになっている。
- 著者
- 近藤 明人 中川 剛 臼井 郁敦 杉田 真一
- 出版者
- 一般社団法人映像情報メディア学会
- 雑誌
- 映像情報メディア学会技術報告 (ISSN:13426893)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.23, pp.17-20, 2013-05-29
多くの機械式フェーダやハードスイッチ、出力状態を表示するモニタから構成されていた調光卓、及び、負荷回路制御卓、照明バトン制御卓等を、一つのタッチパネル・ディスプレイに集約して開発することに成功した。これまで既に、TBSの看板番組「輝く!日本レコード大賞」で、メイン調光卓として使用した実績があり、限られたスペースでの多チャンネル制御の実現を証明している。
2 0 0 0 東京臨海副都心線国際展示場駅の照明設備
- 著者
- 金井 智 佐伯 智明 近藤 正紀
- 出版者
- 一般社団法人 照明学会
- 雑誌
- 照明学会雑誌
- 巻号頁・発行日
- vol.81, pp.159, 1997
2 0 0 0 乳癌集検は有効か
- 著者
- 阿部 力哉 近藤 誠 久道 茂
- 出版者
- Japan Association of Breast Cancer Screening
- 雑誌
- 日本乳癌検診学会誌 (ISSN:09180729)
- 巻号頁・発行日
- vol.4, no.2, pp.145-157, 1995
近藤 誠<BR>慶應義塾大学医学部放射線科<BR>乳がん検診の意義があるというためには, 次の5つの項目をすべて充たす必要があります。すなわち, (1) 乳がんの性質が検診に適していること (性質上, 早期発見・早期治療による乳がん死亡減が合理的に予想されること), (2) 検診により乳がん死亡が減ること (いわゆる有効性), (3) 他の死因を含めた総死亡数が減少すること, (4) 検診による不利益がないこと, (5) 不利益がある場合には, 上記 (3) の程度との比較衡量, です。しかし, (1) から (5) までの点はいずれも否定されます。詳しくは, 拙書「それでもがん検診うけますか」 (ネスコ/文藝春秋), 大島明氏 (大阪がん予防検診センター) の「癌検診は果して百害あって一利なしか……近藤誠氏の著書を読んで」 (メディカル朝日95年2月号), および私の「癌検診・百害あって一理なし」 (同95年3月号) を読んでください。<BR>ここではすべての論点に触れるのは不可能ですから, (1) 乳がんの性質が検診に適しているかどうかについて考えてみますが, まず, 乳がんと病理診断される病変のなかには, 放置しても人の命を奪わない「がんもどき」と, 「本物のがん」とがあります!その場合, がんもどきは定義上, どこまでいっても致死性でない病変ですから, 早期発見が無意味なことは当然です。が, 本物のがんに対しても, 検診は理論上無意味なのです!というのも, 本物の乳がんが人の命を奪う原因のほとんどは転移ですから, 検診に意味があるがんは, 早期発見時点ではまだ転移が生じてなくて, そのまま放置すると転移が生じるもの, ということになります。ところが転移が生じる時点は, 数々の証拠からは, 早期発見できる大きさになるはるか以前, と考えられるので, それでは検診は無意味です。<BR>また, がんの本質からも, 乳がんは検診に適していないといえます。というのも, がんは遺伝子の異常をその本質とするので, 個々のがん細胞は同じ遺伝子異常をそなえており, それゆえ転移に関しても同じ性質をもっているはずだからです。発見されたがんが転移する性質をもっているなら, その性質は1個のがん細胞が発生したときから, 個々の細胞にそなわっていると考えるのが素直です。そしてがん細胞は早期発見できる大きさになるまでに, 二分裂を約30回繰り返しています (細胞数は10億個になる) から, 転移する性質のがんでは, 発見した時点までに, もう転移が成立している, と考えるほうが自然です!他方, 早期発見したがんに転移がない場合, 30回もネズミ算を繰り返すうちにも転移できなかったわけですから, それ以降も, 仮に放置しておいてももう転移しないと考えられるでしょう。このように, 乳がんは (そして他臓器のがんも), その本質からも性質からも, 検診に適している (検診で死亡数を減らせる) とは考え難いわけです。<BR>久道 茂<BR>東北大学医学部公衆衛生学<BR>がん検診は早期発見, 早期治療によって, がん死亡率を減少させることを目的としている。厚生省成人病死亡率低減目標策定検討会がまとめた目標は, 40歳から69歳の壮年層の死亡率を平成元年を基点として2000年までに, 胃がん, 子宮がんの半減, 肺がん, 乳がん, 大腸がんの上昇を下降に転じさせるとした。<BR>がん検診にはそれを行う条件がある!死亡率, 罹患率の高いこと, 集団的に実施可能な検診方法であること, 精度の高いスクリーニング法であること, 早期発見による治療効果が期待できること, 費用効果・便益のバランスがとれていること, 死亡率の減少効果があること, 一次スクリーニングだけでなく, 精度検査も含めて一連の検診体系で安全であること, などである。<BR>がん検診に関する研究の方法には手順がある。検診を実施する前に行うスクリーニングテストの精度, 実施可能性, 安全性, 信頼性, 有効性および費用の検討である!その方法として, ケースコントロール研究, 長期のコホート研究, 時系列研究などがある。重要なのは, 実施前から研究計画の手順を踏んでたてておくことである!<BR>がん集検には得失の両面がある。「百害あって一利なし」というキツイ言葉もあるが, がん検診の最大の得 (gain) は早期発見による救命効果である!一方, 失 (loss) は見逃しや偶発症などがある。これらの得失に関してきちんと評価しなければならない。<BR>評価の方法には事前評価, 平行評価および振り返り評価があるが, 別な視点から, 検診を受けたグループが当該がんの死亡数と率が確かに減少したのかを評価する疫学的評価がある。次に, スクリーニングの精度検討や安全性などの検討を行う技術的評価がある。それから経済的評価, システム評価などがある。国際的にはUICC (国際対癌連合) ががんのスクリーニングの評価に関する定期的な会議を行っている!第6回会議 (1990年) では, 世界各地で行われているがん検診を再評価して1冊の本にまとめている。
- 著者
- 松田 えりか 近藤 宏 木下 裕光 砂山 顕大 石崎 直人 鮎澤 聡
- 出版者
- 一般社団法人 日本温泉気候物理医学会
- 雑誌
- 日本温泉気候物理医学会雑誌 (ISSN:00290343)
- 巻号頁・発行日
- vol.83, no.3, pp.122-130, 2020-10-31 (Released:2021-02-10)
- 参考文献数
- 30
【目的】慢性腰痛患者に対する鍼治療の直後効果に影響する因子について,心理社会的要因を探索的に検討した. 【対象と方法】対象は2019年8月~12月までに本学東西医学統合医療センター鍼灸外来を訪れた初診慢性腰痛患者のうち,初診時にVisual Analogue Scale(以下VAS)にて評価した腰部疼痛強度が30mm以上の者56人とした.初診時に自記式質問票を使用し,心理尺度(Pain Catastrophizing Scale(以下,PCS),Hospital Anxiety and Depression Scale,Pain Self-Efficacy Questionnaire),社会的要因(同居家族状況,最終学歴,社会参加状況),腰部機能障害,鍼治療に対するイメージなどを調査した.初回治療直後のVAS値が30mm未満となり,かつ対象者自身が疼痛の改善を認めた者を「高反応群」,それ以外を「低反応群」とした.この2群間で対象者の属性と身体的および心理社会的調査項目を探索的に比較し,さらに2群の区分を二値の従属変数とするロジスティック回帰分析を行った. 【結果と考察】高反応群は22人,低反応群は34人であった.2群間の探索的な比較において統計学的な有意差が認められた項目は,鍼治療に対するプラスイメージ(P=0.001)とマイナスイメージ(P=0.004)のみであった.ロジスティック回帰分析では,PCS(OR:0.886(95%CI:0.808~0.971);P=0.010),鍼治療に対するプラスイメージ(OR:5.085(95%CI:1.724~15.002);P=0.003),同居人数(OR:0.355(95%CI:0.149~0.844);P=0.019)が直後効果に影響を与える因子として抽出された.この結果,慢性腰痛患者の鍼治療効果に心理社会的要因が影響を及ぼすことが示唆された.
TLS によるセキュリティモデルでは,host-to-host の通信路の識別・秘匿化 を可能にするが,PaaS プロバイダや CDN プロバイダなど複数のサービスプロバイダを跨がる Web サービスにおいて,TLS はサービスプロバイダ同士の関係性を保証できない.ユーザは第三者の攻撃やサービスプロバイダの運用事故などにより,サービスプロバイダの意図しない通信先に reroute される可能性がある.本稿では,サービスプロバイダ同士で相互に署名した TLS 公開鍵を DNSSEC で保護された権威 DNS ゾーンで公 開する,軽量な自己管理型相互宣言機構 M2DMRT を提案する.M2DMRT により,サービスプロバイダは第三者に頼らずサービスプロバイダ同士の関係性を相互に宣言でき,ユーザは署名を検証することで容易に関係性を信頼し脅威を回避することができる.本稿では M2DMRT における相互宣言の登録にかかるプロトコルを設計して,そのサーバサイドにおける Proof of Concept の実装を行い,基本性能を評価した結果,実用に耐えうる性能を持つことがわかった.
2 0 0 0 IR 伝中院通躬筆『狭衣物語』巻一翻刻(下)
- 著者
- 青木 祐子 鈴木 幹生 勝亦 志織 近藤 さやか 千野 裕子 Aoki Yuko Suzuki Mikio Katsumata Shiori Kondo Sayaka Chino Yuko
- 出版者
- 学習院大学文学部国語国文学会
- 雑誌
- 學習院大學國語國文學會誌 (ISSN:02864436)
- 巻号頁・発行日
- no.61, pp.16-33, 2018
- 著者
- 近藤 佑子
- 出版者
- 一般社団法人日本建築学会
- 雑誌
- 学術講演梗概集 (ISSN:18839363)
- 巻号頁・発行日
- vol.2012, pp.55-56, 2012-09-12
- 著者
- 宮澤 大輔 栗本 康夫 竹内 篤 近藤 武久
- 雑誌
- あたらしい眼科 = Journal of the eye (ISSN:09101810)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.10, pp.1441-1443, 1998-10-30
- 参考文献数
- 3
- 被引用文献数
- 3
- 著者
- 三木 有咲 波多江 崇 猪野 彩 井上 知美 上野 隼平 笠谷 君代 近藤 亜美 坂口 知子 佐々木 信子 田内 義彦 竹下 治範 辻 華子 中川 素子 野口 栄 長谷川 由佳 水田 恵美 矢羽野 早代 山根 雅子 濵口 常男
- 出版者
- 日本社会薬学会
- 雑誌
- 社会薬学 (ISSN:09110585)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, no.1, pp.24-33, 2015
We implemented a questionnaire survey targeting mothers who are in child care and had participated in consultations regarding drugs and diseases. We examined the future roles of community pharmacists by exploring the mothers' concerns and, anxieties about child cares and their backgrounds, and their expectations for profession of community pharmacist. Mothers have listed anxiety and concerns of child care about "dermatitis such as rash and atopic eczema"; "food allergies"; "infectious diseases such as measles, chicken pox, and mumps"; and "side effects of vaccination". In addition, most of them indicated their own concerns and anxiety about "solutions to children's illnesses." Despite their anxieties and concerns, however, approximately 60% of the mothers have never consulted with community pharmacists. Among them, approximately a half of them indicated the following three reasons why they have never consulted with pharmacists: "I have nothing to talk about,", "I do not know what I should talk about,", and "I was not sure if it was alright to talk about my concerns.". From these results, we concluded that community pharmacists in the future should improve their communication skills and inform their availability to consult about medicine and disease to local residents.
2 0 0 0 OA マムルーク朝におけるウラマーの家系の隆盛 スブキー家の場合
- 著者
- 近藤 真美
- 出版者
- 一般社団法人 日本オリエント学会
- 雑誌
- オリエント (ISSN:00305219)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, no.1, pp.84-102, 1999-09-30 (Released:2010-03-12)
- 被引用文献数
- 1 1
This paper is written with the following aims: To show concretely how al-Subki family took opportunities to increase the prosperity of their family and how they kept this prosperity, and to consider what the limit of this prosperity was. I would like to take as a starting-point an examination of the actual conditions of ‘ulama’-society under the Mamluks.The following summarize the main points made in this paper:(1) The first step in the family's prosperity occurred when two members of the family took the post of qadi of Egypt, and one of the two took the post of mudarris in Cairo. The two were devoted to the education of their son, Tagiy al-Din (d. 756/1355). (2) After Taqiy al-Din received the post of qadi al-qudat of Syria, members of the family began to receive the many important posts in the fields of the judiciary and education, and they thus became rich. This was because of Taqiy al-Din's fame in jurisprudence, and because of the families' efforts to secure these posts, for example, through the use of bribery. (3) It is thought that one of the reasons behind the limitations on the family's prosperity in Cairo is that there was no room for them to establish a base of prosperity, and that, because of this, they tried to establish a base via forming relations with influential Syrian families through marriage. (4) However, a base couldn't be completely established in Syria. The reason may have been because the plague attacked many members of the family.From an examination of the case of al-Subki family, we can get a picture of a part of the rigid ‘ulama’-society in that era. That is in that era a few families were already influential and it was difficult for families to expand their sphere of influence.
2 0 0 0 白金族金属の長期需給見通しに関する一考察
- 著者
- 近藤 敏 武山 眞 大藏 隆彦
- 出版者
- 一般社団法人 資源・素材学会
- 雑誌
- 資源と素材 : 資源・素材学会誌 : journal of the Mining and Materials Processing Institute of Japan (ISSN:09161740)
- 巻号頁・発行日
- vol.122, no.8, pp.386-395, 2006-08-25
- 参考文献数
- 2
- 被引用文献数
- 4 7
Some 400 tons of platinum group metals (PGM) are yearly produced and used mainly for auto-catalyst, jewelries and electric appliances. The annual growth rate is currently more than 4%. Main resources for PGM exist predominantly in South Africa, Russia and North America, showing that they co-exist with Ni-Cu sulphide in the range of 5-10 ppm in their ores.<BR>Meanwhile, technological developments for fuel cells are being promoted, in which PEMFC (proton exchange membrane fuel cell) should be used for vehicles and stationary power. The PEMFC needs platinum as a catalyst due to the lower reaction temperature. The imbalance between supply and demand of Pt should become one of critical paths for the PEMFC promotion, if Japanese Government target is realized.<BR>This paper describes the forecast of supply & demand of Platinum based on various researches and investigations, and self-constructed model. Supply of platinum will be short in 2030's on schedule of the Japanese Government's scenario. Political countermeasure should be applied together with resources developments in order to secure the Pt resource.
2 0 0 0 IR アジ科魚類(マアジ,カンパチ,ヒラマサ)の好中球の形態学的および細胞化学的特徴
Morphological and cytochemical characteristics of neutrophil in Carangid fishes, jackmackerel(Trachurus japonicus), greater amberjack(Seriola dumerili)and yellowtail amberjack(S. lalandi), were examined by light microscopy. Three types of granules, eosinophilic granule(αG), chromophobic granule(βG)and basophilic granule(γG)were observed in the neutrophils of these fish species. Multiple Romanowsky-type stain valuation revealed that αGs of these fish species were stained eosinophilic with May-Gr?nwald(MG), but not with Giemsa. Eosinophilic stain of the αG was disappeared by Giemsa after MG. The βGs were unstained by Romanowsky-type stain and peroxidase-positive. The γG of greater amberjack and yellowtail amberjack were stained light blue with Giemsa, but unstained with MG. On the other hand, the γGs of jack-mackerel were stained not only with Giemsa, but also with MG.
- 著者
- 小林 伸行 中山 和彦 近藤 一博
- 出版者
- 一般社団法人 日本女性心身医学会
- 雑誌
- 女性心身医学 (ISSN:13452894)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, no.3, pp.251-255, 2012-03-31 (Released:2017-01-26)
2 0 0 0 OA 日本水道生物学誌
- 著者
- 近藤 正義
- 出版者
- 日本水処理生物学会
- 雑誌
- 日本水処理生物学会誌 (ISSN:09106758)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, no.1, pp.3-12,19, 1964-06-15 (Released:2010-02-26)
2 0 0 0 OA 強力内閣の待望と顔ぶれ
2 0 0 0 OA 創業期の資生堂と福原有信の経営戦略
- 著者
- 近藤 順一
- 出版者
- 埼玉大学経済学会
- 雑誌
- 経済科学論究 = The journal of economic science (ISSN:13493558)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, pp.67-80, 2017