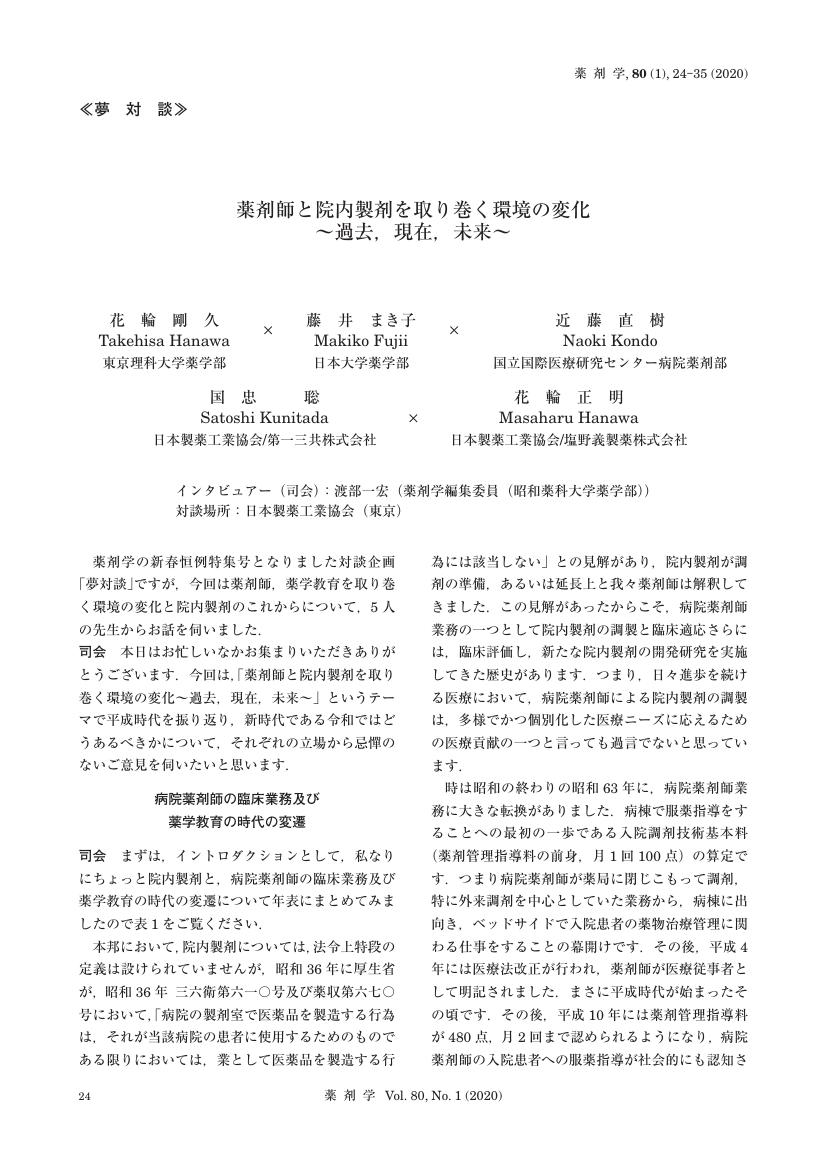2 0 0 0 IR 司馬江漢の面白さ (洋学特集)
- 著者
- 近藤 秀実
- 出版者
- 早稲田大学図書館
- 雑誌
- 早稲田大学図書館紀要 (ISSN:02892502)
- 巻号頁・発行日
- no.41, pp.p169-206, 1995-03
2 0 0 0 OA 慣性センサを用いた身体運動計測における3次元姿勢推定法に関する研究
- 著者
- 近藤 亜希子 土岐 仁 廣瀬 圭
- 出版者
- 一般社団法人 日本機械学会
- 雑誌
- 日本機械学会論文集C編 (ISSN:18848354)
- 巻号頁・発行日
- vol.79, no.803, pp.2351-2361, 2013 (Released:2013-07-25)
- 参考文献数
- 13
- 被引用文献数
- 1 2
This paper proposes the measurement method of 3D posture using inertial sensors. The proposed method estimates the 3D posture (Roll-Pitch-Yaw angles in local coordinate) using the 3-axis angular velocity and the 3-axis acceleration. The 3D posture is compensated for the drift error of gyro sensor output by the translational and gravity accelerations of accelerometer output. The nonlinear state equation and the nonlinear measurement equation were established to estimate 3D posture. The Extended Kalman filter and the Unscented Kalman filter are applied to these equations. The measurement experiment was conducted to clarify the accuracy of proposed method using the experimental setup installing the rotary encoders. The results of the Unscented Kalman filter indicated higher than those by the Extended Kalman filter. In addition, the proposed method estimated the 3D posture compensating the drift error of gyro sensor in the measurement experiment generating the translational acceleration. Therefore, the proposed method can be used for the measurement of body motion.
2 0 0 0 OA 二分脊椎症と葉酸 葉酸経口摂取量と葉酸血清濃度
- 著者
- 近藤 厚生 木村 恭祐 磯部 安朗 上平 修 松浦 治 後藤 百万 岡井 いくよ
- 出版者
- 一般社団法人 日本泌尿器科学会
- 雑誌
- 日本泌尿器科学会雑誌 (ISSN:00215287)
- 巻号頁・発行日
- vol.94, no.5, pp.551-559, 2003-07-20 (Released:2010-07-23)
- 参考文献数
- 18
- 被引用文献数
- 1 1
(目的) 神経管閉鎖障害に罹患する胎児の発生リスクは, 母親が妊娠前に葉酸を摂取すると低減できる. 研究目的は, 女性が食事から摂取する葉酸について検討し, 葉酸血清濃度を測定することである.(対象と方法) 対象者は一般女性, 二分脊椎患者の母親, 妊婦, 二分脊椎患者, 看護学生の5群からなる222名の女性. 食事から摂取した葉酸量は, 食事記録を5訂日本食品標準成分表に準拠して解析した. 葉酸血清濃度は化学発光免疫測定法で測定した.(結果) 対象者は食事から葉酸を平均293μg/日摂取しており, 血清濃度は平均8.1ng/ml, エネルギー摂取量は平均1,857Kcalであった. 妊婦が食事から葉酸を最も多く摂っており, 血中濃度も最高値を示した.「日本人の栄養所要量」が規定する葉酸量を充足しない対象者の割合は, 成人女性が22%, 妊婦が72%であった. 葉酸は第3食品群 (香川綾分類) から最も多く摂取されていた. 葉酸サプリメント400μg/日を16週間内服すると, 基線値は7.8ng/mlから17.3へ上昇した.(結論) 葉酸経口摂取量は平均293μg/日, 血清濃度は平均8.1ng/mlであった. 妊婦の過半数は政府が勧告する葉酸量を摂取していなかった. 妊娠可能期の女性は葉酸に富む第3食品群を多く摂り, 妊娠を計画する女性は妊娠4週前から妊娠12週まで葉酸サプリメント400μg/日の内服が望ましい.
- 著者
- 谷村 嘉彦 平山 英夫 近藤 健次郎 永田 寛 岩永 宏平 鈴木 征四郎
- 出版者
- 一般社団法人 日本原子力学会
- 雑誌
- 日本原子力学会和文論文誌 (ISSN:13472879)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.3, pp.129-132, 2016 (Released:2016-08-15)
- 参考文献数
- 6
Photon energy spectra were measured above the operating floor of unit 3 reactor at the Fukushima Daiichi Nuclear Power Station by using a CdZnTe semiconductor spectrometer. The spectrometer was installed in a lead collimator to measure the photons from the area directly below the detector. The collimator and spectrometer were lifted up by a huge crane and set above the operating floor. The photon spectra were derived by unfolding the pulse height spectra measured using the spectrometer. The response function of the spectrometer was calculated with the MCNP-4C code and was used as an input parameter of the unfolding code MAXED. It was found from the photon energy spectra that low-energy photons with energy below 0.4 MeV were dominant above the operating floor. These spectra are fundamental data for evaluating the dose reduction effect by setting up shields on the operating floor.
- 著者
- 近藤 正一
- 出版者
- 日本建築学会
- 雑誌
- 建築雑誌 (ISSN:00038555)
- 巻号頁・発行日
- no.1351, pp.24-25, 1993-12
2 0 0 0 IR 山の「山の神」と里の「山の神」 : 花嫁のケガレ観をめぐって
- 著者
- 近藤 直也
- 出版者
- 関西大学博物館
- 雑誌
- 関西大学博物館紀要 (ISSN:13414895)
- 巻号頁・発行日
- no.2, pp.113-135, 1996-03-30
2 0 0 0 OA 自宅退院した脳卒中患者の屋外活動における基準値 —退院時の身体的因子による検討—
- 著者
- 吉田 啓志 近藤 駿 増田 裕里 嶋尾 悟 浜岡 克伺 成冨 博章
- 出版者
- 理学療法科学学会
- 雑誌
- 理学療法科学 (ISSN:13411667)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.2, pp.323-326, 2018 (Released:2018-04-27)
- 参考文献数
- 16
- 被引用文献数
- 2
〔目的〕本研究は,リハビリ後自宅退院した脳卒中患者の活動範囲を屋内群と屋外群に分類し,屋外活動の可否を最も予測可能な退院時身体的因子のカットオフ値を明らかにすることとした.〔対象と方法〕自立歩行可能で自宅退院した脳卒中患者31名を対象とした.退院3ヵ月後の活動範囲をLife Space Assessment(LSA)を用いて調査した.退院時評価項目のうちLSA合計点と有意に相関する指標を抽出し,屋外活動判別に最も適したカットオフ値を求めた.〔結果〕6分間歩行距離(6MD)のカットオフ値が最も高い判別能を示し,その値は358.5 mであった.〔結語〕脳卒中患者の自宅退院後の屋外活動を維持・向上させるためには入院中の6MDにおいて350 m以上を目指す必要があることが示唆された.
2 0 0 0 原子力はクリーンエネルギーの4番バッター
- 著者
- 増子 輝彦 近藤 吉明 佐田 務
- 出版者
- 一般社団法人 日本原子力学会
- 雑誌
- 日本原子力学会誌 = Journal of the Atomic Energy Society of Japan (ISSN:18822606)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, no.1, pp.1-2, 2010-01-01
- 著者
- 近藤 雪絵 木村 修平 山中 司 山下 美朋 井之上 浩一
- 出版者
- 一般社団法人 日本薬学教育学会
- 雑誌
- 薬学教育 (ISSN:24324124)
- 巻号頁・発行日
- vol.4, pp.2020-011, 2020 (Released:2020-10-16)
- 参考文献数
- 10
立命館大学薬学部ではディプロマ・ポリシーにおける教育目標の一つである「国際社会でも活躍できる英語での情報収集・発信能力」を涵養するため,「プロジェクト発信型英語プログラム」(Project-based English Program: PEP)を導入し,専門英語を含む英語科目を系統的に配置している.本稿では,専門性の高い領域での英語発信力を育成するために,専門教員と英語教員がどのようにコラボレーションできるかを,専門教員,専門知識を持たない英語母語話者,社会人による学生のプレゼンテーションの評価分析を元に論じた.専門教員はテーマの絞り込みや深め方,英語教員は成果を広く発信する際にどう社会に関連させ伝えるかという点でアドバイスを行い,学生自身がその中で自分の意見をさらに深めるという協同が実現することにより,発信力を “I(自身)”,“Me(客観的に捉えた自身)”,“Connection(自身と他者あるいは社会とのつながり)” の観点から涵養できるという示唆が得られた.
- 著者
- 近藤 智士 数井 航平 野際 大介
- 出版者
- 公益社団法人 日本都市計画学会
- 雑誌
- 日本都市計画学会中部支部研究発表会論文集 (ISSN:24357316)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, pp.5-8, 2020 (Released:2020-10-05)
- 参考文献数
- 17
コンパクトシティ政策を進めている富山市を対象として2005年,2010年,2015年の国勢調査の地域メッシュデータを用いて人口分布を把握した.その結果,2005年から2015年にかけて市全体に占める市街化区域の人口割合が上昇していることを確認した.また,人口規模別階級を整理したところ,2005年から2010年にかけては人口1,000人以上を有するメッシュ数が減少したのに対して,2010年から2015年にかけてはメッシュ数が増加に転じた.これらのデータや基本統計量の推移を考慮すると,富山市では2005年から2010年にかけては人口分布が拡散する傾向にあったが,2010年から2015年にかけては人口拡散に歯止めがかかり,集積する傾向に転じていることが確認できた.
2 0 0 0 OA 烏口突起骨折の治療と分類
- 著者
- 中村 恭啓 那須 亨二 近藤 正貴 伊藤 元一
- 出版者
- 中国・四国整形外科学会
- 雑誌
- 中国・四国整形外科学会雑誌 (ISSN:09152695)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, no.2, pp.461-466, 1993-09-01 (Released:2009-03-31)
- 参考文献数
- 10
We experienced eight fractures of the coracoid process during the period from 1984 to 1992. Seven cases of them were basal fractures and one case was apical one. Two cases were isolated, being in the other six cases combined with acromioclavicular dislocation or clavicular fracture. One patient with minimally displaced fracture of the coracoid process was treated conservatively. But the others were treated by internal fixation with a cannulated malleolar screw, one of which was inserted percutaneously. Postoperatively, Kenny-Howard type harness was worn in each case for four weeks. The result was satisfactory and all surgical cases were united. Neither infection nor loss of function was observed. These fracutures were assessed regarding the cause of injury, region of contusion, and complicated osseous-articular injuries around the shoulder. From the mechanism of injury, they were classified into two major groups: Group I; direct fracture, group II; indirect fracture. The direct fractures were subdivided into two types: Type I; by force from outside, type II; by force from inside. The indirect fractures were further divided into two types; Type I; by ligamentous traction, type II; by muscular traction. It is recommended to treat operatively if a gap of indirect fracture is five millimeter or more on roentgenograms.
- 著者
- 近藤 貴明
- 出版者
- 立命館大学国際平和ミュージアム
- 雑誌
- 立命館平和研究 : 立命館大学国際平和ミュージアム紀要 (ISSN:18827217)
- 巻号頁・発行日
- no.17, pp.55-64, 2016
- 著者
- 天野 成昭 近藤 公久
- 出版者
- 日本音声学会
- 雑誌
- 音声研究 (ISSN:13428675)
- 巻号頁・発行日
- vol.4, no.2, pp.44-50, 2000-08-30 (Released:2017-08-31)
NTT psycholinguistic databases "Lexical Properties of Japanese" were developed for the large number of Japanese words and characters. The databases contain word and character information such as familiarity, frequency of occurrence, appropriateness of accent, appropriateness of orthography, subjective complexity, and other important psycholinguistic properties. Words and characters satisfying multiple search conditions can be very efficiently obtained for stimuli in psycholinguistic experiments, which was impossible without the database in past days. The databases provide a basis for psycholinguistic research on Japanese.
2 0 0 0 OA 厳罰傾向と帰属スタイルの関連
- 著者
- 向井 智哉 松木 祐馬 木村 真利子 近藤 文哉
- 出版者
- 公益社団法人 日本心理学会
- 雑誌
- 心理学研究 (ISSN:00215236)
- 巻号頁・発行日
- pp.91.19211, (Released:2020-07-30)
- 参考文献数
- 58
- 被引用文献数
- 1
This study aims to explore how the relationship between punitiveness and attributional style differs between Japan and Korea. Data from 330 Japanese and 339 Koreans were analyzed. Multi-group structural equation modeling showed that in both Japan and Korea, punitiveness consisted of three factors (support for harsher punishment, greater criminalization, and use of the death penalty) while the attributional style consisted of two factors (dispositional attribution and situational attribution). In both countries, dispositional attribution was related to punitiveness. Regarding differences, the scores for punitiveness on all three subscale scores and for dispositional attribution were higher in Korea whereas the negative relationship between punitiveness subscale scores and situational attribution was stronger in Japan. This suggests that Japanese are less likely to support punitive measures for criminals and to attribute the causes of crime to the criminals themselves than Koreans. In addition, when deciding on the severity of punishment, Japanese are more likely to take situational causes into consideration.
2 0 0 0 OA 物語への没入体験と社会的能力の向上の関連:成人と児童の比較1)
- 著者
- 小山内 秀和 古見 文一 北島 美花 近藤 千恵子 所 歩美 米田 英嗣 楠見 孝
- 出版者
- 日本認知科学会
- 雑誌
- 認知科学 (ISSN:13417924)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.1, pp.108-120, 2019-03-01 (Released:2019-09-01)
- 参考文献数
- 39
The concept of immersion into stories refers to the degree to which readers focus their attention fully on a story and experience the situation in the story like a real world. During such an experience, readers project the representations of the story onto the text itself. Although researchers have investigated whether reading narrative fiction is positively associated with social ability, empirical studies do not provide consistent results. We hypothesized that individual differences in story immersion can influence the relationship between reading stories and mindreading. In Study 1 (with adults) and Study 2 (with children), we measured participants’ exposure to stories, their proneness to story immersion, and mindreading. In contrast to previous studies, we did not find significant correlation between exposure to stories and mindreading. Story exposure,however, was associated with the story immersion in both adults and children. Furthermore, the result of Study 1 showed significant correlation between story immersion and mindreading. These results suggest an important role for story immersion on the enhancement of mindreading. This possibility is discussed in light of the methodology used to measure story immersion and developmental changes in reading experience.
2 0 0 0 「フィールド歴史学」の提案 (特集 フィールド歴史学)
- 著者
- 近藤 一成
- 出版者
- 早稲田大学文学部東洋史学専修室
- 雑誌
- 史滴 (ISSN:02854643)
- 巻号頁・発行日
- no.30, pp.1-6, 2008-12
2 0 0 0 OA 多施設間連携ランダム化比較試験による 慢性膝痛に対するマッサージ療法の有効性の検討
- 著者
- 水出 靖 藤井 亮輔 近藤 宏 和田 恒彦 岡田 富広 柏木 慎太郎 栗原 勝美 西村 みゆき 柴田 健一 高澤 史 古川 直樹 長谷部 光二
- 出版者
- 日本理療科教員連盟
- 雑誌
- 理療教育研究 (ISSN:13498401)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, pp.9-17, 2016 (Released:2019-02-04)
- 参考文献数
- 16
【目的】慢性膝痛に対するマッサージ療法の有効性を検証するため多施設間連携による ランダム化比較試験を行った。 【対象】施術所・通所介護事業所5 施設の利用者で一定の基準を満たす膝痛を有し、本 研究の趣旨に同意の得られた29 例(平均年齢67.9 ± 7.7 歳)を対象とした。 【方法】介入群(膝周囲の軟部組織に対するマッサージと運動療法、以下M 群)と対 照群(安静臥床、以下C 群)に乱数を用いて無作為に割付け、膝関節屈曲可動域、殿 踵間距離、膝窩床間距離、疼痛出現しゃがみ込み角度、TUG test、5 m 歩行時間・ 歩数、疼痛のVAS について介入前後で比較した。 【結果】両群間の介入前後の変化は、膝屈曲角度、膝窩床間距離、疼痛出現しゃがみ 込み角度において交互作用を認め(すべてp<0.05)、M 群で有意に改善した(各 p<0.01、p<0.05、P<0.01)。また、すべての被験者に明らかな有害事象は認めなかっ た。 【考察・結語】慢性膝痛に対するマッサージ療法は、関節機能の改善に有効かつ安全性 の高い方法であることが示唆された。
2 0 0 0 OA 薬剤師と院内製剤を取り巻く環境の変化~過去,現在,未来~
- 著者
- 花輪 剛久 藤井 まき子 近藤 直樹 国忠 聡 花輪 正明
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬剤学会
- 雑誌
- 薬剤学 (ISSN:03727629)
- 巻号頁・発行日
- vol.80, no.1, pp.24-35, 2020 (Released:2020-01-01)