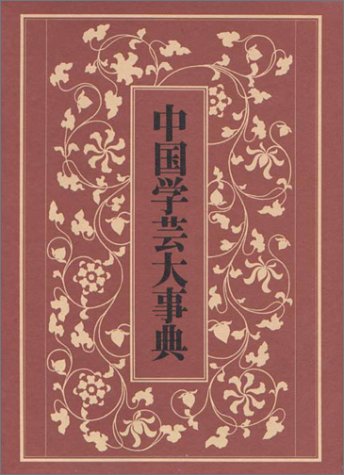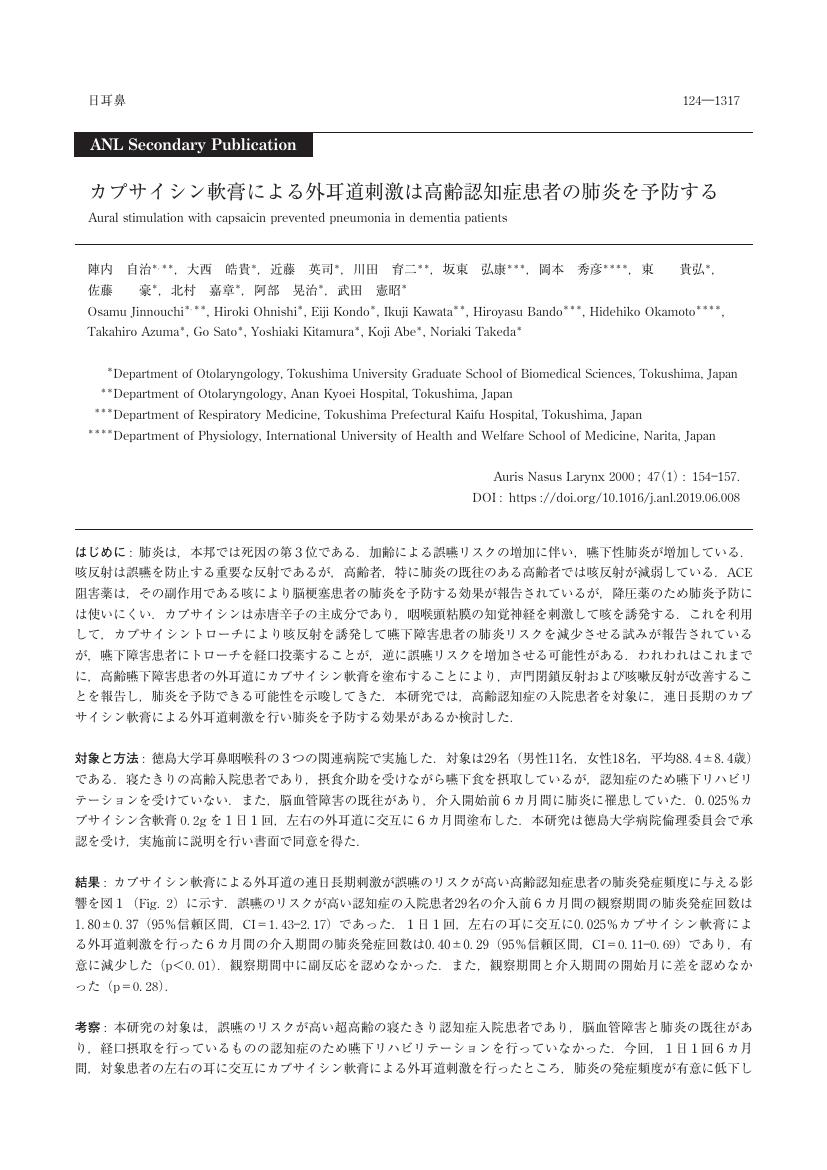2 0 0 0 OA 社会的ひきこもりと自閉症スペクトラム障害
- 著者
- 近藤 直司
- 出版者
- NPO法人 日本自閉症スペクトラム支援協会 日本自閉症スペクトラム学会
- 雑誌
- 自閉症スペクトラム研究 (ISSN:13475932)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, no.1, pp.37-45, 2013-03-28 (Released:2019-04-25)
- 参考文献数
- 15
ひきこもり問題と自閉症スペクトラム障害(広汎性発達障害)との関連性は以前から指摘されてきたことである。本稿では,まず,青年期ひきこもりケースの精神医学的診断と,自閉症スペクトラム障害を背景とするひきこもりケースの特性について述べる。 次に,これらのケースに対する精神療法的アプローチとして,メンタライゼーションmentalization に焦 点付けた方法論について論じてみたい。また,ひきこもりのリスクをもつ子どもへの治療・支援について検討するために,青年期においてひきこもりを生じているケースの特徴について検討した結果,自閉症特性の目立ちにくい受身的・内向的なタイプに留意すべきであることが明らかになった。また,青年期・成人期において激しい家庭内暴力など介入困難な状況に陥るケースがあることを踏まえ,その典型的な精神病理と家族状況,児童・思春期における精神科医療のあり方と,より早期の予防的早期介入に関する視点を示した。
2 0 0 0 日本の消費税の実効税率について
- 著者
- 近藤 里恵
- 出版者
- 環太平洋産業連関分析学会
- 雑誌
- 産業連関 (ISSN:13419803)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.1, pp.3-10, 2007
消費税は導入当初から効率的な間接税であるという了解があったように思われる.しかし現行の日本の消費税には「輸出のゼロ税率」や「資本形成による消費税の還付」の制度がある.ある産業において他の産業よりも多く投資がなされる場合,多くの還付がなされ,どの課税財に対しても定率の従価税という消費税の性質が保存されない可能性がある.よって消費税の実効税率を求める必要性が発生する.これら還付制度を考慮したとき,消費税は効率的と言えるのであろうか.これを消費税の実効税率を求めることによって明らかにすることを本稿の目的とする.実効税率の導出は,入谷(2004)の課税前価格を産業連関論における価格方程式によって計算する手法でなされている.
2 0 0 0 OA 宮古諸島下地島の西沿岸域におけるアンキアライン陥没ドリーネ群の予備調査
- 著者
- 眞部 広紀 長嶋 豊 浦田 健作 山本 祐二 近藤 正義 岡本 渉
- 出版者
- 佐世保工業高等専門学校
- 雑誌
- 佐世保工業高等専門学校研究報告 = RESEARCH REPORTS OF NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY, SASEBO COLLEGE (ISSN:21883688)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, pp.5-13, 2017-01
2 0 0 0 OA 老若男女の発汗能力の解明とその生物学的意義
発汗能力は,思春期前では性差はみられず,思春期以降に男女とも増大するものの,その程度は女性が男性よりも小さかったため,若年者では女性が男性より低かった.発汗能力は男女とも加齢に伴い低下し,その性差は80 歳代で消失する傾向だった.若年者では短期間の運動トレーニング・暑熱順化に伴う発汗能力の改善の程度にも性差(男>女)がみられた.長期間運動トレーニングに伴う発汗能力の改善は,子供や高齢者が若年者より小さかった.女性の少ない発汗量は,体液の損失を最小限に抑えようとする生物学的意義が窺えた.なお,男性の運動トレーニング・暑熱馴化・加齢による発汗能力の変化は性ホルモン・成長ホルモンとは関連しなかった.
2 0 0 0 OA 古代の一日と「ぬばたまの夜」(後篇)
- 著者
- 近藤 信義
- 出版者
- 立正大学
- 雑誌
- 立正大学文学部研究紀要 (ISSN:09114378)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, pp.51-85, 1989-03-20
2 0 0 0 OA 大腸内視鏡検査後7日目に発症した汎発性腹膜炎の1例
- 著者
- 橋本 憲輝 近藤 浩史 衛藤 隆一 小佐々 博明 清水 良一
- 出版者
- 山口大学医学会
- 雑誌
- 山口医学 (ISSN:05131731)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.6, pp.261-265, 2009-12-31 (Released:2010-01-28)
- 参考文献数
- 10
症例は61歳,女性.2008年12月,当院内科にて検診目的で下部消化管内視鏡検査(colonoscopy,以下CS)が施行された.3日後に軽度の嘔気・下腹部違和感を認めたが,経過観察されていた.7日後,腹痛が増悪したため,同科を再診した.腹部骨盤単純CT検査により穿孔性腹膜炎と診断され,加療目的で当科へ紹介された.当科受診時,腹部にやや膨満があり,全体的に圧痛,反跳痛を認めた.腹部骨盤単純CT検査では腹腔内に遊離ガスが散見され,腹水も認めた.結腸穿孔ならびに急性汎発性腹膜炎と診断し,緊急開腹術を施行した.手術所見では,直腸RS部近傍のS状結腸に腸間膜経由での穿孔を認め,腸間膜内には多量の便塊,便汁が貯留していた.穿孔部より口側でS状結腸と骨盤腔内左卵巣近傍の壁側腹膜との間で強固な線維性の癒着を認めた.術式は急性汎発性腹膜炎手術,S状結腸切除術,人工肛門造設術(ハルトマン手術)を施行した.術直後から急性呼吸窮迫症候群を発症したが,集中治療により軽快した.術後第52病日に独歩にて自宅退院された.2009年3月当科にて人工肛門閉鎖術を施行した.CS施行後,汎発性腹膜炎の発症が7日目である稀な症例を経験したので若干の文献的考察を加えて報告する.
- 著者
- 近藤 光 Hikaru Kondo
- 出版者
- 千葉経済大学
- 雑誌
- 千葉経済論叢 = CHIBA KEIZAI RONSO (ISSN:21876320)
- 巻号頁・発行日
- no.67, pp.145-164, 2022-12-01
千葉経済大学
- 著者
- 近藤 乃梨子
- 出版者
- 一般社団法人 集団力学研究所
- 雑誌
- 集団力学 (ISSN:21872872)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, pp.321-376, 2017-12-28 (Released:2017-10-30)
- 参考文献数
- 21
過疎地域において、人口減少という問題は依然進行しているが、過疎地域を「気候や自然に恵まれた場」、「ロハスやスローライフのできる場」、「自給自足のできる場」、「子育てに適した場」として、暮らしや自己実現の観点から肯定的に捉える機運が生まれており、田園回帰志向が高まっている。過疎地域の活性化のためには、過疎地域への移住を促進するとともに、とくに若者世代、子育て世代の仕事づくりを実現することが重要である。 <br> 移住者が地域づくりの主体として、過疎地域に眠る埋もれていた地域資源をヨソモノ視点によって利活用し、「地域のなりわい」を生み出すことは、地域の価値を創造することにほかならず、過疎地域の地域づくりに新たな価値を上乗せする。この移住者による「地域のなりわい」づくりの社会的意義は計り知れない。 <br> 購入型クラウドファンディングは、過疎地域で「地域のなりわい」を起業する移住者のリスクを少しでも軽減し、金銭的負担をわけあい、心理的な応援者を獲得し、万が一失敗しても再チャレンジすることのできる簡便に導入できる資金調達の方法である。過疎地域における購入型クラウドファンディング活用の意義は、起業のための資金が調達できることにとどまらず、資金調達のためのプロジェクト終了後も、過疎地域に人とお金の流れをつくることにある。本稿では、過疎地域の移住者による購入型クラウドファンディング活用の有用性について、山口県長門市油谷向津具半島の移住者の事例を用いて、過疎地域への人とお金の流れを生み出すことを確認した。 <br> また、購入型クラウドファンディングの活用によって得られた、目標達成のために支援メンバーを事前確保したうえで、より多くの「ファン」を効率的に獲得するスキルが、新たな地域資源活用商品の販売プロモーションや都市農村交流及び移住の促進など、過疎地域に人とお金の流れを呼び込むための様々な活動に応用することができると指摘した。
2 0 0 0 OA 両側股関節離断者に対する交互歩行用義足の製作と訓練
- 著者
- 中村 隆 今井 大樹 濱 祐美 近藤 怜子
- 出版者
- 日本義肢装具学会
- 雑誌
- 日本義肢装具学会誌 (ISSN:09104720)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.1, pp.56-58, 2021-01-01 (Released:2022-01-15)
- 参考文献数
- 6
両側股関節離断者はきわめて稀であり,義足の適応を含めリハビリテーションに関する報告はきわめて少ない.症例は24歳,男性.交通事故による両側股関節離断.大振り歩行による義足歩行を獲得したのち,交互義足歩行訓練を試みた.両股義足にはストライドコントロール付き股継手(徳林社製,TH-01C)を改良した遊動股継手と,イールディング機能付き膝継手(オットーボック社製,3R31)を導入した.対麻痺の脊髄損傷者の歩行訓練手法を適用し,左右の重心移動により義足の振り出しが可能になり,交互義足歩行を達成した.また,継手の固定解除機構を工夫し,義足の装脱着と起立,歩行,着座といった一連の訓練動作が自立した.
2 0 0 0 OA セルロースナノファイバーテクノロジーの新展開
- 著者
- 近藤 哲男
- 出版者
- 一般社団法人 日本木材学会
- 雑誌
- 木材学会誌 (ISSN:00214795)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.3, pp.107-115, 2008-05-25 (Released:2008-05-28)
- 参考文献数
- 41
- 被引用文献数
- 16 16
最近のナノテクノロジーの著しい進歩は,さまざまな材料創製の概念を変えてきた。天然素材においても,その影響は大きい。植物体の骨格を形成しているセルロースや昆虫や甲殻類の外皮の主成分であるキチンなどのいわゆるバイオマス資源は,もともとナノファイバーから高次の構造へと天然ビルドアッププロセスにより,その構造が構築されている。そのような構造ができあがっている天然素材を,有効に用い,しかも自然にやさしいプロセスでナノ機能素材へと変換する試みが21世紀に入って急速に展開してきた。本稿では,最近のセルロースナノファイバーの潮流について,その基礎から展開までの概略を述べる。また最近,著者らも,トップダウン的加工法として,天然セルロース繊維を表面から分子やナノレベルの分子集合体を引き剥がすことにより微細化し,最終的にナノ分散水化させる水中カウンターコリジョン法を開発した。この手法についても併せて紹介する。
2 0 0 0 OA 卓上の絵画、線の振幅
- 著者
- 近藤 恵介
- 出版者
- 佐賀大学芸術地域デザイン学部
- 雑誌
- 佐賀大学芸術地域デザイン学部研究論文集 (ISSN:24339679)
- 巻号頁・発行日
- vol.4, pp.143-167, 2021-03
- 著者
- 猪又 直子 池澤 善郎 守田 亜希子 桐野 実緒 山崎 晴名 山口 絢子 山根 裕美子 立脇 聡子 広門 未知子 近藤 恵
- 出版者
- 一般社団法人 日本アレルギー学会
- 雑誌
- アレルギー (ISSN:00214884)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.10, pp.1276-1284, 2007
- 参考文献数
- 13
- 被引用文献数
- 5
【背景・目的】本邦では多数の植物由来食物による口腔アレルギー症候群(oral allergy syndrome : OAS)を検討した報告は稀である.そこで,本研究では本疾患の臨床的特徴と花粉感作との関連性を明らかにするため,OAS診断例63例について検討した.【方法】6年間に植物由来食物摂取後の口腔症状を自覚した例に被疑食物と花粉のプリックテスト(SPT)や特異IgE測定(CAP-FEIA : CAP)を施行した.【結果】被疑食物のSPTが陽性となったOAS診断例63例(男 : 女=1 : 2,平均年齢 : 28.7歳)の原因食品はリンゴ13例,モモ12例,キウイ12例,メロン11例であった.モモは口腔以外の症状を高率に誘発し,モモとウメの各1例でアナフィラキシーショックに至った.上位4食物のSPT陽性率は55.0〜63.2%であった.リンゴではCAPとSPTと間に相関をみとめたが(r=0.39,p<0.05),メロン,モモ,キウイではみとめられなかった.花粉症の合併は66.1%と高率で,花粉のCAP陽性率はリンゴではハンノキで,メロンではカモガヤ,ヨモギ,ブタクサで高い傾向があった.【考察】SPTとCAPの陽性率は食物の種類によって大きく異なる傾向があり,また,全体として患者の訴えより低い.現時点では,植物由来食物によるOASを診断する際に皮膚テストを用いるほうがよいと考えた.
2 0 0 0 OA 高齢難聴者における補聴器導入前後でのフレイルの変化
- 著者
- 杉浦 彩子 サブレ森田 さゆり 清水 笑子 伊藤 恵里奈 川村 皓生 吉原 杏奈 内田 育恵 鈴木 宏和 近藤 和泉 中島 務
- 出版者
- 一般社団法人 日本聴覚医学会
- 雑誌
- AUDIOLOGY JAPAN (ISSN:03038106)
- 巻号頁・発行日
- vol.64, no.1, pp.69-77, 2021-02-28 (Released:2021-03-20)
- 参考文献数
- 23
要旨: 補聴器がフレイルに与える影響を明らかにすることを目的に, 補聴器導入前と補聴器導入約半年後に基本チェックリスト (Kihon Check List: KCL) を実施し, その変化について検討した。 補聴器装用歴のない60歳以上の補聴器外来初診患者64名において, 補聴器導入前後における KCL 総得点の平均は, 装用前が5.1点, 装用後が4.9点で, 有意な変化は認めなかった。KCL の下位項目である日常生活関連動作, 運動器機能, 低栄養状態, 口腔機能, 閉じこもり, 認知機能, 抑うつ気分も有意な変化は認めず, KCL の質問項目それぞれについての検討で, 質問1(公共交通機関での外出) のみ有意な変化を認めた。KCL 総得点がロバスト方向へ変化した群としなかった群の特性の違いについて検討したところ, 補聴器導入前の KCL 総得点が高得点であること, 良聴耳聴力がよいことが有意にロバスト方向への変化と関連していた。一方, KCL 総得点のフレイル方向への変化の有無における特性は明らかでなかった。
2 0 0 0 OA 女子プロゴルファーの腰背部痛に対するM-Testによる円皮鍼治療の一症例
- 著者
- 櫻庭 陽 近藤 宏 泉 重樹 森山 朝正
- 出版者
- 公益社団法人 全日本鍼灸学会
- 雑誌
- 全日本鍼灸学会雑誌 (ISSN:02859955)
- 巻号頁・発行日
- vol.71, no.4, pp.236-244, 2021 (Released:2022-08-10)
- 参考文献数
- 17
2 0 0 0 OA 水稲用除草剤シハロホップブチルの開発と製剤化技術の確立
- 著者
- 関島 恒夫 原 範和 大津 敬 近藤 宣昭
- 出版者
- 一般社団法人 日本生態学会
- 雑誌
- 日本生態学会誌 (ISSN:00215007)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.3, pp.335-344, 2007-11-30 (Released:2016-09-16)
- 参考文献数
- 29
「冬眠」現象を研究する魅力は、5℃以下まで体温を低下させることができる低体温耐性と、そのような極限の体温低下にも関わらず、細胞や組織レベルで異常をきたさず、生体が正常に機能を果たしている点にある。チョウセンシマリスから発見された新規の冬眠特異的タンパク質(Hibernation-specific proteins: HP)に関する研究は、現象の把握に終始してきた冬眠研究を、統合的な生理的調節システムとして理解する道筋を提供した。その結果、チョウセンシマリスでは冬眠を制御する年周リズムが体内で自律的に働き、それが血中のHP量を調節することで、冬眠可能な生理状態を自ら作り出していることが明らかとなった。また、HPの生体内調節の知見に基づき、冬眠期における脳内HPの機能をHP抗体の脳室内投与により阻害したところ、冬眠状態から覚醒状態への速やかな移行が見られ、冬眠の人工的制御が可能であることを証明した。本総説では、これまでに明らかとなっている冬眠調節に関わる生理機構の全貌に加え、冬眠調節の一端を担うことが明らかとなったHPを分子指標として用い、冬眠の進化あるいは地球規模の環境変化による冬眠動物への影響評価といった生態学的・進化学的視点に立った課題の解決に向けた最近の取り組みを紹介する。
2 0 0 0 OA カプサイシン軟膏による外耳道刺激は高齢認知症患者の肺炎を予防する
- 著者
- 陣内 自治 大西 皓貴 近藤 英司 川田 育二 坂東 弘康 岡本 秀彦 東 貴弘 佐藤 豪 北村 嘉章 阿部 晃治 武田 憲昭
- 出版者
- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会
- 雑誌
- 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会会報 (ISSN:24365793)
- 巻号頁・発行日
- vol.124, no.9, pp.1317-1318, 2021-09-20 (Released:2021-10-01)
2 0 0 0 OA 幼少期における人的資本形成と中高齢者の健康格差の関連
健康・機能状態の社会的格差をライフコースの視点から検証する際、幼少期情報を想起情報に頼らざるを得ないことが多い。代理指標として脚長などの客観的マーカーの利用可能性を検討した。高齢者パネル調査(くらしと健康調査)を用いて脚長(幼少期の栄養状態の代理指標)と親職種、幼少期「生活困難度」との関係を見たが、有意な関係は認められなかった。一方、脚長は、学歴と収縮期血圧の関係を有意に媒介していた。社会経済的要因による社会的選択の影響を考慮し、同朋情報を用いてバイアス補正を検討したところ、同朋との到達学歴の一致・不一致により学歴と健康・生活習慣との関連性が異なっていた。社会的選択の影響を考慮する必要がある。