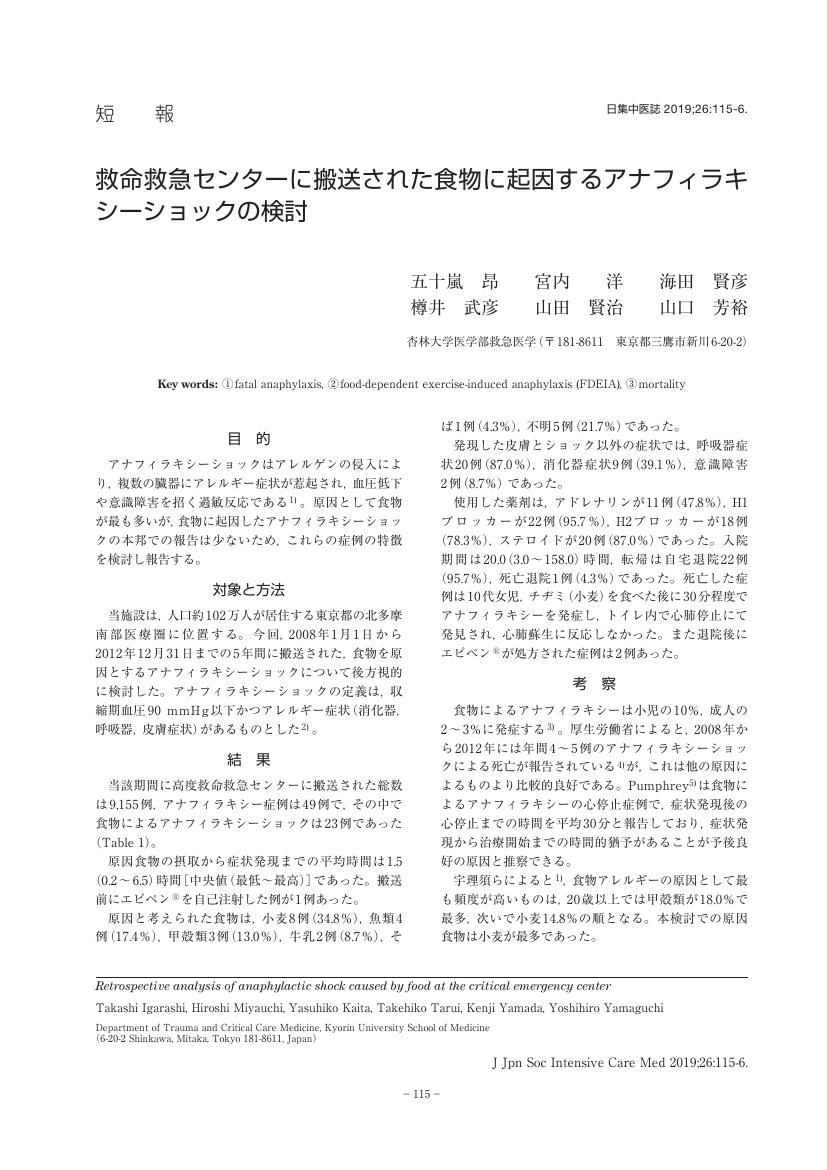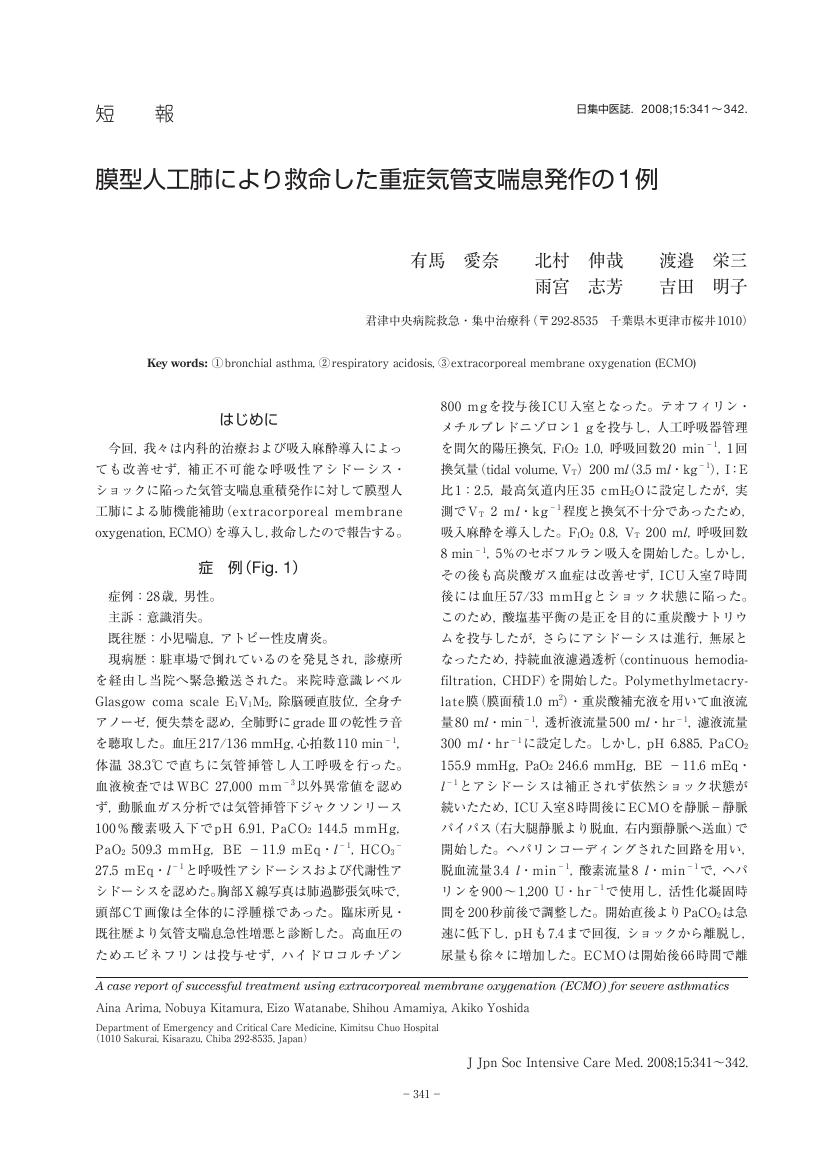1 0 0 0 OA 試験開腹でも早期診断できなかった非閉塞性腸管虚血症の一例
- 著者
- 澤田 健 黒田 浩光 升田 好樹 今泉 均 巽 博臣 小濱 卓朗 秦 史壯 浅井 康文
- 出版者
- 一般社団法人 日本集中治療医学会
- 雑誌
- 日本集中治療医学会雑誌 (ISSN:13407988)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, no.1, pp.71-75, 2007-01-01 (Released:2008-10-24)
- 参考文献数
- 9
- 被引用文献数
- 6 4
試験開腹術にて早期診断できなかった非閉塞性腸管虚血症 (nonocclusive mesenteric ischemia, NOMI) の一例を経験した。症例は76歳男性で, 腹痛を主訴に来院し, S状結腸憩室穿孔に対して, 発症から9時間後にS状結腸切除と人工肛門造設を行った。入室24時間後にショックとなり, 腸管壊死を疑い試験開腹術を行った。術中, 腸管壊死を示唆する所見はなかった。その後も血清乳酸値が上昇し, 再手術から30時間後の胸腹部造影CTでは腸管全体の造影効果の低下を認めたが, 腸間膜動脈・門脈などに血栓を示唆する所見はなかった。その後, 血清乳酸値は低下傾向を示した。しかし, 創が離開し腹腔内を観察したところ, 十二指腸から大腸まで壊死しており保存的治療としたが, 多臓器不全により死亡した。開腹による一回の腸管漿膜面からの肉眼的な判断では, NOMIの診断を見誤る可能性がある。血管造影はもちろんであるが, 開腹にて判断がつかない場合には, 滅菌ドレープを用いて被覆した状態での腹壁開放創とした腸管観察も一つの手段と考えられた。また, 腸管虚血による血清乳酸値の上昇を示す症例で, 上昇後にみられる血清乳酸値の低下は腸管虚血の病態改善を示すものではない可能性が示唆された。
1 0 0 0 OA ICUにおける頭頸部癌患者の遊離皮弁移植術後管理
- 著者
- 横田 泰佑 遠藤 新大
- 出版者
- 一般社団法人 日本集中治療医学会
- 雑誌
- 日本集中治療医学会雑誌 (ISSN:13407988)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, no.4, pp.383-388, 2017-07-01 (Released:2017-07-05)
- 参考文献数
- 49
遊離皮弁は,頭頸部癌・外傷・熱傷患者などの再建術で使用される。皮弁のモニタリングのために,術後はICUへの入室を要する。主な術後合併症は,血栓症・血腫・瘻孔・皮弁壊死であり,術後合併症の発生を認識するために,数時間おきに皮弁の評価を行う必要がある。皮弁の評価は,術後72時間行うことを推奨する報告もあるが,本邦で皮弁のモニタリング目的のみでICUに在室するのは難しいと思われる。遊離皮弁は機械的圧迫により血栓症が発生する可能性があり,安静を保つ必要がある。しかし,興奮と譫妄により安静を保てない可能性がある。現在,遊離皮弁に関する文献の多くは,後ろ向き観察研究であり,今後はランダム化比較試験が課題である。本稿では,ICU管理に必要な遊離皮弁の基本的知識について解説するとともに,問題点を考察する。
1 0 0 0 OA 周術期同種血輸血を必要とした帝王切開術後患者12例の検討
- 著者
- 甲斐 慎一 横田 喜美夫 山下 茂樹 米井 昭智
- 出版者
- 一般社団法人 日本集中治療医学会
- 雑誌
- 日本集中治療医学会雑誌 (ISSN:13407988)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.2, pp.203-206, 2010-04-01 (Released:2010-10-30)
- 参考文献数
- 10
2005年1月~2008年4月に出血により同種血輸血を必要とし当院ICUに入室した帝王切開術後患者12例について検討した。妊産婦の平均年齢は33歳で,疾患は常位胎盤早期剥離4例,弛緩出血2例,前置胎盤2例,癒着胎盤2例,hemolysis, elevated liver enzymes, low platelet count(HELLP)症候群1例,子宮破裂1例であった。8例が産科disseminated intravascular coagulation(DIC)を合併した。ICU入室期間は平均3日,入院期間は平均20日で,全例軽快退院した。平均同種血輸血量は赤血球濃厚液18単位,新鮮凍結血漿15単位,濃厚血小板18単位であった。7例が止血術を要し,うち3例は経カテーテル動脈塞栓術(transcatheter arterial embolization, TAE)のみ施行,2例は子宮全摘術のみ施行,1例はTAE中に出血性ショックとなり緊急で子宮全摘術を施行,1例は子宮全摘術後も出血が持続しTAEを施行した。産科出血は,迅速な輸血や止血術が肝要であり,院内の緊急輸血体制の整備に加え,産科医,集中治療医,麻酔科医,放射線科医の協力体制を整えることが必要である。
1 0 0 0 OA 経直腸投与によるカチノン系薬物中毒で重篤な中枢神経障害を合併した1例
- 著者
- 森岡 貴勢 山本 朋納 加賀 慎一郎 西村 哲郎 山本 啓雅 溝端 康光 下野 太郎
- 出版者
- 一般社団法人 日本集中治療医学会
- 雑誌
- 日本集中治療医学会雑誌 (ISSN:13407988)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, no.2, pp.139-140, 2017-03-01 (Released:2017-03-16)
- 参考文献数
- 7
1 0 0 0 OA 肺結核に罹患した妊婦に対する心肺蘇生経験
- 著者
- 西 啓亨 照屋 孝二 渕上 竜也 垣花 学 須加原 一博
- 出版者
- 一般社団法人 日本集中治療医学会
- 雑誌
- 日本集中治療医学会雑誌 (ISSN:13407988)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, no.1, pp.61-62, 2015-01-01 (Released:2015-01-19)
- 参考文献数
- 4
1 0 0 0 OA 熱中症患者の体温管理における血管内冷却システムの使用経験
- 著者
- 田中 亮 金田 浩太郎 戸谷 昌樹 宮内 崇 藤田 基 河村 宜克 小田 泰崇 鶴田 良介
- 出版者
- 一般社団法人 日本集中治療医学会
- 雑誌
- 日本集中治療医学会雑誌 (ISSN:13407988)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, no.4, pp.398-401, 2016-07-01 (Released:2016-07-01)
- 参考文献数
- 11
- 被引用文献数
- 1
当施設では心停止蘇生後患者に対する目標体温管理の導入と維持など,治療を目的とした体温管理に血管内冷却システムを使用している。今回,38歳男性のIII度熱中症患者に対し,体温管理目的に血管内冷却システムを使用し,良好に体温を管理できた症例を経験した。当施設に救急搬送され,体表冷却・冷却輸液などの従来の冷却方法を用いて管理した症例との比較では,目標温度到達時間や冷却速度は両者に差はなかったが,従来型冷却法では体温のリバウンドが認められたのに対して,血管内冷却システムを使用した本症例では目標温度到達後も体温を安定して管理できた。血管内冷却システムは熱中症症例の体温管理にも有用である可能性が示唆された。
1 0 0 0 OA ミニトラック挿入時の合併症
- 著者
- 前田 敏樹 音成 芳正 関 啓輔 乙宗 佳奈子 藤本 正司 木村 廷和 穴吹 大介 白川 洋一
- 出版者
- 一般社団法人 日本集中治療医学会
- 雑誌
- 日本集中治療医学会雑誌 (ISSN:13407988)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, no.1, pp.95-96, 2013-01-01 (Released:2013-04-23)
- 参考文献数
- 7
- 著者
- 麻喜 幹博 山森 温 増田 崇光 三木 靖雄
- 出版者
- 一般社団法人 日本集中治療医学会
- 雑誌
- 日本集中治療医学会雑誌 (ISSN:13407988)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.4, pp.259-263, 2019-07-01 (Released:2019-07-01)
- 参考文献数
- 7
症例は37歳,男性。幼少期に交通外傷により前頭葉壊死となり人格障害,症侯性てんかんで近医にて投薬を受けていた。搬送前日,数剤の抗てんかん薬を含む処方薬,約40日分を過量服薬し意識障害遷延のため翌日に当院へ救急搬送された。昏睡であり胃内容物吸引・挿管施行し,集中治療を開始した。第4病日の朝に全身痙攣と,多源性心室固有調律,心室頻拍を認めショック状態となった。直流通電や強心薬の投与開始で血圧は上昇したが,左室駆出率は30%,フェニトイン血中濃度は入院時の24.6μg/mLと比し40以上と高値を示し中毒の主体と考えた。その12時間後に再度ショック状態から難治性心停止となったため,veno arterial extracorporeal membrane oxygenation(VA-ECMO)を導入した。フェニトイン除去目的に活性炭による直接血液灌流法(direct hemoperfusion, DHP)も併用した。血中濃度が改善すると循環も安定し,第8病日にVA-ECMO離脱,後日抜管し独歩で退院となった。フェニトインによる心毒性が遅発性に出現しVA-ECMOを要し,DHPの効果も確認できた稀な症例であり報告する。
1 0 0 0 OA 救命救急センターに搬送された食物に起因するアナフィラキシーショックの検討
- 著者
- 五十嵐 昂 宮内 洋 海田 賢彦 樽井 武彦 山田 賢治 山口 芳裕
- 出版者
- 一般社団法人 日本集中治療医学会
- 雑誌
- 日本集中治療医学会雑誌 (ISSN:13407988)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.2, pp.115-116, 2019-03-01 (Released:2019-03-01)
- 参考文献数
- 7
- 著者
- 門野 紀子 大地 史広 出口 志保 日下 裕介 下山 雄一郎 日外 知行 梅垣 修
- 出版者
- 一般社団法人 日本集中治療医学会
- 雑誌
- 日本集中治療医学会雑誌 (ISSN:13407988)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, no.4, pp.267-268, 2015-07-01 (Released:2015-07-10)
- 参考文献数
- 10
- 著者
- 長門 優 岩本 謙荘 原山 信也 岩田 輝男 二瓶 俊一 谷川 隆久 相原 啓二 蒲地 正幸
- 出版者
- 一般社団法人 日本集中治療医学会
- 雑誌
- 日本集中治療医学会雑誌 (ISSN:13407988)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.4, pp.521-525, 2008-10-01 (Released:2009-04-20)
- 参考文献数
- 9
尿管結石症から敗血症性ショック,播種性血管内凝固症候群となり救命できなかった一例を経験した。症例は85歳女性。尿路感染症を疑われ近医に入院したが,翌日にショックとなり当院に紹介された。当院搬送時すでに多臓器機能不全の状態であった。血中エンドトキシン値の上昇と,CTにて左尿管結石,左水腎症を認め,結石嵌頓による敗血症と診断した。呼吸循環管理に加え,経尿道尿管カテーテル留置,エンドトキシン吸着および持続血液濾過透析を行ったが,ICU入室2日目に死亡した。血液・尿培養のいずれからもEscherichia coli(E. coli)が検出された。当院で過去5年間に経験した尿管結石症から敗血症へ移行した10症例のうち,死亡例は本症例のみであった。原因として,高齢であったこと,全身性炎症反応症候群が遷延し重症化したことに加え,抗生物質によりグラム陰性菌からエンドトキシン遊離が助長された可能性が考えられた。
1 0 0 0 OA ICU入室患者における類白血病反応の検討
- 著者
- 町野 麻美 若松 正樹 開田 剛史 森 康一郎 白 晋
- 出版者
- 一般社団法人 日本集中治療医学会
- 雑誌
- 日本集中治療医学会雑誌 (ISSN:13407988)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, no.6, pp.666-669, 2016-11-01 (Released:2016-11-01)
- 参考文献数
- 13
【目的】末梢血白血球数(WBC)が著増する類白血病反応(leukemoid reaction, LR)の臨床的意義をICU入室患者において遡及的に検討した。【対象と方法】最近4年間にWBCが3万/μl以上を呈した患者の基礎疾患,検査所見,転帰などを調べた。【結果】LRは46例に認め,基礎疾患から,感染群(31例)と非感染群(15例)に大別された。前者のうち24例で起因菌が同定された。後者は腹腔内出血6例,心肺蘇生後4例などであった。年齢,WBC最高値,LR持続日数,担癌患者数,ステロイド使用数は感染群で有意に高値であった。好中球の核左方移動は両群とも約87%に認めた。半年後の死亡率に差はなかった(感染群51%,非感染群60%)。【結語】LRはICU入室患者の約2%に発症し,基礎疾患は感染症が多く,非感染例の約2倍を占めた。ICUでのLR発症には,感染症の有無を問わず,予後不良を念頭に置いた全身管理が肝要と考えられた。
1 0 0 0 OA 破傷風とマグネシウムイオン
- 著者
- 佐藤 義昭
- 出版者
- 一般社団法人 日本集中治療医学会
- 雑誌
- 日本集中治療医学会雑誌 (ISSN:13407988)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, no.1, pp.19-23, 2007-01-01 (Released:2008-10-24)
- 参考文献数
- 33
1 0 0 0 OA 日本版敗血症診療ガイドライン2016 CQ6 免疫グロブリン(IVIG)療法
1 0 0 0 OA 深在性真菌症診断とβ-D-グルカン値測定
- 著者
- 吉田 耕一郎 二木 芳人
- 出版者
- 一般社団法人 日本集中治療医学会
- 雑誌
- 日本集中治療医学会雑誌 (ISSN:13407988)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.1, pp.1-3, 2010-01-01 (Released:2010-07-30)
- 参考文献数
- 5
1 0 0 0 OA 降下性壊死性縦隔炎:早期発見と適正な治療のために
- 著者
- 野中 誠 門倉 光隆
- 出版者
- 一般社団法人 日本集中治療医学会
- 雑誌
- 日本集中治療医学会雑誌 (ISSN:13407988)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.1, pp.41-48, 2008-01-01 (Released:2008-08-15)
- 参考文献数
- 38
- 被引用文献数
- 9 9
縦隔炎は様々な疾患に引き続いて発生するが,降下性壊死性縦隔炎は歯科および頚部感染症によって起こる,致死的で緊急を要する病態である。歯科および頚部感染症は一般的に見られるものであるが,頚胸部の臨床所見を認める場合には直ちに頚胸部CTを施行することにより,降下性壊死性縦隔炎を早期に発見することが可能となる。患者を救命するためには,積極的な頚部や縦隔の外科的ドレナージが必要である。また術後も膿瘍の再燃が起こり得るため,その早期発見のためにCTが有用である。降下性壊死性縦隔炎はすべての臨床医が把握すべき病態であり,総説した。
1 0 0 0 OA Richmond Agitation-Sedation Scale日本語版の作成
- 著者
- 卯野木 健 桜本 秀明 沖村 愛子 竹嶋 千晴 青木 和裕 大谷 典生 望月 俊明 柳澤 八恵子
- 出版者
- 一般社団法人 日本集中治療医学会
- 雑誌
- 日本集中治療医学会雑誌 (ISSN:13407988)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.1, pp.73-74, 2010-01-01 (Released:2010-07-30)
- 参考文献数
- 8
- 被引用文献数
- 1 4
1 0 0 0 OA 膜型人工肺により救命した重症気管支喘息発作の1例
- 著者
- 有馬 愛奈 北村 伸哉 渡邉 栄三 雨宮 志芳 吉田 明子
- 出版者
- 一般社団法人 日本集中治療医学会
- 雑誌
- 日本集中治療医学会雑誌 (ISSN:13407988)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.3, pp.341-342, 2008-07-01 (Released:2009-03-31)
- 参考文献数
- 7
1 0 0 0 OA ネオスチグミン長期内服によるコリン作動性クリーゼの1例
- 著者
- 大邉 寛幸 小張 祐介 遠山 昌平 小林 正和 小林 道生 石橋 悟
- 出版者
- 一般社団法人 日本集中治療医学会
- 雑誌
- 日本集中治療医学会雑誌 (ISSN:13407988)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, no.2, pp.149-150, 2017-03-01 (Released:2017-03-16)
- 参考文献数
- 6
- 著者
- 木下 裕貴 橋場 英二 竹川 大貴 渡邉 洋平 緑川 陽子 斎藤 淳一 廣田 和美
- 出版者
- 一般社団法人 日本集中治療医学会
- 雑誌
- 日集中医誌 (ISSN:13407988)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.5, pp.401-402, 2018