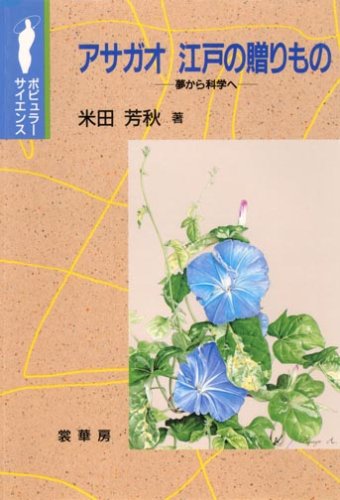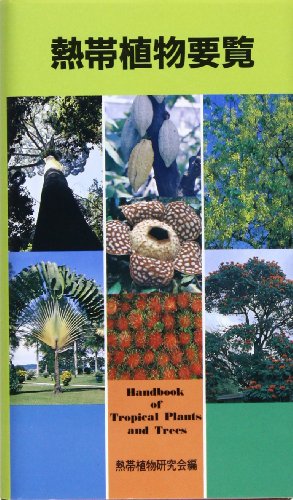1 0 0 0 OA ステアリング操作における人間の手先インピーダンス特性の解析
- 著者
- 田中 良幸 神田 龍馬 武田 雄策 山田 直樹 福庭 一志 正守 一郎 辻 敏夫
- 出版者
- The Society of Instrument and Control Engineers
- 雑誌
- 計測自動制御学会論文集 (ISSN:04534654)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, no.12, pp.1353-1359, 2006-12-31 (Released:2009-03-27)
- 参考文献数
- 15
- 被引用文献数
- 5 7
The present paper investigates human mechanical impedance during the operation of a virtual steering system according to dual-arm configurations. The developed steering system using an impedance-controlled robot can accurately estimate mechanical impedance properties around the rotational axis. Experimental results demonstrate that a human changes his/her impedance properties in both the grip position on a steering wheel and the magnitude of steering torque. Overall stability of a human-steering system is then discussed by means of the measured human impedance parameters.
- 著者
- Hiroko Takumi Kazuko Kato Hiroki Nakanishi Maiko Tamura Takayo Ohto-N Saeko Nagao Junko Hirose
- 出版者
- Japan Oil Chemists' Society
- 雑誌
- Journal of Oleo Science (ISSN:13458957)
- 巻号頁・発行日
- vol.71, no.7, pp.947-957, 2022 (Released:2022-07-01)
- 参考文献数
- 36
- 被引用文献数
- 10
Precision nutrition, also referred to as personalized nutrition, focuses on the individual to determine the individual’s most effective eating plan to prevent or treat disease. A precision nutrition for infants requires the determination of the profile of human milk. We compared the lipid profiles of the foremilk (i.e., the initial milk of a breastfeed) and hindmilk (the last milk) of six Japanese subjects and evaluated whether a human milk lipid profile is useful for precision nutrition even though the fat concentration fluctuates during lactation. We detected and quantified 527 species with a lipidome analysis by liquid chromatography-tandem mass spectrometry. The fat concentration in hindmilk (120.6 ± 66.7 μmol/mL) was significantly higher than that in foremilk (68.6 ± 33.3 μmol/mL). While the total carbon number of fatty acids in triglyceride (TG) was highest in C52 for all subjects, the second or third number differed among the subjects. Both the distribution of total carbon number of fatty acids included in TG and the distribution of fatty acids in TG classified by the number of double bonds were almost the same in the foremilk and hindmilk in each subject. The lipids levels containing docosahexaenoic acid and arachidonic acid in total lipids of the foremilk and the hindmilk were almost the same in each subject. Among the sphingolipids and glycerophospholipids, the level of sphingomyelin was the highest in four subjects’ milk, and phosphatidylcholine was the highest in the other two subjects’ milk. The order of their major species was the same in each foremilk and hindmilk. A clustering heatmap revealed the differences between foremilk and hindmilk in the same subject were smaller than the differences among individuals. Our analyses indicate that a human-milk lipid profile reflects individual characteristics and is a worthwhile focus for precision nutrition.
1 0 0 0 OA 中・近世移行期の施錠具と真鍮生産にみる外来技術導入をめぐる諸問題
- 著者
- 坪根 伸也
- 出版者
- 国立歴史民俗博物館
- 雑誌
- 国立歴史民俗博物館研究報告 = Bulletin of the National Museum of Japanese History (ISSN:02867400)
- 巻号頁・発行日
- vol.210, pp.123-152, 2018-03-30
中世から近世への移行期の対外交易は,南蛮貿易から朱印船貿易へと段階的に変遷し,この間,東洋と西洋の接触と融合を経て,様々な外来技術がもたらされた。当該期の外来技術の受容,定着には複雑で多様な様相が認められる。本稿ではこうした様相の一端の把握,検討にあたり,錠前,真鍮生産に着目した。錠前に関しては,第2次導入期である中世末期から近世の様態について整理し,アジア型錠前主体の段階からヨーロッパ型錠前が参入する段階への変遷を明らかにした。さらにアジア型鍵形態の画一化や,素材のひとつである黄銅(真鍮)の亜鉛含有率の低い製品の存在等から,比較的早い段階での国内生産の可能性を指摘した。真鍮生産については,金属製錬などの際に気体で得られる亜鉛の性質から特殊な道具と技術が必要であり,これに伴うと考えられる把手付坩堝と蓋の集成を行い技術導入時期の検討を行った。その結果,16世紀前半にすでに局所的な導入は認められるが,限定的ながら一般化するのは16世紀末から17世紀初頭であり,金属混合法による本格的な操業は今のところ17世紀中頃を待たなければならない状況を確認した。また,ヨーロッパ型錠前の技術導入について,17世紀以降に国内で生産される和錠や近世遺跡から出土する錠の外観はヨーロッパ錠を模倣するが,内部構造と施錠原理はアジア型錠と同じであり,ヨーロッパ型錠の構造原理が採用されていない点に多様な技術受容のひとつのスタイルを見出した。こうした点を踏まえ,16世紀末における日本文化と西洋文化の融合の象徴ともいえる南蛮様式の輸出用漆器に注目し,付属する真鍮製などのヨーロッパ型の施錠具や隅金具等の生産と遺跡出土の錠前,真鍮生産の状況との関係性を考察した。現状では当該期の大規模かつ広範にわたる生産様相は今のところ認め難く,遺跡資料にみる技術の定着・完成時期と,初期輸出用漆器の生産ピーク時期とは整合していないという課題を提示した。
1 0 0 0 OA 一酸化窒素 (NO)
- 著者
- 金子 武彦
- 出版者
- 日本医療ガス学会
- 雑誌
- Medical Gases (ISSN:24346152)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, no.1, pp.15-19, 2010 (Released:2020-01-27)
- 参考文献数
- 15
1 0 0 0 OA 追悼記事
- 著者
- 三浦 俊彦
- 出版者
- The Philosophy of Science Society, Japan
- 雑誌
- 科学哲学 (ISSN:02893428)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, no.1, pp.77, 2012 (Released:2016-01-13)
1 0 0 0 OA 第1回犯罪被害実態(暗数)調査(第2報告) : 先進12か国に関する国際比較
- 著者
- 岡田和也
- 出版者
- 法務省
- 雑誌
- 法務総合研究所研究部報告
- 巻号頁・発行日
- no.18, 2002-03
1 0 0 0 OA 「今」と「瞬間」 フッサール/デリダ/バタイユ
- 著者
- 髙橋 紀穂
- 出版者
- 学校法人 天満学園 太成学院大学
- 雑誌
- 太成学院大学紀要 (ISSN:13490966)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, pp.209-218, 2010 (Released:2017-05-10)
本稿の目的はバタイユの「至高性」の「瞬間」の概念をデリダのフッサール批判から考察することにある。議論は以下の手順でなされる。まず、「1」において、バタイユの「至高性」の概念を明確にするために、デリダのフッサール批判を考慮する必要の確認。「2」において、フッサールの「今」概念、および、それに対するデリダの批判を素描。とりわけ「今」には「差延」からなる記号作用があるゆえ「今」は決して捉えられない、というデリダの批判を確認。「3」において、われわれの世界には記号作用には含まれないものがあることを考察。「4」において、「差延」のさまざまな性質を把握。続いて、上記の性質とバタイユの「至高性」の「瞬間」を比較し「至高性」が記号作用では捉えられないものであることを考察。こうして、フッサール、デリダが議論の対象とした「今」と「至高性」の「瞬間」の概念を結びつける。そして「5」において、「今」と「至高性」の「瞬間」の概念的つながりをより考究するための今後の課題を検討する。
1 0 0 0 実用建設名鑑
- 著者
- 日刊建設通信社出版部 編
- 出版者
- 日刊建設通信社
- 巻号頁・発行日
- vol.1967年版, 1966
- 著者
- 末延 岑生
- 出版者
- 兵庫県立大学神戸商科キャンパス学術研究会
- 雑誌
- 人文論集 = Journal of cultural science (ISSN:04541081)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, pp.103-133, 2022-03-14
1 0 0 0 OA 琉球の創造力(五)ー泡盛の創造と泡盛文化考ー
- 著者
- 比嘉 佑典
- 出版者
- アジア・アフリカ文化研究所
- 雑誌
- アジア・アフリカ文化研究所研究年報 = Annual Journal of the Asia-Africa Cultures Research Institute (ISSN:02883325)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, pp.38-59, 2001
55ページに57と誤植あり。
1 0 0 0 アサガオ江戸の贈りもの : 夢から科学へ
1 0 0 0 OA ゼネラル・エレクトリック社の経営者群像:1892-1913
- 著者
- 谷口 明丈
- 出版者
- 中央大学商学研究会
- 雑誌
- 商学論纂 (ISSN:02867702)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.1・2, pp.171-281, 2015-09-15
- 著者
- 末延 岑生 Mineo SUENOBU
- 出版者
- 神戸芸術工科大学
- 雑誌
- 芸術工学2012
- 巻号頁・発行日
- 2012-11-30
本稿では「ニホン英語(Open Japanese― OJ)」の形態論上の類型化を試みた。ニホン英語はこの一世紀の間に、日本人の手で従来の英米英語を日本文化・母語と照合させ、自由に取捨選択し変形しながら、現在ほぼすべての日本人が、好むと好まざるに拘らず使っている英語である。今回の類型化分析の過程から得られたニホン英語の特徴、アジア英語の特徴とは次の5つである。(1)母語(踏襲)化によって英語の中に母語の伝統を復活させ、個性化することでニホン英語に誇りを持たせた。(2)英米英語を拡大解釈化することでことばの規制を緩和し、使いやすくした。(3)簡素化で無駄な飾りを取り払い、すっきりしたデザインにした。(4)置き換え化でより理解を明快にした。(5)入念化で英語がより丁寧・親切化され、英語をよりユニバーサル・デザインに近づける言語へと磨き上げてきた。ところが日本の英語教育界は「ニホン英語」を「誤文」とみなし、完璧なアメリカ英語以外を認めない。しかし、本稿で分析した誤文1,413文のうち、1,279の文(94.7%)が冠詞やsといった些細な規範文法のズレであり、推理すれば意味が取れることが判明した。これは筆者がすでに「ニホン英語は78%以上の高率で理解される」ことを実証した(Suenobu 1988)が、それを超える確率となった。
1 0 0 0 OA Open Japanese(ニホン英語)をデザインする
- 著者
- 末延 岑生 Mineo SUENOBU
- 出版者
- 神戸芸術工科大学
- 雑誌
- 芸術工学2011
- 巻号頁・発行日
- 2011-11-30
人間は本来、親から自然にことばを教わる。母語の学習に失敗した人がほとんどいないのは、ことばは猿人から人類に至る歴史の中で醸造され培われてきたもので、遺伝子の一部として生まれつきその能力がそなわっており、親がそれをうまく引き出しているからだ。だから環境に合わせてデザインすれば、外国語であっても必ずできる。たとえば、奈良時代に中国大陸から入ってきた複雑な漢字文字は、平安時代の人々がうまく日本語に溶け込ませながら、思い切ったシンプルなデザインとして「ひらかな」「カタカナ」を生みだした。この便利さは今も本場の中国人たちをも羨ませる。では日本の英語教育はどうか。歴史ある日本文化と日本語を土台としながら工夫しデザインすれば、誰でもある程度はできるというのに、逆に多くの学習者たちの英語離れを生んできた。その原因は何か。本論文はこのような英語教育の状況を「世界諸英語」という視点から、さらに学生とともに授業現場の中でつぶさに分析した上で、日本人の母語である日本語と英語の接点を探りつつ、日本人にやさしい、世界に開かれた第二の母語としての日本語、すなわちOpen Japanese をデザインしようと試みるものである。
1 0 0 0 OA ニホン英語(Open Japanese)の類型化研究(語順編)
- 著者
- 末延 岑生 Mineo Suenobu 兵庫県立大学 University of Hyogo
- 雑誌
- 人文論集 = Journal of cultural science (ISSN:04541081)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, pp.93-120, 2013-03-27
1 0 0 0 OA ニホン英語(Open Japanese)の類型化研究 : 音声編
- 著者
- 末延 岑生 Mineo Suenobu 兵庫県立大学 University of Hyogo
- 雑誌
- 人文論集 = Journal of cultural science (ISSN:04541081)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, pp.127-159, 2014-03-25