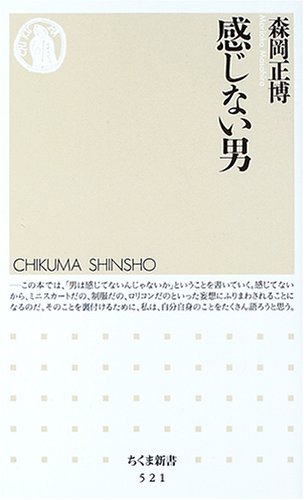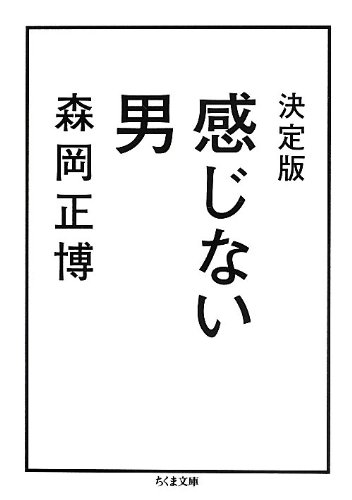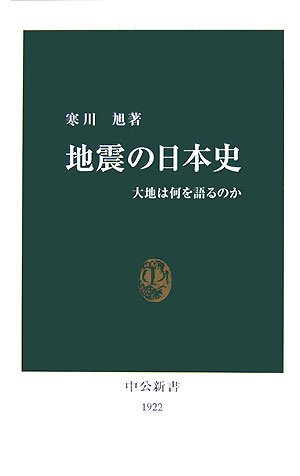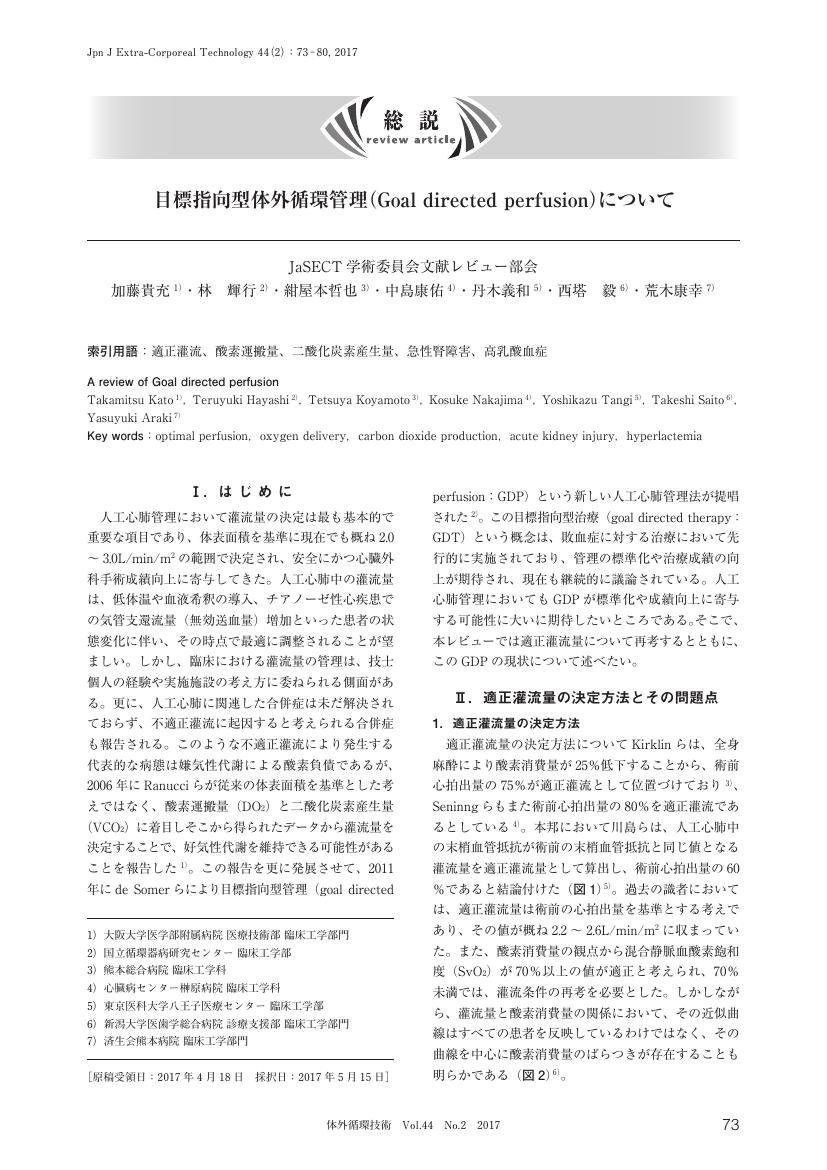1 0 0 0 OA 抗加齢医学の過去、現在、そして未来(総論)
- 著者
- 川北 哲也 坪田 一男
- 出版者
- 一般社団法人 日本総合健診医学会
- 雑誌
- 総合健診 (ISSN:13470086)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.2, pp.212-222, 2011 (Released:2013-08-01)
- 参考文献数
- 4
抗加齢医学(アンチエイジング医学)とは、加齢という生物学的プロセスに介入を行い、加齢に伴う動脈硬化や、がんのような加齢関連疾患の発症確率を下げ、健康長寿をめざす医学である。アンチエイジング医学が注目されてきた背景には、老化研究が進んだことにより老化が科学的に解明されはじめたことによる。 老化は避けられないものではなく、細胞生物学的なプロセスのひとつとであり、介入することにより遅らせることができる可能性があることがわかってきた。1980 年代までは、加齢のプロセスは非常に複雑で、とても介入など不可能であると考えられていた。現在でも加齢のメカニズムに関してはさまざまな説があるが、次第に研究や情報の整理により、徐々に加齢のメインメカニズムが解明されてきている。 現時点においては、酸化ストレスが老化のメカニズムに関わり、カロリーリストリクションにより介入できることは老化のサイエンスとして認識されてきている。 ヒトにおいては、カロリーリストリクションが寿命を延長するという確実なエビデンスはいまだ存在しないが、最近では、長寿の代謝マーカーとして低体温、低インシュリン血症、高DHEA-s 血症が、カロリーリストリクションをしたサルに認められたことが報告された。1)このカロリーリストリクションによる寿命延長には、Sir2/SirT1 というNAD 依存症ヒストン脱アセチル化酵素が重要な役割を果たしていることが明らかになってきた。運動に関しても、自発的な運動をさせたラットで約10%の寿命延長が観察されている。これらは、食事制限や適度な運動によって、老化過程で認められる動脈硬化などの病的現象が抑制される可能性を示している。 食事制限や適度な運動といった生活習慣の改善はヒトにおいても寿命を延長し、また健康にとってプラスになることが示唆されている。今後も老化に関するメカニズムが少しずつ明らかになり、ヒトの健康寿命の延長に貢献し、日本が健康大国となることを願ってやまない。
1 0 0 0 OA サラリーマンのワークライフバランス ―その影響要因と階層構造―
- 著者
- 神原 理
- 出版者
- 公益財団法人 年金シニアプラン総合研究機構
- 雑誌
- 年金研究 (ISSN:2189969X)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, pp.3-26, 2022-03-31 (Released:2022-03-31)
- 参考文献数
- 5
本稿では、サラリーマンのワークライフバランスに焦点をあて、その影響要因(因果関係)と構造、及び、そこから導き出される課題を明らかにした。因子分析の結果、ワークライフバランスに影響を及ぼす主要因は、「就労環境」や「積極的な生活姿勢」であり、特に「仕事への満足度」が重要な存在であることが明らかになった。クラスター分析からは、「Clu01.低バランス層(30-40 代、未婚率が高く、世帯収入と金融資産が少ない)」「Clu02. 中バランス層(Clu01.とClu03.の中間値にある層)」「Clu03.高バランス層(50-70 代、既婚率が高く、世帯収入と金融資産が多い)」という3 層構造の存在が浮き彫りとなった。 サラリーマンの間で「ワークライフバランスの階層化」が生じている。
1 0 0 0 OA 棄却検定法について
- 著者
- 小嶋 迪孝
- 出版者
- 北陸大学
- 雑誌
- 北陸大学紀要 = Bulletin of Hokuriku University (ISSN:0387074X)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, pp.53-61, 1998-12-31
1 0 0 0 OA 外れ値を検出する方法の特徴比較
- 著者
- 青木 勇太 松田 眞一
- 雑誌
- アカデミア. 理工学編 : 南山大学紀要 = Academia. Sciences and engineering : journal of the Nanzan Academic Society (ISSN:24344125)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, pp.60-76, 2021-03
1 0 0 0 沖縄救らいの歩み : 沖縄愛楽園開園25周年記念誌
- 出版者
- 沖縄らい予防協会
- 巻号頁・発行日
- 1963
1 0 0 0 培養神経細胞の生存と発育分化に及ぼす高濃度カリウムの効果の分析
高濃度カリウム培養液が培養初期の脊髓神経節細胞の生存率を著しく上昇させることが報告されている. しかし, その他の種類の神経細胞についての報告, ならびに長期培養による発育分化に対する影響についての報告は殆んど見られない. そこで本研究ではニワトリ胚の脊髓神経節と交感神経節, ならびに脊髓の神経細胞を培養し, 高濃度カリウムの効果について検討を加え次のような結果を得た.1.高濃度カリウム培養液は脊髓神経節のみならず, 交感神経節の神経細胞の生存率を著しく上昇させた. しかし, 脊髓の神経細胞の生存率の上昇は見られなかった.2.高濃度カリウム培養液は脊髓神経節細胞の分化を抑制した. 交感神経節細胞ではコリン作動性への転換を抑制し, アドレナリン作動性を保持した.3.上記2.の効果はカルシウム拮抗薬であるマグネシウム, ジルチアゼムで抑制されたので, カルシウムが関与しているものと考えられる.4.対照培養液下で交感神経節細胞を脊髓と併置して培養した場合にも, 交感神経節細胞のアドレナリン作動性が保持されることが判明した.5.高濃度カリウム培養液下では脊髓神経節と交感神経節の神経細胞の生存率が上昇するので, これまで困難であった培養初期の遊離単独神経細胞の動態を微速度映画に撮影して分析することが容易となった.6.分離培養脊髓神経節細胞に細胞内可溶性蛋白を除去後, 急速凍結・ディープエッチング法の適用を試みた結果, 細胞骨格, 細胞小器官の三次元的微細構造を詳細に観察することが可能となった. 高濃度カリウム培養液下では微小管とニューロフィラメントによる束状構造が著明となり, 小胞体から多数の輸送小胞が形成されている像が観察され, 細胞内活動の増加を示唆する所見が得られた.
1 0 0 0 地震の日本史 : 大地は何を語るのか
1 0 0 0 OA 解釈レベル理論を用いた消費者行動研究の系譜と課題
- 著者
- 外川 拓 八島 明朗
- 出版者
- 日本消費者行動研究学会
- 雑誌
- 消費者行動研究 (ISSN:13469851)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, no.2, pp.2_65-2_94, 2014 (Released:2018-08-31)
- 参考文献数
- 64
近年の消費者行動研究においては、解釈レベル理論の導入が盛んに進められている。しかしながら、各研究は個別的に行われており、全体を体系づけた研究は行われていない。そこで本研究では、マーケティングおよび消費者行動研究関連のジャーナルを対象としたレビューを行うことにより、既存研究における知見の整理と体系化を図った。既存研究を4つのグループに分類しレビューした結果、研究の進展に伴い、解釈レベル単独の効果に注目した研究から他の理論を取り入れた研究へと潮流が変化していることや、消費者行動研究において解釈レベル理論の位置づけが変化していることなどが明らかになった。最後に、レビュー結果を踏まえ、消費者行動研究において解釈レベル理論を導入することの意義と課題について議論を行った。
1 0 0 0 OA 目標指向型体外循環管理(Goal directed perfusion)について
1 0 0 0 OA 乳幼児の耳鼻咽喉科疾患
- 著者
- 笠井 美里
- 出版者
- 順天堂医学会
- 雑誌
- 順天堂医学 (ISSN:00226769)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.1, pp.24-28, 2010-02-28 (Released:2014-11-21)
- 参考文献数
- 16
耳鼻咽喉科の開業医が見ている小児患者は平均で30%, 多い施設では50%です. 免疫獲得中の小児には感染性の耳疾患・鼻疾患・上気道炎が頻発します. 小児耳鼻咽喉科領域で近年問題になっていることは耐性菌による急性中耳炎の増加・滲出性中耳炎の増加と遷延化アレルギー性鼻炎の増加と低年齢化, 睡眠時無呼吸症候群の増加などが挙げられます. 一方, 小児耳鼻咽喉科領域の治療の進歩としては内視鏡手術の進歩による気道異物や鼻副鼻腔手術の技術向上, 人工内耳の進歩, 難聴遺伝子の解明などが挙げられます. 少子化の傾向は進んでおりますが, 周産期医学の進歩により以前は致死的であった病態も救命できるようになりました. 小児の成長に際し重要な意味を持つ聴覚や呼吸機能に障害をもつ小児の増加が予想されます. 本項では耳鼻咽喉科を受診する患児に多い疾患の診断と治療, 最近の知見について述べます.
1 0 0 0 OA 睡眠時無呼吸症候群(SAS)と子どもの発達の問題
- 著者
- 加藤 久美
- 出版者
- 日本小児耳鼻咽喉科学会
- 雑誌
- 小児耳鼻咽喉科 (ISSN:09195858)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.3, pp.209-215, 2010 (Released:2012-12-28)
- 参考文献数
- 8
- 被引用文献数
- 1
小児の閉塞性睡眠時無呼吸症候群(OSAS)は成人と異なり,眠気よりも学力低下や,多動性・攻撃性などの注意欠陥/多動性障害(AD/HD)様の認知・行動面の問題が生じやすく,発達に影響を及ぼすとされているが,そのメカニズムはまだ明らかではない。脳に器質的な影響を及ぼすとの報告,全例ではないが OSAS 治療後に落ち着きや集中力などが改善することより,小児 OSAS に対する早期介入が重要であると考えられる。小児睡眠診療では AD/HD,広汎性発達障害(PDD)の発達障害を持つ児の受診が多く,未診断のケースも少なくない。小児睡眠診療を行う上では,発達面に留意して診療を行い,保護者の困り感や,脳波所見など気になる所見がある場合に,小児科や児童精神科,療育センターなどにコンサルテーションできる体制を整えておくべきである。小児 OSAS では,発達面を含めた長期視野でのフォローが重要である。
1 0 0 0 OA 少年団日本連盟の練習船と少年たち 第二次世界大戦前夜における海洋教育
- 著者
- 圓入 智仁
- 出版者
- 日本野外教育学会
- 雑誌
- 野外教育研究 (ISSN:13439634)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, no.1, pp.49-59, 2003 (Released:2010-10-21)
- 参考文献数
- 53
The aims of this research are to examine the activities of the Sea Scouts just before World War II, and consider the reaction of the Scouts who participated in these activities. In this research, the following three topics are taken up as concrete examples of sea activities where the Scouts who got in the training ship, which the Boy Scouts of Nippon got from Hokkaido Imperial University.First, the participation in the naval reviews held in 1927 and the following year. Second, the boarding to the training ship by H. M. the Emperor Showa in May, 1930. Third, the long voyage to Southeast Asia between July and November, 1934. These activities must have had big influence on the Scouts. Since this research took up these Sea Scouts activities just before World War II as case studies in outdoor educational research, it did not dare have touched on the political intention or ideology by the adults in these activities. Rather, I have forcused on showing clearly the historical facts, what the Scouts had been experienced through such activities. The historical record which I mainly used is the bulletin “Shonendan Kenkyu” which Shonendan Nihonrenmei, the Boy Scouts of Nippon, had published every month.