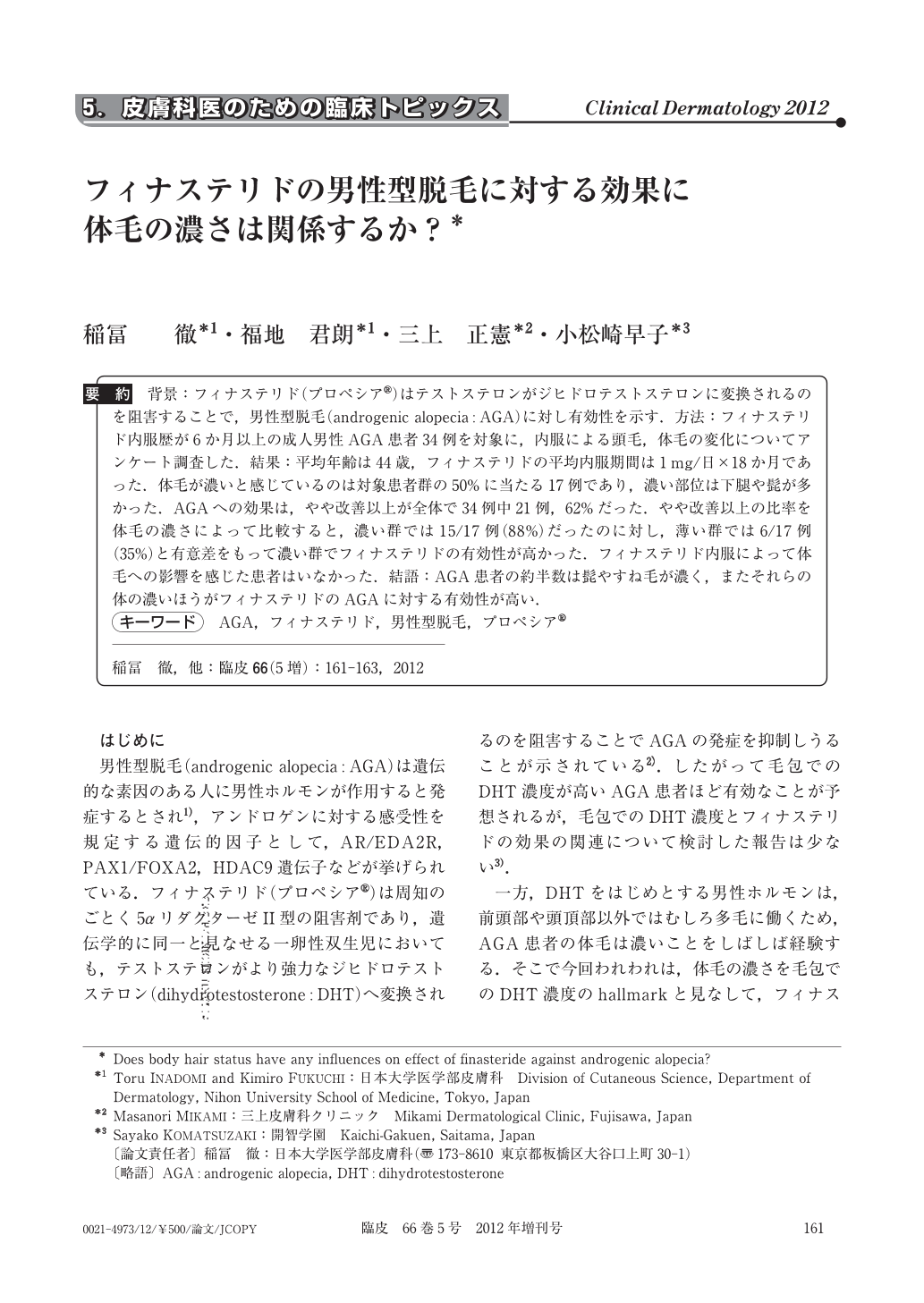1 0 0 0 OA 劣化映画フィルムから析出した白色固体の分析 -ビネガーシンドロームの化学的検証(1)
- 著者
- 高橋 圭子 早川 大 岡本 智寛 藤原 章司 矢島 仁 Keiko Takahashi Hiroshi Hayakawa Tomohiro Okamoto Shoji Fujiwara Hitoshi Yajima 東京工芸大学工学部生命環境化学科/ナノ化学科教授 東京工芸大学大学院工学研究科工業化学専攻博士前期課程 東京工芸大学工学部生命環境化学科学部4年生 東京工芸大学工学部工学研究科工業化学専攻博士後期課程 東京工芸大学芸術学部映像学科准教授
- 雑誌
- 東京工芸大学工学部紀要 = The Academic Reports, the Faculty of Engineering, Tokyo Polytechnic University (ISSN:03876055)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.1, pp.27-33, 2013
- 著者
- 下川 公博 手塚 大輔 鹿田 慧 邑瀬 邦明 杉村 博之 粟倉 泰弘
- 出版者
- 一般社団法人 資源・素材学会
- 雑誌
- Journal of MMIJ : journal of the Mining and Materials Processing Institute of Japan (ISSN:18816118)
- 巻号頁・発行日
- vol.129, no.2, pp.72-77, 2013-02-01
- 参考文献数
- 28
- 被引用文献数
- 4
The surface smoothness, S and Ag content of electrodeposited copper were investigated to clarify the influence of chloride ions on electrorefining using hydrochloric acid and SbCl<SUB>3</SUB>. The surface smoothness of electrodeposited copper was improved with increasing amounts of hydrochloric acid and SbCl<SUB>3</SUB> as well as lower S and Ag content. The tensile strength and elongation of the electrodeposited copper were also studied to determine if they could be used as criteria for evaluating the cathode strippability in the permanent cathode process. The tensile strength and elongation increased when the total concentration of chloride ions released from hydrochloric acid and SbCl<SUB>3</SUB> was 20 mg/L. Metallographic observations indicated that lower rate of twin crystal formation resulted in higher tensile strength and elongation at approximately 20 mg/L of chloride ion concentration.
1 0 0 0 佐賀関製錬所における自溶炉リニューアルと生産性向上
- 著者
- 安田 豊 千田 裕史 本村 竜也
- 出版者
- 一般社団法人 資源・素材学会
- 雑誌
- 資源・素材学会誌 (ISSN:18816118)
- 巻号頁・発行日
- vol.136, no.8, pp.88-98, 2020
- 被引用文献数
- 3
<p>Flash smelting furnace at Saganoseki was build 1973 and its capacity increased to 3.5 times the original during 40 years. The degradation progressed in that process, so it was replaced to higher potential furnace in the long-term shutdown at 2017 for further capacity improvement. In addition, gas treatment facility for FSF off gas and other related facilities were modified in order to accommodate the increased FSF capacity. As a result, FSF capacity increased to 4 times the original after the long-term shutdown at 2019 and the competitiveness of Saganoseki smelter and refinery was improved.</p>
1 0 0 0 OA 知識科学 知識創造プロセスのモデリング
- 著者
- 中森 義輝
- 出版者
- 横断型基幹科学技術研究団体連合(横幹連合)
- 雑誌
- 横幹連合コンファレンス予稿集 第4回横幹連合コンファレンス
- 巻号頁・発行日
- pp.42, 2011 (Released:2012-03-14)
知識科学は問題解決型の学際的学問分野であって、知識創造プロセスのモデリングとその応用を中心として、知識マネジメント、技術マネジメント、知識発見、知識の総合と創造、イノベーション理論などの研究教育によって、より良い知識基盤社会の構築を目指している。本発表では、知識科学におけるいくつかの重要な概念(知識テクノロジー、知識マネジメント、知識発見、知識総合化、知識正当化、知識構成など)を振り返り、システム科学の視点から知識科学の再考を試み、開発中の知識構成システム論について紹介する。
1 0 0 0 IR 高次桁のカプレカ変換(2)数のループに現れる規則性
- 著者
- 平田 郁美
- 出版者
- 共愛学園前橋国際大学
- 雑誌
- 共愛学園前橋国際大学論集 = Maebashi Kyoai Gakuen College ronshu (ISSN:2187333X)
- 巻号頁・発行日
- no.15, pp.1-28, 2015
32桁を除く33桁までの整数についてカプレカ変換を実行し、到達点として得られる2558個の数のループの持つ規則性を調べた。すべてのループは、周期1(固定点、カプレカ数)、2,3,4,5,7,8または14に分類され、他の周期のループは現れない。すべてのループは周期ごとにいくつかの系列に分類され、系列ごとにただ一つの種となるループを持つ。種となるループの各要素に、いくつかの決まった桁数字を加えることによって、高次桁のループが生成され、系列を形成している。系列によっては、他の系列との間に親子関係がある。親系列の種となるループの各要素に特定の桁数字を加えることによって、子系列の種となるループが生成され、系列群を形成している。周期1のループは5つの系列群に、周期2のループは3つの系列群に分類される。
1 0 0 0 陰謀論者の「不安」 (特集 「陰謀論」の時代)
1 0 0 0 過疎問題の人口論的考察
- 著者
- 皆川 勇一
- 出版者
- 日本人口学会
- 雑誌
- 人口学研究 (ISSN:03868311)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, pp.25-35, 1989
1960年頃から,農山村および山村地域では,新規学卒者ならびに若者の激しい都市への流出,中高年層にまでおよぶ出稼ぎ,さらに,大量の挙家離村が生じ,その結果,地域人口および世帯の減少が顕著となった。これらの現象およびそれにともなう産業衰退ならびに農山村住民の生活困難が過疎問題である。この過疎の問題が認識され,過疎への対応策が取られてから20年を経た今日,過疎地域はどのような状況にあるか,過疎問題は改善されたと言えるだろうか。本稿ではこうした問題を人口学的側面から検討した。過疎白書にもとづき過疎地域の人口の動向をみると, 1960年代の急激な人口流出とくらべ,最近では,全体としての人口減少は鎮静化しつつある。1960年代のセンサス間人口減少率は10%をこえていたが, 1980〜85年間には3%台に低下し,各センサス間に10%以上の人口減少をみた市町村数も, 1965〜70年期の877から, 1980〜85年期には107に減少した。しかしながら,若年層の人口流出率は依然高い。その上,過去20年以上にわたる若年層の流出の必然的結果である人口老齢化にもとづく出生減と死亡率の上昇によって,過疎地域の人口減少率は今後ふたたび上昇することが将来推計によって明らかにされている。現在,過疎地域の最も深刻な問題は高齢者比率の急上昇である。過疎地域全体の65歳以上の人口の比率は, 1985年現在, 17%に達しており,今後の老齢化の進行も全国にくらべはるかに急速と推計される。この結果,過疎地域では,これから人口の自然減がさらに増大し,高齢者夫婦および高齢者の一人暮らしの世帯が急激に増加することになる。高齢化の進行は過疎地域の社会福祉問題を深刻化させるが,さらに今ひとつの問題は,'高齢化が地域経済の動向におよぼす影響の大きさである。1970年代には,地方経済のささやかな成長が生じたが,それを可能にした第一の主体的条件は,地元居住の中高年世代の多就業化であった。20代30代の若者の大量流出にもかかわらず,戦後農村部に留まりつづけた現在50歳以上層の多就業化こそが70年代の地方経済の拡大の一つの基礎条件であった。しかし,今後これらの就業者は引退ないし死亡し,地方の労働力の供給源は急速に萎縮せざるをえなくなる。とくに過疎地域ではこれは深刻な問題である。村おこし町づくりが様々な形で試みられるなかで,過疎地域の産業ならびに生活の再構成は,当面の地域政策に対し最大の難問を提起している。
1 0 0 0 OA サウナ入浴後急性肝不全とDICを併発した一症例
- 著者
- 吉村 良之介 貫野 徹 藤山 進 門奈 丈之 山本 祐夫 西平 守也 森田 次郎部衛
- 出版者
- 一般社団法人 日本肝臓学会
- 雑誌
- 肝臓 (ISSN:04514203)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, no.10, pp.1089-1093, 1979-10-25 (Released:2009-07-09)
- 参考文献数
- 19
- 被引用文献数
- 1
32歳の男性で大量飲酒後サウナに入浴し,血圧低下,意識障害と第II度の火傷のため入院した.入院後肝性昏睡IV度となり出血傾向が出現した.hematcrit値の上昇,白血球数増多,Transaminase値の著高,prealbuminの減少を認め,凝血学的検査では,血小板数,fibrinogenは著減し,FDP, SDPS testは陽性を呈した.血清遊離アミノ酸総量は正常人の約3倍に増加し,分画では,Glutamine, Phenylalanineなどは増加し,Valineは減少し,急性肝不全時に認められるアミノ酸パターンに類似した.死亡直後の肝組織像は肝小葉内にびまん性に肝細胞の好酸性凝固壊死な呈した.以上の点より,本症例の発生機序は,飲酒後のサウナ入浴が契機となり,脱水,血液濃縮と,末梢循環不全が相俟って,急性肝不全とDICを併発したと考えられた.
- 著者
- 井上 和彦
- 出版者
- 日本皮膚科学会
- 雑誌
- 日本皮膚科学会雑誌 (ISSN:0021499X)
- 巻号頁・発行日
- vol.88, no.8, pp.p499-507, 1978-07
1 0 0 0 如来蔵思想とは何か
- 著者
- 常盤 義伸
- 出版者
- 禅文化研究所
- 雑誌
- 禅文化研究所紀要 = Annual report of the Institute for Zen Studies (ISSN:02899604)
- 巻号頁・発行日
- no.35, pp.1-32, 2021-05
1 0 0 0 マヨネーズの流動学的研究, マヨネーズの粘弾性について
- 著者
- 辻 量平 杉原 奈津子 寺林 大史 森腰 恵 大下 裕夫 天岡 望 種村 廣巳
- 出版者
- 東海北陸理学療法学術大会
- 雑誌
- 東海北陸理学療法学術大会誌
- 巻号頁・発行日
- vol.28, 2012
<b>【目的】 </b>がん患者に対するリハビリテーション(以下リハ)は多くの施設で提供され、がん拠点病院や緩和ケア病床、ホスピスでの活動も活発である。当院のような施設基準を有さない民間病院であっても、がん拠点病院の指導を受けながら、がん緩和ケアについてより質の高い医療とケアを提供できるかを模索することは大変重要なことである。今回、術中に腹膜播種などが確認できバイパスのみとなった切除不能がん患者に対し、周術期リハチームの方から、緩和ケアチームに対し予後も含めた情報提供を行い、周術期リハチームと緩和ケアチームがともに早期介入ができ、良好なかたちで在宅へ移行できた症例を経験したので、当院の今後の方針も含めて報告する。なお、ご本人・ご家族に本件の主旨を口頭および当院所定の文書で説明し、署名による同意を得た上で病院長の許可も頂いた。<br><b>【方法】 </b>症例は86歳男性。入院1か月前に食欲不振、嘔吐で近医受診し、当院紹介され、胃前庭部癌と診断され手術となった。手術1週間前のカンファランスにて手術方針や告知状況など情報を共有した。術前リハビリにより患者とのコミュニケーションを図り、患者が早い時期に在宅への移行を希望していることを知った。開腹の結果、腹膜播種が確認できたため、胃切除不能、胃空腸吻合に終わった。予後は3~6ヶ月との情報を得た。手術翌日に緩和ケアチームの早期介入を依頼した。<br><b>【結果】 </b>緩和ケアチームの早期介入によって術後の苦痛緩和が図れ、周術期リハは効果的に進んだ。術後の食欲不振、摂食障害は緩和ケアチームの一員である管理栄養士による食事相談や内容変更により術後第14病日には全量摂取可能となった。患者からの在宅復帰への強い希望もあり周術期リハの実施と緩和ケアチームとの連携により、高齢でしかも切除不能胃癌患者の術後としては比較的早い術後26病日に退院できた。なお地域連携の看護師やMSWによって術後19病日から退院や退院後調整が行われた。<br><b>【考察】 </b>当院では平成22年11月より緩和ケアチームが発足し、医師、看護師、薬剤師、管理栄養士、MSW、訪問看護師、理学療法士、作業療法士で構成されている。このような施設は少なくなく、がん緩和医療への質の高いリハの需要は高まっている。今回、進行胃癌患者に対し、術前からのリハを通してコミュニケーションがとれたこと、周術期に手術情報、予後情報、その他の患者情報をがん緩和ケアに携わる他職種と理学療法士とで共有でき、余命短い本患者が求める在宅へという希望を実現するため、早い時期から多職種が同じベクトルでそれぞれの専門職としての役割を果たすことで、患者の希望である早期在宅へ誘導でき、ひいては患者のQOLに益したものと考えられる。このような進行がん患者をケアするにあたり、それぞれの専門職でのチーム医療がいかに重要であるか痛感させられた1症例である。今後も本症例での経験を生かし、がん治療の早期から多職種が情報を共有することで、患者のQOLを高める実績づくりを行っていきたい。
1 0 0 0 フィナステリドの男性型脱毛に対する効果に体毛の濃さは関係するか?
要約 背景:フィナステリド(プロペシア®)はテストステロンがジヒドロテストステロンに変換されるのを阻害することで,男性型脱毛(androgenic alopecia:AGA)に対し有効性を示す.方法:フィナステリド内服歴が6か月以上の成人男性AGA患者34例を対象に,内服による頭毛,体毛の変化についてアンケート調査した.結果:平均年齢は44歳,フィナステリドの平均内服期間は1mg/日×18か月であった.体毛が濃いと感じているのは対象患者群の50%に当たる17例であり,濃い部位は下腿や髭が多かった.AGAへの効果は,やや改善以上が全体で34例中21例,62%だった.やや改善以上の比率を体毛の濃さによって比較すると,濃い群では15/17例(88%)だったのに対し,薄い群では6/17例(35%)と有意差をもって濃い群でフィナステリドの有効性が高かった.フィナステリド内服によって体毛への影響を感じた患者はいなかった.結語:AGA患者の約半数は髭やすね毛が濃く,またそれらの体の濃いほうがフィナステリドのAGAに対する有効性が高い.
- 著者
- 松木 興一郎
- 出版者
- 産労総合研究所
- 雑誌
- 医療アドミニストレーター : 病院事務管理者のための病院経営情報誌
- 巻号頁・発行日
- vol.4, no.42, pp.18-24, 2013-09
- 著者
- 仙田 麻子
- 出版者
- 日本女子体育連盟
- 雑誌
- 女子体育 (ISSN:02889935)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, no.5, pp.31-33, 2001-05
1 0 0 0 日本タイプライター株式會社(竣功建築物)
1 0 0 0 OA シュウ酸製造技術の変遷
- 著者
- 板谷 博
- 出版者
- The Society of Synthetic Organic Chemistry, Japan
- 雑誌
- 有機合成化学協会誌 (ISSN:00379980)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, no.9, pp.891-896, 1985-09-01 (Released:2009-11-13)
- 参考文献数
- 8
- 被引用文献数
- 1 3
Oxalic acid is the simplest dicarboxylic acid formed by oxidation of organic compounds. Oxalic acid has been prepared by several methods in countries, because the industrial process depends on natural resouces, economical demands of the country, and chemical technology. This paper deals with its advantage and view points of each process ; oxidation of carbohyrates with nitric acid, thermal decomposition of sodium formate, two step oxidation of propylene, one step oxidation of ethyleneglycol, and the CO-coupling process, respectively.
1 0 0 0 口腔環境に及ぼす唾液の影響 : イグ・ノーベル賞受賞論文を中心に
- 著者
- 渡部 茂
- 出版者
- 日本アンチエイジング歯科学会
- 雑誌
- 華齢 : 日本アンチエイジング歯科学会誌 (ISSN:21863571)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, pp.41-45, 2020-11
1 0 0 0 OA 輸入食料・飼料の環境負荷を考慮した産業連関表によるCO2排出原単位の作成
- 著者
- 吉川 直樹 天野 耕二 島田 幸司
- 出版者
- 日本LCA学会
- 雑誌
- 日本LCA学会研究発表会講演要旨集 第4回日本LCA学会研究発表会(会場:北九州国際会議場)
- 巻号頁・発行日
- pp.9, 2008 (Released:2009-02-05)
食料・農業分野において,産業連関表による環境負荷排出原単位は,簡易的なLCAや積み上げ法とのハイブリッドLCAなどに用いられている.しかし,食料自給率の低い日本においては,輸入品と国産品との環境負荷の差異や,国内外の価格差により,原単位が実態と大きく乖離している可能性がある.本研究では,主要な輸入食料・飼料について,ハイブリッド法によるLCAを行った上で,輸入品の環境負荷を考慮した産業連関法による部門別のCO2排出原単位を作成した.その結果,畜産品において環境負荷の乖離が大きいことがわかった.また,食品加工・漁業・飲食業などの環境負荷への影響を定量的に明らかにした.
- 著者
- Masaaki UNO Kenji YAGI Hiroyuki TAKAI Naoki OYAMA Yoshiki YAGITA Keita HAZAMA Hideki NAKATSUKA Shunji MATSUBARA
- 出版者
- The Japan Neurosurgical Society
- 雑誌
- Neurologia medico-chirurgica (ISSN:04708105)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, no.2, pp.124-133, 2021 (Released:2021-02-15)
- 参考文献数
- 35
- 被引用文献数
- 4
We compared the rate of selective shunt and pattern of monitoring change between single and dual monitoring in patients undergoing carotid endarterectomy (CEA). A total of 121 patients underwent 128 consecutive CEA procedures. Excluding five procedures using internal shunts in a premeditated manner, we classified patients according to the monitoring: Group A (n = 72), patients with single somatosensory evoked potential (SSEP) monitoring; and Group B (n = 51), patients with dual SSEP and motor evoked potential (MEP). Among the 123 CEAs, an internal shunt was inserted in 12 procedures (9.8%) due to significant changes in monitoring (Group A 5.6%, Group B 15.7%, p = 0.07). The rate of shunt use was significantly higher in patients with the absence of contralateral proximal anterior cerebral artery (A1) on magnetic resonance angiography (MRA) than in patients with other types of MRA (p <0.001). Significant monitor changes were seen in 16 (12.5%) in both groups. In four of nine patients in Group B, SSEP and MEP changes were synchronized, and in the remaining five patients, a time lag was evident between SSEP and MEP changes. In conclusion, the rate of internal shunt use tended to be more frequent in patients with dual monitoring than in patients with single SSEP monitoring, but the difference was not significant. Contralateral A1 absence may predict the need for a shunt and care should be taken to monitor changes throughout the entire CEA procedure. Use of dual monitoring can capture ischemic changes due to the complementary relationship, and may reduce the rate of false-negative monitor changes during CEA.