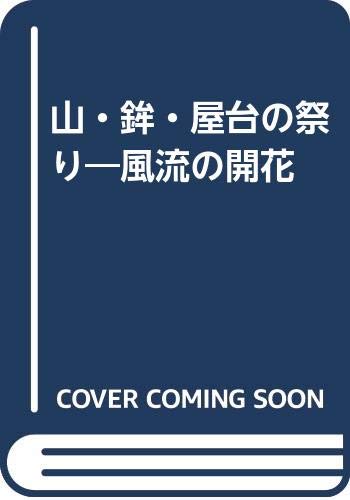2 0 0 0 OA ガレット・エクボの初期作品にみる形態の暖昧性
- 著者
- 村上 修一
- 出版者
- 社団法人日本造園学会
- 雑誌
- ランドスケープ研究 : 日本造園学会誌 : journal of the Japanese Institute of Landscape Architecture (ISSN:13408984)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.3, pp.238-245, 2003-01-31
- 被引用文献数
- 1
近代の空間成果として注目すべき形態の多重解釈性(暖昧性)という観点から検証すべく、ガレット・エクボ(1910-2000)の初期4事例の図面を調査し分析考察を行った。その結果、樹木列植による囲みを単位空間として、列植の隙間・延長の交差・ずれという空間構造や高木列植の視線透過性による暖昧性が明らかになった。また、その空間構造によって視点移動にともなう空間変化が顕在化することが明らかになった。これらの結果は、近代の空間成果としての暖昧性が、エクボの初期作品に共有されことを示し、成果がいかに空間化されたかを示す。
2 0 0 0 第16回日本助産学会学術集会集録一般演題 (口演)(その2)
- 著者
- 塩谷 由美子 長安 幸子 高室 典子 西田 令子 山本 令子
- 出版者
- Japan Academy of Midwifery
- 雑誌
- 日本助産学会誌 (ISSN:09176357)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.3, pp.122-127, 2001
2 0 0 0 OA ロシアの「タンゴ狂」
- 著者
- 吉田 文憲
- 出版者
- 思潮社
- 雑誌
- 現代詩手帖 (ISSN:13425544)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, no.3, pp.150-156, 2000-03
- 著者
- 高橋 由桂
- 出版者
- 教育出版センタ-
- 雑誌
- 解釈 (ISSN:04496361)
- 巻号頁・発行日
- vol.47, no.7, pp.30-37, 2001-07
- 著者
- 田中 実
- 出版者
- 日本文学協会
- 雑誌
- 日本文学 (ISSN:03869903)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.2, pp.32-42, 2010-02-10
童話集『注文の多い料理店』の「序」文には、「わたくしは、これらのちいさいものがたりの幾きれかが、おしまひ、あなたのすきとほつたほんたうのたべものになることを、どんなにねがふかわかりません。」とある。この童話はその願いを実現しようとしたもの、それにはこの作品のパースペクティブを日常的遠近法で読むのでなく、その向こう、永劫の虚無を定点にして読まれなければならない。そのためには大森哲学の「知覚されたものがその人にとっての真実」であるという知見に立つ必要がある。この童話集がそれを要求しているというのが、私見である。また童話にもジャンル論が必要で、物語童話と小説童話とが峻別されなければならない。この作品は後者、プロットの末尾は作品の末尾ではない。深層批評が求められ、そこは絶対的なものの前で全てが相対の海に化すべく<仕掛け>られているのである。
2 0 0 0 IR 玄界灘を渡った川上音二郎
- 著者
- 李 応寿
- 出版者
- 学術雑誌目次速報データベース由来
- 雑誌
- 日本研究 : 国際日本文化研究センター紀要 (ISSN:09150900)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, pp.49-67,v, 2001
川上音二郎(一八六四~一九一一)の新派の活動については、四回にわたる洋行と、それに伴う西洋の新技法の取り入れが、広く知られている。しかし、実のところ、川上音二郎は、西洋にばかり交流を求めていたのではない。日清戦争の最中の一八九四年の一〇月、彼は玄界灘を渡り、戦場の韓半島(朝鮮半島)で取材をし、添えを自分の演劇に反映している。 『壮絶快絶日清戦争』に続く『川上音二郎戦地見聞日記』がそれで、彼は、韓半島で蒐集した資料をもとに、写実的な演技を披露し、爆発的な人気を集めた。そしてその裏には、韓国人俳優丁無南の役割も大きかった。新聞に、彼の演技を眼目にして客を呼んだと報道されたほどである。 なお、川上の韓国観は、一九一〇年の一〇月、大阪の帝国座で上演された『新国王』からうかがい知ることができる。検閲を受ける前の題目が『朝鮮王』であったこの戯曲は、マイアー・フェルスター(Wilhelm Meyer Förster)の『アルト・ハイデルベルク(Alt Heidelberg)』を翻案したもので、書き手は巌谷小波(一八七〇~一九三三)、舞台の背景は朝鮮王宮と京都、内容は、日本に留学した朝鮮の王子と日本の料理屋の下女との悲恋の恋物語である。 しかし、原作に比べ、この作品には、王子の留学目的が意図的に強調されていた。それはおそらく、時のイベントであった英親王李垠(一八九七~一九七〇)の日本留学をそのまま反映したためであり、ひいては、日頃の川上の支援者であった亡き伊藤博文に対する鎮魂の意味を持たせていたためでもあったように思われる。
2 0 0 0 OA 世紀末ウィーンとウィトゲンシュタイン
- 著者
- 岡田 雅勝
- 出版者
- 北海道大学哲学会
- 雑誌
- 哲学 (ISSN:02872560)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, pp.57-72, 2003-07-20
2 0 0 0 石田和康×藤沢久美 サウジアラビア視察ツアー 緊急リポート
- 著者
- 石田 和康 藤沢 久美
- 出版者
- 日経BP社
- 雑誌
- 日経マネー (ISSN:09119361)
- 巻号頁・発行日
- no.334, pp.146-148, 2010-09
石田 サウジアラビアは「眠れる巨人」と呼ばれている国です。ポテンシャルは大きいけれど、外国資本に対する様々な規制があって、経済成長の足かせになっていた。それが、新国王の開放政策によって、急速にグローバル化しつつあるんです。中東の友人たちは、「いよいよ巨人が目覚める」と大騒ぎしていますよ。
- 著者
- 前田 宜包 樫本 温 平山 雄一 山本 信二 伊藤 誠司 今野 述
- 出版者
- Japanese Association for Acute Medicine
- 雑誌
- 日本救急医学会雑誌 (ISSN:0915924X)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.4, pp.198-204, 2010
症例は56歳,男性。単独で登山中,富士山8合目(海抜3,100m)で突然昏倒した。居合わせた外国人医師が救助に当たるとともに同行者が8合目救護所に通報した。自動体外式除細動装置(automated external defibrillator; AED)を持って出発し,昏倒から30分後胸骨圧迫を受けている傷病者と接触した。AEDを装着したところ適応があり,除細動を施行した。まもなく呼吸開始,脈を触知した。呼吸循環が安定したところでキャタピラ付搬送車(クローラー)で下山を開始。5合目で救急車とドッキングし,約2時間後山梨赤十字病院に到着した。第1病日に施行した心臓カテーテル検査で前下行枝の完全閉塞,右冠動脈からの側副血行路による灌流を認めた。低体温療法を施行せずに第1病日に意識レベルJCS I-1まで回復し,とくに神経学的後遺症なく4日後に退院となった。富士山吉田口登山道では7合目,8合目に救護所があるが,2007年から全山小屋にAEDを装備し,山小屋従業員に対してBLS講習会を施行している。今回の事例はこれらの取り組みの成果であり,healthcare providerに対するBLS・AED教育の重要性が再確認された。
- 著者
- 黒澤 昌洋
- 出版者
- メディカ出版
- 雑誌
- Emergency care = エマージェンシー・ケア : 日本救急看護学会準機関誌 (ISSN:13496557)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, no.9, pp.963-967, 2014-09
2 0 0 0 IR ふたつの"北の大地"で情報リテラシー教育を考える (特集 海外に目を向ける)
- 著者
- 千葉 浩之
- 出版者
- 大学図書館問題研究会
- 雑誌
- 大学の図書館 (ISSN:02866854)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, no.3, pp.34-38, 2015-03
2 0 0 0 IR 形式のショーケース : マルチ視点ミステリー・湊かなえ『告白』
- 著者
- 松本 和也
- 出版者
- 信州大学人文学部人文学科松本和也研究室
- 雑誌
- ゲストハウス
- 巻号頁・発行日
- pp.14-25, 2013-12-25
2 0 0 0 IR 日本における「組織行動」研究の現状と課題 : ひとつの覚えがき
- 著者
- 南 隆男
- 出版者
- 慶應義塾大学産業研究所
- 雑誌
- 組織行動研究
- 巻号頁・発行日
- no.4, pp.3-15, 1979-03
慶應義塾大学産業研究所社会心理学研究班モノグラフ ; No. 81,はじめに一社会心理学のフロンティアーとしての「組織心理学」一シェイン(EH・Schein)のOrganizational Psychologyがわが国で翻訳・出版されたのは, 原著刊行の1年後,1966年のことであった。この翻訳・出版が契機となって, 「組織心理学」の名称が社会心理学の一領域の呼称として, わが国にも次第に定着してきたといえ.る。ところで同著の最大の眼目は, 「組織内での人間の行動の決定因に関するあらゆる問題は, 全体的な社会体系という視野から考xなければならない」(松井訳,1966,P・4)という視点の強調にあった。すなわちシェインは, 「開放体系」(open system)の枠組から組織を捉え直し, 在来, 産業心理学(industrialpsychology), 産業人事心理学(industrial personnelpsychology), 産業社会心理学 (industrialsocial psychology)の名称のもとに追求されてきた組織における人間行動諸側面の研究を統合化していくことの必要性を主張したのであった。
- 著者
- 梅澤 貴典
- 出版者
- 私立大学図書館協会西地区部会東海地区協議会
- 雑誌
- 館灯 (ISSN:03873919)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, pp.14-33, 2015
2 0 0 0 山・鉾・屋台の祭り : 風流の開花
2 0 0 0 OA 日本の小学生の英語コミュニケーション能力を養う:マニフェストと事実
- 著者
- ANTHONY Gregory C.
- 雑誌
- 八戸学院大学紀要 (ISSN:21878102)
- 巻号頁・発行日
- no.50, pp.11-29, 2015-03-31
日本の歴史上初めて、20011年4月から、公立小学校の必修科目 として英語教育が導入された。この目的はコミュニティーケーション能力を養うことであるが、現場の教員のアンケートを分析すると、明らかにこの目標の実現を妨げる障害物の数がたくさんあることに気づく。多様なクラス目標の解釈、あまり効果のなさそうな指導方法、教員の英語力、限られた授業時間などの課題がある。ここでは、これらの問題と向き合い、より良い方法を提案し解決する。
- 著者
- 野嶋 新斗 石井 一洋
- 出版者
- 一般社団法人日本機械学会
- 雑誌
- 日本機械学会関東支部総会講演会講演論文集
- 巻号頁・発行日
- vol.2015, no.21, pp."10907-1"-"10907-2", 2015-03-20
In this study, operating conditions of a rotating detonation engine with internal mixing has been studied. Hydrogen and oxygen are supplied separately from gas storage tanks and mixed in an annular combustion chamber. The mixture is initiated by a spark discharge placed at the chamber wall surface. As a result, a strong deflagration after ignition is initially generated in the combustion chamber. The experimental results show that the following stages are involved to achieve stable propagation of the rotating detonation : i) a deflagration wave moves to the downstream, ii) a DDT process occurs in the downstream, iii) a detonation wave propagates in the upstream direction, iv) a rotating detonation is stabilized in the combustion chamber.
2 0 0 0 OA お月さまいくつ : 理科小話
- 著者
- 上條 剛志
- 出版者
- へるす出版
- 雑誌
- 救急医学 = The Japanese journal of acute medicine (ISSN:03858162)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.7, pp.826-831, 2013-07