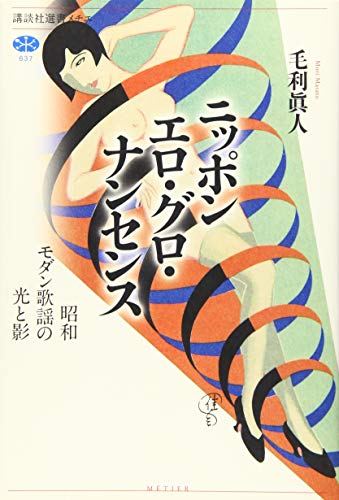2 0 0 0 IR 『イパーチイ年代記』翻訳と注釈(1)『原初年代記』への追加記事(1110~1117年)
- 著者
- 中沢 敦夫
- 出版者
- 富山大学人文学部
- 雑誌
- 富山大学人文学部紀要 (ISSN:03865975)
- 巻号頁・発行日
- no.61, pp.233-268, 2014
本稿から始まる連載で翻訳と注釈を試みるのは,キエフ・ルーシ史研究のもっとも基本的な史料である『イパーチイ年代記』(Ипатьевская летопись) の,『原初年代記』(Повестьвременных лет) 以降の部分,記事の年代から言うと,6618(1110)年から6800(1292)年に相当する部分で,ほぼ12~13 世紀をカバーしている。『イパーチイ年代記』は中世ロシアのほとんどの年代記(летописи)がそうであるように,様々な時期に成立した個々の歴史的・年代誌的な記録が,特定の段階でまとめられて編集され,それがさらに何度かの再編集を経ることで成立した「年代記集成」(летописный свод)である。本連載の第1回目では,『キエフ年代記集成』の翻訳に入る前に,『原初年代記』と『キエフ年代記集成』をつなぐかたちになっている,『イパーチイ年代記』の,6618(1110)~ 6625(1117)年の記事の翻訳と注釈を行う。この部分は,『原初年代記』の主要諸写本の共通部分から離れ,『イパーチイ年代記』だけに認められる記事であり,なおかつ,のちの『キエフ年代記集成』の編集とは別個に行われたとされている部分である。研究史上は,『イパーチイ年代記』だけに見られる『原初年代記』の追加編集記事と考えられている。
2 0 0 0 肛門疾患における画像診断 : 特に痔瘻に対する画像診断について
- 著者
- 辻 順行
- 雑誌
- 日本大腸肛門病学会雑誌 (ISSN:00471801)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.3, pp.194-202, 2001-03
- 参考文献数
- 20
2 0 0 0 OA 官報
- 著者
- 大蔵省印刷局 [編]
- 出版者
- 日本マイクロ写真
- 巻号頁・発行日
- vol.1944年08月07日, 1944-08-07
2 0 0 0 ニッポンエロ・グロ・ナンセンス : 昭和モダン歌謡の光と影
2 0 0 0 OA Web版農業経営診断サービスの特徴とユーザ評価
- 著者
- 大室 健治 佐藤 正衛 松本 浩一
- 出版者
- 日本経営診断学会
- 雑誌
- 日本経営診断学会論集 (ISSN:18824544)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, pp.112-118, 2015 (Released:2016-09-15)
- 参考文献数
- 15
本稿では,農研機構が開発した「Web版農業経営診断サービス」(以下,Webサービス)の特徴を詳述したうえで,Webサービスの試行版に対する利用者のユーザ評価結果を整理し,ユーザ要求に沿ったWebサービスの今後の改良方向を提示する。これまで,各種団体が農業経営診断ツールを開発してきているが,それらに共通する課題は,営農類型・規模などを考慮した標準値データベースを持たないため,診断対象の値と標準値との比較考量ができない点にあった。Webサービスは,農林水産省が保有する個票データの解析結果に基づく標準値データベースを内蔵しており,各診断指標についての標準値との比較,ならびに良好・不良などのランク判定が可能である。Webサービスの今後の改良方向は,外部診断者の業務内容に沿った対応,営農類型の特殊性を踏まえた診断手法の組込み,6次産業化などの多角的な農業経営への対応である。
2 0 0 0 二十世紀の社会学
- 著者
- ギュルヴィッチ=ムーア編集 東京社会科学研究所監修
- 出版者
- 誠信書房
2 0 0 0 <編集長インタビュ->花房正義氏(日立クレジット社長)自分で基準作り,自身で成長 バランス経営で「AA」実現 (1996年版 「こんな会社」がなぜ強い 市場が選ぶ新エクセレント100社)
- 著者
- 花房 正義
- 出版者
- 日経BP社
- 雑誌
- 日経ビジネス (ISSN:00290491)
- 巻号頁・発行日
- no.860, pp.42-45, 1996-10-07
バブルに踊らず格付けAAという金融界有数の優良企業に育てあげた。「理念を守る,過去に学ぶ」が市場からの評価につながったと説く。経営とは「理念と財務諸表の2つの中心をもつ楕円形」が持論。定期採用・年功序列・終身雇用を見直す人事改革にも着手。(聞き手は本誌編集長,永野健二)問日本興業銀行の経営陣の1人が「日立クレジットがうらやましい」と言っていました。
2 0 0 0 OA 大阪鉱山監督署管内鉱区一覧
- 出版者
- 大阪鉱山監督署
- 巻号頁・発行日
- vol.明治44年7月1日現在, 1911
- 著者
- 守山 久子
- 出版者
- 日経BP社
- 雑誌
- 日経アーキテクチュア (ISSN:03850870)
- 巻号頁・発行日
- no.840, pp.78-83, 2007-01-22
いろいろな人に配慮しつつ、魅力を備えたデザインとはどうあるべきか。今号から3回にわたって、田中直人・摂南大学教授がユニバーサルデザインに配慮した建物や施設を巡り、設計のポイントや使い勝手の実際について検証していく。第1回は、2005年2月3日に開業した福岡市地下鉄・七隈線を訪れた。 福岡市地下鉄・七隈線は、福岡市南西部と都心を結ぶ市内3番目の地下鉄として誕生した。
- 著者
- 鎌倉 智子 黒瀬 重幸
- 出版者
- 一般社団法人日本建築学会
- 雑誌
- 日本建築学会研究報告. 九州支部. 3, 計画系
- 巻号頁・発行日
- no.45, pp.381-384, 2006-03-01
2 0 0 0 OA アブノーマルグロー放電プラズマによるセラミックと金属の接合
- 著者
- Wang Yao-Wen Zhao Peng-Sheng Zhang Yong-Qing
- 出版者
- 公益社団法人日本セラミックス協会
- 雑誌
- 日本セラミックス協会学術論文誌 : Nippon Seramikkusu Kyokai gakujutsu ronbunshi (ISSN:18821022)
- 巻号頁・発行日
- vol.113, no.1318, pp.409-412, 2005-06-01
- 被引用文献数
- 1 2
A novel joining technique of ceramics to metals is presented, in which depositing Ti on ceramics with arc-added glow discharge is used as a prior metallizing technique and then brazing the ceramics to metals by abnormal glow discharge is carried out. The heating temperature of the base metals is easily controlled by varying the operating voltage and barometric pressure. The ions beam from the glow discharge anode is efficiently able to sputterclean the surfaces of the base materials, which thereby improves better Ti-deposited adhesion on the ceramics and the wetting and spreading properties of the filler metal. The thickness of the Ti-deposited layer is readily adjusted in terms of the actual requirement. The vacuum pressure during brazing can be up to 5Pa. The cost and duration of the glow discharge plasma brazing are reduced as compared with the traditional vacuum brazing process. The joining technique developed holds potential for industrial applications leading to high product quality.
- 著者
- 三村 高志 小林 和夫
- 出版者
- 一般社団法人照明学会
- 雑誌
- 照明学会誌 (ISSN:00192341)
- 巻号頁・発行日
- vol.90, no.4, pp.193-194, 2006-04-01
福岡市地下鉄3号線は,福岡市西南部地域の慢性的な交通渋滞の改善を図り,将来の交通需要の増大に対処するとともに,西南部地域における高速輸送サービスの普及および均衡あるまちづくりを推進することを目的に計画された.
- 著者
- 鈴木 重行
- 出版者
- 日本物理教育学会
- 雑誌
- 物理教育 (ISSN:03856992)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, no.5, pp.488-491, 2001
本校で,毎年(もう6年間も)行っている実験,知り尽くしているはずだった,頭の中では分かっていた。時間を節約できるつもりだった。忙しさにかまけて予備実験をせず,頭の中での実験だけで,こうなるだろうと思いこんでしまったためにやってしまった失敗を報告(懺悔)いたします。ひとつ間違えば,生徒の感電という事故につながったかもしれない。今考えるとぞっとする。実験道具を1セットは使いものにならなくしてしまった位ですんだのは,不幸中の幸い。やっぱり実験はやってみないと分からない。
2 0 0 0 OA 官報
- 著者
- 大蔵省印刷局 [編]
- 出版者
- 日本マイクロ写真
- 巻号頁・発行日
- vol.1893年02月17日, 1893-02-17
2 0 0 0 A (H1N1) pdm09の壱岐市における流行調査
- 著者
- 江田 邦夫 大田黒 滋 松嶋 喬 品川 敦彦 池松 秀之 柏木 征三郎
- 出版者
- The Japanese Association for Infectious Diseases
- 雑誌
- 感染症学雑誌 : 日本伝染病学会機関誌 : the journal of the Japanese Association for Infectious Diseases (ISSN:03875911)
- 巻号頁・発行日
- vol.86, no.3, pp.274-281, 2012-05-20
- 参考文献数
- 12
- 被引用文献数
- 3
長崎県壱岐市(人口約30,000 人の島)におけるA(H1N1)pdm09 の流行状況を調査した.流行は,2009 年8 月に始まり2010 年3 月に終ったが,流行が始まる以前より市医師会では対策委員会を立ち上げていた.流行開始後各医療機関ではインフルエンザと診断した患者について,その日のうちに保健所にFax で連絡した.保健所はその報告患者数を毎日集計し,流行状況により医師会は学校長及び教育委員会と協議し,学級・学年閉鎖,休園・休校を行った.本市での流行は,ピークが分散し2 峰性となったが,これらの措置が迅速かつ徹底して行われたためと考えられた. <BR> A(H1N1)pdm09 ウイルスの罹患者は2,024 例で全人口の6.6%であった.年齢群別の人口における罹患率は10~19 歳が最も高く849 例(26.8%),ついで0~9 歳の594 例(21.3%)で,19 歳以下が全罹患者の71.3%を占めた.60 歳以上の高齢者の罹患率はきわめて低かった.A(H1N1)pdm09 ウイルスの抗体保有状況をみるため,流行終息後の2010 年9 月21 日~11 月15 日までに一般住民358 例の採血を行い,A(H1N1)pdm 09 ウイルスのHI 価を測定した.HI 価≧1 : 40 は全体の57.3%で,7~49 歳までが約70%と高率であった.これらのHI 価≧1 : 40 の要因を検討したが,最も多いのはワクチン接種,次いでA(H1N1)pdm09 罹患で,不顕性感染は11.7%と低かった. <BR> 以上から,壱岐市でのA(H1N1)pdm09 の流行について, <BR> 1.罹患率は全人口の6.6%であった. <BR> 2.罹患者の71.3%は19 歳以下であり,高齢者の罹患率はきわめて低かった. <BR> 3.流行に対して学級・学年閉鎖,休園・休校が有効であり,2 峰性となった.
2 0 0 0 ミュー粒子による土木物理探査の可能性
- 著者
- 鈴木 敬一
- 出版者
- 社団法人 物理探査学会
- 雑誌
- 物理探査 (ISSN:09127984)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, no.4, pp.251-259, 2012-10-01
- 参考文献数
- 27
- 被引用文献数
- 1 3
社会インフラ施設の老朽化などにより,地盤内部に空洞が発生し,陥没事故などが発生している。場合によっては死傷者が出るなどの惨事になる場合もある。そのため陥没が生じる前に地盤の空洞化を検出することが求められている。一方,空洞を調べるには地中レーダや反射法地震探査,電気探査などが適用されるが,探査深度や分解能が不足する場合がある。地盤の密度に関係する物理探査手法は,重力探査や密度検層などの方法しかない。宇宙線ミュー粒子を利用した探査技術は地盤の密度分布を求めることが可能である。従来の物理探査手法を補う方法として宇宙線ミュー粒子を利用した地盤探査技術を実用化することを目標として,ミュー粒子計測器と三次元トモグラフィ技術を開発してきた。本稿では,宇宙線ミュー粒子探査技術の原理と基礎的な実験および土木物理探査への可能性について示す。
2 0 0 0 OA 官報
- 著者
- 大蔵省印刷局 [編]
- 出版者
- 日本マイクロ写真
- 巻号頁・発行日
- vol.1889年09月14日, 1889-09-14
- 著者
- 長原 裕希 大山 博司 安積 卓也 西尾 信彦
- 雑誌
- 組込みシステムシンポジウム2013論文集
- 巻号頁・発行日
- vol.2013, pp.114-122, 2013-10-09
- 著者
- 福本 一朗 織田 豊 佐橋 昭
- 出版者
- 一般社団法人電子情報通信学会
- 雑誌
- 電子情報通信学会技術研究報告. MBE, MEとバイオサイバネティックス (ISSN:09135685)
- 巻号頁・発行日
- vol.105, no.304, pp.1-6, 2005-09-15
- 被引用文献数
- 1
2004年は中越大震災やインド洋大津波などの大規模な自然災害に見舞われた年であった。ただ新潟県においては6400名の死者を出した1966年の阪神淡路大震災の教訓を生かせたために、地震の二次被害も少なく、死者が46名に止まったことは不幸中の幸いであった。しかし筆者の避難所救護活動の経験からも、ライフラインの廃絶した孤立都市での医療安全に関しては、ハード・ソフトともにこの10年ほとんど改善が見られなかったと言わざるを得ない。本研究では大災害時における病院・診療所・避難所などにおける医療活動が必要最低限確保できるための医療安全システムに要求されるスペックを考察するとともに、抗堪性の高い医療機器を作り上げるための基礎研究を行うとともに、バイタルサイン計測装置・避難所救急医療電子カルテ装置・診療情報伝送システムなどを開発することを目的とした。本研究はさらには最低限の供給が望まれるessential drugとその常備方法などのハード面および、緊急時医療福祉通信システムや災害時の高齢者福祉システム・医療従事者リクルーティングシステムや緊急時食料・備品の配布システムなどのソフト面に到るまで総合的な大災害時医療安全システムについての調査検討と行政と市民に対する提案に繋がるものである。
2 0 0 0 建設廃棄物の 「全品目巡回回収システム」
- 著者
- 大平 将之
- 出版者
- 公益社団法人 日本コンクリート工学会
- 雑誌
- コンクリート工学 = Concrete journal (ISSN:03871061)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, no.10, pp.3-8, 2001-10-01
全作業所に共通の分別ルールを設定し, 発生するすべての廃棄物を品目ごとに収集運搬する巡回回収システムを紹介する。このシステムはリサイクルの向上が狙いであり, 一般家庭から出るゴミの収集と同じように, 品目別に全作業所を巡回回収するものである。また, 木くず, 紙くず, せっこうボード, ロックウール, コンクリート, ALC, 塩ビ管等の再生される品目に加え, リサイクルが困難であった混合廃棄物を「もえるもの」「もえないもの」に分け, 「もえるもの」はサーマルリサイクルしている点にも特徴がある。