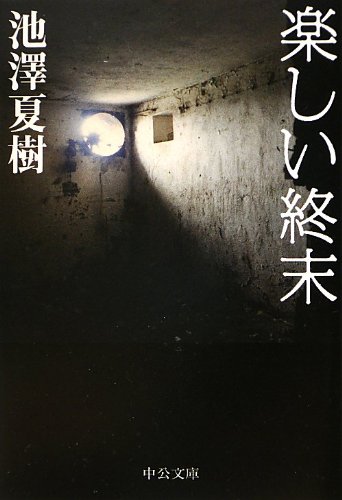2 0 0 0 OA 富士火山,北東麓の新期溶岩流及び旧期火砕丘の噴火年代
- 著者
- 中野 俊 高田 亮 石塚 吉浩 鈴木 雄介 千葉 達朗 荒井 健一 小林 淳 田島 靖久
- 出版者
- 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 地質調査総合センター
- 雑誌
- 地質調査研究報告 (ISSN:13464272)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.11-12, pp.387-407, 2007-03-31 (Released:2014-06-11)
- 参考文献数
- 23
- 被引用文献数
- 1 4
富士火山噴出物の噴火年代決定を目的として産総研が実施したトレンチ調査のうち,北東山麓で行ったトレンチ調査結果及びそれに関連した露頭観察の結果をまとめ,そこから得られた放射性炭素年代測定値を合わせて報告する.トレンチ調査の対象は,新富士旧期の大臼,小臼などの火砕丘群及び新富士新期の檜丸尾,鷹丸尾,中ノ茶屋,雁ノ穴丸尾,土丸尾などの溶岩流群である.
- 著者
- 藤上 隆治
- 出版者
- 桜美林大学大学院国際学研究科
- 雑誌
- 桜美林シナジー (ISSN:13485431)
- 巻号頁・発行日
- no.6, pp.115-129, 2008
2 0 0 0 IR 1920年代日本の正貨収支の数量的検討 : 「在外正貨」再考
- 著者
- 岸田 真
- 出版者
- 慶應義塾経済学会
- 雑誌
- 三田学会雑誌 (ISSN:00266760)
- 巻号頁・発行日
- vol.96, no.1, pp.61-90, 2003-04
論説はじめに1 政府・日銀の在外金融資産勘定と資産残高2 日銀・政府の正貨収支の数量的検討3 1920年代の在外金融資産の動向と日本の正貨・為替政策結論と展望1920年代における日本の国内外での正貨保有の実態を、日本銀行保有史料を用いて残高(ストック)と収支(フロー)の両側面から明らかにし、その分析結果から日本の対外金融政策を再検討した。特に、海外保有正貨の有価証券(外国政府証券・日本政府外債)への運用に着目し、日本の在外金融資産の構成と対外決済構造の変化を指摘するとともに、研究史上通説となっている。「在外正貨の払い下げ」と「在外正貨の枯渇」への評価に対する新たな論点を提示した。This study elucidates the actual conditions of Japan's specie holdings both domestically and abroad during the 1920s using the historical documents and statistics held by the Bank of Japan, thereby reexamining Japan's foreign monetary policy. Particularly focusing on investments of foreign specie holdings in securities (foreign government securities, Japanese government bonds issued abroad), this study highlights a change in the composition of Japan's foreign financial assets and the foreign settlement structure, and proposes a new perspective towards "the drying up of Japan's foreign specie" in the late 1920s, which are commonly held views in the past studies.
- 著者
- リクトマン アラン
- 出版者
- 同志社大学
- 雑誌
- 同志社アメリカ研究 (ISSN:04200918)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, pp.27-33, 2001-03
アメリカ研究所・アメリカ研究科公開講演会, Lecture(In Conjunction with the Graduate School of American Studies)2000年12月18日、アメリカ研究所は、アメリカ研究科との共催でアメリカン大学のアラン・リクトマン教授の公開講演会を明徳館21番教室で開催した。リクトマン教授は、アメリカ大統領制やアメリカ政治史に関する多くの著書や論文があるが、代表的な著書や共著は、一番最近の著書であるThe Key to the White Houseのほか、The Thirteen Keys to the Presidency, Prejudice and the Old Politics: The Presidential Election of 1928, Historians and the Living Pastなどがある。同教授は、また、ABC、CBS、NBC、BBC、CNN、FOXなど、米国や諸外国のメディアでゲストとして発言を数多く行っている。クリントン大統領の弾劾裁判の最中は、CBSの顧問を勤めていた。下記の英文原稿が示すように、同教授の講演は、大接戦となったゴア - ブッシュ大統領選に関する大変示唆にとんだ内容となっている。
- 著者
- 杉江 修治 谷口 篤 仲 律子
- 出版者
- 日本教育心理学会
- 雑誌
- 日本教育心理学会総会発表論文集
- 巻号頁・発行日
- no.46, 2004-09-10
2 0 0 0 OA 習熟度別少人数クラスの授業効果 : 高等学校「英語1」を通じて
- 著者
- 長谷川 修治
- 出版者
- 植草学園大学
- 雑誌
- 植草学園大学研究紀要 (ISSN:18835988)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, pp.87-95, 2009-03
2 0 0 0 IR アメリカの大統領予選制度
- 著者
- 寿田 竜輔
- 出版者
- 成城大学
- 雑誌
- 成城大學經濟研究 (ISSN:03874753)
- 巻号頁・発行日
- no.28, pp.201-224, 1969-03
2 0 0 0 アメリカ大統領候補のスピーチの計量言語学的比較
- 著者
- 伴 浩美 南保 英孝 大藪 多可志
- 出版者
- 日本知能情報ファジィ学会
- 雑誌
- 日本知能情報ファジィ学会 ファジィ システム シンポジウム 講演論文集
- 巻号頁・発行日
- vol.24, pp.71-71, 2008
本年2008年、アメリカの大統領選挙が行われる。本研究では、3人の有力候補、Barack Obama、Hillary Clinton、John McCain候補のスピーチについて計量言語学的な解析を行い、比較を行った。すなわち、それぞれスピーチについて文字や単語の出現頻度の特徴を調べた。これらの特性を指数関数によって近似を行った。さらに、日本の中学校の必修単語とアメリカの基礎単語("The American Heritage Picture Dictionary" を使用)を用いて、各試料の難易度を求めた。さらに、各試料のK特性値を求めた。結果として、McCain候補のスピーチには文字頻度において英語の文学作品と同様の傾向が見られることや、彼のスピーチは他の候補より難しい傾向があることなどが明らかとなった。
2 0 0 0 親鸞聖人の佛性論について
- 著者
- 普賢 大圓
- 出版者
- JAPANESE ASSOCIATION OF INDIAN AND BUDDHIST STUDIES
- 雑誌
- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)
- 巻号頁・発行日
- vol.4, no.1, pp.237-240, 1956
2 0 0 0 増進的介入と生命の価値 : 気分操作を例として
- 著者
- 島薗 進
- 出版者
- 日本生命倫理学会
- 雑誌
- 生命倫理 (ISSN:13434063)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.1, pp.19-27, 2005-09-19
- 被引用文献数
- 2
医学が治療という任務を超えて、心身の能力を増進させたり、性格を変化させたりすることは許されるのか。許されるとしても限度があるとすれば、どのような限度だろうか。増進的介入をめぐるこうした論議の中で重要な意義をもつものに、軽度のうつ気分の改善に効果があるプロザックなどのSSRI(選択的セロトニン取り込み阻害薬)をめぐるものがある。気分操作という面でSSRIが切り開いた新たな医薬の機能を解説し、心理療法と対比しつつその使用を巧みに弁護した書物にピーター・クレイマーの『プロザックに耳を傾ける』がある。その弁論とレオン・カスが座長を務めるアメリカの大統領諮問生命倫理委員会の批判論を対比し、増進的介入の限度を論じる際の根拠となる生命の価値の概念について考察する。自律ではなく、痛みを免れられず、また与えられたものによってこそ生きる人間の条件を知り、受け入れることの価値について論じる。
2 0 0 0 IR 袋中(良定)『青天集』翻刻と紹介--夢窓疎石『谷響集』への反論書
- 著者
- 西山 美香
- 出版者
- 駒沢大学歴史学研究室内駒沢史学会
- 雑誌
- 駒沢史学 (ISSN:04506928)
- 巻号頁・発行日
- no.58, pp.147-154, 2002-03
2 0 0 0 OA イブニングセミナー
- 出版者
- 日本耳鼻咽喉科免疫アレルギー学会
- 雑誌
- 耳鼻咽喉科免疫アレルギー (ISSN:09130691)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.2, pp.20-21, 2015 (Released:2015-06-29)
2 0 0 0 OA Future Changes in Winter Precipitation around Japan Projected by Ensemble Experiments Using NHRCM
- 著者
- Hiroaki KAWASE Hidetaka SASAKI Akihiko MURATA Masaya NOSAKA Noriko N. ISHIZAKI
- 出版者
- (公社)日本気象学会
- 雑誌
- 気象集誌. 第2輯 (ISSN:00261165)
- 巻号頁・発行日
- vol.93, no.5, pp.571-580, 2015 (Released:2015-11-17)
- 参考文献数
- 33
- 被引用文献数
- 3 19
We investigate future changes in winter precipitation around Japan and their uncertainties using the downscalings of a non-hydrostatic regional climate model (NHRCM) with 20-km grid spacing according to global climate projections. The global climate projections were conducted by the atmospheric general circulation model with three patterns of sea surface temperature changes in the Coupled Model Intercomparison Project Phase 5 under the Representative Concentration Pathway 8.5. Moreover, three cumulus convective parameterizations were applied in the present and future climate experiments. The ensemble mean of nine future NHRCM experiments shows decreases in the winter precipitation on the coast of the Sea of Japan and over the Pacific Ocean in the south of the Japanese archipelago. The former decrease in precipitation results from a weakened winter monsoon. The latter corresponds to changes in extratropical cyclone number around Japan, which have a large uncertainty. On the other hand, winter precipitation increases over the northernmost part of Japan (Hokkaido) and the northeastern Asian continent. The strengthened northwesterly around Hokkaido, which results from the reduction of sea ice in the Sea of Okhotsk, causes increased precipitation in the inland area of Hokkaido. In addition, moistening due to global warming relates to increased precipitation in extremely cold regions. These signals are common to most experiments.
- 著者
- 池井 優
- 出版者
- 慶応義塾大学法学研究会
- 雑誌
- 法学研究 (ISSN:03890538)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, no.11, pp.1-46, 1973-11
2 0 0 0 IR 日本の対ソ承認(1917-1925)--対ソ交渉過程の外交史的研究
- 著者
- 池井 優
- 出版者
- 慶應義塾大学法学研究会
- 雑誌
- 法学研究 (ISSN:03890538)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, no.11, pp.1-46, 1973-11
論説
- 著者
- 池井 優
- 出版者
- 慶応義塾大学法学部法学研究会
- 雑誌
- 教養論叢 (ISSN:04516087)
- 巻号頁・発行日
- no.43, pp.p65-76, 1975-12
2 0 0 0 OA Effect of QBO and ENSO on the Solar Cycle Modulation of Winter North Atlantic Oscillation
- 著者
- Yuhji KURODA
- 出版者
- (公社)日本気象学会
- 雑誌
- 気象集誌. 第2輯 (ISSN:00261165)
- 巻号頁・発行日
- vol.85, no.6, pp.889-898, 2007 (Released:2008-03-20)
- 参考文献数
- 22
- 被引用文献数
- 8 15
The effect of the Quasi-Biennial Oscillation (QBO) and the El Niño Southern Oscillation (ENSO) on the 11-year solar cycle modulation of the winter-mean North Atlantic Oscillation (NAO) is examined through analysis of observational data from 1958 to 2000. It is found that the solar cycle modulation of the NAO is more strongly enhanced in the westerly phase of the 50-hPa QBO wind and the cold phase of ENSO, although separation of these effects is statistically difficult. On these phases, the signal of the winter-mean NAO extends more to the upper stratosphere and summer-AO reappears more strongly in high solar years, whereas the signal is weaker throughout in low solar years.
2 0 0 0 18世紀フランスの「農業革命」について
- 著者
- 阿河 雄二郎
- 出版者
- 大阪外国語大学
- 雑誌
- Etudes francaises (ISSN:0285984X)
- 巻号頁・発行日
- no.15, pp.p67-92, 1977
2 0 0 0 OA アンギオテンシン変換酵素阻害薬により誘発された喉頭血管性浮腫の1例
- 著者
- 藤田 芳史 鈴木 一雅
- 出版者
- 耳鼻咽喉科展望会
- 雑誌
- 耳鼻咽喉科展望 (ISSN:03869687)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.3, pp.167-171, 2012 (Released:2013-06-15)
- 参考文献数
- 16
アンギオテンシン変換酵素阻害薬は, 高血圧治療の第一選択薬の一つとされ, 高血圧や心不全の治療に広く使用されている。同薬剤の副作用の一つに血管性浮腫があり, 喉頭浮腫をきたすと致死的な経過をたどることもあるため注意が必要である。今回我々は, アンギオテンシン変換酵素阻害薬による薬剤誘発性の喉頭血管性浮腫と考えられた症例を経験したので報告する。症例は19歳女性。高血圧に対し, 2年前からアンギオテンシン変換酵素阻害薬を内服していた。今回咽頭痛, 頸部腫脹で受診し, 咽頭, 喉頭浮腫を認め入院となった。血液検査上, 炎症反応の上昇は認めなかったため, アンギオテンシン変換酵素阻害薬による薬剤誘発性の血管性浮腫を疑い, 内服を中止した。C1 inhibitor活性, 血性補体価の低下は認めず, 遺伝性血管性浮腫は否定的であった。入院6日目には喉頭浮腫はほぼ消失し, 退院となった。退院後はアンギオテンシン変換酵素阻害薬をCa拮抗薬に変更したが, 浮腫の再発は認めていない。炎症所見の乏しい, 咽喉頭の浮腫を認めた場合には, 血管性浮腫を念頭において診療にあたるべきと考えた。