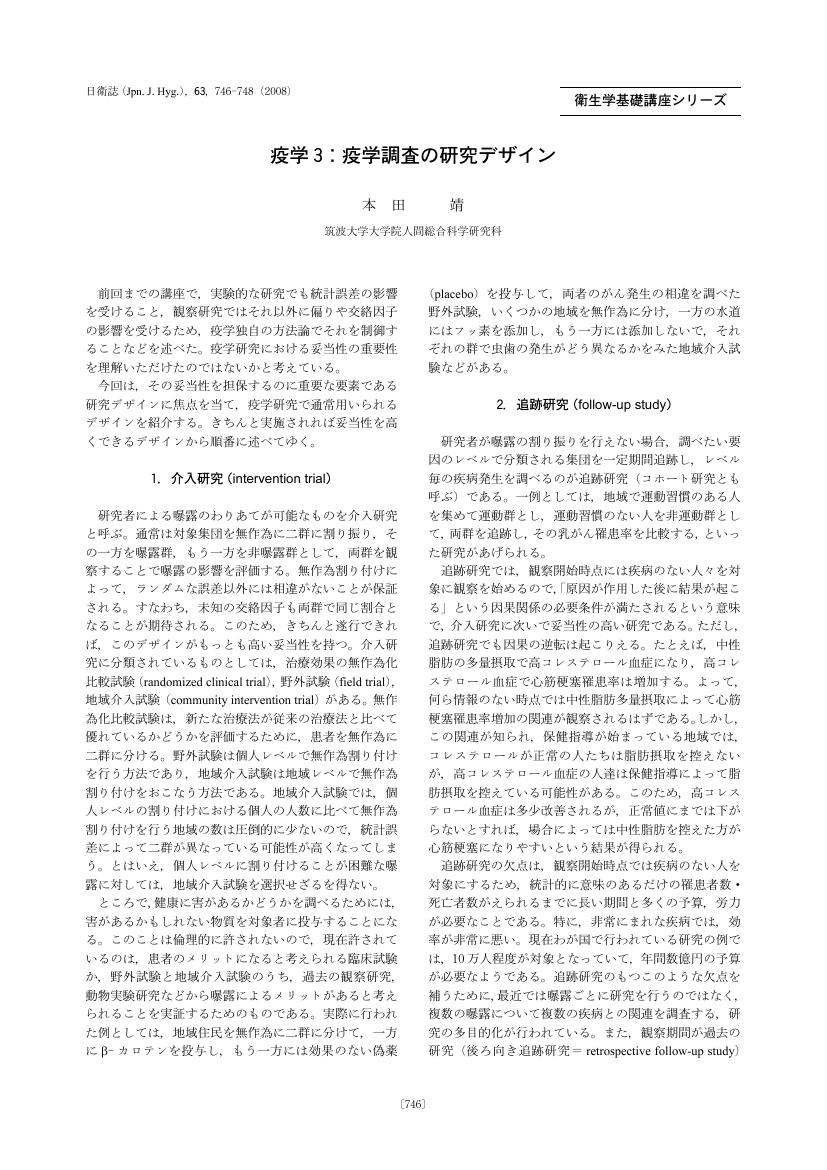- 著者
- 中川 千帆
- 出版者
- 上智大学アメリカ・カナダ研究所
- 雑誌
- アメリカ・カナダ研究 (ISSN:09148035)
- 巻号頁・発行日
- no.26, pp.37-58, 2008
2 0 0 0 OA ベトナム戦争と婦人国際平和自由連盟アメリカ支部
- 著者
- 高 村 宏 子
- 出版者
- 日本女子大学英語英文学会
- 雑誌
- 日本女子大学 英米文学研究 = Japan Women's University Studies in English and American literature
- 巻号頁・発行日
- no.51, pp.69-84, 2016-03-20
2 0 0 0 IR 2009年朝鮮社会主義憲法改正に関する若干の考察 : ~先軍思想からみた憲法改正~
- 著者
- 大内 憲昭
- 出版者
- 関東学院大学[文学部]人文学会
- 雑誌
- 関東学院大学文学部紀要 (ISSN:02861216)
- 巻号頁・発行日
- vol.117, pp.189-231,
朝鮮民主主義人民共和国は2009年4月に1998年憲法を修正補充した。しかし最高人民会議で承認された憲法は公表されなかった。筆者が2009年9月に訪朝し、政府の関係機関から憲法テキストを入手し、朝鮮の憲法学者から改正内容に関して詳細な説明を受け、かつ質疑をすることができた。改正憲法は今日の朝鮮の政治状況を反映し、新たに「先軍思想」を規定し、国防委員会委員長を国の「最高指導者」とした。これにより1998年憲法以来「空席」であった「元首」の役割を国防委員会委員長が担うことになった。本稿では、朝鮮の憲法学者の講義を踏まえながら、憲法の改正点と特徴を明らかにしたいと思う。なお、2009年改正憲法全文を翻訳した。
2 0 0 0 OA 官報
- 著者
- 大蔵省印刷局 [編]
- 出版者
- 日本マイクロ写真
- 巻号頁・発行日
- vol.1944年12月19日, 1944-12-19
2 0 0 0 IR 朝鮮民主主義人民共和国相続法
- 著者
- 大内 憲昭
- 出版者
- 関東学院大学[文学部]人文学会
- 雑誌
- 関東学院大学文学部紀要 (ISSN:02861216)
- 巻号頁・発行日
- vol.105, pp.95-113,
本稿は、2002年に制定された朝鮮民主主義人民共和国の相続法に関する概説および条文の翻訳である。朝鮮における相続制度の規制は、建国時期から1980年代までは民法、1990年に家族法が制定されて以降、民法から家族法に変わった。2002年相続法の制定は、家族法からも分離されたことになる。朝鮮の相続制度が、財産的関係あるいは人格的(身分的)関係を主たる規制対象としているのかが問題となる。また2002年相続法は、これまで民法あるいは家族法で規制されていた内容を詳細なものとした。とくに法定相続、遺言相続に関しては詳細な規定を置いている。本稿では、民法、家族法、相続法における規制内容を比較することにより、2002年相続法の特徴を考察した。
2 0 0 0 IR 任意捜査の適正に関する比較法的研究
- 著者
- 洲見 光男
- 出版者
- 明治大学社会科学研究所
- 雑誌
- 明治大学社会科学研究所紀要 (ISSN:03895971)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, no.1, pp.159-172, 2007-10
任意捜査は、その呼び名から自由に許されるかのように思われがちであるが、程度および方法において「必要な」限度を超えることは許されない(197条1項。なお、198条)。他面、任意捜査は、相手方の承諾・協力を得て行う捜査であって、何ら個人の権利・利益を制約するものではないことを想像させるが、実は、それは「強制捜査ではない」ことを意味するにとどまり、個人の権利・利益を制約し得る場合があるとされているω。捜索・押収などによる強制捜査は、広い意味で、個人情報の収集活動と捉えることもできるが、これについては憲法および刑事訴訟法に規定が置かれており、手続・要件の「法定主義」(憲法31条、刑訴法197条1項但書)および「令状主義」(憲法35条、刑訴法218条等)による規制が加えられている。
- 著者
- 鉄井 孝司 テツイ タカシ Takashi Tetsui
- 雑誌
- 史苑
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.2, pp.88-102, 1977-03 (Released:2012-11-21)
- 著者
- 浅井 隆
- 出版者
- 慶應義塾大学大学院法務研究科
- 雑誌
- 慶應法学 (ISSN:18800750)
- 巻号頁・発行日
- no.18, pp.263-269, 2011-01
判例評釈(労働法)【評釈判例】【事実関係】【判決の内容】【本件事件を巡る社会的背景と企業実務への影響度】【本件判決の意義】
2 0 0 0 ららぽーとスキードーム「ザウス」における 造船技術の応用
- 著者
- 石川 嘉一
- 出版者
- 公益社団法人日本船舶海洋工学会
- 雑誌
- Techno marine (ISSN:09168699)
- 巻号頁・発行日
- vol.857, pp.772-774, 2000-11-25
2 0 0 0 二一世紀における海洋安全保障
- 著者
- 山崎 眞
- 出版者
- 一般財団法人 日本国際政治学会
- 雑誌
- 国際政治 (ISSN:04542215)
- 巻号頁・発行日
- vol.2008, no.154, pp.154_145-154_160, 2008
Recently, it has been closed-up again that Japan relies on the import mostly of the energy source, food, and the raw material because the sudden rise of the oil price and the price hike of food and various raw materials, etc. occurred in early 2008. A serious discussion about the food security is happening, too. Japan imports most 99 percent of oil, 87 percent of wheat, 95 percent of the soybean, and 100 percent of other iron ore and rare metals, etc. and 98 percent of those materials are transported through Sea Lane. Japan has developed economically for 60 years after the war because such a raw material etc. were able to be imported without trouble by can the free use of the sea, and to export the product.<br>A two great sea power of U. S. -Soviet was rivaled, and the stability of the ocean was kept because two great military power of U. S. -Soviet faced it at the cold war era. The balance of such a sea power collapses when the cold war is concluded, and the element of instability in the ocean has increased. Therefore, the confrontation by the race and the religion, etc. came to light, and the pirate and the outrage, etc. for the capital work of these group and organization came to be generated. Moreover, maritime terrorism came frequently to occur chiefly when becoming after 2000 years. Safety and the stability of the ocean are deteriorating than the cold war era because of such a situation, and it has come not to be able to disregard the influence given to the economy of the world. For instance, the Strait of Malacca passes by 50 percent of the amount of the oil transportation in the world and 30 percent of the amount of the world trade, and if here would be blockaded by the terrorism such as mines, it is said that the economy of the world will become a situation that nears panic.<br>And furthermore, recent Chinese naval modernization and reinforcement and North Korean nuclear armament under opaque situation will bring insecurity in this region. 90 percent of the trade of the world depends on marine transport now. Moreover, 75 percent of the world's population and 80 percent of the capital are in the coastal frontier. Safety in the ocean therefore can be called a base for the world economy as well as the human race living. Especially, this is extremely important for Japan that is the maritime country.<br>The ocean policy of Japan was something like a inconsistent stripe passes existed in the situation in which the national interest in the ocean was being lost for this by the government office organizations of lack of coordination so far. The former political administration of Prime Minister Abe enforced “The Basic Law of the Sea” to demonstrate a strong statesmanship considering such a situation and to straighten the situation as the country in July, 2007. The Cabinet Council was continuously decided to “Oceanic basic plan” based on this law in April 2008.<br>On the other hand, the United States that valued safety and the stability of the ocean made “New Maritime Strategy” public after an interval of about 20 years in October 2007. This is a new idea of acquiring safety and the stability of the ocean in the world by cooperate about the ally and the friendly country strong. It is the one that the Maritime Self-Defense Force's being sending the fleet to the multinational fleet in the Indian Ocean coincident with such an idea. Now, there is no country that can defend safety in the ocean in the world by one country. Peace in the sea can be acquired only by concentrating the imperative power such as naval forces and coast guards in the world.<br>It is necessary that Japan cooperate positively in such the world strategy.
2 0 0 0 OA ダブルスポット高出力けい光ランプ用安定器の設計
- 著者
- 南淵 幸雄
- 出版者
- 一般社団法人 照明学会
- 雑誌
- 照明学会雑誌 (ISSN:00192341)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.6, pp.287-293, 1970-06-25 (Released:2011-07-19)
- 参考文献数
- 4
Descriptions are made of the theory and practice of the double spot high output ballast in which a fluorescent lamp is used.The theory states that, when the phase of the filament terminal voltage runs 90 degrees ahead of the tube voltage, the potential difference becomes equal between the opposing electrodes at both ends of the fluorescent lamp, thereby giving rise to the double spots, while the fluorescent lamp is in operation.Not only this fact in proved true, but also the quantitative reasoning on the formation of double spots is presented and backed up by some test data.
2 0 0 0 OA 禅林句集 : 和訓略解
2 0 0 0 ダークネットトラフィックの相関分析
- 著者
- 深澤 成孝 佐藤 直
- 出版者
- 一般社団法人情報処理学会
- 雑誌
- 情報処理学会研究報告. マルチメディア通信と分散処理研究会報告
- 巻号頁・発行日
- vol.2015, no.20, pp.1-7, 2015-02-26
ダークネットでは,DDoS 攻撃,DNS アンプ攻撃などの大規模な攻撃を行うための事前活動や新しいマルウェアの出現によるスキャン活動などのトラフィックが観測される事例が数多く報告されている.また,近年,官公庁・政府機関・企業などを狙った標的型攻撃や新たな攻撃手法である水飲み場型攻撃などのサイバー攻撃は,今まで以上に高度化・巧妙化している.本論文においては,日本における NICTER と世界規模の NORSE,二つのダークネット観測網のトラフィックデータの相関分析を行い,両者のダークネットトラフィックに相関関係があることがわかった.
2 0 0 0 OA 小学作法教授書 : 文部省調査参照国定修身書準拠
2 0 0 0 冷戦と国吉康雄--なぜ画家は「赤狩り」の標的となったのか
- 著者
- 星野 睦子
- 出版者
- 歴史人類学会
- 雑誌
- 史境 (ISSN:02850826)
- 巻号頁・発行日
- no.46, pp.45-61, 2003-03
- 著者
- 真柳 誠
- 出版者
- 日本医史学会
- 雑誌
- 日本医史学雑誌 (ISSN:05493323)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.4, pp.p435-476, 1987-10
2 0 0 0 OA 批判に答えて : 拙著『生を肯定する倫理へ――障害学の視点から』への批判に反論する
- 著者
- 野崎 泰伸 Nozaki Yasunobu
- 出版者
- 大阪府立大学大学院人間社会学研究科
- 雑誌
- 人間社会学研究集録 (ISSN:1880683X)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, pp.237-255, 2012-03-23
- 著者
- 秋鹿 研一
- 出版者
- 公益社団法人 日本化学会
- 雑誌
- 化学と教育 (ISSN:03862151)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, no.10, pp.680-684, 1994
アンモニア合成反応は平衡論(ルシャトリエの法則)の説明の実例として教科書になじみ深い。一方, 化学工業的大量生産の最初の例としても有名である。1913年ハーバー, ボッシュ等により開発されたこの高圧合成プロセスと(鉄)触媒は基本的にはそのまま今日まで用いられてきた。しかし1992年から, はじめて非鉄系のルテニウム触媒が商業生産に用いられはじめ, 新しい考えのプロセスも発表されている。アンモニア合成のブレークスルーとなったルテニウム触媒をはじめて本格的に研究したグループにいた著者が鉄とルテニウムの違いをできる限りやさしく解説した。
2 0 0 0 OA 疫学3:疫学調査の研究デザイン
- 著者
- 本田 靖
- 出版者
- 日本衛生学会
- 雑誌
- 日本衛生学雑誌 (ISSN:00215082)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, no.4, pp.746-748, 2008 (Released:2008-09-30)
- 著者
- 田代 光輝
- 出版者
- 大妻女子大学
- 雑誌
- 大妻女子大学紀要. 社会情報系, 社会情報学研究 (ISSN:13417843)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, pp.197-207, 2014