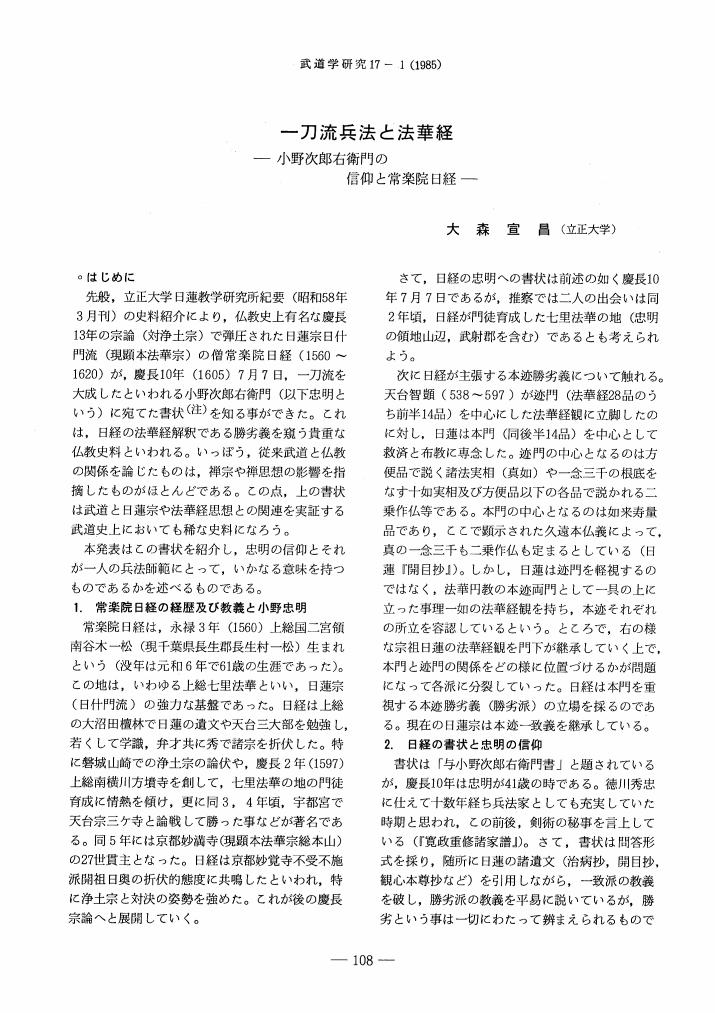2 0 0 0 松前藩と松前 : 松前町史研究紀要
- 著者
- 松前町史編集室 [編]
- 出版者
- 松前町史編集室
- 巻号頁・発行日
- 1972
- 著者
- 北芝 健
- 出版者
- セキュリティスペシャリスト協会
- 雑誌
- セキュリティ研究 (ISSN:13479210)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, no.11, pp.20-27, 2006-11
2 0 0 0 美術シソーラスデータベース形成の諸問題
- 著者
- 福田 博同 五十殿 利治
- 出版者
- 国立研究開発法人 科学技術振興機構
- 雑誌
- 情報管理 (ISSN:00217298)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, no.9, pp.790-809, 1997
- 被引用文献数
- 1
文部省科学研究費補助金データベース公開促進費の援助により「筑波大学日本美術シソーラスデータベース作成委員会」が作成した「日本美術シソーラスデータベース:絵画編」を基に,美術シソーラスデータベース作成に関する以下の問題点を明らかにした。第一に日本における美術データベースの現状と課題。第二に美術分野におけるAATや各目録のシソーラスとを比較し,日本標準となり得るシソーラス形成のため(1)ディスクリプタ収集の問題点(2)時代区分,地域区分,名号や読み,あるいは階層構造の決定など。第三に筑波大学学術情報処理センターのオンライン情報検索システムUTOPIA(紹介はhttp://www.tsukuba.ac.jp/sipc/utopia.htmlにある)へ組み込みの問題点。
2 0 0 0 被災地住民の震災時情報行動と通信不安 : 仙台・盛岡訪問留置調査
2 0 0 0 IR 近世期倉敷村の豪商・大橋家の経営
- 著者
- 山本 太郎
- 出版者
- 岡山大学大学院文化科学研究科
- 雑誌
- 岡山大学大学院文化科学研究科紀要
- 巻号頁・発行日
- vol.16, no.1, pp.129-150, 2003-11
2 0 0 0 OA 感情社会学の可能性 : 感情の社会性をめぐって
- 著者
- 樋口 昌彦 ヒグチ マサヒコ Higuchi Masahiko
- 出版者
- 大阪大学人間科学部社会学・人間学・人類学研究室
- 雑誌
- 年報人間科学 (ISSN:02865149)
- 巻号頁・発行日
- vol.20-2, pp.509-523, 1999
2 0 0 0 OA 活動の空間的および連鎖的な組織――話し手と聞き手の相互行為再考――
- 著者
- 西阪 仰
- 出版者
- 日本認知科学会
- 雑誌
- 認知科学 (ISSN:13417924)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, no.1, pp.65-77, 2009 (Released:2010-06-11)
- 参考文献数
- 33
- 被引用文献数
- 3
In the Conversation Analytic tradition, one has noted and discussed the substantial contribution of hearers' conduct to the constitution of each utterance in conversation, in ways very sensitive to some prominent sequential positions in interaction such as a possible completion point of an utterance. In this article, I focus on the spatial distribution of orientations which all the participants in interaction show in and through their bodily arrangement. The spatial distribution of participants' orientations constitutes, and is incorporated into, a distinct and describable activity. One should note, however, that the organization of a distinct activity with a distinct distribution of orientations is still embedded in the sequential order of interaction. I show that various context-free, general resources are available in interaction for participants to organize the current, on-going activity sequentially and jointly in and through the actual development of interaction.
2 0 0 0 OA 協同作業場面の身体配置
- 著者
- 高山 啓子
- 出版者
- 関東社会学会
- 雑誌
- 年報社会学論集 (ISSN:09194363)
- 巻号頁・発行日
- vol.1997, no.10, pp.157-168, 1997-06-05 (Released:2010-04-21)
- 参考文献数
- 27
This paper investigates how the arrangement of participants' bodies, talks and activities in particular time and space organize their interactions. The empirical research was done by using videotapes of dispatchers receiving emergency calls in a 119 dispatch center. While one dispatcher (call taker) replies to an emergency call, he and his colleague are able to silently interact with each other. This shows that their actions construct a type of back region and the call taker is embedded within two ‘participation frameworks’: one with the caller, and the other with his colleague.This analysis shows that these concepts, “region” and “participation framework”, proposed by Erving Goffman, apply to actual settings and that they are organized by the arrangement of the participants' bodies, talks and activities.
2 0 0 0 OA 現実の会話における「発話」の知覚 : 発話の何が知覚され、そこで何が起こるのか
- 著者
- 名塩 征史
- 出版者
- 北海道大学大学院国際広報メディア・観光学院院生論集制作委員会
- 雑誌
- Sauvage : 北海道大学大学院国際広報メディア・観光学院院生論集
- 巻号頁・発行日
- vol.6, pp.7-18, 2010-03
- 著者
- 今田 絵里香
- 出版者
- 大阪国際児童文学館
- 雑誌
- 国際児童文学館紀要 (ISSN:09111832)
- 巻号頁・発行日
- no.24, pp.1-14, 2011
2 0 0 0 琉球諸島における洞穴棲コウモリの条虫相
- 著者
- 沢田 勇
- 出版者
- 日本動物分類学会
- 雑誌
- 動物分類学会誌 (ISSN:02870223)
- 巻号頁・発行日
- no.14, pp.5-9, 1978-06-26
- 被引用文献数
- 1
1.沖永良部島,沖縄本島,宮古島,石垣島および西表島の洞穴棲コウモリの条虫相を明らかにし,それらの条虫相を奄美大島以北の日本各地のそれと比較した。2.沖永良部島のユビナガコウモリMiniopterus schreibersiiは剖検した12頭中わずかに1頭に同定不能の幼弱虫体1条のみが寄生していたが,沖縄本島のオキナワコキクガシラコウモリRhinolophus cornutus pumilusには条虫の寄生は認められなかった。3.宮古島ではコウモリの生息が確認できなかった。4.石垣島および西表島のリュウキュウユビナガコウモリM. s. blepotisにはVampirolepis hidaensisが,西表島のヤエヤマコキクガシラコウモリR. c. pumilusにはV. isensisがそれぞれ寄生していた。5. V. hidaensisは西日本一帯に生息するユビナガコウモリおよびキクガシラコウモリに寄生する条虫と同一種であり,V. isensisは奄美大島以北の北海道を除く日本各地のコキクガシラコウモリに寄生する条虫と同一種である。こうしたことから八重山諸島のリュウキュウユビナガコウモリとヤエヤマコキクガシラコウモリは条虫相からみて奄美大島以北に生息するキクガシラコウモリおよびコキクガシラコウモリと何らかの関連性があると考えてよい。
2 0 0 0 OA もう間違わないil estとc'est
- 著者
- 井元 秀剛
- 出版者
- 日本フランス語学会
- 雑誌
- フランス語学研究 (ISSN:02868601)
- 巻号頁・発行日
- no.42, pp.83-85, 2008-06-01
本文データはCiNiiから複製したものである
2 0 0 0 OA 近世後期水戸藩における剣術の様相について―杉山復堂『公覧始末』をめぐって―
- 著者
- 長尾 進
- 出版者
- 日本武道学会
- 雑誌
- 武道学研究 (ISSN:02879700)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.Supplement, pp.70-70, 1995 (Released:2012-11-27)
- 著者
- 牧下 英世
- 出版者
- 筑波大学附属駒場中・高等学校研究部
- 雑誌
- 筑波大学附属駒場論集 (ISSN:13470817)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, pp.147-158, 2012-03
2 0 0 0 一般児童における抑うつ症状の実態調査
- 著者
- 佐藤 寛 永作 稔 上村 佳代 石川 満佐育 本田 真大 松田 侑子 石川 信一 坂野 雄二 新井 邦二郎
- 出版者
- 日本児童青年精神医学会
- 雑誌
- 児童青年精神医学とその近接領域 (ISSN:02890968)
- 巻号頁・発行日
- vol.47, no.1, pp.57-68, 2006-02-01
- 被引用文献数
- 9
2 0 0 0 OA 剣道技術の目的の変遷に関する研究―一刀流兵法とその展開―
- 著者
- 吉谷 修
- 出版者
- 日本武道学会
- 雑誌
- 武道学研究 (ISSN:02879700)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, no.1, pp.1-2, 1984-01-31 (Released:2012-11-27)
- 参考文献数
- 6
2 0 0 0 OA 学校剣道からみた剣道野試合の価値に関する研究―岡崎市第8回剣道野試合大会を中心に―
- 著者
- 中林 秀治
- 出版者
- 日本武道学会
- 雑誌
- 武道学研究 (ISSN:02879700)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, no.1, pp.53-53, 1968-12-25 (Released:2012-11-27)
2 0 0 0 OA 小野家伝書に見る“切落し”の仕様―特に,組太刀全体における位置づけ―
- 著者
- 吉田 鞆男
- 出版者
- 日本武道学会
- 雑誌
- 武道学研究 (ISSN:02879700)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.Supplement, pp.28-28, 1992 (Released:2012-11-27)
2 0 0 0 OA 一刀流兵法と法華経―小野次郎右衛門の信仰と常楽院日経―
- 著者
- 大森 宣昌
- 出版者
- 日本武道学会
- 雑誌
- 武道学研究 (ISSN:02879700)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.1, pp.108-109, 1985-01-30 (Released:2012-11-27)