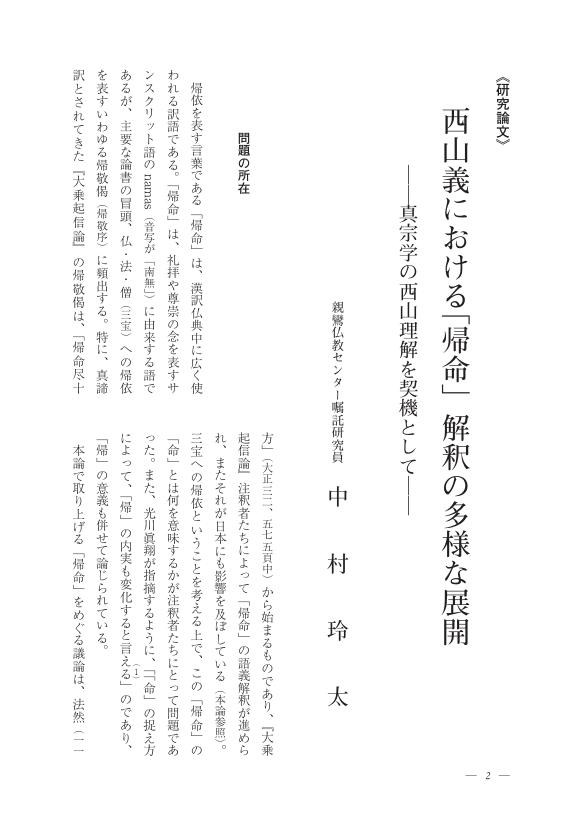- 著者
- 井上 大介 INOUE Daisuke
- 出版者
- 創価大学社会学会
- 雑誌
- SOCIOLOGICA (ISSN:03859754)
- 巻号頁・発行日
- vol.47, no.1-2, pp.35-56, 2023-03-20
本稿ではインターネットをはじめとする電子メディアを媒介としたコミュニケーション、相互行為が社会をどのように変容させつつあるのかという点について、宗教文化に限定して考察したものである。日本におけるデジタル・メディアと宗教に関する研究では、宗教教団がどのようにインターネットを活用しており、組織の形態や運営がどのように変化しつつあるのか、といった事例研究が中心となってきた。他方、欧米における研究動向では、Digital Religion という領域において様々な研究が、 990 年代以降蓄積されてきた。本論の前半では、同研究領域の概要を先行研究に沿って紹介し、特にそこでの理論的枠組みが宗教観、儀礼、帰属意識、共同体、権威、身体化という6つの領域である点を整理した。後半では、その中の権威について注目しつつ、キューバにおけるヨルバ系宗教であるレグラ・デ・オチャ=イファ信仰を題材に、そこにおける伝統的指導者と現代的指導者の相違点、およびそこでの師弟関係の変容および孤独化の現状に注目しつつ論を展開した。
1 0 0 0 OA 司書合格体験記
- 著者
- 西村 清宏 江藤 由香里 生田 奈津実 Kiyohiro Nishimura Yukari Eto Natsumi Ikuta
- 出版者
- 同志社大学図書館司書課程
- 雑誌
- 同志社大学図書館学年報 = Doshisha Library Science Annual (ISSN:09168850)
- 巻号頁・発行日
- no.45, pp.104-107, 2020-03-31
1 0 0 0 OA 花山の姿 : 大鏡の<カタル>方法
- 著者
- 辻 和良 ツジ K. Tsuji
- 雑誌
- 名古屋女子大学紀要. 人文・社会編 = Journal of Nagoya Women's University. Humanities・social science
- 巻号頁・発行日
- vol.36, pp.304-297, 1990-03-05
1 0 0 0 OA 現代ミャンマーの宗教的ランドスケープをめぐる一考察 タイッに関する言説と実践の事例から
- 著者
- 飯國 有佳子
- 出版者
- パーリ学仏教文化学会
- 雑誌
- パーリ学仏教文化学 (ISSN:09148604)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, pp.39-58, 2019 (Released:2020-08-14)
Arguments regarding anthropological studies of religion in Myanmar have primarily focused on how to comprehend canonical Theravāda Buddhism and indigenous spiritual worship. In contrast with Spiro’s dualistic argument, which regards Burmese Buddhism and spiritual worship as comprising independent religious fields, Brac de la Perrière does “not consider the spirit cult a religion unto itself, but as part of Burmese religion” and views “Burma’s mainstream religion as a religious system that incorporates within the Buddhist framework practices of seemingly different horizons such as the spirit cult or the weikza cult” [Brac de la Perrière 2009]. Furthermore, Brac de la Perrière indicates that the “nat line” and “dat line”, which are distinguished by ritual specialists such as spiritual mediums, emerged as fluctuating domains in an overall fluid religious landscape [Brac de la Perrière 2014]. Although my study supports the argument of Brac de la Perrière, her study lacks not only non-specialists’ discourses or practices about spiritual beings or “non-human” agencies but also an analysis of Pāli canons concerning spiritual beings, despite canonical knowledge being the main component of the framework of reference for “orthodox” Buddhism. To further develop these arguments, I will focus on practices and discourses of spiritual beings called thaik, which are viewed as an adjunctive subordination of nat [Spiro 1967]. After considering basic configurations about thaik, such as differences between thaik and ouksasaun, the world of thaik, or the relationship between thaik and human beings, I will show how thaiks are written in Pāli canons. Through these arguments, I will indicate that discourses or practices about thaik have appeared through a process of re-rationalization of a group of spiritual beings within the framework of “orthodox” Buddhism based on the criticism of belief in indigenous, unseen spiritual beings. Further, it shall be Pāli canons that boosts the existence and agencies of thaik through the intermediary of rejoicing for transmitting merit (anumodana).
- 著者
- Teruaki Hayashi Takehiko Yamanashi Masahiro Tanaka Masaaki Iwata
- 出版者
- Tottori University Medical Press
- 雑誌
- Yonago Acta Medica (ISSN:13468049)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.2, pp.263-272, 2023 (Released:2023-05-25)
- 参考文献数
- 25
Background In Japan, the number of suicides has increased since the coronavirus disease (COVID-19) epidemic. However, only a few studies have examined the trends among individuals who attempted suicide. In this study, we examined the background characteristics and motives of individuals who attempted suicide and visited the emergency room because of suicide-related behavior before and after the spread of COVID-19.Methods This single-center retrospective observational study collected information from electronic medical records. We included patients who presented to the emergency department of Tottori University Hospital with suicide-related behaviors between May 1, 2017, to August 31, 2022. The period from May 1, 2017, through December 31, 2019, was designated as ‘the period before COVID-19” (before-period), and that from January 1, 2020, through August 31, 2022, was designated as “the period after COVID-19” (after-period). We compared the total number of cases, their background, and motives for suicide-related behaviors between the before- and after-periods.Results The total number of suicide events was 304. Of these, 182 and 122 occurred during the before-period and after-period, respectively. The incidence of the F3 category of the International Classification of Diseases, 10th Revision, increased, while that of the F4 and F6 categories decreased during the after-period. The proportion of suicide attempts due to health problems decreased and that of work problems increased during the after-period.Conclusion The total number of suicide-related behaviors decreased after the COVID-19 pandemic. This may be because patients with psychiatric disorders other than depression and schizophrenia often engage in suicidal behavior through non-fatal methods, such as drug overdose and wrist-cutting, which may have led them to refrain from seeing a doctor. The proportion of suicidal motivation due to work-related fatigue has increased, perhaps because the quality and quantity of work changed significantly due to COVID-19.
1 0 0 0 OA 粉末X線回折法の基礎とその解析法
- 著者
- 菅原 義之
- 出版者
- 公益社団法人 日本化学会
- 雑誌
- 化学と教育 (ISSN:03862151)
- 巻号頁・発行日
- vol.70, no.3, pp.134-137, 2022-03-20 (Released:2023-03-01)
- 参考文献数
- 6
粉末X線回折分析は,広く化学研究に用いられていることから,理工系学部の化学系の学科では機器分析に関する学生実験で取り上げられることが多い。またブラッグの法則は,高校物理で学習する内容である。本講座では,結晶学の関連する内容を含め化学系の学科で学ぶX線およびX線回折に関する基礎的内容を概説するとともに,広く使われている粉末X線回折法について,原理とこの分析を用いる主な解析法について述べる。
1 0 0 0 OA 日帰り温泉旅行における要介護高齢者自身の生活機能に対する認識の変化:解釈学的現象学的分析
- 著者
- 喜多 一馬 池田 耕二
- 出版者
- 日本医療福祉情報行動科学会
- 雑誌
- 医療福祉情報行動科学研究 (ISSN:21851999)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, pp.55-66, 2021-03-26
【目的】日帰り温泉旅行に参加した個々の要介護高齢者自身の生活機能に対する認識の変化を明らかにすること。【方法】日帰り温泉旅行に参加した要介護高齢者9名に対して,温泉旅行の過程やその前後で生じた自身の生活機能の変化についてインタビュー調査した。インタビュー結果を,解釈学的現象学的分析を用いて分析した。【結果】分析の結果,13サブテーマと【楽しさに繋がる行動を促進する】,【喪失されていた思いの再獲得】,【豊かな感情を喚起する環境に対する認識】,【スタッフの関り方や置かれた立場によって生じる感情】,【自身の在り方に対する認識の変化】という5テーマが抽出できた。【結論】要介護高齢者は温泉旅行を経験したことにより,多様な生活機能に対する認識の変化を生じていた。
1 0 0 0 OA 過労死・過労自殺の心理的要因と職務状況との関係
- 著者
- 岩田 一哲
- 出版者
- 労務理論学会
- 雑誌
- 労務理論学会誌 (ISSN:24331880)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, pp.151, 2009 (Released:2018-05-04)
- 著者
- 駒木 定正
- 出版者
- 日本建築学会
- 雑誌
- 日本建築学会計画系論文集 (ISSN:13404210)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, no.538, pp.219-225, 2000-12-30 (Released:2017-02-03)
- 参考文献数
- 6
- 被引用文献数
- 2 2
This paper is intended as a study of the buildings of the Horonai Public Railway in Otaru for the period from 1884 to 1885. Since the removal of the Head Office to Temiya had been a great undertaking for three years, preparations for the establishment of the colliery and railway office and the transport of coal were considered. The process of the introduction of brick into the construction of buildings of the Horonai Public Colliery and the Railway were examined. The Temiya Locomotive Shed (1885) is an important building as the oldest brick locomotive shed in Japan. Survey research reveal the distinctive feature of the standard measure of the design , the brick masonry and the roof trusses. In the final chapter, the historical characteristics for the entire buildings are summarized.
1 0 0 0 OA AIとビッグデータのための医療情報の標準化
- 著者
- 大江 和彦
- 出版者
- 一般社団法人日本医療機器学会
- 雑誌
- 医療機器学 (ISSN:18824978)
- 巻号頁・発行日
- vol.89, no.6, pp.545-551, 2019 (Released:2020-01-20)
- 参考文献数
- 9
1 0 0 0 OA 事業廃止の政治学
- 著者
- 砂原 庸介
- 出版者
- JAPANESE POLITICAL SCIENCE ASSOCIATION
- 雑誌
- 年報政治学 (ISSN:05494192)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.2, pp.2_237-2_257, 2008 (Released:2012-12-28)
- 参考文献数
- 18
This article analyzes how Japanese local governments decide to terminate policy programs, by examining the experiences of terminating dam construction in prefectural governments. Though Japanese local governments are commonly regarded as subordinate to the central government, they are granted considerable autonomy to implement investment programs. In fact, after the last half of 1990s, many prefectural governments have decided to terminate investment programs, such as dam construction programs which this article deals with. The author advances several hypotheses that the election system of local governments affects the motivations of politicians to implement dam construction programs, and examines those hypotheses by using the techniques of Event History Modeling. The empirical results of this article suggest that a change of local governor is the most important factor of policy termination and that the local assemblies which tend to oppose to the governor become substantive resistance force against termination. These findings demonstrate that the policy termination is not only economical or technical decision, but highly political decision.
1 0 0 0 OA 自己免疫性肝炎の寛解に伴って原発性胆汁性肝硬変が顕在化した1例
- 著者
- 村田 洋介 阿部 雅則 道堯 浩二郎 松原 寛 舛本 俊一 山下 善正 堀池 典生 恩地 森一
- 出版者
- Japan Gastroenterological Endoscopy Society
- 雑誌
- 日本消化器内視鏡学会雑誌 (ISSN:03871207)
- 巻号頁・発行日
- vol.44, no.8, pp.1186-1190, 2002-08-20 (Released:2011-05-09)
- 参考文献数
- 15
- 被引用文献数
- 1
症例は53歳,女性.初回入院時,抗ミトコンドリア抗体陰性.腹腔鏡では,溝状および広範陥凹があり,肝組織では広範壊死がみられた.自己免疫性肝炎(AIH)と診断,副腎皮質ステロイドの投与を開始.その後,胆道系酵素の上昇がみられた.第2回目の腹腔鏡では,陥凹所見は改善.肝組織では非化膿性破壊性胆管炎がみられた.AIHの経過中に原発性胆汁性肝硬変が顕在化し,その経過を腹腔鏡で観察しえたので報告する.
1 0 0 0 OA 『シベリヤ日記』にみる鉱山業フロンティア
- 雑誌
- 金沢大学文学部地理学報告 (ISSN:0289789X)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, pp.8-22, 1986-12-25
金沢大学文学部地理学
1 0 0 0 OA 伊藤勇剛先生の御逝去を悼む
1 0 0 0 東北地方における巫俗と冥界結婚の実態調査
東北地方においてイタコ、カミサマ、ゴミソなどと呼ばれる民間巫者を介して施行されている冥婚習俗の実態調査を行なった。まず金木町川倉地蔵堂、木造町弘法寺では、夭折した不幸な男女を供養する目的で、1955年頃から死霊結婚を具象する花嫁花婿人形の奉納が始まり、1970年代後半からその数が急増していることが判明した。これは、一般に言われているように冥界結婚が日本列島から消滅したのではなく、東北地方の一部では、むしろ新しい習俗として蘇生したことを意味している。おそらく、巫者の口寄せが人形製作者の商業主義とむすびついたと推察されるが、中牧弘允(民博助教授)の指摘するとおり、東北地方における深刻な農村の嫁不足に対応して、こうした冥婚習俗の施行が盛んになったと解釈されるのである。同様に、山形県山寺立石寺でも掲額されている死後結婚の絵、写真、肖像画、肖像写真は、現代風俗に合せた花嫁花婿人形に変りつつある。また、天童市鈴立山若松寺では、死者の彼岸での幸福な結婚を祈願して、婚礼場面を描いた絵馬が奉納されている。この種の絵馬は、この地方では「むかさり絵馬」と呼ばれ、古い風習として存続していた、「むかさり絵馬」の奉納者は山形県北部と宮城県の在住者が圧倒的に多いが、東京方面から奉納された絵馬も散見され、裾野の広いことが分る。通常、冥界結婚は民間巫者の口寄せ、すなわち、死者の結婚したいという烈しく切ない声を伝えることによって親兄弟等が死霊の怨念を除去するために施行されるが、最近では、病や事故で早世した未婚の子どもを不憫におもう親心から自主的に行なう事例が多くなってきた。東北地方の冥婚習俗はまだ調査を開始したばかりで、資料の整理も不十分であるが、民間巫者によって奉納物に変化があらわれても決して消滅しないものと考えられる。
1 0 0 0 OA 予算使途別分類から見た外務省
- 著者
- 北村 亘 Wataru KITAMURA
- 出版者
- 甲南大学法学会
- 雑誌
- 甲南法学 = Konan Hogaku : Konan Law Review (ISSN:04524179)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, no.1・2, pp.61-81, 2004-12-20
1 0 0 0 OA 西山義における「帰命」解釈の多様な展開 真宗学の西山理解を契機として
- 著者
- 中村 玲太
- 出版者
- 宗教法人 真宗大谷派 親鸞仏教センター
- 雑誌
- 現代と親鸞 (ISSN:13474316)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, pp.2-23, 2022-06-01 (Released:2022-06-01)