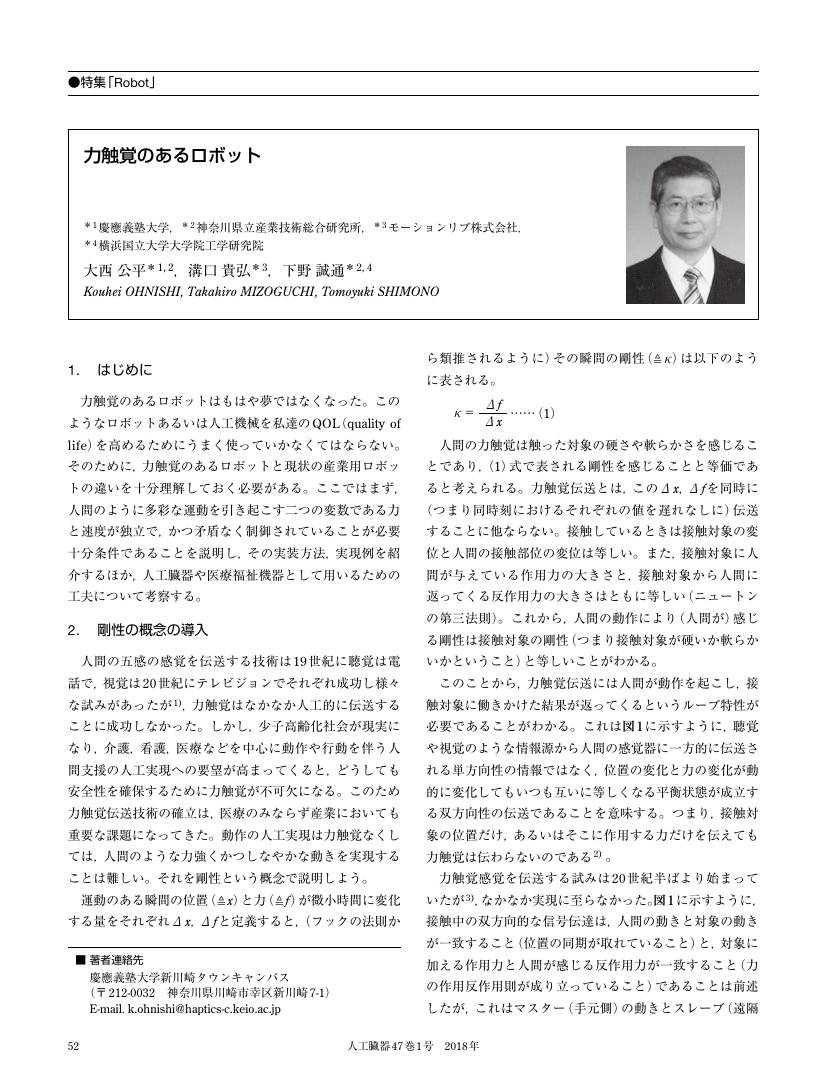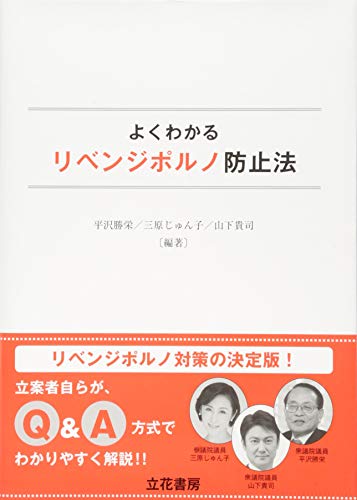1 0 0 0 OA セメント系材料を用いた建設用3Dプリンタの開発
- 著者
- 金子 智弥 坂上 肇 中村 允哉
- 出版者
- 一般社団法人 日本ロボット学会
- 雑誌
- 日本ロボット学会誌 (ISSN:02891824)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, no.4, pp.318-321, 2021 (Released:2021-05-25)
- 参考文献数
- 3
1 0 0 0 OA シンポジウム《リアリズム演劇とは何か》報告
- 著者
- 瀬戸 宏
- 出版者
- 日本演劇学会
- 雑誌
- 演劇学論集 日本演劇学会紀要 (ISSN:13482815)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, pp.40-58, 1995-05-10 (Released:2019-11-11)
1 0 0 0 OA 関節リウマチにおける最新治療と装具療法の創意工夫
- 著者
- 浅見 豊子
- 出版者
- 日本義肢装具学会
- 雑誌
- 日本義肢装具学会誌 (ISSN:09104720)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.2, pp.116-121, 2022-04-01 (Released:2023-04-15)
- 参考文献数
- 8
『関節リウマチ診療ガイドライン2020』が発刊された.バイオ後続品を含むbDMARD, JKA阻害薬等の新規薬剤や手術治療・リハビリテーション治療に対する推奨,薬物治療および非薬物治療・外科的治療のアルゴリズムの作成,医療経済学的評価,患者の価値観・意向の検討など多面的に記載され,RA治療の進歩を感じとれる内容である.しかし一方,『リウマチ白書2020』では「主治医に装具やリハビリについて処方・助言してほしい」という声が18%存在する.RAの治療についてはより一層の進展が期待されるところであるが,患者や家族の声に日頃より耳を傾け,リハビリテーション治療の1つである装具療法の視点からもしっかり支援することが望まれる.
1 0 0 0 OA 有痛性手関節拘縮に対して新しい人工筋型動的牽引スプリントを試みた関節リウマチの1例
- 著者
- 中山 淳 砂川 耕作 岡 久雄 田野 確郎
- 出版者
- 一般社団法人 日本作業療法士協会
- 雑誌
- 作業療法 (ISSN:02894920)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, no.1, pp.89-94, 2023-02-15 (Released:2023-02-15)
- 参考文献数
- 19
近年,リウマチ手に対して局所の安静を確保することは,関節痛を軽減すると報告されている.また,拘縮手に対する運動療法の一つとしてダーツスロー運動の有効性が報告されている.そこで我々は,固定機能と矯正機能を兼ね備えた新しい人工筋型動的牽引スプリント(DTSaM)を考案した.DTSaMは,これまでの矯正部分の力源にマッキベン型空気圧ゴム人工筋を取り入れ,ダーツスロー運動と固定機能を併存させたスプリントである.今回我々は,本スプリントをリウマチ患者に適応したところ,装着開始8週経過時に可動域,疼痛および握力も改善した症例を経験した.本スプリントは疼痛軽減にも有効な福祉用具となりえる可能性がある.
1 0 0 0 OA 悪性リンパ腫との鑑別を要した神経Sweet病の2例
- 著者
- 東野 真志 西原 賢在 蘆田 典明 橋本 公夫 石原 美佐 髙原 佳央里 篠山 隆司 甲村 英二 細田 弘吉
- 出版者
- 一般社団法人日本脳神経外科コングレス
- 雑誌
- 脳神経外科ジャーナル (ISSN:0917950X)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.2, pp.119-124, 2020 (Released:2020-02-25)
- 参考文献数
- 11
神経Sweet病は典型的には皮膚病変の特徴や皮膚生検によって診断されることが多い疾患である. われわれは頭部MRIで, 周囲に浮腫を伴い, 造影される脳実質内斑状病変の1例と, 広範囲のleptomeningeal enhancementを呈した1例を経験した. いずれも皮膚病変を認めず, 脳原発悪性リンパ腫を疑って腫瘍摘出術と生検術を施行した. 両疾患ともにステロイドが著効し, 画像所見も似ることがある. 神経Sweet病はまれな疾患だが, 悪性リンパ腫が疑われる症例では鑑別診断として本疾患や血管炎などの炎症性疾患を挙げ, 疑わしい場合はヒト白血球抗原検査を施行するとよい. また, 手術に際してfluorescenceを用いたところ, 病変同定に有用であり, 併せて報告する.
1 0 0 0 OA 第3回 太平洋戦争中の日本の科学史
- 著者
- 道家 達将
- 出版者
- 公益財団法人 日本学術協力財団
- 雑誌
- 学術の動向 (ISSN:13423363)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, no.4, pp.51-55, 1996-07-01 (Released:2009-12-21)
1 0 0 0 OA 幼稚園教諭・保育士の成長過程に関する研究
- 著者
- 大熊 美佳子
- 雑誌
- 秋草学園短期大学紀要 (ISSN:09109374)
- 巻号頁・発行日
- no.33, pp.1-16, 2017-03-01
1 0 0 0 OA 志賀直哉『網走まで』を読む -「網走」という場所をめぐって-
- 著者
- 冨澤 成實
- 出版者
- 明治大学教養論集刊行会
- 雑誌
- 明治大学教養論集 (ISSN:03896005)
- 巻号頁・発行日
- vol.557, pp.23-34, 2021-09-30
1 0 0 0 OA 保育者としての成長過程に関する研究
- 著者
- 関谷 みのぶ 多川 則子 堀 美鈴
- 出版者
- 名古屋経済大学教育保育研究会
- 雑誌
- 教育保育研究紀要 = Journal of Education and Childcare (ISSN:24337676)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, pp.1-11, 2020-02-28
1 0 0 0 OA 社会福祉協議会の実践理論の変遷に関する一考察─社協創設期から1962 年までの考察─
- 著者
- 山下 順三
- 出版者
- 明治学院大学大学院社会学研究科社会福祉学専攻
- 雑誌
- 社会福祉学 (ISSN:09125035)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, pp.1-10, 2021-03-31
1 0 0 0 OA 「私」への「なぜ」という問いについて : 面接法による自我体験の報告から
- 著者
- 天谷 祐子
- 出版者
- 一般社団法人 日本発達心理学会
- 雑誌
- 発達心理学研究 (ISSN:09159029)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, no.3, pp.221-231, 2002-12-20 (Released:2017-07-20)
- 被引用文献数
- 3
「私はなぜ私なのか」「私はなぜ存在するのか」「私はどこから来たのか」「私はなぜ他の時代ではなくこの時代に生まれたのか」といった問い等,純粋に「この私」,世界も身体も剥ぎ取った純粋な「私」といった意味での「私」についての「なぜ」という問いが発せられる現象-自我体験-を解明することが本研究の目的である。自我体験が一般の「子ども」に見られるという仮定のもと,先行研究や哲学の存在論的問いを参考に,自我体験の下位側面を「存在への問い」「起源・場所への問い」「存在への感覚的違和感」と仮定した。そして中学生60名を対象として,半構造化面接法により自我体験の収集を行った結果,38名から51体験の自我体験が得られた。そして自我体験の3つの下位側面がそれぞれ報告され,小学校後半から中学にかけてを中心としたいわゆる「子ども」時代に初発することが示された。自我体験は子どもにとっては身近なものであることが示された。
- 著者
- 小畑 仁司 荻田 誠司 川上 真樹子 二村 元 杉江 亮
- 出版者
- 一般社団法人 日本脳卒中の外科学会
- 雑誌
- 脳卒中の外科 (ISSN:09145508)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, no.6, pp.445-450, 2017 (Released:2017-12-22)
- 参考文献数
- 23
- 被引用文献数
- 2 1
Fever in subarachnoid hemorrhage (SAH) is associated with vasospasm and poor outcome. To mitigate early brain damage in SAH, we have been treating World Federation of Neurological Surgeons (WFNS) Grade 5 patients with rapid induction of therapeutic hypothermia (TH) initiated immediately following onset of SAH and continued for approximately 7 days. Management after rewarming has been problematic. Rebound fever, especially during the period of post-SAH vasospasm, may increase the risk of cerebral infarction. We prospectively studied the feasibility and safety of endovascular cooling for maintaining prophylactic normothermia following initial TH in patients with severe SAH.TH (core body temperature 34.0°C) using surface cooling was initiated immediately after a diagnosis of WFNS Grade 5 SAH was made. All ruptured aneurysms were surgically clipped as soon as possible within 6 hours after arrival. At approximately postoperative day 7, after rewarming to 36°C, an endo- vascular catheter with 2 cooling balloons (Cool Line® Catheter, Asahi Kasei ZOLL Medical Corp., Tokyo, Japan) was inserted into the left internal jugular vein and connected to the Thermogard XP® Temperature Management System (Asahi Kasei ZOLL Medical Corp.) for the following 7 days. Temperature recordings in 11 SAH patients immediately before the period of endovascular cooling served as the control.Eleven patients (6 women; mean age of 63.8 ± 6.4 years [range, 50-73 years]) were enrolled in the study. Endovascular cooling was initiated at 7.9 ± 1.4 days (range, 6-11 days) after admission and continued for 6.7 ± 0.9 days (range 4-7 days). Unfavorable outcomes were associated with minimal shivering and good temperature control, whereas favorable outcomes were associated with vigorous shivering and increased temperature. Nine patients manifested shivering with increased temperature and were treated with acetaminophen, dexmedetomidine, and/or propofol. During the study period, two patients developed fevers above 38°C, and 8 of 11 patients without endovascular cooling developed fevers (p=0.03, two-tailed Fisher's exact test). There was no evidence of cerebral infarction related to vasospasm during endovascular cooling, and no catheter-related sepsis or thromboembolic events. In one patient, fasudil hydrochloride was administered intra-arterially for angiographic vasospasm, resulting in no cerebral infarction. In another patient, intensive treatment was withdrawn because of massive brain swelling; however, slight but extensive early ischemic change was retrospectively confirmed on computed tomography prior to endovascular cooling. Vasospasm-related cerebral infarction occurred in one patient 2 days after removal of the cooling catheter. In one patient, fatal bacterial meningitis related to spinal drainage occurred on Day 29. Three-month outcomes showed good recovery in 2, moderate disability in 4, severe disability in 2, vegetative state in 1, and death in 2. Amelioration of fever burden during the first 14 days after onset of SAH was safe and feasible with combined surface and endovascular cooling in patients with WFNS Grade 5 SAH.
1 0 0 0 OA 電子カルテデータを活用したAIホスピタルモデル構築の試み
- 著者
- 西村 邦宏
- 出版者
- 公益財団法人 日本心臓財団
- 雑誌
- 心臓 (ISSN:05864488)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.8, pp.794-799, 2019-08-15 (Released:2020-10-26)
- 参考文献数
- 5
1 0 0 0 OA 用語集の整備と情報モデルの開発,そして標準化
- 著者
- 小林 慎治
- 出版者
- 国立保健医療科学院
- 雑誌
- 保健医療科学 (ISSN:13476459)
- 巻号頁・発行日
- vol.68, no.3, pp.229-234, 2019 (Released:2019-09-14)
- 参考文献数
- 12
インターネットで大規模に収集されたデータを用いて,機械学習をベースとした人工知能技術が発展し,創造的価値が生み出されつつある.医療分野においも国家レベルで診療データを収集し,保健行政や臨床研究,創薬に役立てていこうとする試みが世界各国で進められてきた.日本においても診療データの二次利用に向けて法制度が進められると同時に,普及が進んだ電子カルテから診療情報を大規模に収集する事業が国家的プロジェクトとして進められている.しかしながら,電子カルテのデータを収集すること,そしてそのデータを活用していくことは実際にはそう簡単ではない.関心のあるデータを特定の用語を使って高速に検索してデータを収集することは電子化のメリットの一つであるが,診療データに記録されている用語が標準化されておらず,効率よくデータを検索できないなどの問題がある.そのため医学用語集の整備と標準化が進められており,複数の用語でも効率よく対応できるシソーラスやタキソノミーの開発や,知識工学を応用したオントロジーの開発も進められている.さらに,概念の構造と用語の関係を明示した情報モデルの開発により,質の高い情報基盤の整備へと発展しつつある.本稿では臨床情報を機械的に処理する際の問題点とその解決法として,用語と情報モデルについて解説し,その標準化について概説する.
1 0 0 0 OA 集中豪雨下の道路冠水状態と交通動画シミュレーションの開発
- 著者
- 坂本 淳 藤田 素弘 鈴木 弘司 三田村 純
- 出版者
- Geographic Information Systems Association
- 雑誌
- GIS-理論と応用 (ISSN:13405381)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, no.1, pp.9-19, 2006-06-30 (Released:2009-05-29)
- 参考文献数
- 9
Natural disaster might cause traffic congestion, changing traffic network. In this paper, we propose the way of developing the road condition analysis, animated traffic simulations of GIS and apply to the traffic situation under the Tokai downpour by using travel survey and tachometer of the drivers who had been driving under the disaster, from 9.11 to 9.12, 2000. As a result, it was revealed that many drivers who had driven at that time had involved chronic traffic jam and it took many hours to reach to destination.
1 0 0 0 OA 崖災害対策へのGISの活用
- 著者
- 川崎 昭如 服部 一樹 浦川 豪 中島 徹也 佐土原 聡
- 出版者
- Geographic Information Systems Association
- 雑誌
- GIS-理論と応用 (ISSN:13405381)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, no.2, pp.25-32, 2001-09-30 (Released:2009-05-29)
- 参考文献数
- 10
- 被引用文献数
- 3 1
Two methods and a system for the measure against slope failure disaster using GIS are proposed in this paper. 1) Method of extracting cliff and potential area, suffered from slope failure, by DEM and Landuse data. 2) Method of extracting potential slope failure area by rainfall data, and a system of conveying this information to local residents. These methods can be applied to many places where these data are available. Moreover, dangerous cliffs and the areas are extracted at the same time even in wide city area. These methods will allow us to extract dangerous cliff and area without fieldwork, and this information will help local residents with proper actions. Minami ward, Yokohama city, was selected as a study area.
1 0 0 0 OA 力触覚のあるロボット
- 著者
- 大西 公平 溝口 貴弘 下野 誠通
- 出版者
- 一般社団法人 日本人工臓器学会
- 雑誌
- 人工臓器 (ISSN:03000818)
- 巻号頁・発行日
- vol.47, no.1, pp.52-57, 2018-06-15 (Released:2018-09-15)
- 参考文献数
- 6
1 0 0 0 OA オフセットインキ
- 著者
- 村中 武雄
- 出版者
- 一般社団法人 色材協会
- 雑誌
- 色材協会誌 (ISSN:0010180X)
- 巻号頁・発行日
- vol.70, no.2, pp.132-142, 1997-02-20 (Released:2012-11-20)
- 参考文献数
- 18
- 被引用文献数
- 1 1
1 0 0 0 よくわかるリベンジポルノ防止法
- 著者
- 平沢勝栄 三原じゅん子 山下貴司編著
- 出版者
- 立花書房
- 巻号頁・発行日
- 2016