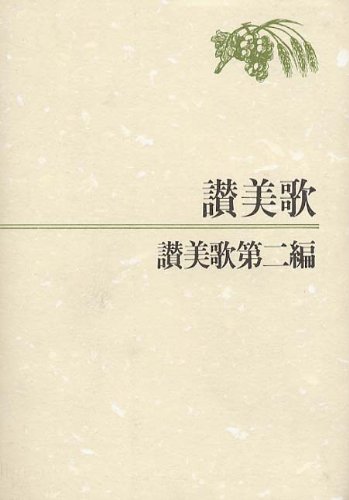1 0 0 0 OA <論考>いまだ悪夢から覚めることができない:新しい難民認定制度と難民申請者の現在
- 著者
- 西中 誠一郎
- 出版者
- 大阪経済法科大学アジア太平洋研究センター
- 雑誌
- アジア太平洋研究センター年報 = CAPP Report (ISSN:13491997)
- 巻号頁・発行日
- no.3, pp.9-15, 2006-03-20
1 0 0 0 OA 難民及び難民申請者と地域福祉 : 最近の事例からの検討
- 著者
- 森 恭子
- 出版者
- 文教大学
- 雑誌
- 生活科学研究 = Bulletin of Living Science (ISSN:02852454)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, pp.151-161, 2013-03-01
日本は2010年より第三国定住を試験的に開始した。しかし、すでにインドシナ難民以外の新たな難民/申請者が長期間滞在しており、その社会的支援は制限されている。彼らは政府の十分な支援がなく、日本の地域社会とどのように関わりながら、「サバイバル」しているのだろうか。 本小論では、難民/申請者の日本の地域社会との関係について焦点を絞り、近年の難民に関する調査報告、定期刊行物、報道、筆者の経験等の断片的な情報や知識をつなぎ合わせ、そこから垣間見る様相を描くことを目的とし、今後のフィールド調査への足掛かりとするものである。同時に、ソーシャル・キャピタル(社会関係資本)を重視することを踏まえ、社会統合を意図した支援に向けて若干の示唆を与えた。難民/申請者は地域社会の中で孤立しており、社会資源からも排除されていること、しかし一方で、地域住民からの支援を得たり、東日本大震災を通して日本の一員として貢献したい意欲などもみられる。政府が現在進めている生活支援戦略における中間的就労や社会的孤立の予防を視野にいれた地域福祉施策の中で、その対象範囲を難民/申請者にも広げ、メインの支援体制の中に組み入れていくことが必要である。そこでは地域福祉推進の主たる担い手である社会福祉協議会や民生委員等の積極的な介入が期待される。 \n The Japanese government introduced its third-country resettlement pilot project in 2010 in trial basis. New types of refugees and asylum seekers except Indo-Chinese refugees, however, have lived in Japan for long time and there has been a limitation of social support. How they have survived in local Japanese community without sufficient supports by the government? This short paper focused on the relationship between refugee/asylum seekers and local Japanese community and aimed to draw a sketch of life situation through fragmental information of research reports, periodical documents, the press regarding refugees/asylum seekers and author's experiences in order to gain a footing a field research of them in future. Also, the paper made some suggestion for support intended to promote social integration, based on the importance of social capital. Their social isolation in local community and social exclusion from social resources were brought out and it was founded that some of them were supported by local Japanese residents and had feelings of contribution to Japanese society as one of members composed in this society through the experiences of the Great East Japan Earthquake. It could be necessary to incorporate refugees/asylum seekers' support into the mainstream welfare support system including the internship program for finding employment under the strategies of life support which the government just started currently, and the prevention of social isolation under the community care system. The intervention in refugee/asylum seekers' support by the Councils of Social Welfare and Welfare volunteers , who are main leaders to promote community care, would be expected strongly.
1 0 0 0 OA <研究ノート>日韓における難民申請者等への対応-法的地位と公的支援を中心に-
- 著者
- 呉 泰 成
- 出版者
- 大阪経済法科大学アジア研究所
- 雑誌
- 東アジア研究 = East Asian Studies (ISSN:13404717)
- 巻号頁・発行日
- no.73, pp.47-64, 2020-03-31
1 0 0 0 OA 高リン鉄鉱石からの直接脱リン
- 著者
- 雀部 実 飯田 佳未 横尾 友美
- 出版者
- 一般社団法人 日本鉄鋼協会
- 雑誌
- 鉄と鋼 (ISSN:00211575)
- 巻号頁・発行日
- vol.100, no.2, pp.325-330, 2014 (Released:2014-01-31)
- 参考文献数
- 9
- 被引用文献数
- 7 7
Iron ore containing higher concentration of phosphorus is reduced by hydrogen gas containing water vapor. 13% of removing yield of phosphorus is obtained. It is observed that removing rate of phosphorus can be expressed as apparent 1st order reaction equation. The reaction rate equation is divided into two parts. Rate constant of the former reaction is about 10 time larger than that of the latter equation. It is estimated on the basis of a previous research result that phosphorus removed from iron oxide is gaseous phosphorus and form of remained phosphorus is Fe2P.
1 0 0 0 OA 死をめぐる言説 : 「フランドン農学校の豚」を読む(読む)
- 著者
- 押野 武志
- 出版者
- 日本文学協会
- 雑誌
- 日本文学 (ISSN:03869903)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, no.12, pp.30-34, 1994-12-10 (Released:2017-08-01)
1 0 0 0 OA 咀嚼筋腱・腱膜過形成症のMR画像診断の現状
- 著者
- 小林 馨 下田 信治 依田 哲也 覚道 健治
- 出版者
- 一般社団法人 日本顎関節学会
- 雑誌
- 日本顎関節学会雑誌 (ISSN:09153004)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.1, pp.35-39, 2009 (Released:2012-02-15)
- 参考文献数
- 8
- 被引用文献数
- 3
1 0 0 0 OA 東洋文庫年報2021年度
- 出版者
- 東洋文庫
- 雑誌
- 東洋文庫年報 = Toyo Bunko nenpō (ISSN:27585077)
- 巻号頁・発行日
- vol.2021, 2023-03-16
1 0 0 0 OA 肝腫瘤で発見された消化管外アニサキス症の1例
- 著者
- 森田 道 曽山 明彦 高槻 光寿 黒木 保 安倍 邦子 林 徳真吉 兼松 隆之 江口 晋
- 出版者
- 日本臨床外科学会
- 雑誌
- 日本臨床外科学会雑誌 (ISSN:13452843)
- 巻号頁・発行日
- vol.74, no.2, pp.483-487, 2013 (Released:2013-08-25)
- 参考文献数
- 8
- 被引用文献数
- 5 7
59歳,女性.主訴はなし.検診目的の腹部超音波検査で肝腫瘤を指摘され当科紹介となった.腹部造影CTでは肝外側区域から肝外に突出する造影効果に乏しい腫瘤を認めた.肝腫瘍の他,肝胃間膜内発生の悪性リンパ腫や胃GIST,炎症性腫瘤との鑑別が困難であり,診断的意義も含め腹腔鏡下腫瘤摘出術を施行した.術中所見では腫瘤は肝胃間膜内に肝外側区域背側に接するように存在していた.腫瘤と接する肝外側区域を一部合併切除し腫瘤を摘出した.病理組織所見は変性壊死を中心とした好酸球性肉芽腫で,内部にアニサキス虫体を認め消化管外アニサキス症と診断した.アニサキス症の多くは消化管に発生し激烈な腹痛を特徴とするが,初回感染では本症例のように無症状で消化管壁を穿通し消化管外アニサキス症として発見される例の報告もある.発見契機としては,絞扼性イレウス,膵腫瘤などの報告があるが,肝腫瘤として発見された例は国内では5例と稀である.
1 0 0 0 OA 葉のさまざま
- 著者
- 吉良 竜夫
- 出版者
- 公益財団法人 国際緑化推進センター
- 雑誌
- 熱帯林業 (ISSN:09105115)
- 巻号頁・発行日
- no.42, pp.23, 1976-10-20 (Released:2023-03-04)
1 0 0 0 OA 日米欧の高血圧診療ガイドラインにおける医療経済評価の活用状況について
- 著者
- 伊藤 かおる 池田 俊也
- 出版者
- 国際医療福祉大学学会
- 雑誌
- 国際医療福祉大学学会誌 = Journal of the International University of Health and Welfare (ISSN:21863652)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.1, pp.101-109, 2016-03-31
日米欧の主要な診療ガイドラインにおける推奨降圧薬とその決定過程において,医療経済的視点がどの程度反映されているかを検討した.その結果,欧州高血圧学会/ 欧州心臓病学会(ESH/ESC)2013 はすべての降圧薬が対象にされており,患者の臨床的・社会的背景に応じて個別に薬物治療を行うよう記載されていた.日本高血圧学会(JSH)2014,米国合同委員会(JNC8),英国保健医療研究所/ 英国高血圧学会(NICE/BHS)2011 は4 種類が推奨されていた.推奨降圧薬の決定根拠として,JNC8,ESH/ESC2013 は医療経済学的視点による記述はほとんどなく,臨床的エビデンスを基に推奨降圧薬の決定をしていた.JSH2014 は医療経済評価を行った文献は紹介されていたが,推奨薬の決定根拠には反映されていなかった.NICE/BHS2011 では評価指標として費用効果分析を実施し,その結果から具体的で明確な薬物治療の方針を提示していた.高血圧治療の標準化と効率化を図るために,わが国においても医療経済評価の結果を反映した診療ガイドラインの必要性があると考えられた.
1 0 0 0 OA 朱印船のアジア史的研究:16~17世紀、日本往来の「国書」と外交使節
- 著者
- 松方 冬子 蓮田 隆志 橋本 雄 岡本 真 彭 浩 高野 香子 川口 洋史 木村 可奈子 清水 有子 原田 亜希子 北川 香子 西澤 美穂子
- 出版者
- 東京大学
- 雑誌
- 基盤研究(B)
- 巻号頁・発行日
- 2015-04-01
主たる成果として、松方冬子編『国書がむすぶ外交』(東京大学出版会、2019年)を刊行し、前近代のユーラシアの全域にみられた「国書外交」とその周辺にあった通航証について明らかにした。おもな論点は、今までtributary system(華夷秩序・朝貢体制・東アジア国際秩序などと訳される)と呼ばれてきたものは、その実態からみるならば国書外交と呼べるものであること、国と国をつなぐ仲介者(商人や宗教者、国書の運び手となることが多い)の役割が重要であること、である。台湾の中央研究院で日明勘合底簿の手掛かりとなる史料を発見するなど、多くの実証的な新知見を明らかにした。
1 0 0 0 大原社会問題研究所雑誌
- 著者
- 法政大学大原社会問題研究所 [編集]
- 出版者
- 法政大学出版局 (発売)
- 巻号頁・発行日
- 1986
1 0 0 0 OA 選擇集新考
- 著者
- 福井 康順
- 出版者
- Japanese Association of Indian and Buddhist Studies
- 雑誌
- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, no.2, pp.405-419, 1962-03-31 (Released:2010-03-09)
1 0 0 0 讃美歌 : 讃美歌第二編
- 著者
- 日本基督教団讃美歌委員会編
- 出版者
- 日本基督教団出版局
- 巻号頁・発行日
- 1971
1 0 0 0 讃美歌略解
- 著者
- 日本基督教団讃美歌委員会編
- 出版者
- 日本基督教団出版局
- 巻号頁・発行日
- 1986