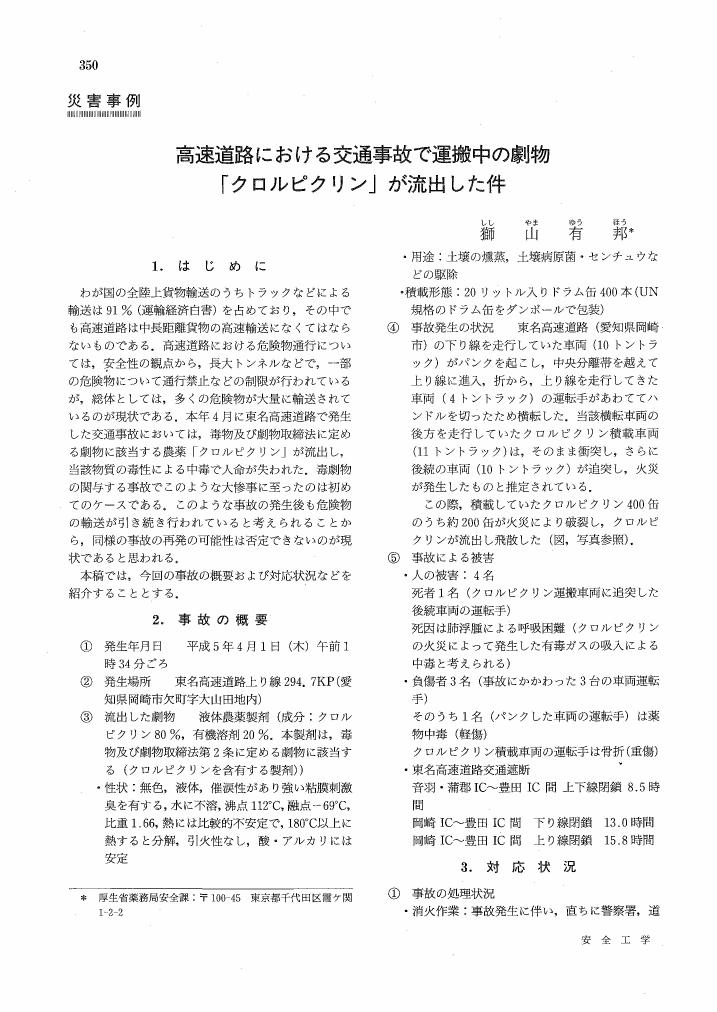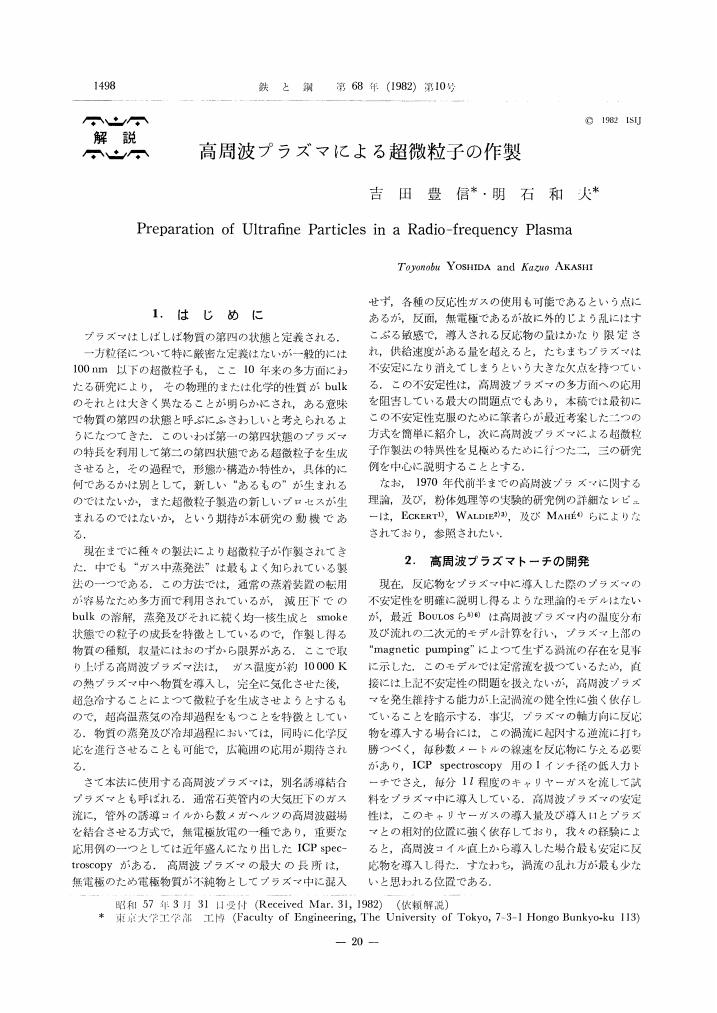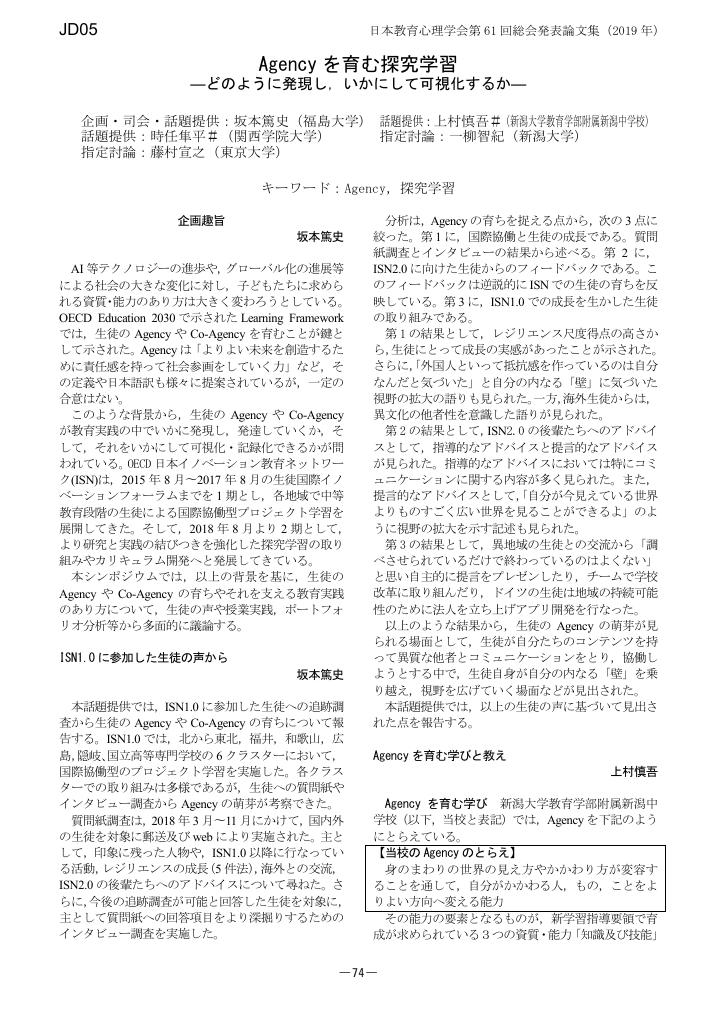- 著者
- 田島 敬之 原田 和弘 小熊 祐子 澤田 亨
- 出版者
- 日本公衆衛生学会
- 雑誌
- 日本公衆衛生雑誌 (ISSN:05461766)
- 巻号頁・発行日
- vol.69, no.10, pp.790-804, 2022-10-15 (Released:2022-10-01)
- 参考文献数
- 42
目的 本研究では,アクティブガイドの認知・知識・信念・行動意図の現状と,身体活動・座位行動,個人属性との関連を明らかにする。方法 オンライン調査会社に登録する20~69歳のモニター7,000人を対象に,横断的調査を実施した。アクティブガイドの認知は,純粋想起法と助成想起法により,知識は「1日の推奨活動時間(18~64歳/65歳以上)」と「今から増やすべき身体活動時間(プラス・テン)」を数値回答で調査した。信念と行動意図はアクティブガイドに対応する形で新たに尺度を作成し,信念の合計得点と行動意図を有する者の割合を算出した。身体活動は多目的コホート研究(JPHC study)の身体活動質問票から中高強度身体活動量を,特定健診・保健指導の標準的な質問票から活動レベルを算出した。座位行動は国際標準化身体活動質問表(IPAQ)日本語版を使用した。記述的要約を実施した後,従属変数を認知・知識・信念・行動意図のそれぞれの項目,独立変数を身体活動量,座位行動,個人属性(性別,年代,BMI,配偶者の有無,教育歴,仕事の有無,世帯収入)とし,ロジスティック回帰分析でこれらの関連を検討した。結果 アクティブガイドの認知率は純粋想起法で1.7%,助成想起法で5.3~13.4%であった。知識の正答率は,「1日の推奨活動時間(18~64歳)」で37.2%,「1日の身体活動時間(65歳以上)」で7.0%,「プラス・テン」で24.8%,3項目すべて正答で2.6%だった。信念の中央値(四分位範囲)は21(16~25)点であった(32点満点)。行動意図を有する者は,「1日の推奨活動量」で51.4%,「プラス・テン」で66.9%だった。ロジスティック回帰分析の結果,認知・知識・信念・行動意図は中高強度身体活動量や活動レベルでいずれも正の関連が観察された一方で,座位行動では一貫した関連は観察されなかった。個人属性は,評価項目によって異なるが,主に年代や教育歴,仕事の有無,世帯年収との関連を認めた。結論 本研究より,アクティブガイドの認知や知識を有する者は未だ少ない現状が明らかとなった。さらにアクティブガイドの認知・知識・信念・行動意図を有する者は身体活動量が多いことが明らかとなったが,座位行動は一貫した関連が観察されず,この点はさらなる調査が必要である。さらに,今後は経時的な定点調査も求められる。
- 著者
- 大森 信
- 出版者
- 日本サンゴ礁学会
- 雑誌
- 日本サンゴ礁学会誌 (ISSN:13451421)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, no.1, pp.1-9, 2016 (Released:2016-10-13)
- 参考文献数
- 23
- 被引用文献数
- 2 2
いろいろなさんご礁修復再生事業や港湾開発に伴うサンゴ移設事業でサンゴ幼生の着生基盤として採用され,大量に用いられている連結式サンゴ幼生着床具CSD(Okamoto et al. 2008)はそれほど効果のある人造基盤ではない。CSDをほかの3種の基盤(ホタテガイ貝殻,素焼き褐色陶板,自然分解樹脂ネット)と比較した結果,幼生の着生数密度は何れの場所でも素焼き褐色陶板がもっとも高かった。6ヶ月後の稚サンゴの生残率はCSDがほかの基盤より勝った。今日では明らかなことであるが,幼生の多くは基盤の表面に生じたサンゴモ(無節石灰藻)やバクテリアフィルムからの特定の化学シグナルの刺激によって着生・変態するのであって,基盤の素材は結果を左右する要因にはならない。着生・変態の過程は,1)着生シグナル受容→2)着生行動→3)着生→4)変態,の4段階からなる。基盤の評価は,1)着生・変態,2.育成,3.植え込み,4.その後,の4段階を総合してなされるべきである。幼生の着生率や着生後の生残率は基盤の構造や形状の物理的特性にも影響される。平板な基盤の場合は,サンゴは縁辺部に付きやすく,水平面より鉛直面での生存率が高い。また,稚サンゴがウニや魚類の食害から逃れやすい構造であるものが望ましい。最良の人造基盤は,サンゴ幼生の着生・変態への誘引効果をもつばかりではなく,着生後の生残率が高く,さらに,植え込み作業や運搬が容易で,波浪に強く,はがれにくいものである。
- 著者
- Aika Okazawa Mami Iima Masako Kataoka Ryosuke Okumura Sachiko Takahara Tomotaka Noda Taro Nishi Takayoshi Ishimori Yuji Nakamoto
- 出版者
- Japanese Society for Magnetic Resonance in Medicine
- 雑誌
- Magnetic Resonance in Medical Sciences (ISSN:13473182)
- 巻号頁・発行日
- pp.mp.2022-0056, (Released:2023-05-26)
- 参考文献数
- 17
Purpose: We aimed to investigate the diagnostic feasibility of an adjusted diffusion-weighted imaging (DWI) lexicon using multiple b values to assess breast lesions according to DWI-based breast imaging reporting and data system (BI-RADS).Methods: This Institutional Review Board (IRB)-approved prospective study included 127 patients with suspected breast cancer. Breast MRI was performed using a 3T scanner. Breast DW images were acquired using five b-values of 0, 200, 800, 1000, and 1500 s/mm2 (5b-value DWI) on 3T MRI. Two readers independently assessed lesion characteristics and normal breast tissue using DWI alone (5b-value DWI and 2b-value DWI with b = 0 and 800 s/mm2) according to DWI-based BI-RADS and in combination with the standard dynamic contrast-enhanced images (combined MRI). Interobserver and intermethod agreements were assessed using kappa statistics. The specificity and sensitivity of lesion classification were evaluated.Results: Ninety-five breast lesions (39 malignant and 56 benign) were evaluated. Interobserver agreement for lesion assessment on 5b-value DWI was very good (k ≥ 0.82) for DWI-based BI-RADS categories, lesion type, and mass characteristics; good (k = 0.75) in breast composition; and moderate (k ≥ 0.44) in background parenchymal signal (BPS) and non-mass distribution. Intermethod agreement between assessments performed using either 5b-value DWI or combined MRI was good-to-moderate (k = 0.52–0.67) for lesion type; moderate (k = 0.49–0.59) for DWI-based BI-RADS category and mass characteristics; and fair (k = 0.25–0.40) for mass shape, BPS, and breast composition. The sensitivity and positive predictive values (PPVs) for 5b-value DWI were 79.5%, 84.6% and 60.8%, 61.1% for each reader, respectively; 74.4%, 74.4% and 63.0%, 61.7% for 2b-value DWI; and 97.4%, 97.4% and 73.1%, 76.0% for combined MRI. The specificity and negative predictive values (NPVs) were 64.3%, 62.5% and 81.8%, 85.4% for 5b-value DWI; 69.6%, 67.9% and 79.6%, 79.2% for 2b-value DWI; and 75.0%, 78.6% and 97.7%, 97.8% for combined MRI.Conclusion: Good observer agreement was observed in the 5b-value DWI. The 5b-value DWI based on multiple b-values might have the potential to complement the 2b-value DWI; however, their diagnostic performance tended to be inferior to that of combined MRI for the characterization of breast tumors.
1 0 0 0 OA 臭気の官能試験におけるパネル評価の信頼性と統計的特性
- 著者
- 竹村 明久 山中 俊夫 相良 和伸 甲谷 寿史 桃井 良尚
- 出版者
- 日本建築学会
- 雑誌
- 日本建築学会環境系論文集 (ISSN:13480685)
- 巻号頁・発行日
- vol.77, no.673, pp.153-159, 2012-03-30 (Released:2012-07-02)
- 参考文献数
- 13
It is necessary to prepare a plenty of subjects in order to ensure the statistical confidence in the sensory evaluation of odor. Therefore, it is convenient if the minimum number of subjects can be prepared according to the necessary accuracy of measurement. In this paper, the sensory evaluation experiment with 1-butanol was conducted and evaluations by six subjects were compared with those by sixty subjects under the same sixty votes in total. Moreover, confidence intervals of intensity and percentage of person dissatisfied were estimated, and relationships between confidence intervals and the number of subjects were indicated.
1 0 0 0 OA 地域における継承的アーカイブと学習材としての活用⑷ -昭和館を事例として-
- 著者
- 外池 智 TONOIKE Satoshi
- 出版者
- 秋田大学教育文化学部附属教職高度化センター
- 雑誌
- 秋田大学教育文化学部教育実践研究紀要 (ISSN:24328871)
- 巻号頁・発行日
- no.44, pp.1-13, 2022-03-31
「本研究の目的」も含めて,以下本稿の概要を述べる.本研究は,2009(平成21)年 度から推進している戦争遺跡に関する研究1,2012(平成24)年度から推進している戦争 体験の「語り」の継承に関する研究2,2015(平成27)年度から推進している継承的アー カイブを活用した「次世代の平和教育」の展開に関する研究3 の継続研究であり,さらに 2018(平成30)年度から取り組んでいる地域の継承的アーカイブと学習材としての活用に 関する研究4 の一端を発表するものである. 戦後76年の歳月が経ち,戦争体験を語れる終戦時の年齢を仮に10歳とすれば,もはやそ の人口は全人口の5 %以下となった.こうした状況の中,あの貴重な体験や記憶を残し, 継承していこうとする試みが続いている.また教育現場においても,直接的な戦争体験の 「語り」ではなく,そうした継承的アーカイブを活用したいわば「次世代の平和教育5」と 呼ぶべき実践が次々と展開されている. こうした状況を踏まえ,本稿では,戦争遺物の学習材としての活用,そして戦争体験の「語 り」の継承について,特に今回は東京都の昭和館に注目し,昭和館の学校教育に関わる事 業や「語り部」養成事業,そして昭和館を活用した地元小学校における教育実践を取り上 げ検討したい.his study is based on research on war ruins that have been promoted since 2009, on the succession of "narratives" of war experiences that have been promoted since 2012, and from 2015. This is a continuing study on the development of "nextgeneration peace education" utilizing the inherited archives, and presents a part of the research on the use of "next-generation peace education" as an inherited archive and learning material in the region that we have been working on since 2018. After 74 years of the war, if the age at the end of the war, which can be talked about the war experience, is 10 years old, the population is no longer about 8% of the total population. In this situation, attempts to preserve those precious experiences and memories and try to inherit them continue. In addition, in the educational field, rather than the "story" of the direct war experience, so to speak, the practice to be called "the next generation of peace education" utilizing such an inherited archive is being developed one after another. In light of this situation, this paper will focus on the use of war relics as a learning material and the succession of "storytelling" of war experiences, and this time I would like to focus on Showakan in Tokyo, and take up and examine the school education-related business of Showakan, the "storytelling department" training project, and the educational practice at local elementary schools using Showakan.
1 0 0 0 成長期の運動不足は認知症発症リスクを高めるか?
本研究では、成長期、特に発達早期の運動不足が将来的な認知機能に悪影響を及ぼす可能性について検討を行い、その対抗策の基盤となる分子メカニズムの解明を目指す。初年度は、生活習慣病に起因した認知機能低下を想定し,2型糖尿病を誘導するモデルラットを対象に、通常飼育群、活動制限による運動不足群を設定し、成長期の運動不足が成年期以降の認知機能に影響するか否かについて、エピジェネティック制御機構の観点から解明する。2年目以降は、成長期の中でも最も脳の可塑性が活発な発達早期における運動不足経験がその後の認知機能の変化に及ぼす否かについて実験動物を用いて検討する。
1 0 0 0 ランボー全詩集
- 著者
- アルチュール・ランボー著 宇佐美斉訳
- 出版者
- 筑摩書房
- 巻号頁・発行日
- 1996
1 0 0 0 OA 高速道路における交通事故で運搬中の劇物 「クロルピクリン」が流出した件
- 著者
- 獅山 有邦
- 出版者
- 安全工学会
- 雑誌
- 安全工学 (ISSN:05704480)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.5, pp.350-352, 1993-10-15 (Released:2017-07-31)
1 0 0 0 OA 「家屋もしくは邸館」:ルネサンス期フィレンツェにおけるパラッツォの社会的機能と意義
- 著者
- 金山 弘昌
- 出版者
- 学校法人 開智学園 開智国際大学
- 雑誌
- 日本橋学館大学紀要 (ISSN:13480154)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, pp.29-49, 2007-03-01 (Released:2018-02-07)
- 被引用文献数
- 1
ジョヴァンニ・ルチェッラーイは有名な『雑記帳』の中で、「人の一生で一番重要なことはふたつある。第一は子を産むこと。そして第二は家を建てること」と記している。この言葉はルネサンスの有力者たちが自分たちの邸館に期待していた社会的な重要性について明らかにしている。本稿では、このテーマ、すなわちルネサンス期フィレンツェの パラッツォが持つ社会的機能と意義について概観を試みる。この目的のため、ゴールドスウェイト、F・W・ケント、プレイヤーらの主要な研究に沿いつつ、とりわけこのような活発な建設事業を許した、あるいは推進した倫理的基盤について、そして中世のコンソルテリーア解体後にルネサンス社会が被った、社会や家族の絆の劇的な変動の影響について検討する。社会的変動の影響については、とりわけゴールドスウェイトの仮説に関わる論争についての検証を試みる。すなわち、巨大な規模と豊かな装飾をもつルネサンスのパラッツォは、本当に「施主とその核家族のためのプライヴェートな隠れ家」なのか、それともケントが考えるように、「隣人、友人、親戚」、つまりクリエンテーラの政治的・社会的中核なのか、という論議である。パラッツォの建築的特徴と同時代の史料の検討から、ケント説の妥当性を認めることができる。さらに、パラッツォの大きさや芸術的性格は、中世のコンソルテリーアの基盤となっていた血縁と共住による物理的な絆の代替となって、個人間の関係として成立した新たな社会的ネットワークを表象する、象徴的な価値となっていたと考えられるのである。
- 著者
- 山内 基一 島崎 真一 小林 純一 下司 昌一 渡辺 三枝子 橋本 幸晴
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育心理学会
- 雑誌
- 日本教育心理学会総会発表論文集 第17回総会発表論文集 (ISSN:21895538)
- 巻号頁・発行日
- pp.376-377, 1975-08-10 (Released:2017-03-30)
1 0 0 0 OA 抵抗としての嗜好品 なぜ精神科医がビール醸造に挑むのか
- 著者
- 高木 俊介
- 出版者
- 嗜好品文化研究会
- 雑誌
- 嗜好品文化研究 (ISSN:24320862)
- 巻号頁・発行日
- vol.2021, no.6, pp.33-44, 2021 (Released:2022-06-30)
- 著者
- 針貝 真理子
- 出版者
- 日本演劇学会
- 雑誌
- 演劇学論集 日本演劇学会紀要 (ISSN:13482815)
- 巻号頁・発行日
- vol.67, pp.9-29, 2019-03-15 (Released:2019-03-20)
The concept of the “postdramatic” theatre proposed by Hans-Thies Lehmann and performances within the so-called “Flemish Wave” have influenced each other. Lehmann's concept does not criticize the use of literary texts in theatrical plays but rather the concept of the “dramatic”, which stresses actions springing from a conflict between a character (subject) and a community, or between subjects. Postdramatic theatre questions the notion of an acting subject.An extreme example of this questioning can be found in The Lobster Shop by Needcompany, one of the most important Flemish performance groups. The piece, which is aimed at building a theatrical place of the “future”, shows, according to Nicolas Truong, “the end of grand narratives and the blotting out of ideological alternatives to global capitalism”. What merely seems to be the central plot told by the performers is full of contradictions and is interrupted again and again by marginalized characters. In these interruptions, the play gives priority to the marginalized subalterns who are forgotten in “grand narratives” and exploited in the system of global capitalism.In the last scene, a subaltern character, who appears threatening but at the same time pitiful, remains alone on stage. An excess of incomprehensible images in this character transcends the idea of a dramatic or performing subject. At this moment neither an acting subject nor any shared future has yet been performatively produced, but these are, in the words of Werner Hamacher, “afformatively” interrupted. Postdramatic theatre emphasizes the importance of this “afformative” dimension which calls a “strike” at the “factory” of performative success within a compulsive capitalism.
1 0 0 0 OA 糖尿病性踵骨骨髄炎に対する PTB 装具の有用性
- 著者
- 庄司 真美 桑原 大彰 小川 令 赤石 愉史
- 出版者
- 一般社団法人 日本創傷外科学会
- 雑誌
- 創傷 (ISSN:1884880X)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, no.2, pp.67-70, 2023 (Released:2023-04-01)
- 参考文献数
- 15
1 0 0 0 OA 小画面ディスプレイに適した日本語フォントの可読性と判別性に関する研究
- 著者
- 楊 寧 須長 正治 藤 紀里子 伊原 久裕
- 出版者
- 一般社団法人 日本デザイン学会
- 雑誌
- デザイン学研究 (ISSN:09108173)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.2, pp.2_19-2_28, 2019-09-30 (Released:2019-12-25)
- 参考文献数
- 9
本研究では,小画面ディスプレイ,特にApple Watchを想定し,その画面表示環境下にて,日本語フォントの可読性と判別性を測定した。さらに,フォントの形態属性および差分についても調査を行い,小画面表示に適した読みやすく見やすいフォントの属性を探った。可読性に関しては,短文,連続文(大),連続文(小)の3つの提示条件ともに,濃度と字面面積の大きさから影響を受けていることがわかった。ただし,白背景か黒背景かによって,字面面積と濃度の直接影響の有無はまちまちであった。判別性に関しては,混同しやすい文字対を選定し,文字対を特定できる実験方法を用いて実験を行った。その結果,各フォントの特定の文字対の判別性を確認できた。また,差分分析を行った結果,ひらがなより,カタカナや英数字のような単純な文字対については,差分からの影響が明確であり,特定の文字対の字形の特徴も確認できた。
1 0 0 0 OA インクルーシブ教育へ向けての一提案 ー初級日本語クラスの留学生を対象としてー
- 著者
- 野口 逸美 中谷 舞知子
- 出版者
- 日本語教育方法研究会
- 雑誌
- 日本語教育方法研究会誌 (ISSN:18813968)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, no.1, pp.10-11, 2021 (Released:2021-08-12)
- 参考文献数
- 3
Recently supports for children with developmental disabilities has been improved at educational sites in Japan. On the other hand, it is far from satisfaction in the field of Japanese education for students from abroad. Nevertheless, efforts can be confirmed such as to adjust fonts and sizes of letters and to increase pair or group activities. Authors investigated if these supports are useful for university exchange students. It revealed that their problems are too multifarious to be responded with uniform methods. It is essential to ascertain what they are perplexed by and what kind of supports are required. It is desired to examine and implement effective methods constantly.
1 0 0 0 OA J.S.フィシュキン著, 曽根泰教監修, 岩木貴子訳, 民主主義理論と現実を架橋する実験:討論型世論調査『人々の声が響き合うとき-熟議空間と民主主義』, 早川書房, 2011.4
- 著者
- 林 香里
- 出版者
- 公益財団法人 日本世論調査協会
- 雑誌
- 日本世論調査協会報「よろん」 (ISSN:21894531)
- 巻号頁・発行日
- vol.108, pp.48-52, 2011-10-31 (Released:2017-03-31)
1 0 0 0 OA 大根種子の低温感応と湿度との関係
- 著者
- 井上 頼数 渋谷 正夫 鈴木 芳夫
- 出版者
- Japanese Society of Breeding
- 雑誌
- 育種学雑誌 (ISSN:05363683)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, no.3, pp.202-206, 1955-12-25 (Released:2008-05-16)
- 参考文献数
- 13
In order to study the effect of moisture on the vernalization of seed in Japanese radish, Rapfaaleus sativus L., some experiirnents, were held in 1951, usingi the stock seed of. Nerima-shiriboso variety. In each treatment, the seed was placed, in Petris dish which was put in desicator. Moisture treatments were as follows:,
1 0 0 0 OA 高周波プラズマによる超微粒子の作製
- 著者
- 吉田 豊信 明石 和夫
- 出版者
- The Iron and Steel Institute of Japan
- 雑誌
- 鉄と鋼 (ISSN:00211575)
- 巻号頁・発行日
- vol.68, no.10, pp.1498-1502, 1982-08-01 (Released:2009-06-19)
- 参考文献数
- 28
- 被引用文献数
- 2 4
1 0 0 0 OA 中国の大学改革
- 著者
- 小林 立
- 出版者
- 香川大学一般教育部
- 雑誌
- 香川大学一般教育研究 = Studies in general education, Kagawa University (ISSN:03893006)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, pp.1-23, 1976-10-01
1 0 0 0 OA Agencyを育む探究学習 どのように発現し,いかにして可視化するか
- 著者
- 坂本 篤史 上村 慎吾 時任 隼平 一柳 智紀 藤村 宣之
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育心理学会
- 雑誌
- 日本教育心理学会総会発表論文集 第61回総会発表論文集 (ISSN:21895538)
- 巻号頁・発行日
- pp.74, 2019 (Released:2020-03-21)