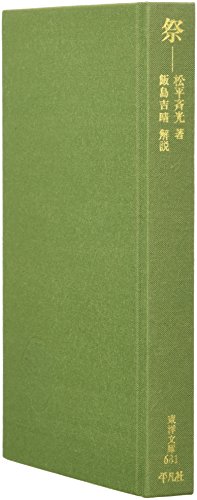1 0 0 0 近代ヨーロッパの政治と思想
1 0 0 0 フランス啓蒙思想の研究
1 0 0 0 OA 若者向け競馬アプリケーションのデザイン
- 著者
- 村井 貴行 山崎 和彦
- 出版者
- Japanese Society for the Science of Design
- 雑誌
- 日本デザイン学会研究発表大会概要集
- 巻号頁・発行日
- pp.189, 2014 (Released:2014-07-04)
本研究は「若者向け競馬アプリケーションの提案」というテーマで、これから競馬を始める初心者向けの競馬アプリケーションを提案する。本研究では対象とするユーザがアプリケーションを通して魅力的な競馬体験ができることを目標とする。本研究の背景は、競馬はイギリス発祥の紳士のスポーツであるが、日本の競馬は人気が落ちてきている。特に若い人の競馬離れが競馬の売り上げの減少に影響している。現在、競馬を行うにあたり使用するツールは主に競馬新聞で、これから競馬を始める競馬初心者も競馬経験者と同様に競馬新聞を使用するケースが多い。競馬新聞は競馬情報の多くを文字で表している。また、競馬新聞は内容の多くを競馬の専門用語で表している。このため競馬初心者は競馬新聞の内容を読み取ることができず、競馬を楽しむことができないことが現状である。競馬を始めることが難しいことが現在の若い人の競馬離れに繋がり、競馬の売り上げ減少の原因になっている。本研究の目的は競馬初心者の若者のための、競馬情報をわかりやすく視覚表現したアプリケーションを提案し、競馬初心者が競馬経験者と同様に競馬を楽しむことで多くの人に競馬の魅力を伝えることである。
- 著者
- 中村 久男
- 出版者
- 同志社大学言語文化学会
- 雑誌
- 言語文化 (ISSN:13441418)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, no.2, pp.261-284, 2005-12
日本ではいまだに知名度の低いアメリカ南部再建期から世紀転換期にかけ作家活動を行ったアフリカ系アメリカ人チエスナツトの第二短編集『彼の若き日の妻とその他のカラー・ラインの物語』を扱った論文である。カラー・ラインとは肌の色による差別が歴然と存在するが、その見えざる人種の境界線を指す。彼は、短編集を編むにあたり、9編の物語の配列に最善の努力を惜しまず、その結果に満足した。では、彼が目指した最良の配列とはどのようなものであり、それによって彼が伝えようとした作家の意図とは何であるのかを探求した。第一には、各短編が次ぎの物語と相互に関係しあい、相互に対照・照射し合う、間テクスト的配置が認められた。第二には、ブルー・ヴエインズと呼ばれる裕福な中流黒人層を描く物語で始め、カラー・ラインを越えようとする黒人の生活の諸相が描かれるが、最後には、貧しい黒人の悲劇的な物語を二編配置することによって、カラー・ラインは恣意的な見えざるの境界線ではあっても、それを越えるのは非常に困難であること、白人読者が興味をもち受け入れ易い短編から次第に南部黒人が置かれた厳しい現実を突きつけるような物語の流れを作ることによって作者はカラー・ラインへの挑戦姿勢を明確に打ち出しているのである。
- 著者
- 前田 裕二 村上 恵理子 秋山 一男 長谷川 眞紀 早川 哲夫 金子 富志人 宮本 昭正
- 出版者
- 一般社団法人 日本アレルギー学会
- 雑誌
- アレルギー (ISSN:00214884)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, no.10, pp.1248-1255, 1994
ネコに感作されている40例の成人喘息患者を対象としてネコの喘息における臨床的な意義を検討するために吸入誘発試験を行った. 即時型 (IAR) および遅発型 (LAR) いずれかの反応は40例中29例にみられた. IARのみがみられた例は12例 (30%), LARのみは7例 (17.5%), ニ相性反応 (DAR)は 10例 (25%), 反応がみられなかった例は11例 (27.5%)であった. 各反応群における年齢, 吸入前 FEV_<1.0>%,%MMF, ネコ上皮へのRASTスコアおよびアセチルコリンによる気道過敏性の閾値の常用対数値はいずれの2群間においても統計学的には有意差はみられなかった. ネコとの接触歴がLAR群ではl4%と他の2群 (DARでは78%, 無反応群では70%)よりも有意に低い率であった. ラストスコアが高くかつ気道過敏性が亢進している例は他の二群よりもDAR群に多くみられた. 喘息反応はネコとの接触歴がある患者では15/22 (68.2%)に, 接触歴のない例では10/16 (62.5%)にみられ出現率は同じであった. 以上の成績から小児のみではなく成人においてもネコアレルゲンは重要であると考えた.
1 0 0 0 OA 将棋解説文への固有表現・モダリティ情報アノテーション
- 著者
- 亀甲 博貴 松吉 俊 John Richardson 牛久 敦 笹田 鉄郎 村脇 有吾 鶴岡 慶雅 森 信介
- 出版者
- 一般社団法人 言語処理学会
- 雑誌
- 自然言語処理 (ISSN:13407619)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.3, pp.847-873, 2021 (Released:2021-09-15)
- 参考文献数
- 40
近年,シンボルグラウンディングや言語生成,自然言語による非言語データの検索など,実世界に紐づいた自然言語処理への注目が高まっている.我々は,将棋のゲーム局面に付随する解説文がこれらの課題の興味深いテストベッドになると考えている.解説者は現在の局面だけでなく過去や未来の指し手に言及しており,これらはゲーム木にグラウンディングされることから,ゲーム木探索アルゴリズムを活用した実世界対応の研究が期待できる.本論文では,我々が構築した,人手による単語分割・固有表現・モダリティ表現・事象の事実性のアノテーションを行った将棋解説文コーパスを説明する.
1 0 0 0 カラーストーンの測色
- 著者
- 高橋 泰 三木 かおり
- 出版者
- 宝石学会(日本)
- 雑誌
- 宝石学会(日本)講演会要旨
- 巻号頁・発行日
- vol.25, pp.8, 2003
一般的な色彩学の分野で論じられている色知覚の特性は、塗料(反射光)や特定の光源についての実験が大半である。宝石の場合、ファセット・カットされたカラーストーンは表面反射光、内部反射光、透過光が入り交じり複雑な外観を示すため、一般論で論じることができるとは限らない。カラーストーンにも人間の色知覚の特性が作用するか確かめるため、最初に透明な平板状の着色ガラスに対する近似色をカラーフィルムを組み合わせて作成し、機械測色により色差を算出した後、同じサンプルを被験者に目視検査で比色してもらった。その結果、色差の判定においては、明度の高い黄色、ピンク色、青色では機械測色の色差が小さかった割に、敏感に反応した。一方、明度の低い赤色、青色で色差の数値の割に、反応が鈍かった。また、緑色では明度の高低にかかわらず、肉眼は敏感に色差を知覚できることがわかった。このことは、透明体においても人間の色知覚の鈍感な色と敏感な色が同様に存在することを示し、色彩学での一般論に準ずる結果であった。<br> 次にカラーストーンのカット石について、前述した着色ガラス同様の比色実験を試みた。各カット石の近似色をカラーフィルターで作成し、それぞれのカラーストーンとの比色実験を被験者による目視検査で行った。結果は着色ガラスの場合に類似していた。高明度の黄色、青色、ピンク色、青紫色、緑色は機械測色における色差が比較的小さいにもかかわらず、その差を感じ取った被験者が多かった。イエロー・ダイアモンド、イエロー・トルマリン、ブルー・フルオライト、ロードライト・ガーネット(明)、クンツァイト、モルガナイト、タンザナイト、グリーン・フルオライトがその例である。逆に機械測色の色差が比較的大きいのに対し、肉眼がその色差を感じ取れなかったものは、暗色の赤色、青色、紫色であり、例としては、ロードライト・ガーネット(暗)、合成ブルー・スピネル、アメシストであった。<br> また、これらの検証を通して新たな問題点が浮上した。ファセット・カットされた石の色は外観上非常に複雑であり、平板状の着色ガラスに比べ近似色を作成する場合、難易度が格段に上がったことである。それは近似色フィルムとカット石の色差が着色ガラスの場合に比べ大きいことにも現れている。人間の目は複雑なカット石の色をどう捉えているか確認するため、カット石中の色を明度により明、中、暗の3段階に分け、それぞれの近似色を前述の実験同様に作成し、被験者に目視検査で比色してもらった。ここでの明色はKatzの色分類における「光輝」に、中色は「明るい容積色」、暗色は「暗い容積色」に相当する。比色実験の結果、中明度の「明るい容積色」を人間の目はファセット・カットされたカラーストーンの色として認識していることがわかった。
1 0 0 0 IR 実体主義の論理としての部分論理(1)
- 著者
- 加地 大介
- 出版者
- 埼玉大学教養学部
- 雑誌
- 埼玉大学紀要. 教養学部 (ISSN:1349824X)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.1, pp.21-36, 2021
本稿に始まる一連の論考では、実体的対象を基礎的存在者として認定する「実体主義的形而上学」の観点から要請される「部分論理」はどのような基準のもとでどのような選択を行うべきであるかを検討していく。本稿では、その具体的作業に踏み込む前の基礎的考察として、ダ・コスタとフレンチがパースやジェイムズのプラグマティズム的真理論を参照しつつ『科学と部分的真理』(2003)の中で展開した議論を手がかりとしながら、部分論理の前提となる「部分的真理」の形而上学的含意について考究する。その結果として、彼らの議論には実体主義的形而上学の観点からも評価できる側面をいくつか見出せるが、彼らの真理論がもっぱら認識論的観点に基づいているために、真理の部分性や時間性を消極的な形でしか捉えられていないという問題点を指摘する。そのうえで、特にジェイムズの真理論にはより積極的な動機があったことを確認するとともに、存在論的観点に基づけば、部分的真理には実在そのものの動的性格や形而上学的な不確定性を捉える等の積極的意義を見出すことができる、ということを示す。
1 0 0 0 OA 世界の大学教育の歴史と国際比較
- 著者
- 関 正夫
- 出版者
- Japanese Society for Engineering Education
- 雑誌
- 工学教育 (ISSN:13412167)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, no.6, pp.6-13, 1995-11-30 (Released:2009-04-10)
- 参考文献数
- 11
本論文では,第1に,19世紀から20世紀に於ける世界の学術中心地である欧米諸国等の大学教育の特質を比較考察した。第2に,以上の成果に基づき,21世紀に向けて日本の大学教育及び工学教育の改革課題を検討した。
1 0 0 0 パキスタン産モルガナイト中のセシウムの位置
- 著者
- 志村 玲子 杉山 和正
- 出版者
- 日本鉱物科学会
- 雑誌
- 日本鉱物科学会年会講演要旨集
- 巻号頁・発行日
- vol.2009, pp.140-140, 2009
ベリルは多様な色を呈するサイクロケイ酸塩鉱物である。本研究では、パキスタン産の桃色のベリルであるモルガナイトの解析を行った。このモルガナイトはCsに富んでいる。単結晶構造解析により、Csは[Si6O18]リングの2a(0,0,1/4)サイトに分布していることが確認され、また、Cs K-XAFSによりCs-Oの距離は0.35nmとなり、2aサイトへの分布が支持された。
1 0 0 0 OA 光の点滅と色で文字に感情を付加する研究
- 著者
- 三河 美幸 田邉 里奈 大谷 義智 近藤 邦雄
- 出版者
- Japanese Society for the Science of Design
- 雑誌
- 日本デザイン学会研究発表大会概要集
- 巻号頁・発行日
- pp.199, 2013 (Released:2013-06-20)
デジタルメディアを介したコミュニケーションの多くはテキストコミュニケーションである。対面コミュニケーションや電話と異なり、テキストコミュニケーションは非言語の情報を伝えるということが難しく、対面コミュニケーションや音声会話でのコミュニケーションに比べて、相手の感情が読み取りにくいといえる。非言語の情報が無く、線の幅などが統一され、素っ気ない印象を与えがちなデジタルフォントにおいて、手書き文字のように書いた時の感情が留められているような表現を、デジタル媒体でもうまく表現する事はできないだろうかと考えた。 本研究では光のゆらぎと色を用いて新たな文字の表現をすることを目的とする。文字に光の点滅を加えた文字で印象評価調査を行い、色の要素を加えて書き手の視点と読み手の視点の両方からの感情表現方法について調査を行う。光の点滅速度と感情との関係性を明らかにし、文字自身が感情情報を持つようなテキストの表現方法を提案する。
1 0 0 0 OA 点滅光の精神作業及び感情への影響
- 著者
- 佐藤 愛子
- 出版者
- 公益社団法人 日本心理学会
- 雑誌
- 心理学研究 (ISSN:00215236)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, no.3, pp.146-151, 1972-08-10 (Released:2010-07-16)
- 参考文献数
- 12
- 被引用文献数
- 3 3
1 0 0 0 IR 第3者所有物の没収--関税法違反事件の違憲判決にちなんで
- 著者
- 植松 正
- 出版者
- 日本評論新社
- 雑誌
- 一橋論叢 (ISSN:00182818)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, no.2, 1963-08
論文タイプ||研究ノート
1 0 0 0 OA 連体形終止法の意味するもの : 係り結びの意味構造とその崩壊
- 著者
- 久島 茂
- 出版者
- 静岡大学人文学部国文談話会
- 雑誌
- 靜大国文 (ISSN:0288223X)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, pp.36-47, 1989-03
1 0 0 0 IR 連体形終止法の意味するもの : 係り結びの意味構造とその崩壊
- 著者
- 久島 茂
- 出版者
- 静岡大学人文学部国文談話会
- 雑誌
- 靜大国文 (ISSN:0288223X)
- 巻号頁・発行日
- no.34, pp.36-47, 1989-03
- 著者
- 本間 裕朗
- 出版者
- 日経BP社
- 雑誌
- 日経ビジネス (ISSN:00290491)
- 巻号頁・発行日
- no.1094, pp.109-111, 2001-06-04
4月1日をもって、当社の本間敬啓社長が引責辞任して相談役に退き、代わって副社長だった私が新しく社長職に就きました。関税法違反幇助ほうじょの容疑に消費税法違反容疑。これらの捜査に関連して、当社が直接関与もしていない「地下銀行」なる組織とも深い関連があるようにもマスコミで紹介されてしまった。
1 0 0 0 難聴学級児童の聴力・構音検査成績 定期健康診断を通して
- 著者
- 立本 圭吾 塔之岡 彰子 山崎 祥子 進藤 昌彦 志多 真理子 安野 友博 村上 泰 大島 渉 寺薗 富朗 小宮 精一 真島 玲子
- 出版者
- 日本聴覚医学会
- 雑誌
- AUDIOLOGY JAPAN (ISSN:03038106)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.6, pp.755-762, 1989
京都市の難聴学級健康診断結果を報告する。 結果は以下の通りである。<br>1) 児童の裸耳および矯正聴力の平均はそれぞれ93.7dBHL, 57.6dBHLであった。<br>2) 発語明瞭度は平均が37%であったが, 矯正聴力より裸耳聴力に強い相関を示した。<br>3) 聞き取り検査では絵カードを参考させることで有意に正解率が上昇した。<br>4) 難聴学級児の構音は確立されたものではなく容易に変化を示した。<br>5) 就学前教育として一般保育・幼稚園へ通園していた者が未経験者より発語明瞭度が有意に高かった。