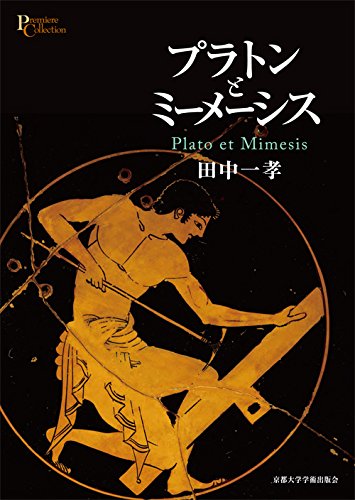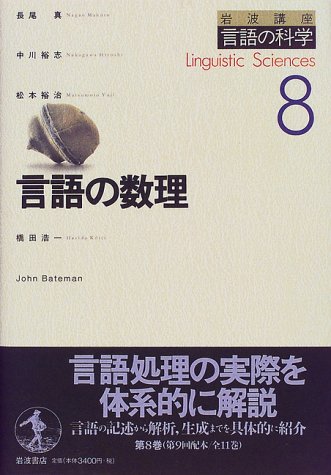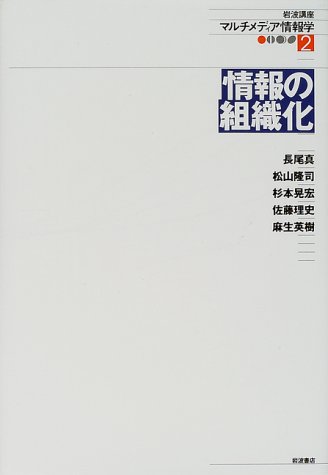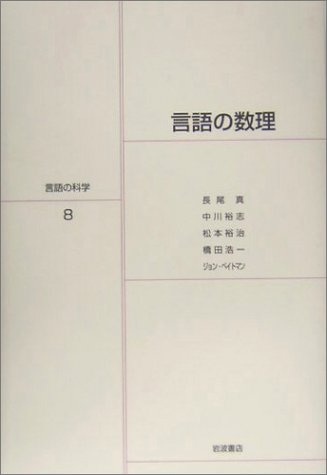1 0 0 0 地域熱供給用小型原子炉システムの開発に関する研究
- 著者
- 今村 瑞
- 出版者
- 一般社団法人 日本原子力学会
- 雑誌
- 日本原子力学会 年会・大会予稿集
- 巻号頁・発行日
- vol.2008, pp.431, 2008
現在の地球は数十年の内に化石燃料の枯渇の危機にさらされており、また、増加し続ける世界人口、大気中のCO2濃度の急激な変化など、環境面で多くの問題を抱えている。本研究ではこうした問題に対応すべく、現在地球上の最もクリーンなエネルギー源の一つと考えられている原子力を用いて発電し、さらに排熱も熱供給などに有効活用して、エネルギーを効率よく利用しつつ地球環境を守ることを基本コンセプトとし、既存の安全性の高い技術を使うことで、早期の開発を目指している。
- 著者
- 高坂 健次 吹野 卓
- 出版者
- 数理社会学会
- 雑誌
- 理論と方法 (ISSN:09131442)
- 巻号頁・発行日
- vol.4, no.1, pp.93-116, 1989
天然の漁業資源は、一方では自然的再生産メカニズムを享受しているものの、他方では、人間の手による乱獲のためにしばしば枯渇の危機に晒されている。本稿では、資源の再生産メカニズムの仮定をモデルに組み込み、(1)漁獲規制を遵守した漁獲戦略と、(2)規制を無視して可能な限りの漁獲をする漁獲戦略、の2戦略が選択可能な状況について考察する。そして、漁獲活動がDawes(1975)の定式化による「社会的ジレンマ」に陥るのは、資源再生産と漁獲に関するパラメータが特定の関係を持つ場合だけであることを示す。あわせて、囚人のジレンマ・ゲーム論的な観点から、乱獲の数理モデルの社会学的含みについて考察を加える。
- 著者
- 吉良 秀美 吉羽 雅昭 麻生 昇平 蜷木 翠
- 出版者
- 一般社団法人 日本土壌肥料学会
- 雑誌
- 日本土壌肥料学会講演要旨集 29 (ISSN:02885840)
- 巻号頁・発行日
- pp.295, 1983-03-25 (Released:2017-06-27)
1 0 0 0 OA 瀬戸内海の気象と海象
- 出版者
- 海洋気象学会
- 巻号頁・発行日
- 2013-01-25
1 0 0 0 ミクロ空間を反応場とする色素増感半導体光触媒の設計
色素ロ-ダミンB(RhB)をミクロ孔やメソ孔を有するゼオライト(ZSM-5、MCM-41)に吸着させ、担体の変化に伴うRhBの光物理化学特性の違いについて検討した。RhBの分子径よりも小さい細孔を有するZSM-5ゼオライトに吸着したRhBは蛍光寿命がnsオーダーのものに加え数百psオーダーの蛍光寿命を示し、RhBがゼオライトの外表面に、モノマー種およびダイマー種として存在することが解った。一方、RhBの分子径より大きいメソ細孔を有するゼオライトに吸着したRhBの蛍光寿命はnsオーダーの長い寿命成分のみが観測され、モノマー種のみでダイマー種の存在は見られないことが解った。すなわち、メソ細孔を持つゼオライトを用いて機能性色素を孤立した分布状態で吸着できることが解った。さらに、Ti種が四配位構造で高分散状態で固定化されているTi-MCM-41ではTi種とRhBが相互作用することにより、高い吸着量の範囲まで孤立した分布状態でRhBが存在できることを見出し、光増感型光触媒系の設計に適した反応場を構築できることが解った。また、Ti-MCM-41触媒は光照射下NOを選択性良くN_2とO_2に分解し、主にN_2Oを生成する粉末TiO_2光触媒とは異なった反応性を示した。以上の結果は、RhB-Ti-MCM-41が可視光照射下で機能し、粉末TiO_2光触媒系と全く異なる触媒選択性を有する色素増感光触媒として作用する可能性を強く示唆するもので、新規な光触媒の設計に重要な知見を与えるものである。
- 著者
- 峰尾 恵人 松下 幸司
- 出版者
- 日本森林学会
- 雑誌
- 日本森林学会大会発表データベース
- 巻号頁・発行日
- vol.126, 2015
「木の文化」は近年注目を集めているが、従来林学分野で考慮されることは少なかった。人工林長伐期化や広葉樹林化が課題となっている現在、「木の文化」を一つの視角として導入してはどうかというのが本報告の提案である。わが国の伝統的な「木の文化」から森林利用の歴史を見ると、多様な樹種・寸法の植物性資材が持続的に活用されてきたことが浮かび上がる。<br> 「木の文化」は持続可能であるという言説がしばしばあるがこれは誤りで、枯渇性資源的性質の強い長大材は近世に枯渇の危機を迎え、近代には外材に供給を依存するようになり、近年では違法伐採材まで利用されるようになっている。その他の再生可能資源も、社会経済の近代化の過程で林野利用の様式や需要のあり方が変化し、近年では生産の最終局面を迎えている資材があることも報告されている。これらの原因には、選好の変化や不完全情報などの市場の失敗が挙げられ、公的な介入の必要がある。<br> かつて林学は高齢林・広葉樹林を林相「改良」の対象とみなしてきたが、ポスト産業社会における森林科学にとって、「木の文化」という概念は生態系・経済・文化や川上・川下の関係を再構築する鍵となりうるのではないか。
- 著者
- 児玉 桜代里
- 出版者
- 明星大学経営学部経営学科研究紀要編集委員会
- 雑誌
- 明星大学経営学研究紀要 = Meisei University, the bulletin of management science (ISSN:18808239)
- 巻号頁・発行日
- no.16, pp.1-17, 2021-03-15
1 0 0 0 IR 木材粉末の圧縮成形による新しい環境調和材料の開発
鉱物や化石燃料等の埋蔵資源は年々減少して枯渇の危機が近づいており、また、これらを原料とした製品が廃棄される場合は、産業廃棄物として扱われ、特にプラスチック系材料の焼却では有害ガス等が発生するため、今日深刻な環境問題を引き起こしている。 本研究では、石油系の接着剤等を一切使用せずに木材の構成要素のみに注目して、木材粉末を固形化する技術を開発し、環境・人間にやさしい任意形状の木質製品を製造することを目的としている。そのための基礎的実験として、木材粉末の圧粉成形および押出し成形を行い、最適固形化条件および押出し成形時の木材粉末の流動特性を明らかにした。そして、木材粉末を原料とした複雑形状部品を製造するための技術として、射出成形に代表されるニヤネットシェイプ成形の可能性とその問題点について検討した。京都工芸繊維大学環境科学センター報「環境」第14号 2002-04 pp.36-41
1 0 0 0 OA 仙台藩の武士身分に関する基礎的研究
- 著者
- 堀田 幸義
- 出版者
- 宮城教育大学
- 雑誌
- 宮城教育大学紀要 = Bulletin of Miyagi University of Education (ISSN:13461621)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, pp.279-302, 2017-01-31
日本近世史分野では、身分制研究の進展を背景に、大名家の家臣団のなかでどの階層からが世襲の武士身分であったのかという点が議論されており、一方、武士身分とは誰が認定するのかといういう点についても研究されている。 本稿は、以上のような認識のもと、「武士身分の者」の多さが特徴とされる仙台藩の武士身分について整理するものである。果たして、仙台藩の領内では誰が武士として認められたのか、いわゆる武士身分であると認められる存在について、直臣、陪臣、金上侍、浪人まで含めて考察を加え、同藩における武士身分の重層的なあり方を論じたものである。 なお、その過程で従来の研究の誤りや等閑に付されてきた点についても言及している。
1 0 0 0 朝とタ方のジョギングにおける血中基質の動態と代謝特性
- 著者
- 豊岡 示朗 吉川 潔 足立 哲司
- 出版者
- 日本体力医学会
- 雑誌
- 体力科学 (ISSN:0039906X)
- 巻号頁・発行日
- vol.44, no.4, pp.419-430, 1995-08-01
- 参考文献数
- 27
- 被引用文献数
- 3 1
朝の起床後におけるジョギングの問題点, その実施時間帯による代謝特性を明らかにすることを目的として, 男子長距離選手5名 (19~26歳) とジョガー (32~50歳) を対象に, 絶食, スナック, 夕方の3条件を設定して60分間のトレッドミルによるジョギングを課し, 血中基質と代謝反応を測定し, 次のような結果を得た.<BR>1) 絶食条件のジョギング前後の血液グルコースは, ジョガー群で100.8mg/d<I>l</I>: 93.0mg/d<I>l</I>, ランナー群で101.0mg/d<I>l</I>: 105.6mg/d<I>l</I>となり, ジョガー群の低下が大きい傾向が見られた.しかしながら, 両群間に有意差は認められなかった.また, 夕食を摂らなかった被験者1名 (48歳) が, 走行後65mg/d<I>l</I>となり, 低血糖レベルに近づいた.<BR>2) 同条件での遊離脂肪酸は, ジョガー群の安静で, 0.37mmol/<I>l</I>, 運動後, 0.57mmol/<I>l</I>, ランナー群の場合, 運動前0.25mmol/<I>l</I>, 運動後0.37mmol/<I>l</I>となり, いづれも, 約50%の上昇がみられたものの, 安静値の2倍に達した被験者は1名であった.また, その最大値は, たかだか, 0.86mmol//<I>l</I>であった.<BR>3) 上述の結果から, 起床後の空腹状況において, 50~60%VO<SUB>2</SUB>maxで60分間のジョギングを実施した場合, 脱力感, 不快感や低血糖症状に陥る例は稀であり, 遊離脂肪酸が急上昇 (安静の3~4倍) することもほとんどないことが示唆された.しかしながら, 中高年ジョガーの場合, β-ヒドロキシ酪酸が, 運動前に比べ1.3~2.6倍も増加する例 (6名中5名) が見られた.<BR>4) 血中基質の動態からみた夕方ジョギングの特徴は, 朝の2条件 (絶食とスナック) と比べ, 運動前のインスリンレベルが2.7倍高く, 運動中のアドレナリン分泌の亢進, 血液グルコース取り込みの増加, 脂肪分解能の抑制であった.一方, 朝の2条件の動態は, ほぼ同様となり, インスリン, アドレナリン, ノルアドレナリン, 血液グルコースの変動が小さく, グリセロールの増加, FFA代謝回転レベルの高いことが認められた.<BR>5) 60分間のジョギングによる全消費エネルギーは, スナック条件が他の条件より4~5%高く (P<0.01) 654.4kcal, 以下, 夕方条件・627.5kcal, 絶食条件・619.2kcalとなった.この差異の要因は, スナック摂取からくる酸素摂取量の増加に依る.<BR>6) 呼吸商 (RQ) から60分間のジョギングによる炭水化物と脂肪の酸化比率をみると, 朝の2条件 (絶食とスナック) の場合, 約51~50%: 49~50%とほぼ同様になったのに比べ, 夕方条件の場合は, 67.4%: 32.6%となり, 朝のジョギングの方が約16~17%脂肪の酸化が多い (P<0.01) ことが認められた.<BR>7) 以上の結果から, 朝の2条件 (絶食とスナック) によるジョギングは, 夕方実施する場合に比べて脂質代謝が高いと示唆された.
- 著者
- 廣瀬 公彦
- 出版者
- 北海道大学大学文書館
- 雑誌
- 北海道大学大学文書館年報 (ISSN:18809421)
- 巻号頁・発行日
- no.16, pp.1-22, 2021-03
1 0 0 0 大学文書館における新型コロナウイルス感染症対策について
- 著者
- 井上 高聡
- 出版者
- 北海道大学大学文書館
- 雑誌
- 北海道大学大学文書館年報 (ISSN:18809421)
- 巻号頁・発行日
- no.16, pp.137-146, 2021-03
1 0 0 0 遠友夜学校の歴史
- 出版者
- 北海道大学大学文書館
- 雑誌
- 北海道大学大学文書館年報 (ISSN:18809421)
- 巻号頁・発行日
- no.16, pp.72-136, 2021-03
- 著者
- 佐々木 朝子
- 出版者
- 北海道大学大学文書館
- 雑誌
- 北海道大学大学文書館年報 (ISSN:18809421)
- 巻号頁・発行日
- no.16, pp.23-37, 2021-03
1 0 0 0 東北帝国大学農科大学・北海道帝国大学の大学院制度について
- 著者
- 山本 美穂子
- 出版者
- 北海道大学大学文書館
- 雑誌
- 北海道大学大学文書館年報 (ISSN:18809421)
- 巻号頁・発行日
- no.16, pp.38-71, 2021-03
1 0 0 0 学術無窮 : 大学の変革期を過ごして : 1997-2003
1 0 0 0 言語の数理
- 著者
- 長尾真 [ほか] 著
- 出版者
- 岩波書店
- 巻号頁・発行日
- 1999
1 0 0 0 情報の組織化
- 著者
- 長尾真 [ほか] 著
- 出版者
- 岩波書店
- 巻号頁・発行日
- 2000
1 0 0 0 言語の数理
- 著者
- 長尾真 [ほか] 著
- 出版者
- 岩波書店
- 巻号頁・発行日
- 2004