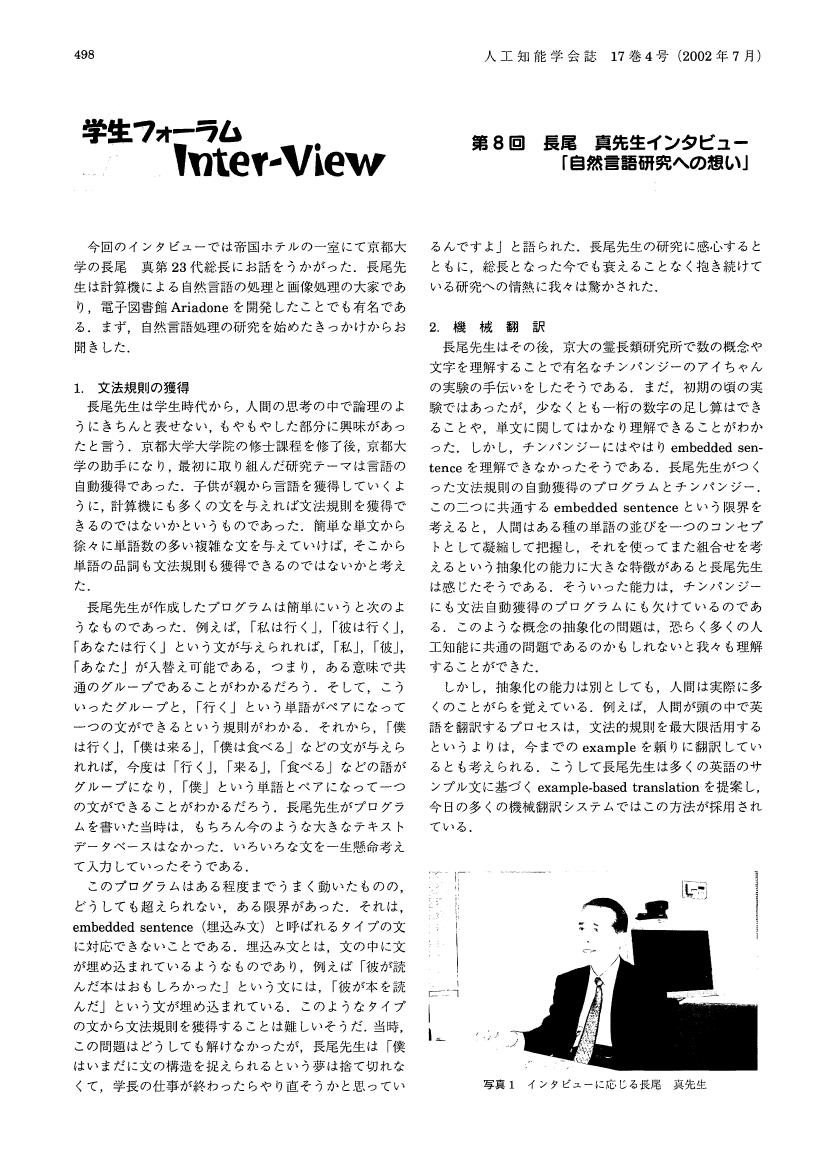1 0 0 0 OA A 1D Bayesian Inversion Applied to GPM Microwave Imager Observations: Sensitivity Studies
- 著者
- BARREYAT Marylis CHAMBON Philippe MAHFOUF Jean-François FAURE Ghislain IKUTA Yasutaka
- 出版者
- Meteorological Society of Japan
- 雑誌
- 気象集誌. 第2輯 (ISSN:00261165)
- 巻号頁・発行日
- pp.2021-050, (Released:2021-04-30)
- 被引用文献数
- 3
The assimilation of cloudy and rainy microwave observations is under investigation at Météo-France with a method called ‘1D-Bay+3D/4D-Var’. This method consists of two steps: (i) a Bayesian inversion of microwave observations and (ii) the assimilation of the retrieved relative humidity profiles in a 3D/4D-Var framework. In this paper, two estimators for the Bayesian inversion are used: either a weighted average (WA) or the maximum likelihood (ML) of a kernel density function. Sensitivity studies over the first step of the method are conducted for different degrees of freedom: the observation error, the channel selection and the scattering properties of frozen hydrometeors in the observation operator. Observations over a two-month period of the Global Precipitation Measurement (GPM) Microwave Imager (GMI) on-board the GPM-Core satellite and forecasts of the convective scale model Application of Research to Operations at Mesoscale (AROME) have been chosen to conduct these studies. Two different meteorological situations are analysed: those predicted cloudy in AROME but clear in the observations and, on the contrary, those predicted clear in AROME but cloudy in the observations.Main conclusions are as follows. First, low observational errors tend to be associated with the profiles with the highest consistency with the observations. Second, the validity of the retrieved profiles varies vertically with the set of channels used. Third, the radiative properties used in the radiative transfer simulations have a strong influence on the retrieved atmospheric profiles. Finally, the ML estimator has the advantage of being independent of the observation error but is less constrained than the WA estimator when few frequencies are considered. While the presented sensitivities have been conducted to incorporate the scheme in a data assimilation system, the results may be generalized for geophysical retrieval purposes.
1 0 0 0 次世代型廃プラスチック油化技術の開発に関する先導調査研究
- 著者
- 小寺 洋一 石原 由美子 武藤 大志郎 黒木 健
- 出版者
- 一般社団法人 廃棄物資源循環学会
- 雑誌
- 廃棄物学会論文誌 = Journal of the Japan Society Waste Management Experts (ISSN:18831648)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, no.1, pp.35-43, 2008-01-30
- 参考文献数
- 21
- 被引用文献数
- 1 3
既存の廃プラスチック類の油化技術および油化リサイクルの進展を阻害した要因を分析し,油化リサイクルの普及に必要な,次世代型油化技術の基本的要件の調査研究を行った。従来の主な油化技術はバッチ式タンク反応器をもつ小規模油化プラントによるもので,炭化物障害による処理能力の不足から油化事業は経済的に成立困難であった。廃プラスチックの発生量・流通量の実態調査と試算から,油化リサイクル普及に必要なプラントの仕様・性能は,油化能力日量3~7ton,装置コストは処理量1tonにつき0.5億円,油化コスト約40円/kgであった。既存技術は,日量1ton程度と過少かまたは,日量20ton以上の過剰設備で,いずれも企業の事業規模に適合しなかった。油化リサイクルの促進には新型式反応器の開発,実用化が必要で,その基礎となる事業性と技術的鍵となる反応器の伝熱効率の評価を通じて,次世代型油化技術の具備すべき基本的要件を明らかにした。
1 0 0 0 寛政改革と長崎 : 『宇下人言』・『翁草』の分析を踏まえて
- 著者
- 鈴木 康子
- 出版者
- 花園大学史学会
- 雑誌
- 花園史学 (ISSN:02853876)
- 巻号頁・発行日
- no.41, pp.1-71, 2021-02
1 0 0 0 インピンジメント
●インピンジメント(impingement)とは インピンジメントは「~に突き当たる,衝突する」という意味で,整形外科領域においてもその意味の通りに一般的な言葉としても使用されるが,殊に肩に関するある病態を表す言葉として半ば固有名詞的に認識されている.つまり,肩甲骨肩峰下と上腕骨頭との間(第2肩関節)で生じる衝突に由来する障害のことをimpingement syndrome,impingement lesions,あるいは単にimpingementと表現する. 従来より,この肩峰下での障害に対して,肩峰切除術が諸家により提唱されてきた(Watson-Jones,Smith-Petersen,McLaughlin).切除する範囲は報告者により異なるものの,肩峰を全層的に切除(acromionectomy)したため,三角筋の起始部を失ったことによる弊害が起こった.これに対し,Neer1)は衝突が起こるのは肩峰下面の前方1/3のみであるとの見地から,三角筋起始部を温存し,衝突する部分のみを水平にそぎ落とす方法(anterior acromioplasty)を提唱した.これ以降,インピンジメントという言葉が“Neer”とセットで固有名詞化していったようである.さらにNeer(1983)は,烏口肩峰アーチ(つまり棘上筋の出口)の形状が原因のものをoutlet impingement,そして元来インピンジメントの主役であった石灰沈着や大結節の変形治癒などをnon-outlet impingementと分類した.前者を3つのステージに分け,急性の肩峰下滑液包炎(スポーツによるオーバーユースなど)をステージ1,慢性の肩峰下滑液包炎や腱板炎(五十肩など)をステージ2,腱板不全断裂,腱板完全断裂,骨棘形成をステージ3として,インピンジメントが重症化していくなかで腱板が滑液包側から断裂していくとした.これに対し,腱板不全断裂はそのほとんどが関節面側にあり滑液包側ではないことから,断裂が滑液包側から起こるという説には異論を唱え(Uhthoff,信原2)),ステージ3を否定する者もある.
- 著者
- 松村 真宏 小林 郁夫
- 出版者
- 一般社団法人 人工知能学会
- 雑誌
- 人工知能 (ISSN:21882266)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.4, pp.498-500, 2002-07-01 (Released:2020-09-29)
- 著者
- 椎名 渉子
- 出版者
- 名古屋市立大学人間文化研究所
- 雑誌
- 人間文化研究所年報 (ISSN:18812686)
- 巻号頁・発行日
- no.15, pp.69-72, 2020-03
- 著者
- 独立行政法人科学技術振興機構
- 出版者
- 国立研究開発法人 科学技術振興機構
- 雑誌
- JSTnews (ISSN:13496085)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, no.1, pp.12-13, 2010
<p>「恐怖を感じる」とはいったいどういうことなのだろうか? 怪奇現象の正体は科学で解明できるのか?そんな疑問に答えてくれるユニークなお化け屋敷が、日本科学未来館に現れた!科学を通して恐怖を考えることにより、また新しい未来の扉が開かれるかもしれない!?</p>
- 著者
- 秦 正樹 酒井 和希
- 出版者
- 生活経済政策研究所
- 雑誌
- 生活経済政策 (ISSN:13429337)
- 巻号頁・発行日
- no.288, pp.22-26, 2021-01
- 著者
- 秦 正樹
- 出版者
- 関西大学経済・政治研究所
- 雑誌
- セミナー年報 (ISSN:18822010)
- 巻号頁・発行日
- pp.115-129, 2020
- 著者
- 秦 正樹
- 出版者
- 中央公論新社
- 雑誌
- 中央公論 (ISSN:05296838)
- 巻号頁・発行日
- vol.135, no.5, pp.34-41, 2021-05
1 0 0 0 農薬の使用とその問題点
- 著者
- 浅沼 信治
- 出版者
- 一般社団法人 日本農村医学会
- 雑誌
- 日本農村医学会学術総会抄録集 (ISSN:18801749)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, pp.10, 2010
1.農薬の使用と中毒発症の現状<BR>1)農薬使用状況の推移<BR> わが国で農薬が本格的に使用されるようになったのは、第二次世界大戦後である。戦後、農薬は農作物の生産性向上、労力の軽減など農業には重要な資材としての役割を果たしてきた。生産量の推移をみると、戦後30年の間に急増し、1974年に過去最高の75万トンに達し、その後は暫時減少し、90年代後半からは60年代の水準(30万トン台)になっている。殺虫剤の使用が最も多いが、兼業化など人手不足による省力化のため、除草剤の使用も多くなっている。<BR>2)急性中毒および障害<BR> かつてはホリドールやテップなどの毒性の強い農薬による中毒が多かったが、1971年に強毒性農薬が禁止になり、中毒事故は減少した。しかし、その後パラコート系除草剤による死亡事故(主として自殺)が相次いだ。1976年にパラコート系除草剤のうちグラモキソンが製造中止になり、代わってプリグリックスLが使われるようになり、死亡事故はやや減少した。<BR> 農村病院を受診した者の統計からみると、急性中毒と皮膚障害が多い。「健康カレンダーによる調査」によると、4人に1人が中毒症状の経験がある。<BR><BR>2.農薬使用の問題点<BR>1)2006年5月の「ポジティブリスト制度」の施行による問題点<BR> 「ポジティブリスト制」は、基準が設定されていない農薬が一定量以上含まれる食品の流通を原則禁止する制度である。以前の「ネガティブリスト制」は、農薬の残留基準値がない場合、規制の対象にならなかったが、新制度により一律基準0.01ppmが適用、規制される。消費者にとっては残留農薬の減少など好ましいことではあるが、生産者にとってはドリフトなど問題が多い。これは農薬の登録制度にも問題がある。<BR>2)ネオニコチノイド系農薬の使用<BR> 最近、有機リン農薬に代わって新農薬「ネオニコチノイド」(新しいニコチン様物質)が大量に、しかも広範囲に使用されている。今、ミツバチが忽然と姿を消す怪奇現象が多発し、その原因の究明が急がれているが、ネオニコチノイド系の農薬もその一つに挙げられている。<BR>3)農薬の表示についての問題点<BR> 日本では、「農薬」と表現されているように危険なイメージは少ない。 農薬には、その中毒を防止する観点から「毒物・危険」の表示が必要である。アメリカはドラム缶に「ドクロマークとPOIZON」表示がされている。フィリピンでは、その毒性により分類し、農薬のビンの下に幅広のテープを貼ったように色を付けている。色分けされ、一見してこれがどのランクの毒性を持つ農薬なのかが分かる。しかも毒性の強い農薬は、一般の店では販売されていない。日本は赤地に白文字で「毒物」、白地に赤文字で「劇物」と小さく書かれているだけである。<BR>4)農薬による皮膚炎<BR> 農薬による中毒・皮膚炎などにはその種類により特徴があり、注意する点も多い。とくに石灰硫黄合剤による皮膚傷害は深刻である。中毒を防ぐためにマスクの使用や、通気性がよく防水性のある防除衣の使用などについても考えてみたい。
1 0 0 0 IR 試験問題としての小説 : 芥川龍之介「酒虫」論
- 著者
- 小林 幸夫
- 出版者
- 上智大学大学院文学研究科文化交渉学専攻
- 雑誌
- 上智大学文化交渉学研究
- 巻号頁・発行日
- no.9, pp.1-18, 2021
1 0 0 0 OA 日本産アザミ属における雄性不稔と雌性雌雄異株
- 著者
- 川窪 伸光
- 出版者
- 日本植物分類学会
- 雑誌
- 植物分類,地理 (ISSN:00016799)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, no.2, pp.153-164, 1995-01-28 (Released:2017-09-25)
- 参考文献数
- 10
日本産アザミ属植物はすべてが両性花を咲かせる雌雄同株として取り扱われてきたが, 最近になってノマアザミCirsium chikushiense Koidz.がメス株を分化させた雌性雌雄異株(gynodioecy)であることが判明した。そこで日本産アザミ属全体に, メス株を分化させた分類群が, どの程度存在しているかを明らかにするために, 京都大学理学部所蔵の乾燥標本(KYO)を材料として雄ずいの形態と花粉の有無を観察した。その結果, 観察した97分類群のうち約40%の39分類群において, 花粉を生産しない退化的雄ずいをもつ雄性不稔株を確認した。これは種レベルで換算すると, 68種中の約43%の29種で雄性不稔が発生していることを意味した。発見された退化的雄ずいのほとんどは株内で形態的に安定しており, 雄性不稔の原因が低温障害などの一時的なものではないと考えられた。また22種類の推定雑種標本中, 5種類においても雄性不稔を確認したが, それらの雑種の推定両親分類群の少なくとも一方は, もともと雄性不稔株を生じていた分類群であった。雄性不稔株を確認したすべての分類群がメス株を分化させているとは言えないが, 雄性不稔株の発生頻度の高い分類群の多くは遺伝的にメス株を維持し, 雌性雌雄異株の状態にあるのかもしれない。
1 0 0 0 OA 『四季』派の抒情 ― その伝統的側面と変革の側面 ―
- 著者
- 河野 仁昭 Hitoaki Kono
- 出版者
- 同志社大学人文科学研究所
- 雑誌
- 人文科学 = The Humanities (ISSN:04196740)
- 巻号頁・発行日
- no.7, pp.16-40, 1974-07-20
論説
1 0 0 0 学術は「知覚的知識」とどのように付き合っていくべきか
- 著者
- 西村 歩 新井田 統
- 雑誌
- 2021年度 人工知能学会全国大会(第35回)
- 巻号頁・発行日
- 2021-04-05
1 0 0 0 OA ポリカーボネートの光劣化機構
- 著者
- 田原 省吾
- 出版者
- 公益社団法人 高分子学会
- 雑誌
- 高分子化學 (ISSN:00232556)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, no.253, pp.303-309, 1966-05-25 (Released:2010-10-14)
- 参考文献数
- 12
- 被引用文献数
- 1
ポリカーボネートの紫外線照射による劣化機構について, 主として赤外および紫外分光分析法により解析し, その劣化機構に2種の波長依存性が存在することを明らかにした。1) 太陽光にも含まれる約280mμ以上の長波長紫外線を照射すると, 炭酸結合部のC=Oのp電子によるn-π*遷移に相当する約287mμの光吸収が起こり, その励起エネルギーが分子内移動現象により炭酸結合部を構成するエーテル結合を切断し, COまたはCO2の系外離脱が起こるとともに, フェノール, エーテル, エステル, 酸などの助色団を生成して解重合反応が進む。2) 約280mμ以下の短波長紫外線域では258~273mμ付近に微細構造を有するベンゼン核のπ-π*禁制遷移による光吸収が起こり, n-π*励起移動と同様に炭酸結合部の切断が起こるとともに, イソプロピリデン結合部への励起移動現象も現われ, おそらくイソプロペニルやジフェニルエチレンなどの助色団が生成しつつ解重合反応が進む反面, 橋かけ反応も進行して不溶化現象が現われるものと思われる。さらに, 本実験では, 生成ラジカル, または反応中間体の寿命が比較的長いためか, 光照射中断後も経時的なスペクトルの変化が認められ, しかも, 長波長紫外線と短波長紫外線とでは異なった継続現象が観測された。
1 0 0 0 OA アトピー性皮膚炎,脂漏性皮膚炎患者を対象とした固形石鹸の使用試験
- 著者
- 旗野 翠 安原 美帆 髙山 良子 小畑 裕之 茂呂 修 佐伯 秀久 船坂 陽子 畑 三恵子
- 出版者
- 日本香粧品学会
- 雑誌
- 日本香粧品学会誌 (ISSN:18802532)
- 巻号頁・発行日
- vol.44, no.1, pp.6-12, 2020-03-31 (Released:2021-03-31)
- 参考文献数
- 11
We investigated the safety and usefulness of transparent solid soaps in parallel with ongoing treatment in patients with mild to moderate atopic dermatitis and seborrheic dermatitis with symptoms on the face. The soap is designed to be low in stimulation to the skin. Although there were no severe adverse effects, a minor one was noted related to the soap. One of the subjects discontinued the test product due to worsening of itching and eczema. After using the soap for four weeks, a significant improvement in the symptoms of drying and lichenification was observed. The visual analog scale score related to the skin condition also significantly improved, compared to that during the start of the study. In the questionnaire-based test response, approximately 90% of the subjects liked the feeling of using the soap. Overall, this study indicated that the investigated solid soap was safe and did not hamper the ongoing treatment.
1 0 0 0 輓用種牡馬における精液性状,繁殖成績,肪び精液の保存性の関係
- 著者
- フェルナンドトーレス ボジノ 佐藤 邦忠 岡 明男 菅野 幸夫 保地 真一 小栗 紀彦 ヨアヒム ブラウン
- 出版者
- 社団法人日本獣医学会
- 雑誌
- The journal of veterinary medical science (ISSN:09167250)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.2, pp.225-229, 1995-04-15
- 参考文献数
- 22
輓用種牡馬4頭について, 精液性状, 繁殖成績, 及び精液の保存性(液状保存と凍結保存)の関係を検討した. 精液性状については膠質除去後の精液量, 精子の濃度, 正常精子率, 及び精子運動性を調べ, また繁殖成績については過去3年間の累積の妊娠率とした. 精液の液状保存は5℃で行い, 0, 24, 48, 72時間目に精子の運動性を調べた. 精液の凍結保存には2種類の異なる希釈液(ブドウ糖-EDTA-ラクトース・卵黄希釈液, 脱脂粉乳-清澄卵黄希釈液)を用い, 凍結融解後の精子運動性と正常精子率を調べた. 精液性状の各値と繁殖成績は通常の変動範囲内にあったが, 膠質除去後の精液量, 正常精子率, 精子運動性, 及び繁殖成績に種牡馬間で有意差が認められた. しかしこれらのパラメーター間には相関性は認められなかった. 液状精液の保存性には種牡馬間で有意差が認められ, 保存前の精子運動性が最も高い個体で最も良好であった. また凍結精液では使用した希釈液にかかわらず融解後の精子運動性(13.8〜26.3%)と正常精子率(19.5〜38.0%)はともに低い値であった. 個々の種牡馬において精液の液状保存と凍結保存の結果には相関性が認められなかった. 以上の結果から, 精液の保存に対する適性を他のパラメーターから類推することは困難であると思われた. 輓用種牡馬精液の耐凍性を向上させるには,現在の凍結精液作製に関わる標準的手法に改良を加える余地が残されている.
1 0 0 0 IR 戦前期における大学史・高等教育史の再検証 : 東アジアという視点から
- 著者
- 石田 雅春
- 出版者
- 広島大学文書館
- 雑誌
- 広島大学文書館紀要 (ISSN:1880263X)
- 巻号頁・発行日
- no.22, pp.1, 2021-03-31