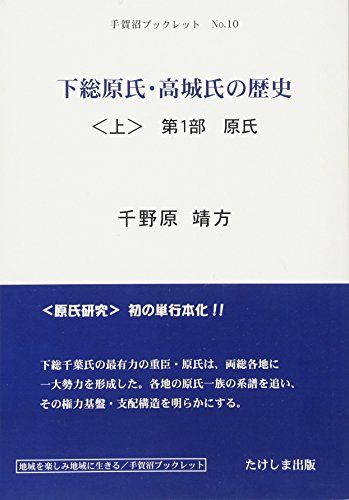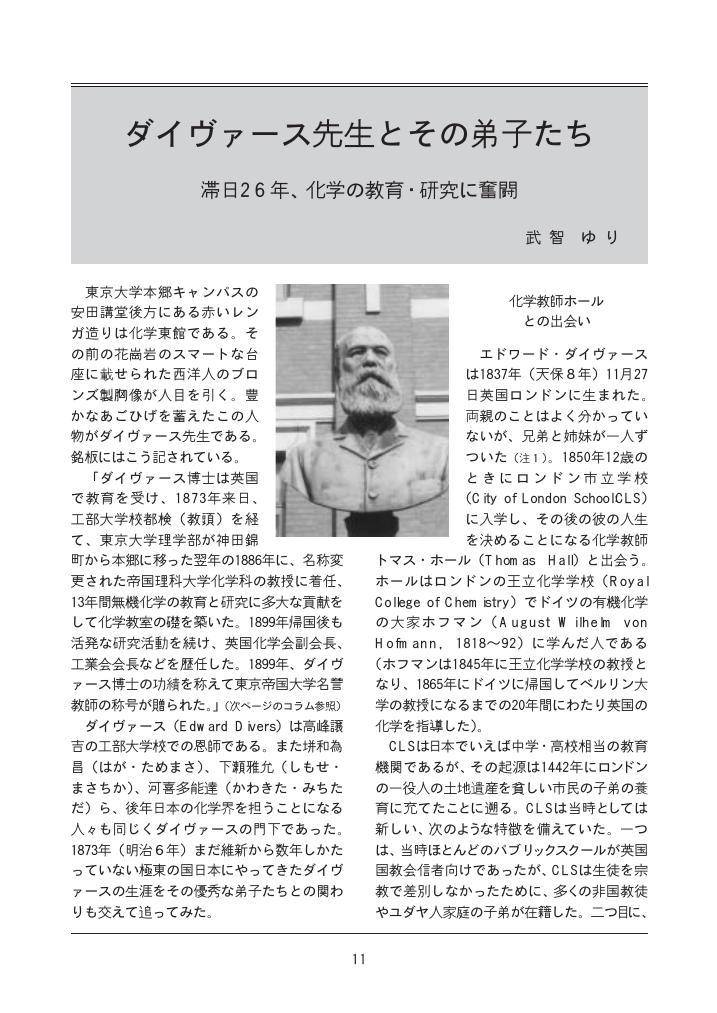1 0 0 0 OA ロボットを用いた自己の外部投影による行動変容のモデル化
- 著者
- 高橋 英之 石黒 浩
- 出版者
- 一般社団法人 人工知能学会
- 雑誌
- 人工知能学会全国大会論文集 第32回全国大会(2018)
- 巻号頁・発行日
- pp.3D1OS7a03, 2018 (Released:2018-07-30)
近年,様々なコミュニケーションロボットが開発されている.これらのロボットは,人間のパートナーとして生活に溶け込み,我々の暮らしをより豊かにすることが期待されている.我々は,コミュニケーションロボットが提供する一つの価値として,ロボットとの交流により,人間の自己の外部投影を促進し,行動変容を引き起こすことで個人の成長につながる“気付き”を生じさせることにあると考えている.本発表では,「ロボットを用いた自己開示の促進」と「ロボットを用いた批判的思考の促進」という二つの具体的な研究事例を紹介することで,ロボットが促す自己変容過程のモデル化について議論したい.
1 0 0 0 OA 人間と機械が調和する未来へ 声や視線で走る自動運転車
- 著者
- 国立研究開発法人科学技術振興機構
- 出版者
- 国立研究開発法人 科学技術振興機構
- 雑誌
- JSTnews (ISSN:13496085)
- 巻号頁・発行日
- vol.2019, no.5, pp.3-7, 2019-05-10 (Released:2019-06-09)
ハンドルやブレーキに触れずとも、声や視線で自在に操作できる自動運転車が誕生した。名古屋大学未来社会創造機構の武田一哉教授らの産学連携プロジェクトは、高い運転技術とコミュニケーション能力を兼ね備えた自動運転システムを開発し、人間と知能機械が調和した社会を実現するプラットフォームの構築に挑む。
1 0 0 0 OA “ナッジ”エージェント:人をウェルビーイングへと導く環境知能システム
- 著者
- 小野 哲雄
- 出版者
- 一般社団法人 人工知能学会
- 雑誌
- 人工知能学会全国大会論文集 第34回全国大会(2020)
- 巻号頁・発行日
- pp.3J1OS9a01, 2020 (Released:2020-06-19)
本研究では,行動経済学で提唱されている“ナッジ”を「心のナビゲーション」として捉え,その認知的なメカニズムの解明・モデル化を行うとともに,我々がこれまで研究を行ってきたエージェント基盤技術を用いて“ナッジ”エージェントとして実装することにより,人間とAIシステムを融和させ,人々をウェルビーイング(人間的に豊かな生活)へと導く意思決定を促す環境知能システムの実現を目指す. 本研究で提案する“ナッジ”エージェントの新規性・独自性は、(a) 行動経済学の「理論」とAIシステムの「学習」により少ないデータから人間の意思決定を予測可能,(b) エージェントが環境にあるIoTデバイスへ「移動」(agent migration)することにより文脈に適した意思決定の支援が可能,(c) ナッジを構成するプロセスを可視化することにより人間の意思決定力を「育てる」ことが可能なことである.本研究ではさらに,実験室実験により本システムの機能の有効性を検証した後,フィールド実験を行い社会実装へとつなげていく予定である.
1 0 0 0 OA 視線と音声を用いたマルチモーダルインタフェースによるワークロードの低減
- 著者
- 森田 祐介 古屋 友和 田村 総 平尾 章成
- 出版者
- 公益社団法人 自動車技術会
- 雑誌
- 自動車技術会論文集 (ISSN:02878321)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.5, pp.944-949, 2020 (Released:2020-09-30)
- 参考文献数
- 8
人の認知に関わる複数のリソース(視角/聴覚/言語/空間、等)を分散させることで負荷を低減させるHMIの実現を目指す。本研究では想定タスクについて従来の手動操作及び音声操作と、視線・音声を用いたマルチモーダル操作のワークロード評価を比較し、負荷低減への効果を明らかにする。
- 著者
- 杉本 知子
- 出版者
- 一般社団法人 日本老年看護学会
- 雑誌
- 老年看護学 (ISSN:13469665)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, no.1, pp.5-11, 2006
- 参考文献数
- 33
- 被引用文献数
- 2
本稿では,Rodgersの手法を用いて高齢者の長期ケアにおけるinterdisciplinary teamの概念構造を明確化した.文献データベースの検索等から48文献を分析し概念の先行要件,属性,帰結,さらに関連概念の検討を行い,以下の結果を得た.(1)概念の先行要件には,患者/クライアントの「ニーズの複雑化・拡大化」とそれを取り扱う専門職の「専門性の細分化・明確化」があった.(2)チームメンバーの属性にはチームメンバーへの「信頼」「理解」等が含まれ,チームの属性には「協働連携」「開放的なコミュニケーションの実施」等が含まれた.(3)概念の帰結はチームメンバーの協働連携に基づく相互作用によって導かれるものであり,ケアの提供者と対象者双方に有益性をもたらすものであった.(4)Interdisciplinary teamは患者/クライアントをチームの中心に据え,メンバー間の協働連携やコミュニケーションを重視した概念である.
1 0 0 0 IR ハンス・アスペルガーの1938年講演論文とウィーン大学の治療教育
- 著者
- 加戸 陽子 眞田 敏 齋藤 公輔 眞田 敏
- 出版者
- 関西大学人権問題研究室
- 雑誌
- 関西大学人権問題研究室紀要 (ISSN:09119507)
- 巻号頁・発行日
- no.66, pp.1-21, 2013-09
Aspergerが自閉的特徴に関する最初の報告を行った人物であるという認識は広まりつつある。本論文では、1930年代のオーストリアにおいて治療教育の拠点となり、Asperger自身も主任を務めたウィーン大学小児病院治療教育部門への、Michaelsによる視察の報告を中心にその取り組みを概観した。また、1938年のAspergerの講演論文中の自閉的精神病質と思われる1症例に関する記述部分を邦訳し、その臨床像の解釈を行った。さらに、米国で最初に自閉症に関する報告を行ったKannerの見解に対するAspergerの論文の影響についても論じた。
1 0 0 0 少年犯罪と精神疾患の関係の語られ方:戦後の新聞報道の分析を通じて
- 著者
- 赤羽 由起夫
- 出版者
- 日本犯罪社会学会
- 雑誌
- 犯罪社会学研究 (ISSN:0386460X)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, pp.104-118, 2012
本論の目的は,少年犯罪と精神疾患の関係の語られ方の内容とその歴史的な変遷の分析を通じて,1990年代以降の少年犯罪の医療化の特徴を明らかにすることである.そのために本論が分析資料として用いるのは,終戦から現在までの『朝日新聞』,『毎日新聞』,『読売新聞』の縮刷版から選出した精神疾患に言及のある少年犯罪の記事,および精神疾患についての記事である.分析の結果,明らかになった知見は,次の三点である.第一に,終戦から1970年代までに少年犯罪と関係づけられて語られた主な精神疾患には,精神分裂病,精神病質,精神薄弱,ノイローゼがある.第二に,1990年代以降に少年犯罪と関係づけられて語られた主な精神疾患には,行為障害と発達障害がある.第三に,1990年代以降の少年犯罪の医療化の背景には,第一に,精神疾患が指摘されやすい「普通の子」による少年犯罪が社会問題化したことと,第二に,教育問題までも包含する精神疾患として行為障害と発達障害の概念が登場したことがあげられる.
1 0 0 0 OA 情報科学の歴史(2)―初期コンピュータのソフトウェア[1]
- 著者
- 廣野 喜幸
- 出版者
- 東洋大学国際哲学研究センター
- 雑誌
- 国際哲学研究 = Journal of International Philosophy (ISSN:21868581)
- 巻号頁・発行日
- vol.別冊13, pp.73-87, 2020-03
1 0 0 0 OA ダイヴァース先生とその弟子たち 滞日26年、化学の教育・研究に奮闘
- 著者
- 武智 ゆり
- 出版者
- 特定非営利活動法人 近代日本の創造史懇話会
- 雑誌
- 近代日本の創造史 (ISSN:18822134)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, pp.11-20, 2006 (Released:2007-11-09)
- 参考文献数
- 30
1 0 0 0 日本学術会議ニュース
- 著者
- 高橋 康夫
- 出版者
- 日本建築学会
- 雑誌
- 建築雑誌 (ISSN:00038555)
- 巻号頁・発行日
- no.1480, pp.78-79, 2001-12-20
- 著者
- 栄 セツコ Setsuko Sakae
- 出版者
- 桃山学院大学総合研究所
- 雑誌
- 桃山学院大学総合研究所紀要 (ISSN:1346048X)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, no.3, pp.53-74, 2010-03
- 被引用文献数
- 1
Provision of high-quality care to support the independent living of people with psychiatric disabilities has been strongly emphasized in the field of mental health care. Cooperation among specialistsis said to be essential in this regard. In 2009, Setsuko Sakae et al. summed up their previous studies on such cooperation, defining the concept of cooperation as "a process of interaction between persons and organizations who share a common goal, in which they establish a cooperative relationship and work together to achieve their goal." This study targets clarification of relevant factors of cooperation. The authors consequently focused on the hospital discharge facilitation program, in which cooperation among organizations is considered to be indispensable. As the surveying method, a semi-structured interview was designed for the seven secretariats in charge of the program. Interview questions were about promotional/ obstructive factors of cooperation. As a result, the following four types of factors were extracted in relation to cooperation: (1) personal factors (empirical knowledge and motivation); (2) team factors (common goal, mutual respect /understanding, shared information, shared values in working toward the goal, flexible role allotment, and presence of a leader); (3) environmental factors (societal resources and laws and systems for mental health). To promote cooperation in the future, client involvement as well as discussions from the perspective of professional education will be required.
1 0 0 0 家計簿アプリを活用した家計データの構築と分析
家計簿アプリにより収集されたデータによって、新たな家計データを構築する。家計簿アプリとは銀行口座の出入金情報を自動的に収集するウェブサービスで、家計の収入・支出を自動的に記録するサービスである。誤記や記入漏れが発生せず、より正確な家計収支や資産保有の情報が把握できる。さらに、アプリ利用者を対象に、独自調査を実施して世帯属性を把握する。通常の統計調査では協力を得ることが難しい世帯行動・取引項目を把握することができる。構築されるデータは、家計内分配、消費税引上げの影響、家計の資産保有と消費の関係、などの分析に活用される。
1 0 0 0 OA ディープラーニング
- 著者
- 岡谷 貴之
- 出版者
- 一般社団法人 映像情報メディア学会
- 雑誌
- 映像情報メディア学会誌 (ISSN:13426907)
- 巻号頁・発行日
- vol.68, no.6, pp.466-471, 2014 (Released:2016-07-30)
- 参考文献数
- 17
- 被引用文献数
- 3 4
1 0 0 0 OA カスタマー・アドボカシーと顧客志向
- 著者
- 山岡 隆志
- 出版者
- 早稲田大学大学院商学研究科
- 雑誌
- 商学研究科紀要 (ISSN:02870614)
- 巻号頁・発行日
- vol.72, pp.77-92, 2011-03-25
1 0 0 0 IR 共に生きる社会を目指す ~「浦河べてるの家」の実践を通して
- 著者
- 向谷地 生良
- 出版者
- ルーテル学院
- 雑誌
- ルーテル学院研究紀要 = Bulletin of the Japan Lutheran College and Theological Seminary (ISSN:18809855)
- 巻号頁・発行日
- no.53, pp.1-8, 2020-03-01
本稿は2019 年11 月30 日にルーテル学院大学チャペルにて開催された学校法人ルーテル学院創立110 周年&三鷹移転50 年 記念講演会を収録したものである。
1 0 0 0 OA 岡山県三吉鉱山産砒銅ウラン雲母
- 著者
- 逸見 吉之助
- 出版者
- 一般社団法人 日本鉱物科学会
- 雑誌
- 鉱物学雜誌 (ISSN:04541146)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, no.3, pp.182-186, 1955-05-30 (Released:2009-08-11)
- 参考文献数
- 4