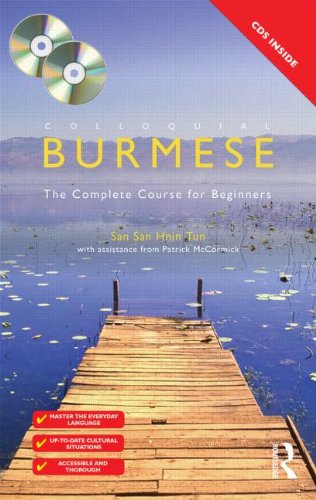- 著者
- 武田 知樹 大嶋 崇 尾方 英二 川江 章利 大野 智之 平野 真子
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学Supplement
- 巻号頁・発行日
- vol.2012, pp.48100442, 2013
【はじめに、目的】 医療分野においても患者中心の医療を推進する流れがますます強まる中,患者満足度(Patient Satisfaction)に関する研究も散見されるようになった. 医療機関において提供されている各種サービスの中でも,理学療法士や作業療法士等が行うリハビリテーションに関連するサービス(以下,リハサービス)は,患者自身の主体的参加が不可欠な点や,患者のモチベーションがそのまま治療効果として反映されるなどの特徴があることから,リハ領域における患者満足度の特徴やその影響性を把握することは効果的なリハサービス実施に向けて重要な知見となる. そこで今回,リハビリテーションに関する患者満足度と患者の運動に対する動機づけとの関連性について検討した.【方法】 調査協力の得られた医療機関を受診している入院および外来患者の内,理学療法を含むリハビリテーションサービスを受療している患者88名(男性23名,女性65名,平均年齢73.8±9.0歳)を対象とした. なお,言語による意思疎通が困難な者または知的機能の低下が疑われる者は対象より除外した. 調査方法は,担当理学療法士によって調査協力の依頼およびアンケート用紙の配布を行い,患者は自室もしくは自宅にて記入後,専用の返送用封筒にて郵送してもらった.なお,その際の回収率は59%であった. 調査内容について,リハビリテーション部門の理学療法サービスに関する患者満足度(以下,リハ満足度)の評価については,田中らが作成した「欲求充足に基づく顧客満足測定尺度(Customer Satisfaction Scale based on Need Satisfaction;CSSNS)」,また,患者が利用した医療機関のサービス全般に対する満足度(以下,病院満足度)の評価は「サービス満足度評価(SERVQUAL)」をそれぞれ使用した. さらに,患者の運動に対する動機付けについては,大友らの先行研究をもとに「高齢者用運動動機尺度(以下,運動動機)」を用いた. また,顧客満足度に関連する要因として,年齢,性別等の基本的属性データも同時に調査した.【倫理的配慮、説明と同意】 調査実施にあたっては,対象者の十分な同意を得るために調査協力依頼書を作成し,研究の趣旨および内容に対し理解および同意が得られた者を対象とした.【結果】1)性別の比較 リハ満足度を示すCSSNS得点(平均値±SD)は,男性20.8±3.4点に対し女性20.6±3.4点で明らかな性差は認められなかった(Unpaired t-test, N.S.). 2)年齢別の比較 中年者(65歳未満)のCSSNS得点は19.7±3.3点,前期高齢者(65~74歳)21.3±3.4点,後期高齢者(75歳以上)20.6±3.4点で年齢別の有意差を認めなかった(Kruskal Wallis test, N.S.).3)リハ満足度別の運動動機の比較 CSSNS得点を低得点グループ(17点以下:低満足),中得点グループ(18~24点:中満足),高得点グループ(25点以上:高満足)の3群に分類した上で,それぞれのグループの運動動機を比較した. 結果,低得点グループの運動動機は35.2±6.1点に対して,中得点グループ39.3±5.1点,高得点グループ43.1±2.4点で,CSSNS得点が高いほど運動動機が高い傾向にあることが確認された(Kruskal Wallis test, p<0.01).4)患者満足度と運動に対する動機付けとの関連性 患者満足度と運動動機との関連性について,CSSNSと運動動機(r=0.48),SERVQUALと運動動機(r=0.42)ともに中等度の相関関係を認めた(無相関の検定 p<0.01). 【考察】 患者満足度に関する性差や年齢差を調査した先行研究では,女性または高齢者で満足度が高くなりやすいとした報告が散見される中,本研究では満足度の性差および年齢差は明確にすることができなかった. リハ満足度別に運動に対する動機付けの高さを比較してみたところ,リハ満足度が高い患者ほど,動機付け(アドヒアランス)が高い傾向にあった. また,それぞれの患者満足度と運動に対する動機付けとの関連性を検討したところ,リハ満足度(CSSNS)のみならず,病院満足度(SERVQUAL)においても有意な相関を示した.つまり,リハ部門のみならず病院全体での患者満足度を高めていく取り組みは,患者の運動に対する動機づけを高める上で有益であることが示唆された.【理学療法学研究としての意義】 リハビリテーションに関する患者満足度が運動に対する動機づけに肯定的な影響を及ぼしていることが示唆された.理学療法士個々人の技能に加えて,リハビリテーション部門および病院全体の取り組みとして良質なサービスを提供することは,患者の運動動機を高めて疾病管理や介護予防を図るうえで有意義であるといえる.
- 著者
- 森 三十郎 Mori Sanjeuro
- 出版者
- 福岡大学研究推進部
- 雑誌
- 福岡大学法学論叢 = Fukuoka University Review of Law (ISSN:04298411)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, no.1, pp.59-112, 2003-06
- 著者
- 長縄 洋司
- 出版者
- 東洋大学大学院
- 雑誌
- 大学院紀要 = Bulletin of the Graduate School, Toyo University (ISSN:02890445)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, pp.343-358, 2017
Alcoholics Anonymous(AA)など「12のステップ」と「12の伝統」を用いる「12ステップ系セルフヘルプグループ」の効果については,すでに報告もある.本論は,近年のものを中心に海外,および日本における先行研究を改めて精査し,現時点でどのような効果があると言及できるか,それに基づけば,今後,日本においてどのような研究の実現が待たれるといえるのかを検討した.その結果,専門的治療との組み合わせで断酒等に関する一定の効果増進は認められるが,特異的効果については証明されておらず,他の専門的介入と共通する要素の抽出や,断酒等の医療的尺度に留まらない,より包括的な視点からの有効性に関する評価が求められることが判明した.日本においては研究の絶対数が少ないことから,将来的な他の治療的介入との無作為化比較試験や新たな評価尺度の開発を視野に入れつつ,システムや機能に関する理解を深めるところから取り組むべきであると考察した.This manuscript is a narrative review of the papers about effectiveness of twelvestep self-help groups, such as Alcoholics Anonymous(AA), in Japan and the other countries. The results show that, twelve-step self-help groups have effectiveness to abstinent clients with using professional care, but there are problematic evidences of specificity to abstinent by meta-analysises. We consider necessity to research common factors from professional care to twelve-step, and to evaluate of the effectiveness more total view and scale. In Japan, there were few research of them, and we may start to analysis the system and function of twelve-step programs.
1 0 0 0 OA 間質性肺炎・肺線維症 (2)
- 著者
- 岩田 猛邦 長井 苑子 大城 元 泉 孝英 渋谷 泰寛 瀬口 光代 伊藤 百合子 菅谷 文子 大畑 一郎
- 出版者
- 社団法人 日本呼吸器学会
- 雑誌
- 日本胸部疾患学会雑誌 (ISSN:03011542)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.Supplement, pp.368-369, 1993-03-10 (Released:2010-02-23)
1 0 0 0 OA 東アジアの経済・通貨危機と多国籍企業・国際金融機関の戦略対応
- 著者
- 奥村 皓一
- 出版者
- 日本国際経済学会
- 雑誌
- 国際経済 (ISSN:03873943)
- 巻号頁・発行日
- vol.1999, no.50, pp.101-102, 1999-06-15 (Released:2010-07-07)
1 0 0 0 OA 村嶌由直編『アメリカ林業と環境問題』
- 著者
- 村尾 行一
- 出版者
- 地域農林経済学会
- 雑誌
- 農林業問題研究 (ISSN:03888525)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, no.3, pp.161-162, 1999-12-25 (Released:2011-09-05)
- 著者
- Haruo Mimura Shinichi Nagata
- 出版者
- Japanese Society of Microbial Ecology / Japanese Society of Soil Microbiology / Taiwan Society of Microbial Ecology / Japanese Society of Plant Microbe Interactions / Japanese Society for Extremophiles
- 雑誌
- Microbes and Environments (ISSN:13426311)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, no.2, pp.121-123, 2001 (Released:2001-07-16)
- 参考文献数
- 8
- 被引用文献数
- 4 4
We used Brevibacterium sp. JCM 6894, which was isolated from seawater, to degrade the water-soluble fraction of jellyfish. After 27 h of incubation, the protein content in the supernatant was reduced from 1.97 to 1.31 mg/ml with an increase in cell yield of 0.40 mg cell protein/ml. The missing protein content in the fraction was 0.26 mg/ml. By the cell growth, the content of NH3 was increased from 0.38 to 4.57 μmol/ml. The value of chemical oxygen demand, which is a marker of remaining organic compounds in the fraction, was reduced from 890 to 431 mg O2/liter.
1 0 0 0 OA 配管減肉メカニズムに関する流体力学的考察
- 著者
- 稲田 文夫 米田 公俊 森田 良 藤原 和俊 古谷 正裕
- 出版者
- 公益社団法人 腐食防食学会
- 雑誌
- Zairyo-to-Kankyo (ISSN:09170480)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.5, pp.218-223, 2008 (Released:2008-11-08)
- 参考文献数
- 12
- 被引用文献数
- 2 6
配管減肉に対する流体現象の寄与について説明した.流れ加速型腐食(FAC)とエロージョンでは,壁面への流体作用力が全く異なることを示した.FACの主要因子である乱流物質移動は熱伝達とアナロジがあり,壁面近傍の粘性底層内の分子輸送が支配的とするモデルが実用的である.さらに物質移動は数値流体解析コードで求められる.最後にこれらの手法によりオリフィス,エルボにおける物質移動現象を予測した結果を説明した.
1 0 0 0 上方はなし
- 巻号頁・発行日
- 1936
1 0 0 0 OA 鹿児島県下で見出されたLycoris新種の成立について
- 著者
- 上野 敬一郎 野添 博昭 坂田 祐介 有隅 健一
- 出版者
- THE JAPANESE SOCIETY FOR HORTICULTURAL SCIENCE
- 雑誌
- 園芸学会雑誌 (ISSN:00137626)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, no.2, pp.409-417, 1994 (Released:2008-05-15)
- 参考文献数
- 13
- 被引用文献数
- 1 1
鹿児島県下で, 新しい系統と思われる2種類のLycorisが見出された. これら両系統は著者らの諸特性調査により, 同一起源の雑種, つまりL. traubiiとL. sanguineaの交雑により生じたものであると推定されている. 本報はこれら両系統の成立を実証するため,人為的な交雑を行い, 両親種とこの2系統のLycoris(L. sp. AおよびB) ならびに得られた交雑実生にっいて形態学的, 細胞学的な観察から比較検討を行うとともに, 両種の分布ならびに開花期の調査も併せて行った.L. traubii×L. sanguineaおよびL. sanguinea×L. traubiiの交雑における結実率は, それぞれ7.3%および30.1%であった. 正逆双方の交雑で得られた実生の形態は, 両親種の中間的形質を示し, 実生の出葉期,葉の光沢, 葉先の形および葉長/葉幅比などの形態的特性は, L. sp. AおよびBとそれぞれ一致していた.また, 交雑実生の染色体数ならびに核型は, 異数体や部分的に染色体欠失を生じた個体も存在したが, 基本的にはL. sp. AおよびBとそれぞれ一致する5V+12R型と4V+14R型であった.L. sanguineaおよびL. traubiiの分布ならびに開花期を調査した結果, 九州の中~南部にかけて秋咲き性のL, sanguineaが存在することを見出し, 特にL. sp. AおよびBが濃密に分布する鹿児島県山川町成川で,開花期が完全に一致するL. sanguineaとL. trattbiiが同所的に分布する事実をつきとめた.以上の結果からこの2系統のLycorisは, 秋咲きのL. sanguineaと9V+4R型のL. traubiiとの自然交雑により, 鹿児島県薩摩半島南部, おそらくは山川町成川で誕生したものであろうと推断した.
1 0 0 0 OA 文章における著者の特徴解析
- 著者
- 國廣直樹 長谷川智史 穴田一
- 雑誌
- 第73回全国大会講演論文集
- 巻号頁・発行日
- vol.2011, no.1, pp.379-380, 2011-03-02
文章の書き方には人それぞれ特徴がある.一番特徴が表れるのは文字の筆跡であるが,電子テキストの普及等から,筆跡以外の特徴を用いて解析を行い,著者不明の作品や文献等の書き手を識別する研究が行われている.<br />既存の研究では,読点直前の品詞や単語の出現頻度等に著者の特徴が表れると考え,主成分分析や類似度等を用いて比較することで著者の識別が行われてきた.しかし,比較文章における文字数の統一や,短い文章を使用できないという制約があるものが多い上,未だに著者の特徴がどこに表れるか明確になっていない.そこで,本研究では,文章の文字数に依存しない著者の特徴を抽出する方法を提案し,その有効性を検討する.
1 0 0 0 OA 看護倫理への旅
- 著者
- アン デービス
- 雑誌
- 長野県看護大学紀要 = Bulltein Nagano College of Nursing (ISSN:13451782)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, pp.1-10, 2017-03-31
アン・デービス名誉教授の看護師および看護学者としての半生記である.英文学と哲学で身を立てるよう勧める親に背いて看護を選んだこと,その動機はアフリカでシュバイツアーと働くためだったこと,大きく人生を決定づけたのは,自身の選択とともに,さまざまな偶然や人との出会いであったこと,シュバイツアーの自伝を読んで以来,常に旅に憧れ,実行に移した大小の旅が人との出会いや人生の転機をもたらしたことが述べられている.具体的なエピソードを通して,臨床で体験した精神看護の面白さや,カリフォルニア大学や長野県看護大学での教員生活につながった自身の選択,重要な人々との出会い,自身を有名にした生命倫理の著書執筆の学術的・時代的背景,長野県看護大学に来た経緯とそこで見藤学長と一緒にした仕事,アイデアの提案と実現に関する日米間の社会文化的差異の観察などが語られている.
1 0 0 0 OA 日本における行政救済制度の形成史と公権力概念
本研究は、日本における行政救済制度(行政事件訴訟および国家賠償訴訟・損失補償訴訟)の形成過程の通史を比較法制史の視角からまとめること、を目的とした。具体的には、(1)公法学における歴史研究の基本的な視点と方法論を明らかにした、(2)国の損害賠償責任の範囲と「行政処分」概念との関係史という視点から、憲法・行政法・民法理論と判例の歴史的分析を行った、(3)経済行政法理論の形成史および裁判制度史の視点から行政争訟法制度の歴史的位置づけと変遷過程の分析を行った。これらの研究の成果として、いくつかの学会報告を行うとともに、10本の論文等を公刊した。
1 0 0 0 中国の近代化政策と気功の変遷
- 著者
- San San Hnin Tun with assistance from Patrick McCormick
- 出版者
- Routledge
- 巻号頁・発行日
- 2014
1 0 0 0 OA 就業における連続性への規範
- 著者
- 藤本 昌代
- 出版者
- 社会学研究会
- 雑誌
- ソシオロジ (ISSN:05841380)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.1, pp.73-80, 2011-06-30 (Released:2015-05-13)
- 参考文献数
- 9
1 0 0 0 OA アミノ酸類の旋光分散および紫外部吸収スペクトルの研究 その分析化学への応用
- 著者
- 瀬戸 寿太郎
- 出版者
- 公益社団法人 日本分析化学会
- 雑誌
- 分析化学 (ISSN:05251931)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, no.8, pp.672-679, 1960-08-05 (Released:2010-02-16)
- 参考文献数
- 15
17種の高純度蛋白質性アミノ酸について旋光分散を測定し,その分析化学への応用について検討した.1.各アミノ酸について簡略Drudeの式[M]=A/(λ2-λ2c)±B/λ2を求め実測値と比較した.2.λ2~1/[M]曲線をつくり,チロシンを除くすべてのアミノ酸が直線となることを示した.また,これを利用してアミノ酸の純度検定のおこなえることを示唆した.3.アミノ酸の紫外部吸収スペクトルを測定し,その吸収極大値λmaxと旋光分散より求めたDrude式中のλc(固有振動の波長)の関係を検討した.
1 0 0 0 IR 随心院蔵『峯殿詠哥集』考
- 著者
- 海野 圭介 ウンノ ケイスケ
- 出版者
- 大阪大学古代中世文学研究会
- 雑誌
- 詞林 (ISSN:09139338)
- 巻号頁・発行日
- no.34, pp.26-48, 2003-10
正誤表あり論文中34ページに用いられている図版、35-48ページに用いられている翻刻は著作権等の都合により削除
1 0 0 0 IR 平成八年度 特別研修員 研究発表要旨 : 戦国時代の興正寺について
- 著者
- 熊野 恒陽
- 出版者
- 大谷学会
- 雑誌
- 大谷学報 = THE OTANI GAKUHO (ISSN:02876027)
- 巻号頁・発行日
- vol.76, no.3, pp.110-111, 1997-03
- 著者
- 工藤 朝子
- 出版者
- 九州理学療法士・作業療法士合同学会
- 雑誌
- 九州理学療法士・作業療法士合同学会誌 第33回九州理学療法士・作業療法士合同学会 (ISSN:09152032)
- 巻号頁・発行日
- pp.244, 2011 (Released:2012-03-28)
【はじめに】 幼児期の子どもは、成功や失敗を漠然と感じることはできるが、自身の行動を客観的に捉えることは難しく、身近な人の言動に影響を受けながら自己のイメージを築いていく。しかし、発達障害を持つ子どもの多くは、共感性の乏しさや独自の解釈などにより、周囲の言葉をうまく取り入れられないことがある。 今回、自信の無さから課題に取り組めない事例に対し、課題の調整のみでは変化が見られず、関わり方を配慮したところ、取り組みに変化がみられたので報告する。なお、報告にあたりご家族の同意を得ている。【症例紹介】 地域の保育園に通う5歳男児。診断名は言語発達遅滞、発達性協調運動障害。田中ビネー知能検査ファイブIQ99。興味の限定や儀式的な行動がみられるが対人面は良好である。ADLはFIM96/126点で、環境やその時の気分により遂行に差がある。体幹の支持性が乏しいため、机上課題では姿勢の保持が難しく片方の手を支持に使う。鉛筆は握り込み、肩関節の動きで、ぬりえや自由画などを行う。視知覚検査では、年齢相当から2歳程度の遅れを示すものまであり、項目間の差が大きい。作業療法場面では、ぬりえ課題の背景や図柄・線の太さの段階付けを行ったが、失敗ばかりを気にして、賞賛や励ましを聞き入れられず、課題に取り組めない。ぬりえに取り組めない状態は、自宅や保育園でも同様である。【方法】 作業療法士(以下OT)は、子どもの課題に対する自発性を育てる目的で、児の思いを尊重する関わりを行う。関わりは、OTが「ここは線からはみ出ていないね」など、上手くできている部分を具体的に児に伝え、反応を待つ。うなずきなどの共感的な反応がみられたときに限りさらに褒める。【経過および結果】 作業療法を5ヶ月間、全8回実施。児は、2回目まで自発性に乏しく、OTの言葉にもほとんど反応しなかった。3回目以降は、課題に自発的に取り組んだ。OTの言葉には反応しないこともあったが、少しずつ共感することが増えた。7回目からは、よくできたところを自ら指差し、周囲に伝えるようになった。なお、自宅や保育園でもぬりえや自由画に取り組むようになった。【考察およびまとめ】 今回OTは、児が持つ達成感に注目して肯定的な視点を伝え、児が肯定的なイメージを持ったと確認できたときのみ賞賛を行った。そのことで、児は失敗だけでなく成功した部分にも気づけるようになり、OTの言葉を受け入れられるようになったと考える。結果、児の上肢機能などに大きな変化はなかったが、課題に対して自信を持つことができ、自発的に取り組めるようになったと考える。OTは、課題の調整だけでなく、子どもが持つ達成感を尊重し、成功体験を積む機会が得られるように支援することが重要である。