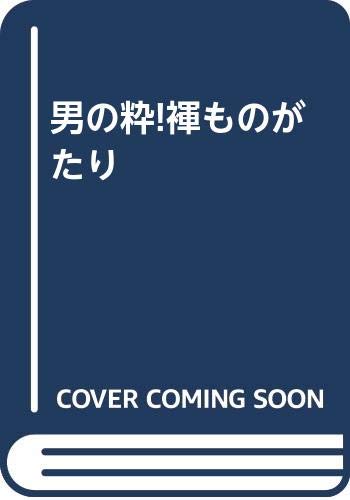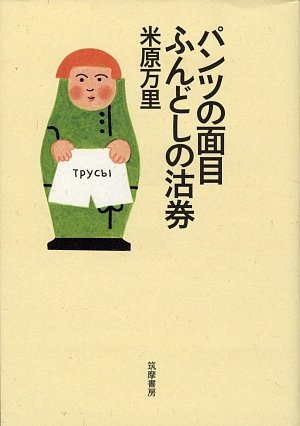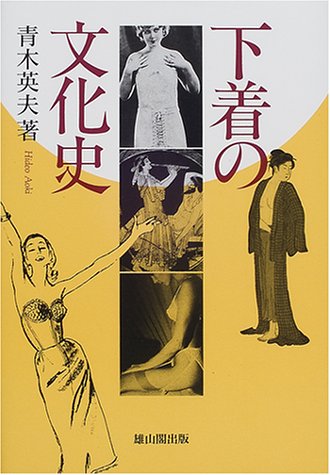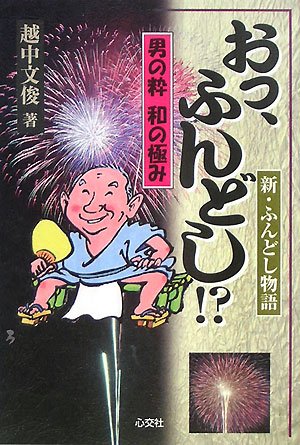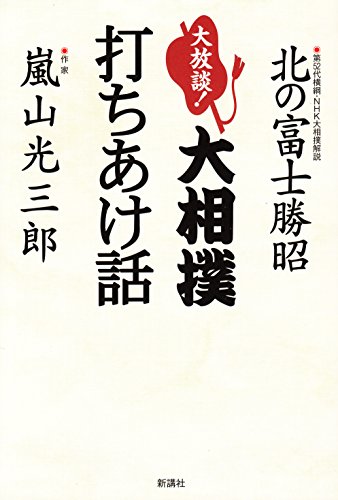1 0 0 0 OA 産後1週目から8週目の母乳中葉酸濃度の経時的変化
- 著者
- 三嶋 智之 中野 純子 唐沢 泉 澤田 未緒 伊佐 保香 柴田 克己
- 出版者
- Japan Society of Nutrition and Food Science
- 雑誌
- 日本栄養・食糧学会誌 (ISSN:02873516)
- 巻号頁・発行日
- vol.67, no.1, pp.27-31, 2014 (Released:2014-03-03)
- 参考文献数
- 20
本研究では母乳中の葉酸濃度の経時的変化について縦断的に調べた。25名の授乳婦より提供された産後1週目から8週目までの母乳中の葉酸濃度をバイオアッセイにより定量した。授乳婦の食事調査は行っていないため葉酸の摂取量は不明であった。本研究で分析した200検体の母乳中葉酸濃度は54.2±31.9 μg/L (平均±標準偏差) , 中央値が46.6 (4.9-161.9) μg/Lであり, 被験者全体の葉酸濃度は5週目まで上昇し, 1週目と比較して3週目から8週目の各週では有意に高値を示した (p<0.05) 。また, 1週目の葉酸濃度の中央値にて2群に分けて解析を行ったところ, 高値群の母乳中葉酸濃度は低値群に対してすべての週において有意に高値を示した (p<0.05) 。
1 0 0 0 OA うわさの伝播モデル
- 著者
- 蜷川 繁 津田 伸生 服部 進実
- 雑誌
- 情報処理学会論文誌 (ISSN:18827764)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, no.2, pp.517-520, 2000-02-15
うわさに代表されるような集団における情報の伝播を調べるために,構成要素間にランダムに張りめぐらされたネットワーク上を情報が伝播する,うわさの伝播モデルを提案し,個人の間の関係と情報の伝播との関係を計算機シミュレーションを用いて調べた結果,各個人が平均して3人に情報を伝達すると,ほぼ集団全体に情報が伝搬することが明らかになった.この結果から,物理的あるいは経済的な制約条件によって構成要素間の接続が限られているようなネットワークで,ほぼ全体に情報を行きわたらせるためには,各構成要素から3本の出力を出し,それをランダムに接続すればよいことが分かる.
1 0 0 0 OA どのようなダイエット行動が摂食障害傾向やbinge eatingと関係しているか?
- 著者
- 松本 聰子 熊野 宏昭 坂野 雄二
- 出版者
- 一般社団法人 日本心身医学会
- 雑誌
- 心身医学 (ISSN:03850307)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.6, pp.425-432, 1997-08-01 (Released:2017-08-01)
- 参考文献数
- 21
- 被引用文献数
- 4
摂食障害患者は健常者よりも食事制限の程度の高いことが指摘されているが, これまでその具体的内容の違いについての検討は行われていない。そこで本研究では, ダイエット行動尺度, EAT-20,BingeEating尺度を女子高校生2,019名, 女子大学生847名に施行し, 実際にどのくらい, どのような食事制限を行っているのかというダイエット行動と摂食障害傾向, さらにbingeeatingとの関連の検討を行った。その結果, ダイエット行動には構造的ダイエットと非構造的ダイエットがあり, 摂食障害傾向が高くなるにつれて, 構造的ダイエットも非構造的ダイエットも高頻度で行うようになるが, 摂食障害群では特に非構造的ダイエットの頻度の高いことが示唆された。また, bingeeatingにはダイエット行動の中でも非構造的ダイエットのみが影響していることが明らかにされた。
1 0 0 0 褌ものがたり : 男の粋!
1 0 0 0 パンツの面目ふんどしの沽券
1 0 0 0 おっ、ふんどし!? : 男の粋 和の極み : 新・ふんどし物語
1 0 0 0 大放談!大相撲打ちあけ話
- 著者
- 北の富士勝昭 嵐山光三郎著
- 出版者
- 新講社
- 巻号頁・発行日
- 2016
1 0 0 0 OA 歯科用CAD/CAM「セレック2」システム・クラウンの支台形態と適合性
- 著者
- 風間 龍之輔 福島 正義 岩久 正明
- 出版者
- 日本接着歯学会
- 雑誌
- 接着歯学 (ISSN:09131655)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, no.3, pp.214-219, 2001-12-15 (Released:2011-06-07)
- 参考文献数
- 9
「Cerec 2」システムにおける臼歯部クラウンの支台形態が, クラウンの適合性に与える影響について検討した.ヒト抜去下顎大臼歯に全部被覆冠の支台を形成した.辺縁の位置の設定は水平型と傾斜型の2条件, 咬合面形態は平坦型と逆屋根型の2条件とし, 「Spacer」設定は30μmとした.各条件につき5個のクラウンを製作した.作製されたクラウンは接着性レジンセメントで支台歯に合着された.合着試料を歯冠中央で近遠心的に切断し, その断面上の7つの測定点で接着性レジンセメントの厚さを測定顕微鏡で計測した.その結果, 辺縁の位置設定が水平型および咬合面形態が平坦型のクラウンが最も良好な適合性を示した.
1 0 0 0 OA 佐藤直方の理気論:朱・陸の太極論争との関連において
- 著者
- 嚴 錫仁 Eom Seog-In
- 出版者
- 筑波大学倫理学原論研究会
- 雑誌
- 倫理学 (ISSN:02890666)
- 巻号頁・発行日
- no.14, pp.61-74, 1997-12-20
1 0 0 0 OA HMM に基づく歌声合成のためのビブラートモデル化
- 著者
- 山田 知彦 武藤 聡 南角 吉彦 酒向 慎司 徳田 恵一
- 雑誌
- 研究報告音楽情報科学(MUS)
- 巻号頁・発行日
- vol.2009-MUS-80, no.5, pp.1-6, 2009-05-14
HMM に基づく歌声合成は歌い手の特徴を歌声データと楽譜から自動学習し,任意のメロディからその特徴を再現した歌声を合成できる.その際,歌声の音色・発音と音高における歌い手の特徴を,それぞれスペクトルと基本周波数の時間変化として HMM でモデル化している.本稿では,歌唱表現のひとつであるビブラートを音高の周期的な揺らぎと仮定し正弦波でモデル化する.そのパラメータをスペクトル及び基本周波数と同時に HMM でモデル化する.歌声の合成実験では,女性 1 名による童謡 60 曲の歌声データを学習し,主観評価実験によってビブラートモデルの導入による自然性の向上が確認できた.
1 0 0 0 OA 〈原著論文〉電磁界(EMF)の健康影響はどのように認識されているか
- 著者
- 巽 純子
- 出版者
- 近畿大学原子力研究所
- 雑誌
- 近畿大学原子力研究所年報 = Annual Report of Kindai University Atomic Energy Research Institute (ISSN:03748715)
- 巻号頁・発行日
- no.56, pp.7-17, 2020-03-22
[要旨]電気機器類の増加および通信技術の進展に伴い、電磁界(EMF)源の数と多様性が増加している。そこで本研究では現在、EMFのリスクがどのように認識されているか、他の環境要因のリスク評価も含め、健康影響の認識など13の設問を質問紙法によって調査した。対象は796名の学生(文系395名、理系379名)、一般市民170名、専門家(放射線、電力に携わる人)108名の合計1074名であった。これらの各集団において46項目の環境要因について7を最大として7段階で恐怖度合いを評価してもらった。また、EMFに対するリスク認識は、性別、健康問題の経験の有無、専門性などの要因で変わるかどうかについて解析検討を行った。その結果、各集団においてEMFに限らず、女性の方が多くの環境項目のリスク評価を高く見積もる傾向があり、動力線のEMFのリスク評価は一般市民女性の4.0が最も高く、専門家の1.9が最も低く2倍の違いがあった。また、ENFへの恐怖は家電や携帯電話の使用にあたって身体に異常を感じた経験に基づいている可能性があることもわかった。EMFは我々の生活の場の身近な存在であり、情報が氾濫する現代でEMFを過大評価または過小評価することなく、健康影響が生じない周波数、時間で使用するための指導啓発が必要なのではないかと考える。[Abstract]With the widespread use of domestic appliances and rapidly developing in wi-fi technology, the variety and the number of electromagnetic sources are increasing. This study aim is to provide risk perception data related to electromagnetic fields (EMF) arising from power lines, domestic appliances, and mobile phones, and to compare the risk perception related to EMF with other environmental objects. We administered a questionnaire concerning risk-perception and knowledge about EMF and health problems associated with the domestic appliance or mobile phone use to 796 undergraduate students (395 in literary arts and 379 in science), 170 public citizens and 108 professionals who work at the electric power company or the research institute of radiation. Participants in each group were instructed to rate each item on a seven-point fear scale with 7 as maximum value about 46 various environmental items. An analysis was conducted to determine whether risk perception for EMF changes depending on factors such as gender, experience with health problems, and expertise. As a result, women in each group tended to overestimate the risk assessment of many environmental items, not only EMF. The risk of the power line of EMF was evaluated at 4.0 of the highest score for civilian women, with professionals at 1.9 being the lowest, with a two-fold difference. We also found that fear of ENF could be based on experience with physical abnormalities when using home appliances and mobile phones. These results suggest that students’ vague fear of EMF may not be based on accurate knowledge of the risk, but based on their own experience of health problems associated with the household appliance or mobile phone use.
1 0 0 0 OA 聖書は肉食・動物をどう扱っているか : 創世記
- 著者
- 奥田 和子
- 出版者
- 甲南女子大学
- 雑誌
- 甲南女子大学研究紀要. 人間科学編 = Studies in human sciences (ISSN:13471228)
- 巻号頁・発行日
- no.41, pp.57-70, 2005-03-18
Our country has long lived on rice. However, meat consumption has gained in quantity during the last half-century. The eating of meat has been growing in popularity. It differs completely from eating food from vegetable matter. Here arise several points for discussion: 1. Killing animals is an act of cruelty. 2. Since the amount of energy needed in producing meat is ten times greater than that for producing grain, the productivity of meat production is lower than that of grain. Grain can feed far more people than meat. As a large swell in the population of the world is expected, we will surely face a shortage of food. 3. Eating meat intakes not only protein, but also animal fat. It is injurious to our health. It can cause obesity, heart disease, cerebral blood problems and cancer. 4. It may be difficult to avoid infections such as bovine spongiform encephalopathy, foot-and-mouth disease and chicken influenza in raising cattle or pigs and breeding chickens. Such affected animals are not fit for providing a steady supply of food. Plants and grain are better qualified as food sources. 1 looked over the Bible to pick up some ideas about the contract between God and man, His ideas on eating meat, and the co-existence between man and animals. Here I have followed up the Book of Genesis, which consists of fifty chapters. The contents of the Book of Genesis are as follows: the Creation of Heaven and Earth, the Garden of Eden, Cain and Abel, from Adam to Noah, the Flood and Noah, the New World Order, the Tower of Babel and the Family Tree of Abraham, the Story of Abraham and the First Half of the Life of Isaac, the Latter Half of the Life of Isaac and the Story of Jacob, the Family of Esau, the Last Blessing and Death of Jacob, and the Death of Joseph. Finally, I came to understand "what" and "how" man eats, how man eats "meat" and how "created man, plant and animal" can co-exist.
1 0 0 0 OA マナと聖霊
- 著者
- 石森 大知
- 出版者
- 日本文化人類学会
- 雑誌
- 日本文化人類学会研究大会発表要旨集 日本文化人類学会第42回研究大会 (ISSN:21897964)
- 巻号頁・発行日
- pp.171, 2008 (Released:2008-05-27)
マナをめぐる議論は、19世紀末のコドリントンによる報告以来、大変な蓄積がある。しかし、太平洋の人々がキリスト教徒となった現在でも、マナは伝統的信仰の象徴として扱われる一方、同概念とキリスト教的価値観との関連性は不問にされてきた。そこで本発表では、ソロモン諸島の事例に依拠し、マナは、聖霊とも結びつき、名詞的または実体的な「超自然的力」と認識されていることを明らかにするとともに、その社会・歴史的背景について考察をおこなう。
1 0 0 0 OA 胃上部 (C領域) 早期癌のX線診断学に関する研究
- 著者
- 最所 大輔 加治 文也 浜田 勉
- 出版者
- 順天堂医学会
- 雑誌
- 順天堂医学 (ISSN:00226769)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, no.4, pp.507-515, 1990-02-20 (Released:2014-11-20)
- 参考文献数
- 22
胃上部 (C領域) における早期癌の診断を向上させるために, 同領域の早期癌83例86病変 (噴門部癌19例20病変を含む) について, 食道胃接合部から癌の中心までの距離が1cm以内にあるものをCA1群, 2cm以内にあるものをCA2群, 2.1-4cmの噴門部近傍にあるものをNC群, 4.1cm以上離れた体上部にあるものをUB群とし, 各々の病巣についてX線診断学的な観察を行った. 1) C領域および噴門部における早期癌の頻度は11.2%と2.6%で, 他の領域に比較して早期癌の占める割合が低く, 陥凹型にm癌が少なく, 同部における陥凹型早期癌の診断が困難であることを示していた. 食道胃接合部に近づくにつれて分化型癌の占める割合は増加し, 11-30mmの大きさを示すものではsmへ浸潤する病変が増加した. 2) X線による確定診断は隆起型では18病変中15病変 (83.3%) が可能であり, 陥凹型では60病変中39病変 (65.0%) であり, うちCA1群では9病変中3病変 (33.3%), CA2群では6病変中6病変 (100%), NC群では22病変中12病変 (54.5%), UB群では23病変中18病変 (78.3%) であった. CA1群では接合部に接する瘢痕のない癌の診断が不良で, 空気量を多くして噴門部の粘膜ひだを伸展し, 噴門が開いた状態で撮影することにより診断能が向上できた. また, NC群およびUB群では前壁にある早期癌の診断率が低く, 腹臥位二重造影を加えることにより診断率が向上した.
1 0 0 0 OA 最近の産業用インクジェット技術について
- 著者
- 柴谷 正也
- 出版者
- 社団法人 日本印刷学会
- 雑誌
- 日本印刷学会誌 (ISSN:09143319)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, no.4, pp.246-250, 2011 (Released:2011-09-15)
- 参考文献数
- 9
- 被引用文献数
- 1
Inkjet textile printing and IC marking devices are examples of the latest advances in industrial inkjet applications. The use of the inkjet textile printing technology is spreading in the Italian high-quality cloth market because of its ability to cater to on-demand printing requirements while providing excellent quality. For example, Monnalisa, which has specific colored inks and requires an integrated, densely-packed print head, has successfully achieved high-grade print quality even for high production rates. It will produce the expected result in markets in other nations provided users take interest in the promotion of digitalization for small-lot production. Inkjet IC marking devices have the advantage of being able to produce damage-free ICs, while printing images having good visibility and providing the on-demand printability feature. For example, IP2000 is printed on with visible white ink that is used in combination with UV and heat cure systems. This technology will evolve suitably to enable its use with small IC chips or thinned array packages in the near future. Inkjet technology is said to have a wide range of existing and potential applications in the industrial sector. As inkjet technology progresses, it appears that further progress in this technology requires simultaneous advances in the peripheral technology that enhances the overall inkjet printing system.
1 0 0 0 秋元安民選『類題青藍集』姓名録
- 著者
- 板東 優実
- 出版者
- 人文資料学会事務局
- 雑誌
- 人文資料研究 (ISSN:18834671)
- 巻号頁・発行日
- no.12, pp.1-14, 2020-03-25
1 0 0 0 OA 李登輝総統の言語文化体験について
1 0 0 0 IR 催馬楽《貫河》考 : 詞章解釈の視点を定める
- 著者
- 本塚 亘
- 出版者
- 法政大学大学院
- 雑誌
- 法政大学大学院紀要 (ISSN:03872610)
- 巻号頁・発行日
- no.70, pp.198-188, 2013
1 0 0 0 書評 山寺美紀子著『国宝『碣石調幽蘭第五』の研究』
- 著者
- 遠藤 徹
- 出版者
- 東洋音楽学会 ; [1936]-
- 雑誌
- 東洋音楽研究 = Journal of the Society for Research in Asiatic Music (ISSN:00393851)
- 巻号頁・発行日
- no.78, pp.133-136, 2012