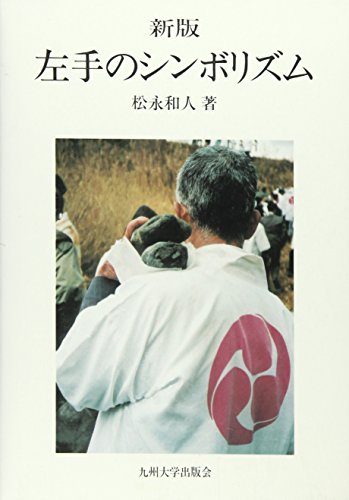1 0 0 0 IR 『弁論術』と『トポス論』のトポスの共通点と差異
- 著者
- 髙橋 祥吾
- 出版者
- 広島大学比較論理学プロジェクト研究センター
- 雑誌
- 比較論理学研究 (ISSN:18806376)
- 巻号頁・発行日
- no.14, pp.7-20, 2017-03-25
広島大学比較論理学プロジェクト研究センター研究成果報告書(2016年度)本稿は,文部科学省科学研究費補助金(研究活動スタート支援)「アリストテレスの問答法の理論とその発展的解釈の研究」(研究課題番号:15H06815) の研究成果の一部である.
1 0 0 0 IR アリストテレスの倫理学の自然学への依存関係についての論点
- 著者
- 高橋 祥吾
- 出版者
- 広島大学比較論理学プロジェクト研究センター
- 雑誌
- 比較論理学研究 (ISSN:18806376)
- 巻号頁・発行日
- no.16, pp.5-12, 2019-03-25
広島大学比較論理学プロジェクト研究センター研究成果報告書(2018年度)本稿は,文部科学省科学研究費補助金「アリストテレス倫理学の再定位を通した新たな自然主義的倫理学の構想」17H02257の助成の成果の一部である.
1 0 0 0 IR <研究>近世史學史上に於ける國學の貢獻
- 著者
- 村岡 典嗣
- 出版者
- 史學硏究會 (京都帝國大學文學部内)
- 雑誌
- 史林 = THE SHIRIN (JOURNAL OF HISTORY) (ISSN:03869369)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, no.1, pp.30-41, 1928-01-01
1 0 0 0 早稲田大学改革運動史〔大正5〜6年「大学紛争事件」の記録〕
- 著者
- 村岡 典嗣
- 出版者
- 早稲田大学大学史資料センタ-
- 雑誌
- 早稲田大学史記要 (ISSN:05111919)
- 巻号頁・発行日
- no.4, pp.39-52, 1971-03
1 0 0 0 特集 村岡典嗣--新資料の紹介と展望
- 出版者
- ぺりかん社
- 雑誌
- 季刊日本思想史 (ISSN:03853195)
- 巻号頁・発行日
- no.74, pp.3-159, 2009
1 0 0 0 OA 平成5年産水稲不作の原因と今後の稲作技術対策
- 著者
- 宮田 悟
- 出版者
- 公益財団法人 日本醸造協会
- 雑誌
- 日本醸造協会誌 (ISSN:09147314)
- 巻号頁・発行日
- vol.89, no.8, pp.585-588, 1994-08-15 (Released:2011-09-20)
- 参考文献数
- 1
米の品種と醸造特性はもとより, 最近は栽培条件と醸造特性に関心が払われるようになってきた。米作に携わる人々にとっては何よりも収穫量の確保が最優先課題と思われるが, 過去に例をみない平成5年の不作のときでさえ, 周辺が壊滅状態の中で平年並みに近い収穫をあげた農家があるという。それほど栽培技術はいろいろな可能性を秘めているが, 今後醸造特性との関連を究明していくうえで興味ある体験であったと言える。酒造家が稲作も兼業するケースがみられるようになって, 今後ますますその分野の研究が進展することが期待される。
1 0 0 0 OA 肥育牛の血中ビタミンAセンサの開発ならびに地域戦略に基づく精密管理
1 0 0 0 裁判員裁判と法の素朴理論
- 著者
- 松村 良之 木下 麻奈子 白取 祐司 佐伯 昌彦 村山 眞維 太田 勝造 今井 猛嘉 林 美春 綿村 英一郎 長谷川 晃
- 出版者
- 明治大学
- 雑誌
- 基盤研究(B)
- 巻号頁・発行日
- 2017-04-01
2020年度には実査が予定されているので、総括班、社会調査班を中心に実査の大枠を固めた。本調査は継続調査であり、第1、2波の調査と同一の調査方法によることが必須であることが確認された。予算制約の結果、抽出サンプル数は900(予想回収数500)であり、第1波、第2波調査の半分程度となるが、統計学的に許容できる水準であることが確認された。調査票については、16頁構成のうち、シナリオ部分約4頁を新規設問に入れ替えることが確認された。そして、心理学班も加えて検討した結果、責任主義関連項目では、心理学的な能動性(moral agency)評価と責任能力、少年、過失・故意を取り上げることとした。心理学班は第1に、日本人の法意識の背後にあると想定される公正観(公正世界尺度に由来する「運の等量仮説」、ハイトに由来する道徳尺度の日本バージョンなど)尺度の開発を試た。さらに、agency性評価の心理尺度について、その妥当性、信頼性を検討し調査票に組み込むべく準備した。第2に、少年犯罪について、人々が少年を罰しようとする応報感情の性質について検討した。世論は非行少年に対して厳罰志向的な態度を有しているが、他面、非行少年の置かれた環境的負因(責任主義につながる)について全く意識していないわけではない。そのことを踏まえて、少年に対する保護と刑罰という観点からの質問票作成を試みた。第3に、刑事法学班と協力して、刑法学の観点からは学説史に遡りつつ、また近年の脳科学の成果を踏まえた自由意思についての見解にもよりつつ、錯誤論、共犯論と関連させて過失・故意の教義学的議論について検討を深めた。それを踏まえて、大きくは結果責任と主観責任という枠組みで、質問項目を検討した(なお、少年、過失・故意については、シナリオを用いた実験計画法による)。
1 0 0 0 ヒドロキシクロロキン
- 著者
- 横川 直人
- 出版者
- 一般社団法人 日本内科学会
- 雑誌
- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)
- 巻号頁・発行日
- vol.100, no.10, pp.2960-2965, 2011-10-10
- 参考文献数
- 31
- 被引用文献数
- 2
ヒドロキシクロロキンは,半世紀以上前に初めて承認されて以降,日本を除く全世界70カ国以上で皮膚エリテマトーデス,全身性エリテマトーデス,関節リウマチの治療薬として承認され,世界的な標準的治療薬として,教科書や欧米のガイドラインには必ず記載されている.日本では過去に抗マラリア薬は存在したが,適切な使用方法が周知されなかったことによるクロロキン網膜症の懸念より昭和49年より一剤もなくなり,ヒドロキシクロロキンは開発されることはなかった.日本にSLEの標準的治療薬がないことに危惧した著者らは,2009年に日本ヒドロキシクロロキン研究会を結成し,未承認薬の開発要望書を提出した.その結果,2010年11月の未承認薬・適応外薬検討会議において,本剤の医療上の必要性が正式に認められ,製薬企業に対して開発要請が出された.2012年より,産官学の協力により全身性エリテマトーデスおよび皮膚エリテマトーデスの患者を対象に製薬企業による本薬の開発治験が行われる.稀だが重篤な副作用である網膜症を生じさせないためにも,本治験後の国内承認を待ち,本剤の個人輸入は控えることが肝要である.<br>
1 0 0 0 OA アクリル酸エステルの配合によるジアリルフタレート樹脂の 硬化物物性への影響
- 著者
- 大塚 恵子 木村 肇 松本 明博
- 出版者
- 合成樹脂工業協会
- 雑誌
- ネットワークポリマー (ISSN:13420577)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, no.1, pp.24-30, 2014-01-10 (Released:2014-04-23)
- 参考文献数
- 19
- 被引用文献数
- 3
ジアリルフタレート樹脂の接着性と靭性向上を目的として,ポリエチレングリコールユニットの異なるアクリル酸エステルをジアリルフタレート樹脂に配合し,ラジカル重合で同時に反応させることで相互侵入高分子網目構造(IPN)を形成させた。破壊靭性値,およびはく離接着強度とせん断接着強度は,アクリル酸エステルのポリエチレングリコールユニットの分子量や配合割合が大きくなるに従って大きく向上した。特にポリエチレングリコールユニットの分子量が大きい場合に,破壊靭性値と接着強度はジアリルフタレート樹脂と比較して2 倍以上の値を示した。これは,ポリエチレングリコールユニットの導入による柔軟性付与,および柔軟性付与により硬化過程で生じる接着剤層の内部応力が緩和されるためであると考えられ,動的粘弾性挙動と一致した。また,ポリエチレングリコールユニットの分子量の小さいアクリル酸エステルを配合した場合やポリエチレングリコールユニットの分子量の大きいアクリル酸エステルの配合割合が小さい場合には,ジアリルフタレート樹脂にアクリル酸エステルが相溶したIPN を形成した。一方,ポリエチレングリコールユニットの分子量の大きいアクリル酸エステルを20 wt% 以上配合した場合には,ジアリルフタレート樹脂架橋構造中にアクリル酸エステルが分子レベルで微分散した相分離型IPN を形成した。
1 0 0 0 作家用語索引夏目漱石
- 著者
- 近代作家用語研究会 教育技術研究所編
- 出版者
- 教育社出版サービス(発売)
- 巻号頁・発行日
- 1984
1 0 0 0 OA 災害時にコミュニティFMが果たす役割
- 著者
- 初澤 敏生 天野 和彦
- 出版者
- 公益社団法人 日本地理学会
- 雑誌
- 日本地理学会発表要旨集 2020年度日本地理学会春季学術大会
- 巻号頁・発行日
- pp.216, 2020 (Released:2020-03-30)
1.コミュニティFMとは コミュニティFMは1992年に市区町村単位の地域を対象として制度化された半径10〜20km程度の範囲を受信エリアとする地域限定のラジオ放送局である。地域に密着した放送局であることから、地域の災害対応などで大きな役割を果たすことが期待されている。しかしその活動の実態に関しては十分に把握されていない。本研究では福島県須賀川市のコミュニティFMであるULTRA FMを事例に、令和元年台風19号への対応を検討する。 2.ULTRA FMの概要 ULTRA FMはまちづくり会社「こぷろ須賀川」が運営するコミュニティFMである。「こぷろ須賀川」は須賀川市、須賀川商工会議所、地元企業等の出資によって2017年に設立された第三セクターで、中心市街地の活性化に取り組んでいる。ULTRA FMは2019年1月11日の開局であるが、2018年11月12日に須賀川市との間で「災害時における放送要請及び緊急放送等に関する協定」を結んでいる。設立当初から災害対応が期待されていたと言える。 運営に当たる職員は営業を含めて5名であるが、パーソナリティは30名を超える。年間運営経費は人件費を除き約1500万円、このうち約800万円が須賀川市からの補助金である。放送時間は24時間であるが、独自番組(生放送)は月〜金曜日は6時間、土・日曜日は2時間で、残りの時間は東京FM系のMusic Birdから番組を購入して放送している。 3.ULTRA FM設立の背景 ULTRA FMの設立に当たっては、何人かのキーパーソンがいた。その一人が「こぷろ須賀川」副社長のA氏である。A氏は東日本大震災の際に須賀川市の災害FMの運営に当たったが、これは短期間で閉局を余儀なくされた。A氏はその後もラジオを用いたまちづくりを追及し、ULTRA FMの開局につなげた。 局長を務めるB氏は地元の地域紙である「マメタイムス」の記者を長く務め、地域の事情に精通している。 ディレクターを務めるC氏は東京FM系の制作会社に勤めていたが、ふくしまFMの設立にともなって移籍、その後独立して活動していたが、2010年に郡山市のコミュニティFM設立に携わり、その後郡山市に避難していた富岡町のコミュニティFMを運営し、ULTRA FMの設立にともなって現職に就いた。 このように、ULTRA FMではキーパーソンがいずれも東日本大震災を報道・放送の場で経験し、その後の災害FMの運営などに関わっていた。災害対応に強い思いを持つ人々がこの放送局の核となっている。それが令和元年台風19号への対応に活かされた。 4.令和元年台風19号への対応 ULTRA FMは通常は夜間は無人で放送を行っているが、台風19号は夜に来ることがわかっていたので、10月12日から13日にかけてはA・B・C3氏と急を聞いて駆け付けた市内のパーソナリティの方、計4名で24時間体制で放送を行った。 放送にあたって課題になったのは情報収集である。前述のとおりULTRA FMは市と災害協定を結んでいた。市としては風雨が強い際には防災無線が聞こえない恐れがあるため、ラジオ放送でそれを代替したいと考えていた。そのため、災害時には市が情報を提供することになっていたが、十分な情報が伝えられなかった。そのため、A氏とB氏が市内を取材して、C氏とパーソナリティの方が放送を担当した。A・B両氏は市内の状況を熟知していたため、どこが被災しやすいかを知っており、そこを取材した。取材内容は電話を通して放送された。 5.今回の対応の課題 ULTRA FMの今回の対応で最も大きな課題は情報収集である。従業員数5人のFM局の取材能力は限られる。そのために市と災害協定を結んで情報提供を受けることになっていたが、市からの情報提供は滞りがちになり、独自の情報収集を強いられた。発災時、市には様々な情報が集まる。それを市民と共有することが必要である。 また、放送に関する課題もある。ULTRA FMは通常の番組の途中に臨時ニュースを流す形をとったが、このような放送では、より多くの情報を求める人々は他の手段を求めることになろう。従業員数から見ればやむを得ないことではあるが、災害時の番組編成を再検討する必要がある。行政等と連携した日常的な準備を期待したい。
1 0 0 0 IR 若王子神社(禅林寺新熊野社)の創始 : 覚讃と後白河院
- 著者
- 菅野 扶美 Fumi Sugano
- 出版者
- 共立女子短期大学文科
- 雑誌
- 共立女子短期大学文科紀要 (ISSN:03883647)
- 巻号頁・発行日
- no.62, pp.11-22, 2019-01
1 0 0 0 IR 元正天皇期の政権構造
- 著者
- 佐々木 律子 SASAKI Ritsuko
- 出版者
- 北海学園大学大学院文学研究科
- 雑誌
- 年報新人文学 (ISSN:18831524)
- 巻号頁・発行日
- no.15, pp.58-102, 2018-12