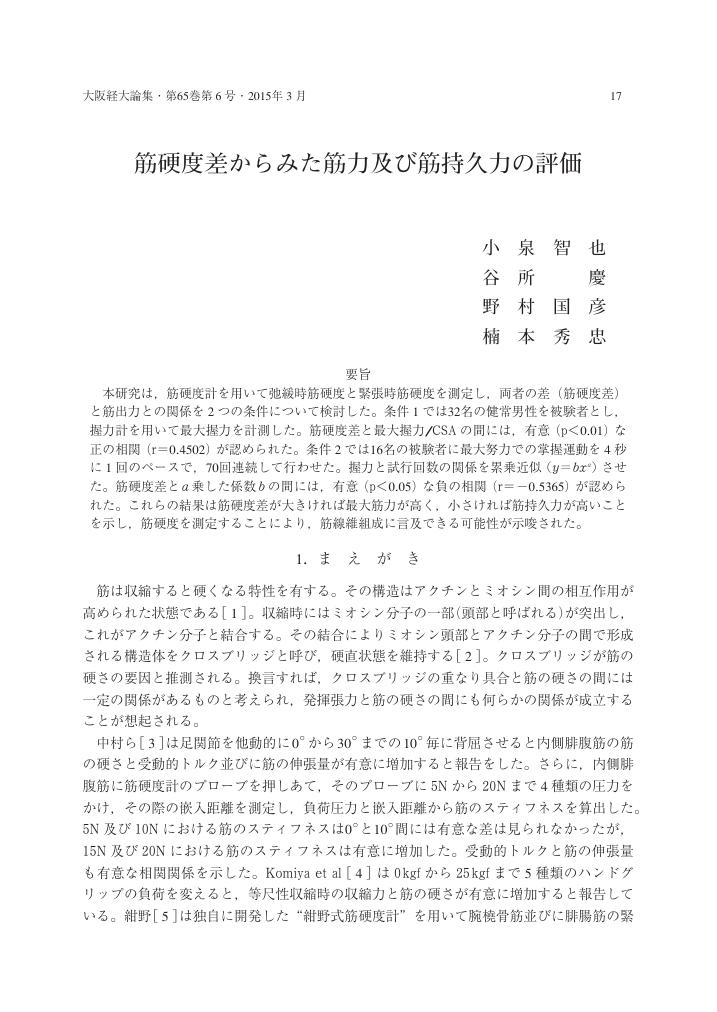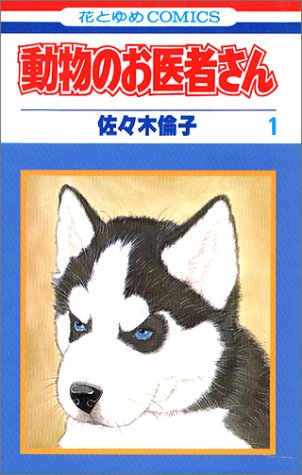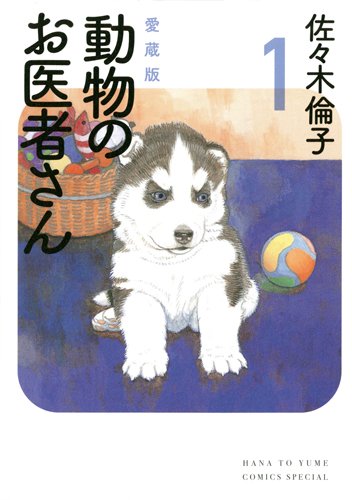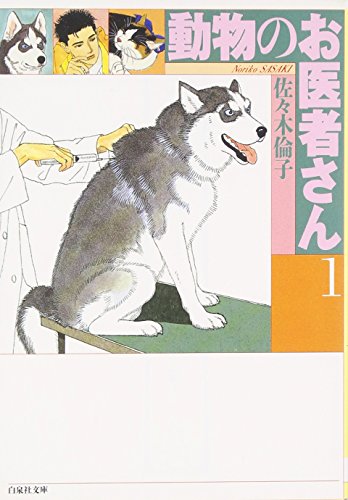1 0 0 0 OA 記録としてのテレビ番組が描く「核と人間」
- 著者
- 松下 峻也
- 出版者
- 法政大学社会学部学会
- 雑誌
- 社会志林 = Hosei journal of sociology and social sciences (ISSN:13445952)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.3, pp.89-103, 2019-12
- 著者
- 別府 三奈子
- 出版者
- 法政大学社会学部学会
- 雑誌
- 社会志林 = Hosei journal of sociology and social sciences (ISSN:13445952)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.2, pp.1-41, 2019-09
1 0 0 0 主観性と見えない参与者の可視化 : 客体化の認知プロセス
- 著者
- 町田 章
- 出版者
- 日本認知言語学会
- 雑誌
- 日本認知言語学会論文集
- 巻号頁・発行日
- vol.12, pp.246-258, 2012
1 0 0 0 OA 「自立」概念の歴史的変遷と現代的意義の検討
- 著者
- 真鍋 里彩
- 出版者
- 大阪府立大学大学院 人間社会システム科学研究科
- 雑誌
- 人間社会学研究集録 (ISSN:1880683X)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, pp.167-188, 2020-03-31
1 0 0 0 OA 競泳選手のクロール泳動作中の膝関節可動域および筋活動について : 反張膝に着目して
- 著者
- 栗木 明裕 市川 浩 田場 昭一郎 田原 亮二 田口 正公 Kuriki Akihiro Ichikawa Hiroshi Taba Shoichiro Tahara Ryoji Taguchi Masahiro
- 出版者
- 福岡大学研究推進部
- 雑誌
- 福岡大学スポーツ科学研究 = Fukuoka University Review of Sports and Health Science (ISSN:13459244)
- 巻号頁・発行日
- vol.44, no.2, pp.67-75, 2014-03
1 0 0 0 OA 戦前から戦後にかけての頭髪における記事分析 : 『主婦之友』から読み解く黒髪の変遷
- 著者
- 横山 友子
- 出版者
- 大阪府立大学大学院 人間社会システム科学研究科
- 雑誌
- 人間社会学研究集録 (ISSN:1880683X)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, pp.93-112, 2020-03-31
1 0 0 0 OA 各種消毒薬の殺菌効果について(第3報)
1 0 0 0 OA 炭化物を含有する胎土の土偶
- 著者
- 宮内 信雄 吉田 邦夫 菅沼 亘 宮尾 亨
- 出版者
- 一般社団法人 日本考古学協会
- 雑誌
- 日本考古学 (ISSN:13408488)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, no.23, pp.89-104, 2007-05-20 (Released:2009-02-16)
- 参考文献数
- 28
胎土に黒色物質を持つ縄文時代中期の土偶を,新潟県十日町市幅上遺跡で発見した。このような黒色物質が土偶胎土に含まれる例は見たことがなく,軟X線とX線CT画像による含有状態の観察,蛍光X線分析,安定同位体分析による材質分析,さらに放射性炭素年代測定を実施し,その由来について分析を行った。分析の結果,(1)黒色物質は胎土全体に均質に含まれていると推測でき,素地土の中に練りこまれていたと考えられる。(2)黒色物質は炭化物である。炭素・窒素安定同位体比では,C3植物の樹木,種実などに相当する値を示しており,C3植物あるいは,C3植物を食料とする草食動物の肉に由来する炭化残存物であると考えられる。(3)黒色物質の放射性炭素年代は,土偶の型式学的分類に基づく編年によって与えられた年代と調和した値を示し,それゆえ,自然堆積粘土に元来含まれていたとは考えにくいことがわかった。素地製作時の黒色物質の状態については,X線CTによる断面画像に黒色物質の大きさほどの空洞が観察されないこと,加熱時の収縮率が高い生の物質を焼成にした際に推測される,素地土と黒色物質との間の隙間がほとんどなく,よく密着していることから,炭化物を混入したものと考えられる。最も大きい含有物であるこの炭化物が製作途中で気付かれないことは考えにくく,しかも,含有物が土偶の胎土全体に均質に混じっている状況は,製作者の何らかの意図があったことを想定させる。祭祀・儀礼の道具とされる土偶は,カタチのみならず素材の選定や調整にまで目配りすることで様式化される観念技術(小林1997)の所産であることを,異物が含まれる土偶や,民俗・民族例を参照することで傍証するとともに,本土偶の胎土に含まれている炭化物についても,このような工程の中にあった可能性を考えた。
1 0 0 0 OA 生駒西麓(東大阪市)産の縄文土器の胎土材料
- 著者
- 藤根 久 小坂 和夫
- 出版者
- Japan Association for Quaternary Research
- 雑誌
- 第四紀研究 (ISSN:04182642)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.1, pp.55-62, 1997-02-28 (Released:2009-08-21)
- 参考文献数
- 42
生駒山地西麓地域(東大阪市河内地域)から産出する縄文時代後期および晩期の土器の中には,その胎土が暗褐色~茶褐色を呈し,角閃石類を多量に含むという特徴を有する土器群があることが知られている.これらの特徴を有する土器は,“河内の土器”と一般的に呼称されており,他地域の土器とはもちろん,この地域のほかの土器とも容易に識別される.これらの土器について,土器薄片を作成し,偏光顕微鏡下において観察と記載とを行った.その結果,(1)これらの胎土中の粒子の大きさ分布は5μmから250μmの範囲で,破砕物が一般的に示すフラクタル性(スケーリング則)を有すること,(2)粘土の質・量とも断層内物質の一般的特徴を有すること,(3)粘土は一般的に用いられていたものとは異なり,接着性が非常に高い特異なものであることが明らかになった.さらに,鉱物・岩石片からなる粒子には,破片状の尖った外形を呈するものが多く,断層岩に特徴的な粒内微小断層や微角礫状組織あるいはカタクラサイト状組織を呈するものもあり,顕著な不連続的波動消光や双晶面のたわみ・キングバンドや機械的双晶という変形岩・断層岩を特徴付ける組織が多いこと,が明らかになった.以上のような土器胎土の特徴から,その材料として断層内物質が用いられた可能性がきわめて大きいと考えられ,胎土材料としてほかの材料を考えることは困難である.その産地としては,岩石学的・地質学的特徴から生駒山地西縁を南北に走る生駒断層の破砕帯が最も可能性が高いものとしてあげられる.
1 0 0 0 OA 強酸性湖潟沼におけるサンユスリカ幼虫の二次生産
1 0 0 0 マンガン製糖法に関する研究
1 0 0 0 IR 恋愛関係における別れに関する研究(1) --別れの主導権と別れの季節の探求--
- 出版者
- 高松大学
- 雑誌
- 高松大学紀要 (ISSN:13427903)
- 巻号頁・発行日
- no.41, pp.87-105,
1 0 0 0 OA 筋硬度差からみた筋力及び筋持久力の評価
1 0 0 0 OA 学会消息
- 出版者
- 中世文学会
- 雑誌
- 中世文学 (ISSN:05782376)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, pp.42-45, 1960 (Released:2018-02-09)
1 0 0 0 OA 筋硬度に関する研究 (第一報)
- 著者
- 紺野 義雄
- 出版者
- 一般社団法人日本体力医学会
- 雑誌
- 体力科学 (ISSN:0039906X)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, no.5, pp.180-185, 1952-04-02 (Released:2010-09-30)
- 被引用文献数
- 3 1
本調査の結果を摘要すると次の如くなる。(1) 11才より18才迄年令的に, 男子に於て著うしい変化をみない。(2) 男女の筋硬度の差は13, 14才頃より現れ, 漸次その差は大きくなる。即ち女子は13, 14才頃より硬度が低くなる.(3) 女子は男子に比して硬度差が稍々小さい。(4) 硬度差は, 身長, 体重, 周囲長, 皮下脂肪との関係はないと思あれる。(5) 走力, 跳躍力, 握力と相関があり硬度差の大なる者は運動能力が大であると言える。(6) 集団の相関より個人相関が大である。(7) 優秀選手は一般の者より硬度差が大きい, 又緊張硬度が高かつた。
1 0 0 0 OA 外来種フタモンテントウの日本における分布状況と在来テントウムシとの関係
- 著者
- 戸田 裕子 桜谷 保之
- 出版者
- 日本生態学会
- 雑誌
- 日本生態学会大会講演要旨集 第51回日本生態学会大会 釧路大会
- 巻号頁・発行日
- pp.186, 2004 (Released:2004-07-30)
フタモンテントウ(〈I〉Adalia bipunctata〈/I〉)は、1993年に大阪市南港において日本で初めて発見され、外来種と考えられている。1993年以降これまで発見地を中心に継続的に調査を行ってきた。本研究では発見地および周辺の公園・緑地等において、侵入後の分布や生活史、在来テントウムシとの種間関係を調査した。分布については、最初の発見地である南港中央公園(350m×500m)において発見以来ほぼ毎年発生が確認されているが、他の場所では2001年まで発生がみられず、分布の拡大は起こっていないと考えられた。しかし、2002年には2から3kmほど離れた2ヶ所で発生がみられるようになり、2003年には新たに2ヶ所で分布が確認された。2004年には南港地区(約3km四方)のほとんどの調査地で発生が確認され、南港以外の大阪府内や、約20km離れた兵庫県神戸市でも発生が確認された。発生密度は南港中央公園で最も高く、そこから離れるに従って減少する傾向にあった。したがって、南港中央公園が最初の侵入地で、発生の中心と推察された。この2から3年で分布がかなり広がり、さらに飛び火的に拡大する傾向にあると考えられる。種間関係については、フタモンテントウと同じ樹上(シャリンバイやトウカエデ)に生息する在来種ナミテントウとの個体数関係を中心に調べた。その結果、フタモンテントウの生息密度が高い地域の方が低い地域よりもナミテントウの個体数の割合が低い傾向がみられ、フタモンテントウの個体数増加や分布拡大はナミテントウやダンダラテントウ等、在来テントウムシの生存に影響を与えつつあると推察される。
1 0 0 0 IR 過去の反実帰結を表すフランス語の半過去形と過去前未来形
- 著者
- 曽我 祐典 Yusuke Soga
- 出版者
- 関西学院大学人文学会
- 雑誌
- 人文論究 (ISSN:02866773)
- 巻号頁・発行日
- vol.67, no.1, pp.61-78, 2017-05