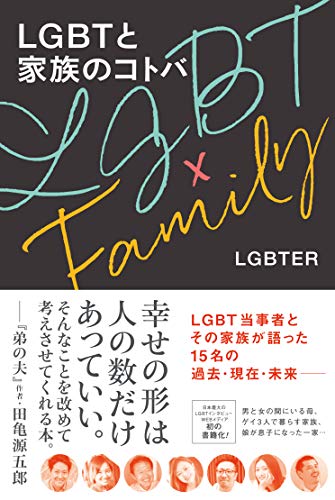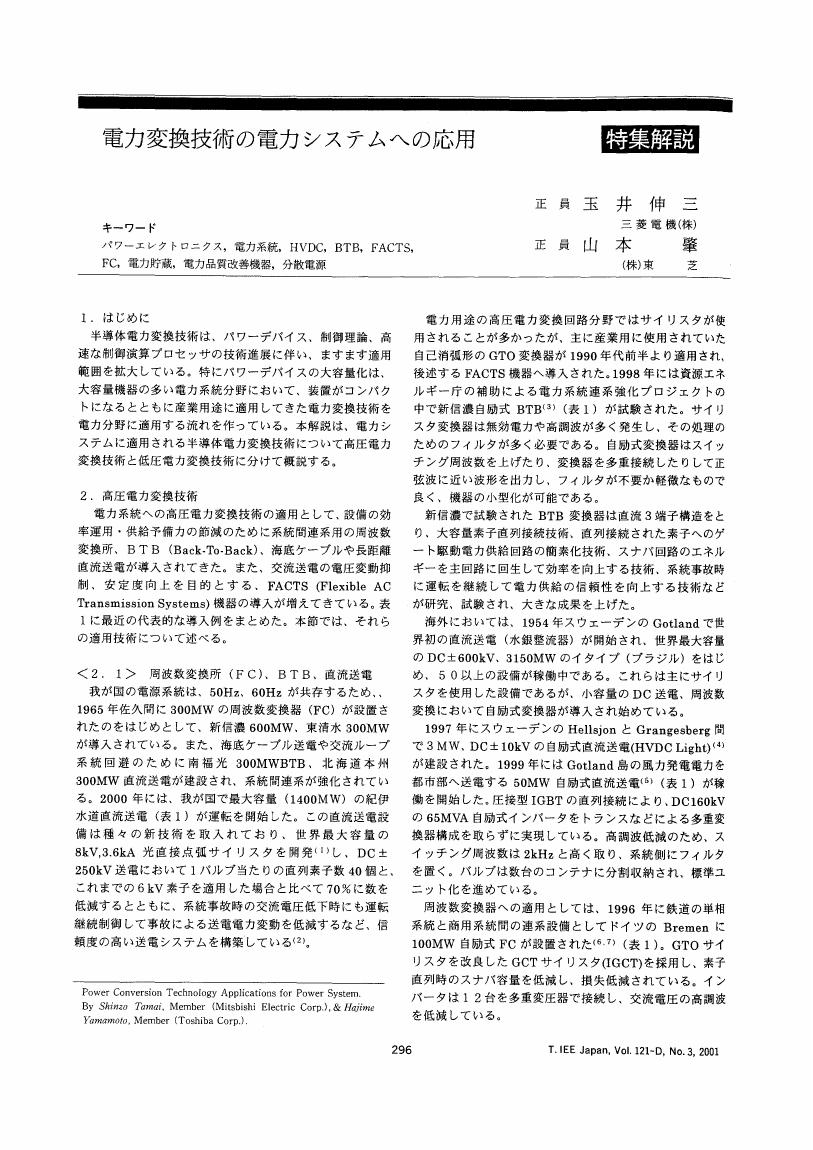1 0 0 0 OA 高齢者層の貧困化と社会保障制度の調整の失敗(2)
- 著者
- 北島 滋
- 出版者
- 旭川大学短期大学部
- 雑誌
- 旭川大学短期大学部紀要 = The journal of Junior College, Asahikawa University (ISSN:21861544)
- 巻号頁・発行日
- no.49, pp.9-16, 2019-03-31
In previous journal number 48th of our junior college, my thesis dealt with the declining or impoverishment of living standard concerning elderly people, and analyzed their factors. Firstly, it focused that impoverishment of elderly people was due to failure of the regulationin social security system according to regulation theory. Secondly, Aging in Japan was possible to predict such situations based on demographics since 1980's, therefore, and possible to do that fiscal expenditure of annuity insurance, medical insurance and care insurance would increase with aging. That reason why, government could get out of the trap of economic growth strategy, or not tried to get out of it. As result, government had to get debts deficit bonds beyond trillion yen. I called such situations "failure of regulation" in that thesis.This paper deal with a problem of national budget concerning elderly people in journal number 49th of our junior college. Especially I focus on a problem of reduction and restraint of the budget distributed to the Ministry of Health, Labour and Welfare. It's analyzed about a possibility of the reorganization of national budget concerning elderly people. When government is keeping reducing and restraining budget allocation to elderly people, persons with disabilities and people who need support, their life won't consist any more the near future. By a relation with failure of a regulation of a social security system, I refer about the theory of Prof. Taro Miyamoto's community which cooperates each other. I think his theory claims attention very in formation of citizen autonomy.
- 著者
- Akiyoshi TANI Taisuke SENO Nozomu YOKOYAMA Taisuke NAKAGAWA Hirotaka TOMIYASU Yuko GOTO-KOSHINO Hajime TSUJIMOTO Koichi OHNO
- 出版者
- JAPANESE SOCIETY OF VETERINARY SCIENCE
- 雑誌
- Journal of Veterinary Medical Science (ISSN:09167250)
- 巻号頁・発行日
- pp.19-0560, (Released:2020-02-14)
- 被引用文献数
- 1
Inflammatory colorectal polyps (ICRPs) are frequently observed in miniature dachshunds in Japan and treated by prednisolone and immunosuppressive drugs such as cyclosporine and leflunomide. The purpose of this retrospective study was to compare the treatment efficacy, such as response rate, response interval, recurrence rate, and adverse events between cyclosporine and leflunomide. While the response rates were significantly higher in dogs treated with leflunomide, no significant differences were observed in the response interval or recurrence rate. Two of the 11 dogs treated with leflunomide showed hematological or gastrointestinal adverse events, while no dog treated with cyclosporine showed any adverse events. A case-controlled prospective study to compare the treatment efficacy of leflunomide with that of cyclosporine should be conducted.
1 0 0 0 OA 新制度以降の自治体発の子育て支援・保育の取り組み
- 著者
- 大豆生田 啓友
- 出版者
- 公益財団法人 医療科学研究所
- 雑誌
- 医療と社会 (ISSN:09169202)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, no.1, pp.89-97, 2017-05-25 (Released:2017-06-13)
- 参考文献数
- 12
本論文では,子ども子育て支援新制度以降の自治体において取り組まれている子育て支援および保育の動向から,その意義と課題について考察した。1では,子ども・子育て支援新制度の目的を概説し,地方版の子ども・子育て会議を置くことを努力義務として位置付けられていることが,各自治体が独自の子育て支援の事業計画を作るチャンスであることを述べた。自治体の取り組みの調査では,その会議において,子育て当事者などの委員が意見を出しやすい雰囲気があることや,専門部会やワーキンググループを設置することなど市民参画が重要な傾向としてあげられたことを紹介した。2では,先進自治体の事例を紹介した。東京都墨田区では,委員による話し合いによる合意形成を行う取り組みや,幼稚園および保育所が協働した保育の質の向上の取り組みについて取り上げた。東京都世田谷区では,区の住民が主体的に行う子ども・子育て会議の取り組みと,保育ガイドライン作成について取り上げた。埼玉県和光市は,妊娠や出産からの切れ目のない子育て支援を行う「ネウボラ」の実践について取り上げた。神奈川県・横浜市では,利用者支援事業の取り組みと,幼保小の取り組みおよび保育の質向上の実践について取り上げた。3では,2での先進自治体の取り組みを通して,今後の自治体の取り組みのポイントとして,3点について考察した。第一は,市民の参画による自治体力の育成について考察した。第二は,産前から産後までの切れ目のない包括的な支援体制について考察した。第三には,乳幼児期の教育・保育の質向上の体制づくりについて考察した。
1 0 0 0 OA どうなっちゃったの?日本経済
- 著者
- 箕輪 京四郎
- 出版者
- 経済教育学会
- 雑誌
- 経済教育 (ISSN:13494058)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.36, pp.58-71, 2017 (Released:2018-08-10)
①A3用紙に,タテは1955〜2016年,ヨコは9つの時系列をとり,「基本統計表」を作った。②主にその基本統計表から,いくつかグラフを描いた。③教材に使える新聞記事(日付と見出し)を紹介した。④効率・成長第一の経済を反省し,福祉優先の,温かい経済を目指したい。⑤経済を学ぶ楽しさも伝えたい。これらの教材と姿勢を,パワーポイントで投影するか,コピーして配布,時系列の推移,また時系列間の関係を眺めると,いくつもの発見・驚き・感懐・疑問が生まれる。それらを,みんなでワイワイがやがや話し合いたい。教科書で用語の意味を確認しながら。
1 0 0 0 OA ポリエステル繊維の深色化加工
- 著者
- 平野 豊
- 出版者
- The Textile Machinery Society of Japan
- 雑誌
- 繊維機械学会誌 (ISSN:03710580)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.3, pp.P131-P135, 1984-03-25 (Released:2009-10-27)
- 参考文献数
- 31
- 被引用文献数
- 8 10
1 0 0 0 LGBTと家族のコトバ
1 0 0 0 生まれる性別をまちがえた!
1 0 0 0 IR 「緑」の「光」の「水」の--吉本ばなな『キッチン』論
- 著者
- 武田 信明
- 出版者
- 島大国文会
- 雑誌
- 島大国文 (ISSN:02892286)
- 巻号頁・発行日
- no.33, pp.159-168, 2011-03
1 0 0 0 OA アイスランド語のウムラウト : 名詞格変化の多様性
- 著者
- 八亀 五三男
- 出版者
- 名古屋学院大学総合研究所
- 雑誌
- 名古屋学院大学論集 言語・文化篇 = THE NAGOYA GAKUIN DAIGAKU RONSHU; Journal of Nagoya Gakuin University; LANGUAGE and CULTURE (ISSN:1344364X)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.1, pp.39-51, 2017-10-31
ゲルマン諸言語では,ウムラウト現象が大きな言語的特徴になっている。中でも,北ゲルマン語に属するアイスランド語には,他のゲルマン語に見られないような複雑なiウムラウト,uウムラウトが観察できる。ウムラウトという音韻現象を分析することによって,共時的言語現象を新たに通時的な視点から見直してみることがいかに重要であるかを明らかにするのが本稿の目的である。
1 0 0 0 IR 『資本論』形成史における『哲学の貧困』
- 著者
- 内田 弘
- 出版者
- 専修大学社会科学研究所
- 雑誌
- 社会科学年報 (ISSN:03899519)
- 巻号頁・発行日
- no.47, pp.27-57, 2013
1 0 0 0 OA 宇宙雪氷学から見た土星衛星系の成り立ち
- 著者
- 荒川 政彦
- 出版者
- The Japanese Society of Snow and Ice
- 雑誌
- 雪氷 (ISSN:03731006)
- 巻号頁・発行日
- vol.67, no.2, pp.147-154, 2005-03-15 (Released:2009-08-07)
- 参考文献数
- 7
雪氷のフィールドを地球から太陽系の惑星・衛星にまで広げた時に現れる雪氷学の新たな研究課題を総称して宇宙雪氷学と呼ぶ.この課題の一つに土星の衛星系が持つサイズと平均密度の正の相関関係がある.この関係は,衛星の衝突集積時に起こる衝突分別過程で説明できる.この分別過程は,氷衛星の岩石含有率の差に起因する衝突破壊強度の違いにより引き起されると考えられる.
- 著者
- 白戸 健一郎
- 出版者
- 京都大学大学院教育学研究科生涯教育学講座
- 雑誌
- 京都大学生涯教育学・図書館情報学研究 (ISSN:13471562)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, pp.123-137, 2010-03
1 0 0 0 OA 超越論的仮象としての未来
- 著者
- 中島 義道
- 出版者
- 日本哲学会
- 雑誌
- 哲学 (ISSN:03873358)
- 巻号頁・発行日
- vol.2014, no.65, pp.43-54_L5, 2014-04-01 (Released:2016-06-30)
Es ist fragwüerdig, die Zukunft wie die Gegenwart und die Vergangenheit als Zeitmodus zu verstehen. Während die Wahrnehmung direkt die gegenwärrtigen Sahen und die Erinnerung direkt die vergangenen Sachen erreichen können, gibt es keinen Bewusstseinsakt, der direkt die zukünftigen Sachen erffassen könnte. Eine zukünftige Sache (A) kann nicht jetzt, sondern erst in der Vergangenheit, in der A „zukunfutig gewesen ist“ , gewährleistet werden. Also, muss man, um zu erfahren,ob A wahr ist oder nicht, immer bis zu dem Zeitpunkt warten, an dem A verwircklicht geworden ist d. h., an dem A den Charakter der Zukünftigkeit verloren hat. Man kann also die zukünftigen Sachen an sich nicht erfassen. Überdies kann man nicht leugnen,,, dass die Möglichkeit besteht, dass die nächste neue Zukunft nicht konnt. Es ist sicher so, dass bis jetzt die Zukunft immer gekommen ist,aber dies beweist keineswegs, dass von jetzt an die (nächste) Zukunft kommen wird.Die Zukunft scheint mir also kein Zeitmodus sondern nur ein Begriff, oder besser gesgt, eine Idee (nach Kant) zu sein.Die Zukunft ist nämlich kein Gegenstand der objektiven Erkenntnis,sondern nur ein Gegenstand unsres menschlichen (subjektiven) Interesses.Wir Menschen wissen gut, dass die Zukunft nicht objektiv existiert,aber sind geneigt, zu meinen dass die Zukunft objektiv existieren könnte und täuschen nus vielmehr absichtlich. Man muss (wieder nach Kant) sagen dass die Zukunft „ein transzendentaler, Schein“ ist.
飛騨外縁帯・南部北上帯・黒瀬川帯の古生界は, 層相と化石相が互いに類似する.3帯の基盤は前〜中期オルドビス紀のオフィオライトからなる.中部オルドビス系〜デボン系は頁岩と酸性凝灰岩を主体とするメランジュまたはタービダイトからなり, それらの一部は高圧型変成岩類になっている.石炭・ペルム系は頁岩, 砂岩, 礫岩, 石灰岩などで構成される陸棚相浅海成層からなり, 特に石炭系は大量の火山砕屑岩類を伴う.これらの古生界は前期オルドビス紀に中朝地塊縁辺の沈み込み帯で形成されはじめ, ペルム紀には北半球中緯度に位置した中朝地塊の東縁大陸棚に堆積盆が存在したと推定される.3帯の構造の大枠は, 前期白亜紀(Valanginian)に複数のナップやクリッペを形成した東または南フェルゲンツの衝上運動, および前期白亜紀(Aptian-Albian)の棚倉-中央構造線沿いの約1,500kmの左横ずれ運動によって形成した.
1 0 0 0 OA 東京女子医科大学東洋医学研究所における面状電気温熱器を用いた置鍼治療の安全性
- 著者
- 蛯子 慶三 高田 久実子 伊藤 隆 木村 容子 佐藤 弘
- 出版者
- 一般社団法人 日本東洋医学会
- 雑誌
- 日本東洋医学雑誌 (ISSN:02874857)
- 巻号頁・発行日
- vol.69, no.4, pp.402-406, 2018 (Released:2019-08-01)
- 参考文献数
- 3
当研究所では寒証に対して面状電気温熱器を用いた置鍼治療を行っている。腰背部8ヵ所に置鍼後に面状電気温熱器を被せ,6段階に温度調節できるダイアルのうち2番目に熱い5チャンネルで20分間加温する本法を,寒証の治療および検査として用いている。加温途中で熱さを不快に感じたときには,治療目的で用いた場合は温度を下げて継続,検査目的で用いた場合はその時点で終了としている。2016年3月から10月までの8ヵ月間に実施した75例(224件)を対象に有害事象を調査したところ,皮膚表面のヒリヒリ・チリチリした感じが5件(2.2%),かゆみが3件(1.3%),体調不良が1件(0.4%)みられたが,いずれも一時的なものであり,重篤な有害事象は認めなかった。結果より,本法の安全性は高いと考えられた。漢方と鍼灸の臨床研究に繋げていくことが今後の課題である。
1 0 0 0 OA ポリウレタン塗料について
- 著者
- 岡 福一
- 出版者
- 一般社団法人 色材協会
- 雑誌
- 色材協会誌 (ISSN:0010180X)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.7, pp.269-275, 1964-07-30 (Released:2012-11-20)
- 参考文献数
- 22
1 0 0 0 OA 訪問看護師が高齢者のフットケアについて感じていること ─実態調査の記述分析─
- 著者
- 平尾 由美子 小笠原 祐子
- 出版者
- 一般社団法人 日本フットケア学会
- 雑誌
- 日本フットケア学会雑誌 (ISSN:21877505)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.4, pp.175-180, 2019-12-25 (Released:2019-12-25)
- 参考文献数
- 14
【要旨】フットケア実施率向上への示唆を得ることを目的とし,訪問看護師による在宅療養高齢者へのフットケアに関する実態調査(2016年9月)の質問項目の1つである「在宅療養高齢者のフットケアについて感じていること」の自由記述回答を分析した.全国750か所の訪問看護事業所に対して郵送法により245施設(32.7%)から返送され,上記質問には122人から回答があった(回答率49.8%).質的記述的に分析し,319コードが得られ,【重要性・必要性】(88コード),【困難】(231コード)の2つのコアカテゴリーに分けられた.コード数が7割を占めた【困難】は,《療養者の要因》,《看護師の要因》,《環境の要因》のカテゴリーで構成された.《療養者の要因》から,在宅療養高齢者の医療処置を含むフットケアニーズの高まりが明らかとなった.在宅において,予防的フットケアの推進と同時に,医療的フットケアが実施可能な環境の整備の必要性が示唆された.
1 0 0 0 OA 戦時期,食品企業の満州進出について : 満州ヤマサ醤油株式会社を例にして
- 著者
- 落合 功 オチアイ コウ Kou Ochiai
- 雑誌
- 修道商学
- 巻号頁・発行日
- vol.45, no.2, pp.25-83, 2005-02-28
1 0 0 0 OA 電力変換技術の電力システムへの応用
- 著者
- 玉井 伸三 山本 肇
- 出版者
- The Institute of Electrical Engineers of Japan
- 雑誌
- 電気学会論文誌D(産業応用部門誌) (ISSN:09136339)
- 巻号頁・発行日
- vol.121, no.3, pp.296-301, 2001-03-01 (Released:2008-12-19)
- 参考文献数
- 30
- 被引用文献数
- 2