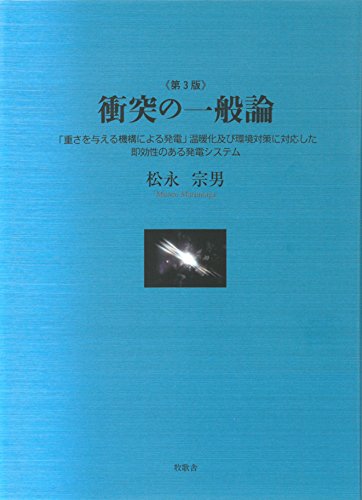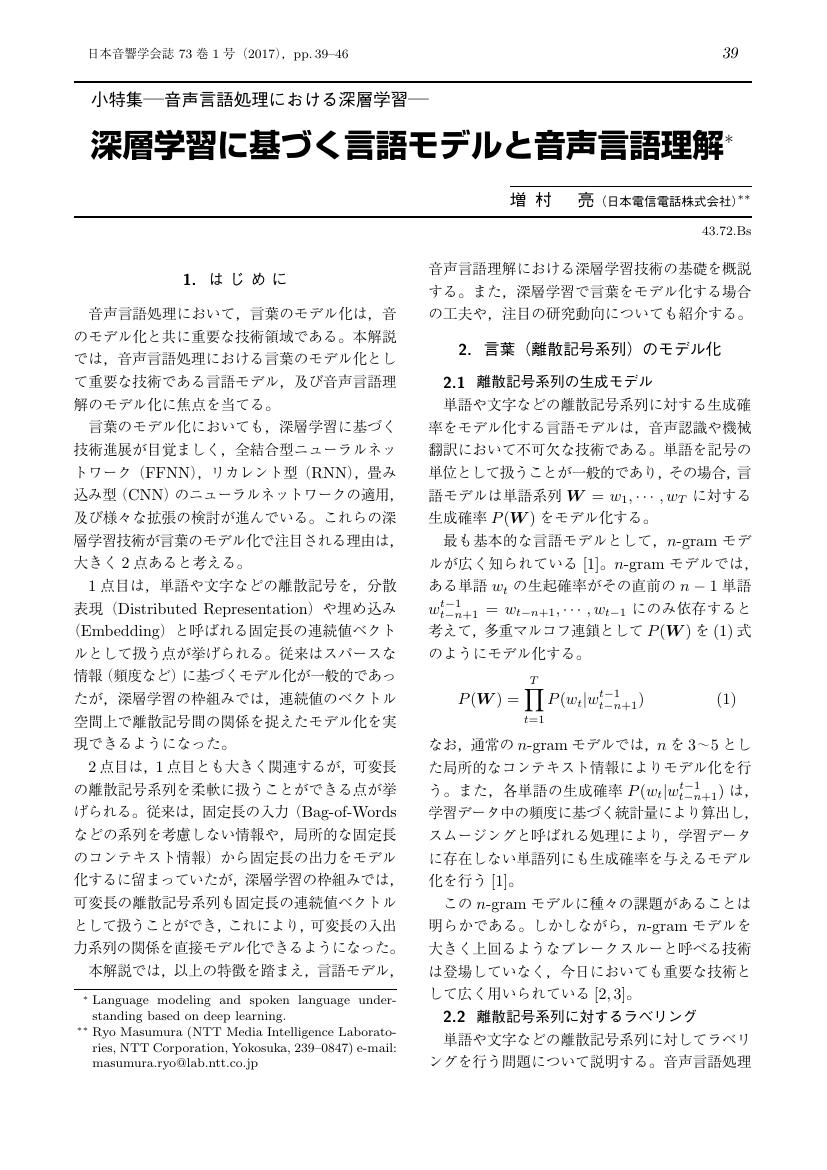- 著者
- 鈴木 建治
- 出版者
- 北海道大学大学院文学研究科北方研究教育センター
- 雑誌
- 北方人文研究 (ISSN:1882773X)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, pp.1-12, 2012-03-31
The purpose of the paper is to examine the contents and a part of history of an Ainu collection which were collected by A.V. Grigor’ev at the time of Japanese stay for one year from 1879 to 1880: 1) Why did he stay in Japan? 2) What kinds of materials were collected by him? 3) Why did he begin research Ainu culture and collect Ainu materials?
1 0 0 0 IR 在日中国人ニューカマーと教育-非集住地域に着目して-
1 0 0 0 OA 翻訳 中国人の宗教[含 解題]
- 著者
- 張 愛玲 徐 青[訳]
- 出版者
- 愛知大学国際問題研究所
- 雑誌
- 愛知大学国際問題研究所紀要 = Journal of international affairs (ISSN:05157781)
- 巻号頁・発行日
- no.137, pp.175-196, 2011-03
1 0 0 0 アイヌ文化展示と文化人類学的課題
- 著者
- 山崎 幸治
- 出版者
- 日本文化人類学会
- 雑誌
- 日本文化人類学会研究大会発表要旨集
- 巻号頁・発行日
- vol.2012, pp.20, 2012
本発表では、アイヌ文化に関する二つの展示実践を事例として、アイヌ研究にとどまらない文化人類学研究へのフィードバックが見込まれるトピックについて検討を加える。とりあげるトッピックは、【物質文化資料と情報】、【語りの「調整」】、【現代の展示】、【ノイズとしての「展示する側」】である。そこでは海外をフィールドとする文化人類学研究では見えにくい問題や、研究者に求められている「実践」についても論じる。
- 著者
- 渡辺 裕
- 出版者
- 岩波書店
- 雑誌
- 文学 (ISSN:03894029)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, no.6, pp.70-87, 2010-11
- 著者
- 西岡 弥生
- 出版者
- 一般社団法人 日本社会福祉学会
- 雑誌
- 社会福祉学 (ISSN:09110232)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.1, pp.17-32, 2019-05-31 (Released:2019-06-13)
- 参考文献数
- 15
本研究の目的は,「心中による虐待死」事例の家族危機形成プロセスを検証することによって,加害者とされた母親の「喪失体験」を明らかにすることである.具体的には,自治体報告書で報告された9事例を対象に,心中が企図されるまでの家族の生活状況を二重ABC-X理論を援用し検討した.家族は【前危機段階】で,すでに不安定な生活基盤と脆弱な家族機能の状態にあった.【危機発生段階】で母親は既存の役割を失い,【後危機段階】では母親を支える重要な家族成員や日常生活の安全感,さらに関与のあった支援機関等の間での社会関係を失うという複数の「喪失体験」にみまわれていたことが示された.喪失の累積によって母親は「悲哀の病理」に陥り,認知が閉塞した状況で「心中」を企図したものと推察された.母親の精神の危機は虐待の定義では捉えきれず,社会生活が困難な母親の状況と支援者側の認識との間に齟齬が生じ見過ごされた可能性が高いと考えられる.
- 著者
- 森田 亜希子 森 恵美 石井 邦子
- 出版者
- 日本母性衛生学会
- 雑誌
- 母性衛生 = Maternal health (ISSN:03881512)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.2, pp.425-432, 2010-07-01
- 参考文献数
- 18
- 被引用文献数
- 1
本研究の目的は,初めて親となる男性における,産後の父親役割行動を考える契機となった体験を明らかにすることである。妊娠34週以降の妊婦をもつ夫21名を対象に,半構成的面接法によって研究データを収集した。データを質的・帰納的に分析した結果,産後の父親役割行動を考える契機となった体験は,父親役割モデルとの出会いや想起により,自分なりの理想的な父親像について考える,妊娠・出産する妻への愛情を再確認して,夫/父親として協力する気持ちが芽生える,周囲から育児に関する情報を受けて,仕事と家庭内役割のバランスについて考えるなど,10の体験が明らかになった。導かれた産後の父親役割行動を考える契機となった体験の3つの特徴と,この体験をもつための前提条件から,父親としての自己像形成に必要な素材の内容を把握し提供すること,妊娠・出産をする妻に対して関心を高めるよう促すこと,仕事と家庭内役割の役割調整の必要性に気づくよう促すこと,が示唆された。
1 0 0 0 大規模コーパスに基づく発信型和英連語辞書の構築に向けて
- 著者
- 内田 諭 内田 聖二 赤野 一郎 Danny Minn 工藤 洋路 石井 康毅 ハズウェル クリストファー
- 出版者
- 九州大学
- 雑誌
- 基盤研究(B)
- 巻号頁・発行日
- 2018-04-01
2018年度の研究計画は和英連語辞書に収録すべき見出し語の選定と連語抽出の試行を主眼とし、次の3段階で実施した。・(1)見出し語の選定:BCCWJやTWCなどの日本語大規模コーパスを用いて、収録すべき見出し語の選定を行った。名詞を中心に選定し、日本の英語教育(特に高等学校レベル)の実情に合ったものになるように心がけた。・(2)連語表現の抽出の試行:(1)で選定した見出し語のうち、頻度の高い最重要名詞について、連語表現の抽出を行った。研究分担者の意見や研究会や学会などでの専門家からの助言、コーパスにおける共起指数等を基に、教育目的で有益な連語表現を選定した。また、次年度以降の研究・執筆作業が円滑に行えるよう、連語抽出に関する全体の方針について議論し、手続きをある程度明確化した。・(3)英訳の試行:(2)で抽出した連語表現について、英訳を予備的に実施した。英語母語話者の意見・助言を基に、特に日本語と英語でずれのある表現について集中的に討議した(例えば、「体」は英語ではbodyであるが、「体が温まる」はbecome warm from inside、「体が覚える」はbecome automaticなどのように必ずしもbodyを使うとは限らず特別な注意が必要となる)。これらの作業に加えて、辞書を公開する際に用いるウェブインタフェースのプロトタイプを作成した。これにより、早い段階から研究の最終成果物のイメージを共有することが可能となった。
1 0 0 0 遠山荷塘『療啞塵談』巻之三翻字稿
- 著者
- 遠山 荷塘 樊 可人
- 出版者
- 広島中国文学会
- 雑誌
- 中國學研究論集 (ISSN:13441795)
- 巻号頁・発行日
- no.37, pp.66-75, 2019-04
- 著者
- 間庭 大祐
- 出版者
- 大月書店
- 雑誌
- 唯物論研究年誌 (ISSN:13437372)
- 巻号頁・発行日
- no.21, pp.90-114, 2016-10
1 0 0 0 OA ハーンのミューズ : 「暗号」解読の試み
1 0 0 0 OA フランス・オペラの誕生 その五 : グルック 『オーリドのイフィジェニー』
- 著者
- 内藤 義博
- 出版者
- 関西大学フランス語フランス文学会
- 雑誌
- 仏語仏文学 (ISSN:02880067)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, pp.113-133, 2009-03-15
- 著者
- 川瀬 哲明 Liberman M. Charles 高坂 知節
- 出版者
- Japan Otological Society
- 雑誌
- Otology Japan (ISSN:09172025)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, no.2, pp.105-111, 1995-05-15 (Released:2011-06-17)
- 参考文献数
- 20
Anti-masking effects mediated by the sound-evoked efferent activity were discussed in the present paper. In the cats, masked auditory responses were enhanced by adding the noise to the contralateral ear both in the compound action potential (CAP) and in the responses of single auditory nerve fibers. These anti-masking effects were disappeared when the olivocohlear bundle (OCB) was interrupted. It has been suggested that classic suppressive effects of OCB on the auditory-nerve responses to the back ground masker are an important component of this OC mediated anti-masking phenomenon. Similar anti-masking phenomena were observable in the human subjects as well. Small but significant enhancements of masked CAP in amplitude were seen in some patients with facial palsy, in which acoustic reflexes of middle ear muscles (MEMs) had disappeared or were impaired.
1 0 0 0 OA 蝸牛アクティブメカニズムと遠心性神経の役割
- 著者
- 川瀬 哲明
- 出版者
- Japan Otological Society
- 雑誌
- Otology Japan (ISSN:09172025)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, no.2, pp.72-77, 2000-05-25 (Released:2011-06-17)
- 参考文献数
- 18
It is known that the olivocochlear (OC) efferent fibers innervated to the outer hair cells (OHCs) can modulate the active process in the cochlea which is related to the motile response of the OHCs.The basic known effect of the activation of this OC efferent neurons is suppression of the auditory system. On the other hand, when tones are presented with background noise, the OC activation can enhance the responses of the auditory nerve.In the respect of the effective signal perception in the cochlea, the OC-system should not act during the signal perception in the background quiet, however, should be activated when the signals are perceived in the masking situation.In the present study, the practical role of this system is discussed by observing the effects of the severance as well as the stimulation of the OC-neurons on the auditory responses. The results obtained suggest that the OC system are not activated in the signal (short duration) perception in quiet. That is, in this situation, the benefit from the active mechanism is not disturbed by the OC efferent system. On the other hand, in the condition of the signal perception in the background continuous noise, OC system is activated effectively by the noise and can improve the perception of the newly presented signal in the cochlea.
1 0 0 0 OA 深層学習に基づく言語モデルと音声言語理解
- 著者
- 増村 亮
- 出版者
- 一般社団法人 日本音響学会
- 雑誌
- 日本音響学会誌 (ISSN:03694232)
- 巻号頁・発行日
- vol.73, no.1, pp.39-46, 2017 (Released:2017-07-01)
- 参考文献数
- 88
1 0 0 0 OA 照明のデータ・シート (No.411)(No.412)(No.413)(No.414)
- 出版者
- 一般社団法人 照明学会
- 雑誌
- 照明学会雑誌 (ISSN:00192341)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.12, pp.plate1-plate4, 1973-12-25 (Released:2011-07-19)
- 著者
- Kentaro Iwata Tomoko Toma Akihiro Yachie
- 出版者
- The Japanese Society of Internal Medicine
- 雑誌
- Internal Medicine (ISSN:09182918)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.21, pp.3185-3188, 2019-11-01 (Released:2019-11-01)
- 参考文献数
- 14
- 被引用文献数
- 1
A 38-year-old Japanese man without any significant past medical history was referred to our clinic to undergo further examination for a "refractory infection in his joints". He suffered recurrent migratory polyarthritis starting from bilateral knees to his right elbow. Certain antibiotic therapies appeared to improve his symptoms, but the symptoms recurred due to the migratory nature of arthritis. A diagnosis of familial Mediterranean fever (FMF) was considered and diagnostic tests were performed. Not many differential diagnoses exist for migratory polyarthritis, particularly when it has a recurrent nature. The administration of antibiotics without sufficient diagnostic consideration can cause a delay in making an accurate diagnosis and thereby also cause a delay in administering appropriate treatment.