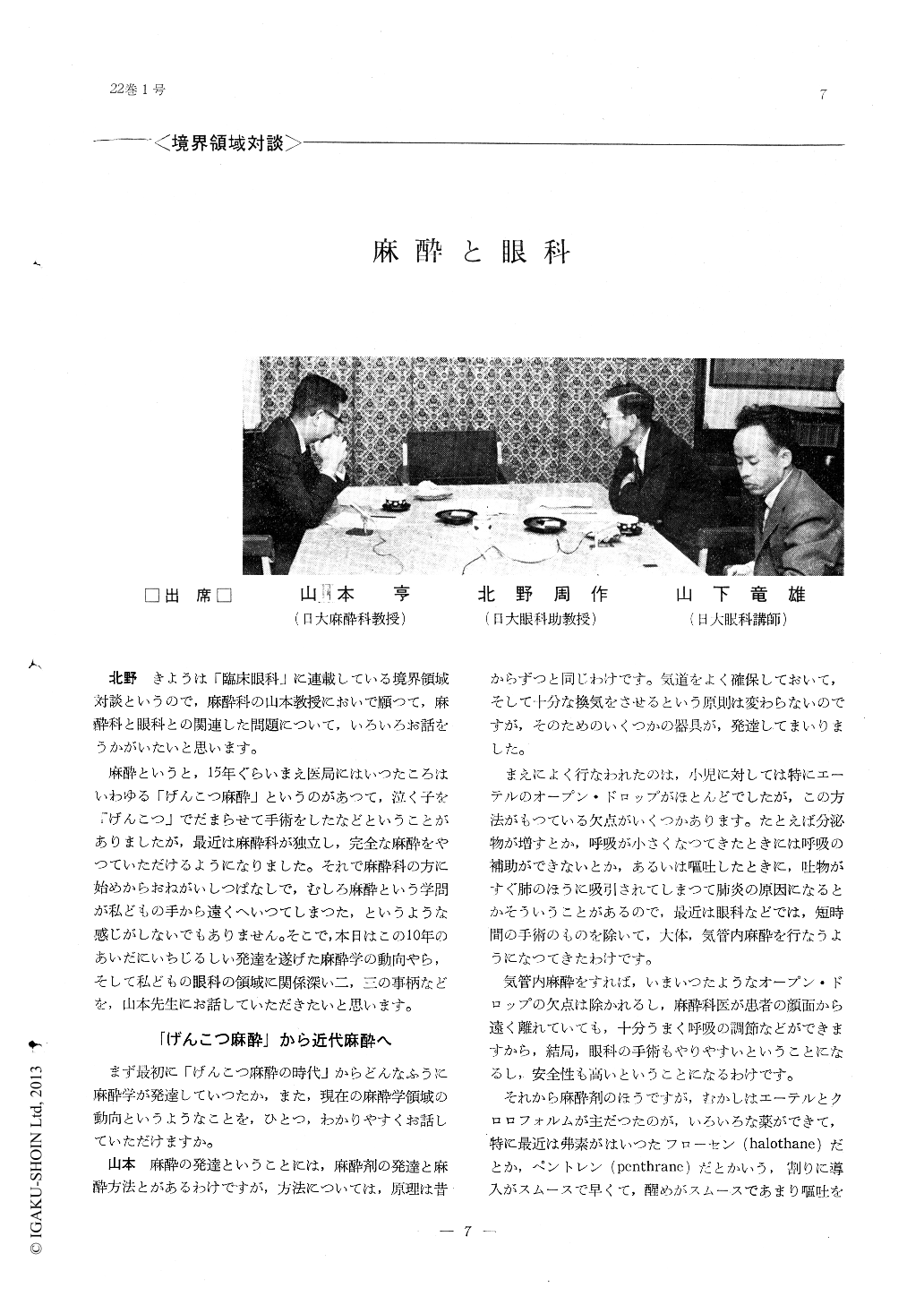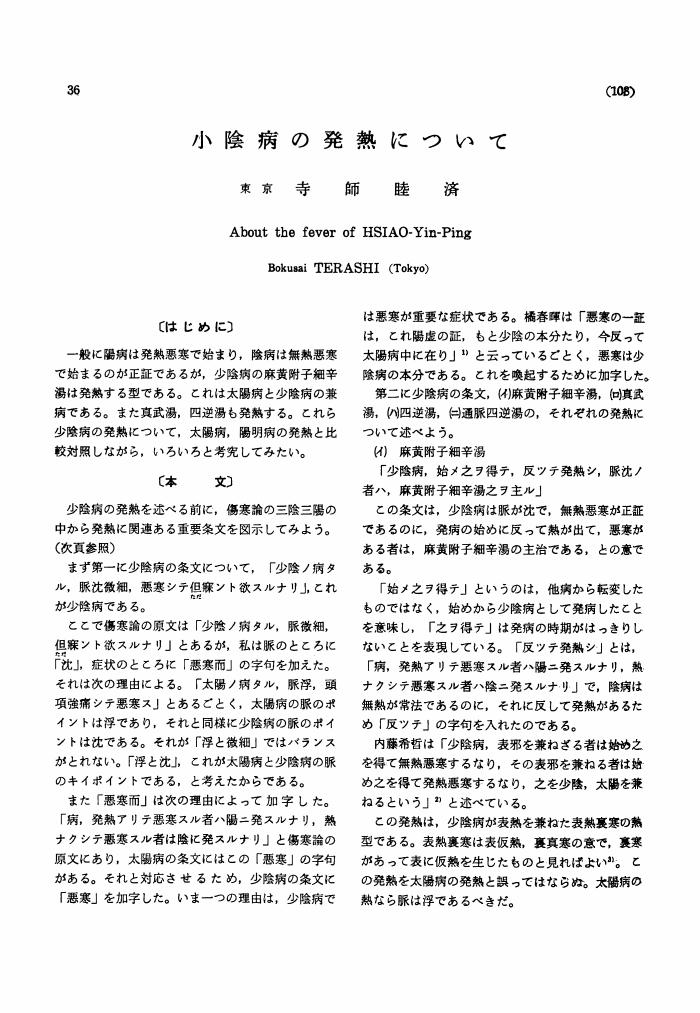- 著者
- Yota Takamura Hayato Onozawa Soki Urashita Shigeki Nakagawa
- 出版者
- 応用物理学会
- 雑誌
- 2020年第67回応用物理学会春季学術講演会
- 巻号頁・発行日
- 2020-01-28
1 0 0 0 OA 衆議院議員総選挙一覧
- 出版者
- 衆議院事務局
- 巻号頁・発行日
- vol.第28回, 1958
1 0 0 0 OA 身代限褒賞恤救棄児行旅死亡人ニ関スル令達類集
- 出版者
- 福島県
- 巻号頁・発行日
- 1888
1 0 0 0 鳥類における遺伝子量補正機構
- 著者
- 黒岩 麻里 松田 洋一
- 出版者
- 共立出版
- 雑誌
- 蛋白質核酸酵素 (ISSN:00399450)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, no.14, pp.1934-1939, 2003-11
1 0 0 0 麻酔と眼科
北野きようは「臨床眼科」に連載している境界領域対談というので,麻酔科の山本教授においで願つて,麻酔科と眼科との関連した問題について,いろいろお話をうかがいたいと思います。 麻酔というと,15年ぐらいまえ医局にはいつたころはいわゆる「げんこつ麻酔」というのがあつて,泣く子を「げんこつ」でだまらせて手術をしたなどということがありましたが,最近は麻酔科が独立し,完全な麻酔をやつていただけるようになりました。それで麻酔科の方に始めからおねがいしつぱなしで,むしろ麻酔という学問が私どもの手から遠くへいつてしまつた,というような感じがしないでもありません。そこで,本日はこの10年のあいだにいちじるしい発達を遂げた麻酔学の動向やら,そして私どもの眼科の領域に関係深い二,三の事柄などを,山本先生にお話していただきたいと思います。
1 0 0 0 OA 1.ビタミン補給療法の再検討
- 著者
- 高橋 和郎
- 出版者
- 一般社団法人 日本内科学会
- 雑誌
- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)
- 巻号頁・発行日
- vol.81, no.2, pp.219-221, 1992-02-10 (Released:2008-06-12)
- 参考文献数
- 4
ニューロパシー,特にビタミン欠乏性ニューロパシーのビタミン補給療法の問題について述べた.ビタミンA, Dなどの脂溶性ビタミンについては従来より,その副作用が問題となっているが,最近ではビタミンB6過剰でニューロパシーがみられるなど,過剰投与による副作用が問題となっている.従って,補給療法にはむやみに大量,長期に行わないことに注意すべきである.
1 0 0 0 OA 変形性膝関節症患者における股関節周囲筋の筋力水準
- 著者
- 石阪 姿子 田中 彩乃 八木 麻衣子 西山 昌秀 岩﨑 さやか 立石 圭祐 大沼 弘幸 清水 弘之
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学Supplement Vol.38 Suppl. No.2 (第46回日本理学療法学術大会 抄録集)
- 巻号頁・発行日
- pp.CbPI2198, 2011 (Released:2011-05-26)
【目的】 変形性膝関節症(以下,膝OA)における股関節周囲筋筋力増強は膝関節負荷軽減や膝関節痛軽減,運動機能向上などの効果が得られたとする研究が散見され,トレーニングプログラムの一つとして行われることが多い.しかし実際に膝OA患者の股関節周囲筋の筋力水準を提示した研究は少なく,健常者と比較してどの程度の筋力水準なのかは不明である.よって運動処方の際に,目標とする筋力水準を設定出来ない現状がある. 本研究では膝OA患者の股関節周囲筋の年代別筋力水準を提示し,筋力低下の有無や程度を検討することを目的とした.【方法】 対象は当院に人工膝関節全置換術目的に入院した重度膝OA女性患者71名(以下,OA群)と過去6ヶ月に1週間以上の臥床経験が無く独歩可能で日常生活活動が自立し,さらに骨・関節疾患,脳血管障害,神経・筋疾患の既往や認知症が無いという取り込み基準を満たす女性56名(以下,コントロール群)の合計127名である. 筋力測定は等尺性筋力測定装置μ-Tas(アニマ社製)を使用し,股関節外転,伸展,膝関節伸展筋力を約5秒間の最大努力により2回測定,その最大値を記録した.OA群は手術予定側,コントロール群は全例右下肢の筋力値を採用,体重で除した値を用いた. 統計解析には統計ソフトSPSS(Ver.12.0J)を使用した.属性の比較,OA群とコントロール群の筋力値の水準比較には対応のないt検定を使用,筋力値に対する体重の影響を検討するために体重を共変量とし,共分散分析をおこなった.OA群,コントロール群各々における各年代間の筋力値の比較は一元配置の分散分析を使用した.なお,統計学的判定の有意水準は5%とした.【説明と同意】 倫理的配慮として当院倫理委員会の承認を得た(承認番号第1313号).対象者には研究についての適切な説明を行い十分に理解した上で同意を得た.【結果】 属性において両群の体重に有意差を認めたが,共分散分析を行った結果,筋力値に対する体重の影響は棄却された. 年代別筋力値の体重比(単位kgf/kg)を60歳代(OA群13名/コントロール群18名),70歳代(48名/20名),80歳代(10名/18名)の順に述べる.膝関節伸展筋力はOA群では0.26±0.10,0.27±0.09,0.24±0.05,コントロール群では0.47±0.14,0.39±0.09,0.38±0.10, 股関節外転筋力ではOA群では0.23±0.11,0.22±0.08,0.20±0.08,コントロール群0.33±0.08,0.28±0.05,0.27±0.09, 股関節伸展筋力ではOA群では0.23±0.11,0.23±0.08,0.23±0.07,コントロール群0.40±0.11,0.31±0.09,0.27±0.12であった.OA群とコントロール群との比較では80歳代の股関節外転,伸展筋力以外すべてにおいて有意にOA群の筋力が低値であった(p<0.05). また,コントロール群とOA群各々における各年代の筋力値の比較ではコントロール群の股関節伸展筋力にのみ60歳代から80歳代にかけて有意な筋力低下がみられたが(p<0.01),OA群では60歳代から80歳代にかけての筋力値に統計学的な有意差は見られなかった.【考察】 OA群ではコントロール群と比較し,従来から筋力低下がおこるといわれている膝関節伸展筋力のみならず,股関節外転,伸展筋力にも筋力低下を生じていることがわかり,その予防対策やトレーニングの必要性が示唆された.トレーニングプログラムとして股関節周囲筋の筋力増強を図る場合には,今回の結果から得られたコントロール群の年代別筋力値を目標値の一つとして使用できると考える.しかし,今回は筋力値とパフォーマンスや疼痛との関連,また,下肢のアライメントや身体活動量の違いなどとの関連は検討しておらず,今後の課題である. また,OA群ではコントロール群に見られる加齢による筋力低下の傾向が見られなかった.疾患由来による筋力低下が60歳代においてすでにみられるが,その後,加齢による筋力低下は見られない.重度膝OA患者ではあるが全例歩行が可能であったことから,今回得た筋力値は日常生活維持可能な最低限の筋力水準であることが予想された.高齢女性では予備体力低下が問題であり,今後は筋力低下を生じる前に予防策を講じる必要性があると考えられた.【理学療法学研究としての意義】 本研究の意義は膝OA患者において膝関節伸展筋力とともに,股関節周囲筋にも筋力低下を生じていることを示した点、またその水準を示した点である.股関節周囲筋の筋力トレーニングを実施するにあたり、目標値を設定する一助となると考える.
1 0 0 0 OA 変形性膝関節症患者の歩行における股関節周囲筋の筋活動の特徴
- 著者
- 澳 昂佑 福田 章人 奥村 伊世 川原 勲 田中 貴広
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学Supplement Vol.41 Suppl. No.2 (第49回日本理学療法学術大会 抄録集)
- 巻号頁・発行日
- pp.0525, 2014 (Released:2014-05-09)
【はじめに,目的】本邦の変形性膝関節症患者数は約3000万人と推測され(平成20年介護予防の推進に向けた運動器疾患対策に関する検討会-厚生労働省),膝関節機能不全によって,歩行能力の障害を呈することが多く,生活機能の低下を引き起こしてしまう。このため,膝OAの病態を把握し,適切な理学療法を模索することは重要である。とりわけ内側型変形性膝関節症(膝OA)患者の立脚期における膝関節内反モーメントの増加は膝関節内側のメカニカルストレスや痛みの増加に関与していることが報告されている(Schipplenin OD.1991)。これに対して,外側広筋は筋活動を増加することによって側方不安定性に寄与し,膝関節内反モーメントを制動することが知られている(Cheryl L.2009)。一方,股関節は体幹を立脚側に側屈することにより,立脚側へ重心を保持する代償動作を行い(Hunt MA.2008),股関節内転モーメントが減少することが知られている(Janie L.2007)。さらにこの戦略によって股関節外転筋は不使用による筋力低下を引き起こし,二次障害を誘発すると考えられている(Rana S.2010)。これらの知見は膝OA患者に対して膝関節のみではなく,股関節の筋にも着目したトレーニングを行う必要性を示唆している。しかしながら,膝OA患者において歩行中の股関節の筋活動の特徴は明らかとなっていない。そこで本研究の目的は膝OA患者における歩行中の股関節の筋活動の特徴を明らかにすることとした。【方法】対象者は健常成人7名(25歳±4.5)とデュシェンヌ歩行を呈する片側・両側膝OA患者4名(85歳±3.5)とした。膝OAの重症度はKellgren-Lawrence分類(K/L分類)にて,IIが4側,IIIが1側,IVが2側であった。対象者には筋電図の記録電極を外側広筋,中殿筋,内転筋に設置し,足底にフットスイッチを装着させた。筋活動の測定には表面筋電計(Noraxson社製MyoSystem1400)を使用した。歩行中の筋活動の測定は,音の合図に反応して快適な歩行速度で歩行させた。歩行計測終了後,各被検筋の最大随意収縮(Maximal Voluntary contraction:MVC)を等尺性収縮にて3秒間測定した。解析は得られた波形を整流化し,5歩行周期を時間にて正規化した。各筋の1歩行周期における平均EMG振幅,MVCの平均EMG振幅を算出した。各歩行周期の平均EMG振幅は%MVCにて正規化した。統計処理は健常成人とOA患者のEMG振幅をMann-Whitney U-testにて比較した。健常成人,OA患者それぞれの外側広筋と中殿筋,内転筋のEMG振幅をPaired t-testにて比較した。OA患者のEMG振幅とK/L分類の関係をSpearmann順位相関係数にて検証した。有意水準は0.05とした。【倫理的配慮,説明と同意】本研究はヘルシンキ宣言に基づき対象者の保護には十分留意し,阪奈中央病院倫理委員会の承認を得て実施された。被験者には実験の目的,方法,及び予想される不利益を説明し同意を得た。【結果】OA患者における外側広筋,中殿筋,内転筋のEMG振幅は健常成人と比較して有意な増加を認めた。健常成人の外側広筋と中殿筋,内転筋のEMG振幅は有意差を認めなかった。他方,OA患者は外側広筋と比較して,内転筋のEMG振幅は有意な増加を認めた。OA患者のK/L分類と外側広筋(r=0.79,p>0.05),内転筋(r=0.83,p>0.05)のEMG振幅は有意な正の相関関係を認めた。【考察】健常成人は外側広筋と内転筋,中殿筋の筋活動に差がないにも関わらず,膝OA患者においては外側広筋の筋活動より,内転筋の筋活動が増加した。これは健常成人と膝OA患者の歩行中の筋活動パターンが異なることを示している。OA患者の外側広筋の筋活動が増加し,K/L分類と相関関係を認めたことはOAの進行による側方不安定の増加に対して外側広筋が制動に寄与しようとした結果であり,先行研究(Cheryl L.2009)と一致した。OA患者の内転筋の筋活動が増加し,K/L分類と相関関係を示したことは膝OAの進行による側方不安定の増加に対し,内転筋が遠心性収縮に作用することによって,体幹を立脚側に側屈(デュシェンヌ歩行)し,メカニカルストレスを軽減しようとした結果であると考える。しかしながらこれらの結果は筋活動であり,筋力を反映していないため,今後,筋活動と筋力の関係を調査する必要があると考える。【理学療法学研究としての意義】膝OA患者の歩行中の外側広筋と内転筋が同時に代償的に活動していることは新たな知見であり,理学療法として膝関節のみではなく,股関節の筋活動にも着目したトレーニングを行う必要性が示唆された。
1 0 0 0 OA 由布・鶴見火山の地質と最新の噴火活動
Yufu-Tsurumi volcanoes are situated at the northeastern part of Kyushu island, Japan. Lavas and pyroclastic rocks ranging from the late Pliocene to the late Quaternary in age form the basemment of this area and are cut by many active faults bringing about the blocks tilted variously. Judging from the tephrochronology of the wide-spread tephra, it has been confirmed that both Yufu and Tsurumi volcanoes started their activities more than 35,000 years ago. Yufu-dake is a stratovolcano with several parasitic lava domes and lava flows. The latest eruption occurred ca. 2,000-1,500 years ago issued the Tsukahara pyrodastic flow, the Ikeshlro lava, the Yufu-dake summit lava, and the Yufu-dake ash. The Tsukahara pyroclastic flow deposit is oxidized under the high temperature condition and has secondary fumarolic pipes. The Tsukahara pyroclastic flow is judged to have been formed by the collapse of an ascending lava dome. Stratigraphic relation between the pyroclastic flow and the volcanic ash shows that the collapse of the lava dome happened repeatedly at least two times. The last ascending of lava formed the Ikeshiro lava dome accompanied with lava flow. Shortly after that, the Yufu dake summit lava was issued and formed a summit lava dome. All the activities mentioned above represent a single cycle of eruption ceased within a short period of time. Based on the documentary record, however, it is convinced that the fumarolic activity was continued until the time ca. 1,100 years ago. Tsurumi volcano is composed of highly dissected volcanic edifice and the younger parasitic volcanoes. Based on the tephrochronology of wide-spread tephra, the younger parasitic volcanoes other than the Tsurumi-dake summit lava are judged to have been formed during the period of time ranging from 22,000 to 6,300 years before present. Garan-dake, Uchi-yama, and Nanpeidai are all lava domes and Oninomi-yama alone is a scoria cone with basaltic lava flow. The Tsurumi-dake summit lava which filled up the summit crater and formed a summit lava dome flowed down southward and eastward. One of the lobes of lava flow dammed up the river resulting in the developemment of a volcanic fan formed from the tip of a lava flow. Judging from the distrbution pattern of historic sites on the fan and the descriptions in the ancient manuscripts, it is reasonably concluded that the lava was issued about 1,500-1,200 years ago. Most of the rocks in this area is hornblende andesite ordacite, but a complicated assemblage of phenocryst, namely the olivine-clinopyroxene-orthopyroxene-hornblende-biotite-quartz-plagioclase-Fe-Ti oxides is frequently found in the rocks of of these volcanoes.
1 0 0 0 OA 新春放談会
- 出版者
- 公益社団法人 高分子学会
- 雑誌
- 高分子 (ISSN:04541138)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, no.1, pp.60-73, 1961-12-20 (Released:2011-09-21)
1 0 0 0 OA 第三国による歴史認識問題への介入の要因と帰結
- 著者
- 向山 直佑
- 出版者
- 一般財団法人 日本国際政治学会
- 雑誌
- 国際政治 (ISSN:04542215)
- 巻号頁・発行日
- vol.2017, no.187, pp.187_30-187_45, 2017-03-25 (Released:2017-05-23)
- 参考文献数
- 39
Since the end of the Cold War, two significant political phenomena have attracted a considerable amount of attention of researchers in political science and related fields: the politicization of history and third-party intervention in domestic jurisdiction matters or bilateral issues. Particularly interesting is the fact that these two not only coexist but are also intertwined in the form of third-party intervention in historical issues.Previous studies on historical issues have presupposed that historical issues are bilateral conflicts, leaving studies on the third-party practically nonexistent, and the literature on third-party intervention has largely ignored the motives for it and its effects on the relationship between the intervener and the intervened. This study fills these gaps.The case explored in this paper is the issue of genocide recognition of the Armenian Massacre. The predecessor of the Republic of Turkey, the Ottoman Empire, allegedly deported and killed hundreds of thousands of Armenians residing in its territory during World War I. The Armenian government and the Armenian diaspora demand that Turkey admit it was genocide and apologize. However, the Turkish government has not offered an apology to date. Consequently, the Armenian side requests foreign governments to officially recognize the atrocities as genocide, while Turkey threatens them with potential deterioration of bilateral ties. This case is the most notable example of historical issues involving third-party intervention and, therefore, the best case for this research.The results of this study can be summarized as follows. As for the causes, cross-national and time-series qualitative analyses reveal that the genocide is mainly recognized by countries with a Christian majority and large Armenian communities. International norms of human rights also play an important role.Regarding the effects, two aspects of bilateral relationships are examined. First, simple observations of official diplomatic relations show that the Turkish government usually recalls its ambassadors from recognizing countries immediately after recognition, but it sends him/her back after several months, preventing further damage to the relationship. Second, panel data analyses on the amount of bilateral trade and the number of foreign visitors illustrate that there are statistically significant negative effects of genocide recognition, but these effects only last for a few years at most. To summarize, genocide recognition imposes a negative impact on bilateral relations between Turkey and the recognizer in the short run, but the deterioration is only temporary.
1 0 0 0 OA ファミリービジネス事業承継のコミュニケーションについての研究
- 著者
- 村尾 佳子 那須 清吾
- 出版者
- 一般社団法人 グローバルビジネス学会
- 雑誌
- グローバルビジネスジャーナル (ISSN:24340111)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, no.1, pp.13-24, 2019 (Released:2020-01-29)
- 参考文献数
- 10
ファミリービジネスの事業承継で多くを占める親族への承継において,先代と後継者間のコミュニケーションに課題があり,承継が上手く行かず,時には承継候補者が会社を辞めてしまうといった問題にまで発展することがある.先代から後継者への承継を成功させるためには,先代と後継者間で円滑なコミュニケーションが行われる必要があるが,そのプロセスにおいて,どのようなことに留意しながら,コミュニケ―ションを行えばよいのか,といった点について明らかにしている先行研究は存在しない.本研究では,ファミリービジネスにおける先代と後継者間のコミュニケーションに着目し,事業承継のプロセスにおける必要要素が継承されるコミュニケーションのメカニズム,留意点と,コミュニケーションの支援者の存在の効果のメカニズムについて,事例研究を通じて明らかにした.
1 0 0 0 OA 改良版近距離音響ホログラフィ法による高周波数域の測定
- 著者
- 髙松 麻緒
- 出版者
- 法政大学 (Hosei University)
- 巻号頁・発行日
- 2013-03-24
1 0 0 0 SiCエピ膜から得られるμ-PCDおよびTR-PL減衰曲線の比較
- 著者
- 加藤 正史 片平 真哉
- 出版者
- 応用物理学会
- 雑誌
- 2020年第67回応用物理学会春季学術講演会
- 巻号頁・発行日
- 2020-01-28
1 0 0 0 TAVIと心臓リハビリテーション
- 著者
- 岩波 裕治 内 昌之 福田 大空 黒田 悠加 杉澤 樹 海老原 覚
- 出版者
- 公益社団法人 日本リハビリテーション医学会
- 雑誌
- The Japanese Journal of Rehabilitation Medicine (ISSN:18813526)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.12, pp.1002-1008, 2019-12-18 (Released:2020-01-27)
- 参考文献数
- 19
- 被引用文献数
- 1
大動脈弁閉鎖不全症(aortic stenosis:AS)は,高齢化に伴い急速に患者数が増加している.高度な侵襲を伴う大動脈弁置換術(surgical aortic valve replacement:SAVR)が従来の標準治療であったが,ハイリスクのため適応とならない症例に対し,低侵襲治療の経カテーテル的大動脈弁植込み術(transcatheter aortic valve implantation:TAVI)が積極的に実施されるようになった.適応に関しては,ハートチームでの検討が必要とされ,理学療法士もその一員で,術前後でのfrailty評価を含め心臓リハビリテーションの重要な役割を担う.TAVIに対しての心臓リハビリテーションに関するデータは少ないのが現状であるが,高齢frailtyな症例に対し,個々に適したプログラムの適応が重要となる.
1 0 0 0 OA 小陰病の発熱について
- 著者
- 寺師 睦済
- 出版者
- The Japan Society for Oriental Medicine
- 雑誌
- 日本東洋醫學會誌 (ISSN:1884202X)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, no.2, pp.108-111, 1971-10-30 (Released:2010-10-21)
- 参考文献数
- 8
1 0 0 0 OA 吹塵録
- 著者
- 勝安房 (海舟) 編
- 出版者
- 大蔵省
- 巻号頁・発行日
- vol.上巻, 1890
1 0 0 0 紀要
- 著者
- 東京聖栄大学 [編]
- 出版者
- 東京聖栄大学
- 巻号頁・発行日
- 2008