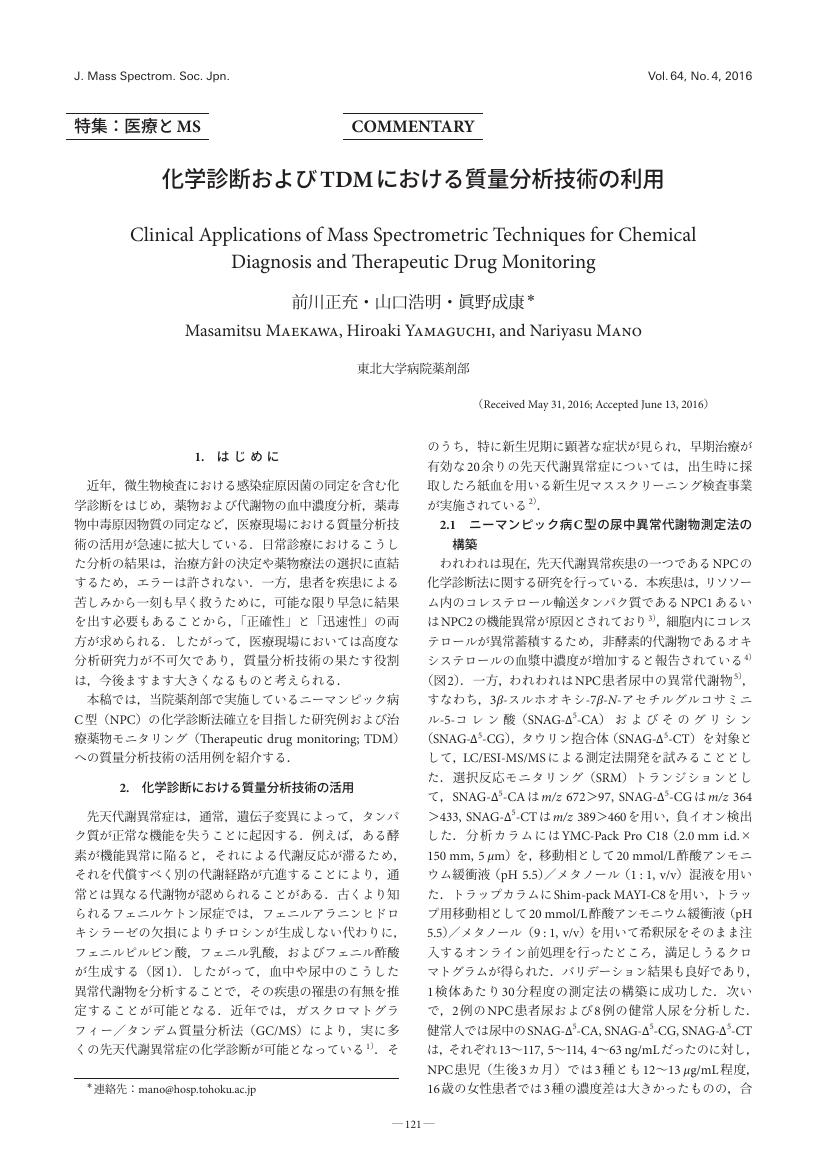3 0 0 0 OA 救命救急センターにおけるバンコマイシン負荷投与の有用性
- 著者
- 近藤 匡慶 菅谷 量俊 長野 槙彦 磐井 佑輔 金子 純也 諸江 雄太 工藤 小織 久野 将宗 畝本 恭子 村田 和也
- 出版者
- 一般社団法人 日本臨床救急医学会
- 雑誌
- 日本臨床救急医学会雑誌 (ISSN:13450581)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, no.4, pp.571-577, 2016-08-31 (Released:2016-08-31)
- 参考文献数
- 18
目的:バンコマイシン(以下,VCM)負荷投与は,抗菌薬TDMガイドラインに記載されているが,有用性を示す報告は少なく,今回,救命救急センターでの有用性を検討した。方法:トラフ値,治療効果,投与日数等を負荷投与群,通常投与群(以下,対照群)で比較検討した。負荷投与は初日1〜2g投与し,維持投与はトラフ値10〜20μg/mLを目標に薬剤師が投与設計した。結果:負荷投与群7例,対照群21例を認め,トラフ値は,対照群9.4±5.4μg/mLと比較して負荷投与群15.8±6.8μg/mLと有意な増加を認め(p<0.05),トラフ値10μg/mL以下の症例が対照群62%から負荷投与群29%と減少傾向を示した。治療効果は有意差を認めなかったが,投与日数では,負荷投与群で有意な短縮を認めた(p<0.05)。結論:VCM負荷投与は,早期に血中濃度を上昇させ,治療効果に寄与する可能性が示唆された。
3 0 0 0 OA 日本プライマリ・ケア連合学会誌がオンライン版に
- 著者
- 竹村 洋典
- 出版者
- 一般社団法人 日本プライマリ・ケア連合学会
- 雑誌
- 日本プライマリ・ケア連合学会誌 (ISSN:21852928)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, no.1, pp.1-1, 2016 (Released:2016-03-25)
- 被引用文献数
- 1
3 0 0 0 OA 桃介橋の修復事業の検証
- 著者
- 馬場 俊介
- 出版者
- Japan Society of Civil Engineers
- 雑誌
- 土木史研究 (ISSN:09167293)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, pp.205-218, 1994-06-09 (Released:2010-06-15)
- 参考文献数
- 7
木曽川・読書発電所の建設工事用の吊橋として1922年に架設された桃介橋は、4径間、全長247m、わが国に現存する最大・最古の木製補剛吊橋である。桃介橋は1978年の被災以降は放置されてきたが、1992年度の自治省の「ふるさとづくり特別対策事業」による起債を用いて修復・復元が進められた結果昔日の姿を取り戻し、1993年10月17日2度目の渡り初めが行われた。土木史的な観点から見た桃介橋の意義は、「文化財にふさわしい復元」のあり方を、近代土木構造物に対し初めて正面切って論じた点にある。吊橋のような複雑な構造物の場合、力学的な安全性の照査は多枝にわたり、しかも荷重、形状・寸法、発生応力は互いに線形関係にない (少しでも前提が変われば全て再計算となる) ことから、中間段階での安全性照査はどうしても簡略計算に頼らざるを得ない。桃介橋の保存・修複に係わる委員会では、こうした推定値に従って修復方針を決定し、それを受けてより正確な推定値が計算され、さらに異体的な修復工程が詰められていった。本論文では、こうした力学的な検討の変遷を詳らかにすることにより、技術的検討のもつ重要性とそれに伴う責任の重さについて分析を加える。
- 著者
- Wei Wei Akihiro Nakamata Yoshihiro Kawahara Tohru Asami
- 出版者
- 一般社団法人 情報処理学会
- 雑誌
- Journal of Information Processing (ISSN:18826652)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, no.6, pp.835-844, 2015 (Released:2015-11-15)
- 参考文献数
- 17
- 被引用文献数
- 4
In this paper, we demonstrate a food recognition method by monitoring power leakage from a domestic microwave oven. Universal Software Radio Peripheral (USRP) is applied as a low-cost spectrum analyzer to measure the microwave oven leakage as received signal strength indication (RSSI). We aim to recognize 18 categories of food that are commonly cooked in a microwave oven. By analyzing 180 features that contain the information of heating-time difference, we attain an average recognition accuracy of 82.3%. Using 138 features excluding the heating-time difference information, the average recognition accuracy is 56.2%. The recognition accuracy under different conditions is also investigated, for instance, utilizing different microwave ovens, different distances between the microwave oven and the USRP as well as different data down-sampling rates. Finally, a food recognition application is implemented to demonstrate our method.
3 0 0 0 OA 元良式船舶動搖制止裝置の試驗成績
- 著者
- 元良 信太郎
- 出版者
- 社団法人 日本船舶海洋工学会
- 雑誌
- 造船協會會報 (ISSN:18842054)
- 巻号頁・発行日
- vol.1925, no.36, pp.109-117, 1925-07-15 (Released:2009-09-04)
- 被引用文献数
- 1
3 0 0 0 OA 漢音の聲明とその聲調
- 著者
- 頼 惟勤
- 出版者
- 日本言語学会
- 雑誌
- 言語研究 (ISSN:00243914)
- 巻号頁・発行日
- vol.1951, no.17-18, pp.1-46,182, 1951-03-20 (Released:2010-11-26)
Japanese Buddhist priests have tradition of sutra reading, This sutra reading is performed melodiously and is called-“Syomyo”. Some kinds of syomyb were brought from China at the time of T'ang dynasty. We called These Kan-on-syomyo: For the pronunciation of these syomyos is called kan-on that is, a kind of Sine-Japanese pronunciation.In this thesis the author warift to confirm the tone, in which Chinese characters were. pronounced at the time of Tang dynasty, utilizing Kan-on-syomyo as clues. Signs used. for describing sycmyo music are called “Hakase”, One hakase stands for one. Chinese character, like the Ssu-henfu in Chu.-yin-fu-hall. Utilizing these hakase signs as key under certain methodological considerations, the author wants to find out the tone class and tone' value. The composition of syomyo in hakases is always done under musical consideration-that is, determined by the position the. character takes in the musical structure of phrases. The result is that the same tone can be sung in. various ways.Because of the discrepancy between music and spoken language, the tone confirmed through this inquiry correspond only to a certain. group of characters which resemble each other as regards the tone class or tone value.
- 著者
- Yuta Fujii Yutaka Kodama
- 出版者
- 日本植物細胞分子生物学会
- 雑誌
- Plant Biotechnology (ISSN:13424580)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.1, pp.81-87, 2015-03-25 (Released:2015-04-04)
- 参考文献数
- 31
- 被引用文献数
- 3 22
Green fluorescent protein (GFP) was discovered from the jellyfish Aequorea victoria, and several improvements have been carried out to change its physicochemical properties. The resulting improved GFP variants have been used as reporter proteins for bioimaging techniques in various research fields including plant science. Almost all GFP variants were developed using Escherichia coli to improve fluorescence properties in mammalian cells, but the impact in other organisms such as plant cells remains to be determined. In this study, we performed comparative analysis of four improved GFP variants, GFP-S65T, eGFP, frGFP and sfGFP, with reference to the fluorescence intensity in Arabidopsis protoplasts, and found that sfGFP is the brightest. Using non-fluorescent fragments from the GFP variants, we also conducted bimolecular fluorescence complementation (BiFC) assays to find appropriate fragment pairs of GFP-based BiFC for visualization of protein–protein interactions in living plant cells. Our observations revealed that the brightest is the sfGFP-based BiFC. Further, as an evaluation method for the sfGFP-based BiFC, a BiFC competition assay was successfully completed for the first time in planta. The present study provides useful information for selection and improvement of the GFP molecule and its application to BiFC technology in plants.
3 0 0 0 OA 電子書籍ビューアーのアクセシビリティ機能:関係者会議における議論の報告
- 著者
- 青木 千帆子 小高 公聡 丸山 信人
- 出版者
- 国立研究開発法人 科学技術振興機構
- 雑誌
- 情報管理 (ISSN:00217298)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.5, pp.315-321, 2016-08-01 (Released:2016-08-01)
- 参考文献数
- 8
出版社,電子書籍ビューアー開発者,電子書籍ストア,読書障害者による一連の関係者会議を開催し,読書障害者による使用に関して課題が残されている電子書籍ビューアーに焦点を当てて議論をした。本稿はその成果報告書である。会議における議論から,ビューアーに実装や対応が求められる最も優先度の高い要素として,(1)音声読み上げ機能(TTS)の有効化,(2)TTSによる購入,(3)TTSによる書棚操作,(4)表示されている順にTTSで読む,(5)TTSで文字ごとに読む,(6)TTSによる読む位置の指定,の6項目を示した。また,電子書籍のアクセシビリティを総体的に実現するための提案として,1)アクセシビリティに関する方針を設けること,2)アクセシビリティに関する対応状況を示すこと,そして,3)アクセシビリティについて考える担当の人を設けること,を挙げた。
3 0 0 0 OA 日本のボツリヌストキソイドワクチンの開発
- 著者
- 高橋 元秀
- 出版者
- 日本食品微生物学会
- 雑誌
- 日本食品微生物学会雑誌 (ISSN:13408267)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.2, pp.110-114, 2015-06-30 (Released:2015-09-11)
- 参考文献数
- 5
3 0 0 0 OA 化学診断およびTDMにおける質量分析技術の利用
- 著者
- 前川 正充 山口 浩明 眞野 成康
- 出版者
- 日本質量分析学会
- 雑誌
- Journal of the Mass Spectrometry Society of Japan (ISSN:13408097)
- 巻号頁・発行日
- vol.64, no.4, pp.121-125, 2016-08-01 (Released:2016-08-15)
- 参考文献数
- 13
- 被引用文献数
- 1
3 0 0 0 OA シャンカラにおける瞑想の一側面
- 著者
- 村上 幸三
- 出版者
- 日本印度学仏教学会
- 雑誌
- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, no.2, pp.964-962, 1991-03-20 (Released:2010-03-09)
3 0 0 0 OA 任意の話題を持つユーザ発話に対する係り受けと用例を利用した応答文の生成
- 著者
- 杉山 弘晃 目黒 豊美 東中 竜一郎 南 泰浩
- 出版者
- 一般社団法人 人工知能学会
- 雑誌
- 人工知能学会論文誌 (ISSN:13460714)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.1, pp.183-194, 2015-01-06 (Released:2015-01-06)
- 参考文献数
- 18
- 被引用文献数
- 1 1
The development of open-domain conversational systems is difficult since user utterances are too flexible for such systems to respond properly. To address this flexibility, previous research on conversational systems has selected system utterances from web articles based on word-level similarity with user utterances; however, the generated utterances, which originally appeared in different contexts from the conversation, are likely to contain irrelevant information with respect to the input user utterance. To leverage the variety of web corpus in order to respond to the flexibility and suppress the irrelevant information simultaneously, we propose an approach that generates system utterances with two strongly related phrase pairs: one that composes the user utterance and another that has a dependency relation to the former. By retrieving the latter one from the web, our approach can generate system utterances that are related to the topics of user utterances. We examined the effectiveness of our approach with following two experiments. The first experiment, which examined the appropriateness of response utterances, showed that our proposed approach significantly outperformed other retrieval and rule-based approaches. The second one was a chat experiment with people, which showed that our approach demonstrated almost equal performance to a rule-based approach and outperformed other retrieval-based approaches.
- 著者
- Elbert Frank COX
- 出版者
- Mathematical Institute, Tohoku University
- 雑誌
- Tohoku Mathematical Journal, First Series (ISSN:00408735)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, pp.327-348, 1934 (Released:2010-03-19)
3 0 0 0 OA ハオコゼの求愛, 産卵行動
- 著者
- 櫻井 真 広瀬 純 四宮 明彦
- 出版者
- 日本魚類学会
- 雑誌
- 魚類学雑誌 (ISSN:00215090)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, no.2, pp.165-168, 2003-11-25 (Released:2011-07-04)
- 参考文献数
- 8
Abstract We conducted underwater observations on courtship and spawning be-haviors of the tetrarogidid fish, Hypodytes rubripinnis in Kyushu Island, Japan. The reproductive behavior and seasonal changes of gonad somatic index on col-lected specimens showed that spawning occurred from late April to early August. Individuals of various sizes in both sexes reproduced in the study area. About 90 min before sunset, a male courted a female actively with several patterns of be-haviors such as male's lying by a female in a side-by-side position, display of his lateral side around a female, and male's riding on a female back. Finally, the pair swam toward 20 to 100 cm above the bottom to release gametes. Spawning time was around sunset. The average egg number in each spawning was about 1600. Upward rush of the pair to the middle water occurred very quickly. Frequent sneaking behavior by another male was also observed.
3 0 0 0 OA スーパーコンピュータ「京」の共用 産業利用を中心に
- 著者
- 西川 武志
- 出版者
- 国立研究開発法人 科学技術振興機構
- 雑誌
- 情報管理 (ISSN:00217298)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.12, pp.882-890, 2013-03-01 (Released:2013-03-01)
2011年6月,11月とTOP500リストで世界一となったスーパーコンピュータ「京」は2012年6月に完成し2012年9月末から共用が開始されている。応用分野でも先駆的な「京」利用者がゴードン・ベル賞を2011年,2012年と2年連続で受賞する等成果を上げ始めている。本報告ではスーパーコンピュータ「京」について,概要,完成までの道のりと現状,運用と共用体制,計算資源配分,利用課題の公募・選定方法と2012年度の採択結果,産業利用のための支援や拠点,利用可能なソフトウェア等,共用がどのように行われているか産業利用を中心に紹介する。
- 著者
- Yoshimune Nonomura Takehito Baba Takaaki Miyashita Takashi Maeno
- 出版者
- The Chemical Society of Japan
- 雑誌
- Chemistry Letters (ISSN:03667022)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, no.12, pp.1426-1427, 2011-12-05 (Released:2011-12-03)
- 参考文献数
- 19
- 被引用文献数
- 2
We evaluated the softness of various silicone elastomers installed on a tactile evaluation system. The softness of the elastomers was reflected by the vertical force when subjects pushed the elastomers with their fingers. The moving behavior depended on the elastic properties of the contacted objects; namely, a pushing pattern and a sliding pattern were observed for the soft and hard elastomers, respectively.
- 著者
- Kayoko Ozeki Takahisa Furuta Michio Asano Tatsuya Noda Mieko Nakamura Yosuke Shibata Eisaku Okada Toshiyuki Ojima
- 出版者
- 一般社団法人 日本内科学会
- 雑誌
- Internal Medicine (ISSN:09182918)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.13, pp.1729-1734, 2016-07-01 (Released:2016-07-01)
- 参考文献数
- 43
- 被引用文献数
- 3
Objective Recently, the number of patients receiving Helicobacter pylori eradication treatment has dramatically increased in Japan, although the eradication rate has gradually decreased. Patient characteristics could affect the eradication rate. Our aim in this study was to investigate the association between failed first-line eradication therapy and hay fever. Methods We researched 356 patients who visited a pharmacy adjacent to the Internal Medicine clinic with a prescription for first-line H. pylori eradication treatment and investigated whether the patients had hay fever using a questionnaire. We separated these patients into 2 groups based on the success or failure of eradication according to the clinical data and performed a logistic regression analysis to investigate the influence of hay fever on first-line eradication failure. Results The eradication rate of patients with and without hay fever was 65.6% and 77.7%, respectively. The adjusted odds ratios according to which patients with hay fever would fail eradication therapy gradually lowered with increasing patient age [≤50 years, odds ratio (OR) 6.81, p=0.089; 51-60 years, OR 2.75, p=0.145; 61-70 years, OR 1.60, p=0.391; >70 years, OR 1.02, p=0.979]. A significant relationship was found for all patients (OR 1.88, p=0.047) and the age group ≤70 years (OR 2.31, p=0.024). Conclusion Patients with hay fever have difficulty with first-line eradication, especially younger patients. The existence of clarithromycin-resistant bacteria is suspected, and other factors may also be involved. When a hay fever sufferer receives first-line treatment, eradication might be difficult and other treatment may be required.
3 0 0 0 OA 太古の化合物ギンコライドの周辺
- 著者
- 中西 香爾
- 出版者
- 社団法人 有機合成化学協会
- 雑誌
- 有機合成化学協会誌 (ISSN:00379980)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.5, pp.462-465, 2000-05-01 (Released:2009-11-13)
- 参考文献数
- 3
私は1963年に東京教育大学 (現筑波大学) から東北大学理学部の藤瀬新一郎教授の後任として赴任し, 幸運にも藤瀬研で手がけ始めたイチョウ成分の単離構造研究に携わることになった。この構造研究は構造決定がいわゆるルーチン化して推理小説を解くような興奮がなくなる直前になされたものであるが, 異常構造に基づく異常反応, 異常スペクトル現象が続出し, 研究者一同を大いに悩ませ, 楽しませてくれた。その上ギンコライドは血の流れ滑らかにして記憶力増進, アルツハイマー病の悪化防止に効果があるとして急激に需要が増えているイチョウエキスの有効成分の1つとしてここ数年急速に脚光を浴びてきている。イチョウは古生代 (250億年前) に出現した属の生き残りで, 一属一種しかなく, 化石の木といわれている。世界中に繁茂していたが絶滅し, わずか中国の寺院などに残っていたものが, 1800年後半に世界中に紹介され, 再び各国で見られるようになった。構造が最終的に出たのは1967年の夏であるが, 構造決定には珍しいくらいの感動の瞬間がいくつかあった 。私が行った構造研究では群を抜いて印象に残るものであり, 私にとり浪漫的な最後のクラシカル研究である。研究に携わったのは丸山雅男, 寺原昭, 中平靖弘, 板垣又丕, V.Woods (故人), 高木良子, 幅口一夫 (故人), 広田勇二, 菅原徹, 出井敏雄, 宮下正昭と私である。仙台に台風が来たおかげでイチョウが倒れ, 仙台市の許可を得て5本を伐採しその根皮100Kgから抽出, 再結晶を10数回繰り返し (液クロ以前の時代, NMRも100MHz) 10gずつのGAとGB, 20gのGCと200mgのGMを得た。ギンコライドは多形や混晶を形成する傾向が強く, ずいぶんてこずった。構造決定中に作られた50個の誘導体は今でも最低数ミリずつ小グラス管にいれられ, 立派なサンプル箱に整頓されてコロンビア大の研究室に保存されている。丸山さん以下よくこんなに整理ができたものといまさらながら感心している。
3 0 0 0 OA 現下の経済動向を踏まえた公共投資効果に関する基礎的研究
- 著者
- 門間 俊幸 樋野 誠一 小池 淳司 中野 剛志 藤井 聡
- 出版者
- 公益社団法人 土木学会
- 雑誌
- 土木学会論文集F4(建設マネジメント) (ISSN:21856605)
- 巻号頁・発行日
- vol.67, no.4, pp.I_327-I_338, 2011 (Released:2012-03-30)
- 参考文献数
- 20
- 被引用文献数
- 2
公共事業関係費の適正規模を検討するには,公共投資額とその効果についての適切な把握は重要な判断材料となる.現在,財政支出を行うための財源調達については,税金,利用者負担だけでなく,政府の公債発行が行われることが多い.公債発行は金融市場の需給に影響することから,経済状況がインフレ期なのかデフレ期なのかによって,公共投資効果も大きく異なることが予想される.本稿では,現在のマクロ経済状況を最新のデータに基づき分析・整理した上で,道路投資額及び道路整備量から国内総生産の変化等を推計するマクロ計量経済モデルを構築する.その際にインフレやデフレの時の需給バランス及びこれに伴う価格調整メカニズムを考慮することにより,現下の経済情勢等を踏まえた従来のマクロ計量経済モデルの課題点の検証を行った.その結果,現在の経済状況は流動性の罠に陥っているデフレ状態の可能性があること,デフレ時には国債発行によるクラウディング・アウトが生じ難いこと,公共投資の効果がインフレ時に比べ効果が大きく表れる傾向があることが示された.
3 0 0 0 OA 反転授業を導入したアクティブラーニングの取り組み
- 著者
- 岩崎 公弥子 大橋 陽
- 出版者
- 一般社団法人 CIEC
- 雑誌
- コンピュータ&エデュケーション (ISSN:21862168)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, pp.98-103, 2015-12-01 (Released:2016-06-01)
専門知識の教授だけでなく汎用的能力を育成するために,高等教育機関では様々な教育手法を取り入れ,試行錯誤を行っている。そのひとつが,アクティブラーニングである。筆者らは,反転授業(Flipped Classroom)を導入し,知識習得の部分を宿題(予習動画)にすることで,専門知識に基づくアクティブラーニングを実施した。本研究では,中規模クラスにおいて反転授業を導入し,1)質の高いグループアクティビティの実施,2)予習動画を閲覧させる工夫,3)予習動画のナレーション(人の声,合成音声)の違いについて検証し,より深い学びや動機付けがなされたか,国際情報概論(1年生必修)のなかで考察した。