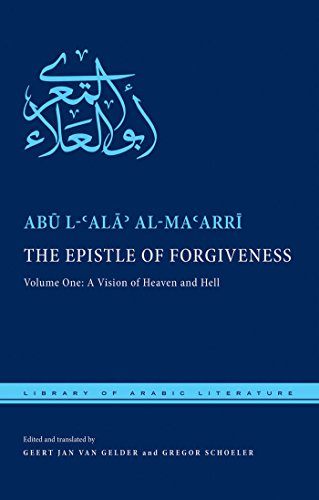- 著者
- 内川 勇太 菊池 雄太 鶴島 博和 ポペスク エイドリアン ネイスミス ローリー デイ ウィリアム デンツェル マルクス ウチカワ ユウタ キクチ ユウタ ツルシマ ヒロカズ ポペスク エイドリアン ネイスミス ローリー デイ ウィリアム デンツェル マルクス Yuta Uchikawa Yuta Kikuchi Hirokazu Tsurushima Adrian Popescu Rory Naismith William Day Markus Denzel
- 雑誌
- 立教經濟學研究
- 巻号頁・発行日
- vol.71, no.4, pp.143-191, 2018-03
6 0 0 0 構造生成器による医薬品分子設計の新展開
- 著者
- 海東 和麻 山西 芳裕
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬学会
- 雑誌
- MEDCHEM NEWS (ISSN:24328618)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.1, pp.26-30, 2022-02-01 (Released:2022-02-01)
- 参考文献数
- 19
構造生成器は、初期条件を元に、新規化学構造を出力する創薬AIの1種である。本稿では、主要な構造生成器として、ビルディングブロック型構造生成器と深層学習型構造生成器について、その概要を解説する。また、近年、大規模なオミクスデータの利用が可能となりつつある。そこで、筆者らが最近独自に開発した、オミクスデータを入力とし、新規化合物の構造式を出力する構造生成器であるTRanscriptome-based Inference and generation Of Molecules with desired PHEnotypes by machine learning(TRIOMPHE)について、実際に生成した化合物の構造式を交えて紹介する。
6 0 0 0 IR 鼎談 「日文研問題」をめぐって (特集 日本研究の過去・現在・未来)
- 著者
- 宮地 正人 仁藤 敦史 井上 章一 倉本 一宏
- 出版者
- 国際日本文化研究センター
- 雑誌
- 日本研究 (ISSN:09150900)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, pp.171-207, 2017-05
6 0 0 0 IR 「慰め発話」の形式的特徴 : 文末衣現を中心に
- 著者
- 田中 妙子
- 出版者
- 慶應義塾大学日本語・日本文化教育センター
- 雑誌
- 日本語と日本語教育 (ISSN:02865742)
- 巻号頁・発行日
- no.41, pp.31-46, 2013-03
論文1. 研究の目的2. 「慰め発話」に関する先行研究と日本語教科書での扱い3. 「慰め発話」の定義4. 分析対象5. 用例資料と記載方法6. 分析7. おわりに
6 0 0 0 OA うつ病と海馬神経新生
- 著者
- 増田 孝裕 中川 伸 小山 司
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬理学会
- 雑誌
- 日本薬理学雑誌 (ISSN:00155691)
- 巻号頁・発行日
- vol.136, no.3, pp.141-144, 2010 (Released:2010-09-13)
- 参考文献数
- 17
現在,うつ病の治療薬はセロトニンやノルアドレナリンといったモノアミンを増加させる薬剤が中心として用いられているが,脳内の細胞外モノアミン濃度は抗うつ薬の投与数時間後には増加するのに対し,臨床における治療効果発現までには数週間の慢性投与が必要とされることもあり,抗うつ薬の治療発現メカニズムは未だ明らかとされていない.近年,成熟期の脳においても海馬歯状回といった特定領域において,神経幹・前駆細胞が存在し,神経細胞が新生されることが明らかにされている.この海馬における神経新生は,うつ病発症の危険因子とされるストレスによって抑制され,逆に抗うつ薬を慢性投与することによって促進される.さらに,海馬神経新生を阻害すると,行動薬理評価モデルにおける抗うつ薬の作用が消失するなどの報告から,抗うつ薬による治療メカニズムの新しい仮説として海馬の神経新生促進仮説が提唱され,注目を集めている.本稿では,うつ病と海馬神経新生の関わりについて概説するとともに,我々が確立した成体ラット海馬歯状回由来神経幹・前駆細胞(Adult rat Dentate gyrus derived neural Precursor cell: ADP)の紹介を交えて,海馬神経新生をターゲットとした新規抗うつ薬創製のアプローチの可能性について記載する.
6 0 0 0 IR 本質的に論争的な概念をめぐって : コンセプトとコンセプションの区別の再考
- 著者
- 伊藤 克彦
- 出版者
- 一橋大学大学院法学研究科
- 雑誌
- 一橋法学 (ISSN:13470388)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.1, pp.423-474, 2016-03
Normative concepts are said to lead to controversial discussions and involve indefinite and valuable elements, unlike other concepts. Although we have to elucidate these concepts (such as justice, equality, and freedom) in the philosophy of law, we do not know how to discuss these matters rationally. In order to solve this problem, legal philosophers, especially those in Japan, have widely accepted the distinction between concept and conception used by John Rawls and Ronald Dworkin. If this distinction applies to the concept of justice, it leads to problems with theories of justice and with the methodology of these theories. Additionally, if this applies to the concept of law, it is connected with problems of jurisprudence. I doubt this distinction is appropriate for addressing these problems. Before extending my argument from this doubt, in this paper, I pay attention to the idea of the "Essentially contested concept," which was introduced by W. B. Gallie in 1956. Many people consider the idea that an "essentially contested concept" has a strong influence on the distinction between concepts and conceptions and often discuss the two of them together. Certainly, these ideas commonly emphasize the contestability of normative concepts. However, rather than the distinction between concept and conception, the seven criteria of the "Essentially contested concept" is complicated, and Gallie also emphasizes the historical influence of the normative concept. In this paper, I examine the issue of the normative concept itself over the discussions of two ideas together. Firstly, I summarize the idea that we divide normative concepts into two elements, and also explain Gallie's original idea of the "essentially contested concept." Secondly, I point out that Jeremy Waldron and Kenneth Ehrenberg apply Gallie's criteria to examples such as the "rule of law" and "law" itself. Thirdly, I consider the problem of both Gallie's idea and the distinction of concept and conception through Christine Swanton's critique. Finally, I conclude that it is difficult to preserve the coherency of the distinction of concept and conception, and if this distinction were collapsed, our discussions about normative concept would not lead to relativism and skepticism. Finally, I introduce David Wiggin's position of "Sensible subjectivism" and present a model of value judgment after the collapse of the distinction of concept and conception.
6 0 0 0 OA 高橋祥友著『中高年自殺-その実態と予防のために』
- 著者
- 上杉 孝實
- 出版者
- 日本ジェンダー学会
- 雑誌
- 日本ジェンダー研究 (ISSN:18841619)
- 巻号頁・発行日
- vol.2003, no.6, pp.57-58, 2003-08-31 (Released:2010-03-17)
6 0 0 0 OA 維新豪傑談 : 天囚聞書
- 著者
- 西村天囚 (時彦) 著
- 出版者
- 春陽堂
- 巻号頁・発行日
- 1891
6 0 0 0 OA 兵器模型 : 少年科学工作
6 0 0 0 OA コーポレート・ガバナンスが企業不祥事に与える影響
- 著者
- 青木 英孝
- 出版者
- 特定非営利活動法人 組織学会
- 雑誌
- 組織科学 (ISSN:02869713)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.2, pp.18-30, 2021 (Released:2022-01-11)
- 参考文献数
- 31
トップ・マネジメント特性,経営者インセンティブ,所有構造などの企業ガバナンス要因が,粉飾決算,産地偽装,実験データ改竄,カルテルなどの意図的不祥事,およびリコール,情報漏洩,集団食中毒などの事故的不祥事に与える影響を定量的に検証した.その結果,コーポレート・ガバナンスは企業不祥事に影響すること,不祥事の種類によって有効なガバナンスが異なること,ガバナンスでは防げない不祥事もあることが判明した.
- 出版者
- New York University Press
- 巻号頁・発行日
- 2013
- 巻号頁・発行日
- 1945
6 0 0 0 OA エントロピーと情報 : 関数解析の見地に立って
- 著者
- 梅垣 壽春 大矢 雅則 日合 文雄
- 出版者
- 一般社団法人 日本物理学会
- 雑誌
- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, no.3, pp.241-252, 1980-03-05 (Released:2008-04-14)
- 参考文献数
- 23
数学という基盤に立って物事を体系付けようとする場合, まず定義を与えることから始められる. 定義は論理的な約束, 或いは規約に基づいた条件の組合せによって設定される. エントロピーという物理学上の概念が三つの条件からなる公理系によって定義付けられたことによって遂には情報理論という全く新しい数学が構築され, 古くからの数学の問題が解決されたり, 新たな数学の概念が発見され, それが数学の進歩を促し, その結果自然科学以外の他の領域にも重大な関わりをもたらしている. エントロピーとは非常に不可思議な数理形式をしている. それが必ずS(P)=Σpklogpk-1とかS(f)=∫flogf-1dXというように表わされる必然性は偶然を支配する神々のなす業なのであろうか. 最近では再び物理, 詳しくは数理物理学ともいわれる境界領域に, 情報理論的に構成された相対エントロピーなどが頻りに立場して来ている. まさに, これは数学と物理学との交流の接点とでもいうべきか. 今後も問題点がこの接点の近傍で探求されることが期待される.
6 0 0 0 OA 愛媛県紳士録
- 著者
- 愛媛新報株式会社 編
- 出版者
- 愛媛新報
- 巻号頁・発行日
- 1934
- 著者
- Yutong Zou Bo Guo Songlin Yu Danchen Wang Ling Qiu Yu Jiang
- 出版者
- SOCIETY FOR FREE RADICAL RESEARCH JAPAN
- 雑誌
- Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition (ISSN:09120009)
- 巻号頁・発行日
- vol.69, no.3, pp.229-237, 2021 (Released:2021-11-01)
- 参考文献数
- 41
- 被引用文献数
- 5
Objective of the present study was to evaluate the effect of vitamin D supplementation on glycose homeostasis, islet function, and diabetes progress. Literatures were searched via electronic databases, websites, and previous reviews from the earliest available time to the end of May 2020. Randomized controlled trials initially designed for diabetes and prediabetes with 25-dihydroxyvitamin D [25(OH)D]<30 ng/ml were included. All data were analyzed and presented based on the Cochrane guidelines and PRISMA guidelines. In total, 27 articles (n = 1,932) were enrolled in this study. Vitamin D supplementation significantly improved fasting blood glucose, postprandial blood glucose, and quantitative insulin sensitivity check index in diabetes and prediabetes with baseline 25(OH)D<30 ng/ml. Higher percentages regressing from prediabetes to normal glucose status [1.60 (1.19, 2.17), p = 0.002, n = 564] and lower percentage progressing from prediabetes to diabetes [0.68 (0.36, 1.27), p = 0.23, n = 569] were found in the supplementation group. The positive effects of vitamin D supplementation on body mass index, waist, HDL-C, LDL-C, and CRP were also demonstrated. In conclusion, modest improvements in vitamin D supplementation on short-term glycose homeostasis, insulin sensitivity, and disease development in diabetes and prediabetes with 25(OH)D<30 ng/ml were demonstrated, but more research needs to be conducted in the future to support the clinical application. (Register ID: CRD42020186004)