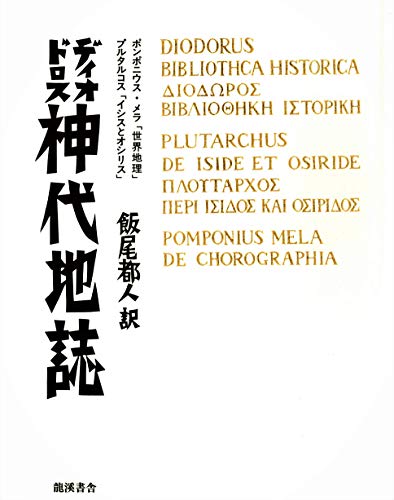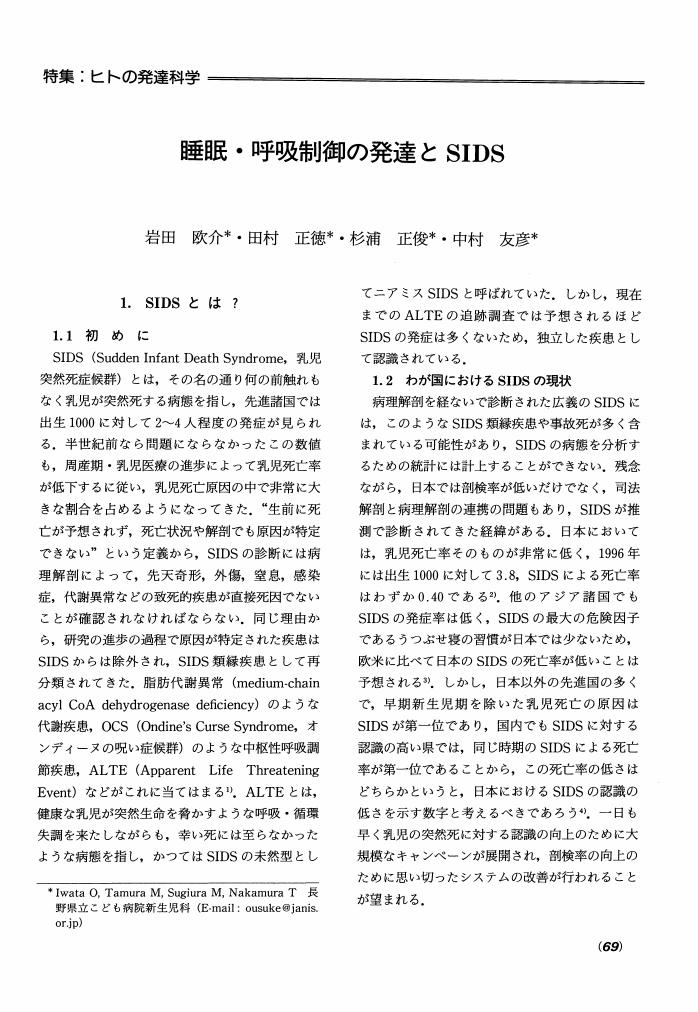- 著者
- Bernhard Glienke
- 出版者
- Wachholtz
- 巻号頁・発行日
- 1975
- 著者
- edited by Stefan Berger Chris Lorenz and Billie Melman
- 出版者
- Routledge
- 巻号頁・発行日
- 2012
1 0 0 0 北海道の赤飯文化について:-甘納豆入り赤飯-
- 著者
- 佐藤 恵 田中 ゆかり 藤本 真奈美 鴫原 正世
- 出版者
- 一般社団法人 日本家政学会
- 雑誌
- 一般社団法人日本家政学会研究発表要旨集
- 巻号頁・発行日
- vol.64, 2012
<b>【目的】 </b>北海道は明治維新後の国策により、沖縄を除く日本各地からの移住者が入植し、この地を築いた開拓の歴史があり、その中から独自の文化が生まれた。食文化についても例外ではなく、各々出身地の伝統食を継承しつつ、そこに厳寒の地で生き抜くための工夫が施され、北海道独自のものへと変化していった。本研究は、北海道が発祥ともいわれ、道民に慣れ親しまれている郷土料理の一つ「甘納豆(金時豆等)入り赤飯」について、そのルーツを辿り、他都府県とは異なる“北海道の赤飯文化”を明らかにすることを目的とした。<br><b>【方法】 </b>2008年~2011年の入学生に対し、6月~8月に『赤飯アンケート調査』・『家庭での聞き取り調査』・『市場調査』を実施した。調査対象者は、本学学生、食物栄養科569名・保育科585名、合計1154名である。回答者のうち、北海道出身学生の回答を集計し、甘納豆入り赤飯の実態を調査した。<br><b>【結果】 </b>アンケート調査の結果、甘納豆入り赤飯の認知度は100%であったが、全国的に認知度が低いことを「知らなかった」「聞いたことがある・最近知った」と回答した学生が、全体で67%、多い年で74%であった。好きな赤飯の種類については、「甘納豆入り赤飯が好き」と回答した学生が全体で68%、多い年で76%、「小豆の赤飯が好き」と回答した学生が全体で9%、多い年で10%であった。また、市場調査の結果、北海道で販売されている赤飯は、年中行事に関係なくお弁当やおにぎりと常に同等に扱われ、販売店のもち米売り場では甘納豆と食紅が並べられている等、陳列方法も独特であった。これらのことから、道民には甘納豆入り赤飯が、北海道の赤飯として一般的であることが示唆された。
1 0 0 0 丁抹國における酪農業
1 0 0 0 デンマアクの國民體操 : 興國の大原動力
- 著者
- 平林廣人執筆
- 出版者
- ジャパンタイムス社國際パンフレット通信部
- 巻号頁・発行日
- 1928
1 0 0 0 デンマアク農民の努力
1 0 0 0 超音波断層法の読影について
- 著者
- 井出 正男
- 出版者
- 日本産科婦人科学会
- 雑誌
- 日本産科婦人科學會雜誌
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.8, pp.813-814, 1974
1 0 0 0 超音波計測による胎児発育診断
- 著者
- 浅田 昌宏
- 出版者
- 日本産科婦人科学会
- 雑誌
- 日本産科婦人科学会雑誌 (ISSN:03009165)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.7, pp.p996-1004, 1981-07
- 被引用文献数
- 1
超音波検査を中心として, すべての胎児を妊娠初期から分娩に至るまで, 経時的に監視する流れをシステム化し, この流れに従つて, 下記の如く, 実時間超音波断層法による胎児の発育診断を行つた.1)妊娠初期においては, 羊水腔径や胎児坐高長の計測を打つだ.BBT起算による妊娠日数と羊水腔径との相関係数は0.914であり, 胎児坐高長との相関係数は0.990であつた.また, 妊娠日数の推定の誤差範囲は, それぞれ, ±5日, ±3日であり, 胎児の直接的計測値である坐高長の方が, 間接的計測値である羊水陸径より優れた胎児発育診断のパラメータであることが知られた.2)BBT起算による坐高長発育曲線を利用して, 最終月経起算による坐高長値をブロつトすると, 妊娠日数の推定が1週間以上ずれる症例が7.1%みられた.3)妊娠中期以降は児頭大横径や胎児腹囲の計測を行つたが, これら単独計測では, 正常月経周期を有し, 最終月経が明確な妊娠においても, 正常胎児発育群から, 発育異常群を明確に除外診断しがたく, 児頭大横径によるSFDの正診率は54.3%であり, 胎児腹囲による場合は63.7%であつた.しかし, 胎児腹囲によるLFDの正診率は81.3%であつた.4)児頭大横径と胎児腹囲を同時測定後, 1週間以内に出生した73例の未熟児分娩の判別式は, Z=0.6012X+3, 100Y-45.204となり, 正診率は, 90.4%, 偽陽性率は38.5%, 偽陰性率は3.6%であつた.10例のIUGRのうち9例が出生前に診断された.5)児頭大横径, 胎児腹囲, 超音波検査時点での妊娠日数と子宮底長の4項目による多変量解析から胎児体重推定値を求め出生体重との相関を求めるとR=0.852で, 1S.D.=±281gであつた.
1 0 0 0 IR INF条約の法構造(一)
- 著者
- 黒沢 満 Kurosawa Mitsuru
- 出版者
- 新潟大学法学会
- 雑誌
- 法政理論 (ISSN:02861577)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.1, pp.69-114, 1988-07
1 0 0 0 子宮内外同時妊娠の1例
- 著者
- 益本 貴之 尾形 理江 森本 規之 岡田 朋子 三浦 徹
- 出版者
- 近畿産科婦人科学会
- 雑誌
- 産婦の進歩 (ISSN:03708446)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.4, pp.265-268, 2007
今回われわれは子宮内外同時妊娠の1例を経験した.文献的考察を加えて報告する.症例は35歳既婚.0経妊0経産.平成○年2月3日を最終月経の開始日とした無月経を主訴に,当院を平成○年3月22日初診となった.既往歴,家族歴に特記事項なし.排卵誘発等の不妊治療歴はなし.初診時の腟鏡診,内診では異常所見を認めず,経腟超音波検査にて子宮内に胎嚢と思われるエコーフリースペースを認めた.平成○年4月4日,性器出血を主訴に再診.腟鏡診にて外子宮口からの少量の性器出血を認め,内診では右付属器領域に圧痛を認めた.経腟超音波検査にて子宮内にエコーフリースペースと,右付属器領域に胎児心拍を伴うエコーフリースペースを認めた.子宮内外同時妊娠(右卵管妊娠および稽留流産)を疑い,本人および家族に十分なインフォームドコンセントを行ったうえで,同日腹腔鏡下手術を施行とした.腹腔内には凝血塊を含む約200gの血液が貯留していた.右卵管は腫大しており,同部位の妊娠が疑われた.右卵管切除術を行い,同時に経腟的に流産手術を施行した.患者の術後経過は良好にて,術後3日目に退院とした.摘出組織の病理組織検査にて,右卵管は右卵管妊娠組織,子宮内組織は流産組織であることが確認された.近年のARTのめまぐるしい進歩に伴い,子宮内外同時妊娠の頻度は増加していると考えられる.本症例では初診時に超音波検査にて子宮内に胎嚢を確認したが,右付属器の異常所見を確認するには至らなかった.再診時に内診にて右付属器領域の圧痛を認め,初めて超音波検査にて右卵管妊娠の存在を確認できた.日常診療において子宮内に胎嚢が確認できたとしても,子宮内外同時妊娠の存在を念頭に置き,付属器領域等を注意深く超音波や内診により診察する習慣をつけることの重要性を再認識した.〔産婦の進歩59(4):265-268,2007(平成19年11月)〕<br>
1 0 0 0 IR INF条約の法構造 (二・完)
- 著者
- 黒沢 満
- 出版者
- 新潟大学
- 雑誌
- 法政理論 (ISSN:02861577)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.3, pp.49-113, 1989-01
1 0 0 0 OA インドネシアにおける応用地質の現状
- 著者
- 中原 正幸 永田 聰 高木 圭介 Anwar MAKMUR
- 出版者
- Japan Society of Engineering Geology
- 雑誌
- 応用地質 (ISSN:02867737)
- 巻号頁・発行日
- vol.44, no.6, pp.349-359, 2004-02-10 (Released:2010-02-23)
- 参考文献数
- 18
インドネシア共和国は, 構造地質的には島弧海溝系で構成される変動帯の中にあり, 日本と同様に複雑な地質構造を有している. 応用 地質的特徴としては, 熱帯気候下での岩石の著しい風化浸食, それを覆う火山堆積物, 広く分布する石灰岩の存在である. これらの地質的特徴が示す地盤特性によって, 地盤災害, あるいは土地利用などが特徴づけられている. ここでは同国での水資源開発の調査経験から, ダム開発, 地下水開発に伴う応用地質的現状を示すとともに, 現場での技術的対応事例について示した.
1 0 0 0 OA 埼玉県に現存する煉瓦水門の景観特性と保全のあり方に関する研究
- 著者
- 宍戸 勇気 深堀 清隆 窪田 陽一 三ツ畑 紀子
- 出版者
- Japan Society of Civil Engineers
- 雑誌
- 土木史研究論文集 (ISSN:13495712)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, pp.59-71, 2007-06-15 (Released:2010-06-04)
- 参考文献数
- 23
There are many historical brick sluice gates constructed in Saitama Prefecture during the Meiji-Taisho era. This study aims at creating criteria to clarify the characteristics of the sluice gate in Saitama Pref. According to the field and literature survey, they are classified into authenticity, aesthetics, and accessibility to the site and they include surrounding spatial features and situations. These criteria were rated by counting or judging physical and spatial features of the sites. In addition, in order to know the value of the site, the impression of people was observed in a questionnaire survey. It is important to know what criteria contribute the historical impressions of the site for the future conservation and improvement of the site. The impression is quantified into the score of attractiveness, oldness, and historical feeling. The relationship between these scores of impression and scores of physical and spatial features was analyzed. In addition, techniques of conservation and site improvement were classified into nine principles and the method to select appropriate techniques based on the scores of physical and spatial features of each sluice gate.
1 0 0 0 OA 地球のリフォームの目的 - 人類圏への道に復帰する
- 著者
- 水谷 広
- 出版者
- 生態工学会
- 雑誌
- Eco-Engineering (ISSN:13470485)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, no.4, pp.167-174, 2010-10-31 (Released:2011-01-05)
- 参考文献数
- 21
Recently, so-called geoengineering appears to be championed by some in the fight against global warming as a possible alternative to reducing greenhouse gas emissions. Instead, I believe that there is a root cause for the emissions that should be first taken care of. In this paper, I argue that what needed most is not a fix to the global warming and that the current conditions of our environments need to be viewed in the context of Earth system evolution. The terrestrial life began to be present around four billion years ago; however, it only achieved the enduring basis for its continued existence when the oxygen respiration emerged. It, thus, took two billion years to become a sustainable sphere with its own rule, the biosphere. Then, about ten thousand years ago, humans started agriculture, departing from the biological rule. It formed a bud of the humanosphere and kept growing until the 16th century, when the need for larger amount of metals and other goods turned our eyes to underground resources. Unfortunately, these resources are not renewable. Thus, we unknowingly derailed ourselves from the path to the formation of an enduring sphere of humans, the humanosphere. Now we are seeing the end of our way that has lasted for five centuries and some of us might be at a loss in front of the deteriorating environments. During this period, however, our understanding about this universe and its various laws has advanced greatly and it will help us to return to the course to the humanosphere. Some notes to be observed for successfully getting back to the track are also discussed.
1 0 0 0 OA 睡眠・呼吸制御の発達とSIDS
- 著者
- 岩田 欧介 田村 正徳 杉浦 正俊 中村 友彦
- 出版者
- 一般社団法人 日本生体医工学会
- 雑誌
- BME (ISSN:09137556)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, no.7, pp.69-78, 1998-07-10 (Released:2011-09-21)
- 参考文献数
- 47
1 0 0 0 マルチメディアの著作権情報の定義と伝達について
- 著者
- 喜多村 政贊
- 出版者
- 一般社団法人情報処理学会
- 雑誌
- 情報処理学会研究報告電子化知的財産・社会基盤(EIP) (ISSN:09196072)
- 巻号頁・発行日
- vol.1998, no.85, pp.57-64, 1998-09-19
- 被引用文献数
- 1
設問 デジタルネットワーク社会で著作権をどう扱うべきか解釈 著作権処理技術の取り組み不足定義 人々の意志を伝える技術的な枠組みを提供する伝達 権利者、利用者の意志を翻訳し、契約と合意を支援する効果 適性利用の促進、不正行為の抑止、新しい文化交流の社会マルチメディアで話題となる著作権問題は契約上の不備から生じている。権利者と利用者の間で権利の所在や内容の情報交換をし、合意の上、利用する機器をその合意条件に沿って制御して利用し、対価を支払う。かかる仕組みによってはじめて権利者側の恐れる無断利用の広がりをなくし、また利用者側も正規の利用を約束される。デジタルネットワークの環境下では、今までのやり方では破綻が来るであろうとの声が大きく、コピー禁止機能への要望が根強いが、別の面からは、デジタルネットワークによってはじめて権利者と利用者間の情報交換ができ、根本的な解決への道ができる。つまり、正確な権利処理が可能となり、これにもとづいた需要と供給双方の合意による適正な利用がひろがり、無断や不正な利用が防止できるようにもなる。本論では、かかる視点から権利者にも利用者にもバランスのとれる技術の枠組みをつくる試みを紹介する。Copyright issue is introduced by rapidly advancing technology that has produced a many kind of copy functions such as photo copy, VCR and PC, but that has not yet made in general use of a copyright clearing system in synchronicity with such functions among consumers. This report shows a series of ideas of how to improve the market environment of the copyrighted contents delivery. Firstly copyright and contract information exchange is discussed as a mandatory requirement for the solution and the identifications and also the transfer method are defined. Secondly a translation function is introduced between content provider, service provider and content user. This will facilitate the trade of contents supporting the information exchange in semantic between contracting persons as an contract agent. Finally with use of an appropriate level of security, and improved environment of the trade is sketched out.