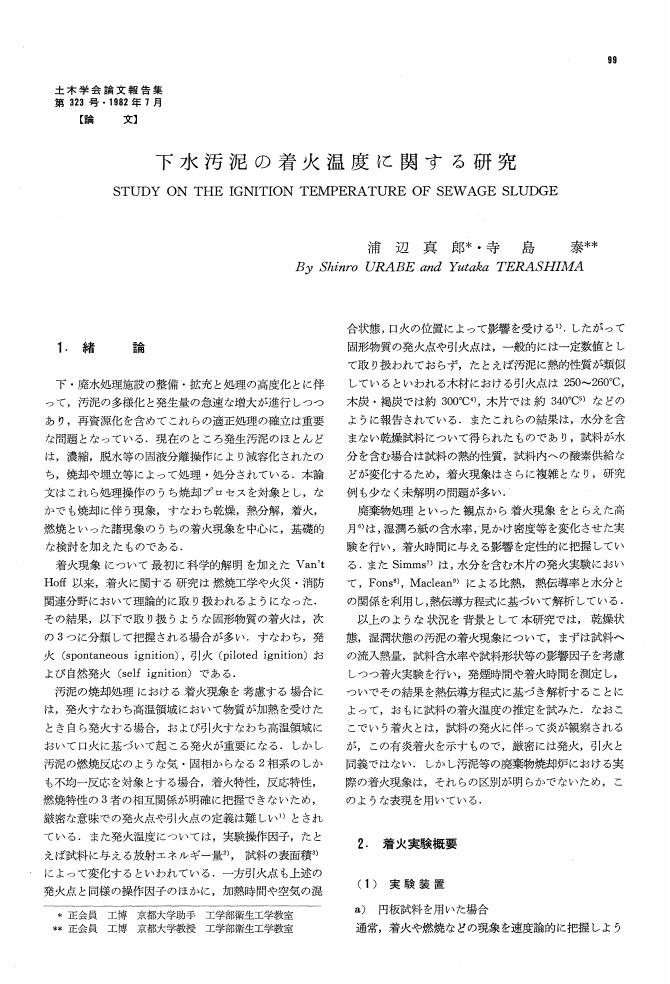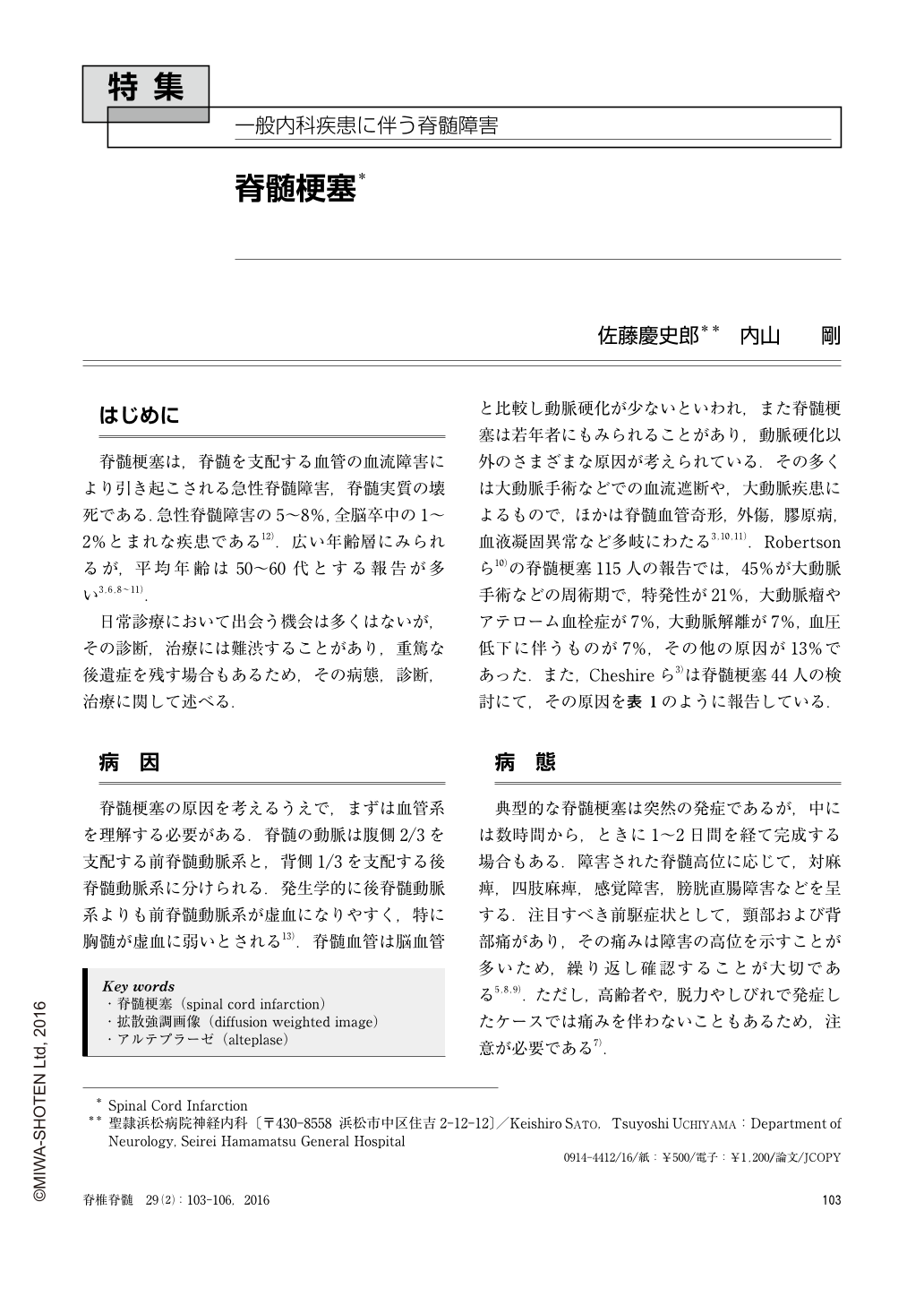1 0 0 0 ブレイクダンスにおける技術学習プロセスの複雑性と創造性
- 著者
- 清水 大地 岡田 猛
- 出版者
- 日本認知科学会
- 雑誌
- 認知科学 (ISSN:13417924)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, no.1, pp.203-211, 2015
Focusing on the process of a dancer's acquisition of a new technique in breakdance,<br>,"Inside Ninety", this longitudinal case study aims to disclose the process of skill acqui-<br>sition through practice. We conducted a fieldwork study (participant observation and<br>interviews) to analyze the dancer's endeavours to acquire and improve skills. By avoid-<br>ing the specification of goals and movements by the researchers, as is often the case<br>in experimental settings, we observed the development of movements in each practice<br>session. The results indicate that the process of acquisition of a new dance technique<br>consists not only of the refinement of a particular skill, but also of two other activities<br>;the exploration of new and original skill utilizing the characters of a particular skill, <br>and the arrangement of that skill so that it should fit into his full performance. The<br>process of an expert's acquisition of a particular technique is a complicated and creative<br>one, integrating each skill into a full performance.
1 0 0 0 IR 一人ひとりが生きる学級経営の在り方 : 「教育山形『さんさんプラン』」の良さを生かして
- 著者
- 山口 絵里子
- 出版者
- 山形大学大学院教育実践研究科
- 雑誌
- 山形大学大学院教育実践研究科年報 = Bulletin of graduate school of teacher training Yamagata University
- 巻号頁・発行日
- vol.2, pp.146-153, 2011-02-19
本研究では,山形県の公立小学校及び公立中学校で導入されている「教育山形『さんさんプラン』」による少人数学級編制の良さを生かし,子ども一人ひとりが生きる学級経営の在り方を考察した。調査では,褒める・認める・励ますなどの温かい声がけや,係活動や委員会活動,クラスでの役割を与え活躍できる場をつくることが効果的な働きかけであることが分かった。これらの一人ひとりを生かそうとする教師の働きかけは,子どもたちの自己存在感,自己有用感を高めているものと考えられる。 キーワード:学級経営, 少人数教育, かかわり, 自己効力感, 自己有用感
1 0 0 0 OA 東京市紀元二千六百年奉祝記念事業志
- 出版者
- 東京市
- 巻号頁・発行日
- 1941
1 0 0 0 OA 数学教育の理念と中心概念 : 認識の獲得を目指して
- 著者
- 駒野 誠
- 出版者
- 東京理科大学
- 雑誌
- 理学専攻科雑誌 (ISSN:02864487)
- 巻号頁・発行日
- vol.44, no.1, pp.58-71, 2002-04-01
現在、数学教育には、理念が求められている。中・高一貫の学校で教えている経験によって、分かり得たことが多い。授業で見せる生徒の反応の変化など生徒と共に数学を勉強している現場教師にしか分かり得ないことがあるはずと考える。ここに3つのキーワード : 『無限をいかに掴まえるか』、『共生の掛け橋』、『認識の変化の獲得』をもとに、学校数学のIdentityを示し、数学教育の理念を次のように提案する : 「数学学習は、『無限をいかに掴むか』について学習するが、今までの自分にない新しい概念や認識を獲得し、明日の自分の創造に資するものである。」また、この理念を達成するには、感動をともなうような教材が不可欠であり、その分類として、中心概念となる6つの柱を示した。
1 0 0 0 OA 炭化片分析により証拠づけられた奥日光山域における明治期の山火事
- 著者
- 石田 泰成 逢沢 峰昭 大久保 達弘
- 出版者
- 森林立地学会
- 雑誌
- 森林立地 (ISSN:03888673)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.1, pp.1-8, 2013-06-25 (Released:2017-04-03)
- 参考文献数
- 33
栃木県奥日光山域において,明治期の1905年に撮影された山火事跡の古写真がデジタルアーカイブスとして公開されている。本研究は,この写真の撮影地点の探査と樹齢構造の調査から,山火事が発生した林分を特定し,そこで炭化片分析を行うことで,同分析によって山火事発生が実証可能か検討した。その上で,山火事発生に関する文献記録のない同山域の1915年の古い地形図上にみられる広域的なササ地が,山火事によって成立したものであるかを炭化片析によって明らかにすることを目的とした。踏査の結果,山火事発生林分を特定することができた。山火事発生林分は, 1915年の湯ノ湖周辺の地形図ではササ地となっている場所と,その近くの広葉樹林であった。また,文献および樹齢構造の調査,この場所では約120年前(1890年代)に山火事が発生したこと,この周囲のカンパ林およびミズナラ林の樹齢は120年以下であることがわかった。この林分での炭化片分析の結果,いずれの林分においても炭化片が検出され,同分析によって,山火事発生の実証が可能と考えられた。次に, 1915年にササ地であった別のミズナラ・シラカンバ林において同様の調査を行った結果,すべての地点から炭化片が検出され,樹齢は最大で101年であった。以上から,奥日光山域では明治期に広域的な山火事が発生しており, 1915年地形図のササ地およびその周囲の広葉樹林にみられる現在の森林植生は山火事後に成立したものと推察された。
1 0 0 0 IR <特集 : 行く・読む・感じる>新快速のモダニズム
- 著者
- 岡本 健作
- 雑誌
- KG社会学批評 = KG Sociological Review (ISSN:21870683)
- 巻号頁・発行日
- no.6, pp.85-86, 2017-03-24
1 0 0 0 OA 日英露語のアスペクト体系と結果表現の関係 : 2種類のアスペクト限定
- 著者
- ペトロヴナ スバチェワ インナ
- 出版者
- 筑波大学大学院博士課程文芸・言語研究科応用言語学コース
- 雑誌
- 筑波応用言語学研究 (ISSN:13424823)
- 巻号頁・発行日
- no.17, pp.29-41, 2010-12-20
1 0 0 0 OA アクティブ運用のパフォーマンス評価とマネジャーのスキルに関する研究 : サーベイ
- 著者
- 四方 健彦
- 出版者
- 横浜国際社会科学学会
- 雑誌
- 横浜国際社会科学研究 = Yokohama journal of social sciences (ISSN:13460242)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, no.6, pp.95-113, 2010-02-20
1 0 0 0 IR 雪舟等揚の研究 : その人と作品
- 著者
- 蓮実 重康
- 出版者
- 京都大学
- 雑誌
- 京都大學文學部研究紀要 (ISSN:04529774)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, pp.1-149, 1960-05-30
この論文は国立情報学研究所の学術雑誌公開支援事業により電子化されました。
1 0 0 0 OA 下水汚泥の着火温度に関する研究
- 著者
- 浦辺 真郎 寺島 泰
- 出版者
- Japan Society of Civil Engineers
- 雑誌
- 土木学会論文報告集 (ISSN:03855392)
- 巻号頁・発行日
- vol.1982, no.323, pp.99-108, 1982-07-20 (Released:2010-08-05)
- 参考文献数
- 24
- 被引用文献数
- 1 1
1 0 0 0 OA 農家による加害獣の同定方法とその能力
- 著者
- 菅原 寛 關 義和
- 出版者
- 「野生生物と社会」学会
- 雑誌
- 野生生物と社会 (ISSN:24240877)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, no.1, pp.41-50, 2015-11-01 (Released:2017-06-16)
- 被引用文献数
- 1
We assessed the ability of farmers to accurately identify mammals causing crop damage, by interviewing 134 farmers in Nagano Prefecture, Japan. The farmers identified crop damage caused by Japanese macaque (Macaca fuscata) based on sightings; that caused by sika deer (Cervus nippon) and wild boars (Sus scrofa) based on footprints and/or feeding signs; and that caused by masked palm civets (Paguma larvata), raccoon dogs (Nyctereutes procyonoides), and Japanese badgers (Meles anakuma) based on feeding signs. The result showed a high accuracy of Japanese macaque identification causing crop damage; however, the accuracy of footprint identification for sika deer and wild boars was low. Furthermore, many farmers confused the footprints of three mammals with one another-the sika deer, wild boars, and Japanese serows (Capricornis crispus). Thus, reports regarding the identification of mammals that cause crop damage by farmers need to be carefully reviewed. Generalized Linear Mixed Model analysis indicated that hunting and effective communication with hunters positively affected the accuracy of the answers. This suggests that a platform to communicate with hunters or experts can be effectively offered to farmers to enhance their knowledge and ability to accurately identify mammals that cause crop damage.
1 0 0 0 OA 2.診断プロセス
- 著者
- 松永 卓也
- 出版者
- 一般社団法人 日本内科学会
- 雑誌
- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)
- 巻号頁・発行日
- vol.102, no.7, pp.1676-1681, 2013-07-10 (Released:2014-07-10)
- 参考文献数
- 4
- 被引用文献数
- 1
腫瘍細胞が全身に播種している悪性腫瘍性疾患のうちで,抗癌薬治療により治癒する可能性がある数少ないものの1つに白血病がある.白血病を治癒に導くためには,迅速に確定診断して適切な治療を行う必要がある.臨床症状と血算などの血液検査により白血病を疑い,確定診断は骨髄穿刺・生検試料を用いた形態学的所見,細胞化学染色所見,染色体・遺伝子所見および表面抗原所見によりなされる.
1 0 0 0 OA サンゴモ類の生態
- 著者
- 藤田 大介
- 出版者
- THE SESSILE ORGANISMS SOCIETY OF JAPAN
- 雑誌
- Sessile Organisms (ISSN:13424181)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, no.1, pp.17-25, 1999-08-30 (Released:2009-10-09)
- 参考文献数
- 26
- 被引用文献数
- 1 1
- 著者
- 中兼 和津次
- 出版者
- 比較経済体制学会
- 雑誌
- 比較経済研究 (ISSN:18805647)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.2, pp.2_85-2_98, 2018
<p>現代中国政治・社会の統治構造の柱が,1)権力主義(権力の維持,拡大を最高目的とする思想と政策),2)エリート主義(意思決定は少数の選ばれた人間・集団によってなされるべきだとする思想と政策),そして3)実用主義(目的のためには手段を択ばないという思想と政策)という3つの大きな原理だと私は考えるが,それは空想から現実へと社会主義像が変転する中で生まれ,確立してきた原理であった.そのことを立証するために,1)ロシア革命とマルクス・エンゲルス,レーニンの空想的社会主義構想,2)スターリンによって実施されたソ連型社会主義経済の実態,3)中国に輸入されたソ連型モデルと毛沢東による修正,4)毛沢東の空想的社会主義理念とそれがもたらした結末,5)鄧小平による現実的経済体制の選択といった,社会主義像が空想から現実へと転換していく一連の過程とその結果について考察する.</p>
1 0 0 0 OA 大気汚染の文化財への影響
- 著者
- 古明地 哲人
- 出版者
- 公益社団法人 大気環境学会
- 雑誌
- 大気汚染学会誌 (ISSN:03867064)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.5, pp.A103-A111, 1993-09-10 (Released:2011-11-08)
- 参考文献数
- 26
大気汚染の研究範囲はこれまで専ら人の健康, 植物影響に関する研究分野に関心が集中してきた。そしてこれらに関係する形で大気中での汚染現象を気象, 拡散, 化学反応モデル, 汚染物質と被影響対象との量一反応関係として扱う等, 多くの学問分野を包含する手法も使用されてきた。しかし, 緊急避難としての性格が大きかったこれまでの環境調査研究の中にも, 近年は環境問題のより幅広い現象に関心が広がり, 歴史的な文化遺産, 文化財への影響, その保存法等の調査も徐々に実施されはじめて来た。文化財のおかれている現状, また文化財の面からのより質の高い, 良好な環境について紹介したい。
1 0 0 0 IR 女子卓球選手の動体視力特性
- 著者
- 村上 博巳 山岡 憲二 山本 武司 田阪 登紀夫 ムラカミ ヒロミ ヤマオカ ケンジ ヤマモト タケシ タサカ トキオ Murakami Hiromi Yamaoka Kenji Yamamoto Takeshi Tasaka Tokio
- 出版者
- 同志社大学スポーツ健康科学会
- 雑誌
- 同志社スポーツ健康科学 (ISSN:18834132)
- 巻号頁・発行日
- no.2, pp.26-37, 2010-03
原著(Original investigation)社会人(S群):7名,大学生(U群)22名,高校生(H群)32名,中学生(JH群)19名,小学生(ES群)49名のトップクラスの女子卓球選手を対象にスポーツビジョン研究会で実施している(1)静止視力(2)KVA動体視力(3)DVA動体視力(4)コントラスト感度(5)眼球運動(6)深視力(7)瞬間視力(8)眼と手の協応動作の測定を行い、競技力に重要な因子である動体視力(KVA,DVA)の特性について検討した。対照群は一般女子学生90名の中から日常運動習慣の無い一般女子学生10名(NA群)抽出した。各群とも静止視力1.0以上を対象とした。KVA動体視力,DVA 動体視力を各群間の平均値で見るとKVA動体視力の各群間の平均値に有意な差が見られなかったが、DVA動体視力のU群の平均値はH,ES群の平均値より有意に高い値を示した。KVA動体視力に対する測定項目の貢献度の高い視機能は静止視力,眼と手の協応動作,コントラスト感度、DVA動体視力は瞬間視,眼球運動,眼と手の協応動作であった。そして静止視力,コントラスト感度と競技歴との間には有意な相関関係は認められなかったが、瞬間視,眼球運動と競技歴との間には有意な正の相関関係が認められた。眼と手の協応動作と競技歴との間には有意な負の相関関係が認められた。以上のことから、女子卓球選手のKVA動体視力は潜在的、DVA動体視力はトレーニングの要因が影響し、競技力の向上を目指し動体視力を高めるにはKVA動体視力は視力矯正を含み最適な静止視力を有すること、DVA動体視力は継続したトレーニングが必要であることが示唆された。A study was conducted to investigate the characteristics of kinetic vision in women's table tennis players. There are kinetic visual acuity and dynamic visual acuity in kinetic vision. In the present experiment, sports vision of women's table tennis players were measured; member of society women's table tennis players (S group: aged 24.7±1.3yrs),university women's table tennis players(U group: aged 19.5±1.1yrs),high school women's table tennis players (H group: aged 16.3±0.8yrs),junior high school women's table tennis players(JH group: aged 13.6±0.8yrs),elementary school women's table tennis players(ES group: aged 11.1±1.0yrs), and Kyoto sangyo university student women's non-athletes (NA group: aged 18.7±0.5yrs). Then players 7 numbers in S group,22 numbers in U group,32 numbers in H group,19 numbers in JH group,49 numbers in ES group and 10 numbers in NA groups(their static visual acuity>1.0) were selected as subjects. Static visual acuity, kinetic visual acuity, dynamic visual acuity, contrast sensitivity, ocular motor skill, depth perception, visual reaction time and eye-hand coordination of them were measured. Physical characteristics and experience of training of table tennis were investigated using questionnaire. Mean values of kinetic visual acuity were no significantly among all groups, dynamic visual acuity in U groups were significantly higher than H,ES groups. Kinetic visual acuity and dynamic visual acuity showed difference about contribution rates for measurement item. Static visual acuity, contrast sensitivity and eye-hand coordination showed greater contribution rates for kinetic visual acuity. Visual reaction time, ocular motor skill and eye-hand coordination showed greater contribution rates for dynamic visual acuity. Significant correlations between static visual acuity, contrast sensitivity and experience of training were not found, but significant positive correlations between visual reaction time, ocular motor skill and experience of training were found and significant negative correlation between eye-hand coordination and experience of training was found. These results suggest that the improvement of kinetic visual acuity hold the best static visual acuity, the improvement of dynamic visual acuity are caused by heavier training and these are the important for the level up game ability.
1 0 0 0 OA 昨年経験した非圧迫性病変による麻痺症例の検討
- 著者
- 藤井 洋 岡嶋 啓一郎 高野 晴夫 西 芳徳 村上 直也 福田 朋博
- 出版者
- West-Japanese Society of Orthopedics & Traumatology
- 雑誌
- 整形外科と災害外科 (ISSN:00371033)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.2, pp.319-323, 2002-03-25 (Released:2010-02-25)
- 参考文献数
- 8
We experienced 6 patients with paralysis due to cervical mechanical compression last year at our hospital. One patient had multiple sclerosis. He displayed sudden symptoms which improved and deteriorated. He also showed high T2 lesion in MRI. Another patient sustained spinal infarction. She also suddenly caused symptoms and showed high T1 and T2 lesion in spinal MRI. One patient had alcholic neuropathy. We believe that these diseases can be differentiated by physical examination, MRI, and various other examinations.
1 0 0 0 脊髄梗塞
- 著者
- 佐藤 慶史郎 内山 剛
- 出版者
- 三輪書店
- 雑誌
- 脊椎脊髄ジャーナル (ISSN:09144412)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.2, pp.103-106, 2016-02-25
はじめに 脊髄梗塞は,脊髄を支配する血管の血流障害により引き起こされる急性脊髄障害,脊髄実質の壊死である.急性脊髄障害の5〜8%,全脳卒中の1〜2%とまれな疾患である12).広い年齢層にみられるが,平均年齢は50〜60代とする報告が多い3,6,8〜11). 日常診療において出会う機会は多くはないが,その診断,治療には難渋することがあり,重篤な後遺症を残す場合もあるため,その病態,診断,治療に関して述べる.
1 0 0 0 OA 有機フッ素化合物の分解反応の開発
- 著者
- 堀 久男
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬学会
- 雑誌
- ファルマシア (ISSN:00148601)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, no.1, pp.54-58, 2014 (Released:2016-02-01)
- 参考文献数
- 25
有機フッ素化合物は耐熱性,耐薬品性,界面活性等の優れた性質を持つ.このため様々なところで使われているが,近年になって環境残留性や生体蓄積性,さらには廃棄物の分解処理が困難といった負の側面が顕在化しつつある.環境中で検出されているのは主に界面活性剤として用いられてきたペルフルオロアルキルスルホン酸類(PFAS類,CnF2n+1SO3H)やペルフルオロカルボン酸類(PFCA類,CnF2n+1COOH),およびそれらの誘導体である.中でもペルフルオロオクタンスルホン酸(C8F17SO3H,PFOS)やペルフルオロオクタン酸(C7F15COOH,PFOA)といった化合物は生体蓄積性が高いため,使用や排出に関する規制(自主規制も含む)が世界的に進行している.このような有機フッ素化合物の環境リスクの低減のためには,有害性の度合いに応じて排水や廃棄物の無害化を行う必要があるが,炭素・フッ素結合は炭素が形成する共有結合では最強なため容易に分解しない.焼却は可能であるものの,高温が必要であるだけでなく,生成するフッ化水素ガスが焼却炉材を損傷する問題がある.これらの物質をフッ化物イオン(F-)まで分解できれば,既存の処理技術により環境無害なフッ化カルシウムに変換できる.フッ化カルシウムの鉱物は蛍石で,硫酸処理によりフッ素ポリマーを含むすべての有機フッ素化合物の原料であるフッ化水素酸になるため,フッ素資源の循環利用にも寄与できる(図1).これまでにも電子線照射やプラズマ等の高エネルギー的な手法を使えば,フッ素ポリマーでさえ分解できることは知られていた.しかしその場合,毒性が非常に高いペルフルオロイソブチレン(CF3C(CF3)CF2,PFIB)や温暖化係数が二酸化炭素の数千倍のテトラフルオロメタン(CF4)等の有害ガスの発生が懸念されている.以上の背景から,我々はPFCA類やPFAS類,さらにはそれらの誘導体について種々の比較的穏和な反応手法を開発し,F-までの完全分解,すなわち無機化を達成してきた.本稿ではそれらについて,他の研究者の報告例も交えて報告したい.
- 著者
- Loscher Peter 山川 龍雄
- 出版者
- 日経BP社
- 雑誌
- 日経ビジネス (ISSN:00290491)
- 巻号頁・発行日
- no.1598, pp.106-109, 2011-07-04
問 CEO(最高経営責任者)に就任した直後の2007年夏以来、約4年ぶりの来日です。今回、日本に来られた目的は何でしょうか。 答 痛ましい災害に遭った方々をお見舞いし、日本法人で働く従業員を励ますことです。日本の現状を自分の目で確かめて、重要な市場である日本の事業について、最新の情報を得ようとも考えました。